
|
|
|
カテゴリ:哲学・思想・文学・科学
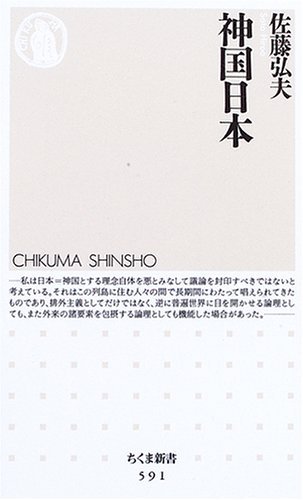 「日本は天皇を中心とした神の国である」 森首相のこの発言に、左右両派が入り乱れて論争したのは、記憶に新しい。 ところが、「自民族中心主義」「天皇中心主義」と同義とされ、戦前は「国体の本義」で鼓吹された神国思想。実は本来、まったく逆の思想だったのだというのが、この書のキモになってます。これがまた、コギミよい位面白い。 神国思想、それは鎌倉の蒙古襲来から始まる。それまで日本人は、自国 社会について、仏教思想の影響下、悪人の群れ集う世紀末社会(末法)、 世界の中心から遠く離れた小島、「辺土粟散」と認識していた。それが 蒙古襲来によって一変。神国思想は、日本を神孫が君臨し、神々が守護 する聖地として丸ごと肯定するようになる。それは、日本的なるものの 自覚と深く結びつき、室町・江戸時代と継続する、日本人による 「日本固有の文化」の胎動であり、他国に対する自国の優越、を主張す るようになる始まりだったのだ… この通俗的神国思想理解を一刀両断。もともと、日本書紀から近現代にまで見られる「神国思想」は、論者によって差異がある。加えて、蒙古襲来以降に限ってもおかしい。そもそも神国思想は、他界の仏が「神」の姿をとって「垂迹」しているという考え方であって、インド・中国が「神国」ではないのは、別の姿をとって「垂迹」している(インドは釈迦)からにすぎない。事象の裏に共通の真理=「法身仏」をみるこの思想は、国土・民族の選別神秘化に本来なじまないものという。 その衝撃的な議論を確認しておきましょう。 そもそも、天皇の地位の神格化とともに、その祖先神・皇祖神たる「アマテラス」とそれを祭る伊勢神宮を頂点として各氏族の氏神の序列化がなされた。主要神社は、官社となって幣帛が下賜され、その代わり天皇の代わりに祈ることを義務づけられた。古代では、天皇は神仏を超越し、国家そのものだった。 ところが、10世紀頃になると、古典的な律令体制が崩壊。国立大学であった寺院は、年貢を取りたてるため、競うように土地集積に乗り出し、「荘園公領制」といわれる体制が出現する。寺社は、氏族や共同体のもので無関係な者に門戸を閉ざしていた方針を転換、「人」「土地」を集めるため、参籠を呼びかけるようになった。「二十二社一宮」制度が出現し、「神々の下克上」時代に突入する。日吉山王社、春日大社、伊勢神宮外宮は、伊勢神宮の権威「社格」に挑戦。彼らは自己の威光と権威を主張し始め、土地を「神領」「仏土」と称して、排他的所有権を主張し始める。この移行にともない、神も性格が変化。それまで神は、遊行して祭祀の時でもない限り来訪しない、人間の都合では会えない存在だった。ところが、「神像」制作の開始と平行するかのように、神社に常駐して人々を監視し、老人や子供・女性に化けて人に指示を下す存在、「人格神」に変貌していくらしい。 こうした変化は、仏教のコスモロジーの下での「神仏習合」と、彼岸現象の拡大に典型的にあらわれるという。律令体制時代と違って、神宮寺と神社の力関係は逆転していた。神社の主導権は、供僧に握られ法会がおこなわれた。それとともに、本地(=仏)垂迹説が流行し始める。娑婆世界における差異を越えて、宇宙には一つの真理があり、神・仏に聖人(釈迦、孔子、孟子)は、それに気付かせるために使わされた使者=「垂迹」である。彼岸現象の拡大によって浄土往生を目指した人々は、「神=垂迹」への結縁をもとめ、霊地霊廟に足を運び帰依していった。 「神=垂迹」は、衆生を真の信仰に目覚めさせる、末法辺土の救世主であるという。そうした変化とともに、非合理的な存在「祟り」なすものから、合理的な応報「罰」を下す存在へと、「神」は変わってゆく。神国思想は、仏教的劣等観「末法辺土思想」を克服するために生み出されたのではない。末法辺土であるが故に強大な力をもつ「神」として現れる必要があった、いわば末法辺土の帰結、仏教の土着化の過程で産み落とされたもの、それが神国思想なのだという。 新羅来寇とともに鼓吹され、古代にあっては仏教要素を排撃するための神国思想は、中世3回に渡って鼓吹された。1度目は院政期。大土地所有者にして国家鎮護をかねる寺社勢力は、寺社経営と年貢徴収、国衙・貴族勢力から所領を守るためにも、「悪僧」(僧兵)集団を必要としていた。彼ら権門寺社勢力の私闘の中止を呼びかけるものだったという。2度目は鎌倉新仏教興隆期。法然の専修念仏や禅宗に対して、南都北嶺側が迫害の口実として「神国」を使った。「垂迹」の権威を荘園支配のイデオロギーの基盤としていた権門寺社勢力にとっては、はなはだ都合が悪かったらしい。3度目は蒙古襲来。荘園体制が分割相続による所領分散化によって、深刻な危機・体制内矛盾を迎えていた時代、襲来は寺社勢力にとっても千載一遇の好機だったらしい。いずれも国家秩序全体の屋台骨を揺るがす時、支配勢力の側から鼓吹された、問題解決のための協調を要請した論理だったというから面白いではないか。 また天皇は、神国の中心ではない。権門寺社体制下では、天皇は国王部分であって、イデオロギー部門である寺社と同レベルの、支配体制を総体として維持するための手段にすぎなかった。幼童天皇が出現したのは、天皇位の急速な低下があるという。中世になると、「国家=天皇」ではなくなり、国家にしめる天皇の比重は急低下、天皇は神罰が下される対象に転落・相対化されてしまっているという。神仏によって初めて光輝き、「悪行」をすれば公卿による首のすげ替えが当然視される天皇。天皇の権威は、儒教的徳治主義、仏教思想によって彩られる。と同時に、制度としての天皇は決して否定されない。それは、武家・権門自身が、天皇に代わるだけの支配勢力結集の核を持ちえず、体制の矛盾が深まれば深まるほど、実態はどうあれ、権門間の座標軸を定め権門同士の調整と支配秩序維持をおこなうために、「国王」=天皇を表面上押し立てねばならなかったこと。さらに、天皇家と人脈的につながっていた公家・権門にとっての敵は、天皇以外の人間が超越的権威と結びつき正当性を得ることであって、垂迹を否定して本地仏と直接結びつこうとする信仰=鎌倉新仏教の方がはるかに危険な存在だったこと。武家政権も、垂迹の権威に依存していて、彼岸の本地に全面的に依拠した国家を打ち立てることは前代未聞の冒険であって、現実的な選択肢にはならなかったこと、があげられるらしい。 これが近世になると、一大転換をとげる。社会は世俗化。もはや超越的・絶対的な「仏」「天」は縮小してしまい、かつて現世の権力・体制を批判する根拠となっていたものが、現世支配を支える道具に矮小化してしまう。「一向一揆」「法華一揆」「キリシタン」は、彼岸の彼方の消滅とともに消える。神国思想は、普遍的世界観を失い、日本の特殊性から日本の「絶対優位」を説く思想へ変質してしまう。それとともに、中世神国思想では排除されていた天皇が、近世神国思想では中心に舞い戻る。思想・学問が、宗教的な束縛から解放された結果、儒者・国学者たちが何の気兼ねもなく様々な根拠を提示して「神国思想」を鼓吹したため、典型的近世神国思想がなんであったのか分からぬ時代、それが近世だという。中世的普遍主義も、近世的多様さも、抹殺して成立した近代神国思想には、独善的自尊意識を相対化するいかなる契機も存在していなかった―――そう語って本書は閉じられる。 豆知識もなかなか豊富で飽きることはない。中世の起請文では、仏の次に、日本の神ではなく、中国の道教神が出てくるらしい。日本より中国の神様が偉かった中世世界。大嘗祭は天皇が天皇霊を身につける行為(折口信夫)。即位の際、「真言」を唱える儀式「即位灌頂」を通して天皇は根源的仏である「大日如来」に変身したらしい。とにかく、豊穣な中世の信仰世界には、圧倒されること請け合いです。 いささか疑念なのは、この本の中核そのもの、神国思想が様々な機能を備えていたとして、それが明らかになった所で、何の意味があるのかが良く分からないことにあるかもしれません。彼はいう。自尊意識と普遍主義が共存する神国思想の研究成果は、世界各地の「自尊意識」と「普遍主義」の関わり方と共存の構造の解明に、何らかの学問的貢献をなし得るものだ、と。しかし「共存」とは何なのか。この本では、同時代に自尊意識と普遍主義の2つが「共存」している姿は、結局描くことに成功していない。どこに、「共存」した姿があったのか、いささか首を傾げてしまう。ある時代には、神国思想に「普遍主義」を摘出し、ある時代には神国思想に「自尊意識」を抽出しただけにしか見えないからだ。そんなものの「関わり方」の構造の解明など、そもそもやらなければならない必要があるとすら思えない。時代や論者によって、異なる機能が見いだされること。それを「共存」といえるのであるならば、キリスト教・ユダヤ教・イスラム教、あるといえばあるし、ないといえばない、その程度のものではないのか。てか、どうみても、「反対物の一致」を手をかえ品をかえ語っているだけの様にしかみえない。また、機能的立場から論じるならば、神国思想の「自尊主義」側面が弱かったとしても、別のものが果たしていただけではないのか。たとえば「武威」概念だの、自尊意識ネタはいくらでも転がっている。しかも、一貫した神国思想の真実の提示とは裏腹に、近世にかけて日本のナショナリズムは、昂揚を続けていたという事実そのものに関しては、なんら検討が加えられていない。非常に面白かっただけに、ちょっと残念としかいえない。 ただ、紹介しなければならない新刊本が山のようにたまっていて、呻吟しているのですが、それでもこの本はすばらしい。ぜひお読みいただきたい。 評価 ★★★★ 価格: ¥ 756 (税込)  ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[哲学・思想・文学・科学] カテゴリの最新記事
|