
|
|
第九話 碧海の彼方(11) 【 第九話 碧海の彼方(11) 】 ところで、その頃、炎上するフロレス艦へ、やや離れた場所から、冷ややかな視線を向けている人物がいた。 ジョンストン艦と対を成す二列縦陣の片翼先頭を守りながら、ジョンストン艦にも勝る強壮な砲撃を続行している戦列艦――その艦尾甲板から、冷徹な灰色の瞳を光らせる人物――ジョンストンに次ぐ英国艦隊の副指揮官パリアである。 激しい砲火を加えながらも、己自身は殆ど無傷なままの強靭な74門艦上で、パリアは望遠鏡をゆっくりと下ろした。 そして、傍に控える副長へそれを渡しながら、抑揚の無い冷淡な声で言う。 「敵方には、ずいぶん非常識な指揮官がいるようだな。 あれでは、さぞ、ジョンストン提督も、唖然としておられることであろう」 「全くです。 窮鼠(きゅうそ)猫を噛むとは、よく言ったものですな。 ですが、パリア艦長、提督をお助けに上がらなくて良いのでしょうか?! あのままでは――」 「助け? ふ…――まさか。 この程度のことで、あのジョンストン提督に、我らの助けなぞ必要あろうはずがあるまい」 そう低く無機質な声で呟き、パリアは鼻で笑った。  「提督がその気になれば、周囲に群がる敵の巡洋艦どもなど瞬時に一掃し、さっさとあの場を離れることなど造作(ぞうさ)無いことだ。 だが、提督は、あそこに留まっている――意図的にな」 「ということは、提督は……」 「さよう」と、パリアは副長を横目で鋭く一瞥した。 「ジョンストン提督は、敢えて、囮(おとり)になっておられるのだ」 「――!」 息を詰める副長をよそに、パリアは、己の僚艦の攻撃によって、着実に戦力を削(そ)がれ、降伏へと追い込まれていく辺りのスペイン艦たちを悠然と見渡した。 それから、幾ばくかの距離を隔てた洋上で炎を上げながら提督艦へと進み行くフロレス艦に、再び氷のような視線を投げる。 「あのスペイン艦、焼き討ち船でも気取っているつもりであろうが、あれほどの朽ちようと船脚では、たとえ船体ごと突っ込んで行こうが、その破壊力の程度はたかが知れている。 提督の旗艦も多少の損傷は免(まぬが)れまいが――まあ、それも、そう甚大なものとはなるまい。 それに、その代償として、あの敵艦の指揮官が、自ら自滅してくれるのだからな」 「――アイ…サー…!」 納得しつつも固唾を呑んでいる副長の脇から、パリアは再び戦闘指揮に戻るため、深い鋼鉄色の髪を風に吹流し、踵を返した。 その後ろ姿を副長が慌てて追いかける。 「し、しかし、パリア艦長! 敵の指揮官が死ぬとは限らないのでは?」  それに対して、パリアの背が冷徹に応えた。 「仮に死せずとも、著しく消耗させることができれば、まずは、それで良かろう。 敵艦隊は、我らの攻撃によって、既にかなりの数が壊滅に瀕している。 敵の物理的な戦力も人的な指揮能力も脆弱化すれば、もともと艦の性能も戦闘能力も勝る我々の勝機は、より確実になる」 かくして、その頃、フロレス艦は、浸水によっていっそう傾(かし)ぎ、しかも、弾痕と炎とによって原型を留め得ぬ横帆たちは、まともに風をとらえるには厳しすぎる状態にあった。 だがそれでも、愛すべき自艦に最後の花道を完(まっと)うさせようと、血塗れの傷とススだらけになった腕利きの水兵たちが、炎上する帆や舵と懸命に格闘している。 そして、ついに、半ばよろめきつつも、グッと、艦が加速する手応えがフロレスや水兵たちの足元に伝わってきた。 ジリジリと肌が焼け焦げる激痛を覚えているにもかかわらず、フロレスの全身に鳥肌が走る。 (これほどに炎上しているというのに、よくぞ――! 極限の中でこそ、何物も、その真価が測れるというもの。 時代は移ったとはいえ、これほどの僚艦や艦乗りたちであれば、かつてスペイン艦隊が世界の海の覇者たる栄光に浴していたことにも頷ける。 この艦とて、このまま海の藻屑としてしまうのは、あまりに惜しい) だが、激しい熱風が吹き荒れる甲板は、もはや人の居場所を持たなかった。  ズタズタに引き裂かれた帆布が燃え上がるマストからは、廃物と化した円材や索具類が次々と崩れ落ちてくる上、マストそのものが業火の中で形を失い崩れかかっている。 その上、穴だらけの船体は海水の流入で、ますます傾きを強めていた。 しかも、辛うじて立位を保っている足元からは、大気が陽炎(かげろう)のように歪んで湧き立ち昇り、全身は、まるで窯で焼かれているかの如く、文字通り燃え上がらんばかりである。 逆巻く硝煙と己の血と汗とで霞む視界の中で、フロレスは、あと一歩の距離まで迫った英国艦隊旗艦を険しい眼で睨(ね)めつけ、それから素早く視線を返し、艦上の水兵たちへと目を凝らした。 皆、今も、必死で各自の持ち場を守らんとしてはいたが、それでも酷く煙にむせ返り、火炎の中で熱せられた肌という肌は真っ赤に変色し、滝のような汗さえ、瞬時に蒸発していく。 (皆、良く頑張ってくれた。 だが、もはや、ここまでが限界か――…) フロレスは口惜しげに唇を噛み、だが、すぐに決意の表情で艦首楼の上から飛び降り、そのまま艦尾方向へと全力で炎の中を駆け抜ける。 かくして、辛うじて辿り着いた艦尾甲板では、燃え立つ火柱の間で、老練の航海長が羅針儀箱の傍に立ち、しかと重厚な舵輪を握り締めていた。  フロレスは、ハッと足を止める。 「航海長…! あなたも、この艦に残っていらしたのですか…!」 ロペス艦長以上に当艦の古参の艦乗りであるこの航海長は、そろそろ老年に差し掛からんとする年代である。 半世紀近くに渡るであろう海軍生活を経て、いかに逞しく頑強ながたいをしているとはいえ、これほどの業火の中では、その厳ついはずの双肩も酷く痛々しく見える。 しかも、その全身の火傷と傷跡が、舐めるような周囲の炎を映して、いっそう生々しい。 一方、航海長は、今も重厚な舵輪をガッチリと強く握り締めたまま、フロレスをチラリと一瞥し、それから、ニンマリと笑って言う。 「いかにお偉いさんとはいえ、新参者のあなたに、こればかりは渡しませんぜ!!」 「…!」  一瞬、フロレスは息を呑み込み、しかし、すぐに真摯な瞳になって航海長に語りかけた。 「航海長、もはや、これ以上、水兵たちの命を危険に晒すことはできません。 即刻、ここから撤退せねば。 ですから、あなたも――」 「それで、あなたが一人で残って、この舵をわしの代わりに操縦するとでも言い出すおつもりじゃないでしょうね?」 言葉に詰まるフロレスに、航海長は再びニヤリと皮肉たっぷりに笑い、「そのやさ腕じゃあ、この舵は扱えねえ」と、嘯(うそぶ)いた。 フロレスが目を見開き何かを言いかけた瞬間、まるで二人を狙ってきたが如く、まっしぐらに両者の間に敵の砲弾が飛び込んできた。 「航海長――!!」 咄嗟にフロレスは航海長の厳つい肩に掴みかかり、相手の全身を己の体で庇いながら、その場から大きく飛び退(すさ)る。 その勢いで、航海長はフロレスに半ば抱きかかえられたまま、ドウッと、熱い床の上を激しく転がった。  他方、フロレスは航海長を庇ったまま、辛うじて鉄弾をかわしたその身を素早く起こし、二人に轟々と覆い被さりくる炎を振り払う。 そして、板張りに強く全身を打ち付けて顔を歪めている航海長を助け起こそうとした。 「航海長…!」 「いや、結構! 自分で起き上がれるす!!」 航海長はフロレスの腕をきっぱりと払って無造作に身を起こすと、視線を合わせぬまま、唇から滴(したた)る深紅の血を荒々しく拭い去った。 フロレスは、彼もまた口元の鮮血を焼け付いた軍服の袖で拭って、改めて真正面から航海長に向き直る。 「航海長、あなたは、何か誤解しておられるようだ。 わたしは、もともと陸軍の人間です。 海の上も魅力的ですが、もし最期の時を迎えるならば、大地の上で、と決めているのですよ」 「――!」 赤黒いススと血潮に塗(まみ)れ、普段の優美な風貌とは別人のようなフロレスの輪郭の中で、しかし、今も清冽で沈着な光を失わぬ双眼が、老練の艦乗りを真っ直ぐ見つめている。 その瞳が、深く碧(あお)い。  「航海長、あなたは海の上の人間だ。 ここで艦と共に散るのも、吝(やぶさ)かではないかもしれぬ。 だが――」 彼は硝煙の間から微かに垣間見える敵艦隊の群影へと鋭利な一閃を走らせ、「まだ戦いは終わっていない。我らの艦隊には、これからも熟練したあなたの腕が必要です」 言葉にならぬままに、スペイン人らしい黒々とした瞳で己を喰い入るように見返す相手に、フロレスは力強く頷いた。 「ですから、まだこのようなところで死ぬわけにはいきません。 あなたも、そして、わたしもです! 我らの蛮勇のつけを払うのは、互いに、もう少し先延ばしにしようではありませんか!!」 「……!!」 やっと顔色を取り戻し、表情も柔らぎかけた航海長に、フロレスも微笑をつくった。 「つまりは、この艦には、無人で突っ込んで行ってもらわねばなりません。 敵旗艦との距離は、もう間近い。 今の角度に固定されている帆と同様、この舵も、最後まで揺るぎないよう、頑強に固定さえできれば……」 そう早口で言い終わるか否かの間にも、フロレスは素早く周囲を見渡し、まだ灰と化していない太いロープの束を決然と指差した。 「航海長! あれで、舵を固縛しましょう!!」 「アイ・サー!!」 野太い声と共に、逞しい笑みを取り戻した航海長が、そのロープを巨大な錨(いかり)のようなゴツい手で鷲掴みにした。 そのまま二人は、目前に迫った敵旗艦に突っ込んでいく現進路を維持させるべく、俊敏な手つきで幾重ものロープを舵輪に巻きつけ、ガッチリと堅く台座に固定していく。 堅固ながらも瞬く間に固縛が仕上がると、航海長は前方を振り仰ぎ、自艦と敵旗艦との間の距離を値踏みするかのように皺の寄った目元を細めた。 「これで、行けまさあ!! これだけ頑丈に固定されてりゃあ、敵の爆撃だろうが、何だろうが、そんじょそこらの衝撃じゃ、ビクともしませんぜ! これなら、無人でも、あの敵の親玉の尻にぶちかましてやれる!!」 そう叫んで、すっかり本来の気の置けない人柄を取り戻した航海長が、満足気にゴシゴシと顎を擦る。 フロレスも目に溜まった汗を拭い、今一度、力強く頷き返した。 彼らが見据える先では、敵旗艦艦尾が、いよいよ大きくせり上がって見える。  かくして、次の風に艦が応え、さらに加速を増した瞬間、フロレスは、轟々と逆巻く焔にかき消されまいと渾身の力を振り絞って叫んだ。 「今だ!! 皆、海に飛び込め!! 撤退するぞ――!!」 さすがの勇兵たちも激炎の中で限界に達していたのであろう、この時を待ち詫びていたかのように、皆、殆ど落下するかの如く海に飛び込んでいく。 一方、フロレスは霞む視界の中を懸命に見渡し、負傷兵や彼らを助けようとしている数名の水兵たちの元へと走り寄ると、己自身も負傷兵の一人をズシリと肩に抱えた。 そして、その姿のまま、炎の広がる甲板の一隅に跪き、高熱を帯びた艦の板張りに、傷だらけの指先をそっと触れる。 (あとは頼んだぞ……!) その時、ふと視線を感じて顔を上げたフロレスの視線の先に、己の方を見つめる航海長の姿があった。 航海長は、サッと、反射的に顔を反らしたが、その年季の入った目尻の端に微かに光るものをフロレスは見逃さなかった。 此度の海戦のほんの数日のみを共にした己でさえ、もはや、この艦への愛着は計り知れないというのに、長年に渡ってこの艦と命運を共にしてきた航海長や、そして、あのロペス艦長の心境はいかばかりであろうか。 フロレスの胸にも、熱いものが込み上げた。 しかし、前方を振り仰げば、英国艦隊旗艦は、今や、ほぼ目前まで肉迫している。 彼は唇を噛み締め、振り切るように立ち上がる。 そして、肩に抱いた負傷兵を担ぎなおしながら、もう一方の手で、航海長の腕を押さえた。 「さあ、航海長、我らも参らねばなりません」 男泣きを堪えているのであろう、押さえた相手の腕が微かに震えている。 「航海長…!」 航海長は顔を反らしたまま頷くと、厳つい肩でグイと目元を拭い去り、彼もまた、逞しいその腕で別の負傷兵を抱き上げる。 そして、次の瞬間には、二人は敏捷に身を翻し、負傷兵と共に、高い甲板上から波立つ海面へと飛び込んだ。  他方、その間も、英国艦隊旗艦では、総指揮官ジョンストン提督が、炎上するフロレス艦で行われている一部始終を見届けていた。 迫り来るフロレス艦が狙い定める彼の僚艦の艦尾楼に、今も超然と立つ、威厳と落ち着きに満ちたその姿は、戦闘開始前と全く変わらない。 しかし、その声音には、幾分険しさが増していた。 「どうやら、あの敵艦の兵たちは脱出を図ったようだな」 「そのようです、提督」 そう相槌を打ちながら、キーン艦長は、火船と化したフロレス艦を鋭い眼差しで睨み据えた。 それから、素早くジョンストンへと視線を返し、早口で問う。 「提督、いかがいたしましょう? もはや無人と化したあの艦の餌食(えじき)となってやることもありますまい」 「うむ」と、ジョンストンも頷き返す。 そして、頤(おとがい)に強靭な指先を添え、思慮深く目を細めた。  「この距離となっては、もはや完全には衝突を避け切れまいが、敵艦の真正面から我らの艦尾を突かれるのは、さすがに御免こうむりたい。 あの長槍のような切っ先でこちらの船体を貫かれては、敵艦の全体重でのしかかられるにも等しい結果になりかねぬ。 その上、火災を当艦の内部まで深く引き込む危険性も高い」 「アイ・サー!! では、せめて側面で受け留められるよう、即刻、当艦を回頭します。 それに、提督も、ここにおられては危険です! どうぞ艦首の方へご避難をなさっていてください」 そう言い残してキーン艦長が慌しく立ち去る足音を背後に感じながら、ジョンストンは、今一度、迫り来るフロレス艦に厳然とした横顔を向けた。 眼前直近まで迫り来ているその敵艦は、まるで燃え盛る巨大な隕石の如くである。 そのさまを一頻(ひとしき)り見据えた後、ジョンストンは冷徹な一閃と共に踵を返した。 (余興であれば、さしずめ、昔、我ら英国海軍に火攻めにされたアルマダの仇討(あだう)ちといったところか。 だが、実戦としては、まだまだ詰めが甘い)  その間にも、炎上するフロレス艦は、頑強に固定された舵の指し示す進路を維持しながら、ジョンストン艦の艦尾目指して猛然と驀進してくる。 対して、当のジョンストン艦は、俊敏で滑らかな操帆によって、突進してくるフロレス艦の艦首をジワジワとかわしはじめた。 今や人員無きフロレス艦は、固定された舵の進路を突き進むことしかできない。 その上、燃え上がる帆もマストも次々と崩れ落ち、それに比例して艦速も次第に弱まっていく。 だが、それでも、ジョンストン艦がフロレス艦を完全にかわすには、両者の距離は既に近くにありすぎた。 しかも、ロペス艦長の指示により、スペイン艦隊の巡洋艦たちが、捨て身の覚悟でジョンストン艦を囲むようにして、逃げ道を与えまいとその進路を阻んでいる。 そうしている間にも、みるみる両者の距離は縮まっていった。 かくして、ついに船体と船体の狭間が消え、僚艦がぶつかり合う瞬間――!  二隻の重厚な戦列艦の間に、雷光の如く巨大な火花が飛び散った。 と同時に、これまでの砲撃音を数百倍にも増したかのような激烈な衝撃音が、うねり波立つ海面を大きく震わせる。 さらに、それに続いて、ガガガガガーーッと、木材と金属が激しく擦れ合い破壊し合う、鼓膜を劈(つんざ)くばかりの轟音が上がる――!! この海戦で生き延びている誰もが、全身を硬直させて、そちらに釘付けられた。 ジョンストン艦艦尾めがけて突撃してきたフロレス艦を、ジョンストン艦自身は見事に己の艦尾からかわし、代わりに艦尾近い舷側部でガッチリと相手の側面を受け留めている。 両戦列艦の堅剛な舷側が強く擦れ合い、両者の手すりがバックリと抉(えぐ)れ、その界隈に設置されていた数門の大砲が互いの船体にメリメリとのめり込んでいく。 しかも、両者の索具類が絡み合って不自然な方向に強度の付加をかけ合うために、その高みにある円材たちが、今にも折れそうになりながら軋んでいる。 そして、その間にも、轟々と燃え盛るフロレス艦の炎は、容赦無くジョンストン艦へと乗り移りはじめていた。 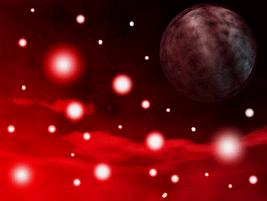 それら燃え移りくる炎を消火せんと、罵声を上げながら奔走する英国艦隊旗艦の水兵たち。 そのさまを、負傷兵を抱えたまま水中にいるフロレスは、辛うじて海面から目におさめていた。 艦尾をかわされ、狙ったほどの破壊力をもたらすことのできなかったことへの口惜しさからか、焼け付いた皮膚に沁みる海水のもたらす疼(うず)きが、いっそう激痛に感じられる。 だが、次の瞬間に目に飛び込んできた光景によって、全ての痛みは完全に吹き飛んだ。 (あれは……!) 海水に濡れて顔に張り付くブロンドの隙間から見上げる視線の先で、喧騒に呑まれている英国水兵たちとは別世界にいるかのように、超然とその長身を艦尾甲板に現しくる人物。 その両肩では黄金色の肩章が風にたなびき、本人は後ろ手に腕を回したまま、飄々(ひょうひょう)たる面差しでこちらを見下ろしている。 (ジョンストン提督か!) フロレスの全身を直感が貫いた途端、己の置かれた状況さえも忘れて、彼の碧眼は、ついに相見(あいまみ)えた敵将の姿に釘付けられた。  対する提督は、その相手の一瞬の虚を衝くかのように、不意に、後ろ手に握っていた銃を前に構え、ピタリとこちらに狙い定めた。 「――!!」 反射的に我に返ったフロレスは、すかさず負傷兵を庇いながら海中に身を沈める。 それと同時に、周囲のスペイン艦から、ジョンストンや英国兵たちに向かって、砲撃と射撃の応酬が一斉に勢いを増した。 互いに苛烈な撃ち合いの展開される隙を縫って、フロレスは負傷兵を抱いたまま、敵艦から離れようと無我夢中で泳いだ。 背筋を銃弾が幾弾もかすめ飛んでいく。 「いたぞお、あそこだ! フロレス殿――!! さあ、どうかこちらに!!」 急激な疲労感に襲われ、かすみそうになる意識の向こうから、馴染みの水兵たちが懸命に己を呼ぶ声が聞こえてきた。 フロレスは鉛のように感じられる己の身体に鞭打って、今一度、海水を掻(か)く手足に力を込める。 ロペス艦長の指示によって決死の覚悟で救助に回ってきた味方のボートに救出されると、彼はズブ濡れのまま、先刻、ジョンストンを見かけた方角を急いで振り仰いだ。 だが、既に、そこに提督の姿はなかった。  (註☆イラストは、ウィキペディア(Wikipedia)よりお借りした当時の海戦の様子です。 イラストのセインツの海戦(1782年)では、英国艦隊とフランス艦隊が激しい戦いを展開しました。 この物語の海戦は、これほど大規模なものではありませんが、雰囲気を感じて頂けましたら幸いです。) そのまま彼らのボートは、彼らを守る盾の如くに前面に回り込んできた味方の小型巡洋艦の陰に滑り込む。 フロレスは荒い息のために肩を大きく上下させながら、周囲の戦況を探ろうと方々を仰ぎ見た。 だが、その位置からは、硝煙や炎の中で響き渡る爆音が聞き取れるばかりで、戦況を見晴るかすことは不可能だった。 強い脱力感のために、グッタリとボートのヘリにもたれかかる。 海水を含んで全身に張り付く軍服が、異様に重く感じられた。 彼は激しい消耗のために朦朧としかける意識を無理矢理つなぎとめながら、今は鈍重な歯車のような己の思考を懸命に働かせようとする。 (今のところ、まともに仕留められたのは、先刻、割り込みをかけて艦尾を縦射したあの一隻のみ。 残る敵の戦列艦は、恐らく、ジョンストン提督の旗艦を含めて5戦艦。 しかも、敵の巡洋艦や輸送船も含めれば、総勢10艦以上は、まだ健在に相違ない。 それに対して、味方艦は、この間に、どれほど生き残ってくれているものか、今は想像すらつかない……!)  フロレスのきつく噛み締められた唇には、海水の塩辛さと共に、火薬のススけた苦味までがジワジワと広がり、口中で切れた傷口から染み出す血の味と混ざり合って、言いようもないほど不快だった。 それと共に、事態の推移を冷徹冷静な目で推し量っているであろうジョンストンの見えざる視線が、己の全身に氷の刃(やいば)の如く突き刺さってくるのを感じていた。 そしてまた、そのようなフロレスへ冷ややかな視線を向けているのは、ジョンストンだけではなかった。 英国艦隊の副指揮官パリアも、その手に望遠鏡を掲げながら、ずぶ濡れの身をボートのヘリに預けて放心しているフロレスを、くまなく観察していた。 「あの軍服、陸軍の将官か。 スペイン海軍も、ずいぶんと人材不足のようだな」 同様に望遠鏡を覗いていた脇の副官が、苛立ちを込めた呻き声を漏らす。 「もっともですな、艦長。 しかし、悪運の強いヤツだ。 未だ、しぶとく生き延びていようとは…!」 「いずれにしろ、我々としては、このまま捨て置くわけにもいくまい。 あの者のせいで、こちらは大事な僚艦を、一隻、戦闘不能にされている。 そのツケは払ってもらわねばならぬ」 そう低く呟いて、パリアは灰色の瞳を冷徹に閃かせた。 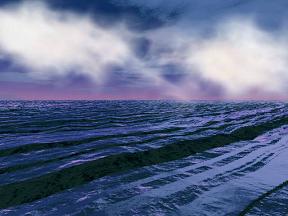 そして、感情の見えぬ横顔のまま、険しい声音で続けていく。 「もし、わたしが先刻の提督の立場であれば、わたしも提督と同じ行動を取ったであろう。 だが、本来なら、このようなところで、我が方が幾ばくかでも損傷を蒙ったり、貴重な戦力を失うなど、もっての他なのだ。 陸地で待ち構える敵軍を撃破することこそ、肝要なのだからな」 「アイ・サー!!」と、副長は、すかさず襟を正して力強く頷いた。 「パリア艦長の仰せの通りですな。 これ以上、味方艦にいらぬ被害が増す前に、ここにウロついているスペイン艦隊なぞ、早々に一掃してしまわねばなりますまい!!」 その頃、それら炎と硝煙に霞む海域を遠くに見晴るかす洋上の小さな岩礁の上に、一人のインカ族の若い娘の姿があった。 彼女は、掲げていた望遠鏡を素早く下ろした。 短い黒髪に巻いた緋色のバンダナとスラリとした褐色の肢体が、紺碧の海に映えている。  暫し鋭い横顔を海戦の行われている洋上へと向けていたが、自分の傍で同様の方角に向けた望遠鏡を覗き込んでいるインカ兵の姿に気付くと、パシッと、相手の頭をはたいた。 兵は咄嗟に頭を押さえる。 「――てっ!」 「ちょっと! そんなに長々と覗き込んでたら、バレるでしょっ!! 望遠鏡のそのガラスの表面、日光を思いっきり反射してんだから。 目ざとい人間が見たら、向こうからでも、私たちがここにいること一目瞭然よ」 「すっ、すいません!!」 「それより、ホラ! はやいとこ伝令鳥、呼んで。 急いでトゥパク・アマル様に戦況をご報告しとかなきゃ」 「はっ、マルセラ様!!」 この女性――マルセラは、インカ軍の総指揮官トゥパク・アマルの重臣ビルカパサの姪にあたるが、そうした血筋や男勝りの性格もあって、今ではインカ兵たちを率いるいっぱしの連隊長の一人である。 そして、そんな彼女の部隊は、トゥパク・アマルの指示の元、ペルー沖沿岸の随所に点在する無人島や岩礁に渡って散開し、それぞれの場所から戦況を観察して陣営本部に報告する任務を遂行していた。 スペイン軍が、英国艦隊との戦端を開くであろう海域を事前に予測していたように、インカ軍もまた、その概ねの海域を予測していたのだった。 とはいえ、小島や岩礁がそう多くあるわけもなく、ましてや、その近くで都合良く海戦が展開してくれるはずもない。 従って、マルセラも、かなりの距離を隔てた場所から辛うじて艦影を追うことしかできず、正確な戦況の報告は困難だった。 それでも、生来の野性的な視力を発揮して彼女なりに目におさめたものを、布切れの上に素早く走り書きしていく。  真剣な眼差しで書き進める彼女の口元から、思わず呟きが漏れる。 「案の定、ジョンストン提督の英国艦隊が、圧倒的に強いわね。 スペイン艦隊の艦船は、かなりの数、既にやられてる。 いきなりの接近戦、その上、乱戦になっちゃってるし、あそこまで砲撃されたらスペイン艦隊の旗艦も、きっと、もう時間の問題……。 だけど、スペイン艦隊にも粘ってる艦はいるし、まだ終わったわけじゃない」 ひとしきり書き終えると、マルセラは布切れを伝令鳥の脚に結び付け、「それじゃ、頼んだよ!」と、優しく鳥の頭を撫でた。 (此度の海戦も、本(もと)を正せば、インカ軍が勝ち残るために、トゥパク・アマル様が密かに采配されたこと。 英国艦隊も、スペイン艦隊も、本当のところは、トゥパク・アマル様の手の平の上で踊っているだけなのかもしれない。 だけど――) これほどの距離を隔てながらも轟然たる爆音の絶え間なく響き来る方角を睨み据えながら、マルセラは、その艶やかな唇を噛み締める。 (スペイン軍の火砲にさえ苦戦を舐めてきた私たちインカ軍が、あれほどの武力を持つ者たちをわざわざ英国から呼び寄せてしまって、本当に勝機はあるのかしら…?) それから、勢いよく頭を振って、既に上空へと舞い上がった伝令鳥を大きく振り仰いだ。 陽光を反射してキラリと煌く白い翼が、細めた目に眩しい。 (ううん、信じよう……! トゥパク・アマル様を、そして、インカ軍を!!)  かくして、沿岸に構えられたインカ軍陣営では、水平線を遥々と見晴るかす断崖上で、洋上から吹きつける潮風に長髪を巻き上げられながら、トゥパク・アマルが鋭利な横顔を沖合いへと向けていた。 ほどなく、彼の視界の中に、マルセラの放った伝令鳥が飛び込んできた。 すっと、天に向けて差し出した彼の逞しい腕に、鴎大ほどの白色の鳥が舞い降りる。 トゥパク・アマルは素早い手つきで伝令鳥の足にくくりつけられていた布切れを解(ほど)くと、敏捷に視線を走らせる。 そして、思慮深気にその切れ長の目を細めた。 少し後方に控えていたアンドレスが、一歩、トゥパク・アマルに近づいた。 「トゥパク・アマル様、海戦の状況はどのように?」 「予想通り、英国艦隊が優勢のようだが、スペイン艦隊の一部の艦も奮戦している」  「フロレス殿の艦ですか?」 低く絞ったアンドレスの声音に、トゥパク・アマルは、そちらを僅かに振り向いた。 「この報告では、そこまでは分からぬ。 そうか――そなたは、フロレス殿と面識があるのだな」 「はい。 スペイン人にも、あのような者がいるのだと、俺の認識を大きく変えてくれた人でした」 アンドレスは、かつてラ・プラタ副王領で幾度かに渡って対決を繰り返した宿命の相手を脳裏に描きながら、ギュッと腰のサーベルを握り締めた。 あのフロレス殿なら、たとえ相手が英国艦隊と言えども、ただでは終わらぬはずです!!――と、そう喉元まで出かけた言葉を、アンドレスは黙って呑み込んだ。 (いや…英国艦隊を相手に、いくらあの者でも、経験の乏しい海戦でできることには限りがあるだろう……) そう思った途端、不意に、背筋を言いようの無い寒気が走り、続いて強い寂寥感に襲われた。 彼の視線は、いつしか足元の断崖絶壁で砕け散る波飛沫へと落ちていた。 そのようなアンドレスの心を見透かすように、トゥパク・アマルの低く響く声が聴こえてくる。 「誰の命運も、まだ、分からぬ。 だが、アンドレス、そなたが、それほどまでに見込んだ人物なら、わたしも見(まみ)えてみたかった」 「トゥパク・アマル様……!」 かつてフロレス殿も同じことを――そう言いかけて、アンドレスは胸に押し寄せる波のような思いに、再び言葉を呑み下した。 (そう…フロレス殿も、以前、同じようなことを言っていたっけ。 あれは、ティティカカ湖畔の戦場で、初めて、あの者と戦った時だった。 トゥパク・アマル様に会いたかったと、確かに、彼も言っていた。 俺は、あの時は完全に頭に血が上っていて、まともに彼の話を聴く耳を持っていなかったが…。 もし――…もし、この反乱がはじまる前に、トゥパク・アマル様が会われていたのが、あのアレッチェやモスコーソ司祭ではなく、フロレス殿だったら? もしそうだったら、事態はもっと違ったものになっていただろうか? このような多大な犠牲を払うことなく、もっと平和裏(へいわり)に、多くのことが進んでいただろうか? それとも、あのアレッチェたちがこの国の権力を牛耳っている以上、たとえフロレス殿とて、やはり、なす術は無かっただろうか……) そのような思念に頭を占められていたアンドレスが、ハッと我に返って見上げた時には、既にトゥパク・アマルは厳然たる総指揮官の顔に戻っていた。  そのトゥパク・アマルの傍に、此度の作戦では、副指揮官であるアンドレスと同様に重要な任にあるロレンソが、敏速な足取りで近づいてきた。 トゥパク・アマルも洋上へ馳せていた視線をそちらへと向ける。 ロレンソは、トゥパク・アマルの足元に素早く跪いて礼を払うと、若者らしい鋭気に満ちた面差しを上げた。 「トゥパク・アマル様、敵方に放っていた斥候が戻って参りました。 斥候たちの報告によれば、敵将アレッチェ殿は、やはりあの陣営に!」 そう言って、彼らが陣を張る断崖上と対峙する高台に敷かれたスペイン軍陣営へと、毅然たる視線を投げた。 トゥパク・アマルも、切れ長の目で敵陣の方角を見つめ、ゆっくり頷く。 無意識に拳を握り締めながら、アンドレスが、さらに一歩を踏み出した。 「恐らく、敵方も斥候を放って、トゥパク・アマル様の所在をつきとめようと躍起になっていることかと。 いえ、恐らく、もう、ここにトゥパク・アマル様がいらっしゃることを早々に突き止めていることでしょう!」 「さもあろう。 だが、この期に及んでまで、わざわざ手間をかけてわたしの所在を探し回らずとも、わたしの方から挨拶のひとつぐらい出向いて行こうものを」 敵陣の連なる対岸に刃物のような一閃を放ち、誰にとも無く嘯(うそぶ)いたトゥパク・アマルの方へと、アンドレスもロレンソも「え?!」と瞳を瞬かせた。 「トゥパク・アマル様、今、何と?」 「そなたたちが案ずるには及ばぬ。 それより、そなたたちは、作戦通り、ぬかりなく事を進めることに全力を注いでくれたまえ」 「はっ!!」 そう恭順の礼を払いながらも、アンドレスは相変わらず険しい眼光で敵陣を睨み据えている。 「クスコ戦の時も、トゥンガスカの本陣戦の時も、あのアレッチェは、トゥパク・アマル様を捕らえるために、どれほど卑劣な手を使ってきたか。 そして、やっと捕らえたトゥパク・アマル様に牢から脱出され、どれほど地団駄踏んだことか。 あの執念深い男が、これほど近くにトゥパク・アマル様がいることを知って、どれほど喉から手の出る思いでいることか…! あの者が、今度は如何なる鎌首をもたげてくるのか、それを思うと、俺はおぞましくてなりません……!!」 込み上げる嗚咽を抑えるかのように胸元を押さえているアンドレスの傍で、ロレンソもまた、常の鋭利な面差しをいっそう研ぎ澄ませて、案ずるようにトゥパク・アマルを見上げている。 そしてまた、彼らの後方でやり取りを見守っていた腹心ビルカパサや他の兵たちも、同様に、険しくも非常に案ずる面持ちで、トゥパク・アマルと敵陣とを交互に見渡していた。 そのような全員に真摯な視線を送ってから、トゥパク・アマルは厳然と応える。 「恐らく、そなたたちの思う通りであろう。 だが、それならばそれで、こちらにも出方というものがある」  褐色の精悍な横顔を再び水平線へと向けた彼のマントが、風の中で、漆黒の翼の如く大きく翻る。 そして、これから海と陸とで起こる激戦の展開をうらなうかのように、沈着さの陰に激情を潜ませた鋭い目元を吊り上げた。 「アンドレス、ロレンソ。 そろそろ時間だ。 行きなさい」 「はっ!!」 若者二人は俊敏に一礼すると、様々に去来する思いを胸に抱きつつも、決然と踵を返した。 こうして出陣の合図を待つ各自の兵たちの元へと急ぎながら、アンドレスは難しい表情のまま、独り言のように呟いた。 「トゥパク・アマル様は、あのように仰っているけど……。 だけど、此度の作戦、トゥパク・アマル様の御身にとって、あまりに危険ではないだろうか」 横を歩む己の横顔を、いつしか、じっと見入っているアンドレスの方へと、ロレンソも視線を返す。 「ああ…そうだな。 わたしも、そなたと同じ思いだ。 できることなら、このような危険な作戦の前面に出られようなどとお考えになられず、当陣営内深くにお留まり頂いて、幾重にも衛兵に守られていてほしいと――心底、そう願いたい心境だ」  「ああ、本当に!! 俺も、全く、君と同じそのままの思いだよ!」 二人は小さく息をついた。 しかし、再び前方に向き直り、歩調を速めながら、「だが、トゥパク・アマル様のお考えも理にかなっているとは思う」と、ロレンソが言葉を継ぐ。 「ロレンソ…!」 「アンドレス、もう決まったことだ。 あとは、わたしたちにできる最善のことを成し遂げるのみだ。 そのことが、そのままトゥパク・アマル様をお守りすることにもつながるのだから」 そう応えた己の方へと、まだ何か言いたげなアンドレスが身を乗り出しかけるのを脇にしたまま、ロレンソは、ちょうど通り過ぎかけた武器庫の方へと足を向けた。 武器庫の周りを堅固に護衛する衛兵たちが、若き二人の将の到来に、礼を払ってサッと入口への道を開く。 二人が武器庫の中を覗くと、アンドレス軍やロレンソ軍に配分された武器は既に搬出され、内部はガランとかなりの隙が空いていた。  その様子に、アンドレスは再び眉間に皺を寄せる。 「トゥパク・アマル様は、武器まで俺たちに均等に配分されてしまっている。 それに、クスコの叔父上たちの元にも送ったと聞く。 ご自分の御身の護身をもっと考えられても良いのに……」 「トゥパク・アマル様は、それだけ我らの援護に期待をかけてくださっているということだろう」 そう言って、ロレンソはアンドレスの懸念を払拭するかのように、決然と力強く続けていく。 「それに、この倉庫に保管されている火器の殆どは、そもそも英国艦隊がトゥパク・アマル様にもたらしたものだ。 英国側の腹の内は見え透いているが、それでも、それなりに英国艦隊のために役立てねばならぬと、仁義に篤いトゥパク・アマル様なら、そのようにお考えになるのは当然だ。 それを思えば、此度の作戦決行において、我らがそれらの武器を供与されたのは、陛下の御心にかなっていよう」  他方、アンドレスは、キッと、鋭く友の顔を振り向いた。 「だけど、結局は、英国は俺たちの真の味方なんかじゃない! あの者たちも、所詮は、この国をスペインから奪い取って、己の植民地にしようと狙っているだけじゃないか!!」 「そう。 だから、此度の作戦には、その先がある。 ともかく、アンドレス、そのような案じ顔は、もうやめにしよう。 そなたがそのようでは、そなたの兵たちにまで、いらぬ不安をかき立ててしまうぞ!」 アンドレスの背を軽く押しながら武器庫から離れかけて、ロレンソは、ふと相手の横顔に目を留めた。 先刻までの険しく難しい表情は陰を潜め、その面差しには、今は深い悲しみを湛え、じっと倉庫の奥の一点を見つめている。 ロレンソは、黙って、その視線の先を追った。 そこには、ただ火薬の詰まった多くの硝子壜が整然と並べられているのみである。 「アンドレス…?」 ロレンソの声に我に返ったアンドレスが、咄嗟に大きな瞳を瞬かせた。 「あ…いや、すまない。 ちょっと気をとられて…」  それから、サッと目を伏せて苦悶の面持ちで口ごもる彼の方に、ロレンソは再び静かに問いかける。 「アンドレス、何を考えていた?」 「いや…」 「アンドレス?」 「あの硝子壜を見て、ちょっとフランシスコ殿のことを思い出したのだ。 フランシスコ殿の天幕にあった山のような酒壜のことを……」 そう語るアンドレスの脳裏に、かつてクスコの陣営にいた頃の己とフランシスコのことが、激しく交錯しながら甦っていた。 トゥパク・アマルに対する激しい思慕と疑心暗鬼との葛藤の中、酒に溺れ、苦悶の中で己を見失っていったフランシスコの姿、そして、為す術も無く戸惑うばかりであった自分自身の姿――。 アンドレスは胸苦しくなって、思わずギュッと瞼を伏せる。  (しかも、フランシスコ殿を追い込んだ最たる張本人は、俺自身であったかもしれないのだ…! あの時、俺さえもっとしっかりしていれば、フランシスコ殿がアレッチェに拐(かどわ)かされてトゥパク・アマル様を裏切ることも、彼が命を落とすこともなかったかもしれない……!!) アンドレスの伏せた瞼が震えている。 「アンドレス……」 悲痛な面持ちで俯(うつむ)く朋友の姿を居た堪れぬ思いで見つめながら、しかし、ロレンソもすぐには返す言葉が見つからず、苦渋の滲む唇を噛み締めた。 暫し継ぐ言葉を探しあぐねているロレンソの傍で、アンドレスは、まるで懺悔の言葉を吐き出すように続けていく。 「トゥンガスカの本陣戦で、トゥパク・アマル様がアレッチェの陰謀にはめられ、そして、無事にご帰還されるまで、あまりに怒涛のように日々が過ぎて、俺は、まともにフランシスコ殿の死を悼むことさえしていなかった。 いや、フランシスコ殿だけじゃない。 反乱がはじまってさえいないのに暗殺されたブラス殿。 本陣戦でアレッチェの手にかかったフィゲロア殿…! そして、ミカエラ様たちをお守りして敵弾に倒れたオルティゴーサ殿! それに、とても数え切れないほどの無数の兵たち……!!」  「アンドレス!!」 ロレンソの手が友の肩を力強く掴み、完全に俯いてしまった相手の顔を正面に向き直らせた。 そして、鋭くゆるぎない面差しで、アンドレスの顔に真っ直ぐ目を据えた。 「アンドレス、そなたの思いは、彼の地に旅立った者たちに、必ずや、しかと伝わっていよう。 それに、そのように彼らを悼む思いがあるのなら、なおのこと、今、我々にできることは、一刻も早くこの戦(いくさ)に決着をつけ、これ以上の犠牲を増やさぬことだ。 その上、そなたは、今、トゥパク・アマル様の副官ではないか! そなたの働きいかんで、この戦の行く末を左右するほどの影響力を持つ立場にあるのだ。 そなたの思いが、此度の決戦でインカ軍の力の源となり、守護の力となるよう祈っている!!」 ロレンソの険しいほどに厳然たる口調に、アンドレスもハッと目を見開いた。 そして、我を取り戻したように頷く。 「そうだな…今こそ、前をしっかり向いていなければ……!」 それから、己の肩を握り締めている友の逞しい褐色の腕に、彼も手を添え、力強く握り返した。 「ありがとう、ロレンソ。 インカの神々の加護が、君と君の兵たちの元に常にあらんことを!!」 ロレンソも力強く頷き返す。 「そなたとそなたの兵たちにも、そう願わん! アンドレス!!」  ◆◇◆ここまでお読みくださり、誠にありがとうございました。続きは、フリーページ第九話 碧海の彼方(12)をご覧ください。◆◇◆ ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
|