
|
|
|
カテゴリ:日本史全般
~わが内なる差別~
 <ねぶた 阿倍比羅夫の蝦夷征伐> 東北に生まれたことで、東北の民が古来より蔑視されて来たことを知りました。蝦夷は「えみし」と読み、野蛮な民とされたのです。それは都から距離が離れていて実態を知らなかったための誤解で、彼らにも彼らの文化があった訳です。えみしはアイヌとは異なり民族的には全く一緒。強いと言う意味もあって、蘇我蝦夷のように有力な古代豪族の名にも用いられました。 古代東北の民、蝦夷と同様の立場が九州南部の熊襲(くまそ)や土蜘蛛(つちぐも)や隼人(はやと)でした。こちらも都から遠く離れていたため実態を知らずに蛮族とされ、日本武尊(やまとたけるのみこと)などによる征伐の対象となったのです。   四国に転勤したことで、東北にはなかった「部落問題」を知りました。何と子供たちが通う学校の直ぐ近くに、その被差別集落があったのです。「士農工商」と言う明確な身分確立の世の不満を解消するため、最下層の「えた、非人」と言う階層を作ったとの説を聞きました。 住井すゑの「橋のない川」は近畿地方のある被差別集落をテーマにした長編小説で、私はこれを読んで部落問題と部落解放運動の存在を知りました。東北人には全く異質な世界です。大阪に転勤して街に出ました。そこは有名な古寺の傍でしたが、とても異様な雰囲気でした。そこにはアンタッチャブルな空気が漂っていて、一角が被差別集落であることを直感したのです。   沖縄に転勤したことで、沖縄についてたくさんのことを学びました。歴史、文化、文学、風土、生態、宗教、芸術、言語などです。戦火で焼失した沖縄関係資料の収集が私の仕事の一つだったこともあって、ずいぶん本を読みましたが、琉球処分で沖縄が近代国家日本に組み入れられる過程についても学びました。近代日本にいち早く馴化させるため、琉球方言を標準語に変える努力を子供たちに強い、学校内で方言を使った子供の首に「方言札」と書かれた札をぶら下げることもあったようです。 東北出身の県令(現在の県知事)が貧しい沖縄に同情して善政を敷いたことも、琉球を支配した旧薩摩藩出身の県令が鹿児島県の商人を優遇したこともありました。貧しかった沖縄県民が当時開かれていた航路で移住した関西で、容貌や言葉で嫌がらせを受けたと聞きます。そしてハワイやブラジルなどへ県民は雄飛しました。勤務当時の部下が先祖は中国人と言ったことがありました。それだけ中国を敬い、誇りにしていたのです。でも彼が言ったことは嘘でした。沖縄では今でも通じる話です。同じ日本民族なのにねえ。 関東大震災  日本の古代史が好きだった私は、手当たり次第にそれらに関した本を読み、やがてその関心が幕末から明治期にまで至りました。その過程で歴史小説も読み始め、関東大震災当時朝鮮人が井戸に毒薬を投げ入れたとの噂を広めて、60名ほどの朝鮮人を虐殺したことを知りました。当時朝鮮は日本に併合され、白丁(ぱくちょん=奴隷)などの身分制度は解体され自由の身となっていたものの、半島では依然として蔑視は残っていたのです。 それで彼らは満州国や内地へと渡りました。そこでは同胞からの差別は無くなったものの、一部の日本人からの蔑視はありました。関東大震災当時は幸徳秋水らの社会主義者が捕らえられているので、きっと憲兵隊などによる思想取り締まりが強かったのだと思います。不幸で暗黒な時代でした。   博物館に勤務したことで、アイヌにも関心を抱くようになりました。アイヌの口承文学「ユーカラ」を読み、動画でそれを耳にし、幾つかの博物館でアイヌの衣装や民芸品を見、一度は北海道に出かけてアイヌ人初の国会議員萱野茂氏から直接アイヌ語の話を聞いたこともありました。それらの中で、明治新政府がアイヌの日本化を図った方策などについても知りました。日本語教育は沖縄と一緒ですが、アイヌからは無理やり土地を奪ったのが、沖縄と全然異なる点です。   広大な北海道の中の好猟場や良漁場を失ったアイヌたちの生活は困窮しました。固有の言葉を失い、宗教を失い、次第に彼らは追い詰められて行きます。その中で純粋なアイヌの血を引く人も激減して行きます。仕事を求めて都会へ出、差別や迫害を避けて道外へと移住したアイヌ。今でも彼らの暮らしは苦しく、日本人に同化することで辛うじて生き延びているのが現状です。そんな中での「アイヌ新法」であり、ウポポイなのでしょう。 この話をある親子の肖像を借りて記しました。女性の名は宇梶静江。詩人、古布絵作家、絵本作家、そしてアイヌ解放運動家です。男性の名は宇梶剛士。職業は俳優で、ウポポイの開設PRアンバサダーを務めています。上の写真はそれぞれの若き日のもの。静江の夫は和人。剛士は元暴走族のリーダーでした。母子が歩んだ道は、恐らく苦難に満ちた茨の道だったのでしょう。  親子はアイヌに対する蔑視と差別から、都会へと逃れて来たようです。その遥かなる苦難の道のりを思います。二人は今、アイヌの誇りと共に生きています。ちょっとしたきっかけから書き始めたこのシリーズですが、何とか書き終えることが出来ました。私は博物館もアイヌも歴史も大好きなので、是非ともウポポイでは真実を伝えて欲しいと願っています。北海道に嘘は似合いません。開拓のことも真正面から受け止め、是非取り上げて欲しいものです。それでこそ「民族の共生」だと思うので。 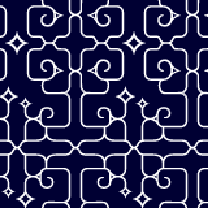 このシリーズを読むために私のブログを訪ねて下さった皆様。どうもありがとうございました。皆様のお陰で何とか最後まで書くことが出来ました。心から感謝します。もしもこれだけたくさんの方が来て下さらなかったら、きっと毎日は書けなかったと思います。私はアイヌに対する偏見は全くありませんが、もしも不適切な表現や間違った理解があったらお許しいただきたいと思います。 確かにアイヌと和人の交流の歴史を見れば、時には戦って血を流したこともあったと思います。気高いアイヌの魂同様に、純粋な魂を持って北海道での開拓に挑んだ和人がいたこともまた確かな事実です。アイヌと和人がこれからも共に心を通じ、共に歩むことが出来るよう願って筆を置きます。ではまた。感謝。<完> お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2021.03.09 00:00:12
コメント(0) | コメントを書く
[日本史全般] カテゴリの最新記事
|
|