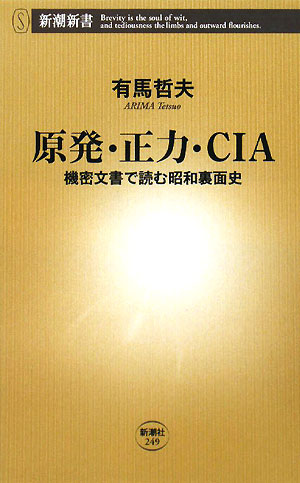 |
 ノーチラス号の進水から始まった連鎖は、第五福竜丸事件を経て、日本への原子力導入、ディズニーの科学映画『わが友原子力』の放映、そして東京ディズニーランド建設へと続いていく。その連鎖の一方の主役が正力であり、もう一方の主役がCIAを代表とするアメリカの情報機関、そしてアメリカ政府であった。(10ページより) ノーチラス号の進水から始まった連鎖は、第五福竜丸事件を経て、日本への原子力導入、ディズニーの科学映画『わが友原子力』の放映、そして東京ディズニーランド建設へと続いていく。その連鎖の一方の主役が正力であり、もう一方の主役がCIAを代表とするアメリカの情報機関、そしてアメリカ政府であった。(10ページより)
|
| 著者・編者 | 有馬哲夫=著 |
|---|
| 出版情報 | 新潮社 |
|---|
| 出版年月 | 2008年02月発行 |
|---|
「原子力の父」と呼ばれることもある讀賣新聞社主・正力松太郎の本来の目的は、マイクロ波通信による放送・通信の融合だった――メディア論が専門の著者・有馬哲夫さんが、公開された CIA 機密文書を読み解くことで、そうした事実が浮かび上がった。なお、本書は福島第一原発事故前の 2008 年 2 月に上梓されている。
讀賣新聞を牛耳り日本テレビを立ち上げた正力は、マイクロ波通信網を「全国に張り巡らせてテレビ、ラジオ、ファクシミリ(軍事用、新聞用)、データ放送、警察無線、列車通信、自動車通信、長距離電話・通信などの多重通信サーヴィスを行おうと計画していた」(14 ページ)という。彼は「あらゆるメディアを一挙に手中にすることを」目論んでいたのだ。
正力は放送事業免許は持っていたが、通信事業免許は持っていなかった。電電公社の独占事業だったからだ。
通信事業免許を獲得するには総理大臣になるしか無いと考えた正力は、衆議院選挙に打って出る。そして見事当選を果たすが、総理への階段を上るには実績が必要だ。そこで目を付けたのが「原子力」だった。
一方、アメリカ政府は、原水爆の開発競争でソ連に追いつかれたため焦っており、友好国に原子力技術を開示して平和利用を促進する「アトム・フォー・ピース」を展開していた。原子力潜水艦ノーチラス号を建造したジェネラル・ダイナミックス社と海軍がディズニーに『わが友原子力』という科学映画を作らせ、米国民および友好国にアトム・フォー・ピースを訴えた。これは後に日本テレビ系列で訪英されることになる。
そこで CIAh、日本における資金力と大衆誘導に優れた正力に目を付けた。だが、「アメリカは「アトムズ・フォー・ピース」政策においても日本など旧敵国に関する限り援助に積極的ではなかった。核兵器の原料を生産できる動力炉を日本に渡すなど問題外だった」(135 ページ)という。
動力炉を使って商業原発を開始することを成果に総理の椅子をたぐり寄せようとしていた正力は、イギリスからの動力炉輸入を検討する。そんな中、イギリスで原発事故が起きてしまう。民間による原発を目指していた正力の意に反し、原子力賠償法という「事業者の賠償責任は 50 億円までで、それ以上は実質的に国が補償する」(217 ページ)という矛盾する法律が成立することになる。
間もなくアメリカはスプートニク・ショックに見舞われ、アトム・フォーピースどころではなくなる。時代は大陸間弾道ミサイル開発競争へと進んでゆく。やがて通信衛星が実用化されると、正力のマイクロ波構想は時代遅れの考えになってゆく。
こうして正力は取り残され、また、原子力発電事業そのものも中途半端な形で実現されたように感じる。たとえば原子力賠償法は 1961 年に成立するのだが、その矛盾は今回の福島第一原発事故で露呈することになった。
動機はどうあれ、正力の放送・通信の融合という目標は、今まさに実現されつつある。その意味では、昭和の巨怪と呼ぶに相応しい人物である。だが、正力にとって、原子力発電がサブの位置づけだったわけで、それ以来、メインとしてこの分野に取り組んだ政治家はいなかったのでは無いかと感じる。
本書では中曽根康弘・元首相にも触れられている。「彼は 1951 年、サンフランシスコ講和条約締結交渉のために来日したジョン・フォスター・ダレス国務長官に原子力の研究開発を日本に禁じないよう談判したという」(44 ページ)。これが事実なら、正力より先に原発の可能性を察知していたわけで、総理大臣にまで上り詰めたのだから、もっと原子力政策に力を注いでも良かったのでは無いだろうかと悔やまれる。

