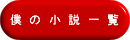冬のある晴れた日の正午
「冬のくせに」
千駄ヶ谷の住宅街を歩いている時、僕はそう思った。
とてもとてもそう思ったのだ。
何故なら前日も、その前日も、そしてそのまた前日も記録的な大雪だったからだ。
大雪の日。
賑やかな原宿の街から「音」が、まるであらゆる物質が壁の中に潜むように消え、そこに居る全ての人々が寒さから身を守るため肩を寄り添い合った。
道路も歩道も真っ白な雪で覆われ、ビルや、服屋や、靴屋や、レストランの電気看板の光も、ひどく滲んで見えた。
口うるさい選挙カーの放送もなくなり、さおだけ屋のスピーカーもなくなり、この世における全ての不純物が取り除かれたような気がした。
その時、僕はずっと窓を見ていた。
なんせ、何十年ぶりかの記録的な大雪だったものだから、僕はそれを永遠に頭の中に記憶したかったのだ。
それなら本当は外に出ればよかったのかもしれない。
しかし、僕は出れなかった。
その時僕は風邪をひいていたのだ。
それも僕の人生における記録的な風邪だった。
多分、今後の人生においても、このようなもの凄い風邪はひかないだろう、とベッドの中で思っていた。
僕の額はステーキ用バターが軽く溶けるくらいの熱さで、意識は氷のように冷え切っていて、手は小刻みに震えていた。
もちろん、こんな記録的な風邪をいきなりひいたわけではない。
風邪をひいておきながら、僕は毎日何時間もかけてアメリカより遠く、立川市より近い僕の勤めているPR宣伝会社に向かい、自分のデスクのある部屋のソファーに横になり、旅行広告のPR宣伝を考えていた。
僕の役職は副社長だった。
この会社は10年位前に、僕が僕の友達と一緒に始めたもので、その僕の友達が社長だった。
みるみる間に会社は大きくなった。
彼の営業指南が天才的であり、堅実で、実用性と宣伝性の高いものばかりだったからだ。
彼はPR宣伝の営業方法を創造するべく生まれてきたような男で、PR宣伝においては才能の塊だった。
この業界でも段々と名が知られてくるようになった頃、彼はガンであっけなく死んだ。
日々仕事に追われていたせいで、彼が会社で倒れるまで誰も彼の異変には気づけなかったのだ。
その後、彼の息子が彼に代わって社長職を引き継いだ。
しかし、彼の息子には全くと言っていいほど才能がなかった。
その上、会社の規模を大きくするために多角経営に乗り出し、失敗を続けた。
借金は膨れ上がり、以前使用していた超高層ビルのオフィスも、彼は売っ払ってしまった。
彼の失敗点は、父親と自分を同等に見ていたことだった。
彼の父親のような人物はごく稀にしか生まれてこない。
しかし、彼と言う人間は、毎時間大量生産されたおもちゃのようなもので、要するに一般人となんら変わらない能力しか持っていなかったのだ。
彼は先日、ようやくその事に気づき、中小企業に成り下がった自分の会社のビルの屋上から飛び降りた。
幸い地面に激突する前に木にぶつかり、即死には至らなかった。
肋骨を十分なほど折ったうえ、手足も完全に折れてしまったらしく、集中治療室から未だに出てこない。
だから、今、会社のトップは社長ではなく、副社長である僕だったのだ。
そのため、僕は無理してでも会社に出なくてはならず、しまいには、会社で寝起きをするような生活を強いられてしまったのである。
そのうえ何故か行き帰りの電車の中は冷房がかかっていた。
僕は毎日分厚いセーターを着込み、分厚いコート―以前登山家の友達が古くなったからといってくれたもの―を羽織り、雪山専用の分厚いズボンを穿き、雪山専用のブーツを履いた。
しかし、そこまでしてもJRの冷房には全くと言っていいほど効果がなかった。
一体どのような冷房システムを彼らは作っているのだろう。
JRの冷房はそこまで他者の冷房より、ずば抜けて性能が良いのうだろうか。
もかしたらJRの山地奥深くにある極秘研究所で、とても暑がりでひどく太った冷房研究員たちが、日夜乗客を暑さから守るという大儀のために研究しているのかもしれない。
もちろんその研究所にはいろんな種類の冷房が至る所でかかっている。その光景は随時監視カメラで記録され、そこの部屋での人間の体温、心拍数、脳のa波の数値を計られている。
部屋を出入りする際には、その理由と、理由に基づく根拠を論文にして提出しなければならない。
そして、乗車してくる乗客の為にその完璧なまでに計算され尽くした冷房を用い、車内を快適な空間にしているのかもしれない。
これで車掌の暑がりも解消されるだろう。
しかし、実際そんな面倒なことをJRはしないのだろう。
だが、僕の乗ったその電車はその概念を打ち崩すほどの冷房具合だった。
それは僕の想像かもしれないし、実際にそのような極秘プロジェクトが運行しているのかもしれない。
そんなことは誰も知らない。
もちろん、僕はその片鱗にさえ触れることは出来ないのだろう。
彼らはひどく光を嫌い、暗闇を好むのだ。
そして、人の頭の中に現れては消えていく、そのような存在でしかないのだ。
そんな想像を3日続けて夢の中でしたあと、僕はスッキリと目覚めた。
床に転がっていた目覚まし時計をにらむと、6時50分だった。
外は暗く、どんよりとしていた。
間延びした黒い雲が空を覆い。地の果てまで続いていた。
そのため、僕には「6時50分」という時刻が夜なのか昼なのか判断できなかった。
しばらく、僕は天井を眺めていた。
いくつもの顔が浮かび出てはまた天井に吸い込まれていった。
すべて僕の人生の登場人物だった。
出て行った僕の妻も出てきた。
もちろん死んではいない、だろう。
こうして天井を眺めていると、天井と言うものは普遍的なものなのかもしれない、と思えてくる。
どれだけ時間が過ぎても、第三者が何かを加えない限り、天井と言うものはそこで何かを生み出し続ける。
しかし、天井自体には何の変化も起こらない。
ただ生み出していくだけだ。
突然、僕は猫に餌を与えていないことを思い出した。
僕はここで3日寝込んでいた。
要するに3日間餌を与えていないことになる。
計9回近くになる。
僕はベッドを飛び出した。
そして、リビングや僕の部屋を探した。
しかし、いくら探しても猫は出てこなかった。
まぁ、頭の良い猫だ。
僕が餌をあげなくても彼女なら必ず自分で餌を調達しているはずだろう。
と、僕は思った。
そして、猫のことはそこで終え、冷蔵庫から水を取り出しコップに注ぎ、一気に飲んだ。
冷たい液体が喉を通り、食道を通り、胃に落ちていくことが手に取るようにわかった。
僕は冷蔵庫の残りを点検した後、少し期限が切れている野菜を手でちぎり、ボールに入れ、上から刻んだチーズをまぶし、ドレッシングをかけた。
ベーコンはフライパンで軽く焼き、オーブンで焼いたカリカリのパンの上にのせた。
ミルクは電子レンジで軽く暖めた。
10分くらいで僕はそれを全部食べてしまった。
なんだか物足りなかったので、再びパンをオーブンでカリカリに焼き、今度はカリカリのソーセージを焼いた。
挟んでむしゃむしゃと食べた。
その後、急いで洗面所に向かい、洗顔フォームで顔を洗い、歯を磨き、ドライヤーとくしを用いて髪の毛を梳かした。
もう2度と風邪はひきたくなかったので、また分厚いセーターに分厚いコートに分厚いズボンに分厚いブーツという格好に着替えた。
外に出ると僕はドアに2重ロックの鍵をかけ、郵便物をチェックすることなく、マンションの扉を開けた。
僕はなんだか無性に外が恋しくなっていた。
外に出たくて出たくてたまらなかった。
そして、やっとのことで3日ぶりに僕はベッドから外に出たのだ。
そこまでの躍動は30を過ぎた僕にはとても久しく感じられた。
しかし、そんな僕の考えは千駄ヶ谷の住宅街を歩いているうちに薄れていった。
いつの間にか僕の頭上にはさんさんと輝く太陽が光線をあたりかまわず放っていたのだ。
彼(彼女?)も3日ぶりの外なのだろう。
しかし、それにしても太陽の力は凄まじく、記録的な大雪の残された記録たちは次々と溶かされていった。
何もそこまでしなくたっていいじゃないか。
容赦ない太陽の破壊光線は止むことはなく、悲鳴も、何もあげることなく彼らは溶かされるだけだった。
そして、その対象は次に僕を狙ってきた。
「冬のくせに」
僕は汗をぐっしょりとかいていた。
早く帰らなければ体が冷えてしまう。
冷えればまた風邪をひいてしまう。
しかし、3日間運動機能を停止していた僕の体は上手く動かない。
僕が太陽に対して深い憎しみを持ち始めた頃、彼は隠れるように雲の中へ姿を消した。
途端に、空は憂鬱な雰囲気を醸し出し、冷気が街を包んでいった。
僕の存在をあざけ笑うように風は強くなっていった。
体から噴き出していた汗は一瞬のうちに衣類に吸い込み、僕の体を凍らせていった。
やっとのことで僕はマンションに辿り着いた。
病み上がりのくせに最初遠くまで行き過ぎたようだった。
エレベーターで4階に上がり、体を引きずりながら僕の家に向かった。
猫だ。
僕の家の前に、一匹の猫が座っていた。
僕の猫だ。
急いで駆け寄ると、猫は突如として走り出し、僕を通り過ぎてどこかに行ってしまった。
僕は猫の後ろをとらえたのは、既に猫が突き当たりを曲がったところだった。
僕はその突き当たりにあった猫の後姿をぼんやりと考えていた。
猫は、大丈夫だった。
そして、2重ロックをはずし、ドアを開けようとしたところ、ドアは開かなかった。
逆にドアを閉めてしまったようだった。
僕は考えた。
確かに、急いでいたにせよ、ここを出る時僕はちゃんと鍵をかけた。
嫌な予感が僕の頭をよぎる。
「やれやれ」
2重ロックを再び開けた後、僕は用心して部屋の中を確認した。
なんと、僕の知らない靴が一足、行儀よく玄関に並べられていた。
何処のメーカーのものでもなく、見たこともないような形の靴だった。
僕はもしかして空き巣が入ったのかと思っていたのだが。
中に入って扉を閉めると、その反動で張り詰めていた部屋の空気が揺れた。
しばらく、僕は玄関で第三者による事態の変動を待っていたのだが、それはいっこうに訪れなかった。
仕方なく僕は靴を穿いたまま部屋に上がった。
その瞬間、部屋のチャイムが鳴った。
僕はその場に凍りついた