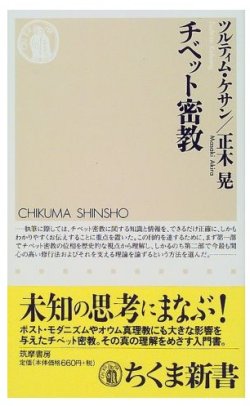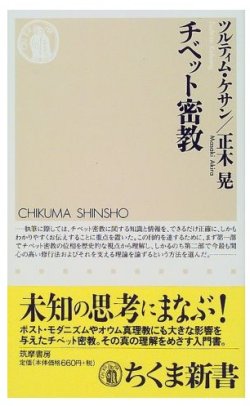
地球人スピリット・ジャーナル2.0につづく
「チベット密教」
ツルティム・ケサン /正木晃 2000/01 筑摩書房 新書 222p
★★★★★★
わがブログの新書本マンダラ百冊以上の中にあって、まさに異色な光を周囲にまき散らしながらも、なお中心に位置しようか、というのがこの本である。新書本というジャンルをジャーナルしているだけで、実に多くの世界への足掛かりをつかむことができるのだが、この本などはまさに異界への扉と言っていい。ナルニア物語の子供達が疎開して、小父さんの家のクローゼットにかくれんぼしたところから始まる世界にさも似ている。
数百円という新書本に、これだけの密教的な秘密が提供されてしまっていいのだろうか、と思ってしまうほどの圧倒感がある。第一部はチベット密教の位相を歴史的な視点から理解し、第二部では、修行法およびそれを支える理論を論じている。
この本、出版されたのは、2000年の1月。あのオウム真理教騒動から数年しか経ておらず、さらに、世間はノストラダムスの1999年7の月、という呪縛の予言の謎解きに没頭していた。まさにそのような世情の中で本書は書かれたということになる。共著ではあるが、どこからどこまでがどちらが書いたのかは、読んでいて判然としない。
しかしそのことが、読者に理論と実践の絶妙な組合せの妙を味あわせてくれる。この本一冊そのものがまさにマンダラであり、また、チベット密教というマンダラへの入口となっている。しかしながら、もうすこし巨視的にみれば、チベット密教は、宇宙スピリットともいうべきコスモロジーへの入口と言っていいだろう。
本書を読むにあたり、とりあえず、このブログに中にあって留意して置くべきことがいくつかある。一つは、700年前(13世紀初頭)のチベットとはどういう状況であったか、ということであり、もう一つは、その時代におけるカルマ・カギュー派の動向である。
しかし、こうした難問をすべて解決するに足る時間を、そしておそらくは人材も、インド仏教界はもちえなかった。1203年、インド仏教最後の大拠点であったヴィクラマシーラ大僧院がイスラーム軍に劫略(こうりゃく)され、インド仏教の命脈が断たれてしまったからだ。
かくて、仏教史上、最高ともいうべき難問の解決は、インド密教の後継者たるチベット密教の手にゆだねられることになったのである。 p039
こうしてインド密教はチベットへのその本拠地を移し、13世紀初頭より1959年に中国共産党の指導の下に人民解放軍がチベットに侵攻し、「チベット動乱」が勃発するまで、チベット密教の基軸を成すところは、歴代、忠実に受け継がれてきたのである。文化大革命の惨禍が全チベットを襲い、寺院の大半は破壊され、僧侶の多くは逮捕され、あるいは強制還俗させられた。1500年来、チベット高原に根ざしてきた密教の歴史は、ここに終焉を迎えることになったのである。
カギュー派は12世紀当時から、ゲルク派、サキャ派、ニンマ派(中沢新一もこの流れに属する)などとともに代表的なチベット密教の流れを作りだしており、マルパ、ナロパ、ミラレパなどの活仏達を輩出したとされる。その流れはさらにいくつかの流れに分かれながらカルマ・カギュー派も形づくられた。この流れの中、700年前(13世紀初頭)のチベットにOshoは106才まで生きたとされる。
当時、私は16才の少年であったという記憶があり、いくつかの残像やインスピレーションなどが再現されつつあるが、ここでちょっと気になったのは、16才、ということである。この本において紹介されているチベット密教の修行過程において、16才とは師の下にあってイニシエーションを受けるべき年齢とされている。また、師へ捧げられる16才の少女についても論述されている。
この16才というのは、数え年なのか満年齢なのかという小さなことより、修行を求めて出家する修行者は永遠の16才のような書かれかたをする場合もあるので、純粋にカレンダーにこだわる必要はないであろう。象徴として使われているところに興味深いもを感じた。
さらにさまざまな経典や修行法が紹介されるが、この本の真髄は次の点に窮まる。
「吉祥秘密集会成就法清浄瑜伽次第」こそ、インドとチベット密教が生み出した最高度の成就法にほかならないのである。 p136
この本には、その詳細が展開されており、入門書といいながら、決してアナロジーを使わず、文献の意味する所を直指するところは、この本の出版された時代性を考えると、驚愕に値する。なぜに著者たちがそのような勇気を持ち得たかというと、まさにその時代性にあったと言えるだろう。
私たち自身が、オウム真理教の信者や元信者を話してみて、おもい知らされることがあった。チベット密教に関する彼らの知識に、極端な偏りがあるのだ。彼らはチベット密教の修行法やそこから生じるとされる神秘体験について、詳しい情報をもっていた。とくに瞑想法に関する知識はかなりのレベルに達し、なかには「瞑想オタク」とよんでもいいほどの信者すらいた。
しかしながら、その反面、チベット密教の歴史については、まったく知識がないといっていいほどであった。さらにいえば、密教を学ぶにあたり、必須の前提となる顕教、つまり密教以外の一般仏教に関わる知識もまた、ほとんどもち合わせていなかった。 p010
そのような緊急性があったからこそ、この本は出版されたともいえるだろう。中途半端なチベット密教オタクたち(私もその中の一人だが)口を閉ざしてしまった時代に、この本は、その道の専門家と実践者としての責任をはたそうとしている。
私は1990年以降、Meditation in the MarketPlaceの標榜のもと、往相よりも還相に重きをおいて、市民社会の中に自らの位置を確保することに専念してきたが、それはある意味、市民社会への逃げ込みではなかったか、という自省の念もある。
オウム事件が発覚して10年以上が経過し、麻原の死刑が確定した今、専門家や実践家ならずとも、チベット密教が、現代地球にいきる我々に指し示していることを、勇気をもって見つめ直す時期がきていると言えるかもしれない。
このブログには、アガルタという隠しキーワードが存在する。その言葉も実は、チベット密教に深く関わる言葉であるが、今は、その分野に特化する道は取らないでおく。また、タントラという修行方法が、現代地球人が自らのコントロールを失いかけている性エネルギーの制御法になんらかのビジョンをあたえてくれる可能性もある。
----------
<再読>2008/09/06