
|
|
第八話 青年インカ(9) 【 第八話 青年インカ(9) 】 「!!…――」 ミカエラや息子たちは、一体、何が起きたのか全く分からぬまま、腰を抜かしたように唖然と、ただ、投げ込まれたままに、岩の上のような平らな床面の上に佇んでいる。 先刻までの銃声や水路際を駆けるけたたましい足音が嘘のような深い静寂の中で、皆が肩で激しく呼吸する音だけが聞こえる。 そこは、暗い地下水路よりも、さらに濃厚な、まさに墨を零したような完全なる闇の世界だった。 あまりに深い闇のために、先程まで、少し暗闇に慣れてきた夜目も、今は、再び、全く利かなくなっている。 「皆…大丈夫か……? ミカエラ? イポーリト? フェルナンド?」 闇の中から、トゥパク・アマルの案ずる声がする。 ミカエラも息子たちも、縋(すが)るように、一斉にそちらを振り向いた。 「あなた…!!」 「父上!」 「父上!!」 闇の中で、3人の声を確認したトゥパク・アマルが、ふっと深い安堵の吐息をつく音がする。 「良かった、皆、無事で……」 「!!…――うわぁっ!! なっ…?!」 トゥパク・アマルが言いかけたところを、イポーリトの声が激しく遮った。 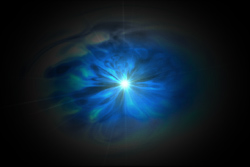 「イポーリト?!」 全く視界の利かぬ中で、トゥパク・アマルは目を凝らしながら、イポーリトの存在を手探りで探す。 「父上っ…!! 誰かいる!!」 驚愕したイポーリトの声が響くと同時に、イポーリトを探して伸ばしていたトゥパク・アマルの腕に、何かが、突然、絡み付いてきた。 「!!」 「助けてくれ!!! 出してくれ――!!! ここは…ここは――!!!」 半狂乱に叫びながら、己の全身に縋りつくように飛びついてくるもの…――トゥパク・アマルは、咄嗟に、その「もの」を引き寄せて、叫びを上げている相手の口を、己の手で堅く塞いだ。 「シッ…! 静かに……! 皆も、声を立ててはならぬ」 闇の中でトゥパク・アマルの押し殺した声が響き、ミカエラや息子たちも、ぐっと言葉を呑んで息を詰めた。 辺りは、水を打ったような静寂に包まれる。 その静けさの中、岩壁か何かを隔てた遠くから、微かに響く声がする。 『いないぞ?!』 『だが…!! 確かに、こっちに逃げていたはずだ!!』 追っ手の役人や敵兵たちの会話であることが、すぐに分かった。 『もっと奥まで行ったか?』 『この水路の先には、既に兵が回っている。 いずれにしろ、逃げおおせるわけはない!!』  それら役人や兵たちの声に混じって、あのアレッチェの凄まじい怒声が、ひと際、激しくこだまする。 『ええい!! 無駄口叩いている暇があったら、探すのだ!! 弾に当たって倒れているかもしれぬ。 水中まで、徹底的に探せ!! 絶対に逃がすな!!』 いつしか、どこからかフェルナンドが、闇の中でトゥパク・アマルを手探りで探し当て、ギュウッと強く身を寄せてきた。 トゥパク・アマルは、震えているフェルナンドを抱き寄せて顔を近づけ、そっと、優しく耳打ちする。 「大丈夫。 ここは、外にいるあの者たちには、見つけることはできぬ」 自分たちを探し回る役人たちのヒステリックな叫び声は、その後も暫く壁向こうで続いていたが、やがて別の場所を探しに行ったのか、次第に声は遠のいていった。 ……フゥ――ッ…――― 無意識のうちに、トゥパク・アマルたち家族4人の間から、深い、深い、安堵の溜息が漏れる。  が、その4人の溜息の合間を縫って、トゥパク・アマルの腕に囚われている何者かの方から、呻き声が聞こえてきた。 「…ウッ!……ウウ……」 ハッと思い出したように、トゥパク・アマルは、己の手によって堅く口を押さえ込まれている者の方に、意識を戻した。 彼は闇の中で苦笑し、低く、囁く。 「そうであった。 我らの命の恩人殿が、ここに……」 「恩人?」 ミカエラの相変わらずの毅然とした声も、今は安堵のためか、柔らかく響く。 トゥパク・アマルは、「そう。まさしく恩人に等しき者だ。が、説明は後だ」と真摯な声で応え、その何者かを押さえ込んだまま立ち上がった。 完全なる暗闇が視界を支配しているため、高さも横幅も、どれほどの広さを為す空間なのか定かではなかったが、そこは、長身のトゥパク・アマルが普通に立ち上がっても天井につかえぬほどに十分な高さがあり、両手を広げて動いても空間の壁に当たらぬほどに、横幅も、決して、そう狭くはないことが分かる。 「ミカエラ、イポーリト、フェルナンド、少し奥まで進もう。 足元に気をつけて」 彼は、腕に捕らえている何者かを片手で押さえたまま、空いた手でフェルナンドの手を取って、ゆっくり歩みはじめた。 そのフェルナンドの手をイポーリトが取り、イポーリトの手をミカエラが取る。 彼らは暗闇の中、はぐれぬようにしっかりと手を結び合って、暫く、黙々と進んだ。  やがて、ミカエラがポツリと言う。 「ここは、自然の洞窟や何かではないようね? まるで、舗装された道路のようだわ。 道幅も高さも十分ね。 大人が横に並んで数名は歩けそう」 「その通りだ。 ここは、人が通るために、意図的に築かれたものだからな」 「え…!」 そこまで聞いて、ミカエラは、深い暗闇の中でも次第に慣れてきた夜目で、夫の方を凛と見つめた。 「歩いていて、もしかしたら、と思ったの。 ここは、インカ帝国時代の地下道ね?」 トゥパク・アマルは、静かな眼差しで頷く。 「その通りだよ、ミカエラ。 ここは、インカの地下道。 正確には、インカ帝国時代以前からあったものだが。 さあ…この辺りまで進んでくれば、もう、あの地下水路に音が漏れることもあるまい」 そう言いながら微笑んで、彼は、やっと、己の腕に押さえ込んでいた何者かを、その全身も、その口も、ゆっくりと解放した。 咄嗟、その何者かが、トゥパク・アマルに向いて半狂乱の叫びを上げる。 「おまえ!!! おまえ…――!! おまえ―――っ!!!!」 そして、叫びながら、手探りのまま、猛り狂ったように、トゥパク・アマルに掴みかかってきた。 それは、紛れも無く、かの強欲な番兵――セパス。 がたいのいいセパスに激しく体当たりされて、トゥパク・アマルの全身は僅かに傾(かし)いだが、彼は、すぐさま強靭な腕で相手の肩をガッチリと押さえ込むと、沈着な声で語りかける。 「落ち着いてくれ…セパス。 そなたは、我らの命の恩人でもある。 十分に、そなたの働きには、報いるゆえ……」 「なに、ほざいてやがるんだぁ!!! 何が財宝だ…騙しやがってっ!! おまえ……俺をはじめから利用しようと謀ったな?!!」 「すまぬ。 此度は、やむにやまれぬ事情だったのだ」 苦笑しつつも閉口ぎみのトゥパク・アマルの方に、イポーリトが溌剌と声を上げる。 「父上、この人、誰なの?」 「あの牢の番兵の一人だよ、イポーリト。 此度の脱獄計画の一端を担ってくれた、我らの恩人だ」 セパスが愕然と唖然で絶句している間にも、イポーリトの利発そうな声が、暗闇の中に明るく響く。 「じゃ、脱獄計画に協力してくれた人?」 「まあ、結果的には、そういうことだ」 トゥパク・アマルは、闇の中で微笑みながら続ける。 「イポーリト、そなたも、インカの地下道が、インカ時代の主要な建造物をつないでいることは、聞いたことがあろう? 特に、インカ帝国の首都であったこのクスコには、網の目のような地下道が今も縦横無尽に走っている。  我々が囚われていた修道院は、もとは、インカ帝国時代の王宮だった。 必ずや、地下道が通じていることは間違いないと思ったが、しかし、その位置までは分かりかねた。 そこで、外界の者と連絡をとって、調べてもらったのだ。 案の定、地下道が、あの建物の地下水路のどこかに繋がっていることまでは分かった。 いや、そもそも、あの地下水路自体が、もともとは地下道の一部であった可能性もある。 だが、現在のあの水路の、どこが、地下道との出入り口なのかまでは、調べても、さすがに分からなかったのだ。 もう200年以上も使われていなかった上に、秘密の地下道だけあって、表面からは、容易に出入り口は分からぬ造りになっているからね。 それ故、ここにいるセパスに、地下道の地上の出入り口のひとつであるサクサイワマンの砦から、逆に、あの地下牢の水路に向けて進んできてもらったのだよ」 その瞬間、トゥパク・アマルの言葉を遮って、再び、セパスの怒り狂った声が響いた。 「それで、おまえは!! 財宝があるなどと、俺を騙してっ…――!!」 「すまぬ、セパス。 いや…かつての太陽神殿の財宝の一部が、地下道の一角に隠されているのは本当のことなのだ。 だが、そこは、もっと奥まった迷宮の先……そこに向かっていたならば、そなたは、恐らく、今頃は、迷った果てに気が狂い、ほどなく命を落としていたはずだ。 余所者(よそもの)だけで、到底、行き着けるような場所ではない。 それは、そなたに地下道について伝えた際にも、警告したであろう? あれは、真実そのものだった。 それでも、そなたは、地下道に踏み込んだ。 本来なら、その時点で、待ち受けるものは、狂気と死のみだったはず。 …――とはいえ、同時に、わたしは、そなたを偽ったことも、また事実。 財宝のありかではなく、修道院の地下…つまりは、地下牢の水路を終着点とした地図を渡したのだからね。 騙したことについては、心から詫びたいと思っている」 そう言って、トゥパク・アマルは、セパスの声の方に本当に深く礼を払った。 ところで、読者の方々の中には既知の方もおられるかと思うが、トゥパク・アマルの説明通り、実際に、インカの地下道は実在している。 そして、それらの地下道が、旧都クスコの王宮や神殿、城塞などを繋ぐようにして、主要な建造物の地下を縦横無尽に走っていることも、ほぼ間違い無いと言われている。 ただし、その実態は、現在も、殆ど明らかにされてはいない。  トゥパク・アマル自身が述べているように、それら地下道の内部は、迷路のように何本ものトンネルがあまりに複雑に入り組んでおり、ひとたび迷い込んだら二度と太陽を拝めぬほどに――現に、既に幾多の人々が地下道に下り、行方不明になっている――今も、まだ謎に満ちた神秘の領域なのである。 実は、代々のインカ皇帝の間では、地下道の詳細について密かに伝承されており、彼らが情報の伝達時などに、その一部を利用していた可能性については、古くから言い伝えられていた。 しかも、その地下道の存在はクスコに限られたものではなく、南米大陸広域に渡るもので、南米大陸の地下深くには数千キロメートル規模の長さを持つ長大な「地下トンネル」が存在する可能性が示唆されている。 そして、それらは、正確には、インカ帝国時代よりも、もっと古い時代からの遺産なのである。 代々のインカ皇帝は、遠い過去からの伝承によって、それらの地下道の存在を知らされており、その地下道をさらに開拓して、活用していたものと考えられている。 彼らは先史文明の遺(のこ)した遺産を、さらに発展させつつ生かしていたのである。 実際、彼らは、その地下道を様々に活用していた。 例えば、トゥパク・アマルの説明のごとく、インカ帝国がピサロたち白人らの侵略を受けた際には、征服者の略奪から逃れるため、「太陽の神殿」にあった黄金を地下道を利用して持ち出し、地下道の一角に隠したと言われる。 現在、そうした地下道の存在そのものは既に確認されているのだが、上述のごとく、それらの地下道は非常に複雑な迷宮になっており、その実態は現代になっても、未だ、解明されてはいない。 今、トゥパク・アマルは、その神秘の地下道を歩みながら、セパスに向かって、さらに続ける。 「そなたは、備えとして、そこそこの灯りや食料を持ち込んでいようが、このような勝手の分からぬ暗く危険な迷路を徘徊しながらでは、ここに辿り着くまでに優に一日は歩き通しであったろう? 精神的にも、肉体的にも、へとへとになっている頃だ。 その状態で、目の前に出入り口らしきものを見つければ、もと来た気の遠くなるような暗黒の道を戻ることなど、考えたくもないものだ。 それより、目の前の出口の外に向かって必死に助けを求めようとするのが、人の心理というもの。 案の定、セパス…――そたなは、その通りに行動してくれた」  「!!!…――おまえっ…そこまで分かって……!!」 セパスは、怒りと悔しさと、そして、実は、命の助かった安堵から、込み上げる様々な感情に翻弄されるままに、けたたましく叫び続けている。 そんなセパスの傍に足を踏み込んで、長男イポーリトが、ついに堪(たま)りかねたように険しい口調で言う。 「さっきから聞いていれば、父上のことを、おまえ、おまえって……!! 無礼であろう!!」 まだ12歳の少年とは言え、はやくも過酷な逆境に次々と直面してきたイポーリトの風貌には、既に毅然とした青年の凛々しさが宿っている。 そのイポーリトの肩に、そっと制するようにミカエラが手をかけた。 「イポーリト…」 「母上!」 先程までセパスを押さえていたトゥパク・アマルに代わって、いつしかフェルナンドを抱き上げているミカエラは、イポーリトの方に微笑んで頷くと、改めてセパスに向いた。 そして、彼女は、闇の中で頭を下げる。 「セパス殿、そなたがどのような心積もりであったとて、夫の言う通り、結果的には、そなたは我らを救ってくれました。 わたくしからも、礼を言います」  「え……っ!」 セパスは、密かに、闇に紛れて顔を紅潮させた。 戦士のような勇壮さを持つとはいえ、女性的な魅力にも富む美貌のミカエラに、牢番の誰もが、よからぬ下心を抱かずにはいられなかったが、この端役の番兵セパスは、訊問や拷問を担当する身分の高い将校たちの所業に、ただ指をくわえているしかなかった。 そのミカエラと、まさか、このような形で道中を共にすることになろうとは…!――セパスは、全く場違いも甚だしいのだが、それでも、ミカエラに直近で頭まで下げられては、舞い上がるほどにドギマギせずにはいられない。 一方、ミカエラは、今度は涼しげな声色になって、冷ややかに言い放つ。 「セパス殿、夫は、そなたに、必ず然るべき返礼はするはずです。 ただ、今は、夫を責めるよりも、そなた自身の身を案ずる方が先ではないかしら。 まだ、そなたも、完全に命の安全が保障されたわけではないでしょう? わたくしたちが、この地下道から、無事に出られるかも定かではないのです。 どこから敵兵の追っ手が迫ってくるかも分かりません。 それに、図らずも、わたくしたちの脱獄に関わってしまったそなたは、要するに、それなりの裏があったわけでしょうし…? それらのことを、スペイン側の役人たちに知られれば、そなたにとっても厄介なことになるはずね。 ましてや……わたくしたちやインカの地下道の秘密を知ってしまったそなたは、この先は、どこまでも、インカ兵たちに命を狙われることになるかもしれなくてよ?」 「!!――」 美しい響きを持ちながらも冷厳なミカエラの声に、そして、その内容に、セパスはギョッと身を固め、シュンとして、急に大人しくなった。 トゥパク・アマルも、「あるいは、そいういうことも、あるかもしれぬ」と、冗談めかして応える。 「!!!…ま、まさか、そんなこと…しねえよな??! 恩人だろ?! 俺…命の……」 トゥパク・アマルは横顔でフッと微笑み、それから、暗闇の中で前方に毅然と顔を上げた。 「さあ、今は、言い合いをしている場合ではない。 まだまだ、決して、状況は予断を許さぬ。 ミカエラの言う通り、まずは、この地下道を利用して、皆で無事に脱出を果たすことが先決だ」 それから、トゥパク・アマルは、セパスの背負っている荷物に闇の中で視線を走らせた。 「セパス、そなた、火の灯せるものは持っているか?」 言葉に窮するセパスに、真っ直ぐ、彼が向く。 「ここを無事に出られなければ、何もはじまらぬぞ。 わたしは、正確な地下道の地図を持っている。 このまま闇雲に歩いて、皆で下手に迷って、死ぬまで彷徨い続けるより、協力し合って早々に地上にでた方が賢いとは思わぬか?」 「……」 セパスはチッとヤケッパチの風体で舌打ちすると、それでも、ミカエラの視線を意識してか、荷の中をゴソゴソやりつつ、渋々ながらも、小さな蝋燭とマッチを取り出した。 「ありがとう」 それらを受け取って、トゥパク・アマルが蝋燭を灯す。 辺りは、ほんのりと明るくなった。 その僅かな光にもかかわらず、完全なる闇から解放されて、皆の表情は明るくなる。 決死の逃亡を経て、なお、生き延びている愛しい家族の者たちの表情を見渡しながら、互いに、思わず笑みが零れた。 トゥパク・アマルは、腰に縛り付けるようにして、しかと持ってきていた松明(たいまつ)の棒の乾き具合を確かめると、己のマントの乾いた一部を引きちぎって棒に巻きつけ、蝋燭の火を移し変える。 たちまち、周囲は、燃え上がる松明の炎に照らし出された。  まるで、命の火が灯るがごとくの、その眩(まばゆ)い厳かな輝きに、そこにいる5人共の誰もが、暫し、魅了されたように見入った。 牢を出て、なお、今も生きている!!…――特に、トゥパク・アマルたち家族4人は、激しく心に迫るものを感じて、今更のように、胸が熱くなるのを覚えた。 (いや、まだ、油断はできぬ……!) トゥパク・アマルは内心で呟くと、懐から例の酒場から取り寄せた地下道の地図――無数の網の目のような線が、くもの巣のように精巧に書き記された図――を、広げた。 脇に立つイポーリトが、松明を父から受け取り、その手元を照らす。 トゥパク・アマルは地図を片手にしたまま、暫しの間ミカエラの腕にいたフェルナンドを、再び、その逞しい腕に抱き上げた。 フェルナンドは深い安心感と高揚感からだろうか、地下水路の冷たい水に浸りまでしたのに、あれほどの高熱もいつしか下がり、ずいぶん楽そうな表情になっている。 そんな息子の様子に目を細めると、彼は前方に真っ直ぐ視線を戻した。 トゥパク・アマルは、地下道の道程に意識を集中しながら、一行を正確に先導しはじめた。 地下道を進み続ける彼ら家族に混ざって、ブツクサ呟きながらも共に進んできたセパスは、いつしか、自分が最初に進んできた道筋から違ったルートに入っていることに、ふと気付いた。 松明を掲げていようが、ほんの一寸先は濃密な闇に閉ざされた迷宮さながらの地下道ゆえ、果たして、いつから異なる道筋に入っていたのか、セパスには検討もつかなかたったが、急激に嫌な予感に憑かれ、彼はトゥパク・アマルを険しい眼で睨み据えた。 「おい…!! 道を間違っていないか? 来る時は、こんな道、通った覚えがないぞ!!」 トゥパク・アマルは相変わらずの沈着な面差しで、セパスを一瞥すると、ふっと微笑んで、「ほお…よく気付いたな」と、感心したように応えた。 「!――なに? やっぱり…! どういうことだ?!」 いきり立って再び噛み付きはじめたセパスを見もせず、トゥパク・アマルは淡々と応える。 「そなたが地下道に入ってきた出入り口のあるサクサイワマンの砦界隈は、恐らく、今頃、スペイン軍で埋め尽くされていることであろう。 我々が地下道を通って逃亡しているとまでは、さすがに敵方も気付いてはおるまいが、クスコから逃亡するには、あの砦界隈を通るはずだと踏んでいるはずだ。 だから、あそこから外界に出ては、わざわざ、囚われに行くも同然」  「じゃ…っ、どこへ…?!」 憤激と、にわかに強い不安に襲われて、セパスが声を荒げる。 「おいっ、言え!! どこへ向かっているんだ?!! 俺は、こんな薄っ気味悪いところは、これ以上ごめんだ!! すぐに外に戻してくれっっ!!」 「―――そうはいかぬ。 クスコを離れるまで、このまま地下道を進む。 もちろん、セパス、そなたも我らと共に行くのだ」 「!!!」 愕然と絶句するセパスの周囲で、ミカエラや息子たちも、ハッと息を詰めている。 トゥパク・アマルは、そんな皆の表情を「案ずるな」と頷いて見渡し、「クスコのどこに出ようとも、今は危険すぎるゆえ。それは、そなたにとっても同じだぞ、セパス」と、穏やかな声で続ける。 「この秘密の地下道は、かつてインカ帝国時代、チャスキ(飛脚)が皇帝からの重要な伝令を携えて、クスコを拠点に国中のあらゆる地域に走った道でもある。 ゆえに、クスコの地下に張り巡らされているだけでなく、国中の様々な地域に延びているのだ」 「確かに…」と、ミカエラは夫の話に頷きながらも、つっと言葉を切って、思慮深げな眼差しになった。 「わたくしたちの脱獄を知ったスペイン軍は、クスコのあらゆる場所で、くまなく捜索していることでしょう。 地上は、どこも、あまりに危険。 もし、このまま地下道を使ってクスコを離れられるなら、それに越したことはないけれど……」 松明の光を受け、輝くように闇に浮き立つミカエラの姿は、全く、どこにあっても女神さながらに美しく、凛然としている。  暫し間を置いて、彼女は続けた。 「だけど、このままクスコを離れるまで地下道を進むとなると、かなりの日数を要するはず。 食料も水も、何も準備の無いまま進むわけには…。 どこかで、何とかして、調達する方法を考えなければならないわね」 「そなたの言う通りだ」 トゥパク・アマルは頷くと、やがて、地下道の脇に少しそれた所に備えられた小部屋のような中に入っていった。 「ここは?」 トゥパク・アマルに続きながら、他の4人が周囲を見渡す。 そこは、地下道の造りと同様の精緻な石組みの壁に四方を囲まれた、10メートル四方ほどの正方形の部屋である。 「大小様々な小部屋が、この地下道の随所に備えられている。 部屋によっては、本当に、インカ帝国時代の財宝が、今も密かに隠されているのだ」 「だけど、ここには、あいにく財宝は無いみたいだね! ガランとしてる!!」 少年らしい好奇心と冒険心に溢れた瞳を輝かせて部屋中を見回しているイポーリトの肩に、トゥパク・アマルは微笑んで腕を回し、片腕にはフェルナンドを抱いたまま、壁際の一隅へと息子たちを誘(いざな)っていく。 「確かに、ここには財宝は無いようだ。 だが、今の我々にとっては、むしろ財宝よりも嬉しいものがあるのだよ、イポーリト、フェルナンド」 見れば、部屋の一隅に、5つの大きな袋のような鞄が置かれている。 「あなた、これは…!」 「父上!! これって、何かの魔法なの?!」 ミカエラも息子たちも、皆、瞳を輝かせ、驚きと歓喜の声を上げた。 案の定、それらの荷の中には、大量の保存食や水などの飲食料、寝袋や薬などの野宿をするための装備、ランプや油などの地下道を歩むための備品が整えられ、なんと、護身用の拳銃や剣までが添えられている。 さらには、当然のように、着替えとしての新たな衣服や防寒具も、しっかりと5人分――それは、とても真心のこもった、気の利いた準備であった。 (あの痒いところまで配慮の行き届いたマスターらしい備えだ…――) トゥパク・アマルは、荷を吟味しながら、切れ長の目を細めて頷く。 彼は、すっかり目を丸くしている周囲の皆を、穏やかに見渡した。 ミカエラの、美麗でありながらも常に鋭いほどに凛々しい目元も、今は、本当に魔法にでもかかったように呆然と大きく見開き、すっかり愛らしい面持ちになっている。 トゥパク・アマルは、そんな妻の様子に、思わず、くすり、と笑う。 「いや、なに…番兵リノに手紙を託した際、これらの荷も、ここに備えておいてもらえるよう、外界に依頼しておいたのだよ」 それから、すっかり興奮している息子たちを交互に見渡しながら、肩を竦(すく)めて微笑んだ。 「残念ながら、魔法ではないのだがね」 そして、最後に、完全に絶句して茫然自失しているセパスに視線を向けた。 「セパス。 そなたには気の毒だが、もう暫く、このまま我々と共に進んでもらう。 今、そなたにクスコに戻られては、我々の身も危険だが、そなた自身の身も守りきれぬ」 「……――」 セパスは、もはや骨の抜けたように、その場に脱力して、へたり込んだ。 かくして、完全な装備も手に入れた5人は、そのまま、地上で血眼になって彼らを捜索しているアレッチェや敵軍団をよそに、本格的にクスコを脱出すべく地下道を進んでいった。 ◆◇◆ここまでお読みくださり、誠にありがとうございました。続きは、フリーページ第八話 青年インカ(10)をご覧ください。◆◇◆ ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
|