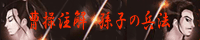☆「危機管理」批判
☆「危機管理」批判
「危機管理」という言葉は、湾岸戦争の時にはじまり、阪神淡路大震災のころから、一般にも流行した言葉である。
何か大きな事件が発生した時に、当局が初動の対処を誤ると、「危機管理がなっていないじゃないか」と非難の声があがる。
しかし、非常に残念なことであるが、「あなたの言う危機管理とは何ですか」と反問すると、ほとんどの人々が「危機管理」の意味がわかっていない。
市ヶ谷に行こうとしている人が、市ヶ谷が東京都内のどこにあるか知らなかったら道に迷うばかりである。
そのように危機管理が何であるかを本当は知らない人々が「危機管理はどうなっている」と感情的な非難をしているのは、本当に奇妙な光景である。
ここで私は、《天地自然の理》という考え方を使う。これは別に難しいことではない。
天は上、地は下、水は上から下に流れる、雨が降ったら傘をさすといった当たり前のことが、非常時には頭が混乱してわからなくなるのである。
そこで非常時に指導者が冷静な判断を下すために、必要な平常心を具体的な形にすれば、≪天地自然の理≫となるのである。
もっと生々しい具体的な例をあげよう。
阪神大震災の時、神戸市は市長が市庁舎に丸一日不在だった。
そこで地震の後、二時間ほどで出勤してきた課長以下の幹部に不幸にも緊急かつ重要な判断が押し付けられることになった。
その後に市内全域で大火災が発生することになったが、その最大の原因は地震の後に都市ガスが停止しなかったこと、逆に水道がストップしてしまったことである。
ガス会社は市役所から停止の要請が来るのを待っていたが、市役所の幹部は「今は自分には判断ができない」と何度も回答を拒否していた。
ガス会社も冬の寒い時にガスの供給を停止すると、損害賠償が発生するから、市役所の上からの要請を待っていたのである。
こうしてお互いの責任逃れと押し付け合いで時間が過ぎ、その間、ガスは市内各地のガス管の亀裂から勢いよく噴出していた。
火災が燃え広がってから、その事実を知った大阪ガスのトップが自社の判断で停止したのである。
しかし、時はすでに遅かった。
倒壊家屋の下敷きになった多くの人々が、救出の手も差し伸べられないまま、あの大火災で焼け死んだのだ。
どうしてこんな非常の時に当たり前の決断が下せないのか。
それが非常時なのである。
人々は災害と被害を目の前にすると、重大な責任を回避し、逃げ回り、何でもないような決断さえ躊躇してしまう。
そこで瞬時に出すべき決断を、まるで平常時のように「明日までに検討しよう」という感覚になるのである。
責任を回避し、決断と実行を遅らせる結果がどのような残酷と悲惨をもたらすものか、想像さえつかなかったわけだ。
特に神戸市の水道局が水道を直ちにストップしたのは、まさに≪天地自然の理≫に逆行するものであった。
その理由はといえば、「大きな地震の時には、水道を停止して、水道管の亀裂や破損の状況を点検調査してから、水道供給を再開する」という業務マニュアルがあって、それで何度も平常時に災害訓練を重ねていたからである。
ここで気がつくことは、その災害マニュアルそのものに重大な欠陥があったこと、すなわち、水道局内部の施設の問題や組織の御都合だけを考え、水道局の想定に反するような都合の悪い事態は起こりえないと《捨象》されていたことだ。
この一点こそ、われわれは深く追及しなければならない。
そのために、大きな地震の後には必ずといってよいほど火災が発生し、緊急に大量の水道供給が必要になるという、少しばかり冷静に考えれば、ごく当然の事の成り行き、つまり天地自然の理を全く想定していなかったことになるのだ。
タンクの穴は上のほうにあっても満水になると漏水の原因になる。
目前の危機が深刻であればあるほど、対応の甘さや事前の想定ミスは破局的な結果をもたらすことを、われわれは肝に銘じなくてはならない。
水道停止の判断を下した水道課次長は、地震発生から六時間を経過した昼ごろになって、市内各所から「どうして水が出ないのか」という苦情が殺到していることに憂慮した部下から事実を指摘されて、やっと自分の思い誤りとマニュアルの欠陥に気づいたらしい。
しかしながら、部署の担当課長が昼過ぎに会議に出てくるまで、次長は自分の判断の撤回はしなかった。周囲の部下はこの人の行動をすべて見ていた。この人は数日後に、自責の念から自殺したが、勝手に死ねばいいというものではない。
≪天地自然の理≫からすれば、神戸市民は無数のガス管の破裂と、道路下の水道管の破裂と、どちらが選んだかがあのような非常時にもわかったはずだ。
消防局も「水が出ない」ということで立ち往生していた。
住民が「川の水を使って消火してくれ」と要請をしたが、「ドブ川の水を家屋にかけたら、後の始末が大変になるから」ということで、それは実現しなかった。
そんな水カケ論ばかりして動けないでいる間に、火炎は燃え広がり、商店街すべてが焼きつくされたのである。
普通は防火用として貯えてあった小学校のプールの水も、一滴も使われなかった。
その理由は、プールは小学校の校舎の防火用に冬でも水をはってあるのであるから、近隣地域の民間の火災で使用されるのは困るというのだ。
そんな愚かな理屈を言っている担当者も、自分たちが実際に罪深い責任逃れをしていることはよくわかっているようであった。
こんな絶望的状況に追い込まれたのは、確かに「大火災時の水道停止」という明らかな人災による異常事態の結末に他ならない。
しかし、私が思うに、最大の原因は最高責任者が不在で、各部署が独自の判断を下してしまったことにあると断定せざるをえない。
全責任を負うべきなのは神戸市長であり、兵庫県知事である。
地震直後に女性の市長が、自転車で市庁舎に駆けつけて、職員全員に緊急召集をかけた芦屋市内では、深刻な火災は起きていない。
地域の消防団が地震直後から活躍した淡路島でも土砂崩れは起きたものの、大きな火災は起きなかった。
これが全てを物語っているであろう。
指導層がちゃんといても、やはり非常時に≪天地自然の理≫に反する判断を下していると失敗する。
最初に紹介した日露戦争の旅順要塞攻撃であるが、第二次総攻撃の時点で第三軍参謀本部はロシア軍が機関銃と手榴弾を使用して、日本軍は連隊が全滅するような被害を出していることにも、もちろん気がついていた。
けたたましく突撃ラッパを吹くことが、敵軍に攻撃を事前に知らせる逆効果を生じていることも発見していた。
もっとも、最初からこんな簡単な理屈がわかっていれば、死傷者の犠牲は相当軽減できたであろうが、それは人事担当者が作戦参謀のメンバーの人選を誤った結果だと言わねばならない。
彼らはいくつか機関銃の実物も捕獲して、試射も行なっていた。
そこで参謀たちが出した結論はこうであった。
「機関銃の性能から考えて、一つの機関銃は十人以上の兵士の一斉射撃には及ばない。したがって、各部隊が攻撃目標を集中し、十字砲火を浴びせて勇猛に突撃すれば、機関銃は問題とはならない。要は将兵の敢闘精神である」
それで第一次攻撃のように波状的な突撃をくりかえして、失敗したのである。
ロシア軍の兵士が機関銃を仁王立ちして射撃していたら、この計算は当たっていたであろう。
しかし、ロシア軍は二百メートル以上の丘陵の上に、セメントで固めたトーチカ(永久堡塁)を建設し、その小さな銃眼から機関銃を撃つのであるから、百人の部隊が村田銃のような鉛管弾の旧式のライフルで、一つの銃眼をめがけて一斉射撃しても相手を倒すことなど不可能であった。
「銃眼」というものは、戦国時代末期に建設された皇居の桜田門にもあるので、当時の作戦参謀たちが全く知らなかったとしたら、亡くなった兵士たちも浮かばれまい。
見るに見かねたイギリス軍の観戦武官が「前線の兵士には鉄板を持たせて、機関銃による無駄死には回避すべきだ」とある参謀に耳打ちしたので、第三次総攻撃には一部の部隊で鉄板の配布がおこなわれたが、それでも全部隊には行きわたらなかった。
第三次総攻撃の口火を切ったのは、全員志願兵による「白襷隊」の夜襲突撃であったが、夜間攻撃であるにもかかわらず、その名前の通り、身体に白い幅広の襷を十字にかけていたので、暗い闇の中でも非常に目立つ格好をしていたと思われる。
特に急所の心臓には、襷の十字が当たっていたので、ロシア側にしてみれば、まるで大きな標的が歩いているようなものだったであろう。
この時の作戦立案担当者は「相手がどう見るか」という想像力も枯渇していたのである。
売れないスーパーマーケットで、「お客さんがどう見るか」という配慮もなしに、しおれたホウレン草を「新鮮野菜」のラベルをつけて定価で陳列するようなものである。
もともと無謀な突撃作戦であったが、情状を酌量をするとすれば、この当時の人々は迷彩服のようなカモフラージュの必要性は知らなかったし、江戸時代の武士の伝家の甲冑のように、国家から支給された正規の軍服を脱いで戦死するのは恥辱だと考えていたのであろう。
白襷隊は突撃後に、数時間でロシア軍に発見され、照明弾と探照燈(サーチライト)を浴びせられ、たちどころに大多数が絶命し、殲滅された。
ロシア側に発見された時、現場責任者の部隊長本人が臆病風のために、真っ先に「探照燈だ。伏せろ、伏せろ」とヒステリックに大声をあげたのも失敗であった。
すでに第二次攻撃において突撃ラッパをやめた理由が、この人物には全くわかっていなかったのだ。
伏せるにも身を隠すことができないところなのだから、さっさと移動すれば、その場の死傷者も少なくなったかもしれないのに、伏せたままだったから、丘の上から串刺しのように機銃掃射を浴びたのである。
兵士たちは、このトチ狂った上官の無意味な絶叫のおかげで、生命を奪われたも同然である。
しかし、この部隊長は負傷して帰還し、その英雄的な行為で賞賛され、勲章を受け、少将から大将まで昇進した。
後に東京市内で、小さな子供を馬車でひき逃げし、たまたま現場にいた大蔵省専売局長浜口雄幸(後に首相)の夫人が、抗議にも立ち会ったので、再び汚名を歴史に記録されることになったが、このことからもこの人物の存在が国家にとって有害無益であったことがわかるのである。
この当時に、ロシア側にもなかった鋼鉄製のヘルメットの支給はムリだったとはいえ、横になって機銃掃射から身を守る1メートル四方の鉄板が、もっと早く事前に全部隊に配布されていれば、旅順要塞の攻撃にこれだけの犠牲は出なかった。
これを簡単に考えれば、「雨が降れば傘をさす」ということなのだ。
知ったかぶり野郎が、言葉だけ「危機管理」などとノウハウ知識で突っ走ってもダメだ。
現場を指導するには、遠くの親戚より近くの他人を頼り、明日のケーキよりお昼の握り飯を心配し、現実・現地の事情を洞察・斟酌して瞬時に決断することだ。
こうした課題で、私がよく学生たち、院生たちに推奨する参考図書は、イギリスのハードボイルド小説家フレデリック・フォーサイスの傑作≪ジャッカルの日≫である。
フレッド・ジンネマン監督で映画化もされており、名作ビデオの一つとしてビデオ・レンタル店には必ずあるものだ。
ちなみにジンネマン監督は助監督の時代に名作「ベン・ハー」の制作も経験している。
話は1962年にフランスのドゴール大統領が国民の世論を押し切って植民地のアルジェリア独立を認めたことで、軍内部の強硬派と植民地の権益を持つ人々がドゴール暗殺を計画するところから始まる。
ここまでは実話で、小説では「ジャッカル」という暗号名を持つ暗殺のプロフェッショナルが登場し、イギリスのロンドン・イタリアのジェノバ、フランスのニース、そしてパリと舞台を次々に移動し、何度も変装や偽造の身分証明書を使い分け、生存競争のように冷血非情の殺人を繰り返して目的地のパリにたどりつく。
映画で観ると、さらにオーストリアのウィーン、ローマの街頭などに舞台は転々とし、大英博物館の中央図書館では「ジャッカル」が記録書類を検索する数秒のシーンが出てきたり、ヨーロッパ旅行の経験がある人はもちろん、はじめて観る人にも緊張で息をつかせないほど面白い。
≪眠狂四郎≫シリーズで知られる時代劇作家の柴田錬三郎という人は一読してこの作品のトリコになって、わざわざ「ジャッカル」の足取りを追体験したというが、実は私も学生時代に柴錬さんの後を追いかけてジェノバからパリまで放浪旅行をしたことがある。
この小説で「ジャッカル」は、偽名申請で取得したパスポートで若づくりした33才ぐらいの金髪のイギリス人ポール・ダカンになりすまし、その事実がライバルのパリ警視庁のクロード・ルベル警視に押さえられると、今度は背格好の似たデンマーク人の教師から盗み取ったパスポートで、黒褐色の髪をしたペール・ルンクイストに変装する。
それも相手につかまれると、さらに白髪で足の不自由な老人に変装して、暗殺の現場として選定した解放記念広場の向かいのマンションにたどりつく。
もちろんフィクションであるから、ドゴール大統領暗殺は成功せず、直前なってに警備がノーマークのマンションで最上階の窓が開いていることに気がついたルベル警視がようやく現場に踏み込んで、ついに「ジャッカル」は射殺される。
すでにジャッカルはイギリス紳士の服装に着替えて、すぐ空港で他国に逃亡できるような姿をしていた。
背が小さいレジスタンス運動の功労者に勲章を授与するため、長身のドゴールが背をかがめて相手に敬礼のキスをしたことが、「ジャッカル」の狙撃弾がはずれた理由だったと設定してあるのは、著者のフォーサイスの天才的なウィットである。
注目すべきことは、「ジャッカル」が眼に見えないライバルの出方を予測して、あらかじめ多くの「布石」を打っておくプロフェッショナルの思考が光り輝く場面である。
ビデオを何度も見ないと細かいところがわからないと思うが、墓場を散歩して、自分と同世代で三歳で死亡したポール・ダカンの墓碑銘を見つけ、その出生証明書や戸籍関係の必要書類を手に入れ、パスポート申請の手紙を送る。
変装のためのヘアカラー染料を普通の店で買ったり、有名なパリの「蚤の市」で古着を探したりする。ロンドンのヒースロー空港で入国手続をするデンマーク人のカバンからパスポートを抜き取るところなど、国際的な犯罪組織に常にマークされているわれわれ日本人も注意しておかねばならないところだ。
そして、この「ジャッカル」の行動に加えて、ストーリー展開を面白くしているのが、エレキュール・ポワロ警視の再来かと思われるほど、頭が切れるルベル警視の推理探偵ぶりである。
この「知恵の追いかけっこ」が暗殺ストーリーにサビを利かせているわけだ。
これは著者フォーサイスがイギリスやフランスの政府機構や軍事組織について、詳細かつ微細にいたる知識を披露しつつ物語の構成を「借景図法」で拡張しているからで、映画ではフランス政府やイギリス政府の協力を得て、本当の大統領官邸・エリゼ宮殿の内部や、内務省・パリ警視庁を伝令のバイクが往来する様子、刑事役の俳優がロンドン・ダウニング街の首相官邸に出入りするところなどに現場の実写が使われている。
内務大臣の特命で全権をゆだねられたルベル警視はまずヨーロッパ全ての警察幹部に通じる直通電話を用意し、若い助手を使って、国際的な警察機関の情報ネットワークをつくりあげる。
イギリス警察庁(スコットランド・ヤード)は協力に消極的だが、フランス政府から正式要請を受けたイギリス首相がスコットランド・ヤードに直接指示の電話を入れて、猛烈に動き出す。まず幹部が仕事の全体方針を論理的に説明して、部下に「あとはこの方針通りに徹底的にやるだけだ」と説得する。
これは別の名画≪戦場にかける橋≫でも観られるように、イギリス軍の伝統的指揮法と同じ方法なのだが、イギリスのチーム・スポーツであるラグビーでも同じ作戦指揮法が取られている。
それは英国貴族の伝統儀式でもある「キツネ狩り・フォックスハント」に由来するもので、この大切な「狩猟儀式」を通じて、イギリス貴族の子弟は古来伝統のリーダーシップの技法を学んでいく。
そこには古代ローマ帝国から連綿と続いてきた起源がある。ただイギリス人のフォーサイスにとってはありきたりのものなので、「陳腐な人海戦術」というカリカチュアとしてごく短く出てくるところである。
首相命令とあって、イギリスの諜報機関もスコットランド・ヤードに協力し、国際的なテロリストの中で、ドミニカの独裁者トルヒーヨを暗殺したという噂のあるイギリス人の貿易商チャールズ・カルスロップの名前を上げてくる。名前のつづりを縮めたCha-Cal=Chacalは、Jackalのフランス語風の読み方に通じる。このあたりの推理は、まるでクロスワード・ゲームのようだ。
「ジャッカル」を追うルベル警視に対して、「ジャッカル」に大統領暗殺を依頼したOAS(アルジェリア植民地機構)のメンバーは、女性スパイを内務省の最高幹部に送り込んで、「ジャッカル」の捜査状況を逐一通知させる。
最終的にはルベル警視も関係者すべての「盗聴」を実施して、女性スパイと愛人関係で同棲していた幹部を洗い出す。息詰まるような双方の作戦と作戦のぶつかり合いの中で、「ジャッカル」は布石を打って準備した変装やさまざまな小道具を使い、ルベル警視の捜査網をくぐりぬけていく。
これは「ジャッカル」の戦略が、ルベル警視の戦術を上回った勝利である。
最終的な結果は、たまたまドゴールの強烈な運命が、ジャッカルの不運に荷担したといえなくもない。
≪ジャッカルの日≫は基本的に犯罪者を主人公とする物語であり、「ジャッカル」も結局は運命と正義の制裁を受けるわけだが、これらをくりかえし検討すると、いわゆる「Executive Actionsエグゼクティブ・アクション」という≪国際標準・グローバルスタンダード≫が見えてくる。
世界で一流の人々は、どのような行動パターンをもって生活し、ビジネスや趣味で活躍しているかをイギリスのパブリック・スクールに行かなくても習得することができる。
このような≪生きる時間の使い方≫を知ることが、実は戦略とは何かを考える上で最も重要である。
それはいわば、「生きる時間の哲学」ということだ。