
|
|
|
カテゴリ:カテゴリ未分類
 これは、もうだいぶ前の早朝、屋上、どこにも出掛けなくても「バード・ウォッチング」(笑)、目の前で、「ばっちりやってね」と鳴いてくれた、シロガシラ(ヒヨドリ科)  捕まってしまったバッタ君の恐怖を思い浮かべると、身も縮む思いだが、普段もっぱら「果実食」のこの鳥が、こんな動物性たんぱくを要するのは、「育雛期」、だからなのである。シロガシラ(ヒヨドリ科)  階段を下りて、郵便受けを見に行く、もちろん(笑)、何も来ていない。昔読んだガルシア・マルケスだったと思う、「大佐に手紙は来ない」という短編があった。郵便を運ぶ船が着くたびに波止場まで出かける「大佐」の話だった。で、そんな風にどこにも出掛けなくても、お隣の垣根に咲いている、ヘクソカズラ(アカネ科)。    またしても、トイレの窓から(笑)、絶叫メジロ(メジロ科)。先日来のものと、「同一個体」なのか?気になるところだが、やっぱり、写真を拡大してみても、わからない。「舌切り雀」などと言う昔話が存在するのは、昔の人が、こんな小さな鳥にも、私たちと同じような「舌」があることを、「見て」、「知って」いたからに他ならない、ということに気づく訳だ。 目次:「国際共産主義運動」そのものが、負った、一つの「トラウマ」体験、について/絶対「負けない」議論です。そこが「トートロジー」に似ている、と思ったんです/ようやくこの最終章に来て、「共感」に似たものをもつことができたのも、・・・「夜明け前」読了/ハルツームから伝わるその記事/「方丈」、とは?/「まことの人の形なり」、浮舟と横川の僧都/「黄色い本」、の探究/世界には、しかし、「失うもの」を何一つ持たない人々が、数多存在していることを、私は知っているから/「誰がために鐘は鳴る」、読了/「ビーグル号航海記」、「南方郵便機」、「悲しき熱帯」  旧暦五月九日の月。 今、調べてみて、思い出しました。その映画、私も観ましたよ。きっと、そのときには「感動」したはずなんだが、おぼろげにしか覚えていないのは、おそらくそのときには、ジョージ・オーウェル「カタロニア賛歌」を既に読んでいて、一応、その従軍記を「ベースにしている」とうたわれたこの映画の、「この細部が違う」、などと言う「不満」があったからかも知れません。 せっかく、いい話を持ち出してくださったのに、あるいはそれに冷水をぶっかけてしまうことになるやも知れないことを恐れますが、「スペイン内戦」は、掲げられた「理想主義」に比して、その結末、ただ「敗北」しただけではない、その「敗北」にいたる、あらゆる道程に、裏切り、内紛、猜疑、陰謀、およそ想像しうるあらゆる醜悪なものが凝縮していて、数多の人々が、必ずしも「敵」ではない者の手で、殺害されたり傷つけられたりし、関わった人々の記憶の中にも、終生、消えることのない傷を残してしまった、「国際共産主義運動」そのものが、負った、一つの「トラウマ」体験だった、ことが、たとえば、私なんかにとっても、いまだに関心を持ち続けてしまう、根拠なんですね。少しも傷は癒えていない、と言えるのは、その後の、今日にいたるまでの、あらゆる、「第三世界」、アフリカ、中米、東南アジア、中東、の「民族解放闘争」には、この「トラウマ」が、影を落とし続けていた、とさえ思えます。「冷戦」時代の、「代理戦争」は、米ソがそれぞれ軍事援助をするゲリラ組織同士が、「現地人」同士が、「血で血を洗う」、「内戦」として戦われましたが、アメリカが「資本主義」、ソ連が「社会主義」を代表していた?とんでもない、そんな単純なものでは、全然、なかった、同じ「マルクス・レーニン主義」を掲げ、「民族解放」を標榜する組織同士が、「敵」以上に激しく敵対し、あるものはソ連に援助を求め、ソ連の「介入」を嫌うものは、中国に頼り、アメリカは、ソ連との対抗上、中国派を支持する、そんな「利害関係」が錯綜する中では、誰が真・に・人・民・の・利・益・を・代・表・し・て・い・る・か・?、という、疑いもなく正当な問いにさえ、にわかには答えられなかった。 1930年代初頭、ドイツでは、「国家社会主義ドイツ労働者党Nazi」が、イタリアでは「ファシスト党」が台頭、ソ連では、スターリンが、かつてのロシア革命時の「盟友」のほとんどすべてを、失脚に追い込み、独裁を実現しつつあった。「赤軍」の創設者トロツキーが、現・カザフスタンのアルマ・アータに流刑に処せられるのが、1926年、コンスタンチノープル(現・イスタンブール)への追放の四年間を経て、ようやくヨーロッパに戻り、スターリン派に対抗する「左翼反対派」の国際組織、「第四インターナショナル」の創建に着手するのが、1933年。ヨーロッパの南西の辺境、スペインでは、カトリック教会と、大地主層が、諸・王党派と結びついて強大な権力を手にしていた。それに対して最も強力な組織的抵抗を示したのも、これも他のヨーロッパ諸国とは大きく異なり、もっぱら、19世紀の「第一インターナショナル」時代に、マルクス派に叩き潰された、とも思われていた、プルードン、バクーニン、クロポトキンに始原する「無政府主義者・アナキスト」だった。 ここに一人の軍人、フランシスコ・フランコが、「労働者革命」を恐れる地主階級、僧職者の支持を集め、植民地モロッコで挙兵、これが「内戦」の開始を画することになる。「ファランヘ党」、「矢を束ねると折れることはない」、と、まるで毛利元就の様ですが、そういう「結束」という意味を持ったスペイン語ですが、これはイタリア語の「ファッショ」と同根だった筈です、と彼らは名乗ることになる。これに対抗して首都のマドリッド、及び、最先端の工業・商業都市であったカタロニア・バルセロナの、「共和国」を守る、「労働者」部隊の圧倒的主流派は、アナキストCNT(全国労働総同盟)、ついで、社会党系のUGT(一般労働組合)、これに対して「スペイン共産党」は、ほとんど影響力をもっていなかった。 「内戦」開始に伴い、ヨーロッパの先進国、フランス、イギリスは、ファシストの台頭に反対を表明する、という言葉とは裏腹に「不干渉政策」を採用、従って「労働者」派は、武器、弾薬をはじめ、必要物資の調達にも、規制を受けることになる。フランコ派・ファランジストの陣営には、それぞれに性格は異なるものの、同じく「ファシスト」国家群の同盟、ということで、ドイツ、イタリアからの、潤沢な援助が流入し始める。この段階で、既に、スターリン独裁に関するネガティブな見聞、まもなく頂点を迎えることになる「大粛清」の予兆はあったものの、西欧各国の「共産党」に対する「コミンテルン(第三インターナショナル)」・ソ連共産党の、権威はまだまだ絶大なもので、国家としてスペインの「左派・労働者派」を支援しうる力を有した唯一の当事者として、揺るぎない地位を占めることになる。 後の歴史学者の考証にも、諸々の見解の相違があるので、確言はできないものの、この段階でスターリンは、ファシスト国家群を、軍事的に打ち負かすことは、全然考えていなかった、とも言われる。数年後の「独ソ不可侵条約」という世界中の共産主義者を困惑に陥れた、ファシスト陣営との妥協と同じく、もはや、「プロレタリア革命」よりも、「ソ連」という「一国社会主義」の存続を、優先させる、という意向だった、少なくとも、反・スターリン派の目にはそう見えました。事実として、既に急速な工業発展を経験していたソ連からの、潤沢な物資、軍備、軍事顧問団の流入は、スペインのファランジストとの軍事バランスを、好転させる部分は大いにあったに違いない。しかし、それ以上に、「共和国」政府内で、前述のようにほとんど影響力を有していなかった「スペイン共産党」に肩入れして、圧倒的主流派であったアナキストCNTを追い落とし、同時に、レオン・トロツキー、ヴィクトル・セルジュなど、スターリンの手によって、追放を余儀なくされた「左翼反対派」にシンパシーをもち、独自の「義勇軍」を送り込んで、アナキストと連帯して闘おうとしていた、西欧の弱小な「独立」共産党の勢力をも、「パージ」することに、むしろ、より大きな力を注いだ、とも思えます。 こうして、「スペイン内戦」を描く、しかも、「貧しい農民・労働者に連帯して」闘ったと称する人々の、膨大な数の、文学、映画作品、が、とても「残念」な事態とは言えますが、くっきりと、少なくとも「二つの」、相互に妥協がほとんど不可能な、部分に、分かたれてしまうことになるのです。 あなたがご紹介して下さった、「大地と自由」Land and Freedom(1995)/Ken Loachは、そのインスピレーションを、ジョージ・オーウェル「カタロニア賛歌」から得ている、と言われている。主人公がPOUM(マルクス主義統一労働者党)の「義勇兵」であることからも、それは見てとることができる。このスペインの弱小政党は、結局第四インターナショナルに加盟することになったかどうかははっきりしませんが、トロツキーへのシンパシーを表明し、明白に反・スターリン主義を標榜しています。ジョージ・オーウェルは、ソ連派の「イギリス共産党」ではなく、ILP(独立労働党)の紹介を求めて、従軍しているのですから、もちろん、明白に「反・スターリン主義」という「党派性」を固持していたと思います。今調べてみると、ケン・ローチKen Loach(1936-)という映画監督は、1960年代、から1970年代にかけて、労働党の、あるいは、おぼろげな記憶では「ミリタントMilitant」と呼ばれる左派の活動家だったようで、後には、イギリスの「新左翼」とも言うべき社会主義労働者党Socialist Workersにも関与しているようで、つまり「正統派」の「共産党」からは、「私たち」と同じく(笑)、「トロツキスト!」と罵倒される陣営に属していたことになります。 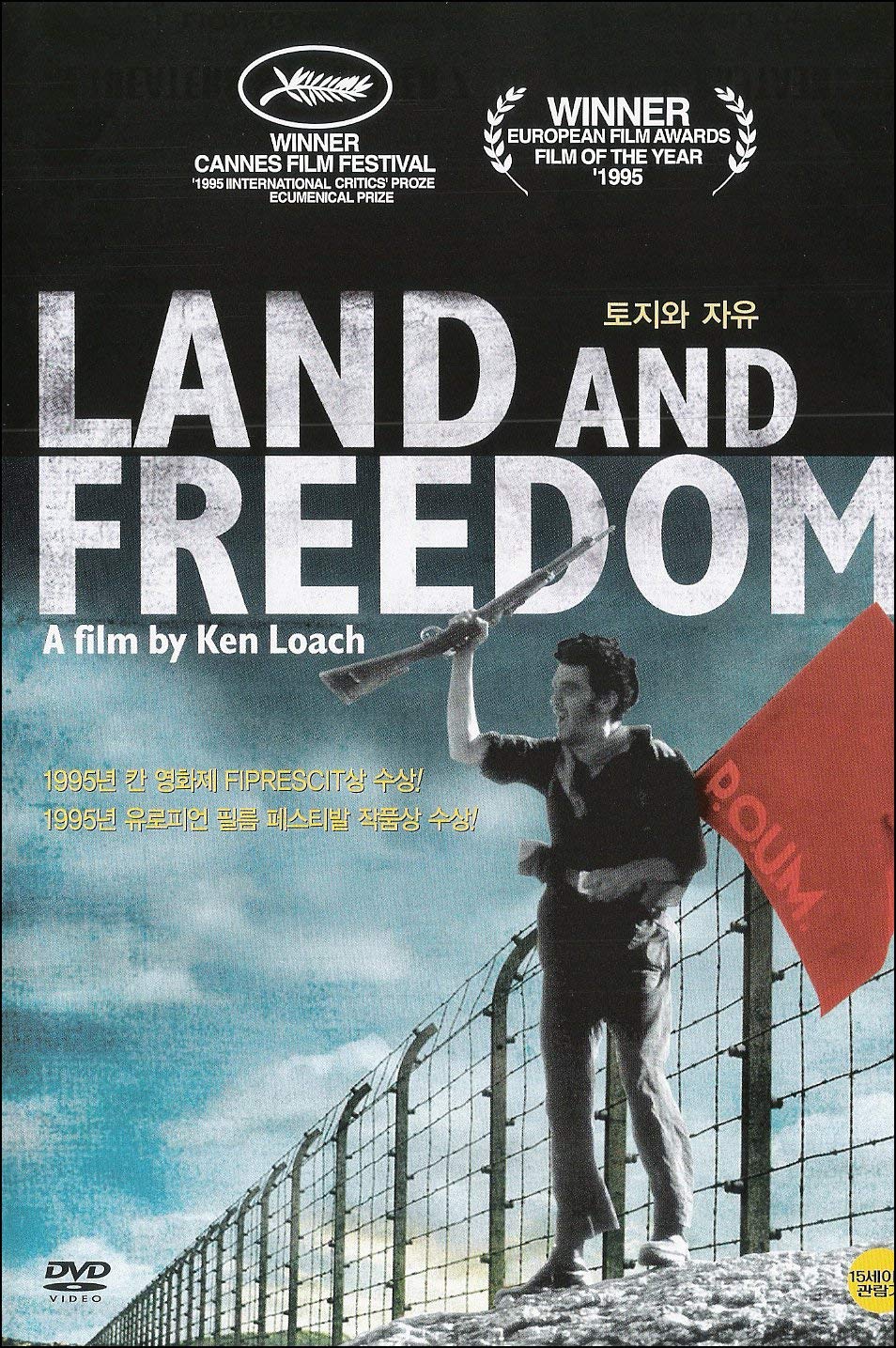 「大地と自由」、DVDアマゾンで探したが五千円もして手が出ない(笑)。それにこれ韓国語字幕版みたい。赤旗に、ちゃんと「POUM/Partido Obrero de Unificación Marxista」って読み取れるのが、嬉しくなった(笑)ので、ご報告。頑固老人らしい(笑)難癖をつけますが、この邦題はいただけない、Land and Freedomというスローガンの、「land」は、所有権、耕作権の対象となる「土地・耕地」なのであって、日本語の「大地」がともすれば含意するようなロマンチックな要素は、あまり、ない、しかし、配給会社が、その、ロマンチックな、方が「売れる」と感じたのだろうし、事実その通りだったのでしょうが(笑)、スペイン内戦は、まさに、大地主とカトリック教会が占有していた「土地所有権」を耕作する人民に解放し、これを、どう、「分配」するか、アナキストは「共同所有」を主張し、おそらく「共産党」は、「ブルジョワ革命」と規定してこれに反対し、「個人所有」に押しとどめようとしたであろう、人々が流血によってでも解決しなければならない、と感じた「争点」は、まさにそこにあったのですから。 「コミンテルン」・ソ連共産党は、各国のコミンテルン加盟の共産党を窓口として、「義勇兵」を募り、「国際旅団International Brigade」を編成します。アメリカの、既に作家、ジャーナリストとして名声を確立していた、アーネスト・ヘミングウェイは、ここに参加します。リリアン・ヘルマンという劇作家も、短期間ですが、そのプロパガンダ放送部門の支援のためにスペインを訪れたりしています。「国際旅団」は、既に十年以上にわたる自国の「内戦」を経験し、十分に組織力を高めていたソ連軍の訓練と装備によって、おそらく、強大な戦闘力を有していたに違いありません。でも、それは、ある部分、スペイン革命が宿していた「最良のもの」の犠牲の上に成立していたものであることも否定できない。アナキストは、その原理的立場からして、軍隊内の「階級制」など、認めるつもりは、さらさらなかった。彼らは敬礼もせず、同じぼろぼろの軍服を着て、互いを「同志Camarada」と呼び合った。 「スペイン内戦」は、フランコ将軍のモロッコにおける武装蜂起が、1936年7月、最終的に彼が勝利宣言を発する1939年4月まで、戦闘が続きます。そのかなり初期において、既に1937年5月「バルセロナ動乱」と呼ばれる、「内戦のなかの内戦」で、「共産党」が、アナキストCNTとPOUMの部隊を、「粉砕」し指導的位置からは、完全に駆逐してしまいます、もちろん、彼らの多くは、その後も各地に散ってファランジストとの戦闘を継続するのだと思われますが、この過程で、立派な制服に身を包み、上等な武器を支給された、そして、もちろん軍隊内の「階級制」は、厳格に回復されます、ソ連軍事顧問団率いる「国際旅団」の「名声」はいやがうえにも高まり、ヘミングウェイがスペインに到着するのは、その「バルセロナ動乱」直後の時期の様ですが、「誰がために鐘は鳴る」の中でも、統制の取れない、粋がって赤と黒のスカーフ巻いているだけのごろつきども、といった具合に、アナキストの兵士を嘲笑する表現が、いくつも見られます。おそらくあなたが映画の中で感じ取った「爽やかさ」も、それとつながるのでは、と想像しますが、ジョージ・オーウェルは、これとは対照的に、その「統制のなさ」の中にこそ、無論いらいらさせられはするものの、なにか「希望」を読み取っているように思えます。 好きでもないヘミングウェイの、この大作を、読むことにしたのは、そんな風にして、一つの歴史的事件が、「党派性」という眼鏡を通してしまうと、どれほど異なった様相が浮かび上がってしまうのか?という、半ば「悪趣味」ですが(笑)、ある種の「絶望」を味わう必要がある、と感じたからかもしれません。もともと「傲慢」な、そして「傲慢」であることを売り物にするような作家(笑)、とは思いますが、その口ぶりの端々から、戦争は勝たなければ何にもならない、と、「厳格な規律」、「冷酷さ」、「現実性」、などを、持ち上げてみせる一方で、「貧しい者のために」といった、臆面もない「理想主義」が、唐突に挟み込まれたり、その「矛盾」、「裂け目」こそが、それのみが、読むに値する部分だ、と我慢して読み進めているところです。「歴史」の「皮肉」は、どこまでも追ってくるわけで、この物語の中で、ヘミングウェイその人を彷彿とさせる主人公、ロバート・ジョーダンが、ソ連の軍人とおぼしきカルコフという人物が登場し、二人で、語り合う、「裏でファシストと密通している」、「あのPOUMのくずども」などと、こちらとしては(笑)、胸が悪くなるような会話なのですが、その人には実在のモデルがあるようで、ミハイル・コルツォフ、「プラウダ」特派員にして、秘密警察職員だったと言われている。この人は、ソ連に帰国した後、スターリンの「大粛清」を批判する記事を書いたことから、後に銃殺刑に処せられている。また、ヘミングウェイ自体はそれほどひどい事態には至らなかったようだが、アメリカの知識人で、「スペイン内戦」に義勇兵として参加した人々、特に「国際旅団」に参加した人々は、十年後、吹き荒れる「マッカーシズム」にの中で、その行為が「共産党」シンパサイザーであることの証拠として、厳しい弾圧を受けることになる。当時は、コミンテルンの「人民戦線」戦略の下で、米ソは、「反ファシズム」の、「同盟」者であったにもかかわらず。リリアン・ヘルマンの「眠れない時代」は、その事情について語っています。 もう一人、シモーヌ・ヴェイユという若くして亡くなったフランス人がいて、30歳も年上の、亡命中のトロツキーに論争を吹っ掛けるほどの、スターリンのみならず、マルクス主義そのものの批判者、だったわけですが、この人が、スペイン内戦のはじまったばかりの頃に、わずかな期間ですが、アナキストの部隊、ブエナヴェントゥーラ・ドゥルティという伝説的な指導者の名を冠した部隊の一兵士として従軍しています。彼女は、自分が、パリ、という、戦争にとっての「後方」の安全な場所にいるままに、「正義」や、「革命」や「人民の利益」などと言ったことに対して、声高に語ること自体への嫌悪感を、語っていて、それが、「戦争反対者」であるにもかかわらず「志願兵」となった動機なのだ、と言っているように見えます。私事になりますけど、1995年に、神戸が震災に見舞われたとき、私は京都に住んでいた、神戸が特別な場所だったのは、そこが「故郷」だったからかもしれない、十六年後の東北に、同じことが起こったとき、私は沖縄にいて、鈍い心の「痛み」は感じたものの、決して同じように感じたわけではなかったからな。「東北」の時も、おそらく、「現場」から離れた「安全」な場所では、「ベクレル」や「ストロンチウム」などと言う言葉を散りばめた会話が、得意そうに弾んでいたに違いない、「神戸」の直後も、当初の衝撃の沈黙の期間が過ぎ去ると、たちまち人びとは、たとえば飲み屋のテーブル越しに、「活断層」をめぐって、得意そうに議論を始めたりしたものだった。慣れない「ボランティア」などというものに参加しようと決断した動機は、実は、「そんな会話」を、聞いていることが、耐えられなかったからに過ぎない。スベトラーナ・アレクシェィヴィチ「チェルノブイリの祈り」にも、あったが、ここ(チェルノブイリ)では、誰も「チェルノブイリ」の話なんてしない、みんな黙々とスコップを使って土を掻き出すだけだ、・・・、同じように、「戦争」についての「お喋り」が聞こえない、唯一つの場所は、「戦場」なのだろう、ということは想像がついた。 シモーヌ・ヴェイユも、伝えられるところによると、明らかに「躁うつ病」的な(笑)傾向を有していたように思えますが、私自身を振り返ってみても、政治的な「正しさ」の判断に導かれて、たとえば、かつては「三里塚」や、今は(笑)、ご無沙汰中ですが(笑)、「辺野古」へ向かったわけでは、全然ないのです。「そこ」にいないことへの、「後方」にいることへの、そんなの、「世界」の大半は「後方」なのですから、そんな罪悪感を引き入れるのは「病的」に決まっています、「罪悪感」を「昇華」する、最も手っ取り早い、確実な方法だった、からなんじゃないか?と、今となっては思えます。 「それはとてもいいお葬式だった。」、←、2014年の10月、ですから、「アラブの春」、シリアの「内戦」がはじまってから三年目頃のものですね、CNNだったかロイターだったかの記事だったと思いますが、それを訳出したものです。イギリスのブライトンに住む、「移民」の子孫のムスリムの十代の少年たち、三人の兄弟とその学校友達が、アル・カイダ系ヌスラ戦線の兵士として、インターネット上で知り合った「リクルーター」の手を借りたのであろう、トルコ国境を越えて、シリアの戦場に向かう。そのうちの二人が「戦死」、それが故郷の母親のもとへ、「スカイプ」経由で伝えられるところを描いたものだ。「テレビの前で、人々が苦しむのを、ただ、見ていることが、出来なかった」と彼らの一人は語っている、「死」の可能性、「危険」の強度において全然異なる事態を並列して述べていることをご容赦いただきたい、それでも、私は、「神戸」や「沖縄」へ、「行かなければな・ら・な・い・」という、有無を言わせぬほどの「義務感」の経験から、「彼ら」の気持を、想像し、「共感」をもつことができるのである。 更に言わずもがななことを付け加えるならば、どうして彼らは、たとえばI●SILのような「テロリスト」に与してしまったのか?と言った「非難」は、あまり有効なものとは感じられない。「そこ」へ行かなければ、と急き立てられている人たちのほとんどは、理性的に「党派」を選んでいるような「余裕」がないことを、経験から知っているからだな。私は「三里塚」にブント系ノンセクトの赤ヘルメットかぶって、「決起」する三日前、中●核派の「オルグ」に、ほとんど「拉致・監禁」同様の方法で(笑)、白い帽子かぶらされて、御堂筋デモに参加さ・せ・ら・れ・て・いる。同級生の中には、同じ4月17日の集会に、中●核で参加して、早々と逮捕されてしまったのが、何人かいるから、私だって、どうだったかわからないのだ。三里塚などで大集会がある前夜は、大阪を夜七時頃出発して、大垣で一回乗り換え、翌朝5時ごろ東京に到着する普通電車があるのだが、「人民列車」と呼ばれていた(笑)、それが、各大学、労働組合、などの「活動家」、及び、それを「尾行」する私服警官で一ぱいになる。高校の一年先輩と、その車内でばったり出くわした。「開港阻止決戦・管制塔占拠」で「勇名」を馳せた、「第四インターナショナル日本支部」の、おそろいのえんじ色のウィンドブレーカーを着ていたから驚いたが、それもまた、当然とは言えた。彼が受験に失敗して「第二志望」として選んだ大学の自治会を、当時掌握していたのがこの党派だったからだな、彼がそんな「純正トロツキスト」の「思想傾向」をもっていたわけではなく、どうしても「三里塚」に行くためには、それしか方法がなかったからそうした、と言ってもよいと思う。もちろん、彼は、その「軍服」に、誇らし気、に見えた。彼は、その「決戦」で逮捕されたらしく、千葉の拘置所に、長らく拘留されているらしいと、風の便りに聞き、何年か後、阪急電車でばったり出会ったときは、お互い、決して「三里塚」の話題なんか、出そうとも思わなかった。 だから、話は戻るけど、「スペイン内戦」についてだって、もちろん、「国際旅団」のヘミングウェイ、よ・り・も・、POUMのジョージ・オーウェル、「ドゥルッテイ軍団」のシモーヌ・ヴェイユに対して、より多くの「共感」をもつことは否定しないけれども、そんな「党派性」だ・け・で、なにか「決定論」的にものが言えるとは、到底、思っていない。容器に閉じ込められた一つ一つの気体分子のように、人は、自分が、どこから来て何処へ向かうかを、原理的に知り得ず、「ランダム」さを、「歴史」として、「受け入れる」しか、ない。いまだかつて、人々が「意識的」に社会を変革したことは一度もない、とマルクスは知っていた、と、シモーヌ・ヴェイユも言っているではないか(笑)。 “No,” Karkov had said. “I have just come back from Valencia where I have seen many people. No one comes back very cheerful from Valencia. In Madrid you feel good and clean and with no possibility of anything but winning. Valencia is something else. The cowards who fled from Madrid still govern there. They have settled happily into the sloth and bureaucracy of governing. They have only contempt for those of Madrid. Their obsession now is the weakening of the commissariat for war. And Barcelona. You should see Barcelona.” “How is it?” “It is all still comic opera. First it was the paradise of the crackpots and the romantic revolutionists. Now it is the paradise of the fake soldier. The soldiers who like to wear uniforms, who like to strut and swagger and wear red-and-black scarves. Who like everything about war except to fight. Valencia makes you sick and Barcelona makes you laugh.” “What about the P.O.U.M. putsch?” “The P.O.U.M. was never serious. It was a heresy of crackpots and wild men and it was really just an infantilism.... ... ...I have sent a cable describing the wickedness of that infamous organization of Trotskyite murderers and their fascist machinations all beneath contempt but, between us, it is not very serious, the P.O.U.M.... ... “But they were in communication with the fascists, weren't they?” “Who is not?” “We are not.” “Who knows? I hope we are not. You go often behind their lines,” he grinned. For Whom the Bell Tolls/Ernest Hemingway(kindle) 「そうだ」とカルコフは言った。「おれはいまバレンシアへ行って、いろんな人間に会って帰ってきたところだ。バレンシアから元気よく帰ってくるやつなんていやしないよ。マドリードじゃ万事いいことばかりで、きれいに整理されていて、勝利の可能性のほか、何もないように見える。バレンシアはちがう。マドリードから逃げ出した臆病者が、まだあすこじゃ政権を握っているんだ。やつらは、気持ちよさそうに落ちついて、だらだらと例の官僚主義の政治をやっているんだ。やつらから見れば、マドリードの人間には軽蔑しか感じられないんだ。いまじゃ、やつらは味方の兵站部を弱化することしか考えていない。それからバルセロナだ。きみは、ぜひバルセロナを見てこなければいけない」 「どんなぐあいなんだ?」 「いまだに、まるで喜歌劇そっくりさ。はじめ、あすこは、うぬぼれ鼠とロマンチックな革命家の天国だった。いまは、贋軍人の天国だ。軍服を着ることばかり好きで、赤と黒の襟巻きを巻いて、いばりかえって歩くことばかり好きな軍人どもの天国だ。要するに、戦うことをのぞけば戦争が大好きという手合さ。バレンシアじゃ胸くそわるくなるが、バルセロナじゃ笑いたくなるよ」 「P.O.U.M.の暴動は、どうなったんだ?」 「P.O.U.M.なんて問題になったこともないよ。あれはうぬぼれ鼠と野蛮人の異端者どもで、まったく一種の小児病に過ぎない。・・・ ・・・ ・・・おれはあのトロツキー的人殺しどもの破廉恥な組織の悪辣さと、軽蔑にすら値しないやつらのファシスト的策謀とを暴露する電報を打っておいたよ。だが、おれたちのあいだじゃ、あれはたいして問題にしていないんだ。・・・ ・・・ 「やつらはファシストと連絡をとっていたんだろう?そうじゃないのかい?」 「ファシストと連絡をとらないやつがいるかね?」 「おれたちはとらないじゃないか」 「どうだかわかるもんか。そうであればいいとは思うがね。きみはよく戦線の向う側へ行くからな」、彼はにやりと笑った。 「誰がために鐘は鳴る」ヘミングウェイ(新潮文庫) これが、ミハイル・コルツォフをモデルとしている、とされる、カルコフと、ヘミングウェイその人と見做し得るロバート・ジョーダンとの会話、こちらこそ(笑)、「胸くそわるくなる」性質のものなので(笑)、あまりにひどい表現には「・・・」と、「検閲」をかけざるを得なかった。 後にもっと詳細に調べる予定であるが(笑)、さしあたりジョージ・オーウェル「カタロニア賛歌」(岩波文庫)の「訳者解説」を瞥見したかぎり、共和国政府の、「バレンシア移転」は1936年11月のようである。この場面、1937年5月末とおぼしき山中の戦場で、ロバートが、かつてのマドリッドでの会話を「回想」しているのであるから、その時期は、実際のヘミングウェイの到着、1937年3月頃以降、と見ることができよう。すると「臆病者」は、共和国政府の中心にいた「社会党」その他を指すことになろう。ソ連の支援を受けた「共産党」がその中で重要な位置を果たしていないから、こんな言い方になるのである。ならば、バルセロナの「うぬぼれ鼠」は、「赤と黒の襟巻き」からも当然、アナキストへの罵倒である。「はじめ」と「いま」の対比が、1936年5月の「バルセロナ動乱」、つまり、「共産党」による、CNT/POUMへの襲撃前後を指しているのかどうか、はっきりしないが、すぐ下の、「P.O.U.M.の暴動」なるものへの言及が、それを意味しているかもしれない。だとすると、会話が行われたのは5月以降ということになるから、時間的になかなか厳しくはあるが。 「トロツキー的…」以下の文言は、「私たち」には、あまりにも耳に馴染んだ、「正統派」共産党から「分派」への罵倒の「ジャーゴン・決まり文句」である。カルコフがそれを冗談混じりに引用しているところが、そのモデル、ミハイル・コルツォフが、後に「筆禍」によって処刑されることになることを思えば、感慨深い。  今度のホルサムが内地の旅は、大体においてこの先着の英国人が測量標 木曾路にはいって見たホルサムはいたるところの谷の美しさに驚き、また、あのボイルがいかに冷静な意志と組織的な頭脳とをもってこの大きな森林地帯をよく観察したかをも知った。ボイルの書き残したものによると、奈良井と藪原の間に存在する鳥居峠一帯の山脈は日本の西北ならびに東南の両海浜に流出する流水を分界するものだと言ってある。またこの近傍において地質の急に変革したところもある、すなわちその北方 「夜明け前・第二部下」島崎藤村(青空文庫) 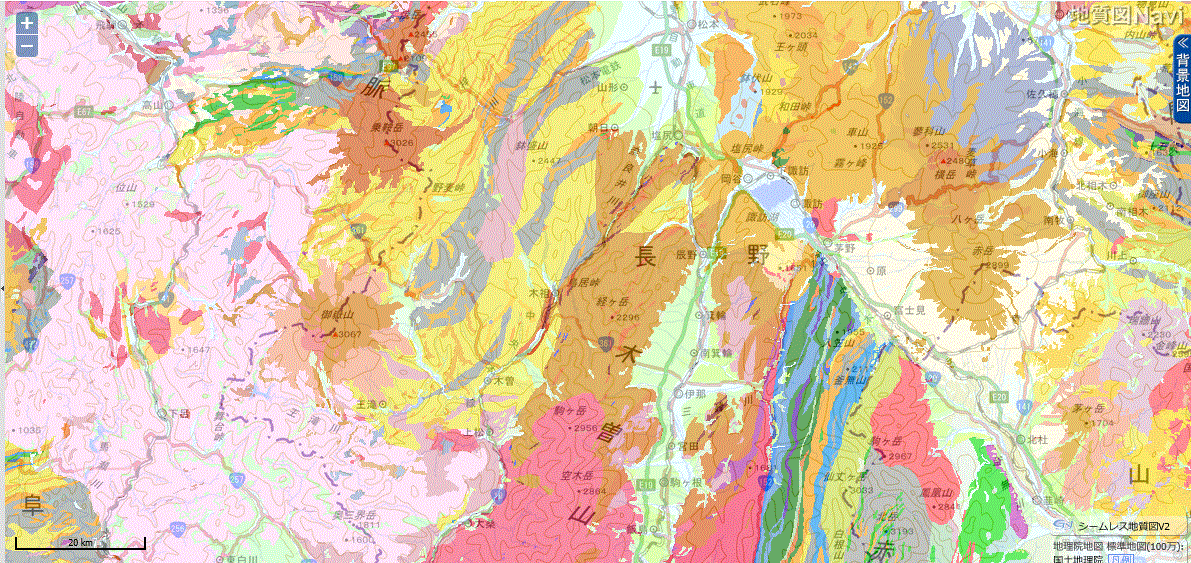 この「ホルサム」なるイギリス人は、明治政府が鉄道敷設計画策定のために招聘した「お雇い外国人」の一人だったようで、東京・京都を結ぶ鉄道路線は、当初は、東海道ではなく東山道経由で考えられていたらしい。だからこの技師は、その路線調査を兼ねて、馬籠にも滞在するのである。私事にわたるが(笑)、たった一年でそれもまた投げ出してしまったが、ずっと「中年」になったのち、地質調査会社に中途採用されたことがある、小さなボーリング屋で、あの、地面を掘削するボーリングboringね、元来は現場の力仕事の助手としてだったんだが、力がないものだから全然役に立たないことが発覚したが、そんな小さな会社に不釣り合いなほど(笑)学歴が高かったものだから、「調査・解析」業務というものに回されて、首がつながった。「地質学」は学んだことがなかったが、理系の書物を「斜め読み」して、誤魔化しのレポートをものにするくらいはお手の物だったから(笑)、土木事務所とかの発注者に提出する報告書の冒頭に付す「地質概要」なども、見よう見まねで、いい加減なものをたくさん書いた。だから、それっぽい一節をここに見つけて、懐かしさのあまり引用したのだが、島崎藤村がこれをどんな文献から引っ張ってきたのか知らないが、「翠増岩石」、「大口火性石」なる用語は、いずれも、聞き覚えがないし、また「ネット」などを調べた限りでは、やはり見つからない。という訳で、オチがつかないもんだから(笑)、この近辺の、「地質図」を探して来てみて、ほら、「またこの近傍において地質の急に変革したところもある」のが、はっきりわかるだろう?と得意そうに言ってみたかったのだが、そのように言えるようでもあり、言えないようでもあり(笑)、いずれにしても、ますますオチのない話になった。図のちょうど中央が、その話題になっている「鳥居峠」になるようにしておいた。  先師と言えば、外国よりはいって来るものを異端邪説として 「夜明け前・第二部下」島崎藤村(青空文庫) 生じた結果に対して、それが不快なものであったとしても、有無を言わせず「受け入れ」なければならないことが、しばしばあるでしょう。そういう時、ああ、それは、「運命だったのだ」とか、「それが神の思し召しだったのだ」という諦観の「型」が、洋の東西を問わず、私たちの身振りの中に刻み込まれているとしたら、それはもとより、そのような「諦観」が、精神の安定を保ち、引いては、生き延びるために、是非とも必要な「措置」だったからに違いないでしょう? 西加奈子「サラバ」(小学館)には、父のカイロ駐在時代、エジプト人の運転手が、寝坊して遅刻するたびに、「アッラーの意のままに」と、「言い訳」する様が、微笑ましく描かれていたね。何も私はここで、砂漠地帯に生まれた「一神教」と、「天●皇制」の違いについて「比較文化論」的に論ずる、などと言う怪しい部分に足を踏み入れようというのではないが、でもここで、感動している半蔵君には申し訳ないが(笑)、この平田篤胤の一節を見て、「あ、それ、ずるい」と思った。この国の「神」たちは、あるいはその存続を危うくしてしまうかも知れない「近代思想」の無制限の流入を、すこしも否定していない、というのである。「神」たち自身は、「善い」ものを選び、「悪い」ものを捨てる、という「選択」は一切行わず、それは、「神」ならぬ「人」に委ねられているようである。申・す・も・畏・き・こ・と・な・れ・ど・も・、失礼を承知で伺うが、ならば、この「神」たちの、「機能」は、何なのだ?「何・も・し・な・い・」、ことが、それなのか? 「神」たちは、何も、しない、すべての事態は、事後的に、「それは、『神』の『御心』であった」として、受け入れられる、何らかの「選択」の行為が行われたとしたら、それは「人」のなしたことで、うまくいけば、それもまた「神」の「御心」であり、また、うまくいかなくても、それもまた「神」の「御心」であったと言える、ただ、うまくいかなかった場合に、「責任」を負うのは、もとより、「神」たちではなく、「人」なのである、当たり前だ、「何もしなかった」ものに責めを負わすわけにはいかない。 大日本帝国憲法第三条「神聖ニシテ侵スヘカラス」は「無答責の法理」の根拠条文と解されている。日本国憲法第四条は、天皇が「国事行為」のみを行いうることを定めているが、この行為についても責任は問われない。「責任」を問うためには、その前・に・、「権力」を与えなければならない、からだ。 おやおや(笑)、ますます危ない領域に差し掛かっているから、後戻りしますけれど、この、「何もしない」、「すべてを許す」、「神」を相手どっては、如何なる戦いも、勝ち目がないのは当然であろう?前回述べたところとつながるが、それは「トートロジー」だからだ。 ある命題が、「真」となるような「論理領域」を、「真理領域」と呼ぶが、論理領域の全域が「真理領域」である命題を「トートロジー」、反対に、論理領域の中に、一切の「真理領域」をもたない命題を、「矛盾」と呼ぶ。これを両極端として、通常の命題は、場合によって「真」であることもあれば「偽」であることもある。   命題P→Q、「PならばQである」は、P∧Q、「PかつQ」の領域では「真」だが、P∧¬Q、「PかつQでない」の領域では「偽」である。右図のように、P⊂Q、「PがQに包含されている」、だったら、つねに「真」である。もし、図がないが(笑)、P∧Q=φ、「PとQに共通部分がない」状態だったら、この命題が「真」であることはあり得ない。 通常、日常言語として、「PならばQだ」と言うとき、PとQとは、もちろん言葉として異・な・る・ものなのだから、その指示する領域が重なり合いをもっていたとしても、完全に一致することはあり得ない。だから、その種の言明が、しばしば差別的で、暴力的な様相を呈するのは故ないことではなく、それは「PであるにもかかわらずQではない」領域、P∧¬Q、に存在する者たち、を除外しているからである。しかし、一方で、残念なことに、多少なりとも、そのような「攻撃性」をもっていなければ、言葉は発せられる「意味」がないこともまた確かなのだ。これを敷衍すると、「トートロジー」は、いつでも正しいから、言ってもか・ま・わ・な・い・、が、言う、意味がな・い・、多少は「正しく」ない、言葉の方が、人の耳を欹てさせるほどの「意味」がある、ならば「矛盾」こそが、全然正しくな・い・が、だからこそ、もっとも「意味」に満ちている、という、困った結論(笑)になってしまう。 「PならばQだ」に対して、「ちょっと、待て、それはひどい、PであってもQでないものがあるじゃないか?」と反問されたとき、しばしば、最初の発言者は、こう答えることになる、「いや、Qでないようなものは、Pであるとは、い・え・な・い・」、これは「Pであること」の定義の中にあとからこっそり「Qでもあること」を潜り込ませているわけだから、ゲームの途中でルールを変えるような不正行為であるが、この操作によって、P=P∧Q、こうして、その命題は常に正しいものとなる。 ちょっと飽きてきたので休憩(笑)、うまくオチがつけられるか、わかんなくなってきたが、一応、この項、続く。 なんだか、論旨が乱れているな(笑)、そういう時は、あ、「論旨が乱れている」と表示して、そこに付箋を貼り付けておいて(笑)、何事もなかったかのように、話題を変えるのが一番であろう、で、更に墓穴を掘ることになるかもしれないが(笑)、別の「数学うんちく」でごまかすことを試みると、確率論に「事前確率/事後確率」という概念がある、本・当・は・おかしな用語なのは、確率は、「事前」に、「結果」が、まだ、わ・か・っ・て・い・な・い・間に論ずる場合にのみ、意味があるのである。外れてしまったくじを前にして、それが「本来」当たる可能性が何パーセントあったかを知りたがる者はいない。雨が降る前に「雨ごい」をして、そうして雨が降ったからこそ、その者に「超能力」が認められるのであって、雨が降ったのちに、ああ、この雨は、私の雨乞いのおかげなんですよ、と自慢しても誰も耳をかたむけない、では、雨が降らなかったらどうするか?私の雨乞いの仕方が、十分でなかった、間違っていた、と反省すれば済む、訳です。平田篤胤のロジックは、これに似てませんかね?だから「ずるい」と思ったんです。絶対「負けない」議論です。そこが「トートロジー」に似ている、と思ったんです。 本居宣長の著作を一つだけ読んだことがあります。「玉くしげ」 だったかな?ずっと年の若い女子学生の気を引くためl(笑)、教養課程の「国史学」だったかのレポートを代筆したのでした。そんな「劣●情」が動機なんですが(笑)、「報酬」は、学生食堂で昼食をおごってもらう、と言った微笑ましいものでしたけどね。「本居宣長は危険な思想家である」というのが書き出しで、当時大流行の(笑)、「ポストモダン」的「ジャーゴン」をふんだんに散りばめたそれは、ちゃんとまだ若そうな新しもの好きの教授の眼鏡にかなったらしく(笑)、「A」だったか「A+」の評価をもらえて、私も上機嫌だった。斜め読みした「玉くしげ」も、そのレポートも何にも覚えていないけれど、たしか、ロラン・バルトが、日本滞在の印象を綴った、あれは「表徴の帝国」でしたっけかね?「皇居」を指して、東京という都市の「空虚な中心」と呼んだのを、聞きかじりだけで知っていて、偉そうに引用したはずです。ロラン・バルトの理解として正しいのかどうか、もちろん分かりませんが(笑)、それは、「何でも受け入れることのできる」、「ブラックホールのような」、「穴」のイメージとして描かれていました。またしても、「熱力学第二法則」などを持ち出して、人を煙に巻くことにしますが(笑)、システムの「内部」の「秩序」を保つ、秩序というのは、「低エントロピー」状態、確率論的には、なかなか起こり得ない事態です、炭素6個、水素12個、酸素6個の原子模型を袋に入れてよく振り混ぜて、開けてみたら綺麗にグルコースC6H12O6の形に並んでいた、などと言うことは、ほぼ絶対にありえないことだが、緑色植物は日々これを、こともなげに(笑)行っているわけです、このような「秩序」、「低エントロピー状態」を創り出すためには、緑色植物においては「太陽光」がそうであるように、システムにとっての絶対的な「外部」からの、エネルギー供給が必須であることが、知られている。「エントロピー」、すなわち「無秩序」の度合い、というネガティブ、否定文の内容をもった用語ですからややこしくなりますが、これを裏から言えば、「外部」へ、「エントロピー」を、「捨てる」ということになる。「秩序」ある「内部」を維持するには、つねに発生し続ける「エントロピー」を、「外部」に廃棄し続ける、必要がある、もちろん、そ・の・た・め・には、システムの「内部」と「外部」を隔てる壁面のどこかに、「外部」につながる「穴」がなければならない。連想はいくらでも膨らみますね。私たちが、自分の部屋の中を「綺麗」にしたい、と思ったら、お掃除をして、ゴミをまとめて袋に入れて、ほら、「外」に、出しておくでしょう?そのゴミ袋が、どこへもっていかれて、誰によって、どんな処理が施されることになるか、私たちは、何の関心も持たなくても生きていけるでしょう?水洗トイレに座って、ことが終わって、レバーを操作して水を流せば、私たちは、自分の「うんこ」を、一度も見なくても、それを、システムの「外部」に「排出」出来るのですね。京都の河原町は、今でこそ繁華街ですが、平安京の頃は、都の果て、処刑場であり、死体の廃棄場所だったのでしょう?つまりそこは、都市の「内部」を清浄に保つために、「穢れたもの」を引き受けるべき「外」の世界につながる「穴」だったのですね。 既に十分差しさわりのあることを言っているのかもしれないが(笑)、一応、こんなイメージ(笑)、と提出するにとどめて、また、引き返すことにしますが、「そのままでよいのだ」、ことさらに手を加えない「自然」のままがいいのだ、およそ、ルネッサンスも、宗教改革も、改革運動というもので、「自然」、「本来の姿」に、「帰れ」と叫ばなかったものはないでしょう?でも、それも、論理的には、おかしな仕組みになっていて、到底「自然」でも「本来の姿」でもな・い・、と思われる「現在」を目の当たりにして、はじめて、そ・う・で・は・な・い・、そうではなかった筈の状態が、遡及的に「過去」のどこかに、あったに違いない、と想定されそれに、「自然」だとか「本来の姿」だとかの、名前が与えられた、既に終わってしまった「過去」に、既に「失われてしまった」ものとして、「発見」、「発明」されたものであることは、少し考えてみれば、明らかではありませんか?だから、「自然」にも「本来の姿」にも、「現在」と異なるものならば、ど・ん・な・も・の・でも盛り込むことができるのですね。「手つかずの自然」を称揚して見せる言論が、ちゃんと(笑)、いかがわしい、と感じられるようになったのは、しかし、ずっと最近、沖縄に来てからのことでしたね。亜熱帯の植生の生命力は猛烈で、そこらへんに「空地」などというものができようものなら、すぐさま、数多の種類の雑草、タチアワユキセンダングサ(キク科)、とか、が繁殖し、ギンネム(マメ科)やシマグワ(クワ科)等の灌木まではやばやと成長する、文字通り、あっという間に、深々と、それこそ「手つかずの自然」と見まがいかねない「密林」が現出してしまいます。いくら「自然」がお好きな方々でも、その中にはいっていくことは、事実として、不可能ですね。私たちが「自然」なるものに触れることができるというのは、あくまでも、それが「破壊」された切断面において、そのはるか向こうにまだ、「破壊」を免れているものの姿を、想像しうる、という意味、だけです。ずっときな臭い話題で、あまり触れたくはないのですが、この島の北部地域の広大な面積を占有している、アメリカ軍の「演習場」は、実際に「演習」に使用されている部分はごくわずかで、ほとんどが、有刺鉄線で囲まれたまま、文字通り「手つかず」の状態に放置されていますから、少しも笑えない皮肉として(笑)、基地の中の方がずっと「自然」は「守られて」いることになる。三年近く前になる、高江の抗議行動が盛んだった時期、「日米地位協定に基づく刑事特別法」に違背することを承知の上で(笑)、敷地内に「侵入」する「ツアー」に何度か参加しましたが、アカショウビン(カワセミ科)の声が身近に聞こえ、せせらぎにリュウキュウハグロトンボ(カワトンボ科)が羽を休め、アカヒゲ(ツグミ科)のオレンジ色が林を横切り、足下にはリュウキュウヤマガメ(イシガメ科)が、ほらそこの樹皮には、オキナワキノボリトカゲ(アガマ科)が、そんな圧倒的な「自然」の存在を、体感できましたが、これまた、全然笑えない皮肉で、それはひとえに、基地建設のために、そこに重機が持ち込まれ、森林が伐採され、通路が開設されたからこそ、私・た・ち・もまた、その「自然」を、初めて、垣間見ることができたのです、もちろん、「見られ」たときにはすでに、それは「本来」の「自然」では、ありえないのは言うまでもない。つまり私たちの「視線」が、その対象をたちまち「自然」ならざるものに変えてしまうのであれば、もし「自然」を「守れ」というのなら、それは「私たち」を「除去」することに他ならない、無論、それは「人間」には解き得ない背理です。「自然」のままがよい、という言論の、いかがわしさは、そのような背理を意識して、葛藤した形跡が、あまり感じられないことに由来するように思います。 ま、今日のところは、これくらいにしといたるわ(笑)、吉本新喜劇の池之めだかの定番ギャグ、自分がぼこぼこにしばきあげられているのに、立ちあがって埃を払いながら、相手に向かって、そううそぶくと、会場が、どっと沸きます、それを真似て、終わりにします。  心の目に「検閲」をかけて、美しいものだけ、ご覧にいれましょう!  「強者(つわもの)どもが夢のあと」の感傷とは、ちょっと違う。芭蕉は、関ヶ原の「戦闘員」ではなかったのだろう?  「どちらが正しいか?」とお尋ねですか?はい、どちらも正しいです。もちろん、それは、どちらも正しくな・い・、と論理的には、同義です。 平素まことに言葉もすくなく、口に往時を語ろうともせず、ただただあわれ深くこの世を見まもって来たような景蔵からこんなに胸をひろげて見せられたことは、ちょっと勝重には意外なくらいだった。年老いたとは言いながらもまだ記憶の確かなのも景蔵だ。勝重はこの老人をつかまえて 「夜明け前・第二部下」島崎藤村(青空文庫) 本日、島崎藤村「夜明け前」、読了いたしました。こんな失礼だが(笑)、長ったらしいだけのもの、読み終われる、とは思っていなかった、返す返すも、「うつ病」再発→「引きこもり」の「恩恵」と言わねばならない、つまり、「本を読むこと」以・外・のことを、絶対にしたくない、というか、出来そうもないときでさえ、それこそ、ご飯を食べるのやトイレに行くのさえ「めんどくさい」時にも、いったん開いてしまえば、右の端からから左の端へと、視線を移動させ、終わりが来たらページをめくる、その単純な動作の繰り返しだけならば、何とか出来た、つまり、それをあえて「中断」することの方が、一層「めんどくさ」かったからだ(笑)。 長い長い作品の冒頭近くに、松雲和尚なる禅宗の僧が、長い修行の旅の末に、馬籠の万福寺の住職として着任する情景が描かれていた。平田派国学の徒であるから、もとより神道家であり、仏教エスタブリッシュメントに対する憎悪をを抱懐している筈の、若き半蔵の目に、しかしこの和尚がなかなか好意的に映っている筆致には、なにかウラがあるな、と睨んでいたが、最後の悲劇的な結末は、半蔵がこの寺院に放火を試み、取り抑えられ、「座敷牢」に閉じ込められ、ほどなく「狂死」する、というものであった。 我が半蔵氏も、飲んでも飲んでも顔に出ない、というから、アセトアルデヒド脱水素酵素ALDHの487番目のアミノ酸が、グルタミン酸であった(笑)、つまり、めっぽうお酒に強い人だったようで、「山林官有化問題」、その請願に対して「戸長解任」をもって報いられる、など、「御一新」政府への幻滅、「志士」としての「挫折」、の「トラウマ」経験が、引き金となったのであろう、アルコール中毒が、初老期うつ病の発現に拍車をかけた、なんのことはない(笑)、私と同じじゃないか?一杯聞し召したうえで、年若い「弟子」を前にして、漢詩だの和歌だのを延々と詠じて悦に入っている場面とかは、明白な「躁症状」であり、身の回りの親しい者たちの姿や声が、遠くなる、というのは、樋口一葉「にごりえ」のお力が駆け出した時、自分の歩いている街が遥か足下に見える、というあれと同じ「解離症状」であろう、部屋の片隅に何か邪悪なものが隠れていて、自分を「狙って」いる、なる被害妄想は、さすがに私も(笑)直接経験したことはないのだが、「同病」の、つまり「アル中・うつ・猫好き」三拍子揃った、早逝の作家中島らも氏などが描いている、いわゆる「提灯行列が見える」、アルコール中毒の譫妄症状かとも思える。という訳で、決して馴染める対象ではなかったこの主人公に対して、ようやくこの最終章に来て、「共感」に似たものをもつことができたのも、また、「病気」のおかげである(笑)。 ずっと以前の章で、島崎藤村は、街道筋の人々の中には、時代の激変の渦中にあって、重篤な「神経衰弱」をきたした人が少なからずいた、と言ったことを記していた。「父」の「発狂」の事実を、言わばそのように「社会化」して捉え直すことが、他ならぬ、「和解」の身振りだったのだと思われる。明らかに筆者藤村自身と見做し得る人物が、半蔵の四男和助として登場する。小学校に入学する頃から東京に知人宅預けられ、徒歩と鉄道馬車で、それでも数日をかけて生前一度だけ訪ねてきた父・半蔵に対して、しかしこの子供は、一向になつくことがなく、時代遅れの田舎者の「志士」のともすれば奇矯な振舞を「恥じて」いるさまが、もちろん、いささか露悪的な彩で、描かれているのもまた、死者に対する、遅ればせながらの、「鎮魂」、「葬送」、「服喪」の身振りなのであろう、もちろん、「鎮魂」、「葬送」、「服喪」、それらは、つねに「遅ればせ」であることを本質とするものであるが。「私はあなたのことを、ちっとも愛せなかったのですよ」と、「告白」することが、どうして「和解」になるのか?私見によれば(笑)、それが「トラウマ」経験を語ることによる「昇華」だからであり、しかも、「愛せない」ことへの「罪悪感」の表示は、「愛する」ことと、見かけ上、そんなに区別がつかないからだ。  「べび」は元気ですよ。もう何年も前から「うちの子」だったみたいに「くつろいで」いるので、こちらも、わざわざ写真を撮る「動機」も、薄れてきた(笑)、と言うものです。  旧暦五月六日の月。夜も大分更けた頃、西の空に沈みかかっているのを発見、速い流れの雲がすぐに隠してしまうので、あまりいい写真が撮れなかった。これが数日前「新月」だった頃、今年の「ラマダン」が終わりを告げることになったのだろう、それを祝福する「エイド・アル・ファトル」のお祭りの最中に、・・・、ハルツームから伝わるその記事に気づいたのも、二三日後だったけれども。 前回書いたが、私が沖縄にやってきたのが、ちょうど二十年前の六月四日で、その日が「天安門事件」のちょうど十年目であることは、知っていた。そんな、たまたま日付が近い、というだけのことで、もちろん、平和裏に座り込んでいた人びとに対して、治安部隊が実弾射撃をもってその排除を開始する、という「類似性」はあるにせよ、二つの異なる事件を、結び付けて想像する、などと言うのは、その「どちら」からも遠い、「後方」においてのみ、出来る業なのだが、そのような「隠喩」、「言い間違い」、「混同」、といったものこそが「言葉」の本来の「機能」であるかも知れないことに免じて、にわかスーダン「通」になってみることにした。 一番上の記事は、デンマーク在住のスーダン人の漫画家のもの、軍司令部前の座り込みへの襲撃の数日後の日付がある。
これは、もうずっと前に、「ブックマーク」をつけておいただけのものを引っ張り出してきたのだが、60年代、70年代、スーダンのヌメイリがまだ、「ナセル主義者」として、寛容な政策を誇示していた時代、この国の首都ハルツームとその隣接する都市オムドゥルマンは、全アフリカ、中東地域に聞こえた、一つの「音楽の都」であったことが語られている。その中に、ワルディという、伝説的な音楽家が登場するが、某Tubeで検索すると、さっそく見つかったので、掲げておく。 「ハルツームの町のどんな一角にも、かならず、音楽があった」、ヴィク・ソホニエ(アル・ジャジーラ2018/09/23) 「ザ・メッセンジャー」モハメド・ワルディAl Mursal(The Messenger)Mohammed Wardi 次は、今からひと月半ほど前になろうか、座り込みの圧力にオマール・アル・バシールが譲歩を見せて、退陣を表明した、という、疑いもない「勝利」の、祝祭的雰囲気が伝わってくる、そんな時期の記事。座り込み場所の軍司令部前に開かれた、「屋外移動図書館」のお話。 ひょっとしたら「勝てる」かも知れない、いや、そんな訳ない、こんなことがいつまでも続く訳ない、そのうち物凄い巻き返しがやってくるに違いない、・・・、そんな危うい「空間」の匂いを、そこには決して「実弾」も、「催涙ガス弾」すら飛んでくることはない、という意味で、せいぜい素手か警棒で追っ払われるに過ぎない、と、加えられる暴力の「強度」において比較を絶しているにもかかわらず、私もまた、類似した「経験」を頼りに「想像」を及ぼすことができるのだ。 プロテスターたちに書物を提供する、スーダンの図書館員(アル・ジャジーラ2019/04/25) こちらは、ケニア在住の政治学者による分析。「国連」と言った「多国間組織Multilateralism」が、どうして破綻したのか?について語っている。難解な文章なので、いつもに増して(笑)、翻訳は怪しい。 どうして、スーダンの人々は、「たった一人で」立ち上がらなければ、ならなかったのか?/ナンジャーラ・ニャボーラ(アル・ジャジーラ2019/06/09)  Sahel(wikipedia) Lake Nubia(googlemap) Shamal Darfur(North Darfur)(googlemap) Janub Darfur(South Darfur)(googlemap) ハルツームという町は、タンザニア、ウガンダ、ケニアの国境地帯「大湖沼Great Lakes」地方に始源する「白ナイルWhite Nile」と、エチオピアの「タナ湖Lake Tana」を水源とする「青ナイル Blue Nile」が合するところなのですね。南東から「青ナイル」、南西から「白ナイル」が、流れ込む、その「青」と「白」に挟まれた三角形と、合流した後の「ナイル」の東岸が、ハルツーム市、「ナイル」西岸がオムドゥルマン市のようです。ニュースの中で、6月3日の襲撃の後、新たにバリケードが築かれた、と伝えられるBahrī地区をgooglemapで検索すると、ハルツーム市のうちの「青ナイル」の北側、地図には「Khartoum North」とある部分が指示されるので、あるいは、その言葉は「北」の意味なのかもしれない。「何週間にもわたる」と言われる「座り込み」の場所を知りたいと思ったのだが、「軍司令部Army Headquater」の前、とか、「軍複合施設Army Complex」の前、とか、どうやら、TMC(暫定軍委員会)が司令部を設けていたのがその場所らしいのだが、それがよくわからない。一枚の写真が、膨大な数の抗議参加者が屋外の「金曜礼拝Friday Prayer」に参加してる様を写していて、そのキャプションに、「防衛省Ministry of Defence」前、とあった。それなら、ハルツーム国際空港の北西端に位置している。地図の中にも見えるが、「Army Road」というのがあって、その東の突き当りのその先になる。 
ハルツームの座り込みは、確かに、失われてしまった。しかし民主的なスーダン、という、その夢はそこに、あり続ける。ヒバ・モーガン(2019/06/13、アル・ジャジーラ)  がうなはちひさき貝をこのむ、これよく身をしるによりてなり。みさごは荒磯に居る、則ち人をおそるゝが故なり。我またかくのごとし。  「がうなはちひさき貝をこのむ」、スベスベサンゴヤドカリ(ヤドカリ科)、資料映像(笑)。  「みさごは荒磯に居る」、ミサゴ(タカ科)、資料映像(笑)。 こゝに六十の露消えがたに及びて、さらに末葉のやどりを結べることあり。いはゞ狩人のひとよの宿をつくり、老いたるかひこのまゆをいとなむがごとし。これを中ごろのすみかになずらふれば、また百分が一にだもおよばず。とかくいふ程に、よはひは年々にかたぶき、すみかはをりをりにせばし。その家のありさまよのつねにも似ず、廣さはわづかに方丈、高さは七尺が内なり。所をおもひ定めざるがゆゑに、地をしめて造らず。土居をくみ、うちおほひをふきて、つぎめごとにかけがねをかけたり。もし心にかなはぬことあらば、やすく外へうつさむがためなり。そのあらため造るとき、いくばくのわづらひかある。積むところわづかに二輌なり。車の力をむくゆるほかは、更に他の用途いらず。いま日野山の奧にあとをかくして後、南にかりの日がくしをさし出して、竹のすのこを敷き、その西に閼伽棚を作り、うちには西の垣に添へて、阿彌陀の畫像を安置したてまつりて、落日をうけて、眉間のひかりとす。かの帳のとびらに、普賢ならびに不動の像をかけたり。北の障子の上に、ちひさき棚をかまへて、黒き皮籠三四合を置く。すなはち和歌、管絃、往生要集ごときの抄物を入れたり。傍にこと、琵琶、おのおの一張をたつ。いはゆるをりごと、つき琵琶これなり。 ・・・ もし日うらゝかなれば、嶺によぢのぼりて、はるかにふるさとの空を望み。木幡山、伏見の里、鳥羽、羽束師を見る。 ・・・ がうなはちひさき貝をこのむ、これよく身をしるによりてなり。みさごは荒磯に居る、則ち人をおそるゝが故なり。我またかくのごとし。身を知り世を知れらば、願はずまじらはず、たゞしづかなるをのぞみとし、うれへなきをたのしみとす。すべて世の人の、すみかを作るならひ、かならずしも身のためにはせず。或は妻子眷屬のために作り、或は親昵朋友のために作る。或は主君、師匠および財寳、馬牛のためにさへこれをつくる。我今、身のためにむすべり、人のために作らず。ゆゑいかんとなれば、今の世のならひ、この身のありさま、ともなふべき人もなく、たのむべきやつこもなし。たとひ廣く作れりとも、誰をかやどし、誰をかすゑむ。 「方丈記」鴨長明(青空文庫)  おやおや、今度は「方丈記」ときましたか(笑)?ひょんなことから、「青空文庫」でただで手に入ったものだし、読みはじめたら、止められなくなった。高校生の頃は、きっと定期試験の前夜などに嫌々読んで、なんで老人がこんなくだらないこと偉そうにぶつぶつうぶやいてんだろ、そんなもの読まされる後世の若者の「迷惑」ってものを考えろよ、などと「逆恨み」していたはずなのに、いやはや、全然様相を異にして眼前に広がるように感じられるのは、もちろん、自分が、ほぼ同年齢の(笑)、「老人」になったからだ。あっという間に(笑)、読み終えてしまったけれど、注釈や現代語訳が付されていないと不安なので、さっそく角川ソフィア文庫版が、廉価で手に入りそうなので注文したから、また、後程、「精読」することにしよう。 「廣さはわづかに方丈、高さは七尺が内なり」、ちょうど一年前くらいかな、山川菊栄「武家の女性」(岩波文庫)を読んでいるときだったか、尺貫法の長さと面積の単位を、調べて図表にしたものがあるから引っ張り出してきた。「方丈記」の「方丈」は、こんな意味だったんだね、知らなかった。「方」は「平方」の「方」、つまり、「一丈・四方」の正方形、を意味する。3.03m四方、面積にすれば、10m2足らず、畳一枚は、確か「京間」とか「江戸間」とかで異同があった筈だが、1m×2mとすれば、ちょうど「四畳半」ってことになるか。高さ方向が0.3×7=2.1、ちょっとこれは、息苦しい感じがするね。古文の教科書に「閼伽棚」の注釈がついていて、サンスクリット語の「アカ」が「水」で、それはヨーロッパ語のaquaとつながっている、とかあったのをおぼえているぞ。「往生要集」は源信、だろ?「源氏の男はみなサイテー」の著者がどこかで引用して口語訳してくれていたけど、「浄土」の美しさを称揚するのではなくて、ひたすら「地獄」の不潔さをおどろおどろしく描いて人びとを脅迫する、どう見てもいただけないものだったので失望した。 ここにあるように、この人は六十を過ぎてから、現在の京都市伏見区醍醐小野、のあたりに「庵」を結んだらしい。懐かしい地名がたくさん出てくる。私は二十年間京都に住んでいて、一時期右京区の太秦にしばらく居た以外、大半は、左京区の、東山の麓に暮らした。でも、その短期間働いていた地質調査会社は伏見区だったし、それぞれ思い出のある場所ではある。「地下鉄東西線」なるものが、このあたりまで延伸計画があることを小耳にはさむ頃に京都を離れ、二度と訪れていないから、そのあたりは不案内であるけれども、ちゃんと「小野」という駅があるのだね。「木幡(こわた)」は、京阪宇治線にその駅名がある。「鳥羽」は広いエリアを指す地名だが、地図には近鉄の「上鳥羽口」が見える。「羽束師(はずかし)」は、長岡京市との境に近いところで、地図ではJR「神足(こうたり)」駅の東側桂川沿いあたり。 「がうな」は、古語辞典引いて初めて知った「ヤドカリ」なんだってね。「みさご」はもちろん、おなじみだ、英語名が「オスプレイ」であることなんか、さしあたりどうでもよく(笑)、当地の「荒磯」でも、しばしば見つけられる。ね、六十過ぎた、ひょっとしたら「老人性うつ病」かもしれない(笑)、「独居老人」の、「引きこもり」ブログなんだ(笑)、「共感」を感じない訳がないのであった。  「西暦・干支・元号、対応表」    要するに(笑)、この老人は、手間暇かけて立派な家を建てても、どうせ、「うたかた」のように消えてなくなってしまうのだから、小さく粗末な家でもいいんだ、と「強がり」を言うためだけに、この書物を書いた(笑)。自己が見聞した都の、出来事、四つの自然災害と、一つは人為的なもの、について記している。 「いにし安元三年四月廿八日かとよ」、は都の大火のようである。「戌の時ばかり、都のたつみより火出で來りていぬゐに至る」、安元三年は、グレゴリオ暦1177年に当たり、鴨長明の満年齢は、22歳。「戌(いぬ)の時」は午後八時ごろ、「たつみ」は南東、「いぬゐ」は北西。 「そのつひえいくそばくぞ」がちょっとわからないな。「つひえ」は「費」、「幾何(いくばく)」の「いく」と「ばく」のそれぞれに「そ/ぞ」という接尾辞を付して強調したのだろうか? 「また治承四年卯月廿九日のころ」、グレゴリオ暦1180年、長明満25歳、「大なるつじかぜ」、暴風のようである。「卯月」は旧暦四月、グレゴリオ暦1180年の旧暦4月29日は、例の、「月齢付きカレンダー・サイト」によれば、新暦6月1日、少し早いが「台風」かも知れない。 「ひはだぶき板のたぐひ」、檜皮葺、檜の樹皮で葺いた屋根。 「おびたゞしくなりとよむ音に」、「とよむ」は「響む」と書く。 「身をそこなひて、かたはづけるもの數を知らず」、「片端付く(かたはづく)」、身体に損傷を生じること。 「この風ひつじさるのかたに移り行きて」、「十二方位」の表現は、「北」を「子」として、以降、「時計回りClockwise」に、角度にして30度ごとに割り振っていく、「ひつじさる」は南西、台風は低気圧だから、その中心に向かって風が吹き込む、京都のあたりでは通常、南西から接近して、北東に抜けていくだろう、直撃したのだとしたら、接近中は北東の風、通過後は、南西の風、となるはずで、なるほど、辻褄は、合う(笑)。 「又おなじ年の六月の頃、にはかに都うつり侍りき」、「遷都」があったことが書かれている、これに伴って、人々が都の家を捨てて出ていくから、街は「荒れる」のである。「攝津國難波の京」に移る、とあるが、これは暫定的にそんな事態があったのかもしれないが、史実としては、「和田」の都、現・神戸市、兵庫区から長田区のあたり、大きな造船所のある和田岬、という地名があるだろ?への計画があったが、「その地ほどせまくて、條里をわるにたらず」ということで、廃案、同じ神戸の、これは、神戸駅から新開地あたりと思われる、「福原」に遷都、しかし、長続きせず、「おなじ年の冬、猶この京に歸り給ひにき」、となった。 「都のてふりたちまちにあらたまりて」の「てふり」は、「手振り」、風俗、風習、だろうか?古語辞典では「手振り(てぶり)」だが。 「大かたこの京のはじめを聞けば、嵯峨の天皇の御時、都とさだまりにけるより後、既に數百歳を經たり」、平安京の歴史を語っているのだが、「嵯峨天皇」在位786-842、平城京から長岡京への遷都が、784年、長岡京から平安京への遷都が、793年、・・・、鴨長明の語る「現在」が、1212年として、1212-793=419だから、「數百歳」は、少し誇張。そういえば、私がまだ京都に住んでいた頃、「建都千二百年」が喧伝されていた、この期に及んでも(笑)、「かつて、都であ・っ・た・」以外に、誇るべきものがないのか、君は、と「嘲笑」していたものである(笑)。 「又養和のころかとよ、久しくなりてたしかにも覺えず」、元号が養和であるのは、1181-1182、二年連続で飢饉が襲ったことが描かれる。こんなひどい飢饉は、「近くは崇徳院の御位のとき、長承のころかとよ」にあったと伝え聞いているが、それ以来だ、と言っている。長承は1132-1135。 「また元暦二年のころ、おほなゐふること侍りき」、グレゴリオ暦では1185年に当たる、「おほなゐ」は大地震のこと、「ふる」は「振る」だろうか?日に二十回も三十回も余震が起こる日が十日も二十日も続いた様が描かれる。「むかし齊衡のころかとよ」、大地震があって東大寺の大仏が損傷した、という故事を引き出している。齊衡は854年から857年、しかし、いずれの地震も、wikipediaの「地震年表」には見つけられなかった。 という、長い長い、自然災害と人為的災害の歴史が語られ、立派な家をつくっても、こわれてしまったり、離れていかなければならないのだから、「方丈」でよいのだよ、という「前振り」にしているようである。 「我が身、父の方の祖母の家をつたへて、久しく彼所に住む。そののち縁かけ、身おとろへて、しのぶかたがたしげかりしかば、つひにあととむることを得ずして、三十餘にして、更に我が心と一の庵をむすぶ。これをありしすまひになずらふるに、十分が一なり。」 父方の祖母の家に寄寓していたが、諸般の事情で出なければならなくなり、以前の「十分の一」ぐらいの狭い家に住むことになった、と言っている。この「庵」の場所がどこなのかも、齢「三十餘」と言うが、いつなのかも、不明。 さらに、「こゝに六十の露消えがたに及びて、さらに末葉のやどりを結べることあり。いはゞ狩人のひとよの宿をつくり、老いたるかひこのまゆをいとなむがごとし。これを中ごろのすみかになずらふれば、また百分が一にだもおよばず」、こうして、更に、規模が縮小して、もとの祖母の家に比べると「百分の一」でしかない、「方丈」に住むことになった、と言っている。これが、現・京都市伏見区醍醐小野、なのであろう。上で述べたように(笑)、「方丈」は、一辺3.03mの正方形、面積が100倍なら、一片の長さ10倍だから、祖母の家は、推定(笑)、一辺30.3mの正方形程度の面積をもっていたことになろう。 鴨長明は、1204年、満49歳の時に、下鴨神社河合社(ただすのやしろ)、おお、今思い出した、河原町通、下鴨神社を北に過ぎたところあたり、「糺の森(ただすのもり)」というバス停があった、の禰宜(ねぎ)職に欠員が生じたので期待したが、その就職活動が不調に終わり、これで、言わば、「世を拗ね」て、出家、隠遁、「引きこもり」に向かった、と言われている。「方丈記」成立が、1212年と言われており、その記述の「現在」から見て、その「方丈」の「庵」に住み始めて、「今ますでに五とせを經たり」とあるから、醍醐小野への引っ越しが1207年とすれば、長明満52歳であり、「六十の露消えがたに及びて」は、やや誇張であることが判った(笑)。 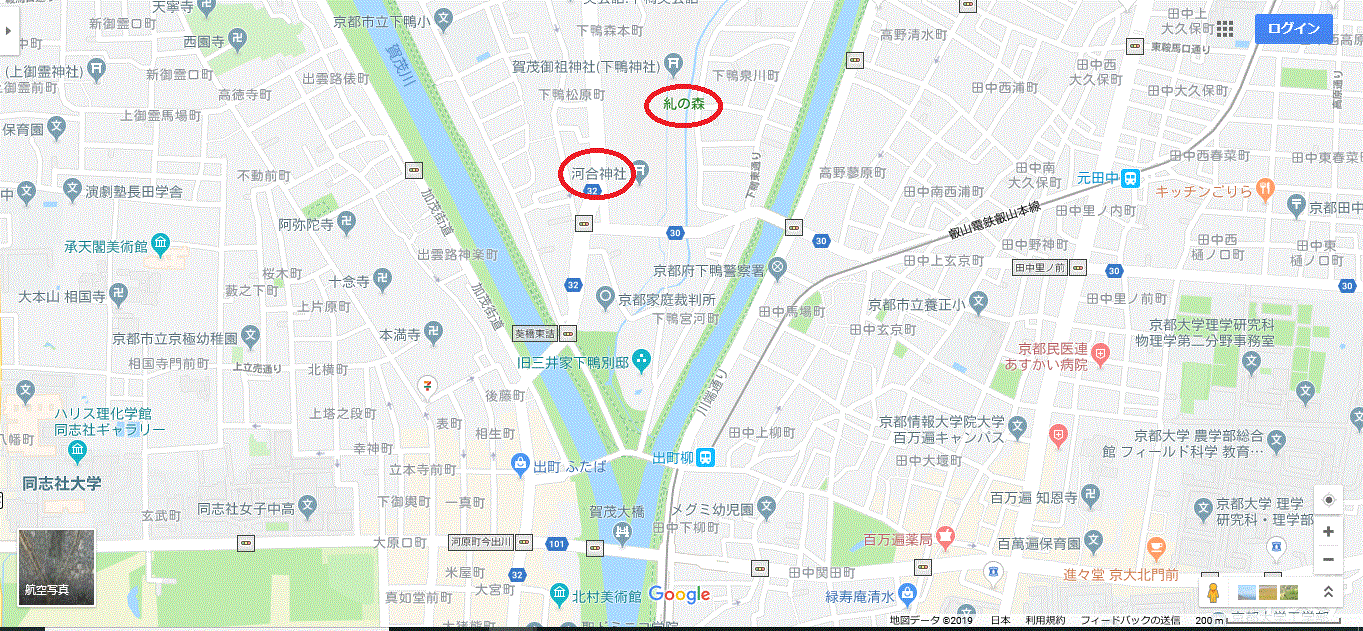   京都に二十年ばかり住んでいたから、ある程度「土地勘」があるのだが、「大原」と言われて思い浮かぶ場所は、互いに遠く離れた二か所、一つは、国道367号線、これは「烏丸(からすま)通」なのであるが、それをどんどん北に辿っていくと、「途中越え」と呼ばれる、琵琶湖の西岸、比良山の西の裏側の谷を伝って、ゆくゆくは日本海岸の敦賀、丹後半島への道になる。京都府と滋賀県、山城国と近江国の国境にあたる「途中峠(とちゅうとうげ)」の手前に広がる盆地が、「大原」、三千院、寂光院、で知られる、そうそう、この沿道には、前にお話しした、有名な「志ば漬(しばづけ)」の老舗の本社工場、があり、付設のレストランでは「漬物バイキング」が行われ(笑)、周り一面が紫色に色付くシソ(シソ科)の畑であった。もう一つは、国道9号線、これは、五条通、今googlepapを瞥見すると、私のあまり記憶にない(笑)バイパスができているようであるが、「老の坂峠」のトンネルを経て、亀岡、福知山経由でやはり日本海側に向かう、その、京都市と亀岡市の境、あるいは山城国と丹波国の境になるのかな?、の手前、京都市立芸術大学、洛西ニュータウン、の西側の山際に広がる、「大原野」、竹藪が多く、タケノコの産地でもある。 鴨長明が、元久元年、1204年、下鴨神社河合社(ただすのやしろ)禰宜職への就職に失敗した年、出家して「大原」に籠る、と言われるときの「大原」は、この「大原」、「大原野」いずれであったかは、議論の分かれるところであるらしい。それで思い出した、これは「大原野」の方であるが、「花の寺」→「西行桜」の連想で、去年か一昨年か、「雨月物語」の「白峯」だったかな?何かがきっかけで西行のことを少し調べた、「歌心」を欠く人間だからなのだろう(笑)、結局あまり興味をもてずに終わったから忘れていた、上の「生没年一覧」をご覧の通り、鴨長明よりは、40歳ばかり年上だが、重なる時代を生きているのである。かたや武士、かたや神官、ではあるが、後に「出家」して「引きこもる」ところは、似ている。西行が庵を結んだのは、洛北、どちらかと言うと「大原」の方に近い鞍馬寺であるが、瀬戸内寂聴「白道(びゃくどう)」(講談社文庫)によれば、気の向くままに色々なところに住み着いた、というような様子らしいから、大原野の「勝持寺(しょうじじ)」、別名「花の寺」も、そのひとつだった可能性は、ある。私は二十年の京都暮らしの間で、二年間だけ、右京区の嵯峨野に住んでいて、そういえば、新丸太町通りを走り抜けるタクシーの客席に、丸坊主の初老の女性が乗っていらっしゃるのを、目撃して、なんか見たことある、ああ、瀬戸内寂聴だ、と仰天した記憶があるが、この人の「庵」とも、ほど近かった筈で、だから、「花の寺」も、何度か訪れたはずで、「西行桜」なるものも、何の感興もなく(笑)、眺めたことがあった筈なのだ、あまり記憶はないが。その「白道」を引っ張り出してきて、「花の寺」に関する記述を探したが、見つからず、でも、当時の貴族社会の、仏教各派の勢力配置図(笑)として、わかりやすい一文があったので、引用しておく。 平安時代は、最澄の開いた天台宗が貴族の間では信仰されていたし、空海の真言宗が次第に勢力を二分するほどに追いついていた。病気も不運も天台の台密、東寺の東密と呼ばれる密教の加持祈祷で追い払う習慣であった。 平安中期になって、恵心僧都源信が「往生要集」をあらわし、浄土宗の源を開いたことから、阿弥陀信仰が広まっていた。平安時代の貴族たちはしきりに寺を建て阿弥陀仏をまつり、臨終には阿弥陀仏の指にかけた五色の糸を、自分の指にからめて極楽往生することを願った。 「白道」瀬戸内寂聴(講談社文庫) 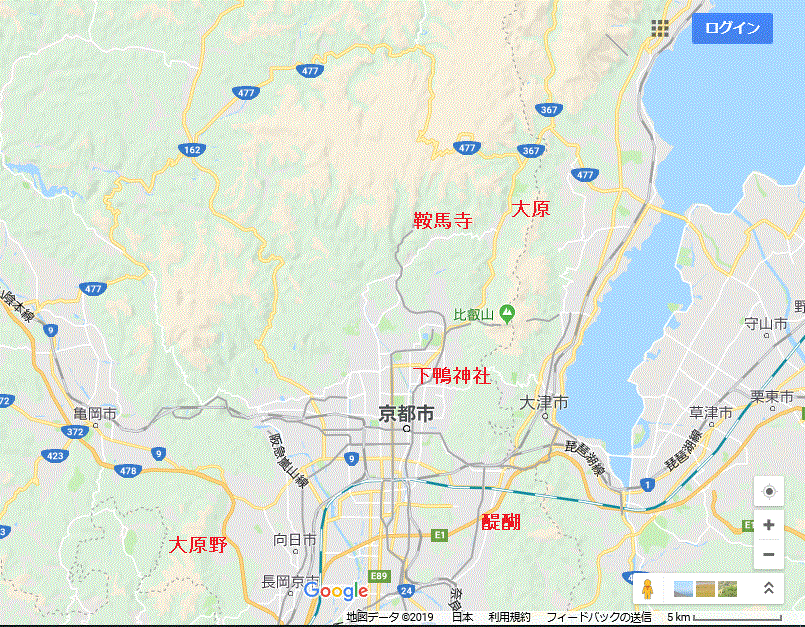 本日、角川ソフィア文庫版「方丈記」が届き、その「解説」をパラパラ眺めていると、こんな一節が目に留まった。 鎌倉幕府の日記である東鑑(あずまかがみ)を見ると、長明は、飛鳥井雅経(あすかい まさつね)の推挙によって、鎌倉に下り、建歴元年(一二一一)十月一三日に、実朝に面会している。菟玖波集(つくばしゅう)には、長明と雅経が連歌に興じながら東海道を下って行ったことが記録されているのであるが、この旅行の目的が何であったかはまったくわからない。・・・長明は、法華堂において、頼朝をたたえる歌を詠じて、さっさと鎌倉を引きあげてしまったようである。 「方丈記」鴨長明(角川ソフィア文庫)・簗瀬一雄による「解説」 それで思い出した。これもに三年前になるか、何がきっかけだったか思い出せないが、太宰治「右大臣実朝」(青空文庫)、これは、多分(笑)、「東鑑」なのだろう、引用部分に引き続いて、それを太宰が実朝の従者の一人の「独話」の形に、「脚色」した体裁をとっているのだが、この、長明との会見の有様が、長々と描かれていて、しかも、この、出家したくせにちっとも「枯れて」いない、いつも「きょとん」とした老人は、一体何しに来たんだろう?頼朝をほめたたえる歌だなんて、わが三代将軍様に対する嫌味なんだろうか?と、なかなか手厳しい、方丈記読みながら、なんかひっかかっていたのは、その忌憚のない「悪口」が、刷り込まれていたからだったのだね。長いが、「青空文庫」だから、「コピー・ペースト」ですむし(笑)、引用する。 同年。十月大。十三日、辛卯、鴨社の氏人菊大夫長明入道、雅経朝臣の挙に依りて、此間下向し、将軍家に謁し奉ること度々に及ぶと云々、而るに今日幕下将軍の御忌日に当り、彼の法花堂に参り、念誦読経の間、懐旧の涙頻りに相催し、一首の和歌を堂の柱に注す、草モ木モ靡シ秋ノ霜消テ空キ苔ヲ払フ山風 同年。十一月大。廿日、戊辰、将軍家貞観政要の談議、今日其篇を終へらる、去る七月四日之を始めらる。 同年。十二月大。十日、戊午、和漢の間、武将の名誉有るの分御尋ね有るに就いて、仲章朝臣之を注し出して献覧せしむ、今日、善信、広元等、御前に於て読み申す、又御不審を尋ね仰せられ、再三御問答の後、頗る御感に及ぶと云々。 また、そのとしの秋、当時の蹴鞠の大家でもあり、京の和歌所の寄人でもあつた参議、明日香井雅経さまが、同じお歌仲間の、あの、鴨の長明入道さまを京の草庵より連れ出して、共に鎌倉へ下向し、さうして長明入道さまを将軍家のお歌のお相手として御推挙申し上げたのでございましたが、この雅経さまの思ひつきは、あまり成功でなかつたやうに私たちには見受けられました。入道さまは法名を蓮胤と申して居られましたが、その蓮胤さまが、けふ御ところにおいでになるといふので私たちも緊張し、また将軍家に於いても、その日は朝からお待ちかねの御様子でございました。なにしろ、鴨の長明さまと言へば、京に於いても屈指の高名の歌人で、かしこくも仙洞御所の御寵愛ただならぬものがあつたとか、御身分は中宮叙爵の従五位下といふむしろ低位のお方なのに、四十七歳の時には摂政左大臣良経さま、内大臣通雅さま、従三位定家卿などと共に和歌所の寄人に選ばれるといふ破格の栄光にも浴し、その後、思ふところあつて出家し、大原に隠棲なされて、さらに庵を日野外山に移し、その鎌倉下向の建暦元年には既におとしも六十歳ちかく、全くの世を捨人の御境涯であつたとは申しながら、隠す名はあらはれるの譬で、そのお歌は新古今和歌集にもいくつか載つてゐる事でございますし、やはり当代の風流人としてそのお名は鎌倉の里にも広く聞えて居りました。その日、入道さまは、参議雅経さまの御案内で、御ところへまゐり将軍家へ御挨拶をなさいまして、それからすぐに御酒宴がひらかれましたが、入道さまは、ただ、きよとんとなされて、将軍家からのお盃にも、ちよつと口をおつけになつただけで、お盃を下にさし置き、さうしてやつぱり、きよとんとして、あらぬ方を見廻したりなどして居られます。あのやうに高名なお方でございますから、さだめし眼光も鋭く、人品いやしからず、御態度も堂々として居られるに違ひないと私などは他愛ない想像をめぐらしてゐたのでございましたが、まことに案外な、ぽつちやりと太つて小さい、見どころもない下品の田舎ぢいさんで、お顔色はお猿のやうに赤くて、鼻は低く、お頭は禿げて居られるし、お歯も抜け落ちてしまつてゐる御様子で、さうして御態度はどこやら軽々しく落ちつきがございませんし、このやうなお方がどうしてあの尊い仙洞御所の御寵愛など得られたのかと私にはそれが不思議でなりませんでした。さうしてまた将軍家に於いても、どこやら緊張した御鄭重のおもてなし振りで、 チト、都ノ話デモ と入道さまに向つては、ほとんど御老師にでも対するやうに口ごもりながら御遠慮がちにおつしやるので、私たちには一層奇異な感じが致しました。入道さまは、 「は?」とおつしやつて聞き耳を立て、それから、「いや、この頃は、さつぱり何事も存じませぬ。」と低いお声で言つてお首を傾け、きよとんとしていらつしやるのでした。けれども将軍家は、例のあの、何もかも御洞察なさつて居られるやうな、また、なんにもご存じなさらぬやうな、ゆつたりした御態度で、すこしお笑ひになつて、 世ヲ捨テタ人ノオ気持ハ と更にお尋ねになりました。入道さまはやつぱり、 「は?」とおつしやつて聞き耳を立て、それから、がくりと項垂れて何か口の中で烈しくぶつぶつ言つて居られたやうでしたが、ひよいと顔をお挙げになつて、「おそれながら申し上げまする。魚の心は、水の底に住んでみなければわかりませぬ。鳥の心も樹上の巣に生涯を託してみなければ、わかりませぬ。閑居の気持も全く同様、一切を放下し、方丈の庵にあけくれ起居してみなければ、わかるものではござりませぬ。そこの妙諦を、私が口で何と申し上げても、おそらく御理解は、難からうかと存じまする。」さらさらと申し上げました。けれども将軍家は、一向に平気でございました。 一切ノ放下 と微笑んで御首肯なされ、 デキマシタカ ややお口早におつしやいました。 「されば、」と入道さまも、こんどは、例の、は? と聞き耳を立てることも無く、言下に応ぜられました。「物慾を去る事は、むしろ容易に出来もしまするが、名誉を求むる心を棄て去る事は、なかなかの難事でござりました。瑜伽論にも『出世ノ名声ハ譬ヘバ血ヲ以テ血ヲ洗フガ如シ』とございまするやうに、この名誉心といふものは、金を欲しがる心よりも、さらに醜く奇怪にして、まことにやり切れぬものでござりました。ただいまの御賢明のお尋ねに依り、蓮胤日頃の感懐をまつすぐに申し述べまするが、蓮胤、世捨人とは言ひながらも、この名誉の慾を未だ全く捨て去る事が出来ずに居りまする。姿は聖人に似たりといへども心は不平に濁りて騒ぎ、すみかを山中に営むといへども人を恋はざる一夜も無く、これ貧賤の報のみづから悩ますところか、はたまた妄心のいたりて狂せるかと、われとわが心に問ひかけてみましても更に答へはござりませぬ。御念仏ばかりが救ひでござりまする。」けれどもお顔には、いささかも動揺の影なく、澱みなく言ひ終つて、やつぱりきよとんとして居られました。 遁世ノ動機ハ と軽くお尋ねになる将軍家の御態度も、また、まことに鷹揚なものでございました。 「おのが血族との争ひでござります。」 とおつしやつた、その時、入道さまの皺苦茶の赤いお顔に奇妙な笑ひがちらと浮んだやうに私には思はれたのですが、或いは、それは、私の気のせゐだつたかも知れませぬ。 ドノヤウナ和歌ガヨイカ 将軍家は相変らず物静かな御口調で、ちがふ方面の事をお尋ねになりました。 「いまはただ、大仰でない歌だけが好ましく存ぜられます。和歌といふものは、人の耳をよろこばしめ、素直に人の共感をそそつたら、それで充分のもので、高く気取つた意味など持たせるものでないやうな気も致しまする。」あらぬ方を見ながら入道さまは、そのやうな事を独り言のやうにおつしやつて、それから何か思ひ出されたやうに、うん、とうなづき、「さきごろ参議雅経どのより御垂教を得て、当将軍家のお歌数十首を拝読いたしましたところ、これこそ蓮胤日頃あこがれ求めて居りました和歌の姿ぞ、とまことに夜の明けたるやうな気が致しまして、雅経どのからのお誘ひもあり、老齢を忘れて日野外山の草庵より浮かれ出て、はるばる、あづまへまかり出ましたといふ言葉に嘘はござりませぬが、また一つには、これほど秀抜の歌人の御身辺に、恐れながら、直言を奉るほどの和歌のお仲間がおひとりもございませぬ御様子が心許なく、かくては真珠も曇るべしと老人のおせつかいではございまするが、やもたてもたまらぬ気持で、このやうに見苦しいざまをもかへりみず、まかり出ましたやうなわけもござりまする。」と意外な事を言ひ出されました。 ヲサナイ歌モ多カラウ 「いいえ、すがたは爽やか、しらべは天然の妙音、まことに眼のさめる思ひのお歌ばかりでございまするが、おゆるし下さりませ、無頼の世捨人の言葉でございます、嘘をおよみにならぬやうに願ひまする。」 ウソトハ、ドノヤウナ事デス。 「真似事でございます。たとへば、恋のお歌など。将軍家には、恐れながら未だ、真の恋のこころがおわかりなさらぬ。都の真似をなさらぬやう。これが蓮胤の命にかけても申し上げて置きたいところでござります。世にも優れた歌人にまします故にこそ、あたら惜しさに、居たたまらずこのやうに申し上げるのでござります。雁によする恋、雲によする恋、または、衣によする恋、このやうな題はいまでは、もはや都の冗談に過ぎぬのでござりまして、その洒落の手振りをただ形だけ真似てもつともらしくお作りになつては、とんだあづまの片田舎の、いや、お聞き捨て願ひ上げます。あづまには、あづまの情がある筈でござります。それだけをまつすぐにおよみ下さいませ。ユヒソメテ馴レシタブサノ濃紫オモハズ今ニアサカリキトハ、といふお歌など、これがあの天才将軍のお歌かと蓮胤はいぶかしく存じました。御身辺に、お仲間がいらつしやりませぬから、いいえ、たくさんいらつしやつても、この蓮胤の如く、」と言ひかけた時に、将軍家は笑ひながらお立ちになり、 モウヨイ。ソノ深イ慾モ捨テルトヨイノニ。 とおつしやつて、お奥へお引き上げになられました。私もそのお後につき従つてお奥へまゐりましたが、お奥の人たちは口々に、入道さまのぶしつけな御態度を非難なさつて居られました。けれども将軍家はおだやかに、 ナカナカ、世捨人デハナイ。 とおつしやつただけで、何事もお気にとめて居られない御様子でございました。 その翌日、参議雅経さまが少し恐縮の態で御ところへおいでになられましたが、その時も、将軍家はこころよくお逢ひになつて、種々御歓談の末、長明入道さまにも、まだまだ尋ねたい事もあるゆゑ遠慮なく御ところへ参るやうにとのお言伝さへございました御様子でした。けれども長明入道さまのはうで、何か心にこだはるものがお出来になつたか、その後両三度、御ところへお見えになられましたけれど、いつも御挨拶のみにて早々御退出なされ、将軍家もまた、無理におとめなさらなかつたやうでございました。 信仰ノ無イ人ラシイ そのやうな事を呟やかれて居られた事もございました。とにかく私たちから見ると、まだまだ強い野心をお持ちのお方のやうで、ただ将軍家の和歌のお相手になるべく、それだけの目的にて鎌倉へ下向したとは受け取りかねる節もないわけではございませんでしたが、あのやうにお偉いお方のお心持は私たちにはどうもよくわかりませぬ。このお方は十月の十三日、すなはち故右大将家の御忌日に法華堂へお参りして、読経なされ、しきりに涙をお流しになり御堂のお柱に、草モ木モ靡キシ秋ノ霜消エテ空キ苔ヲ払フ山風、といふ和歌をしるして、その後まもなく、あづまを発足して帰洛なさつた御様子でございますが、わざわざ故右大将さまの御堂にお参りして涙を流され和歌などおしるしになつて、なんだかそれが、当将軍家への、俗に申すあてつけのやうで、私たちには、あまり快いことではございませんでした。あのひねくれ切つたやうな御老人から見ると、当将軍家のお心があまりにお若く無邪気すぎるやうに思はれ、それがあの御老人に物足りなかつたといふわけだつたのでございませうか、なんだか、ひどくわがままな、わけのわからぬお方でございましたが、それから二、三箇月経つか経たぬかのうちに「方丈記」とかいふ天下の名文をお書き上げになつたさうで、その評判は遠く鎌倉にも響いてまゐりました。まことに油断のならぬ世捨人で、あのやうに浅間しく、いやしげな風態をしてゐながら、どこにそれ程の力がひそんでゐたのでございませうか、私の案ずるところでは、当将軍家とお逢ひになつて、その時お二人の間に、私たちには覬覦を許さぬ何か尊い火花のやうなものが発して、それがあの「方丈記」とかいふものをお書きにならうと思ひ立つた端緒になつたのではあるまいか、ひよつとしたら、さすがの御老人も、天衣無縫の将軍家に、その急所弱所を見破られて謂はば奮起一番、筆を洗つてその名文をお書きはじめになつたのではあるまいか、などと、俗な身贔屓すぎてお笑ひなさるかも知れませんが私などには、どうも、そのやうな気がしてなりませぬのでございます。とにかく、あの長明入道さまにしても、六十ちかい老齢を以て京の草庵からわざわざあづまの鎌倉までまかり越したといふのには、何かよほどの御決意のひそんでゐなければなりませぬところで、この捨てた憂き世に、けれどもたつたお一人、お逢ひしたいお方がある、もうそのお方は最後の望みの綱といふやうなお気持で、将軍家にお目にかかりにやつて来られたらしいといふのは、私どもにも察しのつく事でございますが、けれども、永く鎌倉に御滞在もなさらず、故右大将さまの御堂で涙をお流しになつたりなどして、早々に帰洛なされ、すぐさま「方丈記」といふ一代の名作とやらを書き上げられ、それから四年目になくなられた、といふ経緯には、いづれその道の名人達人にのみ解し得る機微の事情もあつたのでございませう。不風流の私たちの野暮な詮議は、まあこれくらゐのところで、やめた方がよささうに思はれます。 鴨の長明入道さまの事ばかり、ついながながと申し上げてしまひましたが、あの小さくて貧相な、きよとんとなされて居られた御老人の事は、私どもにとつても奇妙に思ひ出が色濃く、生涯忘れられぬお方のひとりになりまして、しかもそれは、私たちばかりではなく、もつたいなくも将軍家に於いてまで、あの御老人にお逢ひになつてから、或いは之は私の愚かな気の迷ひかも知れませぬが、何だか少し、ほんの少し、お変りになつたやうに、私には見受けられてなりませんでした。あのやうな、名人と申しませうか、奇人と申しませうか、その悪業深い体臭は、まことに強く、おそるべき力を持つてゐるもののやうに思はれます。将軍家は、恋のお歌を、そのころから、あまりお作りにならぬやうになりました。また、ほかのお歌も、以前のやうに興の湧くままにさらさらと事もなげにお作りなさるといふやうなことは、少くなりまして、さうして、たまには、紙に上の句をお書きになつただけで物案じなされ、筆をお置きになり、その紙を破り棄てなさる事さへ見受けられるやうになりました。破り棄てなさるなど、それまで一度も無かつた事でございましたので、お傍の私たちはその度毎に、ひやりとして、手に汗を握る思ひが致しました。けれども将軍家は、お破りになりながらも別段けはしいお顔をなさるわけではなく、例のやうに、白く光るお歯をちらと覗かせて美しくお笑ひになり、 コノゴロ和歌ガワカツテ来マシタ などとおつしやつて、またぼんやり物案じにふけるのでございました。この頃から御学問にもいよいよおはげみの御様子で、問註所入道さま、大官令さま、武州さま、修理亮さま、そのほか御家人衆を御前にお集めなされ、さまざまの和漢の古文籍を皆さま御一緒にお読みになり熱心に御討議なされ、その御人格には更に鬱然たる強さをもお加へなさつた御様子で、末は故右大将家にまさるとも劣らぬ大将軍と、御ところの人々ひとしく讚仰して、それは、たのもしき限りに拝されました。 「右大臣実朝」太宰治(青空文庫) 「右大臣実朝」は1943年に書かれているようである。中学生のころから太宰の読者であった、「ファン」というのとは違う、耐えがたいほど「不快」な部分があることにちゃんと気付いていたが、「やめられなかった」って感じだな。その頃は、「富嶽百景」(1939)のような、ほとんど無理に「明るさ」を演じているようなあざといものが好きだった、あるいは、明らかに破局の予感のある、「うつ病」患者の独白としか、今から思えば(笑)見えない、「トカトントン」(1947)とか。でも、今になって、以下に列挙するような、古典の翻案のようなもの、 「駆け込み訴え」(1940)、イスカリオテのユダの独白、 「新ハムレット」(1941)、もちろんシェークスピアの翻案、 「新釈諸国噺」(1944)、井原西鶴の翻案、 「惜別」(1945)、魯迅の仙台留学時代に取材したもの、 のような作品が、もっともよく筆が滑って(笑)、饒舌で、機知に富んでいて、面白い、と思えるようになってきた。「子供」には、背景知識が乏しいから(笑)、難解だったという理由もあるが、無意識に(笑)これらを「敬遠」していたのだとしたら、それは「転向」問題、だったろうか、と思う。いくつかの作品の中で、自分が金持ちの御曹司であることへの「罪悪感」から、学友の誘いを断り切れなかったとして、自嘲的に語っているが、おそらく事実は、なかなか勤勉な、日本共産党地下細胞の活動家だったようにも見える。1932年、と言うから、太宰治(1909-1948)であるから、23歳になるか、長兄の説得に応じて、警察に出頭、二度と左翼活動に関与しない、との誓約書を提出している。「富嶽百景」などに見える、変に取り繕った「明るさ」は、「転向」の事実への、「躁的防衛」と見て差し支えないと思う。それが、もし「円熟」に向かうのだとしたら、「転向」の事実自体に対する、いわば「喪が明けた」ことになる、とフロイトのメランコリー論を調子に乗って敷衍すれば(笑)、言えるだろう?1944年に、「大日本報国文学会」なる翼賛団体が結成され、太宰は、むしろ積極的にそれに関与している。はっきりとはわからないが、「津軽」(1944)と、「惜別」(1945)はこの団体からの資金援助を受けて執筆したようである。平たく言えば、「転向者」であることに、「開き直った」(笑)、のである。「惜別」の中には、もとより魯迅がそんなことを言う訳がない(笑)、見え透いた「国●体賛美」らしき一節もあって、あからさま過ぎてむしろ、こいつは「特●高」警察の検閲官を愚弄しているのでは、と疑うほどなのだが、いや、そんな風にして、この作家がまだ「反骨精神」をもっていた、などと、弁護する必要もなかろう、私のそれらの作品に対する「評価」が変わったとすれば、だから(笑)、私もまた、「転向?、それも、いいんじゃん?」と、同じく「開き直った」からに他ならない。もちろん、「自己弁護」を含んでいることは(笑)、隠すまでもないが、どんな運動にも、かならず、「転向者」が現れるのを、押しとどめることはできない、人が「絶望」するのには、人それぞれの「理由」があり、それは「運動」の「正しさ/正しくなさ」、巧拙、とかにはかかわりのない「私事」である、「同志」を「官憲」に売った「裏切り」行為があったのなら、存分に弾劾し、攻撃してもよかろう、しかし、「変節」したことそ・の・も・の・を取り上げて、ことさらに、難詰して見せる口ぶりは、むしろ、「死穢」に対する忌避感情と同根で、自己愛的にさえ見える、と、まあ(笑)、これも、こちらの、一つの「老成」、なのであった。 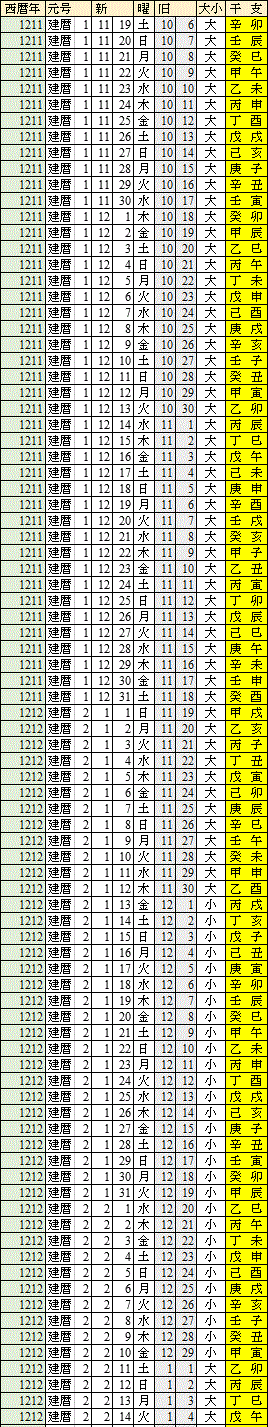 ところで、これも以前に調べたのであるが、またしても、ほとんど「偏執」的「暦」マニア(笑)、上の太宰治「右大臣実朝」に引用してある、「東鑑」とおぼしき書物の記述、史実として、鴨長明が鎌倉に源実朝を訪問したのが、建歴元年、グレゴリオ暦1211年なのだとすれば、そこに「誤り」が含まれることになってしまいそうなのである(笑)。「源氏物語」全文が、ネットで閲覧できる時代であるから、きっと「東鑑」だって調べがつくのだろうが、そこまではしないで(笑)、あるいは、太宰の、写し間違い(笑)、と責任転嫁する余地も残しておいて、 建歴元年、グレゴリオ暦1211年の旧暦、十月は「大」の月、十一月も「大」の月、ここまではよい、十二月は「小」の月である。ちなみに、平均朔望月約29.5の近似法として、「大」の月30日と、「小」の月29日を半々に混ぜて、旧暦の平年は出来上がっている。 次、日付に割り当てられる「干支」であるが、これはいつを起源に設定しているのか知れないが、それこそ「東鑑」の如き歴史書の解読に当たっては、年号、日付の「裏付け」として重要な手掛かりとなるものなのであるが、困ったことに(笑)、 建歴元年十月十三日(グレゴリオ暦1211年11月26日)は「戊戌」、 建歴元年十一月廿日(グレゴリオ暦1212年1月2日)は「乙亥」、 建歴元年十二月十日(グレゴリオ暦1212年1月22日)は「乙未」、 なのである。もとより、同じ「干支」の日は、10と12の最小公倍数、60日毎に現れる、「東鑑」記載の「干支」に該当する、直近の日付を探すと、 建歴元年十月六日(グレゴリオ暦1211年11月19日)が「辛卯」、 建歴元年十一月十三日(グレゴリオ暦1211年12月26日)が「戊辰」、 建歴二年一月四日(グレゴリオ暦1212年2月14日)が「戊午」、 となって、上二つは、綺麗に、一週間の誤差なのだが、最後のものはそうでもない、という、ずれの規則性すらない(笑)、という困った結果になってしまった。いや、それだけの話なんだがな(笑)。  こうして、私たちは、この世でた・だ・一・つ・の、自らを構成するたんぱく質を豊富に含む高栄養物質を「憎悪」する、生き物になったのです。 「雨いたく降りぬべし。かくて置いたらば、死に果てはべりぬべし。垣の下にこそ出ださめ」 と言ふ。僧都、 「まことの人の形なり。その命絶えぬを見る見る捨てむこと、いといみじきことなり。池に泳ぐ魚、山に鳴く鹿をだに、人に捕へられて死なむとするを見て、助けざらむは、いと悲しかるべし。人の命久しかるまじきものなれど、残りの命、一、二日をも惜しまずはあるべからず。鬼にも神にも、領ぜられ、人に逐はれ、人に謀りごたれても、これ横様の死にをすべきものにこそあんめれ、仏のかならず救ひたまふべき際なり。 なほ、試みに、しばし湯を飲ませなどして、助け試みむ。つひに、死なば、言ふ限りにあらず」 とのたまひて、この大徳して抱き入れさせたまふを、弟子ども、 「たいだいしきわざかな。いたうわづらひたまふ人の御あたりに、よからぬ物を取り入れて、穢らひかならず出で来なむとす」 と、もどくもあり。「源氏物語・手習」紫式部(wikisource) 「このまま置けば死にましょう。 と一人が言う。 「真の人間の姿だ。人間の命のそこなわれるのがわかっていながら捨てておくのは悲しいことだ。池の魚、山の と 「よけいなことだがなあ。重い病人のおられる所へ、えたいの知れないものをつれて行くのでは と非難する者もあった。 「源氏物語・手習」紫式部/与謝野晶子(青空文庫)  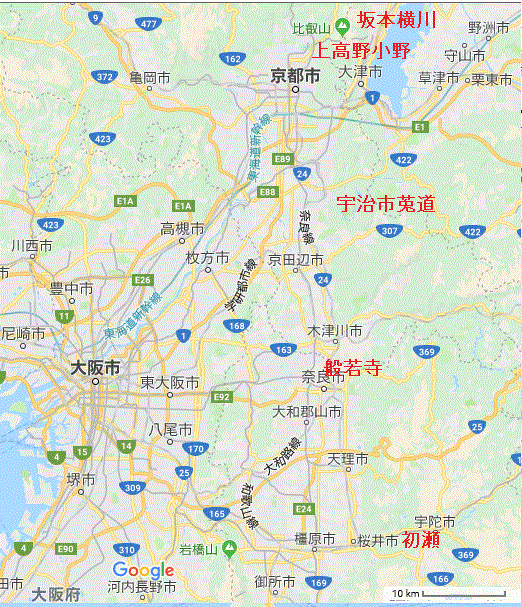 「夜明け前」、「方丈記」の余勢を駆って(笑)、放置してあった、「源氏物語」、角川ソフィア文庫の抜粋版ではありますが、「宇治十帖」の部分、読了しました。前にも書きましたが、大塚ひかり「源氏の男はみなサイテー」の中で、薫と匂宮の二人の、「サイテー」な男たちとの三角関係に疲れ果て、自殺を試みた浮舟を、横川の僧都が、救出する情景にとても興味があったのですが、ソフィア文庫版にはそれがないので、やむなくネットを渉猟しておりますと、おや、wikisourceには、原文全文が、そして「青空文庫」には、与謝野晶子訳が、やはり全文、揃っているのですね。周りの人々がことごとく、 1.この人は、も・う・じ・き・死ぬのだから、「外」へ運び出しましょう、 というのに対して、僧都は断乎として、 2.いや、この人は、ま・だ・、生きているのだから、「中」へ運び入れよう、 と主張する。宗教が社会的存在として存在しうるためには、多かれ少なかれ、「人間主義的humanitarian」装いをまとっていなければならないはずだ、という、近代的な常識からすれば、当然の振舞に見える、2.は、実は、平安時代のモラル体系の中では、異様なものであったかもしれないことに思い至らされます。 「あらすじ」を見ておきますと、比叡山横川(よかわ)中堂の高僧、「横川の僧都」の母が、「初瀬」、現・奈良県桜井市、長谷寺(はせでら)へ巡礼に出掛けた帰途、「奈良坂」、現・奈良市般若寺、辺りで、気分が悪くなる。母も尼僧で、これは、比叡山の麓、「小野」、現・京都市左京区上高野に住んでいるのだが、そこまでは帰り着けそうにないので、途中の、確かに地図で見てもちょうど中間地点、それでも20kmあるが、「宇治の院」、これは平等院のことかとも思いましたが、ここに描かれている裏寂れた雰囲気が、あの絢爛豪華さと折り合わない気もしたので(笑)、現・宇治市莵道(とどう)の三室戸寺(みむろとでら)は、この源氏物語浮舟ゆかりの地と言われているそうなので、そこ、と推定して(笑)、休憩することにする。 その庭に、白装束の、髪の長い、なにか異様な物の怪めいたものがうずくまっている、それが、自殺未遂で衰弱、意識を失っている浮舟であった。 人々のもっぱらの関心事は、そのような「死にかかったもの」に、付着していると想定される「死穢」が、自分たちに「感染」するのではないか?という恐れであって、ならば、そのような「穢れ」は、あらかじめ、「外」へ排除してしまって、「中」を清浄に保たなければならない、と急き立てられるのは、この時代の人々にとっては、当然の、常識的な振舞であったろうことが、言葉の端々から、読み取れるような気がします。まことに、高橋貞樹「被差別部落一千年史」(岩波文庫)が強調していたように、この国の人々に、異様なまでの「死穢」への嫌悪を「研ぎ澄まさせ」たのが、もっぱらこの、平安時代に、教線を拡大した仏教であったことが、頷ける気がします。 「代謝」という生化学的な「振動」系、もちろん、そのうちの「半分」は、「エントロピー減少」という、確率論的には通常ありえない、奇跡のような過程です、そのような「生」という状態に物質的基礎を有するしかない、私たちの「意識」にとっては、その「振動」が減衰、終結してしまった「死」という状態は、文字通り「想像を絶する」ものであれば、それを、否も応もなく「恐れる」であろうことは、当然のこと、でも、「私たち」の身振りの中に刻み込まれているかもしれない、ほとんど「強迫的」な、「穢れ」への「忌避」感情は、それだけでは説明できなさそうに思える。もちろん、「言葉」は、「隠喩」、「類推」によってどんどん観念を増殖させていくから、「忌避」の対象が、「死」そのものから、「死」を「含意」しそうなあらゆるものに、拡大していくのは「自然」の流れであろう、たとえば、ここでも、浮舟は、ま・だ・、死んでいないのである、しかし、「死にそう」だから、既にそれは「死」による「穢れ」を、暗示しているから、あらかじめ、「外」に出しておけ、と言っているのである。 私は、と言えば(笑)、そんなことを考えることになったきっかけは、何十匹もの猫に囲まれた「引きこもり」暮らしのおかげです。猫は、まず、「死体」に対して、何の感情も示しませんね。「言語」というソフトウェアの稼働を可能にするほどの記憶容量を欠いている以上、眼前の「死体」の物質性と、自分たちの「未来」に必ず訪れる「死」という事態を結び付けて考えることができない以上、当然のことです。「動物」には「感情」がないんだ、なんて得意そうに言わないでくださいね(笑)、子猫がいなくなってしまった、つまり、「死体」を私が片付けたからなんだが、母親は、いつまでもあの、子猫に呼びかける甘い甘い声で、「切なく」呼び続けていますよ、それは「嘆いて」いる、と言ってすこしもさしつかえがない、また、猫は、「うんこ」に対する忌避感情をもっていませんね、砂をかけて隠す、と言われているのは、うちの子たちは、それすらしない(笑)ものも多いですが、肉食獣としては、匂いによって被食者に存在が知られることを回避する組み込まれた適応と解することができるのであって、現に、「うんこ」をした後、彼らは自分の肛門の汚れを、綺麗に、舐め取ります。私の「仮説」はこんな感じ(笑)、 1.記憶容量の拡大に見合う頭脳の重量を、「四足歩行」では、支えきれなくなった、 2.重たい頭を、身体の中央部にもってきて、モーメント釣り合いを保つためには、その分、重たい頭の位置が異常に高くなる、というリスクを負うものの、後ろ足で「立ち上がる」しかなかった、 3.この「二足歩行」という、どう見ても、合理性を欠いた、無理な、「決断」は、身体構造のいたるところに、「異常」を発生させた、たとえば、私たちは鳥や猫の足を見ると、折れ曲がり方が「反対」だと思いますね?いえいえ、私たちが「反対」なのです、「元来」足の中央部にあった「くるぶし」まで、着地させないと、重量が支えきれなかったからでしょう、もっと大きな、重大な影響を伴った「無理」が、他ならぬ、私たちが、自らの肛門を、舐めることはおろか、「見る」ことすら出・来・な・く・な・っ・た・、ことでしょう?、 4.「見る」ことができないものが、「恐れ」、従って「忌避」の対象に算入されるであろうことは、想像に難くない、こうして、私たちは、この世でた・だ・一・つ・の、自らを構成するたんぱく質を豊富に含む高栄養物質である、「うんこ」を「憎悪」する、生き物になったのです、 「他人」の手を借りないと、自分の「うんこ」の世話ができない、それが、幼少期の最初の「トラウマ」経験を構成しているのでは、という児童心理学上の知見もあるそうでし、「ス●カトロジー」という一つの「異端」の存在もまた、その傍証となるだろうと思っています。 私自身、そういう、「二足歩行」に伴う「無理」を組み込まれた「人間」ですから、もう、それはそれは、この二十年間の暮らしの中で、膨大な量の猫の「うんこ」処理に投入されてきた手間ひまは並大抵のものでなかった、ひょっとしたら「鬱」がちっともよくならないのは(笑)、そのせいかもしれないと思うくらい、「うんこ」が、人を疲弊させ得るものであることを知りました。それに、もう既に何十匹もの、猫の「死」にも立ち会い、「死体」を目の当たりにすることもしてきたわけですね。あんなにも「愛しかった」生きた個体が、急速に「恐怖」や「忌避」の対象たる物質性を帯びてくる過程は、自分でも、やりきれないものでしたから、だから私は、「死」を、従って「死」を「隠喩」しかねないもろもろのもの、「排泄物」、「病」、「怪我」、「異常」、・・・、ことさらに「憎まない」ように、「努力」せざるを得なかった、私が「優しい」人間だからじゃありませんよ、そうしなければ、「憎悪」に押しつぶされてしまいかねない、「環境」だったからに過ぎません。私の家は、すさまじく(笑)「不潔」です、これだけ猫がいれば、どれだけ「清潔」にしようとしたって、ほとんど無駄ですが、もちろん「鬱」のおかげで身体が動かないから、あんまり掃除をしないようになっただけのことだが、それも私の身体が「選択」してくれた、と言えなくもない、こうして私は、まことに、「千二百年」の歴史を持つ(笑)かもしれない、この国の「禊(みそぎ)」の文化を、多少は距離をもって眺め得る立場にたてているかもしれない、と、やや(笑)誇らしくも、感じています。あのね、「そんな綺麗ごとじゃない」って言い草がありますけど、確かに、たとえば「共生」とかって、まさしく「綺麗ごと」じゃないんですよ。「綺麗」でないかも知れないものも・、愛せる、ためには、自分も、「綺麗」であることを、少しは、「諦め」ないと、いけないんだ。そうそう、「方丈記」に出てきたのかな、「源氏」だったかな、古語の「あきらむ」は、「明らむ」、「明らかにする」、心の中をはっきりさせる、それが「諦める」に変化したのかどうか確証はないが、だとしたら興味深いね。 長谷寺は真言宗、西国三十三所観音霊場の一つ、三室戸寺は、聖護院を本山とする本山修験宗、やはり西国三十三所観音霊場の一つ、本山修験宗は、天台宗の流れを汲むという、・・・、 長谷寺と三室戸寺は、どちらも一度だけだけど、行ったことがあるな。上高野は、うちから近かったから、何度も歩いた、比叡山は、車があるときなら、お決まりのドライブ・コースだったしな。聖護院にいたっては、「極●左暴力集団の巣窟」の誉れ高き(笑)、京大○○寮のすぐ近くだから、毎日のように通りかかったものだ。二十年離れていると、老齢のせいもあるし(笑)、記憶がかすれているから、ああ、こんなことなら、もう一度訪れてみたい、と思わなくもないが、そんなことは決してないことに決めてあるから(笑)、それはそれでよい、この京都の地図も、同じく決して訪れることのない、マラケシュやロンドンやハルツームの地図と同じように、眺めればよい。 「源氏物語・全」紫式部/与謝野晶子(青空文庫) 源氏物語・全文(wikisource) 初瀬、奈良県桜井市初瀬、近鉄大阪線長谷寺(googlemap) 奈良坂、奈良市般若寺(googlemap) 三室戸寺、宇治市莵道(googlemap) 小野、京都市左京区上高野小野町(googlemap) 延暦寺横川中堂、大津市坂本本町(googlemap) 「一生のうちに読むべき三冊の本、『源氏物語』、『カラマーゾフの兄弟』、『夜明け前』」談義が、そもそも、「夜明け前」を読み始めるきっかけだった。で、「長い小説」、と言えば? マルタン・デュ・ガールRoger Martin du Gard「チボー家の人々Les Thibault」、そうですね、私たちより少し上の年代に、爆発的に流行したようですね。小津安二郎の映画「麦秋」、北鎌倉駅で、横須賀線の通勤電車を待つ間、原節子と、相手の俳優の名前は知らない、との会話、 「面白いですね、『チボー家の人々』」 「どこまでお読みになって?」 「第四巻の途中です」 つまり、原節子の方が、自分はもう読んだが、これおもしろいから読め、って勧めたんでしょうね。この映画、1951年の公開ですから、そう、その時代の観客が、「そうそう、あたしも、あれ読んだ」って感じの感想もつように作られている筈ですね。その映画の中で、手にしている本が、岩波文庫に見えた気がしたんだけど、今アマゾンで(笑)調べてみると、白水社からしか、出版されてないみたいだな、今は「白水Uブックス」という新書版のもので、全13巻、ええ、もちろん、読む気はありません(笑)。 1920年から書かれたそうですが、中身は、第一次世界大戦前夜と戦中、時あたかも全ヨーロッパが、革命の予兆に揺れている時代ですね、だそうで、次男のジャックは、おそらく社会主義的な革命運動に、身を投じる、ということになっているみたいですね。ちなみに、戦前に出版されている白水社版は全8巻、これなんだとすれば、その「麦秋」の登場人物は、半分くらい読んだことになるな。ああ、気になる(笑)、から今から、DVD見ることにします。 長い小説、と言えば、中里介山「大菩薩峠」、「青空文庫」でも41巻ありますね。角川文庫で27巻、あの頃の本屋さんでは、棚一つ分これが占めてましたね。剣客ものの時代小説、と侮っていましたが、去年あたり、幸徳秋水とか、堺利彦を調べていると、この作家が、「平民新聞」にも関係した社会主義者だったことを知って、ちょっと見方が変わりました。でも、もちろん(笑)、読む予定はありません。でも「夜明け前」と、舞台も、時代も、近いんだ(笑)、「青空文庫」タダだし、思わず読み始めてしまったら、どうしよう(笑)? 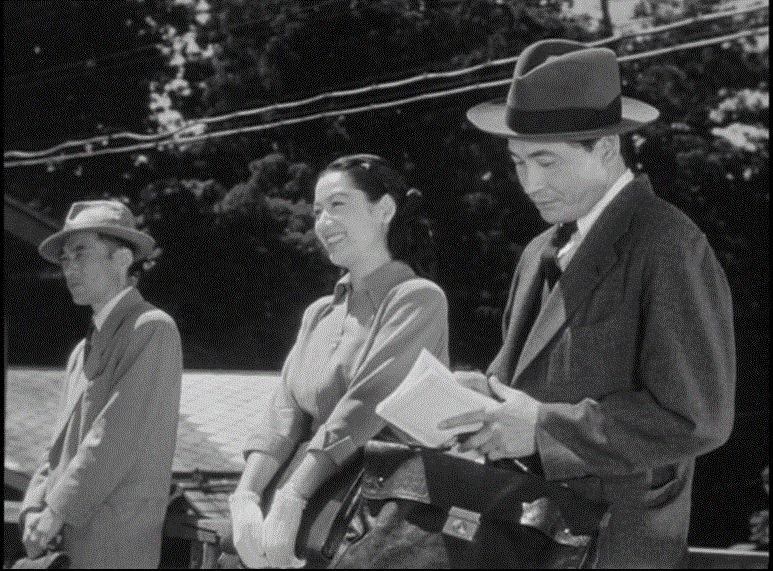 今、小津安二郎「麦秋」(1951)、124分に及ぶこの長いフィルムを、見終えたところ。ああ、確かに、記憶違いだったんですね(笑)、文庫本より版型の大きい単行本ですね、表紙のレイアウトも、確かに、アマゾンで見た白水社版のものと同じだ。二人の会話はもう終わって、電車を待っているところなのに、原節子が、なんだか、思い出し笑いみたいに、無防備に笑っているのが面白い(笑)、こんな風にご家庭で、いとも簡単に、映画の一コマを「写真」にしてしまえるなんて、原節子氏(1920-2015)も、草葉の陰で苦笑なさっていることでしょうが。   前にも言いましたが、世界が小津映画に驚嘆した、ことは数々あろうが、たぶんその一つは、画面割のほとんど「神経質」なまでの、水平線、鉛直線との平行関係、対称性、へのこだわり、なんだろうと思う。さあ、巨匠ヒッチコックを引き合いに出すのは失礼ですが、比較してみます。前にモロッコ談義で触れた、「知りすぎていた男The Man Who Knew Too Much」(1956)、アンブローズ・チャペルという名の人物を探しに、タクシーを降りたところ。左は、「麦秋」、東京、原節子が、「タイピスト」として勤める貿易会社の窓から。 いくつか、例によってどうでもいい事柄だが(笑)、備忘のために。 「麦秋」とは、麦が実る季節を、あたかも米が実る「秋」に見立てた表現であって、旧暦四月頃を指す。イネ科のコムギもオオムギもともに、元来は、秋に種をまいて、翌年春に収穫する。これが「秋播き」で、なんでも、果実が膨らむのに、一定の低温期間を必要とするのだそうである。品種改良によって、「春播き」化されたものも、世界的には多々あるが、日本ではかつてもっぱら、米の裏作として用いられたから、「秋播き」が主流であった。映画の最末尾は大和盆地の畑一面に実った麦の光景だが、既にムギという穀類を、この国がほとんど産しなくなってから久しく、したがって、そのような光景への記憶をもたない「世代」である私には、それがコムギなのかオオムギなのかは、わからない。 北鎌倉の家では、笠智衆、原節子兄妹の父、文筆家であるらしい、が「カナリア」を飼っている。モノクロ映画だし、声からはメジロかと思ったが、「カナリアの餌を買ってくる」という台詞があったからね。アトリ科、そう、「夜明け前」で半蔵の父と隣人の金兵衛が、若い頃よく「食べた」、あのアトリの仲間であるようだ。名前の由来は、これも奇しくも、スペイン領モロッコの沖合、カナリア諸島Islas Canarias、を原産地とすることから。で、調べていて横道に逸れたのだが(笑)、アトリ科は英語で、正式な名、学名とは異なるが、「フィンチfinch」と呼ばれることが多く、かつ、同じ「フィンチ」なる言葉が、必ずしも分類上近縁とも言えない多くのものを指すことがある、文鳥や、当地の「篭脱け」シマキンパラなどを含むカエデチョウ科のものにもあるようだ。それで思い出したのが、ダーウィンフインチ、Darwin’s Finches、これはフウキンチョウ科というそれ自体南北アメリカ大陸にのみ産する科であるが、そのうち、ガラパゴス諸島などごく限られた島にのみ生息する者らしい。もちろん、チャールズ・ダーウィンがビーグル号での航海中に発見したのである。それで、ああ、「ビーグル号航海記」(岩波文庫)、全四巻も、途中で頓挫したままになっていることを思い出した。「夜明け前」、「源氏物語」で、一息ついている場合では、ない(笑)、そう、も・う・、時間は限られているのだからね(笑)。 この北鎌倉の家に越してきてから足掛け16年になる、という台詞があった。映画の公開時1951年を、「語り」の「現在」、28歳の、原節子扮する妹娘が、その、北鎌倉駅で「チボー家の人々」について語る相手、研究所に勤める医師の兄、笠智衆の研究助手でもある、妻に先立たれた、シングル・ファザーの元に、「嫁入る」時点、と想定して、その「16年」は、「明治維新」以降、ほとんど休みなく「戦争」を継続してきたこの国家の、そのひ・と・つ・な・が・り・の戦争最末期と、そして、初・め・て・の・、「戦後」が含まれている。笠智衆、原節子、兄妹の間にはもう一人、男の子供がいて、応召して中国大陸の戦線に赴き、ま・だ・、帰還していない。原節子の結婚相手は、その兄の学校時代の同級生であった。戦地から送られてきた手紙に、麦の穂が封入されていた、と語られる。もちろん、映画のタイトルと、響きあうようになっているのだろう。「そのとき、僕は、ちょうど『麦と兵隊』を読んでいたのでね」、と語られる。という訳で、長年気がかりであったが、ある種「避けていた」、この、コントラヴァーシャル(論争的)な、かつてのベストセラー、を、そう、もう、この際、いつまでも「避けている」場合でもなかろう?、読むことにした。本日、注文、火野葦平「土と兵隊・麦と兵隊」(新潮文庫)。    私は、子供の頃、うちが貧乏だったのと、二人とも教員だった両親が、「低俗文化」として(笑)「排斥」していたので、「漫画」というものをほとんど読んだことがなく、大人になってから、人々の会話についていくには読んでないと困るじゃないですか、だから読んでみましたけど、しかるべき成長期に「文法」を獲得していない言語、みたいなもので、「読み方」が、いまだにわからないんだ(笑)。でも、高野文子って人の作品、たぶん、いくつか読んだ記憶あるし、これ、「黄色い本」、面白そうだから、読んでみることにしますね。 で、さっき、主に猫の餌を買うために(笑)、三日ぶりかな?外に出て、わりと気分もよかったので、チェーン店の古書店に立ち寄り、「コミック」売り場なんて、足を踏み入れたこともない、でも、あっさり見つかって、値段も\360、と格安、今しがた、ご飯食べながら、ゆっくり、二回、読み返しました。漫画の「文法」を獲・得・し・て・い・な・い・というのがどういうことか、そうでない人には想像できないでしょうが(笑)、たとえばこのページに描かれているこの人物と、こちらのこの人物が、同じ服を着ているから同一人物だ、というような事柄が、すぐには飲み込めないのです(笑)。だからゆっくり、繰り返し読まないと駄目なんですよ。でも、もう大丈夫と思う、「トーちゃんは、プロレタリアートか?」と問われる本好きの父と、「知って得する知らねば人に笑わいる」と「煮〆」の作り方を教えてくれる母と、実地子と、弟の基根、が四人家族で、叔母さんの娘の、留ーちゃん、を預かってるんですよね。でも、もっとどうでもいいディテールには、これはある種の精神疾患の症候、かとも思えるが(笑)、気付けます。ラストシーン、図書館に返却してしまう直前、「奥付」がクロースアップされますね、初版が1956年で、白水社の五巻本です。アマゾンでそれに該当するのを探すと、一番右の写真のものになります、古本だから色はかすれていようが、あまり「黄色い本」には見えない。それに、その図書館から借りてきた本を机の上に投げ出すシーンがあるでしょ?表紙には、「Les Thibault 1」とだけ、右下の方に、HAKUSUISHAと読めなくもないようなアルファベットの塊、ひょっとしたら、この版本には、そんな黄色いカバーがかかっていたのかしら?あるいは、末尾に、これは著作権関連の表記なんだろうが、1922年のフランスで発売されたガリマール社Gallimard版に触れてある、ひょっとしたらそれが「黄色い本」だったんだろうか?とも疑ったが、これは調べがつかなかった。ちなみに、上の写真、真ん中のものは、戦後すぐに出た同じく白水社の八巻本で、これが、ご覧ください、上に掲げた小津安二郎「麦秋」、北鎌倉駅のシーンに写り込んでいるものです。wikipediaの説明によりますと、「チボー家の人々」、次男のジャックは、「感化院」を出入りしたりする、なかなか活動的な問題児、革命運動に関与して、1914年夏の、第一次世界大戦開始直後、おそらく前線に反戦ビラを撒くために搭乗した飛行機が墜落して、ほどなく死亡する。友人の妹ジェンニーは、その恋人。雪降ろしのために貸し出したスコップを引き取りに小学校へ行くシーンがあるでしょう?その帰り道、実地子は、ジャックたちとともにデモに参加している自分を幻視する。「ユマニテ社に行く人たちでしょうか」、L'Humanite、「人間性」の意だが、は、今はフランス共産党機関紙だが、当時フランスには、いや世界のどこにも、か、「共産党」は存在していなくて、社会主義インターナショナル(第二インター)フランス支部の機関紙が「ユマニテ」だった筈だ。「ジャック、その人に騙されてはいけません、その人は同志ではありません」という台詞とともに、ついさっき、小学校の宿直室に居合わせた若い男の顔が浮かび上がりますね、タートルネックのセーターを伸ばして顔の下半分を隠して見せ、「トックリって、ヘルメットかぶったとき便利なんだよな」と言います。高野文子さんは私より一歳年上のようで、実地子が作者そのものと仮定すれば、高校三年なら、1975年あたり、「都会」の大学に行って、「新●左翼」の「学生運動」に首を突っ込んでいることを、故郷に帰って、地元の女子高生に向かってこっそり自慢して見せるような、浅はかな(笑)人は、たくさんいただろうと、いや、特に悪口でもない、世の中全体が「浅はか」だったかもしれない時代への哀惜をも込めて言っています。 はい、気に入りましたよ。じわっと、いい作品だと思いました。 自分の好きな人を 大切にすることは それ以外の人には 冷たくすることに なるんでねえの の台詞が、好きです。あ、もう一つ(笑)、冒頭、雨の日バスの中で「チボー家の人々」熟読していて、気分悪くなります。友達に「ほりゅうの質だもんで」って言います、「ときどき難しい言葉使うよね」と言われます、私も分からなかったので調べると(笑)、「蒲柳」、ヤナギ科ヤナギ属カワヤナギ、その枝ぶりがなよなよしているからなんだろうか?「蒲柳の質(しつ)」で、身体が弱く、病気にかかりやすい体質、を言うのだとのこと。 「夜明け前」談義、補遺。 筑波山で挙兵した水戸の勤王派が、半ば「敗走」の軍隊として、東山道を通過して「西」の都を目指す、その描写が、「夜明け前」全編を通して、もっとも「手に汗握る」クライマックスをなしていたように、思います。史実に必ずしも合致しているかどうかはわからないが、これは、たとえば、その後、「王政復古」以降の、「慶喜討伐」を掲げた「官軍」の東上に比すれば、略奪行為なども少なく、沿道の人民にも、ある程度の「好意」をもって迎えられた、少なくとも、藤村はそのように見ているわけで、それは、彼が記述に際して参照した父正樹の日記などから得た印象に由来するのだろうとも思われますが、言わば、この人たちの「志の高さ」が、読者にも伝わるからそうなるのでしょう。興味深いのは、幕府の討伐隊が、その軍勢を追ってやはり東山道を下るのだが、ち・っ・と・も・、追いつかない、明らかに、戦闘を回避しているのです。それも、人心の離反を恐れている、と見ることができる。沿道の諸大名も、幕府の命に反するわけにはいかないものの、出来れば、直接対峙することなく、通過を黙認してしまいたい、という者も多かったのでしょう。 よく言われることですけど、戦争というのは、始めることよりも、終わることの方が、ずっと難しい、更に、そもそものはじめから戦闘を回避することの方が、より高度な政治力を要するわけです。その意味で、幕府方、たとえば尾州藩は、徳川直系であるにもかかわらず水戸と同じく、勤王の強いところのようですから、「建前」としては、討伐軍を出すものの、出来れば戦闘は避けたい、そのために、周辺大名との間で、迂回路の通過を交渉する、などの、「外交」的政治力を発揮できた、伊那谷の「平田派」は、ここでは、ちゃんと、「当事者性」をそなえた、成熟した「政治勢力」として登場している訳で、高い評価を受けるのも、当然だったのでしょうね。人々は、本来、冷静であれば、戦争を扇動する指導者よりも、戦争を終結させ、回避しうる能力を有した指導者を、信頼し、尊敬するものなのだ、ということが判ります。ある意味、この時がまた、「平田派」全体にとっても、「黄金時代」だったかもしれません。中津川の景蔵などが、その渦中で大活躍をしたのに反して、馬籠の半蔵は、本陣・庄屋・問屋としての仕事に縛りつけられていて、焦りを感じている節がありました。それは、同じ役目であるにもかかわらず、彼らの「上部」に立つ管轄者が、中津川なら尾州藩だが、馬籠は、木曽福島の、言わば強硬な佐幕派であった、という事情にもよるのでしょうが、ずっと後年、アルコール中毒を伴う精神の変調とともに、「過激」な行動に出てしまうのは、あるいは、彼、半蔵が、その時代の、「勝利」の経験をもっていないからなのでは、などと言う穿った見方も、思わずしてしまいそうです。 思い出す事件が一つあります。何年前か忘れましたが、外電記事で読んだ、今のように、一方にサウジ・アラビアとUAEの介入、他方にイランからの援助、と「代理戦争」の様相を呈するようになるずっと以前のイエメン、「AQAP/アラビア半島のアル・カイダ」という組織が、誘拐事件を引き起こしました。誘拐されたのは、南アフリカから人道的支援に来ているボランティア教師、あるいはキリスト教徒だから、という理由があったのかもしれないが、ほとんど「人違い」と言ってもいいようなものだったと思われる。派遣元の南アフリカのボランティア団体は、おそらく数日のうちに、様々なチャネルを通じてだろう、誘拐者のAQAPと、交渉の窓口を確立することができ、ほとんど、釈放の日取りも決まっていた。そこへ、アメリカ合衆国の「ネイビー・シールズ」、海軍の特殊部隊です、オスプレイに兵員を乗せて急襲、「人質解放作戦」を展開し始めた。合衆国が、人質解放交渉について、「知らなかった」可能性もある、あるいは、「知って」いて、その上で、「テロリストと交渉しようとする者には、教訓を与えなければならない」と、「パターナリスティック」な振舞に及んだのかは、定かではないが、ともかく、その「作戦」は、失敗、「テロリスト」を殺害することはできたものの、誘拐者はこの振舞を当然、「解放交渉」の「違約」と見做しますから、被誘拐者も、殺されてしまいます。南アフリカ人の教師の妻が、取材に答えて言います、私には、少なくとも、最愛の夫、という「失うもの」、があった、世界には、しかし、「失うもの」を何一つ持たない人々が、数多存在していることを、私は知っているから、私は、この人たちを、責めようとは、思わない。 これを伝える新聞の論調は、アメリカ合衆国という国家の、「当事者能力」の欠如、凋落、という文脈で語っていました。常識的には、「人でなし」としか思われていないアル・カイダ、などという「テロリスト」が、国際ボランティア団体などと、ちゃんと「外交交渉」ができる「当事者性」を発揮しているのに反して、アメリカは、ただ、それを、自分が関与していない、と言うだけの理由で、ぶちこわしにして恥じない、ということを明らかにしてしまった。「世界」は、「アメリカ」がいなくてもやっていけるし、いや、むしろ「アメリカ」がいない方がうまくやっていけるかもしれない、ことが明らかになった訳です。 戦争を終わらせることができるのは、「敵」と、「話」が出来るからなのですね。だから、実は、どんな「戦争」においても、「敵」と「味方」は、「ツーカー」の状態であるような、「回路」、「窓口」が、どこかに確保されているものなのでしょう。ヘミングウェイ「誰がために鐘は鳴る」、やっと読み終えました、へとへとです(笑)、でも、ロバート・ジョーダンが「POUMはファシストと裏でつながってたんだろ?」というのに対して、ソ連のエージェントであるカルコフは、「ファシストとつながっていないものがあるのかね?」と皮肉に問い返しますが、まことにその通りで、ややもすれば「スパイ」と罵られて失脚する憂き目に甘んじなければならない位置に、双方の事情に精通し、交渉の「落としどころ」を弁えた、しばしば有能な「官僚」がいるものなのです。「夜明け前」、第二部の冒頭にも、山口駿河という、幕府の外交方の人物が登場、外国語に精通し、「異人」の心理もある程度弁えているから、建前ばかりの「開国/攘夷」いずれの論とも別に、当面の紛争を解決し、それはもはや「幕府」を守っているのか、それとも「日本国」そのものを守っているのか、よくわからなくなってくるのだが、粉骨砕身するものの、歴史の激変の中に埋もれていく、一人の優秀な「官僚」として、共感をもって描かれている。親・幕府方のフランス外交官ロセス(ロッシェ)の通事、メルメット・カション(メルメ・カション)、もそうですね。両方の「言葉」がわかる、と言うのは、敵対的であるかも知れない、両当事者の立場が分かる、ということなので、「板挟み」は避けられないが、しかし、そこにしか「解決」の糸口は、ないのですね。 そんなことは、コップの中の嵐のような些末なものであっても、少しでも「運動」めいたものを経験すれば、すぐに理解できます。例えば、辺野古のゲート前でも、現場の指導者は、みな、ある意味、沖縄県警と「ツーカー」です、あと、三十分で必ず引かせるから、それまでは、逮捕は控えてくれ、みたいな話が、間違いなく、取り交わされているのです。相手も、それを、ちゃんと、「尊重」してくれるのです。それを、たとえば、「内地」からはるばる航空運賃はたいてやって来たからには、「機動隊と激突した」という「武勇伝」を土産に是非とも持って帰らねば、とばかりに(笑)、最前列で跳ねてしまって、逮捕される、みたいな人が後を絶たない(笑)、おっと、失礼、私もまた、つまらないことに「逆ギレ」して逮捕の憂き目にあった一人ですから、偉そうなことは言えませんね(笑)。 かつての、日本の「軍部」は、どいつもこいつも「好戦的」なだけの無能な人物ばかりだった、みたいな言いぐさは、採用したくない、と思っています。そのような「理解」の「型」は、「悪い」事態が生じた原因は「悪い」奴がいたからだ、という「トートロジー」しかもたらしませんし、では、どうして「悪い」人間が生じるのか?、あなたがもし「悪い」人間でな・い・、と言うのなら、その根拠はどこにあるのだ?という思考に少しも導いてくれない。ただただ、「悪い」のは、自分以外の誰か、え、私?私は大丈夫、私は「悪い」奴じゃな・い・から、という、「自分だけが助かりたい、カンダタの無慈悲な心(蜘蛛の糸・芥川龍之介)」、ほとんど「自己愛」の表明にしかなっていない、とさえ思えます。事実として、かつての戦争中の、日本軍の中にも、膨大な数の「転向」左翼も含め、冷静な世界情勢の分析ができる知識を有し、健全な「愛国心」と、理性的な判断力を備えた人物が、十分にたくさんいたはずだ、と想像しない方が無理があると思う。ならば、どうして、あ・あ・なってしまったのか?「危機」の最中では、か・な・ら・ず・、より「左」の路線が、勝利を収める、これもまた、少しでも「運動」を目の当りにしたら、経験できるでしょう、この場合「左」って、社会主義とか、そんな意味じゃないよ、単に「過激」、「激しい」、「頑固」、「無茶」ってことだ、戦闘を回避するための「交渉」チャネルを維持しようとする者には、「スパイ」、「裏切り者」、と悪罵を投げつけ、一度決めた「方針」は、もう、それが間違っていることが判ったとしても、突き進むのが、「潔い」と言い募る人々が、勢いをもってしまう、そのような言い草が、「正しく」見えてしまうのも、冷静でなければ冷静でないほど、ますます「正しく」見えてしまうのもまた人間の性のようですから、「平時」から、これも弁えておく必要があるでしょうね。またしても、論旨が乱れているようですので(笑)、このくらいにいたしましょう。 本日、ようやく、ヘミングウェイ「誰がために鐘は鳴る」(新潮文庫)読了、引き続き、サム・ウッド監督の同名の1943年公開の映画も、観ました。159minという途方もない超大作も、同じく長い長い原作同様、「早く終わって欲しい」(笑)、と言う印象しかもてなかった。「メランコリー者」としては当然ですが(笑)、自分の「好み」に合わないものが出現した時に、直ちにそれは、自分の方が異常なんだ(笑)、という解釈の仕方を採用してしまうのは、何事にも「自信」というものをもたずに生きてきたからでしょう、だから、「口を極めて罵る」ことがなかったとしてもそれは必ずしも「寛容」さを意味しません(笑)、そこまで言えば、もう「口を極めて罵っている」のも同然ですが(笑)、もう、原文や、一シーンをあげつらって、いちいちこき下ろすことはしませんが、いくつか、考えたことをメモしておきましょう。 1943年、という時点で、この映画を劇場で観たアメリカ合衆国の観客が、どんな印象をもったんだろう?と言うことが、なかなか想像がつきません。私にとっては、山の中のアジトに籠る人々の中で、ゲイリー・クーパー演ずる、ロバート・ジョーダン、というアメリカ人が、回りから、あまりにも、馬鹿々々しいぐらい「浮・い・て・い・る・」としか思えない。これをあっちへ運べ、違う、もっと上だ、わかったか?忘れるんじゃないぞ、・・・、ロバート・ジョーダンはロバート・ジョーダンで、一体どういう権限で、これら「地元の人たち」に対して、偉・そ・う・に・、指図し、命令で・き・る・、と思っているのか?同時に、この「地元の人たち」が、いくら、権威ある「国際旅団」から派遣されてきたからと言って、そんな、ど・こ・の・馬・の・骨・か・わ・か・ら・な・い・「外・国・人・」の言いなりに、唯々諾々と従っているのか?「アメリカ映画」の観客は、アメリカ人の「白人」が、「原住民」、「黒人」の召使、に対して示す「傍若無人」さに、慣れきっていて、この作品もまた、「反・ファシズム」とかいう新趣向を凝らしてはいるものの、その「伝統」に則った新たな例の一つ、でしかないのでは?といういささか紋切り型の「解釈」しか浮かび上がりませんね。 山中の「ゲリラ」が、ペドロという、小説以上に「悪者」キャラクターに単純化されている一人の例外を除いて、直ちにロバートに対して、好意や信頼を寄せるのは、遠くからやってきた「客人」、言わば「まれびと」に対する「ホスピタリティー」と読めなくもない。また私事になりますが(笑)、私事から類推して想像するしかないから仕方ないですね、沖縄の基地反対運動、などと言う例を取り上げても、「内地」からはるばる、「義」のために「馳せ参じ」た善・意・の人、に対して、必・要・以・上・の称賛を贈ってくださることがあります。内実が伴わないそのような「賞賛」に、当惑するとともに、そのような「幻想」がいずれ破れるに決まっていることに脅え、現に「破れ」てしまったときの、今度は、手のひらを返したかのような冷淡さ、を想像してその「被害妄想」に打ち震える(笑)、と言ったところが、私の「発病」の機序だったかもしれません。 なんのことはない、細部にわたって「ケチをつける」ことに、ちゃんとなってしまっていますが(笑)、小説にはない映画のシーンの一つとして、ロバート・ジョーダンがアジトの中でゲリラの仲間に対して、どうして自分のような「外国人」がスペインにまでやってきて「戦わ」なければならないかを、くどくどと説明する。いわく、ドイツとイタリアのファシストは、スペインを新しい武器の実験場にしようとしている、こんなことを放置したら、や・が・て・イギリスもアメリカも安全でない、云々、失礼を承知で言いますが、辺野古に「支援」に来られた「内地」の皆さんが口をそろえておっしゃる、「これは沖縄の問題ではな・い・、私・た・ち・の問題なんだ」、もちろん、かけらの「悪意」も含まれていないことは十分に存じ上げているつもりですが、それら聞き慣れた台詞との類似性に、微苦笑を禁じ得なかったのも事実です。 際限のない悪口、ちくちくとしたい嫌味(笑)に陥ってしまいそうなので、少し方向を変えましょう。どうして、ロバート・ジョーダンが、そんなに「偉そう」に振舞うことができるのか?を別の観点から見ると、彼は、本当に、そんなに、人を指・揮・で・き・る・ほどの「技術」を身に着けていたのか?という問題に逢着します。フィクションを書くことを生業としている小説家に向かって、「嘘をついている」という難癖はあり得ませんが(笑)、本・物・の・ヘミングウェイは、1937年3月にスペインに到着している、カリコフのモデルとなるミハイル・コルツォフと親交をむすぶ、などと言うことができているのだから、早速、「国際旅団」のソ連軍事顧問団から、それなりの訓練はうけたと想像できるものの、もし、この小説に描かれる時期、1937年5月、のマドリッド北西方面の戦闘を目撃したんだとして、その時点で、人にてきぱきと、あるいは「偉そうに」、指図を与えたりできるほどの、経験を積んでいた、とは、あまり想像できませんね。もっとも、この人は、第一次世界大戦にも従軍しているようですから、軍隊、戦場、そのものの経験は、積んでおり、たとえば、いくつかの銃火器の操作には精通していたかも知れない、とは思えますが。「カタロニア賛歌」(岩波文庫)の中でのジョージ・オーウェルも、実は、なかなかに「偉そう」に見えなくもない振舞をしています。所属するPOUMの「寄せ集め」の部隊の中では、まともに銃を扱えるのが、このイギリス人一人だった、と言うような事情が語られていました。彼は、スペイン戦線に志願する前、パリ、ロンドンを「放浪」するその前は、イギリス帝国の「現地」警察官として、ビルマ、現・ミャンマーに赴任していた、だから、銃の扱いには、「職業上」の熟練が、あった。もとより、なにか「結論」を下したいのではありません、ああでもないこうでもない、とぶつぶつ言ってみることで、ロバート・ジョーダンの、引いてはヘミングウェイその人の、どう見ても拭い去れない「傲慢さ」らしきものが、「Tipical American Arrogance典型的・アメリカ人的・傲慢さ」、「植民地主義者」の身振り、以・外・の・も・の・で・あ・る・証拠が探し当てられれば結構、もちろんできなくても結構、と思っているだけです。 「戦争」という過酷な状況が、人をして「学ぶ」密度、速度を、著しく高めるのかもしれない、と言う例証はいくつもありえます。数年前まで、そういう種類のものを注意深く読んでみることをしていなかったからそれまで気付かなかったのだが、日本の先の戦争の折、「学徒出陣」として前線に送られた学生は、原則として「士官候補生」扱いだったのですね。他人に命令を下すべき階級の高い軍人は、やはり「教養階級」でないといけない、と考えられていたことになります。だから、必然的に、応召して戦地に向かった、学生たちが、後に「作家」となって戦場での出来事を綴るとき、彼らもまた、多かれ少なかれ「偉そう」に見えます。島尾敏夫という作家は、最末期に召集され、わずかな訓練期間の後に、奄美諸島の加計呂麻島に作られた、「特攻」艇の秘密基地に、いきなり「隊長」として赴任し、出撃前夜に「終戦」を迎ることになる。そんな短期間に、船の操縦、爆弾や起爆装置の操作、を習得したのみならず、自分と同年代の若者に対して、はっきりと生き延びる可能性のない戦場への、「出撃」を「命令」できることまで期待されていたのですね。司馬遼太郎は、大阪外国語大学でモンゴル語を学ぶ学生だったが、召集され、朝鮮半島の戦線で、確か、戦車部隊の隊長、だったかちょっと記憶が怪しいですが、そんな責任の重い地位についていますね。文科系の学生が、数か月の、もっと短いかもしれない、訓練で、戦車が操作できるようになるのですよ。 「平和」が人を堕落させるんだ、という、ありがちな見解に与する訳ではありませんが、私たち、中学校から六年間「英語」勉強して、かつ、一言もしゃべれない(笑)、予備校の数学講師として言わせていただけば(笑)、丸々三年間、朝から晩まで、何十題何百題という愚にもつかない変わり映えのしない問題を、「模擬テスト」だか何だかで解かされているにもかかわらず、ついぞ「2次関数の与えられた定義域における最大値最小値」を導く方法を学ぶことなく(笑)、去って行った高校生のなんと多いことか、そんなことを考えると、その落差に愕然とさせられるのも事実ですね。 結論の出ないお話はこのくらいにして、もう一つだけ、映画と原作の、「悪口」を言って終わりにしましょう。映画の中でイングリッド・バーグマン演ずるマリアという名の19歳の少女は、断乎たる共和派として知られたある村の村長の娘だった。ファランジスト、そう、原作ではもっぱら「ファシスト」という言葉が用いられていたのに、映画では、これが判で押したように「ナショナリスト」にすり替わっているのも、なにか1943年という時代におけるハリウッド側の事情があるのかもと、疑いますが、それはさておき、ファランジスト、フランコ派が、その村を占領、真っ先に村長とその妻が、娘の眼前で処刑される。娘はそれから床屋に連れていかれ、床屋の主人の多くは、アナキスト系の組合員だったと言いますから、これも真っ先に処刑されている、バリカンで髪の毛を切られ、ヨードチンキで、その坊主頭に、「U.H.P.」と落書きされる。「プロレタリアートの兄弟団Uníos Hermanos Proletarios」、それに先立つ「アストゥリアスの十月革命」の際に、社会党UGTとアナキストCNTが作った連合組織の名前です。そんな小難しい説明はもちろん映画では省略されていますが。イングリッド・バーグマンは、ぜひこのマリア役の座を取りたいがために、自ら髪を切った、との逸話が伝わっている、映画の末尾にも、配役は原作者ヘミングウェイが手ずから決定した、とのアナウンスがありました。そのあと、ファランジストの兵隊たちは、マリアを市長の執務室に連れていき、小説でも映画でも、それ以上は語られませんが、そこでレ・イ・プ・が行われたことが暗示されます。 小説でも、映画でも、マリアがそこまで話し続けると、ロバート・ジョーダンが、もういい、話さなくていい、聞きたくない、と制止するのです。映画に至っては、手のひらで口を覆ってしまいます。 一「うつ病患者」としての経験と実感からは、この情景には、納得できない、腑に落ちない、という印象を禁じ得ませんね。私見では、「うつ病」も「PTSD・トラウマ(精神的外傷)経験後ストレス症候群」と同じく、「愛の対象の喪失」という「トラウマ」経験を引き金にして発症する、と思っていますし、したがって、PTSDがそうである、と言われるように、トラウマ経験について、どんなにそれが苦痛に満ちたものであったとしても、それを「語る」、言葉にして、文字通り「外に出す」ことによって、「浄化」する以外の治療が、ありえない、これは、自分自身の経験としても、また、他の人の有様を目撃したり、聞かされたりした経験からも、ほぼ「確信」に近いものですから、ロバート・ジョーダンが、何よりもすべきだったのは、マリアに対して、決してパターナリスティックな忠告や慰めなどを交えることなく、ただただ、その発せられる言葉に、ひたすら耳を傾けること、だけだった、と思うのからです。 ペドロの「女房」、ピラール、映画の中では唯一生気のある役柄だったと思えますが、彼女が、それまで娘のように世話をしてきたマリアに、その辛い記憶を、ロバートに話せ、と勧めます。ただ、映画の中では特に、それが、将来「結婚」を考えるにあたって、「貞操」の問題として、「夫」の了解を求めておかなければならない、という文脈で読み取られるように誘導されているのが、不満ではありますが、それを差し引いても、ピラールのこの態度は、「正しい」と、私は思いましたね。はい、長い長い「誰がために・・・」談義はここでおしまい、あと、二三、どうでもいいうんちくのために、いくつかの引用をご紹介する予定ではありますが。 “Call the Lieutenant-Colonel,” Gomez said. “This is a matter of the utmost gravity.” “He is asleep, I tell thee,” the officer said. “What sort of a bandit is that with thee?” he nodded toward Andrés. “He is a 'guerrillero' from the other side of the lines with a dispatch of the utmost importance for the General Golz who commands the attack that is to be made at dawn beyond Navacerrada,” Gomez said excitedly and earnestly. “Rouse the 'Teniente-Coronel' for the love of God.” The officer looked at him with his droopy eyes shaded by the green celluloid. “All of you are crazy,” he said. “I know of no General Golz nor of no attack. Take this sportsman and get back to your battalion.” “Rouse the 'Teniente-Coronel', I say,” Gomez said and Andrés saw his mouth tightening. “Go obscenity yourself,” the officer said to him lazily and turned away. Gomez took his heavy 9 mm. Star pistol out of its holster and shoved it against the officer's shoulder. “Rouse him, you fascist bastard,” he said. “Rouse him or I'll kill you.” “Calm yourself,” the officer said. “All you barbers are emotional.” For Whom the Bell Tolls/Ernest Hemingway(kindle) 「中佐を起こしてくれ」とゴメスは言った。「きわめて重大な要件なんだ」 「寝ていると言ったじゃないか」と将校は言った。「いっしょにきたあの山賊みたいなのは、いったい何ものだい?」と将校はアンドレスのほうを顎でしゃくった。 「夜明けにナバセラーダの向うで行われる手筈の攻撃の命令を出したゴルツ将軍あての重大な急報を持って戦線の向う側から来た遊撃隊員だ」と、ゴメスは興奮して熱心に言った。「頼むから中佐を起こしてくれ」 将校は緑色のセルロイドで光をよけた、ねむそうな目でアンドレスを見た。 「きみたちはみんな気ちがいだ」と将校は言った。「おれはゴルツ将軍なんて知らないし、攻撃のことも知らないぜ。この運動選手を連れて大隊へ帰れよ」 「中佐を起こしてくれと言ってるんだ」とゴメスは言った。ゴメスの口が、ぎゅっと引き締められたのがアンドレスに見えた。 「勝手にしろ」と将校は、ものうそうに言って、そっぽを向いてしまった。 ゴメスは重い九ミリのスタア拳銃を革鞘からとりだして、それを将校の肩に押しつけた。 「中佐を起こすんだ、このファシストの私生児め」とゴメスは言った。「さあ、中佐を起こすんだ、さもなければ撃つぞ」 「まあ、落ちつけ」と将校は言った。「床屋ってやつはみんな感情的で困る」 「誰がために鐘は鳴る」ヘミングウェイ(新潮文庫) アンドレスは、ロバート・ジョーダンのいるゲリラ部隊の一員、味方の攻撃計画が敵に筒抜けになっているらしいことをゴルツ将軍に伝え、攻撃計画も、従って橋の爆破も中止すべきことを提言するロバートの手紙を、司令部に届けようとしているが、途上、あらゆる「味方」の検問所で、あらゆる「官僚主義」、あらゆる「怠惰」、あらゆる「猜疑」のために、妨げられる。オートバイの後部座席に彼を乗せて、一心に走ってくれるこのゴメスという大尉、「感情的」ではあるが、誠実な、共産党員らしき元・床屋、だけが、「希望」を体現している。相手の怠惰な将校も、「'Mundo Obrero労働世界」を退屈そうに読んでいるから、やはり共産党員であることが判る。 “Yes,” the corporal said. “I will tell the first responsible one I see. All know that he is crazy.” “I had always taken him for a great figure,” Gomez said. “For one of the glories of France.” “He may be a glory and all,” the corporal said and put his hand on Andrés's shoulder. “But he is crazy as a bedbug. He has a mania for shooting people.” “Truly shooting them?” “'Como lo oyes',” the corporal said. “That old one kills more than the bubonic plague. 'Mata más que la peste bubonica'. But he doesn't kill fascists like we do. 'Qué va'. Not in joke. 'Mata bichos raros'. He kills rare things. Trotzkyites. Divagationers. Any type of rare beasts.” Andrés did not understand any of this. For Whom the Bell Tolls/Ernest Hemingway(kindle) 「いいとも」と伍長は言った。「頼りになりそうなやつに会ったら、すぐに話してやる。あの男は気ちがいだってことはみんな知ってるからね」 「おれはあの男を、今まで、ひどく偉い人物だと思っていたんだがな」とゴメスは言った。 「フランスの栄光だと思っていたんだ」 「栄光だろうとなんだろうとかまわないけどね」と伍長は言って、アンドレスの肩に手をかけた。 「南京虫みたいに気が狂ってやがるんだ。銃殺狂だね」 「ほんとに殺すのか?」 「ほんとだとも」と伍長は言った。 「あのじいさんは人を殺すことにかけちゃ黒死病よりもひどいんだ。だが、おれたちとちがって、ファシストは殺さないんだ。まず殺さないと言った方がいいだろうね。冗談を言ってるんじゃないぜ。変なやつばかり殺すんだ。トロツキー派、日和見主義者、変なやつは、どんな型の人間でも殺す」 アンドレスには、この話はかいもくわからなかった。 「誰がために鐘は鳴る」ヘミングウェイ(新潮文庫) ある検問所で、かつて共産党の集会で見かけたフランス人らしき大物、マルティ将軍、を見かけたので、ゴメスはすがるような気持ちで声をかけるが、すべて話を聞いたうえで、これは、もともと彼の政敵であるゴルツ将軍がファシストと密通している証拠をつかんだ、と妄想し、彼ら二人を逮捕、処刑しようと考えている。フランス共産党から派遣されているこの軍人が、既に「スターリン主義」の「病」に深くおかされていることが、傍にいる伍長にすら見抜かれているのである。 「変なやつ」と訳されているが、rare things, rare beastsだから、字義通り、トロツキストや日和見主義者なんて、そんなにそこら辺にごろごろいるわけでもないのに、無・理・に・見つけ出しては弾圧する、というニュアンスではないかと思う。 「日和見主義者」は、oppotunistではなくdivagationerという言葉を使っているね、divagateで「さ迷う」という意味らしい、当時スターリン派が頻用したジャーゴンかもしれない。 “Stand there,” Marty said without looking up. “Listen, Comrade Marty,” Gomez broke out, the anis fortifying his anger. “Once tonight we have been impeded by the ignorance of the anarchists. Then by the sloth of a bureaucratic fascist. Now by the oversuspicion of a Communist.” “Close your mouth,” Marty said without looking up. “This is not a meeting.” “Comrade Marty, this is a matter of utmost urgence,” Gomez said. “Of the greatest importance.” For Whom the Bell Tolls/Ernest Hemingway(kindle) 「そこに立っていろ」とマルティは顔も上げすに言った。 「聞いてください、同志マルティ」とゴメスは、茴香酒に怒りをあおられて言いだした。 「わたしどもは今夜、一度は無政府主義者の無知にさまたげられました。つぎには官僚的反政府分子の怠慢にさまたげられ、そしていまは、あなたのコミュニストとしての過度の猜疑にさまたげられているんです」 「だまっていろ」とマルティは顔をあげずに言った。「会議じゃないんだぞ」 「同志マルティ、これは実に急を要する用件なんです」とゴメスは言った。「非常に重要な要件なんです」 「誰がために鐘は鳴る」ヘミングウェイ(新潮文庫) これだけの長い小説を読み終わったんだから、最後は気持ちよく、少しは「誉めて」終わりたいからね、ヘミングウェイがこの挿話をどんな「意図」で置いたのかは想像のしようもないが、私は、このゴメスという軍人に、会えてよかった(笑)、と思う。「革命的状況」が、必ずしも、人を「善良」にしたりなどしないことは、わずかな経験からすら、残念ながら、知っている。「良い人」と「良い人」が手に手をを取り合ったりして進んだりするわけじゃない、そんなんだったらむしろ気持ち悪かろう?「革命的」ならざる「日常」と同じように、それはあらゆる醜悪さのただ中を蛇行するのだが、それでも一瞬だけ、「希望」の如きものが光を放つことがあるから、だから、止められない。一度倒れた旅人たちも、生まれ変わって、歩き出す(中島みゆき)、という訳だね。 茴香(ういきょう)酒と訳されているanisは、セリ科ミツバグサ属アニス(anise, Pimpinella anisum)、西洋茴香と呼ばれる。これに対して茴香のほうは、セリ科ウイキョウ属フェンネル(Fennel, Foeniculum vulgare)、映画の中でロバート・ジョーダンが、いつも小瓶に入れて持ち歩いているその酒は、おそらくものすごくアルコール度数が高い、70度とか80度とか、アブサンabsintheのように見えた。ウイキョウ、アニスのほか、キク科ヨモギ属ニガヨモギなどを原料とするのだという。 ダーウィンの乗ったビーグル号の最初の寄港地は、現・カーボベルデ共和国República de Cabo Verde、プライアPraia、であった。 一八三二年の一月十六日には、ケープ・デ・ヴェルド諸島Cape de Verdの主島、サンタ・ハゴSt. Jagoにあるポート・プラヤに錨を下ろした。 「ビーグル号航海記」チャールズ・ダーウィン(岩波文庫) ST JAGO - CAPE DE VERD ISLANDS Jan. 16th, 1832 - The neighbourhood of Porto Praya,... Voyage of the Beagle/Charles Darwin(Penguin Classics) チャールズ・ダーウィンCharles Darwin(1809-1882)、であるから、この時、彼は23歳、ということになる。 caboは、ポルトガル語でもスペイン語でも「岬」、capeは同じ言葉の英語であろう。そしてverdeもまた、ポルトガル語、スペイン語共に「緑」、とすると、ダーウィンの用いたこの表現Cape de Verdは、なにか、混乱があるように思われる。島の名前、港の名前も同様で、現在の、ポルトガル語による表記なら、主島はSantiago、港町は、Praia、となる。ダーウィンは、もとになった旅行記を編集して、いくつもの論文として発表しているようで、そんな事情だろうか、岩波文庫版と、ペンギン・クラシックスの英語版、対応しない部分があるが、英語版でもCape de Verdという表記になっているのは確かだ。Portoは、ポルトガル語、スペイン語の「港」。 ある日、私は二人の将校とリベイラ・グランデRibeira Grandeまでう・ま・で出かけた。ポート・プラヤから東へ二―三マイルの村である。サン・マルティンSt. Martinの谷に到るまでの風光は、相変わらずの生気のない褐色の眺めであった。 「ビーグル号航海記」チャールズ・ダーウィン(岩波文庫) One day, two of the officers and myself rode to Ribeira Grande, a village a few miles to the eastward of Porto Praya. Until we reached the valley of St. Martin, the country presented its usual dull brown appearance; ... Voyage of the Beagle/Charles Darwin(Penguin Classics) ribeiraはポルトガル語の「川」、スペイン語ならrío、grandeは、ポルトガル語でもスペイン語でも「大きい」、Ribeira Grandeは、このままの綴り字で、地図上で発見できた。しかし、プライアの「西」へ10kmばかりのところ、広い行政区画の名称のようである。カーボベルデの歴史を瞥見すると、15世紀中葉にポルトガル人植民者は、西アフリカから奴隷を移入して、この島でもサトウキビプランテーションの経営を試みたが、サヘル地域に特徴的な雨の少ない気候により失敗、ただ、サンティアゴ島のリベイラ・グランデは、ポルトガル船の中継地たるべき良港であったので、この植民地は存続した、と言われる。ダーウィンの記述によれば、「港が埋もれてしまうまでは、この小さな町がこの島では主要な場所であった。The little town, before its harbour was filled up, was the principal place in the island:...」ということであるから、この港は、ほどなく、使われなくなったようである。「この小さな町」の現在の名称は、シダーデ・ヴェーリャCidade Velha、ポルトガル語で、cidadeは「村」、velhaは「お婆さん」、それは、リベイラ・グランデ地区の東の端に位置し、したがって、プライアから「西」に、目測5km、確かに「二―三マイル」ではある。「弘法も筆の誤り」、ダーウィンも方角を間違えるのである(笑)。St. Martinも、ポルトガル語の綴り字ならば、São Martinhoであろう、「サン・マルティン通りCaminho São Martinho」という街路名ならば、確かにプライアと、シダーデ・ヴェーリャの中間に見つけることができた。 他の日には、島の中央に近いサン・ドミンゴSt. Domingoの村にう・ま・を走らせた。・・・この辺の旅行では、不毛の土の上には足跡がほとんど残らないので、われわれは路をまちがえてフェンテスの方へ行ってしまい・・・ 「ビーグル号航海記」チャールズ・ダーウィン(岩波文庫) Another day we rode to the village of St. Domingo, situated near the centre of the island.... The travelling had made so little impression on the barren soil, that we here missed our track, and took that to Fuentes. Voyage of the Beagle/Charles Darwin(Penguin Classics) domingoは、ポルトガル語でもスペイン語の「日曜日」、São Domingosを、確かに、島の中央部に発見。fuenteはスペイン語の「泉」、ポルトガル語ならfonteであろうから、と捜したところ、そのSão Domingosの南方1kmに、Fontes de Ribaを見つけた。ribaは「岸」である。 Cape Verde(wikipedia) History of Cape Verde(wikipedia)   Praia(googlemap) Ribeira Grande de Santiago(googlemap) Cidade Vehla(googlemap) Caminho São Martinho(googlemap) São Domingos(googlemap) Fontes de Riba(googlemap)  ある朝、景色は不思議なほど透明であった。遠方の山々は、濃青色の雲の密集した堆積の上に、極めて鋭い輪郭をして浮き上がっていた。その有様をイギリスで見た同様の状態から判断して、空気中に湿気が飽和していると思った。ところが事実は全く反対であることがわかった。湿度計は空気の温度と露点との間に、二九・六度の差を示していた。この差は、その前の朝ごとに観測したところとは、ほとんど二倍ほどのものである。 「ビーグル号航海記」チャールズ・ダーウィン(岩波文庫) One morning the view was singularly clear, the distant mountains being projected with sharpest outline, on a heavy bank of dark blue clouds. Judging from the appearance, and from similar cases in England, I suppose that the air was saturated with moisture. The fact, however, turned out quite the contrary. The hydrometer gave a differende of 29.6 degrees, between the temperature of the air, and the point at which dew was precipitated. This difference was nearly double that which I had observed on the previous mornings. Voyage of the Beagle/Charles Darwin(Penguin Classics) 空気が、その中に気体としての水蒸気を含みこむことのできる量の限界は温度とともに右上がりになる曲線を描く、これを水蒸気の「分圧」で表したのが、飽和蒸気圧曲線。湿らせた布で覆われた温度計が示す「湿球温度」は、その近傍が水蒸気で「飽和」していることになるから、「露点the point which dew was precipitated」を表すことになる。これと「乾球温度」、これは通常の「気温the temperature of the air」、の差が大きいほど、その空気がまだまだ水蒸気を含みうる余裕を持っている、つまり「湿度」が低い、ことを意味することになる。 乾湿球示度による水蒸気分圧の計算には、次の式が用いられる、とのこと。 e=eSW-Ap(td-tw) e:水蒸気分圧 eSW:湿球温度における飽和水蒸気圧 A:乾湿球係数、0.000662K-1 p:気圧 td:乾球温度 tw:湿球温度 ダーウィン氏は、乾湿球の示度の「差」が29.6°であることを教えてくれているのに、乾球温度自体は書かれていないではないか。気象庁によると(笑)、ギニアビサウでの、1月の平均気温が、26.8℃、だそうなので、この沖合にあるカボベルデも同じとすると、湿球温度は、おや、困ったことに(笑)氷点下になってしまうから、却下、仕方ない、乾球温度自体が、29.6℃、湿球温度は、それから29.6を減じて、0℃、だったとしようか?湿球温度0℃における飽和水蒸気圧は、0.6113kPa、ヘクトパスカル単位にすると、6.113hPa、現在の気圧を常圧、1013hPaとすれば、 e=6.113-0.000662×1013×29.6 この値が算出されたなら、その値の、当該気温における飽和蒸気圧に対する割合を百分率で表示して、「湿度」が計算できる段取りなのだが、あらあら(笑)、また失敗、負の値になってしまうよ。いずれにしても、乾湿球の示度の差29.6というのが、異・様・に・大・き・い・、「湿度」はほぼゼロパーセント、ということだけは(笑)、分かった、ということで満足するしかないね。 いよいよ、大西洋を渡る。カーボベルデ、プライアPraia/Cabo Verde、をいつ出航したのかはわからない。まず、「セント・ポールの岩礁St. Paul's Rock」近傍を、2月16日朝、通過とある。Saint Peter and Paul Rocks/Arquipélago de São Pedro e São Paulo、英語およびポルトガル語表記は、こうなるようである。 セント・ポールの岩礁上には、鳥は間抜けboobyと頓馬noddyとの二種のみがいる。前者はカツオドリgannetの一種で、後者はアジサシternの一種である。 「ビーグル号航海記」チャールズ・ダーウィン(岩波文庫) We only observed two kinds of birds - the booby and the noddy, The former is a species of gannet, and the latter a tern. Voyage of the Beagle/Charles Darwin(Penguin Classics) 「間抜けbooby」は、カツオドリ科カツオドリ属カツオドリSula leucogaster、英名Brown booby、写真を見る限り、顔つきはカワウ(ウ科)に似ていて、背面黒褐色、腹側白色、オレンジ色の水かきの付いた脚。 「頓馬noddy」の方は、カモメ科クロアジサシ属クロアジサシAnous stolidus、英名Brown Noddy、または、カモメ科クロアジサシ属ヒメクロアジサシAnous minutus、英名Black Noddy。   参考画像(笑)、カワウ(ウ科)。  オニアジサシ(カモメ科)、カモメ科オニアジサシ属、英名Caspian Tern、  コアジサシ(カモメ科)、カモメ科アジサシ属、英名Little Tern、  クロハラアジサシ(カモメ科)、カモメ科Chlidonias属、英名Whiskered Tern、「whisker」は「ほおひげ」。 2月20日、フェルナンド・ノローニャに、二三時間滞在、とのこと。Ilha Fernando de Noronha/Pernambuco/Brasil、行政上はブラジル・ペルナンブコ州に所属するようである。ilhaは、ポルトガル語の「島」で、たとえば、台湾は、別名Ilha Formosaと呼ばれるのだが、formosoが「美しい」、語尾が名詞に合わせて女性化しているが、「美麗島」なのである。与那原恵の台湾紀行が、「美麗島まで」(ちくま文庫)となっているのは、そういう訳なのだ。大航海時代のポルトガル人は、大洋のど真ん中に、緑滴る「美しい」島を「発見」するた・び・に、ilha formosa!と叫んだのであろう。スペイン語ならisla、確か、マドンナの歌に、La Isla Bonita/Madonnaというのがあっただろう?プロモーション・ヴィデオに歌詞の字幕を付けてくれているものもあるので見てみると、スパニッシュ・ララバイとか、トロビカル・ブリーズとか、存分に「コロニアル」な用語が散りばめられていて、イメージ画像もカリブ海を思わせる。私はサン・ペドロと恋に落ちた、とあるので、San Pedroという名の島を探してみたが、ちょっと見つからない(笑)。で、bonitoが「良い」なのだ。だから、きっとIsla Bonitaという地名も、たくさん、あったに違いない。 そして、2月29日、南アメリカ大陸、ブラジル バイーア州、サルヴァドールに到着。 バイアBahia一名サン・サルヴァドルSan Salvadorブラジル、二月二十九日。―この日はたのしく過ごした。しかし生まれてはじめて、ひとりでブラジルの森林を逍遥した博物学者の感じをあらわすのに、たのしくという言葉は弱すぎる。草のしなやかなこと、寄生植物の珍奇なこと、あらゆる花の美しさ、葉のつややかな緑、またとりわけて、植物が一般に豊饒なことは驚嘆で一ぱいになってしまった。 「ビーグル号航海記」チャールズ・ダーウィン(岩波文庫) BAHIA, OR SAN SALVADOR, BRAZIL, FEB. 29TH - The day has passed delightfully. Delight itself, however, is a weak term to express the feeling of a naturalist who, for the first time, has been wandering by himself in a Brazilian forest. Among the multitude of striking objects, the general luxuriance of the vegitation bears away the victory. The elegance of the grasses, the novelty of the parasitical plants, the beauty of the flowers, the glossy green of the foliage, all tend to this end. Voyage of the Beagle/Charles Darwin(Penguin Classics) この街は、確か、カエタノ・ベローソが、学生時代を過ごしたところだった筈だ。この航海記の記述にはしばしばみられる、航海中に着けていた日記を、後になって検証しながら、編集しているからだろう、ある動植物なり、地質なりの話題に沿って、旅程とは外れた地名がしばしば登場する。ここでも、おそらく、そういう文脈で、イギリス領セント・ヘレナのアスセンション島(アセンション島)Ilha de Ascensão、ブラジル、サルバドールトリオ・デ・ジャネイロの中間あたりの海岸沿い、アブローロス島Abrolhos Archipelago、が登場する。カーボベルデから、サルバドールに向かうのに、前者は遠回りすぎるし、後者は、行き過ぎているからそう思うのだが、では、アセンションには、いつ、行ったのだろう?という疑問は残る。 「風任せ」なのだからそういうものなのだろう、帆船ビーグル号の「巡航速度」などと言うデータは得られなかった(笑)。そういえば、ハイチ革命に取材した、「この世の王国」アレッホ・カルペンティエール(サンリオ文庫)には、ナポレオンの妹、ポーリーン・ボナパルトが登場する。革命鎮圧軍の司令官の妻として、やってきたものらしい。そのいきさつをwikipediaで調べたところ、1801年12月、ブレストBrestを出航して、45日間の航海の後、カプ市Cap、現・カパイシアンCap-Haïtienに到着、とある。この二つの例で、比較してみようか。 Saint Peter and Paul RocksからIlha Fernando de Noronhaまで4日間で630.42km、日平均速度157.61km/day Ilha Fernando de NoronhaからSalvadorまで9日間で1211.26km、日平均速度134.58km/day Brest(48.39N,4.49W)からCap-Haïtien(19.74N,72.21W)まで45日間で6733.85km、日平均速度149.64km/day おお、なかなか、もっともらしい値になっているではないか。一日、約150km、と思っておけばよいのだな。    Saint Peter and Paul Rocks/Arquipélago de São Pedro e São Paulo(googlemap) Ilha Fernando de Noronha/Pernambuco/Brasil(googlemap) Ilha de Ascensão/Ascension Island/Santa Helena(googlemap) Salvador/Brasil(googlemap) Abrolhos Archipelago/Arquipélago de Abrolhos(googlemap) 言葉が群集の中へ滲み込む。ベルニスはすでに言葉を聴かない、ただ何ものか言葉の中にあってレート・モチフのように繰返される或るものを聴くのみである。 「南方郵便機」サン=テグジュペリ(新潮文庫「夜間飛行」所収) 堀口大學氏の訳文は、あまりに格調高く、何のことやらわからない場合も発生する(笑)。 ライト・モチーフ、音楽用語のようで、「オペラ・標題音楽などで、特定の人物・理念・状況などを表現するために繰り返し現れる楽節・動機」、ドイツ語Leitmotiv、素人が発音記号を見る限り、「ライト・モチーフ」で差し支えない気もするが(笑)。 何やら難解な「恋愛」めいた場面に少し辟易してしまって(笑)頓挫していた「南方郵便機」、本日読了。ちょうど、ダーウィンを乗せたビーグル号が、カーボベルデから、まっすぐにブラジル、バイーヤ州、サルバドルにまっすぐ向かうのと同様に、ほぼ一世紀後の、この郵便機は、現・セネガルのダカールから、ブラジル、リオ・グランデ・ド・ノルテ州Rio Grande do Norte、ナタルNatal、へ向かうのである。そこらが、大西洋を渡る、最短経路なのだろう。物語では、ベルニスの操縦する、トゥールーズ発ダカール行きの郵便機は、カップ・ジュピーをを発ち、ポール・エティエンヌを経て、サン・ルイSaint-Louisに向けて飛び立った後、消息を絶った。不時着した残骸が発見され、着陸後、「匪賊」の襲撃を受けたことが明らかになった。 飛行中の郵便機、と言っただけでは極めてあたりまえのことでしかない。ただそれがアガディールとカップ・ジュビーの間の、不帰順部族の上にいる場合、それはどこかにいる筈で、そしてどこにもいない一人の操縦士だということになる。 ・・・ 僕は君が故障したのかと思って捜索に出かけるところだった。見たまえ、捜索機の用意がもうできていた。アイット・トゥーサ部族が、イザルウィン部族を攻撃した。僕は君があの騒動の中へ不時着したのかと思って心配していた。・・・ ポール・エティエンヌより、カップ・ジュビーに告ぐ。郵便機、午後四時三十分着。 ポール・エティエンヌより、サン・ルイに告ぐ。郵便機、午後四時四十五分、貴地に向け出発せり。 サン・ルイより、ダカールに次ぐ。郵便機午後四時四十五分、当地に向け、ポール・エティエンヌを出発せり、当地着の上は夜間貴地に向け続航せしむる予定なり。 ・・・ 夜明け。モール人らの嗄れ声の叫び、駱駝が疲れきって、死んだように地上に寝そべっている。小銃三百挺を有する 「南方郵便機」サン=テグジュペリ(新潮文庫「夜間飛行」所収) アガディールとカップ・ジュビーの間、なら、それは、現・モロッコ、カップ・ジュビーとポール・エティエンヌの間なら、現・西サハラ、ポール・エティエンヌから、サン・ルイの間だというのなら、現・モーリタニア、ということになる。サン=テグジュペリが、郵便飛行機会社のパイロット、ないしカップ・ジュビーの飛行場長であったのは、1926年から1929年、この時期、もう少し北の、タンジェ周辺を中心と思われるが、「リフ戦争」が、1920年のフェズ条約以降、スペイン占領者に対して、1925年以降はこれに介入したフランス軍に対しても、戦われたが、1926年までには鎮圧された。こうして、ヨーロッパ人の眼前に、見え隠れする、「不帰順部族」、「モール人」、「匪賊」と言った言葉で指示される人々が、一体誰なのか?、それは、まさに、そのような「不帰順部族」との間で、不時着郵便機の操縦士の、身柄解放交渉にあたることを仕事としていた、サン=テグジュペリその人の、エッセイ、「人間の土地」(新潮文庫)、次に読む予定であるから、で、もう少し、実像が浮かび上がってくるだろうことを期待して、今のところは差し当たり、備忘にとどめる。 モーリタニアは、この時期、フランス領西アフリカ、の一部であり、保護国protectorate、ないしは植民地colonyであった。セネガルもまたフランス領西アフリカを構成していたように思えるが、はっきりしたことがちょっとわからない。ここに出てきたサン・ルイ、ダカール北方、モーリタニア国境に近い町、は、この地域のかつての「首都」であったようである。 引用部分にあるカタカナで書かれた二つの部族名は、それらしき発音と思われるものを探索してみたが、見つけるには至っていない。 「匪賊」に「レツウ」なるルビが振ってある、フランス文学者たる堀口大學氏の仕業であるし、これはフランス語であろうと見当をつけ、やはりそれらしき発音のものを探してみたが、辛うじて似ていなくもないものとして、「rustre」が浮上、どうであろう?、「芋」の意だが、「夷人」に対する呼称としても用いられるようである。 ちなみに「モール人」は、英語なら「ムーアMoors」、フランス語「Maures」を堀口大學氏が、このように音訳したのである。  西サハラのダハラDakhlaの、スペイン植民地時代の名称が「シズネロスCisneros」、その南、西サハラ・モーリタニア国境のすぐ南側、ヌアジブNouadhibouが、フランス植民地時代には、ポール・エティエンヌPaul Etienne、と呼ばれていた。更に南、セネガルとの国境のすぐ南側に、サン・ルイSaint-Louis、英語読みしたら「セントルイス」になるが、は、植民地時代の名称をそのまま残しているようである。ダカールの西方数百キロの海上に、Cap Vertと見えるのが、ダーウィンを乗せたビーグル号の寄港地、カーボベルデCabo Verdeであるが、ここでは、地図をフランス語モードにしてあるので、こうなる。岬、cape(英)、cabo(西)、cabo(葡)、cap(仏)、緑、green(英)、verde(西)、verde(葡)、vert(仏)、という訳だ。しかし、ポルトガルの宛て字、「葡萄牙」、手書きで書けと言われても、出来ないな(笑)。「葡/ホ・ブ」、「萄/ドウ・トウ」、どちらも「葡萄(ブドウ)」にしか用いられない漢字のようである。どちらも「艸」とのそれぞれ「匍/ホ・は(う)」、「匋/トウ」との形声文字で、「匋」は「土器をつくる」の意で、「陶」の原字、とのこと、ならば「葡萄」の「牙」、「ぶどうが」と発音して、それが、ポルトガル人が自分の国のことをPortugalと呼ぶのと、「似ている」と、種子島に宣教師が漂着した時代の日本人が、思った、ということなのだな。 Saint-Louis/Sénégal(googlemap) いくつもの小説を「一章ずつ、替わりばんこに読む」(笑)効用は、ここにもあって、サン=テグジュペリの操縦するトゥールーズ・ダカール間の郵便飛行機の中継地の一つ、スペインの地中海岸、バレンシアの少し南、アリカンテAlicanteが、「誰がために鐘は鳴る」にも、「共和派」のために送られた、ソ連製の軍用機の部品が、荷揚げされる港として、言及されていた。オデッサから、黒海を横切って、コンスタンチノープル、ボスポラス海峡Bosporusを通過してマルマラ海Sea of Marmara、ダーダルネス海峡Dardanellesを経て、エーゲ海Aegean Sea、ペロポネソス半島Peloponneseとクレタ島Creteの間をかすめて、地中海に入り、チュニスTunisとマルタ島Martaの間を抜け、サルジニア島Sardiniaの南側から、イベリア半島へ向かったのであろう。前半は、トロツキーが、1929年に追放されたとき、後半は、同じくトロツキーが、1933年であったか、マルセイユに向かうときに、使った航路の一部であろう、それらと、サン=テグジュペリがその上空を飛んだのと、また、スペイン内戦の支援にソ連の軍艦が向かうのとが、ほぼ十年以内の時間差で、「重なって」いることを知るのである。   すると、ここにもう一人「重ね書き」してみたい人物が浮かび上がる。クロード・レヴィ=ストロース(1908-2009)、ダーウィンのビーグル号航海から、ほぼ一世紀後、1935年であったか、サン・パウロ大学の社会学の教授職を得て、彼が初めてブラジルに向けてマルセイユを発つときに乗った船が、奇しくも、後に1941年、親ナチ・ヴィッシー政権のユダヤ人迫害を逃れて、アメリカ合衆国を目指したとき、小アンティーユ諸島マルチニックまで運んでくれたのと同じであり、そこには同乗者として、アンドレ・ブルトンとヴィクトル・セルジュの姿があった、という話は以前にもした。ダーウィンが、乾湿球寒暖計を持ち出して、異常な乾燥について述べていただろう?おそらくその反対の現象になるのではないかと思うのだが、湿った空気が気流に乗って、上昇し、まわりの気圧が下がるので露点に達し、水滴となって落ちてくる、それが「雨」の発生機序だが、こ・こ・では、上空に達する以前にすでに飽和して水滴ができる、その中空からいきなり降り始める雨を、「タピオカ入りのコンソメスープのような」と、まことに「詩的」に表現して見せた部分が記憶に残っていたのだが、私が最初に読んだのが講談社学術文庫の「悲しき南回帰線」、今手元にあるのが、中央公論社「世界の名著・マリノフスキー/レヴィ=ストロース」所収の「悲しき熱帯」、翻訳者が異なるせいもあって、見つけられない。ちなみにTristes Tropiquesを、「悲しき南回帰線」などと訳すのは、この「本邦初訳」版訳者の要らぬおせっかいではないか?と思っていたが、彼が南アメリカ大陸に最初に上陸するのが、サン・パウロ、南緯23.55°、まさに、「南回帰線」直上であり、もとより、ダーウィンと同じく、彼を乗せた船も、カーボベルデから、まっすぐ、バイーヤ方面へと大西洋を横切ったに違いなく、そこから、ブラジルの海岸伝いをずっと南下し、まさに「熱帯」から「南回帰線」への風光の変化を、詳しく記述している章が、「南回帰線を越えて」と題されていることを知れば、なかなか含蓄深い、とも思えてきた。 私たちの船は、いつも数多くの寄港をした。実際、旅の初めの一週間は、船荷が積みこまれたりおろされたりしているあいだ、ほとんど陸の上で過ごした。そして、夜、航行した。目をさますたびに、私たちは別の港の埠頭にいた―バルセロナ、タラゴナ、バレンシア、アリカンテ、マラガ、ある時にはカディス。あるいはさらに、アルジェ、オラン、ジブラルタル、そして最も長い行程をへたのちにカサブランカ、そしてやっとダカールに到着する。それからやっと大航海がはじまるのだ。あるときはまっすぐリオやサントスへ、もっとまれだが、あるときは航海の終わりに進行がゆるめられ、ブラジルの海岸にそって、レシーフェ、バイア、ヴィクトリアなどに寄港しながら、ふたたび沿岸航海がはじまる。 「悲しき熱帯」クロード・レヴィ=ストロース(中央公論社「世界の名著・マリノフスキー/レヴィ=ストロース」所収)   マラガMálagaはジブラルタルGibraltar東北東100km、カディスCádizはジブラルタルGibraltar北西50km、オランOranは、アルジェリアの地中海岸、アルジェAlgiersよりはずっと西のモロッコ国境寄り。  ダカールで、私たちは旧世界に別れを告げ、カボ・ヴェルデ諸島を知らぬまに通り過ぎて、運命を予告するような、あの北緯七度に到着していた。ここで、コロンブスは、一四九八年の彼の三度目の航海のとき、そのまま進めばブラジルを発見したはずの方角に出発していながら、北西に進路を変え、二週間後、奇跡のように、トリニダーと、ベネズエラ海岸に達したのである。 「悲しき熱帯」クロード・レヴィ=ストロース(中央公論社「世界の名著・マリノフスキー/レヴィ=ストロース」所収) 「トリニダー」は、小アンティーユ諸島最南端、ベネズエラの海岸に最も近い、トリニダード・アンド・トバーゴTrinidad y Tobagoを、フランス語風に読んだものだろう。確かに、下図に見るように、「北緯七度」で、それまで南東に向かっていた進路を北西、いや、西北西、くらいかな、に変えれば、そこへ到着することになるだろう。   「北回帰線」はNorthern Tropicまたは、Tropic of Cancer、「かに座」に関係あるんだろうな、「南回帰線」はSourhern Tropicまたは、Tropic of Capricorn、こちらは「やぎ座」、なるほど、それなら、フランス語の「南回帰線」、tropique du Capricorneだから、Tristes Tropiquesを、「悲しき南回帰線」と訳するのも、ますます(笑)、無理がない、と言えるのだな。 2点(x1,y1),(x2,y2)を通る直線 (x-x1)/(x2-x1)=(y-y1)/(y2-y1) が、直線y=nと交わる交点のx座標は、 (x-x1)/(x2-x1)=(n-y1)/(y2-y1) をxについて解けばよいから、 x=x1+(n-y1)(x2-x1)/(y2-y1) プライアPraiaを(x1,y1)=(-23.51,14.93)、レシフェRecifeを(x2,y2)=(-34.93,-8.05.)、北緯7度をy=7.00、として計算すると、プライア-レシフェを結ぶ線と北緯7度の交点として、(-27.45,7.00)を得た。図で見ても、妥当な値だろう?コロンブスが、プライアを出発した後、海洋中のこの地点で、ほぼ直角に航路を変え、トリニダード・アンド・トバーゴに達したとして、距離を計算してみた訳である(笑)。  なるほど、コロンブスは、そのまま進路を変えずに進んでいたら、南米大陸、ブラジルのリオデジャネイロに到達していたであろう、ほぼ同等の距離に、トリニダード・アンド・トバーゴという「島」を、「発見」したことがわかった。 昨日から、すでに新世界はそこに存在している。しかし、それが見えるわけではなかった。船の進路の変化にもかかわらず、海岸はまだあまりに遠いからである。船は、しだいに南に向かって斜行し、サン・アゴスティノ岬からリオまで、海岸線に平行につづく軸にそって進んでいく。すくなくとも二日、おそらく三日のあいだ、私たちはアメリカと連れだって、航行することになろう。そして、私たちに旅の終末を告げるのは、大きな海鳥ではない。それは、飛んでいるカツオドリに襲いかかってその獲物を吐きださせる、そうぞうしい熱帯の鳥、専制者ぶったウミツバメだ。 「悲しき熱帯」クロード・レヴィ=ストロース(中央公論社「世界の名著・マリノフスキー/レヴィ=ストロース」所収) ウミツバメは、ツバメ科ツバメとは、かけ離れた種で、アホウドリ科、ミズナギドリ科、モグリウミツバメ科とともに、ミズナギドリ目を構成する、ウミツバメ科の鳥である、とのこと。当地に住む、または飛来する鳥を掲載した図鑑、「沖縄の野鳥」(新報出版)には、カツオドリ科カツオドリは載っているが、ミズナギドリ目では、ミズナギドリ科のオオミズナギドリのみが見える。オオミズナギドリも、もっと南の八重山諸島の無人島でのみ目撃されるらしいから、近い種類のものさえ、こんな「引きこもり」には(笑)見ることができす、姿を思い浮かべることもできないのが残念である。 サン・アゴスティノ岬は、Cabo de Santo Agostinhoと思われ、これは、レシフェのすぐ南側にある。レシフェから、リオデジャネイロまで、1475.64+414.56=1890.20、これを、「すくなくとも二日、おそらく三日」で進むなら、一日あたり、600kmから900km、前に試算した、トロツキーのプリンキポ―マルセイユの旅が、一日500km、私の(笑)大阪南港―那覇が、一日480km、「帆船」ビーグル号の一日あたりの旅程150kmの、3倍から6倍、まあ、そんなものであろうか(笑)? The prospect of living in Salvador was not unpleasant: the city I now love beyond all others in the world was already familiar to me as to any native of Santo Amaro; moving there posed no particular impedement. Salvador, which we called "Bahia," was in fact so close to Santo Amaro that my father was afraid the new highway being planned would turn our town int "just another suberb." ... It was unusual then for anyone from the backlands of Bahia to call Salvador by any name other than "Bahia," although today everyone uses "Salvador," as people from Rio do. Tropical Truth; A Story of Music & Revolution in Brazil/Caetano Veloso(Da Capo Press) サルバドルに住むという考えは、ちっとも不快ではなかった。その町のことは、今では世界中のどの町よりも愛しているけれども、その頃でもすでに、サント・アマロ生まれのものならば誰でも感じただろうように、私にとっても親しみのある街だった。だから、そこに引っ越すことには、何の問題もなかった。じつのところ、サルバドルは、私たちはその町のことを「バイーヤ」と呼んでいたけれども、サント・アマロと、あまりにも近いので、私の父などは、新しいハイウェイができてしまったら、私たちの故郷が、「ありふれた近郊都市」になってしまうのでは、と恐れていたくらいだ。 ・・・ バイーヤの奥地からやってきた者が、サルバドルのことを「バイーヤ」以外の名前で呼ぶことの方が、当時は珍しかった。今では、リオの人がするみたいに、みんなサルバドル、呼ぶけれども。 「熱帯の真実、ブラジルにおける音楽と革命に関する一つのお話」カエタノ・ベローソ  1942年生まれの、カエタノ・ベローソという、極めて知的な、ブラジルの音楽家のことについて、大して知っているわけではなかった。「ポストモダン/ニューアカデミズム」時代のもっと年若い秀才の友人、音楽にも造詣の深い人だったが、の真似をして、カッコつけて、「知ってるふり」をしているだけだったが(笑)、「知ったかぶり」も、持続していると「板に着いて」(笑)くるもの。「ロンドン・ロンドン」という歌に、観光客とおぼしきグループが、おまわりさんに道を尋ねている、おまわりさんも親切に応えている、ただそれだけの光景に、 It's good at least to live, I agree. 生きている、と言うのは、少・な・く・と・も・、よいこと、それは、認める、 などと言っている。彼は60年代末、ヒッピーの様に髪の長い「過激派」学生で、当時のブラジルは軍政下にあったから、それだけでも命がけだった筈だ。程度は異なるけど、想像はできる、「警察官」の姿には、いつもびくびくしていた。だから、「亡命」先のロンドンの、そんな和やかな光景が、眩しかったんだろう、と想像した。結構値の張ったこの本は、サンバやボサノバの知らない音楽家の名前が山ほど出てくるばかりなので、投げ出してあったが、なんとか、その、ロンドンへの「亡命」の事情辺りまでは、読み進みたいのである。 ダーウィンが、南アメリカ大陸に最初に足跡を残した土地が、バイーヤ、サルバドルであったことにちなんで、引用してみた。 London, London(Black Cab Session-Live London)/Caetano e Gilberto Gil  旧暦五月十日の月  ヤブガラシ(ブドウ科)、果実。  シロガシラ(ヒヨドリ科)  ヒヨドリ(ヒヨドリ科)  そろそろ、もう季節も終わりなのかもしれない、心なしか、「咲き」くたびれた、感、テッポウユリ(ユリ科)  香櫨峰の雪は簾をかかげて見る、だったっけ、「枕草子」?じゃあ、絶叫メジロ(メジロ科)は、トイレの窓をそおっと開けて、見る、でどうだ? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2020.01.04 19:39:47
|