
|
|
|
カテゴリ:読んだ本
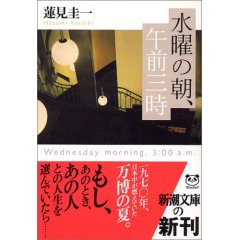 作者:蓮見圭一 なんとも不思議な小説でした。 主人公の男性が妻の母を語るんです。まぁそれは最初と最後で、中の長い部分は、その母が娘に書き残した自分の半生を語る手紙なのですが。 母は大阪万博のコンパニオンをした、当時としてはどちらかというと流行の先端を行っている(?)女性だったようです。いや、コンパニオンをした人が全員そうだった、というわけではありません。そこで恋愛があったりあれやこれや。家庭は(特に父親は)厳しい人だったけれど、あの時代に自分に正直に奔放に生きたいと思うんですね。私自身はその時代の感覚からあまりはずれない方なので、そういう世間とは関係なく自分のやりたいことをやっていきたいと思う人は、ある意味すばらしいと思うし、ある意味では生きにくいだろうと思います。 のちに彼女は親になっても当時の子ども(主人公男性の子ども時代の「ともだちのお母さん」としての印象)から見ても、“ふつうのお母さん”とはすごく違ったみたいで。 私としては、その男性の妻の目から見た「母」というものがどのような人であったのか、その印象も知りたかったかな。その「母」には感情移入できず、時代を超えたヘンな傍観者の感覚で読んでました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012年04月03日 13時23分04秒
コメント(0) | コメントを書く
[読んだ本] カテゴリの最新記事
|