
|
|
|
カテゴリ:読書案内「日本語・教育」
高田瑞穂「新釈現代文」(ちくま学芸文庫)
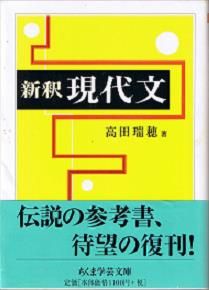 ぼく自身が受験生だった頃、繰返し読んだ現代文の参考書がありました。その参考書がなんと筑摩書房から文庫として復刊されています。高田瑞穂「新釈現代文」(ちくま学芸文庫)です。 ぼく自身が受験生だった頃、繰返し読んだ現代文の参考書がありました。その参考書がなんと筑摩書房から文庫として復刊されています。高田瑞穂「新釈現代文」(ちくま学芸文庫)です。 人間の理解や知識は、関心と経験を経ることなしには決して育ちません。人間の文化を、その根底において支えているものは、いつの場合でも生活の必要ということなのです。懐かしい文章です。学校の先生の授業には飽き足らない毎日だった少年が、心に刻み込んだ記憶があります。 現代文の入試問題が解けなくて困っている人にはこの参考書は難しすぎるかもしれません。知的な守備範囲を拡げようとしない人には、そもそもこの参考書自体が読みきれないと思うのです。 むしろ、現代文は得意だが、問題集の図式解説のばかばかしさに飽き足りない人や、国語の先生になろうと考えているような人にお薦めです。 今さら、受験参考書を、という気持ちはよくわかりますが、これを読むと読書しなければならないという気持ちになる不思議な参考書でした。書店の棚でちょっと覗いてみてください。(初出2011・07・14)(S) 追記 2019・05・18 高校の国語に「論理国語」なる科目が始まるらしい。哲学研究者の内田樹さんが「内田樹の研究室」というブログでこんなふうに書いておられました。 契約書や例規集を読める程度の実践的な国語力を「論理国語」という枠で育成するらしい。でも、模試問題を見る限り、これはある種の国語力を育てるというより、端的に文学を排除するのが主目的で作問されたものだと思いました。 文章を読むとか、書くという行為が、すぐれて「論理的」な行為であることを、諄々と解説し、受験問題を解いてゆく「新釈現代文」という受験参考書は、今こそ読まれるべきだと思います。 しかし、現場の若い教員や、教員を目指す学生さんたちの中に、世の風潮通り「すぐに使えるマニュアル的方法論」を手に入れることに汲々としている傾向があることは否定できません。 「そんな面倒くさいことはやっていられません、さっと、わかるように言ってください。」 そうおっしゃて、こんな本には見向きもされないことでしょう。そういう非論理的感受性には、「文学国語」を読むことも不可能だと思いますが、老人の繰り言でしょうか。 追記2020・09・09 コロナ後の世界が始まりつつあります。蔓延する伝染病を克服する方法は、どうも、なんの根拠もなしに「こんなものはこわくないのだ。」という妄想にも似た「安心感」を蔓延させることのようです。 スター気取りでテレビに出て来て、やりもしていない対策を、やっているかのように語っていた、インチキ政治家たちは、次々と鳴りを潜め、「自助」とか「自衛」とか、公共の責任を果たす態度のかけらもない言葉を政治スローガンとして流行させ国民を煙にまき始めています。 決定的に失われているのは論理ですね。ムードや空気に酔わせることでインチキを煽ることで正当化するのが全体主義者、ファシストたちの常道でしたが、ムードに酔わないための薬は、地道に「論理」を追う「思考力」以外にはありません。 しかし、何よりも「考える」ためには「他者」、「他者」とともにある「社会」、人と出会う「場」を失ってはならないと思うのですが、自らのことばで語ることができない政治家の姿は「まさに」「他者」を失った現代のシンボルだと思います。しかし、彼が失っているのは「振り返って考える力」、すなわち「反省」ということだということを忘れてはいけないと思います。 一人、一人が考え始めることがポストコロナの社会を変える力を芽生えさせるのではないでしょうか。 追記2022・02・09 2年前に「コロナ後の世界」を空想しました。そうはいっても、そろそろ収まるのではないかと考えていたようです。が、コロナの感染の拡大は今年の冬も収まることを知らない様子です。ネット上には恐るべき数値が跋扈していますが、「無検査」とか「みなし」という、いよいよ責任放棄を露わにした言葉も飛び交っています。 60年以上生きのびてきましたが、それでもまだ「初体験」ということに出くわすものだという詠嘆というか、感慨というか、不思議な気持ちにとらわれています。 リスク・ケアを流行り言葉にしてマニュアル社会化した現代社会が、実際のダメージに如何に脆弱であるか。ディストピアというSF小説で語られていたはずの世界が案外身近に現出することに驚いています。  ボタン押してね! ボタン押してね!  
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.01.06 23:36:00
コメント(0) | コメントを書く
[読書案内「日本語・教育」] カテゴリの最新記事
|