
|
|
Episode1 Part1――――・・・ダ・・・・・・・ナイ ―――イ・・ダ・・・ク・・・ナイ ――イヤダ、シニタクナイ 燃え上がる街の中に取り残された幼き少年。 もろく崩れ去った建物の中から聞こえる断末魔の叫び。 夜中の突然の爆音から始まったその出来事は街を壊し、文字通り廃墟となった。 一箇所で起きたその爆発は列火となって街を襲い、焼き尽くす。 それはまるで・・・戦時だ。 街を破壊し焼き尽くし、断末魔の叫びが四方八方から聞こえるそれは戦時中を思い起こさせた。 その中をうつろな表情で歩く少年、ただ生き残るために歩くその少年の後ろでまた爆発が起きた。 「うわぁ!」 立ち上がるように彼は起きた。 その出来事が夢であることを確信した彼は、ため息をついた。 「またこの夢か・・・」 何度目であろう。物心ついたときから忘れずに見る夢。 自らは体験したことのあるはずのない出来事が夢となって現れる。 小学、中学、高校と年追うごとにソレは現れる回数は減ってきた。 高校に入った頃にはソレを観たという事実すら忘れていた。 それなのに2年に進級したとたんに、ソレは連日のように観るようになった。 いつも同じ。何一つ変わることのない内容といっていい夢。 唯一違うことといったら・・・最近の夢のほうがより鮮明に観るようになったこと。 それが返って、自分をある種の恐怖へと引きずり込んだ。 考えるだけで背筋を凍らせる。 この夢を観て、起きたときは大抵学校に行くのにちょうど良い時間帯であるというのが偶然ながらあるのも事実である。 彼はベッドからでるとすばやく着替えを済ませてキッチンまで向かった。 一人しか住んでいない彼の家は、一般的なマンションの一室である。 だからこそ多少の夜更かしはするし、門限を守らない日々を過ごしている。 一人暮らしをしているとはいえ、ちゃんと自炊はする。 ある程度の料理は作れるし、早めに母をなくした彼の家庭では父が働きに出て、自分が家事を行うといった日々を送ってきた。 高校に入ってからはバイトをしながら一人暮らしをはじめた。 一人暮らしをすることに父は反対もせずに後押しをしてくれた。 だからこそ、今まで生活費で余った分は父に送ってきた。 ・・・もっとも最近は音信不通で送れないのだが。 簡単に紅茶とサンドイッチを作って、朝食を済ませるとあわただしく家を出た。 特別にすることはないのだが、自分の奥底に眠る何かが「急げ。」と自分を呼び立てる。 ごく一般の普通の進学校からマンションまでは徒歩にして20分程度。 しかしこれは徒歩であって、急ぎ足で進む自分が要する時間はそれから3分の1は早く着く。 正門をくぐり、そこから見える時計塔を見上げる。 「7時20分・・・ちょっと早めに来ちゃったかな」 特にすることのない彼にしてみれば早すぎるぐらい。 この学校では1階から1年、2年、3年とフロアごとに学年分けされている。 特殊な実習、例えば生物実験であったり調理実習を行う教室は、また別に実習棟として用意されている。 自分は2年生なので2階にある教室まで急ぎ足で進む。 「おはよう~皆」 「おはよー木倉、また今日も早いんだな」 「まぁいろいろあってな・・・ところで宿題何かあったっけ」 「古文ぐらいだろ、何、宿題忘れたから早く着たのか」 「いやいや、本当に違うって・・・まぁしてないけどな」 「やっぱりそうじゃないか」 高校でよくある光景。そうしているうちにすぐに8時になった。 8時のチャイムと同時に担任が教室に来た。 担任は海原といって、数学を受け持っている。もっとも無口なためクラスメートからは[沈黙の海原]とかいわれているが。 朝は30分間の朝自習から始まる。・・・もっとも生徒の間では[魔の0時間目]という愛称がついている。 というのも朝自習でだされるプリントの量は1つの授業分あるわけだが、それが終わらない場合、『当日の宿題』となって放課後襲い掛かるからだ。 自分は数学が得意な分、なんとか朝自習の時間中に終わらせることができるわけだが、苦手な人にとって見れば朝から地獄である。 朝自習が終わり、12時すぎに午前の日程が終了した。 ふぅ、と一息ついているとあるクラスメートから食事の誘いが来た。 あるクラスメートというのも、同じマンションに住む山下っていう冴えない男だ。 勉学も運動も駄目とあって、あまりまわりの評判は良くはない。 しかしせっかくの誘いをこれといって断る理由もなく、一緒に食事をとることにした。 「なぁなぁ、朝自習の内容って絶対時間内には終わらないよなぁ。俺は数学は苦手だから俺なんか特に駄目だ。木倉はいいよなー勉強できるから」 「そこまではできないさ。それに山下、お前の場合『数学は苦手』ではなく『勉強は苦手』というほうが正しいんじゃないか」 「し・・失礼な!これでも古文は今回欠点免れたんだぞ」 「それ以外の10教科はすべて欠点のくせに」 「それをいうなよ~」 会話が弾む昼休みも、わずか40分しかなく、すぐに午後の授業開始5分前のチャイムが鳴った。 「もうチャイムかよ・・相変わらず早いんだよなぁうちの学校」 山下は、すこし不機嫌そうに次の授業の準備をはじめた。 自分も準備をすばやく済ませて午後の授業に臨んだ。 今日一日の授業日程が終わった。 部活に入っていない自分にとってみれば、放課後はただの暇でしかない。 どこからか自分が勉強ができるという噂を聞いて、多くの文化部から誘いがきた、が特別にこれといって入りたい部もなく、 それぐらいならアルバイトに行ったほうが実益があると判断した自分は近くのコンビニで働くことにした。 そのコンビニの店長さんは、さきほど一緒に食事をした山下の親戚だったこともあり、少なからず優遇をしてもらっている。 授業が終わって4時間働き休日は休み、それでいて月に7万という給料をもらっていた。 午後の9時ごろになってやっと自宅に帰ることになった。 コンビニの売れ残りの弁当をもらってきているので、それを暖めて夕食にした。 簡単ではあるけれど、夜9時になって疲れて返ってきた自分にとってみれば楽ではあった。 食事を済ませた自分は風呂も済ませてベッドに寝転がる。 心の奥底から確かに聞こえる「急げ」という呼びかけは気にはかかるが、特にこれといってすることもない自分は寝ることにした。 あの夢を観ないことを願って・・・。 木倉が眠りについて2時間ほどたった頃、マンションの屋上では異変が起きていた。 空は満月。雲ひとつない、透き通った夜空。 そのなかで、ひとつの人影がマンションの屋上にて魔方陣らしきものを書いている。 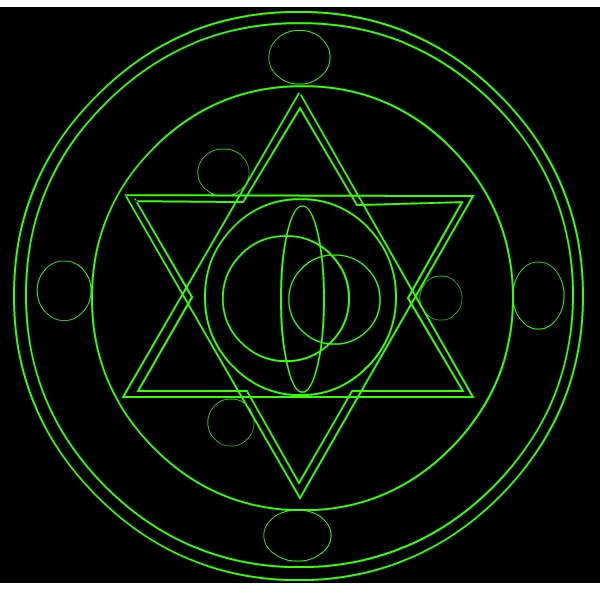 指から描かれるそれは、鮮やかな緑の発光体となって形を成していく。 「ふぅ・・・こんなものかしら?」 一仕事終えたその人影からは、わずかながら笑みが漏れた。 「うんと、魔道書によると・・この長ったらしい文章を読めばいいのね」 そういい終えると魔方陣の隣に立ち、なにやら呪文を唱え始めた 『―――Il y a l'et fait l'obscurité et il y a lumière dans la place. Il y a l'et fait un chiffre et il y a une ombre dans la place. Venez maintenant; le soldat du noir de jais!』 最後の言葉を言い終わって、その少女は様子を見ることにした。 変化が何もない。 「――――失敗しちゃったかな」 周りの空気はそんな不安に包まれた。が、それは気のせいであったらしい。 「――あ、魔方陣が起動し始めた。・・・成功?」  ゆっくりと回転し始めた魔方陣は、少しずつ加速し始めた。 「この魔力、やっぱり成功だわ。さぁ来なさい、私のサーヴァント!」 雷が落ちてきたときのような光が魔方陣から一瞬発せられたと同時に大きな魔法の衝撃が上空にて起こった。 「きゃぁ!なんなの、もう!」 突然の出来事にその少女は驚きと苛立ちを覚えた。――もっともその一瞬だけだったが 突然の光から現れたのは、紅の鎧を着た、槍を携えた長身の女性であった。 「・・・どうやら成功したようね、見た感じ・・ランサーかしら?」 「そうですが、あなたが私のマスターですか?」 「そうよ、もっともこの令呪が正しければの話だけど」 「その令呪・・・どうやら正しいようですね」 「そう、ひとまず先ほどの衝撃でこちらに誰かが駆けつけるかもしれない。一度ここを離れようか」 「わかりました、マスター」 と、言い終わるとサーヴァントは立ちつくした。 「どうしたの?さっさといくわよ。」 「先ほど衝撃が、と言いましたが、あれは魔力によるものですので。」 「え、そうなのね・・・でも魔法使いは私だけではないし・・・とにかくついてきて!」 「わかりました、マスター」 そうして二つの人影はどこかへと消え去った。 一方、マンションで寝ていた木倉は、この衝撃に気づいておきた。 「いったい何が起きたんだ、・・・地震か」 そう思って冷静に回りをみるが、部屋には何一つ変化がない。 「・・・なんだ、今の衝撃は?雷に直撃したような感じだ」 気になって仕方のない木倉は、部屋を出て、屋上に昇ることにした。 階段を走って昇り。勢いよくドアを開けた。 そこには誰も、何もなかった。 ちょうどあの少女らが立ち去った後だった。 何もないことがわかった木倉は、それでも心に残るものがあったのか隈なく捜索し始めた。 ―――やはりなにもない。 それを確信した後、木倉は帰ろうと思ったが、せっかく屋上まで来たのだからついでに夜景を見ることにした。 高層ビルがところ狭しと並び立ち、行きかう車のライトが鮮やかに街を彩る。 雲ひとつない夜空を見上げると、無数の星が光り輝いている。 夜ならではの景色に心を奪われながらも、夜の寒さに体をやられてしまい部屋に戻ることにした。 階段へ降りるためのドアを開けた瞬間、一瞬影が通った気がしたが、さきほどの衝撃のこともあり、疲れているだけとして気に病まなかった。 部屋に戻り、温かい紅茶を入れて飲むことにした。 「・・・どうしたのかな、自分は」 気の晴れない精神状況をどうにかしようとは思っても、どうすることもできず、温かい紅茶を飲み終えてすぐにベッドにうずくまった。 幼い頃から見る夢、今日のような不可思議な出来事 原因がわからないことが、逆に自分自身を不安をいだかせる。 かといってどうすることもできない自分への不甲斐なさと苛立ち。 明日は休みだし、家に帰ってみれば何かわかるかもしれない。 マンションから家までは決して遠くない距離だ。 近くのバスに乗れば20分もかからない距離だ。 ――しかし家まで行く公共機関はそれしかないが。 そうして心の突っかかりと明日の予定を考えながら、いつの間にか眠りについた。 マンションを去って、近くの住宅街に走り込んだ二人はある一軒に入っていった。 一戸建ての、周りと比べると立派な住宅であるその家は、長く建っているのであろう証に、家に美しくコケが生えている。 部屋に入り、リビングにはいるや否やすぐに呪文を唱え始めた。 『――Mouvement』 一般にはわからないこの行動も、霊体であるサーヴァントには即座に理解できた。 「結界を張ったのね、マスター・・・しかし一言のみで結界を張るとはいい腕ね」 「そうかしら?私は毎日こうやって結界を張ってるから普通に感じるんだけどね」 「そうなのね、結界魔術自体は魔力を大きく消費するから私が張ることはお断りだったんだけどその必要はなさそうね」 結界とは、一言で言うことができるが、実際には数多の種類に分かれている。 相手の侵入を探知する結界や、結界に入った者の能力を下げたり、結界に入った者の魔力を奪う結界、または結界を張っている範囲を人目につかないようにするものなど種類は多い。 その内今回張った結界は人目に付かないようにする結界で、他の結界に比べ魔力をより多く消費するものである。 「まだ私の魔術に関する知識と力は未熟だからね、どうなるかわからないけどしないよりはいいでしょう」 「そんなことはない、マスター」 「・・・ひとまず、重要なことから話しましょう あなたはランサーのサーヴァント、ここに来て始めて気づいたけど東洋人みたいね。 そこまではわかったわ。今後のためにあなたの得意技と戦法ぐらい教えていただけるかしら?」 「私の戦法・・ですか、私は一対一が中心です。 得意技といわれましても、ランサーですから突くことと払うこと、流すことしかないですよ」 当然のことなのだが、その当然のことを言われたために逆に動揺してしまった。 「そう・・そうよね、当たり前だよね、そんなこと」 「・・・ところでマスター、私からも聞きたいことがあります」 「うん、なにかしら?」 「戦闘上、私生活上で呼び名は大切です。あなたの名前をお聞かせ願いたい」 「あ、そうね、忘れてたわ。私は桐下 綾、そこの庭に大きい桐があるでしょう、そこからついた名前なんだって」 「桐下 綾ね、呼びやすいのは『綾』かな、綾って呼ばせてもらうわ」 「それでいいわ。あなたの名前も知りたいけど、戦闘自体に支障はないからランサーって呼ばせてもらうわ」 「わかりました、綾」 綾はすこし驚いた。 名前を教えて「綾と呼んでいいわ」とまで言ったが、何一つ不自然さがない、昔からの知り合いのように『綾』と呼ばれたことに不思議な衝撃を受けた。 「どうしました、綾」 「あ・・・いや、なんでもないわ」 「気分でも優れないの?」 「大丈夫よ、ありがとうランサー」 話をしている間に時間も翌日の2時になってきている。 「ランサー、私は学生だから朝が早いの。特別これといったことはないけど、遅刻するわけにも行かないから私は寝るわ」 「綾、そのことに関してだけど、綾が学校にいっている間、私はどうすればいい?私を霊体にすることはできる?」 「え、サーヴァントは霊体なのであるなら、魔力は私から供給しているはずだから私が魔力供給を止めればいいんじゃないの?」 「だから、魔力をコントロールできるかってことを聞いてるのよ」 「それは大丈夫よ。私だって伊達に魔術師を名乗っていないわ」 「ならいいわ。学校といえど、私はできる限りそばにいるから」 「心強いわ」 そして寝ることにした。 夜が明けて朝になった。 ランサーに肩をたたかれ、綾は目覚めた。 「ん~朝かぁ」 「おはようございます、綾」 「きゃぁ!・・・ってランサーね」 「今日は学校でしたね、綾」 「そうね、食事を取ってから行きましょうか ところで現代は変わったのですね」 「なにがいいたいの?」 「前に召喚されたとき、つまり前のマスターと契約を結んでいたときには土曜日には学校はありませんでした」 「え?・・・あ!そうだ、今日は土曜日だった!」 はぁ、とため息をつく綾を見て、ランサーはくすりと笑うのだった。 「綾は夜に弱いんですね」 「~~~!ランサーも昨日言ってくれたらよかったのに」 「召喚されたときには、いったいいつで、今どこにいるかなんてわかりませんから」 「うー・・・。そうね、私が悪かったわ」 「気にしないでください、綾」 「せっかくだし、街を探索しましょうか。状況把握しておかないと作戦も立てられないでしょう?」 ウンとランサーはうなずいて家を出た。 ―――ジリリリ 部屋に響き渡る目覚まし時計の音 時計の針は7時を指していた。 「・・・ん。もう7時か・・・」 木倉は暖かいベッドを恋しそうにゆっくり出た。 夜中に突然起きた衝撃。 走って階段を昇ったが何もなかった屋上。 夜中にあった出来事が、朝起きた木倉の思考のすべてを占領する。 「今日、今日は何をしようとしてたんだっけ・・・そうだ、家に帰るつもりだったんだ」 ようやく目覚めてきたのか、少しずつ冴えてきた。 今日は2年ぶりに家に帰るつもりだったんだ・・・ 連絡は入れてないが、今まで音信不通であったことを考えれば・・・連絡をしても時間の無駄であったろう。 「今から食事をして、急いで準備すれば・・・7時45分のバスに乗れそうだ。しかし不便だなぁ・・」 木倉が浮かない表情になる。 それもそのはずである。 今住んでいる町はそれなりに発展している。 街の中心には木倉の通う高校があり、街は急激な技術発展によって高層ビルが並び立っていた。 街の北には港があり、街と港を囲うように山が連なっている。 木倉の住むマンションやその近くにある高級住宅街は、街のはずれとはいえ徒歩20分程度の距離である。 そんな環境にあって、この周辺には山にいく方向のバス停と街にいく方向のバス停が一つずつしかないのだ。 だが文句を言ってもどうしようもない。 木倉は決意したかのように動き出した。 食事は毎日のように紅茶とパンですませた。 着替えを済まし、自らたてた予定と比べる。 いつも時間には5分は余裕を持たせているので、バス停までゆっくりいくことができる。 マンションからバス停までは歩いても5分ほどであった。 時間は7時35分。 「よし、いいな・・それじゃぁいくか」 木倉は電気・蛇口・窓締めを確認し、足早と家を出発した。 そのころ、綾とランサーは住宅街から程近いバス停にいた。 街中を動き回るのに町の中心部をくまなく通るバスは最高の交通手段であった。 この周辺には街に行くバス停はひとつしかないが、いい具合に朝も早い。 霊体であるとはいえ、できる限り人との接触は避けたかった。 時間は7時40分。 反対側の車線には知っている顔があった。 「やば・・・あれは・・・」 木倉も桐下を見つけたようだ。 「お、おはよう桐下。朝から・・散歩?」 「ま、まぁね。そういうあんたは何してるのよ」 「俺か?俺は今日田舎に帰るんだ。バスでしかいけないんだが、20分程度でつくしな」 「そ、そう」 桐下にとってみれば、サーヴァントであるランサーは霊体に戻してあるから人目から見えないことは知っているにしても、やはり人との接触は避けたかった。 しかも相手は去年同じクラスだった木倉ときた。 少なからず精神を緊張させてしまった。 「・・・おーい桐下。お前は何してるんだ」 「え、えっと・・・街の友達の家に遊びにいこうと思ってね」 「へぇ~・・桐下にも友達はいるんだな」 「何、喧嘩売ってるの遼君?」 「そんなことないさ、桐下はその・・才色兼備だからさ、一人で勉強とかしてるものかと」 「そんなことはないわ。・・あ、私はあのバスに乗るから、それじゃぁまたね」 「おう。また学校でな」 桐下は逃げるようにバスに駆け込んだ。 桐下がバスに乗り込んだ頃、木倉が乗るバスも到着した。 バスに乗り込む木倉を後にして、桐下の乗るバスは出発した。 「(ふう・・まったくびっくりするじゃないのよ)」 「綾、もう話してもよろしいですか?」 「あ、ランサー。もういいわ、途中で話しきれちゃったね。でもランサーが話す『声』は他の人にも聞こえるのかしら?」 「魔力を持つ人間には聞こえるわ」 「そう・・・一応しばらくは人がいるときは今みたいに静かにしといてもらえるかしら」 「心得ております、綾」 バスに乗り込んだ木倉はこれからのことを考えていた。 もし親父がいなかったら? いや、家の鍵はあるし、いないときは書置きをしていけばいい。 何か事件が起きていたら? そうだとしたら何か連絡があるはずだ。確か親父が、同じ町に住む親戚に緊急時は連絡をしてくれるように手配をしたと言っていた。 多くの考えと戸惑いを抱えたまま、山道へバスは進んでいった。 ――窓から見える山々。 もしただの観光として、遊びに来ていたのならどれほど気が晴れただろう。 木倉は窓を見つめ、思いにふけっていた。 いざバスに乗って家に帰ろうと思うと、多くの考えが頭によぎってしまう。 音信不通なのには本当は何か訳があるのではないか? 家に帰って、もし親父が倒れていたら・・・ そんなことはないと頭の中ではわかっているはずなのに、どうしても拭い切ることができない。 それに、もう自分はバスに乗っている―― 頭の中のもやもやを晴らすために自分はバスに乗っている―― ちゃんとわかっている。 それでも考え込んでしまう自分に嫌気がさした。 腕時計を見つめ時間を確かめる。 時計の針は8時をさしていた。 バスに乗り込んだのは7時45分。家の近くのバス停まではほぼ20分でつく。 となると後5分。たったの後5分。 ―――でもその5分が長い。 ため息をつき、ガラス越しに見える山を見上げた。 「・・・確かこの山の頂上には神社があったっけ。」 俺は、毎年初詣のときにはあの神社に行った。 家から近いということもあったが、山から見ることができる街並みは美しかった。 建物から漏れる光は星空で、移動する車のライトは流れ星・・・ 今思えば子どもみたいな例えだなと思えるが、それほどに美しく、きれいだった。 ――――――昨日の夜に見た街とは比べ物にならないぐらい。 思い出にふけっている間に、目的地のバス停が近づいてきた。 降りる準備をし、バス停に着いた。 料金を払い、バスの階段を下りる。 気が晴れないバスでの移動ではあったが、家に向かえば何かわかるはず・・ 古びたバス停を後にして、家に向かうことにした。 バス停から家まで裸眼でも捉えることができるほど近い。 最近になって街から近いことから賑やかになってきた住宅街なのであるが、ひとつ孤立したかのように歴史ある木造住宅がある。 それが我が家だ。 歴史あるといっても、決して「ボロ家」とかではなく、きれいに整えられた、テレビで見るような武家屋敷に近いものがある。 俺はこの家が好きだった。 幼いころから住んでいたということもあるが、いつも何か新しい発見があって飽きることがなかった。 気がつけば目の前には家の門の前にいた。 親父はどうしているだろう、なにか変化はあるのだろうか? 門をくぐり、玄関まで歩く 懐かしい景色もさることながら、しっかりと手入れされている庭。 昔から何も変わっていない。あの当時のままだ。 でも・・・それが逆に怖かった。 仕事に行っている親父がここまで手入れができるものなのだろうか? ひとまず会ってから、それからだ。 ドアチャイムを鳴らし様子を見ることにした。 ・・・人の気配がない。 二度、三度とチャイムを鳴らすが何一つ気配がない。 仕方ないなとばかりに念のためと渡されていた合鍵を使う。 ―――ガチャ 木倉は横開きの窓をゆっくりあけて家の中に入った。 「ただいまー・・・」 すると玄関にはしっかりと並べられた靴と青々とした生け花が置かれていた。 気になって生け花の容器の水を見ると透き通った真水のようだった。 少なくとも1週間以上家にいないというのはありえない。 仕事なのか・・それとも外出? やっぱり無連絡できたのが悪かったか? ひとまず上に上がって家を回ることにした。 キッチン、廊下、親父の寝室・・・ それからリビングにいくと手紙とペンがおかれてあった。 冒頭には「私の息子、遼へ」とあった。 『遼』とは俺のことだ。 せっかく見つけた手紙だ。興味に負けて、見ることにした。 ―――私の息子、遼へ 一人暮らしにはなじんだか?うちは何一つ変わりない。 最近では夜空がきれいだが、都会の空はどうだろうか? 今回手紙を送ることにしたのは、本当は一人暮らしに行く前に伝えておくべきだったのかもしれないことを言っておきたかったからだ。 お前は魔術だとか神秘的といわれるものには興味がなかった。 時代の流れではゲームとかいったもので取り上げられているが、お前は常に現実主義者だった。 だからなのかもしれない。いうことができなかったのは。 前文が長くなる前に本題に移ろう。 魔術は存在する。 それは紛れもない事実だ。 決してゲームなどといった軽い気持ちで考えられるようなものではない。 魔術とは――――殺人道具だ。 お前にはいうのが遅れたが、この家の家系は魔術師の血を引いている。 信じられない、馬鹿げているとも思うだろうが、これは事実だ。 もし、いつの日か家に戻る機会があれば、倉庫の2階に赤い木箱がある。 そこには家宝である『魔術新書』がある。 それをお前に譲り、さらに詳しいことを話したい。 家で待っている。 ―――父より 2007年6月28日 何気なく見たつもりが見入ってしまった。 手紙を見終えると不思議な点に気づいた。 まず、手紙に『お前は現実主義者だった』とあるが、それは親父が『理想のみならず、現実をしっかりとみろ』といったからであって、 決して悪気があってのことではなかった。 また、親父も現実主義者であった。それも頑固なほどの・・・ そんな親父が、子供みたいな魔術について語るなんてあるのだろうか? 仮に、これが事実だとしても・・だ。 とても親父が口にするような言葉とは思えなかった。 そしてもう一つ気づいた。 それは日付だった。 今日は2008年6月4日なのだ。 手紙の日付は2007年6月28日。 つまりこの手紙は俺がマンションに行ってまだ2か月しかたっていない時にかかれたものなのだ。 ・・・矛盾が多すぎる。 ひとまずこれに書かれてあるとおりに倉庫に向かった。 倉庫の扉を開け、2階に上がる。 さすがに倉庫はホコリがする。 浅く呼吸をしつつ奥に進んでみると、赤い木箱はあった。 倉庫に置かれてあるほかのものに比べると、それは厳重に保管されていたほうだった。 赤い木箱をあけ、中身を見ると一冊の本と果物ナイフぐらいの大きさの短剣が見つかった。 木倉はそれらを手にとって家の中に戻ることにした。 リビングに行き、魔術新書と書かれた分厚い本を手にとって見た。 その中身を見て驚愕した。 「げ・・・これって日本語じゃないのか・・・」 しぶしぶアルファベットで記述されている本の1ページ目をめくる。 ―――やはりめんどうだ。 「持って帰ってからみるか・・・」 もって来たかばんの中に短剣と分厚い魔術書を入れて、少しの間親父の帰りを待つことにした。 帰ってこないかもしれないが、どうせ明日は日曜日だしこれといった予定もない。 キッチンから茶葉を探し出し、お湯を沸かすことにした。 ちょうどお昼時。いろいろと動き回ったからおなかもすいてきた。 お湯を沸かし終えると、近くにあったコンビニまでいくことにした。 家を出て、鍵を閉める。 念のため鞄は持って歩くことにした。 近くのコンビニにはいると、手軽にできるインスタント食品を昼と夜の分だけ買って家に戻ることにした。 バス停で木倉と別れたあと、桐下とランサーは街を『視察』していた。 決められたコースを回るバスは、ちょうど『観光バス』と同じ役割を果たした。 商店街から、街の中心である高層ビルが立ち並ぶ商業街、そして港。 一回りし終えたところでバスを降り、近くにある1番高いところから街を見通せるビルに入った。 自動ドアからビルに入り、エレベーターで最上階である30階まで駈けあがる。 最上階につくまでわずか数十秒。 時間は11時を少し回ったところで、人はこれまたいいことにだれもいなかった。 「ランサー、もうはなしていいわ」 「・・・綾、この時代はすごいですね。近づくと勝手に窓が開いたり、すぐに最上階までついたり・・・」 「そうかしら?わざわざ説明するまでもないかと思って何も言わなかったけど。だって前にも聖杯戦争に参加したんでしょ」 「綾、前回の戦争は何年前だと思ってるの?数ヶ月や数年じゃないのよ」 「あ、そうなんだ。てっきり7,8年前のことだと思ってたわ」 「綾、せめて前回の戦争のことぐらい把握しておいてくださいね、教訓とかがわからないじゃないの」 「そうね・・・それは悪かったわランサー」 すこし気まずそうに綾が返答した 「ところでランサー、ここの地形はどうなの?」 「どうといわれましても・・・大通り以外なら道が狭いので、相手によっては戦闘は行いやすいですよ。 もっとも、こんなに建物があると奇襲される可能性も高いので私はできる限り避けたいですが」 「そうね、できる限り見通しのいいところの方がいいわね」 「最適と思えるのはグラウンドなどといった場所がいいですね、となると学校がいいのですが」 ランサーがそういうと綾は悩んでしまった。 平日学校のある日ならば・・・それは有効な防御策であり、戦闘を行ううえで有効な作戦だ。 しかし綾自身は結界がある限り・・できるかぎり家にいるほうが安全だと思っている。 しかし、もし結界が破られた場合、家で地形における『戦略的優位』がない・・・。 まぁそれはひとまず・・・ 「家に帰って考えればいいのです、綾」 思っていたことを言われてびっくりする綾。 「そ、そうね。とにかく先頭に不利ならここに長居する理由はないわ。帰りましょう」 そういってエレベーターに向かうのだった。 コンビニから家に帰ってきた木倉は食事をとることにした。 さっき沸かしたお湯を買ってきたインスタントラーメンにかけて出来上がるのを待つことにした。 時計を見ると12時47分だった。3分のインスタントだから12時50分にはできあがる。 その待ち時間にできる限りこの分厚い魔術書の意味を理解しようと本を鞄から取り出して開けて必死に和訳するが、まったくわからない。 「これ本当にわかるのかな・・・・」 うなされるように頭を抱え込む。 ―――ドサ 「あ、本落としてしまった・・」 やれやれと本を拾い上げると、本に挟まっている紙を見つけた。 それを広げて見ると題名に「和訳」とある。 読んでいくと途中までではあるがしっかりと和訳されている。 しっかり一度本を調べていなかったミスに木倉は後悔した。 気になって分厚いその本をめくっていくと、途中途中で和訳されてある紙があった。 しかも和訳されてあるそれは、一つ一つが繋がっていた。 「なにやってるんだろう俺・・・」 ため息をついて和訳されたその紙を順番どおりに並べる。 そしてそのころお腹がグゥとなった。 「・・・あ、お湯を入れてもう何分たったんだ!」 時計を見ると13時10分・・・20分も越えていた。 まったくついていない。 ひとまず中身を見てみると食べれそうだった。 20分遅れの食事になったが、お腹がすいては何もできない。 一口食べてみることにした。 ――――――――――――予想通り麺が延びていた。 しかしせっかく作ったものだ。・・・・お湯を入れただけだけど。 容器を手に持つと、流し込むように麺を胃袋に入れた。 ひとまずインスタントラーメンを食べ終えて片付ける。 まだ一日が終わるには半日はある。 鞄に分厚い魔術書をいれて、ベランダで寝転がる。 日もいい感じで差し込んできて昼寝するにはちょうどよい。 親父もいつ帰ってくるかもわからないのでそこで寝ることにした。 ―――――なぜか変に寒い。 周りの空気が冷たいという感じではなく、病気で寝込んだときに起こるような悪寒。 目を覚ますと家の近くの公園から変な音が聞こえる。 何か言っているようにも聞こえるが、なんと言っているのかが聞き取れない。 家からも近く、まだ時間は4時と少し夕焼けがかってはいるものの明るい。 親父の帰りをただ待つのも暇だし、変に気にかかって仕方ない。 俺は荷物をまとめて公園に行くことにした。 ところで公園はこの住宅街には1つしかない。 この公園ができるには成り行きが存在する――― ―――住宅街のど真ん中にあるこの公園は、もともと街でも1番の大地主だった老夫婦が 街を引っ越す際に自分の家があった敷地を『整理』し、子供たちのために用意したものだ。 『整理』といっても建物だけでなく、棚から本などありとあらゆるものを埋め立てたわけだが。 ――その老夫婦は近所では有名な奉仕活動を行う評判のいい夫婦だった。 親父とは信仰が昔からあったらしく、俺が進学する際にはわざわざ進学祝として少なからずお小遣いをもらった。 その老夫婦はこの街で一生を過ごすつもりだったのだが、ある『事件』が起きてから引っ越すことに決めた。 ――――――幽霊が出たのだ。 最初は何かの見間違いかと思って誰も信じなかったのだが、数週間後では街のいたるところで幽霊が出たというような事件が発生した。 幽霊といっても、人型とか白装束といったようなものではなく、言霊のような発光物質が家のいたるところから沸いてくるというものだ。 そのような事件が自分の家以外でも頻発するようになったため、逃げるように老夫婦は隣町に引っ越したのだが、 不思議なことに老夫婦が引っ越した後からは一度たりとも『事件』が起こることはなかった――― そんなことがあったので、周りからは老夫婦が悪霊に取り付かれたのだとか家があった付近に魔物が住んでいるのではないかと噂した。 しかし、埋め立てたとはいえそれは地下深く埋めてあるもので、公園用にしっかりときれいな土を用意し、完成してすぐにお清めをした。 それからは何事もなく、ごく普通の公園として子供たちの広場となった。 俺もこの公園にはずいぶん通ったものだ。それなりに遊具はあるし、住宅街にある公園とは思えないほど広い。 大きさだけで言えば、サッカーコートの半分ぐらいはあるだろう。 それだけの敷地を持ってたのだから、相当なお金持ちだったに違いない。 ひとまず、せっかく田舎町に戻ってきたのだから何も異変がなくても見に行くのもいいだろうと思った。 コンビニに向かう道とは逆方向へ歩く。一歩一歩近づくたびにその奇怪な音は不気味さを増した。 自分がおかしいのか、それとも何か本当にあるのか? 家から歩いて3分程度の住宅街の一角に公園はあった。 公園が見える距離にまで近づくと奇怪な音以外の小さい声が聞こえた。 ―――――・・・ダ・・・・・・イ その声は公園から聞こえてくるようだった。 どこかで聞いたことがあるような声なのだが思い出せない。 俺は無性に気になって公園まで全力で走った。 仮にこの時間帯に不審者がいてもまだ明るい時間帯だ。 不審者ぐらいなら俺一人なら逃げられる自信があった。 ついに公園の入り口についた。 公園の中に入り、様子を把握することに専念した。 やはり声は公園から聞こえる。 その証拠にさきほどより声は鮮明になり、音源が広場から聞こえてくる。 だが、それでもまだ聞き取るには小さすぎる声だった。 確かに――どこかで聞いた声なのだが思い出すことができない。 心の引っかかるものを残したまま、広場に行った。 流石広い公園とだけあって、見通しがよかった。 広場にはいり、周りを見渡す。 見渡す限り誰もいないし、近くにある遊具も、砂場も、周りに植えられている木までが変わりなかった。 ―――イ・・・ダ・・タ・・イ 何かは聞こえるが、しっかり聞き取れない。 ついに俺は感情的になってしまった。 「おい、さっきなら何を言ってるんだ?はっきりいってくれ」 口走ってしまったこととはいえ、何か恥ずかしい。 俺は仮にも高校生だし、もし公園には誰もいなくて近くに知り合いがいたら・・・ まぁたとえ口走ったところで誰もいないのだから何も変化などあるわけがないのだが。 ―――そう、それが普通であるならば。 発言をしてから数秒ほどしてから急にはっきり聞き取れる声となって帰ってきたのだ。 ――イヤダ、シニタクナイ 「(!!)」 まさか、そんなことがあるわけがない。 今まで夢で聞こえてきた声とまったく同じだった。 頭の中にめぐる悪夢。 「いったい、いったい何が起きてるんだ!?」 はっ、と気づいたかのようにまた周りを見渡すとそこには夢に見た惨劇のステージとなっていた。 燃え上がる街。住宅街は崩れ去って廃墟となっていた。 何がなんだかわからない。 俺はパニックに陥った。 そう、ここは街だった。今の今まで。 俺が公園に行き、広間に着くそのときまでは。 そして今、街は廃墟となってこうして目の前に広がっている。 まるで俺の存在を否定するかのような状況を前にして俺はその場で倒れこんだ。 俺は誰なんだ? 俺は何のために生まれ、何のために生きているんだ? 頭が朦朧とする中、突然目の前で爆発起きた。 炎が雪崩のように押し寄せる。 炎から逃れようとするが立ち上がることができない。 炎は目前まで迫ってきていた。 『もう逃げられない。』 そして炎は俺を飲み込んでいった。 Copyright © 2008 - 2009 空の向こうに All rights reserved. ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
|