
|
|
黒執事小説『猫化』黒執事「猫化」にゃん、にゃん、僕は猫になる。 ゴロニャン、猫になりたいニャン。 人間よりも猫のほうが楽だから。 生きているのが苦しい時に僕は猫化する。 猫になったら、いっぱい甘えられるし、 いっぱい可愛がってもらえるし、 嫌なことも辛いことも忘れられる。 だから、僕は猫になる。・・・ 「坊ちゃんお目覚めの時間ですよ。」 セバスチャンに起こされて、僕は夢から覚めた。 それにしても、変な夢を見たものだ。猫になる夢とは・・・ 「本日の朝食はポーチドサーモンとミントサラダとスコーンをご用意 致しました。」 「この香り、今日はセイロンか。」 「ええ、本日はロイヤル・ドルトンのものをご用意致しました。」 僕の朝は一杯の紅茶から始まる。 「おや、坊ちゃんの後ろにクネクネと蠢いているものは何です?」 「え?僕の後ろに何かあるのか?」 「何やら尻尾のように見えますが・・・」 言われてみれば、お尻のあたりがムズムズするような・・・ 僕が恐る恐る後ろを振り向くと、やはり尻尾だった。 そして、信じられないことに尻尾は僕のお尻から生えていた。 「こんなものをつけておいでとは・・・坊ちゃんにも困りましたね。」 セバスチャンが僕を見て、ため息をついた。 「頭に猫耳までおつけになって、いったいどういうおつもりです?」 「え?!」 僕は驚いて両手で頭を押さえてみると確かに大きな耳が頭の上に 二つある。いったいこれはどうなっているんだ?あの変な夢が現実 になってしまった・・・僕は途方にくれた。 「魔界ではストレスが原因で猫に変身する病があるとかないとか ・・・坊ちゃんは人間ですが、何らかの影響を受けて、そうなって しまったのかもしれませんね。」 セバスチャンは僕を見てクスクス笑った。 「しかし、まぁ、可愛らしいので問題はありませんね。」 「問題は大有りだ。なぜ、猫になんか・・・」 「それにしても、なんとも可愛らしい。」 セバスチャンが僕の猫耳を撫でた。 ビクッと僕の体は反応し、耳がキュンとなった。 「感じやすいんですね。」 セバスチャンはニヤリと笑って僕の反応を楽しんだ。 「尻尾のほうはどうですか?」 セバスチャンが今度は尻尾をギュッと掴んだ。 「あんっ。」 僕は思わず声を出してしまった。 「やはり尻尾のほうが感度良いですね。」 セバスチャンは僕の尻尾を掴んだまま、ゆっくりと愛撫するように 手を動かした。僕は尻尾を撫でられるたびにゾクゾクした。 快感が体を駆け巡り、我を忘れそうになった。僕は無意識のうちに セバスチャンの手の動きにあわせて尻尾をくねらせて悦んだ。 「おやおや、尻尾が揺れてますよ。そんなに良いですか?」 「あぁ、ああぁ~、もっとぉ~。」 「もっと何ですか?坊ちゃん、おねだりの仕方は教えたでしょう?」 僕は顔が真っ赤になった。尻尾を撫でられてセバスチャンが欲しく なったとは恥ずかしくてとても言えない。意地悪なセバスチャンは 口の端をニヤリとつりあげて、こう言った。 「言えないのなら、罰を与えなければいけませんね。」 セバスチャンは何処からか首輪を取り出して、僕の首につけた。 そして、首輪についた鎖を引っ張って、ベッドから引きずり下ろし、 「罰として、お庭を一周しましょう。フィニたちにもこの滑稽な姿を 見てもらいます。」 「や、やめろ。い、いやだ。やめてくれ。」 僕は必死に抵抗した。しかし、力でかなうわけもなく、無残にも 僕は部屋から連れ出されてしまった。 部屋の外にはフィニ、メイリン、バルドの3人がいた。 庭に出るまでもなく、見られてしまった。 「きゃあああ~可愛いですだぁ~」 「ホント可愛い子猫ちゃんだね。」 「この猫、拾ってきたのか?なんて名前だ?」 僕は3人が口々に言う言葉を理解できなかった。 だが、次の瞬間、僕は完全に猫になっていることに気がついた。 セバスチャンは僕を軽々と抱きかかえ、僕に頬ずりして、言った。 「シエル坊ちゃんですよ。猫になってしまわれたのです。 これからは皆さん、猫にお使えするのです。きっと、毎日が今まで 以上に楽しいですよ。見てください。この肉球を。」 セバスチャンは僕の手をぷにっと押してご満悦の表情を浮かべた。 「わぁ~僕にも触らせて~」 「私にもさせてくださいですだぁ~」 「俺にもやらせろよ。」 3人がよってたかって僕の肉球をぷにぷに押し始めた。 「いやだぁ~やめてくれ~」 僕は叫んだが声にならない。失意の中で僕は意識を失った。 「坊ちゃん、お目覚めの時間ですよ。」 セバスチャンが部屋の窓のカーテンを開けると、眩しい朝の陽ざし が差し込んで、僕は再び目を覚ました。 「うなされておいでのようでしたが、どうかなさいましたか?」 「いや、なんでもない。」 僕は夢だったのかとほっとした。人間が猫化するわけがない。 「本日の朝食はポーチドサーモンとミントサラダとスコーンをご用意 致しました。」 「紅茶はセイロンか。」 僕はウェッジウッドのティーカップに注がれた紅茶に口をつけて、 何気なく部屋のドアの方へ目をやると、首輪が床に落ちていた。 僕は驚きのあまり凝固した。頭が真っ白になった。 「申し訳ありません。首輪を一つ片付けるのを忘れておりました。」 セバスチャンはクスッと笑って、僕に手鏡を差し出し、こう言った。 「ご心配には及びません。すべては元通りに致しました。 ファントムハイヴ家の執事たる者これくらい出来なくてどうします? あくまで、執事ですから。」 セバスチャンは僕にニッコリと微笑んだ。 (完) 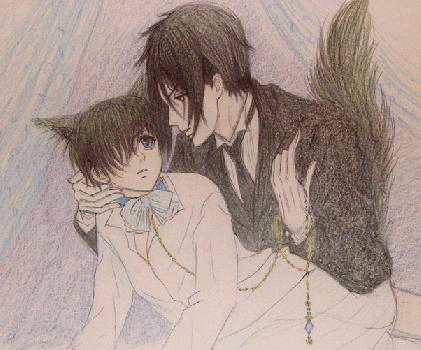 ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
|