
|
|
|
全て
| 見たもの・聴いたもの(雑記)
| その他(時代小説)
| 佐野元春 その他Newsの類
| 大河ドラマ
| その他(現代小説)
| 司馬遼太郎
| 池波正太郎
| 山本周五郎
| 藤沢周平
| ホントは読みたくないビジネス書籍
| 映画「あ」行
| 宮部みゆき(時代小説)
| 宮部みゆき(現代もの)
| 阿刀田高
| 遠藤周作
| 洋書
| 宮尾登美子
| 佐野元春 Back to the Street
| 佐野元春 Heartbeat
| 佐野元春 Someday
| 佐野元春 Visitors
| 佐野元春 No Damage
| 佐野元春 Cafe Bohemia
| 佐野元春 NFと泳ぐ日
| 佐野元春 Time Out!
| 佐野元春 Sweeet16
| 佐野元春 The Circle
| 佐野元春 Fruits
| 佐野元春 The Barn
| 佐野元春 Stones and Eggs
| 佐野元春 The Sun
| 佐野元春 Coyote
| 吉川英治
| 陳舜臣
| 映画「か」行
| 映画「さ」行
| 映画「た」行
| 映画「な」行
| 映画「は」行
| 映画「ま」行
| 映画「や」行
| 映画「ら」行
| 映画「わ」行
| 映画「数字など」
| 佐野元春 月と専制君主
| 塩野七生
| 星新一
| 村上春樹
| 有川ひろ
テーマ:時代小説がダイスキ(480)
カテゴリ:宮部みゆき(時代小説)
愛読漫画ブラックジャックの解説を宮部みゆきが執筆している。
当時(平成六年頃デス)、全く宮部みゆきなる女流作家など知らず、何の人なんだろう?と疑問に思っていた。 一巻が手塚夫人だったり、その他では大森一樹(ゴジラの監督の人デスネ)、立川談志、里中満智子などなど、そうそうたるメンバーが連なっていたのでさぞかし名のある人なんだろうけど… 思えば、思えばその頃はこんなに読書熱が復活するなんて想像だにしなかった。 愛読書が少年マガジンにヤングサンデーを欠かさず、その他青年向け漫画を昼食時に読んでいたっけ。 いつものごとく前置きが長くなりやんしたが、この本所深川ふしぎ草紙、まあ俗に言う『人情もの』なんだけれども、ストーリーの流れがブラックジャックみたいなんだよね。 特に第一話の『片葉の葦』、物語の当初では嫌われ者にしか写らない人物が、『転』を迎えた途端、怒涛のように好ましい人物像に変わる、これって誰かに似ているよな~と。 あ!そうだ、ブラックジャックじゃん、と。 彼女はこの小説を執筆するにあたり、BJの物語の展開をどこかで意識していたに違いない。 そんなことを思っていたら、宮部みゆきがブラックジャックの解説書いていたことを改めて思い出した。 今、その解説を眺めている。 彼女曰く。手塚作品とは。 大人になった人々に、かつて少年少女だった頃に同居していた詩人の部屋の存在を気づかせるだけでなく、空き部屋があるがゆえに理解することができる温かさをも内包している作品を書いている。 そして詩人を同居させている世代であれ、悲しいかな詩人が去ってしまった世代にも平等に同じ強さ、鮮やかさで全く種類の異なる感動、感銘を与える、と。 彼女の作品にも上記のことが当てはまる。 会社で目の前に座る先輩はよく飛行機で出張する人だが、機内で読書をするとき、宮部みゆきを読んでいることがフライトアテンダントに見られるのが恥ずかしいそうだ。 (しょっちゅう乗っているから馴染みになった人もいるそうだ!) ま、もっとも山崎豊子の沈まぬ太陽を読んでいるのもいかがなものか?と思うけれども(苦笑) 宮部みゆきの作品を機内で読むことに恥じらいを持つ、なんとなく分かる気がするナ~~~と、僕なら司馬先生の作品か、池波先生の作品かな~~~と思うもん。 それは何故なのかな~~~?とその会話のとき疑問の解答にふと辿りついたような気がする。 彼女の作風は、僕らの中にいた詩人を他者に気づかれそうにさせるからだ。 〔片葉の葦〕 〔送り提灯〕 〔置いてけ堀〕 〔落葉なしの椎〕 〔馬鹿囃子〕 〔足洗い屋敷〕 〔消えずの行灯〕 いずれも本所を中心にした七不思議を題材にしながら、庶民の姿を通じてヒューマニティを我々に問いかけている。 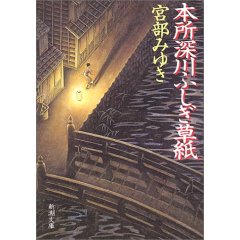 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|