
|
|
|
カテゴリ:ラ・ワ行の著作者(海外)の書評
ロフティング『ドリトル先生航海記』(岩波少年文庫、井伏鱒二訳)
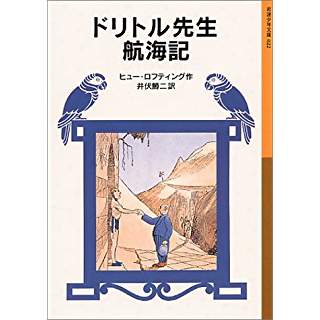 靴屋のむすこのトミー少年は,大博物学者ロング・アローをさがしに,尊敬するドリトル先生と冒険の航海に出ることになって大はりきり.行先は海上をさまようクモサル島.島ではロング・アローを救い出し,ついに先生が王さまに選ばれ活躍しますが,やがてみんなは大カタツムリに乗ってなつかしい家に帰ります。(アマゾン内容紹介) ◎優れた井伏鱒二の訳 『ドリトル先生航海記』が単行本(新潮モダン・クラッシッス、福岡伸一訳、初出2014年)になっていたので、懐かしくなって手にとりました。本書は小学生のときに、図書館で借りて読んでいます。医学博士であり博物学者であるドリトル先生は、犬や鳥や魚と話すことができます。覚えていたのはそれだけで、まったく新鮮な物語として堪能しました。 その後、小学生の孫たちに読ませようと、岩波少年文庫『ドリトル先生航海記』を買い求めました。訳者の井伏鱒二は「標茶六三の文庫で読む500+α」で『山椒魚』(新潮文庫)を紹介しています。 単行本(福岡伸一訳)のあとがきには、次のような文章があります。 ――スタビング君がはじめてドリトル先生と出会い、ドリトル先生の家を訪ねることになるシーンは、何度読んでも心温まる。とても美しい一節です。ドリトル先生の物語のエッセンスがすべてここに凝縮されているといってもいい。(福岡伸一あとがき) というわけで、2つの本のこの場面を再現してみたいと思います。引用文は大雨に遭遇したスタビング少年が、駆けだしているシーンです。 ――ところが、かけ出してからすぐに、私はなにかやわらかいものに、どんと頭をうちつけました。私は道にしりもちをつきました。私は、だれにつきあたったのだろうと顔をあげました。すると、私の目の前に、しんせつそうな顔の、ふとった小柄な人が、これも私と同じように、ぬれた道の上に、しりもちをついているのです。その人は、古ぼけたシルクハットをかぶって、小さな黒いカバンを手に持っていました。(井伏鱒二訳P27) ――いくらも行かないうちに、やわらかいものに頭をぶつけて、気づいたときには尻もちをついていました。いったい何にぶつかったのだろうと、顔をあげました。目のまえでやはり尻もちをついているのは、見るからにやさしそうな顔をした小太りの小柄な男の人でした。古ぼけたシルクハットをかぶって、手には小さな黒い鞄を持っています。(福岡伸一訳P25) 2つの訳文には、大きな差異は認められません。福岡伸一は井伏訳を尊重し、大きな手入れは避けました。そのうえで、原文に忠実に手入れをしたのです。それだけ先達の井伏鱒二の訳文が優れていたのでしょう。もちろん、井伏訳には現代にふさわしくない用語がたくさん出てきます。そのことは巻末で編集部の説明があります。どちらの訳文を選んでいただいても構いませんが、井伏鱒二訳を推薦作とさせていただきました。 ◎浮島の王様 ヒュー・ロフティングの「ドリトル先生」シリーズは、全部で12巻あります。そのなかで『ドリトル先生航海記』(岩波少年文庫、井伏鱒二訳)は2作目となります。 第1作『ドリトル先生アフリカゆき』(岩波少年文庫)では、医者だったドリトル先生がオウムのポリネシアから動物言葉を学び、獣医として活躍するにいたる経緯が書かれています。アフリカのサルの国で疫病が大流行し、ドリトル先生はサルの救助のためにアフリカに渡ります。 今回紹介する『ドリトル先生航海記』は、先に引用した少年トミー・スタビンズが語り手になっています。少年の視点からとらえていますので、ドリトル先生の表情や心の動きが手にとるようにわかります。そうした意味で、本書はシリーズを代表する作品といっても過言ではないと思います。 ドリトル先生はオウムのポリネシア、犬のジップ、猿のチーチー、アヒルのダブダブを助手にしていました。そこに9歳の少年スタビンズが加わったわけです。小学生のとき初めて本書を読んで、「桃太郎」の世界を重ねていた記憶があります。猿、鳥、犬を引き連れた桃太郎とドリトル先生が二重写しになったのだと思います。 ドリトル先生が一目置いているロング・アローが消息不明になったとの知らせが舞いこんできます。ドリトル先生一行は、偉大なる博物学者ロング・アローを探す目的で、南大西洋の浮島(クモサル島)へ向けて航海に出ます。船は途中で難破してしまいますが、一行はなんとかクモサル島へとたどり着きます。そして洞窟に閉じこめられていたロング・アローを救出します。 やがてドリトル先生は、浮島の王様に推挙されます。住人を乗せたまま、島はどんどん押し流されています。これ以上、ものがたりに触れることは控えます。楽しんでください。 ◎殺処分される馬 前記のように、本書にはたくさんの差別用語が出てきます。その点について、ロフティングが本書を執筆した時代を理解しておかなければなりません。 ――ロフティングが生まれた一九八六年は、大英帝国の最盛期、イギリスは世界中に植民地をたくさんもっていた。その時代の常識の多くは、今となっては非常識になっている。(神宮輝夫『監修:ほんとうはこんな本が読みたかった』原書房P89) 『ドリトル先生航海記』の誕生秘話について、書かれている文章があります。 ――第一次世界大戦中に従軍していたロフティングは、兵士らが傷ついたときに手厚く看護されるのに、同じ危険を冒している馬はケガをすれば処分されること知った。馬も同じように看病すべきだ、そのためには馬の言葉を話す医者がいなければ……と考えたのがドリトル先生誕生のきっかけとなった。(定松正編『イギリス・アメリカ児童文学ガイド』荒地出版社P73) 本書を堪能できたら、ぜひ読んでいただきたい一冊があります。ドリトル先生が活躍した時代のイギリスが、よく理解できます。南條竹則『ドリトル先生の英国』(文春新書130)がそれです。 (標茶六三2017.05.21) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2017年11月09日 03時29分22秒
コメント(0) | コメントを書く
[ラ・ワ行の著作者(海外)の書評] カテゴリの最新記事
|