
|
|
9.クモの仲間2クモの仲間2 1.クサグモ2.オナガグモ3.ササグモ4.トリノフンダマシをご紹介します。 1.クサグモ   「体長約12mmの亜成体」2011年7月 「体長約12mmの亜成体」2011年7月 「裏側から見た体長12mmほどの亜成体(別個体)」2011年7月 「裏側から見た体長12mmほどの亜成体(別個体)」2011年7月 「上側から見た亜成体」2011年7月 「上側から見た亜成体」2011年7月 「裏側から見たクサグモの成体」2011年7月 「裏側から見たクサグモの成体」2011年7月 「成体と脱皮殻(写真右上)」2011年7月 「成体と脱皮殻(写真右上)」2011年7月タナグモ科 全長15~17mm 北海道から九州の人家周辺などに分布 観察期間は主に6~10月 えさ 虫 繁殖 秋。晩秋に産卵し、白い卵のうを巣につるす。年内に孵化し、翌春に出てくる。 鳴き声 なし 巣 木の枝の間などに棚状の巣を作る。その奥にトンネル状の住居を作り、危険を察知するとそこを抜けて 外に逃げる。  「住居部分に入る亜成体」 「住居部分に入る亜成体」2011年7月5日、ベニカナメ「レッドロビン」の枝の間に立派なクモの棚網を見つけました。奥にあるトンネル状の 住居から出たり入ったりしていますが、葉が茂っているのであまりよく見えませんでした。翌日、窓辺の 少し出っ張ったところにさらに大きな巣を見つけました。のぞきこむと飛びかかってきたので、お腹の裏側が 丸見えです。しばらくするとクモはピョンと飛び降りて住居に頭だけ突っ込んでかたまってしまいました。 「頭隠して尻隠さず」状態でじっとしていましたが、大丈夫だと判断したらしく、再び出てきて たまにちらちらこちらを見ていました。台風後の7月20日にはベニカナメ「レッドロビン」にいたほうは 姿が見えず、窓辺のほうは脱皮して体長15mmの成体になっていました。7月26日には、 行方不明だったもう1匹も脱皮して15mmの大きさになり、元の巣にちゃんといました。地域によっては 数が減っているらしいので、ここで子孫を残してくれたらと思います。 2.オナガグモ 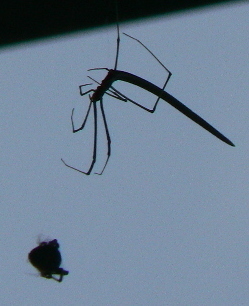 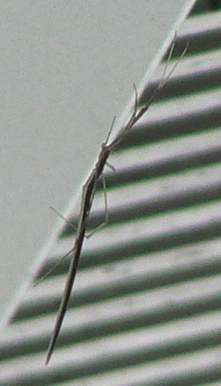  「オオヒメグモを食べる褐色型のメス」2013年7月
「オオヒメグモを食べる褐色型のメス」2013年7月 「同個体?背中側」 「同個体?背中側」 「同個体?横から」2013年6月 「同個体?横から」2013年6月ヒメグモ科 全長オス12~25mm メス20~30mm 本州から沖縄に分布 観察期間は主に5~8月 えさ クモなど 繁殖 5~9月に産卵し、細長い卵のうを巣につるす。 鳴き声 なし 巣 木の枝の間などに不規則に糸を張り、伝ってくるクモなどを捕らえる。 2013年5月22日、ベランダに出ると軒下にオオヒメグモと体長3cmちかい 褐色型のオナガグモがいました。メスのようです。どうやら、オオヒメグモがオナガグモの巣に ひっかかってしまったらしく、とうとう捕まってしまいました。しばらく動きがなかったので そのままにしておくと、翌日にはいなくなっていましたが、6月4日には網戸に同じ個体らしきオナガグモが しがみついていました。すぐにいなくなってしまいましたが、近くで元気にしているものと思います。 3.ササグモ  2013年6月 2013年6月  「卵のうを守るメス」2013年6月 「卵のうを守るメス」2013年6月   「孵化した子グモと母グモ」2013年7月 「孵化した子グモと母グモ」2013年7月ササグモ科 全長オス7~9mm メス8~11mm 本州から沖縄に分布 観察期間は主に5~8月 えさ 虫など 繁殖 7~8月に産卵し、10mmほどの丸い卵のうを葉などにくっつけメスが守る。 鳴き声 なし 巣 なし 2013年6月27日、花壇のペパーミントの花にササグモがいました。また、近くのベニカナメ「レッドロビン」の 葉には卵のうを守っているメスのササグモが見つかりました。7月1日には孵化したばかりの 子グモがいる隣の葉に母グモがいました。翌日には母グモはいなくなり、さらに翌日にはみんな いなくなってしまいました。以来、子グモたちがどうなったのか気になっています。 4.トリノフンダマシ  「メス(真上から)」 「メス(真上から)」 「同(正面から)」2014年7月 「同(正面から)」2014年7月 「同(横から)」 「同(横から)」 「同(腹側)」2014年7月 「同(腹側)」2014年7月コガネグモ科 全長オス1~2mm メス約10mm 本州から沖縄に分布 観察期間は主に6~9月 えさ 虫など 繁殖 夏の終わりに産卵し、10mmほどのしずく型の卵のうを葉などにぶら下げメスが守る。 秋には孵化して越冬する。 鳴き声 なし 巣 夜に水平円網を張る。ガなどが引っかかると横糸が切れるため、縦糸に絡まり ぶら下がって逃げられないようになっている。明け方には網を完全に片づける。 2014年7月25日、ベニカナメ「レッドロビン」の葉の裏にメスが張り付いていました。29日には 糸1本でぶら下がっていましたが、慌てて葉の裏に戻りました。 以下もご覧下さい。 クモの仲間1 ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
|