幻視(まぼろし)-春のほたる-2
幻視(まぼろし)-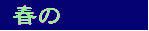 (2) (2) 
ヤヨイを助けるために、池に入ったタカオを、
芳子は風呂に入れたかった。
だが彼女も、無理強いをさせることはなかった。
今日の出来事が、亀夫の家でも話題になったが、
芳子はそれに触れることを警戒した。
狭い村では、何事につけ、言わぬことまでが
“想像力”という尾ひれを付けられて、
被害者が“悪者”にされて、広まってしまうことが多い。
義兄の家族が、そのような原因を造るとは思えないが、
用心するに越したことはない。
そう思った芳子は、
「なぁに、カツラだって悪気があってのことじゃないんだし、
こうしてヤヨイも無事だったんだし、気にしてねぇから。」
と、言葉を逃がした。
狭い村であるばかりでなく、タカオの父とカツラの父、
そして亀夫は、兄弟だった。
それだけでなく、元をたどれば、親類縁者ばかりになりそうな、
すべての出来事が筒抜けになる村だったのである。
村とはそうしたものだ、と芳子は心得ていた。
気苦労はそれなりにあるものの、その点に心を配れば、
別に暮らしにくい村ではなかった。
そう思ってきたが、亀夫のヤヨイに対する心遣いを見て、
この“過ごしやすさ”が、亀夫の庇護の元で作り出されていることに、
今更のように気付かされた。
口の端に噂を立てることが好きな村人が、
余所者の芳子に対して、特に不快を感じさせないのは、
夫がこの村で育ったからというのではなく、
“怖い人”と思われている亀夫が、それとなく目を光らせてくれていたからだ。
亀夫が親切に接している家族に対して、周囲の村人が、
意地悪をすることは憚られたのだ。
亀夫は“怖い人”であるだけでなく、村人にとって
“相談相手になってくれるありがたい人”でもあった。
そのことに気付いてからも、芳子は普段通りに振る舞った。
亀夫の庇護の心を、甘んじて受けることにしたのだ。
亀夫は、自分の末弟に嫁いでくれた“身分違い”の義妹を、
非常にありがたく思っていた。
戦後のことで男の数が不足しているからといっても、
普通ならこんな田舎に、嫁に来てくれるような人(女性)ではない。
その大切な義弟と弟は、何かにつけて口論をする。
口論の原因は、弟の神経質な性格によるところが大きい。
感謝こそすれども、田舎暮らしに慣れない妻に、
不満ばかりをぶつけるものではあるまいに。
そのような思いから、裏表無く、芳子を庇ったのである。
芳子のこのような田舎暮らしは、10年ほど続いた。
芳子の一生から見れば、僅かに10年であった。
それまでの20数年間は、地方の中核都市で生まれ育って、
この田舎暮らしの10年を過ごしたあとは、
また都会に引っ越して、25年ほどを過ごしている。
このことから、彼女にとってのこの“田舎”は、
僅かな期間の仮住まいのような意味合いであったはずなのである。
小屋(タカオの家)の周りは、
朝露の潤いに包まれていた。
山の端を駆け上った朝陽が、梢の隙間を通して、
光芒を投げかけようとしている。
戸口(玄関)の板戸が、そっと曳き開けられた。
芳子は、まだ眠っているらしい。
ゴム長靴を履いたタカオが、夕べ捕まえた“ヨルトンボ”の羽を持って、
戸口の隙間から、抜け出した。
ヨルトンボは、芳子の言いつけ(命令)で、
蚊帳の中で一夜を生き長らえたらしい。
部屋の四隅から下げられた蚊帳の中には、
注意深く出入りをしても、蚊が入り込むことが多い。
タカオは、その蚊をヨルトンボに食わせようと思ったようだ。
ヨルトンボが、その役目を果たしてくれたかどうかは、解らない。
ただ、芳子が蚊帳に入る前に、タカオとヤヨイは眠り込んでいた。
眠っている子供たちを横目に、芳子がひとしきり、
『ぷ~ん』というあの独特の音を頼りに、
蚊を追って奮闘したことは、子供たちは知らない。
タカオはまず、自宅のすぐ上にある小さな池に向かった。
簡単に造られた階段の小径を上ると、水草に覆われて、
僅かに顔を覗かせる水面が、空の明るさを写して静まっていた。
昨日の騒動が、遙かな過去の出来事のような静けさである。
水面では、ミズスマシがくるりくるりと、輪を描いている。
タカオの目標物は、ミズスマシではないようだった。
ヨルトンボは、タカオの指先から解放されて、
夜明けの空に向かって、一直線に上昇していった。
タカオが水際を歩くと、ドミノ倒しのように、
次々に蛙が池に飛び込んだ。
それらの中には、『ゲコッ!』と声を出して、
思いっきりの大ジャンプを試みるヤツもいる。
だがタカオの関心は、そんなところにはなかった。
池の端の密生している菖蒲の葉を、一心に見つめている。
その菖蒲の葉には、オニヤンマのヤゴたちが、しがみついていた。
数えてみると、20匹以上はいそうだ。
池は、昨日にヤヨイが落ちて、タカオも濡れ鼠になったところだ。
再び、池に落ちるのはいやだ。
朝露に濡れる足下を、慎重に踏みしめて、
タカオは、水辺の花菖蒲の群落に近づいた。
斜面になった土手は、油断をすると、
池に滑り込みそうになる。
そんな場所で、羽化を始めたヤゴを、
飽きることなく手にとって、衣服に移し替えた。
その数が十匹を超えたあたりで、タカオは満足したようだった。
ヤゴを衣服にとまらせたままで、朝の光を浴びて、
その羽化を待っている。
オニヤンマたちは、捕らえられたからといって、
羽化を中止することはできない。
思い思いの速度で羽化が進み、中にはタカオのシャツの上で、
羽を伸ばし始めるものもいた。
トンボの羽化直後の羽は、水を含んで重くなっている。
その状態の時に手を触れれば、羽が正常に広がらずに、
奇形のような状態になる。
それを知っているタカオは、トンボの羽が充分に伸びて、
光をきれいに反射するまで、ゆっくりと待った。
ヤンマは、羽を伸ばすと、抜け殻になったヤゴから離れて、
徐々に衣服の上の方に移動を始めた。
タカオはそのヤンマを指に移して、
瑞々しく光る赤子のようなヤンマを、愛おしそうに見つめている。
そのようにして、ヤンマの羽化を次々に見ているうちに、
羽化を終えた順番に、心もとない飛び方で、
タカオのシャツから天空へと舞い上がっていった。
テレビゲームなどというレジャーのない世界に住む子供は、
羽化したトンボの羽のきらめきを見るだけでも、
大きな楽しみになったのだ。
トンボを捕らえて、それをどうにかしようというのではない。
ただその変化を見るのが、楽しみなのだ。
オニヤンマのヤゴは、池を這い出て、
小径を隔てたネギ畑にまで入り込み、
そのネギの露の玉が付いた先端で、羽化するものもいた。
ネギ畑は、昨夜に狐が鳴いていた場所だ。
狐は、タカオの家で飼っている鶏を、襲いに来たのだろう。
タカオの父が、狐の襲撃を予想して、
丈夫な金網で鶏小屋を補強していたので、
被害を食い止められたのだった。
狐の鳴き声が、タカオの寝所まで聞こえて、
落ち着かない夜を過ごした。
その狐は、ネギ畑に足跡だけを残して去った。
タカオは、夕闇の中で瞳を怪しく輝かせる狐の姿を思い出して、
小さく身震いをした。
人に対しては、危害のない狐だったが、
本能的に、身の毛が逆立つ気分になったのだ。
ネギ畑に残された足跡を見て、狐が昨夜も鶏小屋を窺っていた様子が想像できた。
だが、朝になれば、狐どもはその姿を見せることはない。
子供がひとりで野山を歩いても、彼らを畏れる必要は、全くなかったのだ。
タカオは、狐の存在をすぐに忘れた。
瑞々しい輝きを放ち、広げた羽を小刻みに震わせて、
大空に飛び立つ準備をするヤンマたちを、
飽くことなく見続けていた。
オニヤンマは、タカオの胸元を離れて、
1匹、また1匹と、フイッと空へ舞い上がっていった。
上空に達すると、その羽に朝陽を受けて、
いっそう美しい煌めきをタカオの目に届けてくれた。
彼の朝の日課は、そろそろ次の段階に移らなければならなかった。
通学時間が迫っていたのだ。
帰宅した彼を、芳子が並べてくれた朝餉(単なる朝食)が待っていた。
漆塗りの黒く丸いちゃぶ台を、家族3人が輪になって、
つましい朝食をとっていた。
時折、忘れ物を思い出したかのように、
芳子が席を立って、隣接した台所で、
軽やかな包丁の音を響かせる。
たちまちのうちに、きれいに輪切りにされた胡瓜の漬け物が、
食卓に追加された。
タカオは、村の子供たちと誘い合って、
片道40分ほどの道を歩いて、小学校に通っていた。
道中が長いということは、子供にとっての“遊び場”も豊富だということである。
放課後の帰宅時に、タカオは思いもかけない場所に入り込んで、
忘れ物をすることが、たびたびあった。
忘れ物に気付くのは、帰宅後に芳子から指摘されてから、
というのが、いつものパターンだった。
傘1本、風呂敷1枚も、貴重品である時代のこと。
芳子に付き添われて、タカオが通ったあとを、
学校まで逆に辿ることも、珍しくはなかった。
林の奥深くに入り込んで、百合の根を掘って、
タカオがそれを囓りながら帰っていたというのも、
このような“忘れ物の探索”で、初めて芳子が知ったことだった。
芳子にとって、子供の行動を知る貴重な時間ではあったが、
無駄な時間だとも思われた。
野良仕事や家事で疲れた上に、子供の捜し物にまで、
付き合わなければならない。
『身体がいくつあっても足りないぞ。』
これが、芳子の口癖になった時期もあった。
タカオのそんな思い出を、私のシンクロした意識に送り込まれて、
『なるほどねぇ。』と感じているうちに、
タカオは既に、学校から帰宅していた。
午前中の早い時間に、学校は終わっていたらしい。
タカオは、妹のヤヨイと遊んでいる。
芳子の姿が見えない。野良仕事に出ている様子もない。
芳子は子供たちに留守を任せて、隣の市へ買い物に出かけたようだった。
タカオの帰宅を待って出かけたのだろうから、
彼女の帰宅も、遅くなるはずだった。
タカオは、我が家が見下ろせる“稲場(イナバ)”に妹のヤヨイを誘って、
草花を摘んで遊んでやっていた。
タンポポの茎をちぎって、簡単な笛にして口に含んで鳴らすと、
その音でヤヨイは喜んだ。
同じ“タンポポの笛”をほしがるヤヨイに、タカオはまたひとつ、
笛を造って渡した。
タンポポの茎の長さや太さによって、音色が微妙に違った。
二人は、その微妙な音色の違いを楽しんで、
そしてまた、口に広がるほろ苦い味を楽しみながら、
ひとときを過ごしていた。
タンポポの笛に飽きると、二人の子供は、
 シロツメクサの花を摘み始めた。
シロツメクサの花を摘み始めた。
中には、時折アカツメクサの花も、混じることがあった。
二人の両手に、持ちきれないほどの花が摘まれるのは、
造作のないことだった。
摘んだ花を、タカオが長く編み始めた。
母の芳子に教わった“首飾り”を編んでいるらしい。
やがてそれが編み終わると、満足そうに花の輪を眺めている。
シロツメクサの所々に織り込まれたアカツメクサの色 が、 が、
絶好のアクセントになっている。
できあがった“首飾り”を、ヤヨイの首に掛けてやった。
ヤヨイは、「ひやっ!」と声を上げて、首をすくめた。
“首飾り”がひんやりとして、ちょっと驚いたのだ。
タカオも、自分で編んだ首飾りを、首に掛けた。
初夏の汗ばんだからだ身体に、シロツメクサの冷たさが、
心地よかった。
こんな他愛のない遊びでも、子供二人が時間を費やすには、
充分だったようだ。
その子供たちの背に、夕暮れの雰囲気が迫っていた。
どこからともなく、竈から立ち上る煙の匂いが漂ってきて、
風呂を焚く薪割りの音なども、伝わってきた。
カラスが群れをなして、鎮守の山(鎮守様と呼んでいた)に、
帰り始めていた。
二人の頬を撫でる微風も、潤いと冷たさを含み始めていた。
夕日が、かなり傾いている。
「兄ちゃん、母ちゃんはいつ帰ってくるんだ?」
「買い物に行ったんだから、もうちっとで帰ってくるさ。待ってろ。」
「うん。でも・・・母ちゃんはまだかなぁ。」
「何か、食うか?」
「うん。腹減った。」
「よぉし! 任せろ。」
家に帰れば、飯釜にこびりついた“お焦げ”くらいはあるはずだった。
母が残しておいてくれたおかずも、何かしらはあるはずだった。
だがタカオは、この場所(稲場)を、離れたくなかった。
やや谷間になっている我が家よりも、小高い丘の稲場の方が、
ずっと先の丘を越えて帰ってくる母の姿を、
いち早く見られるからだった。
ヤヨイに安請け合いをしたタカオが、手近なところで調達した食べ物は、
畑のトマトだった。
タカオの家は、父の徳洋が、僅かばかりの農地を兄から借りて、
自給の足しにしていた。
タカオには、どの畑が自分の家の物かなど、知る由もなかった。
つまり、このときに調達したトマトが、
どこの誰の家の作物か、見当も付かなかった。
ただ朧気に、「亀夫伯父さんの畑ではないか?」と感じたにすぎない。
カツラの父、定次伯父さんの畑なら、あとで知られたときに、
母からお目玉を食うはずだったが、そんなことは、
気にとめる様子もなかった。
ほぼ2分の1の確率で、どちらかの伯父さんの畑なのだから、
亀夫伯父さんの畑である可能性も、強かったのである。
それよりも、タカオはそんなことには無頓着だったらしい。
蒼く瑞々しいトマトの香りが、タカオとヤヨイの口中に広がった。
赤く熟したトマトは、夕日を映して、いっそう赤味を増して、
太陽の熱を吸収して、ほんのりと温かかった。
トマトは、2つ、3つと、タカオの胃袋に収まった。
幼いヤヨイの胃袋は、2個のトマトを食べ終えたところで、
不満を訴えなくなっていた。
「母ちゃん、まだ帰ってこないのか?」
ヤヨイの言葉は、満腹感とは別に、そのところに戻ってきた。
夕日は、いよいよ傾きかけていた。
その赤い縁を、山の端にかけようとしている。
「まだ帰って来ねぇなぁ・・・。」
風が、冷たさを増している。
二人は、稲場で母の帰りを待ちきれず、自宅に帰り始めた。
自宅に入ると、タカオはヤヨイに絵本を渡した。
“舌切り雀”や“一寸法師”の話が載っている、
ヤヨイのお気に入りの絵本だ。
寝る前に、母の芳子が、何度も読んでくれる絵本だった。
ひとりでその絵本を読んでいるうちに、ヤヨイは静かに寝入ってしまった。
タカオは、ヤヨイが蚊に食われないようにと、
小さな身体を引きずって、蚊帳の中に押し込んだ。
ヤヨイが寝静まると、家の中には静けさだけが、満ちているようだった。
板戸(雨戸)を引いて、心張り棒をかけて、
所在なく家の中で母の帰りを待つと、初夏の暖かさが嘘のように、
寒々とした空気に、押しつぶされそうだった。
母の帰りを待ちきれなくなって、タカオは戸口から外を窺った。
庭に出て、稲場を越える小径を眺めていた。
「母ちゃんは、まだ帰んねぇのか? 家に入ってろよ。」
野良仕事から引き上げてきた亀夫伯父さんが、通りがかりに声をかけてくれた。
人恋しくなっていたのだろうか。
タカオは、一瞬、胸が詰まるような気分になった。
「うん。大丈夫だ、ここで待ってみっから。」
ちょっとだけ、涙声になっていたのだろうか。
亀夫伯父さんが、さらに慰めの言葉をかけてくれた。
「母ちゃんは、買い物だろ? もうすぐ帰って来っから、心配すんな。
龍夫(亀夫の息子)も家にいるはずだから、一緒に遊ぶか?」
「ううん、母ちゃんが心配すっから、家で待つ。」
「そぉか。いつでも遊びに来いよ。」
「うん。」
タカオは、稲場の方から目を離さずに、亀夫に返事をした。
亀夫が帰って、しばらく時間が過ぎても、芳子は帰ってこなかった。
夕日は既に沈みきって、空の色は、群青を濃くしていた。
帰りそびれたカラスが、ねぐらを目指して、あわただしく飛び去っていく。
池の蛙が、賑やかに鳴き始めた。
稲場の丘の端が、空の闇に溶け込もうとしていた。
その稲場の端に、小さな人影が、徐々に浮かび上がった。
背負子にいっぱいの荷物を入れて、
両手にも買い物の荷物を重そうに提げた、芳子の姿だった。
ヨシオは、その影に向かって駈けだしていた。
桑畑の、生い茂る葉をかき分けて、母の元に走った。
「母ちゃん、お帰り! 荷物、俺が持つから。」
「留守番、有り難うな。ヤヨイはどうしてる?」
「眠っちまった。」
「そうか。帰ったら急いで、夕餉の支度をすっからな。」
タカオは、畑のトマトを盗み食いしたことは、話さなかった。
私には、このときにも芳子の姿が見えなかった。
いや、見えてはいたのだが、暗闇に紛れて、
その表情が、確認できなかったのだ。
いつになったら、彼女の表情を、見ることができるのだろうか。
その時、影になった芳子の周囲で、黄色い光が“ふうわり”と舞った。
一瞬の出来事だった。
優しく瞬いた光は、そのまま闇の中に、“すうーっ”と消えた。
柔らかくスゥイングするように、軽やかな弧を描いた黄色い光は、
どこに消えたのだろうか。
目の錯覚だったのだろうか。
“煙”のような幻に誘われて、こんな光景の中に入り込んだ私の視覚には、
何が見えても、不思議なことではあるまい。
だが、その“もの”の姿を確認したくて、彼女(芳子)の周囲に、目を凝らした。
確かに、彼女の身体の周囲で、その光は、軽やかな舞を見せたのだ。
そして、その光は、一度だけの瞬きを見せて、ツイッと消えてしまった。
まるで、芳子の身体に吸い込まれたかのように。
芳子は、行動が楽なように、いつも筒袖の着物を着ていた。
その着物は、夏は涼しくて、冬になれば、
筒袖の中に手を引っ込めることで、寒さを凌ぐことができた。
彼女にとっては、便利この上ない“万能衣服”だったのである。
一瞬の瞬きを見せた光は、彼女のその“筒袖”の中にでも、
吸い込まれたとしか思えなかった。
あの“光”が、同じサイクルで瞬けば、
薄暮から闇へ向かい始めた山里の中で、見失うことはないはずだ。
彼女の“意志”が、あの光を袂に吸い寄せたのだろうか。
-動きを速めた“走馬燈”-
芳子とタカオは、ヤヨイが寝入っている家の戸口をそっと引いて、
中に滑り込んでいった。
部屋にひとつだけ灯されていた電気に、台所の薄暗い電気が追加されて、
多少は家の中が明るくなったのだろうか。
だが何よりも、芳子が帰宅したことで、
家全体にぬくもりが加わった。
板戸(雨戸)の節穴から漏れる白熱灯の光も、
家庭のぬくもりを、初夏の山里に放出しているようだった。
そしてやがて、その節穴からの光も消えた。
柔らかな朝の日射しが、小さな小屋を斜めに照らし始めた。
柿の木には、取り忘れられた熟柿が、真っ赤に色づいて、
風に揺られている。
ざわざわと、ゴウゴウと強い音を鳴らして、
風が吹き荒れている。
『台風か?』
そう思わせるような、強風だった。
だが、台風にしては、風が乾いている。
朝の空が澄んで、高い。空気が冷たい。
周囲の山が、うねるようにざわめいている。
もしかしたら・・・いつの間にか秋になってしまったのか?
これ方訪れるはずの、蝉時雨の夏はどこに行ったのだ?
芹摘みをするタカオの姿が見られるはずだった、
家族で、狭い庭先で線香花火を囲んで楽しむ姿が見られるはずだった、
激しい雷を避けて、蚊帳の中で昼寝をする子供たちの姿が
見られるはずだった、
あの夏の光景は、どこに消えてしまったのか。
それとも、これは“季節をジャンプした”のではなくて、
過去の季節に戻ったのか?
兎に角、一晩が過ぎたら、季節は秋になっていたようだ。
タカオは、早起きをしなくなっていた。
蝉もトンボも、クワガタやカブトムシも、それを捕りに行くには、
すっかり季節が変わっていたのだ。
その代わりに、多少遅い時間になってから、彼は近くの山に入っていった。
彼は、大きな木の下に行っては、丹念に地面を探っている。
ズックの靴先で、何かを踏みつけている。
落ちている栗のイガを見つけては、それを靴先で不器用に剥いているのだ。
そのようにして剥いたイガの中から出てくる栗は、多くが虫食いだった。
まともな栗は、彼よりも早く山に入った、村の大人たちに拾われていたのだ。
だがそれでも、強い秋風は、大人たちが栗を拾っていったあとでも、
吹き続けている。
新たに、高い梢からこぼれ落ちた実の中には、
虫に食われていないものもあった。
タカオは、どうにかこうにか、そのような栗を拾い集めて、
小さな袋に貯め込んで、家に持ち帰った。
「母ちゃん、これ。今日はこれしか拾えなかったよ。」
「これだけあれば沢山だ。虫が湧かないうちに、茹でちまおうね。」
「うん。」
茹でる栗と、皮を剥いてご飯に炊き込む栗との選別を、
芳子が何を基準にして分けているのか、タカオには理解できなかった。
だが芳子は、袋から取り出した山栗を、ひとつずつ選別して、
炊き込みご飯に使う栗は、別の小山に分けていった。
茹でる栗は、そのまま鍋に放り込まれた。
そして、茹で上がった栗の中には、それでも栗虫が、
たくさん潜んでいた。
彼らは、その虫を避けながら、虫食いになっていないところを選んで、
食べていた。
炊き込みご飯用の栗は、芳子とタカオが、
爪先を渋で黒く染めながら、接木小刀で、皮を剥いた。
皮を剥いている時にも、栗の中から、そいつ(栗虫)が、
白い顔を覗かせた。
栗虫の姿が見えれば、その栗は、廃棄された。
炊きあがった栗ご飯は、芳子によって、神棚と仏壇に、まず供えられた。
いつもの日課に過ぎない芳子の行動だったが、
タカオはちょっぴり誇らしげな顔で、神仏に手を合わせている。
自分が拾ってきた栗が、神棚に供えられているというだけで、
何となく嬉しくなったのだろうが、彼は栗拾いが好きではなさそうだった。
苦労が多く、事後の作業が面倒なわりには、
歩留まりが良くなかったからだろう。
彼が栗拾いに出かけるのには、もうひとつの理由がありそうだった。
栗拾いよりも、時にはそちらの方に、興味が奪われるようにも感じられた。
山には、紫に熟して、パックリと大きな口を開けて、
白い実を晒したアケビが、時折見つけられたのである。
これももちろん、先乗りした大人たちが、めぼしいところは、
ほとんど取り尽くしていた。
だが、まだ割れていないアケビも、取り残されていることがあった。
大人の目でも、すべてを取り尽くすことはできないようで、
タカオの低い視線でなければ見逃されるアケビも、
残っていたのである。
樹上の高い場所に残されたアケビは、タカオの手には負えなかった。
木の幹が太すぎて、タカオが登るには、相手が悪かった。
それでも、見逃されたアケビを、3つ、4つともぎ取って、
持ち帰るときがあったようだ。
この日も、栗の袋に、3個ほどのアケビが紛れ込んでいた。
「お? タカオ、アケビもあるな?」
芳子にアケビを見つけられたタカオは、自慢げに鼻を膨らませた。
「うん。もっとあったんだけど、あとは高くて届かなかったんだ。」
「危ないから、無理すんなよ。」
「解ってるって。」
「このアケビは、みんなで食っても良いのか?」
「うん。みんなで。」
芳子は、アケビの実を両手で包み込むと、軽くポンと割った。
中から、輝くような白い実(種)が、顔を見せた。
タカオも同じように、小さな手にアケビを持って、両手でポンと割った。
甘い実を頬張って、口いっぱいに残った種を、
縁側から庭先に、ぷぅーっと吐き飛ばした。
ヤヨイも、芳子の指先から、小さく千切ったアケビを、
口に含ませてもらっている。
秋には、夏とは違った楽しみが、あったのである。
もう熟すことがないイチジクの小さな実を、
芳子はたくさん摘んで、砂糖でぐつぐつと煮ていた。
いわゆるイチジクの甘露煮だろうか。
これが、冬に向けて、子供たちのおやつになるのだ。
熟したイチジクは、そのまま食べるが、未熟な実は、
摘まずに放置すれば、霜に焼かれて黒くなって腐ってしまう。
その利用価値がないような実を、フルに活用していたのだ。
朝のひとときは、たちまちのうちに過ぎ去った。
私は、何を、どのように見ていたのだろうか。
ふと気が付くと、彼らの姿が、かき消したように、見えなくなっていた。
何度も経験していることなので、
この“消滅現象”には、驚かなくなっていた。
村全体が、シィーンと静まりかえっている。
人の気配がない。
私は、板戸が引かれた、暗い家に足を踏み入れた。
土間に靴を脱いで、筵が敷かれた板の間に昇った。
他人の家? だが、私には、この行動が許されると感じていた。
足を踏み入れた家の中は、床下や部屋の隅のあちらこちらで、
コオロギの鳴き声が、寂しく湧き起こっていた。
外の空気に比べて、一層、秋の気配が濃くなっているようだ。
家の中いっぱいに、土間のひんやりとした土の匂いが、広がっている。
長年、芳子がここで立ち働いて、踏み固められた土間だった。
岩のように、粘土を踏み固めたように、すべすべとした土間だったが、
そこから土の匂いが立ち上っているのである。
これは、この家族の、生活の匂いだろうか。
小さく切られた囲炉裏の傍らに、
丸く小さな飯台(=ちゃぶだい)が、置かれていた。
いつもは、足をたたんで壁に立てかけてある飯台が、
広げられてあった。
その飯台には、食卓用の可愛い蚊帳が、そっと掛けられている。
蚊帳の中に、伏せられた茶碗と、胡瓜や茄子の味噌漬けらしいおかずが、
透けて見えている。
この蚊帳の中の食べ物は、誰を待つのだろうか。
芳子が、帰宅する誰かのために、準備をして出かけたのだろう。
その彼女は、どこへ?
タカオが学校に行っている隙に、ヤヨイをおんぶして、
隣町に買い物にでも出かけたのだろう。
近くの田畑に、人の気配はなかった。
村人の誰の気配も感じられなかったのは不思議なことだが、
芳子の行方は、隣町のデパートだろうと、私は勝手に見当を付けていた。
なぜ、タカオが留守の時に?
彼女は、タカオを出し抜いたわけではない。
ヤヨイを手元に置いて買い物をした方が、手間が省けたからだ。
彼女は、タカオにヤヨイの世話を任せて、買い物に没頭したときがあった。
その時に、母の帰りを待ちきれなくなったヤヨイがぐずりだし、
タカオが芳子を捜し求めて、デパート内を駆け回ったという“事件”があった。
ヤヨイに「動くなよ。」と言い聞かせて、タカオがヤヨイの元を離れた。
暫くの間、ヤヨイはその言いつけを守っていたが、
タカオの姿が視界から消えると、ヤヨイの心に不安が広がった。
そこに、芳子と同じような着物を着た夫人が、通りかかった。
ヤヨイの視線は、夫人の顔を確認できない。
着物の雰囲気を頼りにして、その“姿”について行ってしまった。
大売り出しのセール中で、デパート内は混雑していた。
その中で、芳子とタカオは、ヤヨイを捜し回る羽目に陥ったのだった。
幸いにも、ヤヨイは同じ階から移動していなかったので、
比較的簡単に見つけられた。
だがこの出来事に懲りて、家族で揃って買い物に出かける機会は、
減少していたのだ。
タカオは『同じ失敗はしない』と言うが、
芳子の信頼が薄れていたことは、間違いなさそうだった。
そのようなことがあるので、私は彼女が、
彼が帰宅する前に、買い物に出かけたのだろうと、
予測したのである。
多分、タカオもひとりで食事をして、
勝手に遊びに出かける生活に、慣れているのだろう。
板戸の節穴から漏れる光が、外界の様子を、
障子に逆さの景色にして映し出していた。
風に揺れる柿の葉が、障子に淡い色を滲ませる。
竈が据えられた薄暗い台所の隅で、カネタタキの声がする。
板の戸で仕切られた向こう側には、今も蚊帳が吊られたままの、
家族の部屋があるのだろうか。
その区切りとなる部屋の鴨居の上に、柱時計が掛けられている。
静まりかえった部屋に、振り子の音が、カチン・・・コチンと、
規則正しく広がっている。
まるで、生きている“もの”は、彼だけのような空間になっている。
部屋の隅に、弱い光を一身に集めて、健気に光る小さな玉が転がっている。
白く光る“それ”は、真珠のような輝きを、私の目に向けて放った。
家(=小屋)から出ようとしていた私の足は、その“もの”に引き寄せられて、
部屋の隅に戻らされていた。
真珠かと思ったその輝くものは、拾い上げてみると、
真珠に似せたガラス玉だった。
今では、子供のおもちゃとして、“ビーズ”というような名前で、
売られているものに似ている。
なぜこんなものが、ここにあるのだろうか。
芳子の掃除が雑だったから?
そうではなさそうだ。
ガラス玉が、その生い立ちを、私に教えてくれた。
この家の主、芳子の夫である八郎は、仕事先をよく変えた。
ある日突然、早い時間に帰宅したかと思うと、
「今日、会社を辞めてきたぞ。」
そう芳子に告げて、翌日から農作業を始めながら、次の仕事を探した。
最初の“事件”の時には、芳子は驚いた。
だがその次になると、その間隔が短いだけに、
「ああ、またか。」
と思い、驚かなくなっていた。
そのような“無職時代”に八郎が始めた内職が、
“模造真珠造り”だったのである。
小さい部屋にガラス棒を置いて、機械でそれを丸く膨らませて、
糸を通す穴を開けたガラス玉を、ひとつずつ丹念に造り出すのである。
喧嘩っ速い八郎だったが、このように精魂込めて何かを造るような仕事が、
嫌いではなかった。
慣れるまでに時間はかかったが、納品の評判は悪くなかった。
だがそれというのも、八郎の製品に対するこだわりが、
完成度を高めていたに過ぎなかった。
品物のできは悪くなかったが、それは納品に限ってのこと。
不良品の数は、納品数の数倍に達した。
決して歩留まりの良い仕事ではなかった。
爪に火を灯すような生活をしても、将来が見通せる仕事ではなかった。
だがそれでも、芳子が愚痴をこぼすことはなかった。
彼女は、夫が仕事を探してきて、家族の生活のために、
何とかしようと努力をしている姿を、尊敬して、信頼していたのである。
彼女が漏らす愚痴といえば、
『あんな仕事を、業者に騙されて引き受けさせられて。』
という程度だった。
それでも充分に愚痴になっているではないか、と言えなくもないが、
その愚痴は、八郎に向けられたものではなかった。
模造真珠造りは、1年も続いただろうか。
出来損ないをもらって遊ぶ近所の子供たちには好評だったわけだが、
それでは生活ができない。
八郎がこの仕事に見切りを付けたのは、次の就職先が決まったからだった。
八郎の新しい仕事は、海外出張が多かった。
特殊な資格を獲得した彼は、就職先を選べる立場になった。
そこで選んだのが、給料の条件がよい“海外出張”の多い仕事だった。
私が、『芳子の夫は残業なのか、出張なのか。』と思った疑問が、
模造真珠からの“語りかけ”で、解けた。
彼女の夫は、短いときでも数ヶ月は、海外出張のために家を空けていた。
模造真珠を造っていた彼の作業場は、彼の小さい書斎に改造されて、
はめ込みの机と、電球を組み込まれた部屋になった。
そこで彼は、模造真珠造りのあとで、
深夜まで、資格試験のための勉強を続けたのだ。
今はその主人は、海外出張だそうだが、前の仕事(模造真珠造り)の名残が、
小部屋の隅から、転がり出ることがあるのだ。
私がその1粒に出会って、この家の事情を、
多少詳しく教えられた、というわけである。
まぁ、それを知ったからと言って、何かが面白いというわけでもないが、
どうせ、所在ない時間の経過に入り込んでいるのである。
“ついでの話”として、ガラス玉の話に、暫くの間、意識を傾けた。
私が、ある程度は“いきさつ”について意識を傾けると解ったからだろうか。
飯台のヤツまでが、何かを語りかけてきそうになった。
八郎が留守にしている間は、芳子が欠かさずに、
飯台の八郎が座るべき場所に“陰膳”を供えて、
夫の無事を祈っている、というのである。
確かに、八郎が生きていた時代は、海外旅行といえば、
場合によっては“命がけ”。
時によっては、単なる海外旅行でも、“永久の別れ”を考慮させられたらしい。
そんな時代に、時には数年間も、海外を転々と動き回るのである。
“陰膳”で無事を祈る芳子の気持ちが、理解できないことはない。
でも飯台のそんな語りかけまでを、丁寧に受け取っていたのでは、
この片田舎に、何年居候しても、際限がない。
ほどほどのところで“語りかけ”を振り切って、
私は小屋(家)の外に出た。
夏を吹き飛ばした、秋の空が高い。
澄み切った秋空を、アキアカネの大群が、埋め尽くしている。
その中に、白く小さいものが、漂っていた。
まるで風に吹かれた、雪の舞を見せられるようだ。
その数は、多くはないが、少なくもない。
少なくはないということは、これから来る冬は、
それ相応の積雪がある、という知らせでもある。
その“心細げに漂う白い綿毛”は、雪の便りを運ぶ使者であると、
この地方では言い伝えられている。
奇妙な浮遊物だった。
私は、暖かい地方で育って、この生き物を、
滅多に見ることがない。
この地方では、“雪虫”と呼ぶらしい。
井上靖の小説には、“しろばんば”として登場する。
呼び名は、地方によって異なるようだ。
まるで、得体が知れない生き物であることを記すように。
ふと気付くと、タカオが稲場とは逆の方に、駈けていく。
私が雪虫に気をとられている間に、タカオが食事を済ませて、
母を出迎えに、どこかに駈けていくところかと、思われた。
私は、どれほどの時間、アキアカネと雪虫に、見とれていたのだろう。
タカオが食事を済ませて、もしかしたらひと遊びも済ませて、
夕方になって、母を迎えに行く時間になっていたのだ。
時間の経つのが速いのか、私が、ぼんやりとしていたのか。
タカオは、いつもの稲場とは逆の方に向かっている。
この日の芳子は、汽車で買い物に行く隣の市ではなく、
義姉が住んでいて、一通りの買い物が済ませられる隣町に、
出かけたのだろう。
タカオは、大きな柿の木が聳えて、その根元には古い墓石が、
いくつも転がる村の墓地に向かっていた。
そこからは、麓を流れる小川と、その小川に沿ってうねる小径が、
一望できた。
その麓の小川や田畑も、タカオの遊び場のテリトリーに入っていた。
小川の傍らに松の木があって、『一本松』と呼ばれている。
一本松の横に、小川を渡る板の橋が架けられている。
簡素な橋で、台風などの出水時には、簡単に流失し、冠水した。
だがこの日は、穏やかな天気に恵まれて、
小川の水量も可愛らしいほどに少なくて、優しく夕焼けを映していた。
その小橋を、芳子らしい姿が、渡りかけていた。
タカオがいる丘の上から、橋までの距離は200mほどだろうか。
タカオは、芳子に向かって叫んだ。
「かぁちゃ~ん、お帰り~!」
橋の上で、タカオを見上げた人影が、買い物の荷物を下ろして、
手を挙げた。
タカオの声が、届いたようだ。
耳鳴りがするほど、静まりかえった村である。
200mほどの距離なら、確実に声が届くのである。
芳子の背中で、ヤヨイが叫んでいる。
「兄ちゃん、ただいまぁ~!」
見下ろす田畑が、黄金色に染まり始めている。
すっかり、秋が深まってしまった。
秋が深まってしまった・・・?
うだるような夏は、いつの間に通り過ぎたのだ?
通り過ぎたと言うよりも、まるでそこを一瞬でジャンプしたように、
秋に入ってしまっているではないか。
夏休みの間、タカオは“宿題”の一環として、
イナゴ捕りに精を出して、その収穫を学校に持ち寄ったりしたのではなかったのか。
そのイナゴを集める袋は、芳子がタオルを縫い合わせて作ってくれた。
そのタオルで作った袋の口には、亀夫伯父さんが、
息子たちの“道具”を作るついでに、タカオの分も作ってくれた、
竹を輪切りにした“投げ入れ口”が取り付けられていたはずだ。
そんな出来事をも、すべてを飛ばして、秋本番というわけか。
-季節の終章-
ふと顔を上げると、乾いた空気が、肌に突き刺さった。
秋までが一足飛びに吹き飛ばされて、冬模様が押し寄せていた。
秋よりもさらに深い空に、掃いたような雲が流れている。
その色は、雪を含んでいる雲だった。
雲の端から、雪がこぼれ出て、掃いたように薄れた色合いを見せているのだ。
だがまだ、雪にはなるまい。
そう思っているところに、白いものが一気に吹き飛ばされてきた。
雪虫の大群が、舞い飛んでいるような様だった。
空は青い。
雪雲は遠い。
だが、白い“もの”は、容赦なく吹き付けてくる。
北風が冷たい。
“風花”(かざはな)が、空の色を変えるほどに、北風に乗って舞ってきたのだ。
山は、すっかり冬模様らしい。
芳子たちの家族にとっては、長く辛い冬の始まりだった。
いや、タカオにとっては、ほかのシーズンとは違った、
別の楽しみが待っている季節だったかも知れない。
しかし、少なくとも芳子にとっては、楽しい季節であったはずはない。
子供たちは、シモヤケに悩まされて、芳子はヒビとアカギレに悩まされる。
井戸水を暖める暇もなく、氷を割って水仕事をする芳子の手は、
治療薬が追いつかないほど、過酷な条件を強いられるのだ。
タカオは、鼻水をこすって、それが付いた手の甲から、シモヤケが始まった。
ヤヨイは、風に晒される耳たぶから、シモヤケが始まった。
普段からリンゴのように赤く、ふっくらと膨らんだヤヨイの頬は、
冬の風に吹かれて、さらに赤味を増して、
その頬までが、シモヤケになる。
芳子は、自分の治療を後回しにしても、子供たちのシモヤケを、
まず治してやろうとした。
だが、毎日、外で遊び回る子供たちのシモヤケやアカギレは、
治療が追いつけるものではなかった。
シモヤケとヒビ、アカギレが終わるのは、春の訪れを待つより、
仕方がなかったのである。
だからといって、治療を放棄すれば、傷が悪化する。
ヒビは足にもその傷を広げて、足袋を履くときに、踵が引っかかった。
タカオの足袋の爪がとれたと言っては、その繕いをするのだが、
ヒビ切れの指先では、針に糸を通すことも、一仕事だった。
このような冬が、11月から約半年近くも続くのである。
家庭を預かる芳子にとって、楽しい季節のはずがなかった。
どこかに買い物に出かけるにしても、降り積もった雪をかき分けて、
踏みしめて、道と堀との境も見分けられない雪原を、
歩かなければならない。
時々は長靴を履いて出かけることもあるが、
履き慣れた下駄で、出かけることも多かった。
その下駄の歯には、雪が挟まって団子のように盛り上がり、
歩行が困難になる。
下駄の歯に詰まった雪を、雪が積もっていないどこかの庭先で、
コツンコツンとぶつけて、払い落としてから、
また雪道に踏み出した。
その繰り返しを、帰宅するまで続けるのだから、
普段の数倍も、無駄な時間がかかった。
雪国育ちの芳子にとっては、それが普通の冬の生活なのだろうが、
それでも鬱陶しく感じられることが、無いわけではなかった。
「母ちゃん、冬は大変だね。俺らは遊べばいいけど、
母ちゃんは仕事だから。」
タカオが、芳子に問いかけている。
「生意気を、言ってるな。たいしたことじゃないよ。
冬が来れば、そのうちに春が来るのさ。」
芳子の答えは、いつもこんな感じだった。
物事を、『大変だ』と感じれば、それが大変なことになる。
『自然に受け入れよう』と考えれば、苦労が苦労ではなくなるのだ。
芳子は、常々、自分の考えを、そこに置いているらしい。
|
|
|


