幻視(まぼろし)-春のほたる-3
幻視(まぼろし)-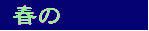 (3) (3) 
小屋(タカオの家)の狭い庭先に、ブリキのバケツと、
竹を割いて簡素に造ったピンセットが置かれている。
いつの間にか帰宅していた八郎が、準備したものだろう。
八郎は、また職を辞めてきたのだろうか。
それとも、数年に一度の休暇だろうか。
休暇の時には、彼は1~2ヶ月ほど、自宅にいる。
それが冬の間となると、芳子にとって、鬱陶しさが倍加したはずである。
八郎は、神経が細かい男で、重箱の隅を突っついても出てこないようなものまで、
事細かにほじくり返して、注文を付けたのだ。
彼の留守中だからと言って、芳子が家事全般に手抜きできないのは、
八郎のこの性格によるところが、大きかった。
どちらかといえば大まかな芳子の性格には合わず、
八郎が帰宅すれば、出納簿の付け合わせから始めて、
多くの食い違いが見つかって、丁々発止のバトルが、
毎度のように繰り広げられた。
それほどに、八郎と芳子夫婦は、切りつめた生活をしていたのだ。
八郎の収入が、少なかったわけではない。
人並み以上の収入は、得られていた。
だが彼は、1円の不足で徹夜をするほど、厳しい細かさを発揮した。
彼は、ほとんど“妥協”ということを許さなかった。
日中は家事をこなして、夜なべ仕事を終えてから、
八郎に付き合って、徹夜で出納簿と現金との食い違いを、
チェックするのである。
小柄な芳子の体力に、感心させられるほどだった。
これほどの“戦い”を繰り返しながら、
子供たちはその二人の苦労を、何も感じずに育てられた。
これは、二人の意見が同じだったためか、
芳子の育児方針が、貫かれたからだろう。
バトルの激しさに、寝入ったタカオが起き出すこともあった。
それでも二人のバトルは収まらない。
大声で、食い違いについて、意見を戦わしている。
ある日、タカオが母に尋ねた。
「母ちゃんは、どうして父ちゃんと一緒にいるの?」
「子供は、そんなことを気にしなくても良いんだ。」
「だって、いっつも喧嘩ばっかりしてんだもの。どうして結婚したんだ?」
「子供には、夫婦のことはわかんないんだ。」
「わかんねぇえよ。」
「大人になったら、解るときが来るだろうさ。」
あれほどの大喧嘩を繰り返しても、芳子には、
その出来事とは違った別の思いがあったようだ。
彼女は、他人(=夫も)の悪い面を大きく捉えるのではなく、
出来の悪い人であっても、その中でいい部分を見つけ出して、
それを膨らませて、その部分を認めるようにしたい。
と、そのような“ものの考え方”をする女性だったらしい。
そう言えば芳子は、帰宅した八郎と、喧嘩を繰り返しながら、
出張中の八郎に対して、陰膳を欠かすことがなかった。
“喧嘩は喧嘩”、“大切さは大切さ”と、
彼女の意識の中で、明確に分離されて、整理されていたと思われる。
そんな彼女の気持ちが、幼いタカオに理解できるはずがない。
母との喧嘩が絶えない八郎を、タカオも自然に敬遠しがちになっていた。
その意識の距離感を、帰宅した八郎は感じ取ったのだろうか。
ことさらに、理由を付けては、タカオを連れ出して、
行動をともにしようとした。
タカオは、それがまた、鬱陶しかった。
だが、感情は微妙なものである。
鬱陶しさと同時に、八郎に連れ出されることの嬉しさも、
感じていたのである。
八郎は、芳子が体験させてくれない多くのことを、教えてくれた。
近所の友達と遊んでいるときとは違った、異質の楽しみを、
提供してくれた。
“異質の楽しみ”のひとつが、庭先に置かれたブリキのバケツと、
竹を割いて造ったピンセントだった。
冬になると、その道具とシャベルを持って、
父子で長靴を履いて、凍り付いた田んぼに出かけるのだった。
田んぼの氷を透かして、うっすらと浮いた水に目を凝らすと、
泥の上を何かが這った痕跡が見える。
その痕跡の先に、小さな穴が見つけられる。
そこを、シャベル(スコップ)で一気に掘り起こすと、
ぬるりとドジョウが滑り出る。
その滑り出たドジョウを、竹製のピンセットで、挟み捕るのだ。
手で捕まえようとすると、ドジョウは滑って逃げてしまう。
竹製のピンセットは、八郎が“ドジョウ挟み”と言っている。
ドジョウのぬめりに影響されずに、挟み捕るには、
竹が最適だったと思われる。
そして、冬になるとドジョウ捕りの季節だという理由は、
田んぼに氷が張ると、田んぼの上を歩きやすくなり、
掘り上げたドジョウを氷の上に放り出して、
それからゆっくりと捕まえることができる。
もちろん、農作業はすべて終了している。
これらの条件が揃ったのが、冬だったということだろう。
ドジョウの味も、最も良くなっている季節だと思われる。
親子が持ち帰ったドジョウは、芳子が料理をした。
料理といっても、味噌汁の中に、
泥を吐かせたドジョウを放り込んで、
暴れるドジョウの力で跳ね上がる蓋を、押さえ込むだけのことだが。
芳子は、豆腐汁にドジョウを入れる料理は、なぜか嫌った。
「豆腐に入れるのは、やらないのかい?」
タカオの質問に、
「豆腐の中に逃げ込んで、そこで熱くなって死ぬドジョウが可哀想だから。」
と芳子は答えた。
何だか私には、結果はどちらでも同じように思えるのだが、
芳子には彼女なりの“思い”があってのことなのだろう。
それは、彼女の“戦争体験”によるものかも知れなかった。
夜が更けると、静まりかえった村が、さらに静かになった。
周囲の音が、何かに吸い込まれるように、掻き消えている。
木の葉のさざめきも、鶏たちの羽の擦れる音さえも、
闇に吸い込まれている。
始めて味わうような“静寂”の原因を、
夜明けと同時に、目の当たりにした。
夜になって迎えた静寂は、降りしきる雪によるものだったのだ。
雪とは不思議なもので、闇夜であるはずの、明かりが全くない世界でも、
景色の輪郭が、うっすらと透けて見えるのだ。
深夜になるにつれて、明るさが増すような情景は、
降り積もる雪によるものだった。
その雪の夜が明けると、空が抜けるように青かった。
そして雪は、まぶしく輝いていた。
小屋(タカオの家)の板戸(雨戸)が、ガタゴトと引き開けられた。
タカオが、まぶしそうに雪に覆われた木々を見上げている。
その傍らに、起き出したヤヨイが寄り添っている。
二人で、青い空を見上げている。
見上げる空は一緒だが、二人の思いは、全く別のものだろう。
タカオは、早速外に飛び出して、ソリ遊びを楽しむ心づもりのようだ。
一方のヤヨイは、昨夜、母の芳子に話して聞かせられた童話を、
思い起こしていた。
ヤヨイを寝かしつけるために、添い寝をしながら芳子が、
絵本を開いて、読んで聞かせたのだった。
「おばあさんの洗濯糊を食っちまったのは、おまえだろうと言われて雀は・・・。」
「はぁ・・・後(あと)。」
芳子の話の続きを、ヤヨイは『はぁ・・・後(を)。』と、
催促の合いの手を入れて、先を促したのである。
いつまでも眠らないヤヨイを持て余して、芳子は適当に寝たふりをする。
だが、それで諦めるヤヨイではない。
芳子の鼻をひねったり、耳を引っ張ったりして、
童話の続きを要求する。
その隣では、昼の遊び疲れで、タカオがあっけなく眠ってしまっている。
ヤヨイの要求に応えながら“寝たふり”を繰り返す芳子だが、
彼女も“寝たふり”なのか、本当に眠ってしまうときがあるのか、
よくわからない状態ではあった。
ヤヨイはそんな童話の世界に、雪景色を見ながら、
没頭していたのである。
一面の“白い世界”の中でも、庭先の一部には、
雪が積もらずに、地面が見えているところがあった。
その“軒先”に、雀が遊びに来ていたのだ。
降り積もった雪の中から、数本の枯れ草が、突き出ている。
その枯れ草で遊ぶ雀が、軒先の地面に、餌を探しに舞い降りてくるのである。
その雀を見ると、ヤヨイは昨夜の話の世界に引き込まれるのだ。
「ちゅんちゅん!」と鳴けない雀がいるのではないだろうか。
舌を切られた雀は、いないだろうか。
そんなことも思っているらしい。
タカオは、朝飯の前に、雪の中に飛び出した。
長靴には、滑り止めの縄が巻き付けられている。
タカオが細い坂道を登っていくと、その先では、
子供たちの叫声が響いていた。
既に、早起きをした近所の子供たちが、坂道で遊んでいるらしい。
ソリ遊びをするもの、雪だるまを造るもの、
雪合戦を始めるものという具合に、思い思いに駆け回っている。
先日までの、人気がまるで無いような村の様相が、一変している。
どこから、これほどの子供が湧きだしたのだろうか。
ヤヨイも外に出たがって、声が聞こえる方を、見つめている。
そのヤヨイに、芳子が声をかけた。
「ほらほら、寒いから障子を閉めろよ。」
「うん、わかった。」
ヤヨイはしぶしぶと、名残惜しそうに、ゆっくりと障子を引いた。
家族が揃って朝食をとることが多い家庭だが、
タカオがいつ帰ってくるか解らないので、
この日は、タカオ抜きの食卓になるのだろう。
芳子はこの雪の日にも、出かける用事があるのだろうか。
村から町に通じる道は、早起きの子供たちがまだ寝床から起きあがらない早朝に、
村の男の誰かが、牛に俵を引かせて、歩きやすいように、
除雪してくれていた。
その除雪は、村から町へ、村と村を結んで、
そして村の公民館や小さな商店へといったように、
主要なルートに限られていた。
それ以外の小径は、それぞれの住人が、
子供が歩きやすいように、雪を踏みしめていたのである。
その作業の後で雪が降った場合には、用事がある人が、
それぞれの行き先に向けて、雪を踏みしめて進路を造るほか、
仕方がなかった。
芳子が町に出かけるとなると、どこかではその“作業”が、
必要になるはずだった。
朝食後の早い時間に出かけても、帰宅は夜になる。
雪明かりを頼りにするとしても、冬の日暮れは早い。
提灯を貸してくれる家もあったが、荷物を手にしては、
提灯を持つ手がない。
その時間のやりくりを考えると、できるだけ早く、
家事を済ませなければならない。
彼女は、井戸から汲んできた冷たい水に湯を足して、
ぬるま湯を作って、洗濯を済ませた。
軒先に広げる先から、洗濯物が凍った。
食事を済ませた芳子の夫の八郎は、
半畳ほどの書斎に籠もって、仕事のための勉強を始めている。
八郎が自宅にいるならば、ヤヨイの子守を頼んで、町に出かけられる。
家を出かける芳子は、もんぺに長靴といった、珍しいいでたちだった。
新雪が深そうなので、長靴を選んだのだろう。
私は、こんな雪国が好きになれるだろうか。
芳子にとっては、苦労のうちに含まれない、日常だったようなのだが。
私はこれから、こんな雪景色を、何日も見ることになるのだろうか。
と心配をしたのだが、速度を増していた走馬燈は、
この冬の時間をも、一気に通り過ぎようとしていた。
走馬燈・・・この“走馬燈”は、誰の思いを私にシンクロさせたものだろうか。
タカオの“心”だろうか、芳子の“思い”なのだろうか。
この場所(ポイント)に私が立ったのは、
確か、頭上でヒバリの声があわただしく飛び交う、
初夏のことだったはずである。
その初夏から、一気に夏を通り越して秋に入り、
さらには冬の厳しい寒さを、瞬間のように体験して、
今また、その冬も過ぎ去ろうとしている。
私は、このポイントに、どれほどの期間留まっていたというのだろうか。
まだ、1日も過ぎていない感覚なのだが、
その間に、季節がめまぐるしく移ろい過ぎていく。
どうせ、得体の知れない“白い煙状の“それ”が、
こんなところに、私を誘ったのだから、
一切を深く考える必要が、ないのだろう。
いつまで、この場所に留まることになるのか知れないが、
とりあえず、事態の流れに、身を委ねてみることにしよう。
というよりも、“それ”に誘われるままに、
この場所を訪れたときから、私の思い通りには、
事態の展開が運ばなくなっている。
身を委ねて置くしか、仕方がないのである。
ふっかりと深く被せられた“綿帽子”が、着実に薄くなっている。
トタン屋根から垂れ下がった雪塊が、
その自身の重さを支えきれずに、時折大きな音を立てて、
『どさり』と庭先に滑り落ちる。
庇にかかった簾のような氷柱も細くなり、
ぽたり・・・ぽたりと、滴を滴らせている。
その滴が、庭先に一定間隔の穴を穿っている。
庭先の細い水路では、薄く張られた氷の下を、
ちょろちょろ、カポカポと、音を立てて水が流れ始めている。
氷の隙間を探して、芹が顔を覗かせ始めていた。
春が間近に迫っている兆しが、至る所で見られた。
タカオが、ウサギの餌を摘みに出かけようとしていた。
ハコベはまだ早いだろうが、雪をかき分ければ、
ナズナなどの野草が、見つけられるのだろう。
彼は、ついでに芹も摘んで帰るに違いない。
彼が“手みやげ”を持参しなければ、芳子が近くの水路から、
芹を摘んでくるだろう。
タカオのウサギは、白くて耳の長い、大きな体の種類だった。
タカオが、特に可愛がっていたわけでは、なさそうだった。
そのウサギは、人に慣れることはなかった。
愛玩用に飼われていたのでなければ、
何のために飼われていたのだろうか。
その答えは、芳子の夫・八郎の所有物の中に、
見つけることができるようだった。
その“所有物”の中に、彼が愛用している“ウサギの毛皮の襟巻き”があった。
ただその“ウサギの毛皮”は、やむを得ずに、
その“運命”を辿ったに過ぎなかったのだが、
それでも“今飼われているウサギの運命”も、想像できるものではあった。
特に裕福な暮らしぶりでもない家族にとって、
餌代が必要ではないにしても、無意味な手間をかける生き物を飼うゆとりは、
無かったはずなのである。
だが、芳子が子供たちのために、ウサギの飼育を考えたとすれば、
“食肉用”と、断定できるものでもなかったが。
彼女の思考は、この場所の地域住民とは、
一風変わっていたのかも知れない。
子供たちの“情操教育”ということも、考慮していたらしいのである。
タカオが、重いウサギを運ぶときに、
その長い耳を持ってぶら下げていると、
「止めなさい! 可哀想だろ! 耳が伸びちまうぞ。」
と諭した。
「ウサギはな、こうやって抱くと、おとなしく抱かれるんだ。」
そうやって、タカオに抱き方を教えた。
「うんなら、やってみる。」
タカオは芳子のまねをしてウサギを抱き上げたが、
後ろ足で強く蹴られて、うまく抱き上げることができなかった。
「やっぱし、俺、だめだ。」
「そうか。でも、耳を持ってぶら下げたら、だめだぞ。」
「うん、解ったよ。」
タカオは、『解った。』と答えたものの、
それではどうやってウサギを運んだらいいのか、
その手段を思い浮かべられなかった。
そのウサギも大きかったが、八郎の襟巻きになった“毛皮”は、
いつもタカオにぶら下げられて、耳が折れてしまったウサギだった。
そろそろ冬の訪れが近いかという、ある深夜のことである。
芳子の家族が寝静まった頃に、少し離れた場所にある井戸から、
水の音が聞こえてきた。
誰かが、水垢離でもしているのだろうか。
ざぁー! ザブン! ザブン! バシャバシャ!
その音が、絶えることなく、深夜の戸外に響いている。
芳子が、寝床から台所の窓を透かして外を窺うと、
月も出ていない漆黒の闇が、のぞき見られた。
その漆黒の世界で、誰かが水を汲み上げている?
井戸の水面を叩いている?
一刻の休憩もせずに、その行為を続けている。
ほとんど何事にも驚くことがない芳子だったが、
その“状況”には、身体がすくんで、様子を見に出ることさえできなかった。
夫の八郎が傍らにいれば、提灯を手にして、
二人で様子を見に行くことも、できただろう。
だがこんな時に限って、夫は出張で、子供は頼りにできない。
“音”は、何時間続いたのだろうか。数十分だったかも知れない。
その井戸の音も、いつしか静かになっていた。
芳子は、震える心地で、夜明けを待った。
うっすらと夜が明けるのを待ちかねるように、
芳子は井戸端に急いだ。
井戸というには広すぎるような水面が、
周囲の石垣を、静かに映している。
まるで昨夜の出来事を、何も知らないかのように、
水面には、さざ波さえ立っていない。
その井戸を覗き込んだ芳子は、“水音の原因”を直視して、息をのんだ。
タカオに世話をさせていたウサギの白い姿が、
暗い水面に、浮かんでいたのである。
夜の間に小屋を抜け出したウサギが、
誤って井戸に飛び込んでしまったのだ。
その井戸から這い出そうと、必死にもがき続けた音が、
あの、昨夜の“不気味な音”の正体だったのだ。
『そんなことだとわかっていれば、助けることができたのに・・・。』
芳子は、まずそのことを悔いた。
必死に這いあがろうと、もがき続けたことだろう。
ウサギといえども、どんなにか恐怖を覚えたことだろう。
それを思うと、不憫でたまらなかった。
そして次に思いやったのは、
この井戸を使っている近隣の人々のことだった。
ウサギが飛び込んで、死んだのである。
そのまま、井戸水を使い続けることはできない。
年に一度は、井戸水を汲みだして、大掃除をする習わしだった。
この年の大掃除は、既に終わっていた。
それなのに、一匹のウサギのために、また多くの人の手を煩わせてしまう。
その“済まないさ”が、芳子の気持ちの中で、急速に強まった。
だが、起きてしまったことは、仕方がない。
芳子は、井戸の持ち主である義兄の家族が気付かないうちに、と、
もうひとりの義兄・亀夫の家に急いだ。
亀夫なら、きっと面倒な相談にも乗ってくれるだろうし、
口うるさい義兄の家族を、とりまとめてくれる。
そう期待をして、亀夫を頼ったのだった。
事情を聞いた亀夫は、簡単に結論を出した。
「ウサギのことだ、仕様があんめぇ。」
その一言で、親類一同の大人が総出で、井戸払いを行うことが決まった。
その後、井戸に水が溜まるまでの数日間は、
芳子の家族はもとより、持ち主の義兄の家族も、
不便を強いられることになる。
暫くの間は、亀夫の家の井戸を、利用させてもらうことになった。
坂道を登って、バケツに水を汲んで運ぶのは、余計な労働だった。
その作業は、タカオも手伝った。
ヤヨイも、小さなバケツを持って、手伝いのまねごとをした。
井戸に飛び込んだウサギは、病死ではないので、
“井戸払い”でお世話になった人々、迷惑をかけた人々に、
その肉を分けて、振る舞われた。
芳子の“子供のための情操教育”が、どんな効果をもたらしたのかは、
よくわからない。
タカオは、特に愛着を持っていたわけでもないウサギ肉を、
美味しそうに噛んでいた。
鶏肉に似た、あっさりとした味わいだった。
そのウサギの“生きた証”が、八郎の襟巻きになって、
姿をとどめたのである。
そして今、タカオが野草を摘んでやっているウサギが、
2代目として飼われていたのである。
福寿草の“体温”が、薄くなった雪を溶かして、
輝く黄色の花を、見せている。
舗装などされていない小径は、所々がぬかるんで、
そのぬかるみを避けるように、踏み石のない場所で、下駄の歯の跡が右往左往している。
融けた雪が水たまりを作り出し、小さなさざめきが、
柔らかな光を跳ね返している。
季節は、春に向かっている。
井戸の水汲みを手伝ったタカオが、大人びていた。
ヤヨイも、動きがしっかりとしている。
ヤヨイは、3歳だったはず。
彼女の行動が、3歳児には見えない。
母親に似たのか、小柄な子供だが、ほかの女の子に混じって、
一人前に遊び回っている。
都会なら、幼稚園に通っている年頃だろう。
もう、5歳にはなっているだろうか。
『もうすぐ、春が来るんだなぁ。』
そんな気持ちに浸るまもなく、季節はさらに回転を速めていた。
夏を、一気に通り越して、またもや、秋が訪れようとしているようだった。
また、夏は素通りなのか?
雪国の夏は、思いがけずに暑くて寝苦しいものなのに、
その夏を、素通りなのか?
-心の対話へ-
先日見たような、秋の日射しに、小屋(タカオの家)が、包まれていた。
日だまりの家は、静まりかえっていたが、ぬくもりを感じさせられた。
まるで“空き家”のような雰囲気が、小屋を覆っていたが、
その“空き家”が、ぬくもりに包まれている。
それは、奇妙な感覚だった。
30歳代の芳子は、出産して間もない3人目の子供を連れて、
都会に転居していた。
八郎の仕事の都合で、交通の便などで何かと便利な、
都会に転居したのである。
この家(小屋)は、住む人のない空き家になっているはずだった。
だが、まるで今、その家から誰かが出かけたかのようにも、感じられた。
数十年もの間、空き家になっていた家だとは、とうてい感じられない。
手入れをする人などいないはずなのに、障子はきれいに手入れをされている。
タカオとヤヨイが、外の様子を窺うために、
指先に唾を付けて、障子に小さく穴を開けた。
その穴は、芳子が桜の花のように、障子の端切れを切り抜いて、
ご飯粒で補修した。
その跡が、今まさに補修が終わったかのように、
新鮮な色の違いを、際だたせている。
そう言えば、芳子たちがこの小屋から引っ越していくまでの間に、
私はついに、芳子の顔を、まともに見ることがなかった。
なぜだろう?
見る機会は、いくらでもあったはずなのに、
その時には、いつも彼女の顔が、反対側を向いていた。
私の気持ちにも、彼女の顔を見ようという欲求が、
そう強くなかったのかも知れない。
だがなぜか、彼女の会話や気持ちは、直接語りかけてくるかのように、
私に伝わってきた。
そのために、彼女の表情までを見ようとは、
思わなかったのかも知れない。
それは、この寂しいような“空き家”を目の当たりにすると、
名残惜しい気分には、させられる。
障子に落ちる柿の木の陰が、ゆっくりと揺れている。
古い建物で、修繕をしなければ住めないはずなのだが、
様子を窺うと、そのような不都合は見あたらない。
この家の住人は、すぐにも帰ってきそうな雰囲気だった。
私は、少しの間、待った。
これまでの過ぎ去った時間の早さを考えれば、
その“少しの時間”が、このポイントでの、
どれほどの時間の経過を意味するのか、考えることもなかった。
夕暮れにはまだ間がある時間に、この小屋の主が、帰ってきた。
落ち着いた柄の着物を着た、60歳を過ぎたほどの、
小柄な婦人だった。
私が始めて芳子の姿を見たときと似たような、
それ以上に懐かしさを覚えさせるような、老齢の婦人の姿だった。
雰囲気が、芳子に似ている。
私が『また秋が巡ってきた。』と感じた季節は、
春だったのかも知れない。
彼女の和服は、“春”を感じさせる、余所行きの出で立ちだった。
彼女の姿を、“老齢”と表現するのは、失礼だろうか。
落ち着きのある彼女の雰囲気が、私に“老齢”を感じさせたのであり、
彼女の年齢は、まだ60歳の半ば前と思われた。
その女性の姿に、私は“心”で問いかけた。
『あなたは、私が知っている芳子さんですか?』
返事を期待したわけではなかったが、思いがけずに、
彼女から返事が返ってきた。
彼女の口から、直接“言葉”が吐き出されたのではない。
彼女は、私に横顔を見せたままで、目元に“ふっ”と、
微笑みの表情を、浮かべて見せたのだ。
私は、その微笑みの中に、彼女の“返事”を、感じ取った。
そして、その“返事”が気のせいではなかったことに、
彼女の“心の答え”が、その後も私に、直接、語りかけて来たのだ。
私からの問いかけに対する彼女の答えは、
『そうですよ。』
というものだった。
『あなたは、急に姿を消して、どうして、こんなところにいるのですか?』
『それについては、あなたが一番よく、知っているはずではないのか?』
彼女の“答え”に、性別は存在しない。
その理由を考えたのは、ずっと後のことである。
その時の私は、彼女との対話に心を奪われていて、
言葉の内容しか、意に止めていなかったのである。
そして、私に投げられた“彼女の言葉”を、
全く“不自然”と、感じることもなかった。
『あなたが、一番よく知っている・・・?』
『今まで“ここ”で、いろいろな情景を見せただろう。』
『あの情景は、貴女が私に見せたものだったのですか。』
『あなたが見た光景が、私が“ここ”に存在する理由だよ。』
彼女は、私の問いかけに、直接答えるようでありながら、
不要と判断したらしい部分については、答えを省略してしまう。
それが、彼女のスタイルであるようだった。
彼女は、他人から相談を持ちかけられても、余計なことを問いかけない。
相談者が、自分から話しかけてくるまでは、
彼女のほうから、詳細を詮索することがなかった。
そして、相談者が内容を話すまでは、
『なぜ尋ねてきたのか?』
と、問うこともなかった。
相手が訪問することを予想していたかのように、
そしてその人がそこにいることが、全く不自然ではないように、
自然に振る舞って見せた。
それが、彼女が慕われる要素であり、彼女の性格でもあったらしい。
私の“問いかけ”の意味には、
“彼女が突然”に“姿を消した”理由も、含まれていた。
だが彼女は、その“問いかけ”の内容を理解しないかのように、
“今この場所にいる理由”だけを、私に答えようとしたのだ。
『あなたが姿を消してから、私は、そして私の家族も、
あなたの行方を、必死に探し求めました。』
『私は、自分の仕事が一通り終えたと判断して、
“あるところ”からの誘いによって、姿を消すことに“なった”のだよ。』
『あなたが姿を消した後も、世間は全く変わらずに、
生活が続けられていました。
私には、その“何も変わらない状況”が、
不思議な世界を見るみたいでしたよ。』
『不思議なことではない。大きな変化を感じるのは、
当事者だけの心の問題であり、直接関わりのない人にとっては、
日常に、変化を与えるものではない。』
『私たちにとっては、始めて経験するような大きな出来事だったのに、
世間の日常には、米粒ほどの影響も与えていません。
それが、不思議なのです。』
『ひとりの人間の存在というものは、
ある部分では、非常に大きいものであり、その“穴”が生じれば、
それを埋めることは、一生を費やしても、できないものであるだろう。
だが、ある面では、ひとりの人間の存在などは、
突然消え去っても、世間の日常生活には、
米粒ほどの“穴”を生じさせる影響さえも、与えるものではない。』
『でも、あなたが消えた後では、あなたの夫の八郎さんが、
非常に大きなショックを受けてしまいました。
あなたの思い出だけに縋って、生きています。』
『それについては、申し訳ないと思っている。』
『あなたの生活は、“ここ”では10年あまりに過ぎなかったでしょう?』
『その意味は、あなたに見せた。』
『でも、納得できない部分があります。
貴女は、生まれ育った故郷の思い出も、たくさん持っています。
そして、友人との思い出を育んだ“場所”もあります。』
また、彼女がふっと微笑みを浮かべた。
『分かり切ったことを、今更なぜ質問するのか?』
と、私には受け取れた。
だが私には、まだ問いかけたいことがあった。
『貴女は、“ここ”での生活よりも長い“転居先での生活”があります。
そこでの生活は、20年を遙かに超えますが、
貴女は“永久の住処”を、なぜその地ではなく、“ここ”に決めたのですか?』
『その意味は、あなたに見せた。』
『貴女が住んだ都会では、貴女は新たな友人を作り、
家を、そして家庭を大切に、育て上げてきた。
その“都会”が、貴女の住処には、なり得なかったのですか。』
『年月の長さだけが、“ふるさと”ではない。』
『貴女は“ここ”で、苦労ばかりを、積み上げたのではなかったのですか?
夫の八郎さんとも、“生きるか死ぬか”の口論を繰り返したではありませんか?
それでも、“ここ”が、貴女の永久の住処”になるほどの、
“心のふるさと”だったのですか?』
『苦労もまた、ふるさとである条件のひとつではある。
狭い“村”ではあったが、私との“心のふれあい”は、
都会で得た“友人とのふれあい”とは、比較できないほど、
深いものだったのだよ。』
『都会で得た友人・・・、たとえば松井さんとの交流は、どうでした?』
『つきあいの深さに、“ここ”での深さと、隔たりはなかった。
私が消えるときに、松井さんの“叫び”も、私には伝わった。
だが、それと同じほどに、“ここ”から“消えた私”に、
“叫び”の心を送ってくれた人がいたのだ。
“心”は数の多さで、処理できる種類のものではない。
しかしながら、“ここ”の多くの人たちが、
私が“消えたこと”に対する“嘆き”を、私に伝えようとしてくれた。』
『私も、貴女の子供たちも、貴女に“叫び”を届けたはずですが・・・。』
『もちろん、それは届いた。』
『それならば、“貴女の永久の住処”を、あの“都会”に置いても、
良かったのではありませんか。』
『なるほどなぁ。だがそれは、おまえが“生身”だから、
そう考えることではないのか?
私にとっては、距離も時間も、意味はない。
私の“心”が、自然に“ここ”に引き寄せられて、
“ここ”に存在しているのだぞ。』
確かに、今まで私が“ここ”で見せられた“世界”には、
距離、時間の概念が、無かったような気がする。
『では、貴女に会うために、貴女の家族は“ここ”まで、
来なければならないのですか?』
『来ればいい。』
彼女は、あっさりと言い切った。
『できれば、貴女の家族の元に帰ってもらいたいのですが、
それは無理なのでしょうか?』
『私に、どこへ戻れというのかい? 戻る場所はないだろう。』
『戻る場所・・・。』
『戻っても、“現世の姿”に、私の魂が入ることはできないだろう。』
『戻る場所・・・。』
私の意識は、彼女の“戻る場所”を、改めて探し求めていた。
確かに、彼女の“魂”が戻る“物体”は、存在していない。
彼女に、もっと早く出会えていたら、
“現世の容れ物”を“焼却”する前に、
彼女に戻ってもらうことが、できただろうに。
それは、まさに“夢”になってしまった。
それならば、彼女には、“ここ”に留まってもらうことが、
“幸せ”ということになるのだろうか。
『貴女の夫は、そして家族は、貴女を捜し求めることができるでしょうか?』
『それは、それぞれの“ふるさと”の中で、私に出会えるだろう。』
『貴女を探し求める人ならば、それぞれの状況の中で、
貴女に出会える、ということで良いですね?』
彼女は、3度目の微笑みを、口の端に浮かべた。
“心のふるさと”は、人それぞれに異なる。
本人が、こここそ“心のふるさと”だと思っていても、
魂の寄る辺は、異なる場所を求めている。
そのようなことも、あり得ないことではない。
つまり、芳子の“魂”には、それぞれの人々の魂が、
現世から離脱した後にも、
“今”の願いに添って、“この場所”に辿り着けるとは限らない。
その場合(この場所に辿り着けないとき)にも、
“出逢い”は、それぞれの魂があるところで、自由に行われる。
時間の観念も、距離感の概念も、すべての意味を持たない次元のこと。
それぞれの“心”が、邂逅を求めるならば、
瞬時に“逢うべき場所”が作り出される。
と、そのようなことであるらしい。
その時にも、芳子の魂が存在する場所は、
ここ(住まい=小屋)がある、山里である・・・と、
芳子の魂が、私に告げている。
『だがなぜ、この山里にこだわるのですか?』
また、私の疑問攻勢が開始された。
『それは、私が気がかりだった“この地から動けない魂”が、
この地に存在するからでもある。』
『その魂が、貴女を呼び寄せたわけですね。』
『そうでもあるし、そうではない。』
『は?』
『先ほども、教えただろう。私を強く呼んでくれた魂たちが、
この地にあった。それが大きな存在だ。
それに呼応して、私の魂が、“この地から動けない魂”の元に、
定着することを、選ばせたのだ。』
『意識を、少し戻してみたいのですが。』
『何だ?』
『貴女は、貴女の夫や子供たちからの、強い呼びかけを振り切って、
現世を離れた。
まだ貴女の役割は、現世に残されていたのではありませんか?』
『私も、まだ心残りはあった。だが、「おまえの役割は終わった。」と、
現世を離れるように求める、逆らえない力が、私を引き離した。』
『貴女が最も心を残した“現世のこと”は、何でしょう。』
『末子のことだ。』
『“ここ”から都会に移転するときに連れていた、あの赤子ですね。』
『そうだよ。』
『彼は、今、何歳に・・・?』
『さぁて・・・。現世の“時”は、観念にない。』
『貴女の転居後の年月を思うと、20余歳・・・?』
『そうかも知れない。』
『貴女が、自分の余生の時間を考慮して、溺愛を隠すことがなかった・・・?』
『溺愛とは、ちょっと違うが、
若くして母親を失うアキラを思えば、これ以上の心残りはない。』
『それならば、アキラ君・・・ですか? 彼のためにも、
この世に留まるという選択肢は、なぜ得られなかったのですか。』
『現世では“運命”という。』
『必要とされていながら、離れるのも“運命”でしょうか。』
『人は、なぜ生きているのだ?』
逆に私が、芳子から質問をされていた。
『人は、生きることにその必要な役割があるから、ではありませんか。』
『そう。人は“自分で生きている”のではない。』
『生かされている・・・と。』
『その時に、どこかで誰かが、その人を必要としているとき、
人の身体は、現世で生かされている。』
『貴女は、まだ周囲の誰からも、必要とされていたのですよ。』
『自分で魂を現世から離すことは、許されていない。
私は、“離れるとき”が来た、と判断された“大きな力”によって、
魂が解放されたのだ。』
『確かに、貴女が自分の意志で、私たちの前から消えたのでないことは、
よく理解しています。』
『そうならば、それで良いではないか。』
そう答える芳子の背後に、赤子の姿が浮かんで見えた。
『そうか、彼女(童女)がいたのか。』
芳子が“動けない魂”の元に定着する、と答えた意味が、読み取れた。
芳子の背後に見える赤子は、まだ歩くことはおろか、
這い動くこともできないような、幼い年齢に思われた。
その表情は、よく見えないが、色の白い、整った顔立ちのようだった。
『その子は、貴女の子供さんですか?』
『そう・・・。』
『もしかしたら、幼くして亡くなっていると?』
『そう・・・、セツという。』
『セツちゃん・・・ですね?』
『その様子では、だいぶ幼いうちに亡くなられたと思いますが、
その子が、貴女を待っていたということでしょうか?』
『この子は、私を60年以上も待っていてくれた。この家で。』
『その子を失ったときの様子は、お伺いできますか。』
『当時は、よくありがちなことだった。』
『どこの家でも、ということですか。』
『この子は、幼い頃のタカオと同じで、風邪を引きやすくて、
体力がないために、ちょっとしたことでも病気になりやすかった。』
『経済的な理由も、ありましたか?』
『それは、理由ではない。』
『つまりは、この里のどの家でも起こりうることだったと・・・。』
『この里ではないよ。日本全国のどこででも、起きていたことだった。
栄養不良が元で、病気にかかりやすく、病気になると、
症状が重くなりがちだった。』
『その子の病気は、何でしたか?』
『風邪をこじらせて、肺炎を起こしてしまった。
可愛い女の子で、まだ半年を過ぎたばかりの命だった。』
『薬は? 病院は?』
『この山里の、戦後間もない時期に、効果的な薬なんかあるものか。』
『病院には、すぐに連れて行ったのでしょう?』
『満足な病院なんか、近くにはなかったよ。
お父さんが、病院を探して駆け回ってくれた。
医者を連れてきたが、効果のある注射を打ってくれなかった。』
『効果のある薬も、あるにはあったのですね。』
『ペニシリンが、素晴らしい効き目があるということだった。』
『それを使えば、助かったのですね。』
『それは、何とも言えない。』
『医者は、ペニシリンを持ってこなかったのですか。』
『その医者は、この家(小屋)に入ってきて、
“この家は、金を持っていないだろう”と思ったらしいのさ。
それで、“ペニシリンは高価な薬だから、使えないよ”ということだった。』
『それで、その医者は治療もせずに、済ませてしまったわけですか。』
『最低限の治療は、してくれたさ。』
『最低限の治療で、貴女は諦めたのですか。』
『医者が、ペニシリンは使わない、というものを、どうしようもなかった。』
『八郎さんは? 抗議をしなかったのですか?』
『言ってくれたが、医者が“ペニシリンの持ち合わせがない”と言う以上、
頼みようがなかった。』
『貴女は、その子、セツちゃんが亡くなったときに、
悲しかったでしょうね。』
『不憫でならなかったが、死んだものは仕方がない、と思うことにした。』
『タカオ君にも、その気持ちは伝えましたか。』
『仕方がなかったんだよ、とだけ。』
『仕方がなかった・・・と、諦められましたか・・・。』
『人の“死”とは、あっけないものだ。』
私は、納得できない気持ちを抱えながら、
芳子の“心”に、共感させられる部分もあった。
何よりも、芳子自身が、あっけなく現世から離れていってしまったのだ。
その現実を、身をもって知らされた。
その時に、“どうしようもないことがある”と、
私も、理解させられたはずだったのだ。
だがその事実を、受け入れたくない気持ちもあった。
そこで、セツちゃんが亡くなったときの気持ちを、
彼女にも確かめてみたのだった。
そこで、“人を失うときの気持ち”は、同じようなものだと、
再認識させられたわけだが、
彼女の気持ちは、私とは別の次元にあるようにも思われた。
つまり、彼女の世代は、直接的に戦争を体験している。
自分の肉親だけでなく、身近に存在する=存在していた=
多くの友人、知人を、戦争で失っている。
その失った命が、知人であるか、我が子であるかの違いなのだ。
セツちゃんを失った時期は、その戦中の気持ちが、
まだ充分に冷却されていない頃のことだった。
彼女(芳子)は、我が子を失ったからといって、
取り乱すことができない状況でもあった。
『死んでしまったものは、仕方がない。』
そう表現するばかりだった芳子の心には、常にセツちゃんの“命”が、
大切に、仕舞われていたはずなのである。
彼女は、セツちゃんの命日のたびに、そして墓参のたびに、
彼女の魂に向かって、日頃の出来事を、語りかけた。
幼かったセツちゃんには、話しても理解できないような内容も、
普通の子供に語りかけるように、話した。
それは、彼女の“心”の中で、
幼くして死んだ子供が、年月に合わせて、成長していたことの
証なのではあるまいか。
彼女は、“死んだ子の歳を数えるようなまねは・・・。”と、
たびたび口にしたが、知ってか知らずにか、
彼女の心に中では、セツちゃんが、自然に成長していて、
今の家族と共に、生活をしていたのだ。
しかし、彼女が永久の住処に選んだ小屋では、
幼いときのセツちゃんの魂が、母親の魂を待ちわびていた。
芳子の魂も、幼い魂を気遣っていた。
『自分は、幼子の魂の元に帰るべきだ。』
彼女は、そう決めていたのだろうか。
現在、彼女は、幼いセツの魂とともに、古い家(小屋)に、定着している。
このことが、芳子の本心を、物語っているだろう。
『貴女は、セツちゃんの魂とともに、未来もこの里に留まるのですか?』
私は芳子に、最後に問いかけた。
『未来のことは、わからない。ただ、あなたや私の子供たちが、
私に会いに来たいときに、会える間は、ここに留まるだろう。』
『それが、いつまでになるのかについては、わからないと言うこと?』
『私の魂が、いつどこから呼ばれるのか、
それは私にはわからないことだから。』
『どこかの新たな身体に、呼ばれていってしまっていることがある、
ということでしょうか。』
『その可能性がある、ということだが、
その時期は、まだ先のことだろうと思うのだ。』
そう答えた芳子の着物の袖から、
ふわりと夕闇の中に、飛び出した光があった。
黄色に明滅しながら、軽やかに、数個の光が舞い始めた。
|
|
|



