
|
|
|
カテゴリ:歴史全般
~野望と変貌そして~
ユリアス・カイザル  ユリアス・カイザル(紀元前100-紀元前44)は共和制ローマ期の軍人で政治家。英語読みのジュリアスシーザーの方が良く分かるかも知れない。「賽は投げられた」。「ルビコン川を渡れ」。「ブルータスお前もか」彼が放ったセリフを知る人も多いはず。若い時から戦い続け、「終身独裁官」に上り詰め、エジプトをあのクレオパトラと共同支配し、彼女との間に息子カイサリオンを設けた。 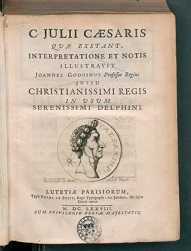 ガリア戦記 ガリア戦記相次ぐ戦いの中で、彼は「ガリア戦記」などを著す。ガリアは現在のフランス。戦った相手はゲルマン民族だった。紀元前45年から「ユリアス暦」を使用し、1582年にグレゴリア暦に変わるまで1600円以上ヨーロッパで採用された。July(7月)は彼の名ユリアスから採り、「ブルータスお前もか」は暗殺された際の言葉。聖書には「神のものは神に、カイサルのものはカイサルに返しなさい」の聖句がある。   キャンベラの街で、黒い帽子を被った一団に出会った。「あっ、これはユダヤ教の人」私は直感した。イスラム教祖のムハンマド(右)も元はユダヤ教徒。それがある時砂漠の中で神の啓示を受け、アラーを信じた。砂漠を旅する商人の彼を救い妻となったのが女の隊商だった。ユダヤ教、イスラム教、キリスト教が一神教であるのは、砂漠のような過酷な環境で生き抜くためには、唯一無二の神が不可欠だった。  フランシスコピサロはスペインの人。スペイン王と神聖ローマ帝国の許可を得て、ペルーのインカ帝国を攻略。インカの財宝をことごとく奪い、金銀製の美術品は鋳つぶし延べ棒にして本国に持ち帰った。メキシコのマヤ文明も然り。征服後やって来たカトリックの神父によってキリスト教に改宗させられた。先住民の宗教施設を破壊し、その上にカトリックの教会を建てたのだ。  ロヒンギャはミャンマー(ビルマ)国内の異民族でイスラム教徒。ミャンマー国内に100万人ほどいた少数民族だが、差別を受けて隣国バングラデッシュに難民として脱出。現在ミャンマー内にはは60万人ほどしかいなくなった由。軍事政権と結託するアウンサンスーチー派も援助せずに見殺し状態。それがかつてのノーベル平和賞受賞者の現状。コロナ禍の今、彼ら難民はどんな暮らしをしているのだろう。   ストーパ(後ろの仏教に因む円形の建造物)を守るヒンズー教風の門(左)と日本の鳥居(厳島神社)   コブラを背後にしたヒンズー教の神(左)と日本の竜神様(右)   太陽(日輪)を背にしたガンダーラ仏(左)と船形光背を持つ日本の仏像(右)。   チベットの歓喜仏(左)と男女の道祖伸(日本)    左からヒンズー教のリンガ(シヴァ神の象徴) 中央は巨大な道祖伸 右は縄文時代の石棒 長命と子孫繁栄の祈りは、時代や国の相違を超えた人類共通の願いなのだろう。自然豊かなアジアでは多神教が普通で、複数の宗教や民間信仰が混合してるのが特徴。そして日本古来のものと思われたものにも、古い時代に海外から伝わった事例もある。古来人類は移動し、文化や言語を伝えて来たのだろう。歴史と文化の遥かなる旅。それをなしうる唯一の存在が人類だ。 <祖父と孫 その2>   阿倍比羅夫(あべのひらふ)は飛鳥時代の武将。斉明天皇4年(658年)、秋田県沿岸部の蝦夷(えみし)を征伐し、翌年は渡島(北海道南部)に来ていた粛慎(みしはせ)を征伐。それらは天智天皇元年(664)の白村江の戦(右)のための訓練だった。百済からの援軍の求めに応じ船200艘で参戦したが、唐と新羅の聯合軍に敗れた。大宰帥(だざいのそち=大宰府の長官)に任じられ、国防に努めた。 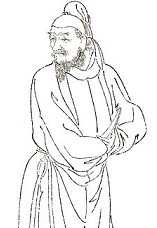  比羅夫の孫が阿倍仲麻呂(698-770)。奈良時代の遣唐留学生として遣唐使に同行し長安で学んだ。後に玄宗皇帝に仕えて文学畑の役職に就き、李白などの文人と親交を結んだ。遣唐使と共に3度帰国を試みるがいずれも船が遭難。長安に戻り、衛尉卿や秘書監などの要職に重用された。右は近年西安に建立された記念碑。故国日本を偲んで詠んだとされる 天の原ふりさけみれば春日なる 三笠の山に出でし月かも が百人一首に採択された。 青ユズ  たまたま観たテレビ番組から始まったこのシリーズが20回近くなった。大好きな歴史について語るのは何よりの喜びだが、いざ公開するとなればあまり不正確なことは書けない。そのため下調べをして構想を練り、載せる写真と文章の内容や順番にかなり神経を使った。そのため思い切って「お気に入り」を整理して執筆に没頭し、ようやく新聞も落ち着いて読めるようになった。  ハーブ ハーブわずかながら知ってることはある。それを足掛かりに、知らないことをネットで調べて補足した。またネットから借りた画像を参考資料としたことも多い。そんな作業の末にようやく本日最終回を迎えた。だがまだ書き残したような気がする。未使用の写真はいずれ特集を組むとして、明日から新たなシリーズに入る。最後までお付き合いいただいた読者各位には深甚の謝意を表したい。最後まで頑張れたのは、物言わぬ読者のアクセスがパワーの源だった。 ホトトギス草  不思議なのは知っていたわずかな知識に、調査で得た知識が加わったこと。「なるほどそういうことか」。新旧の知見が重なってより深まる理解。今まで見えなかった部分が見えて、長年の謎が解ける。「知らざるを知らずと為す。これ知るなり」。論語の一節だがまさに真理。疑問の持続と知に対する謙虚さが発見への近道だ。これからも大いに恥をかこう。人生も、そしてブログも。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2020.10.23 08:01:27
コメント(0) | コメントを書く
[歴史全般] カテゴリの最新記事
|
|