
|
|
|
カテゴリ:国内「ほ」の著者A
風のように去ってゆく時の流れの裡に、人間の実体を捉えた「風立ちぬ」は、生きることよりは死ぬことの意味を問い、同時に死を越えて生きることの意味をも問うている。バッハの遁走曲(フ-ガ)に思いついたという「美しい村」は、軽井沢でひとり暮しをしながら物語を構想中の若い小説家の見聞と、彼が出会った少女の面影を、音楽的に構成した傑作。ともに、堀辰雄の中期を代表する作品である。(新潮文庫案内より)
■堀辰雄『風立ちぬ』(新潮文庫) 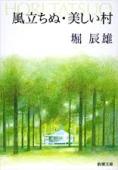 ◎堀辰雄について 堀辰雄は1904年、東京で生まれました。高校時代に室生犀星を訪ね、その紹介で芥川龍之介の知遇を得ています。萩原朔太郎の詩集に没頭したのも、このころです。その後東京帝国大学に進み、中野重治や小林秀雄と知り合いになります。 このときプロレタリア文学や、芸術派の洗礼を受けました。また折口信夫から日本の古典を学び、その影響で『かげろふの日記』や『大和路、信濃路』(ともに新潮文庫)が生まれたといわれています。 1927(昭2)年、芥川龍之介の死に直面し、創作活動の意欲を燃やすようになります。堀辰雄はすでに肋膜炎を患っており、健康をいたわりながらの文筆生活でした。 1934年矢野綾子と結婚。彼女も肺を病んでおり、2人で八ヶ岳山麓の療養所で過ごします。マルセル・ブルースト(推薦作『失われた時を求めて』抄編・全3巻、集英社文庫)やジェイムズ・ジョイス(推薦作『ユリシーズ』全4巻、集英社文庫)に傾倒しはじめます。その年、矢野綾子が死去します。このことが名作『風立ちぬ』の執筆動機となっています。堀辰雄は1953年死去しています。 ◎風立ちぬ、いざ生きめやも 前項で長々と、堀辰雄の履歴についてふれました。堀辰雄の代表作『風立ちぬ』(新潮文庫)は、現実にあったことを描いたものだからです。私は集英社文庫と新潮文庫で2回読みました。集英社文庫のほうは、巻頭に作品モデルの矢野綾子の写真まで掲載されていました。 堀辰雄の文章は、詩的散文調といわれています。初期作『聖家族』(新潮文庫)は、それを畳みかけるような短文で実現したことで知られています。ところが『風立ちぬ』の文章は、ゆったりと流れています。マルセル・ブルーストの文章を、学んだ成果なのでしょう。 『風立ちぬ』の主人公「私」は、別荘地で美しい少女・節子と出会います。少女は熱心に絵を描き、「私」は傍らで過ごす毎日がつづきました。 ――そんな日の或る午後、(それはもう秋近い日だった)私たちはお前の描きかけの絵を画架に立てかけたまま、その白樺の木陰に寝そべって果物を齧っていた。砂のような雲が空をさらさらと流れていた。(中略、画架が倒れて)すぐに立ち上がっていこうとするお前を、私は、いまの一瞬の何物をも失うまいとするかのように無理に引き留めて、私のそばから離さないでいた。お前は私のするがままにさせていた。 風立ちぬ、いざ生きめやも。 ふと口を衝いて出て来たそんな詩句を、私は私に靠(もた)れているお前の肩に手をかけながら、口の裡(うら)で繰り返していた(本文より) 口をついてでた詩句は、ポール・ヴァレリーの「海辺の墓地」からのものです。岩波文庫からポール・ヴァレリー『ヴァレリー詩集』がでています。「風立ちぬ」は、松田聖子の歌でも有名になりました。しかし「いざ生きめやも」をめぐって、これでは「死のう」という意味になってしまう、などという日本語通の意見もあります。そんなことは堀辰雄に、わからないはずはありません。だから陳腐な議論は、うっちゃっておきたいと思います。 「私」は節子と婚約します。そのころ節子は、すでに胸を病んでいました。節子の父親から、サナトリウムへ転地療養させたいと申し入れられます。「私」もいっしょに行くことにしました。「サナトリウム」という言葉は、現代では死語になってしまったようです。簡単にいえば結核療養所のことなのですが、この単語を眺めただけで陰湿な気持ちにさせらます。 「私たち」は八ヶ岳山麓のサナトリウムで、一風変わった愛の生活をはじめます。節子の病状は、けっして楽観をゆるしません。真っ白い病室で、2人だけの時が流れてゆきます。節子の病状は、一進一退をくりかえしています。 ――そのうち彼女が急に顔を上げて、私をじっと見つめたかと思うと、それを再び伏せながら、いくらか上ずったような中音で言った。「私、なんだか急に生きたくなったのね……」/それから彼女は聞こえるか聞こえないくらいの小声で言い足した。「あなたのお蔭で……」(本文より) サナトリウムでの日々は、単調なものでした。しかし窓外の季節は、刻々と姿を変えてゆきます。節子に快復の兆しはありません。 ◎大切にしたい作品 新緑の季節が真夏の陽光に追いやられると、サナトリウムには入居者が増えました。節子は暑さのために体力を失い、ときどき呼吸困難におちいります。「私」はそんな節子を見守りながら、どこかに「生」の喜びを感じています。 秋になりました。サナトリウムの患者は、落ち葉のように消えてゆくようになりました。節子の父親が面会にやってきます。節子は昂奮し、父親が帰ったあとに病状を悪化させました。 そして冬がやってきます。「私」は節子に、2人のものがたりを書こうと思う、と告げます。感動的で幸福なものがたりを書こうと、私は森への散歩をはじめました……。 「私」は病床の節子とともに、緊密な「生」をつらぬきとおしました。『風立ちぬ』の主人公「私」の誠実さと同時に、運命に身をゆだねる節子の気丈さも際立っています。 堀辰雄は人望のある人だったようです。彼を慕って集ったメンバーには、立原道造、中村真一郎、福永武彦(推薦作『死の島』上下巻、講談社文芸文庫)、遠藤周作(推薦作『沈黙』新潮文庫)などがいます。メンバーの一人である中村真一郎は、『風立ちぬ』についてつぎのように書いています。 ――(注:作品が際立っている理由の3つめとして)この物語全体にみなぎっている、息苦しいほどの密度の濃い緊張感である。それは作者であると同時に主人公である、第一人称の人物の、愛人に対する配慮の細やかさの綿密な表現の結果として生じたものであるが、作品を通過しながら、これほど息詰まる思いに読者を閉じ込めるような、緊密な芸術的質を持つ文学作品というものを、戦後の私たちは持つことができないでいる。(朝日新聞学芸部編『読みなおす一冊』所収、中村真一郎『風立ちぬ』より) 『風立ちぬ』を読みながら、高校時代にガールフレンドと観た「愛と死をみつめて」を思いだしてしまいました。あのころは、あれを純愛だと思っていました。そのことを前記の中村真一郎は「暴露的」と切り捨てています。明らかに『風立ちぬ』はその後の、暴露的な作品とはちがうのです。 なにがちがうのかなと思いながら、気がつきました。「つつましさ」という距離感が、後続の暴露的作品とはちがうのです。堀辰雄は読者に、涙を強要しません。淡々と病床と戸外を描ききっています。一つひとつの言葉を大切にし、しぼりだすように「生」と「死」を描ききっています。大切にしたい作品、それが私の『風立ちぬ』です。 私は『風立ちぬ』をつつましい、と書きました。それはあえてふれなかった終章を読んだら、実感できることです。3年半ぶりに「私」は、雪に埋もれた村に戻ってきます。その場面をじっくりと読んでもらいたいと思います。粉雪がかすかに揺れる情景を見ました。風が吹いています。 ◎堀辰雄と遠藤周作 堀辰雄の周囲にいた作家たちについては、すでにふれています。そのなかから、遠藤周作の堀辰雄感を紹介したいと思います。 戦争がしだいにひどくなった時期、慶応の予科生だった遠藤周作は、追分にある堀辰雄宅を訪ねています。そのときの感想です。堀辰雄は療養中の身でした。 ――寝床の右側に書棚があり、そこにインゼル版のリルケ全集をはじめ、いかにも堀さん的な書物が並んでいた。私のその部屋で堀さんから、近頃何を読んだかと言う話をうかがった。「ひさしぶりでトルストイの戦争と平和をよみかえしたが……」とか、「自分はドストエフスキーの小説では白痴が一番、肌に合う」などと言われた。(「新潮日本文学全集16・堀辰雄集」のしおりより) 遠藤周作は予科生の自分には、フランス文学など難しいだろう。堀辰雄はそんな気持ちから、あえてトルストイとドストエフスキーを選んでくれたのだろうと回想しています。文章にも表れている、堀辰雄のやさしさを示す一例だと思います。 (山本藤光:2009.11.22初稿、2015.03.22改稿) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2017年11月25日 07時14分01秒
コメント(0) | コメントを書く
[国内「ほ」の著者A] カテゴリの最新記事
|