☆興味のある周りの商品もチェックしてね(*^_^*)☆
廃用症候群で起こる身体の変化
廃用症候群とは過度に安静にすることや、活動性が低下したことによる身体に生じた状態をさします。
ベッドで長期に安静にした場合には、疾患の経過の裏で生理的な変化として表に示すようなことが起こり得ます。病気になれば、安静にして、寝ていることがごく自然な行動ですが、このことを長く続けると、廃用症候群を引き起こしてしまいます。
○2週間の安静で筋肉の2割が萎縮
特に高齢者では、知らないうちに進行し、気がついた時には、「起きられない」「歩くことができない」などの状況が少なくありません。
たとえば絶対安静の状態で筋収縮が行われないと1週間で10%から15%の筋力低下が起こると言われています。高齢者では2週間の床上安静でさえ下肢の筋肉が2割も萎縮するともいわれています。
過度に安静にしたり、あまり身体を動かさなくなると、筋肉がやせおとろえたり、関節の動きが悪くなります。そしてこのことが、さらに活動性を低下させることになり、悪循環をきたして、ますます全身の身体機能に悪影響をもたらし、最悪な状態では、寝たきりとなってしまうことがあります。
○廃用性症候群を予防するには
治療を必要とする疾患によって安静臥床を余儀なくされている状況で、運動をしないこと、寝ていること、不良肢位で長時間を過ごすことにより生じます。
たとえば、下肢を骨折して、ベッド上での生活が長くなると、骨折した下肢の筋肉が萎縮したり、関節が拘縮してしまうだけでなく、起立性低血圧や、静脈血栓症などを引き起こしたり、尿路感染症や、誤嚥することによる肺炎や、褥瘡(リンク1参照)を起こしやすくなります。
このような廃用性症候群を予防するためには、できるだけ寝た状態を存続させないようにします。座位時間を増やしたり、ベッド上で上肢や下肢を動かす運動を行います。人とのかかわりが薄れると精神機能の低下をきたすので、言葉をよくかけ、面会をよくするようにしましょう。
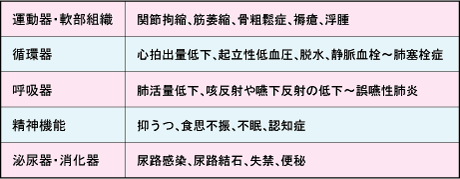
健康長寿ネット
↓↓
http://www.tyojyu.or.jp/hp/page000000100/hpg000000043.htm
