
|
|
|
カテゴリ:カテゴリ未分類
 「植物学の面白さ」本田正次(朝日選書) 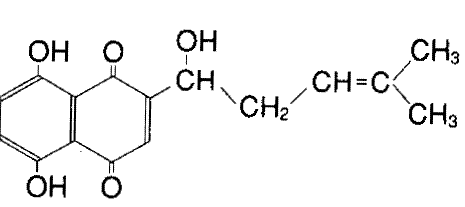 シコニン(shikoninC16H16O5) なるほど、シコニンの分子構造を調べようと思って、「PubChem」サーチhttp://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/、これはアメリカ合衆国(!)の国家機関なんだけど、ってのを「検索」してたら、「別名」みたいなところに、「Tokyo_Violet」って書かれてあったのさ! 「トーキョー・バイオレット」、ってなんか、「おしゃれ(笑)」な、映画のタイトルみたいじゃん♪、って「気に入って」たんだけど、そうか、そりゃそうか?、・・・、「江戸紫」(!)だったんだ。 懐かしい♪、○○屋のびん詰の、海苔のつくだ煮、だよね。ご飯に載せて、それだけで何倍でもおかわりできる(!)、この国の貧・し・か・っ・た・60年代の食卓の「友」、だよね!  リュウキュウコスミレ(スミレ科)。ところで、「紫」は「purple」のはずで、「violet」なら「菫(すみれ)」だ!、「UV=Ultra_Violet」だって、「紫外線」じゃなくて「菫・外線」だ!、宮沢賢治がその用語を使ってたことがあるって、お話もいたしましたな。 「媒染剤」:染色に際して、染料を繊維に固着させるために用いる試薬。多くは加水分解して水酸化物を生成しやすい金属塩であり、これを繊維に吸着させて用いる。染料はこれらの金属塩と水に難溶性の「錯化合物(レーキ)」をつくる。・・・ 「新・化学用語小辞典」(講談社ブルーバックス)  ヒメタネツケバナ(アブラナ科)。「ちょうどこの花時が、発芽をよくするために、稲の種籾を水に漬ける時期に合致するから・・・」「種漬花」(柳宗民の雑草ノオト)。別属だが類縁種にクレソン! そのムラサキ(ムラサキ科)と、多分花の様子が似ている筈の、キウリグサ、・・・、たしかに柳先生のおっしゃる通り、花が終わると、「ゼンマイが巻き戻った」、じゃないか?、それだけのことで、ほんの二日くらいで、キウリグサが咲き揃っていた土手の様子がすっかり変わってしまう。だ・か・ら・、「春」は、目が離せない! キウリグサは誤・っ・て・「勿忘草」と呼はれることもあるという。ワスレナグサは同じくムラサキ科の日本では栽培植物だそうだ。  「巻き締まったゼンマイが、戻りながら花を咲かせるという感じ」(柳宗民の雑草ノオト2)。なるほど、まっすぐになった!、キウリグサ(ムラサキ科)。 去っていく者が、残された者に、「私を忘れないで!」と命・じ・た・とすれば、それは「不可能」を命ずることであり、 (1)メッセージの外形から読み取れる形式的内容と、 (2)その実質的内容とが、 背馳しているのであるから、相手を、典型的な「ダブル・バインド」状況に置いてしまうことになる。 現在までの「積算値」以外のすべての「履歴」を、「忘却」してしまえるからこそ、私たちは、「恐怖」と「不安」と「悔恨」に、・・・、「発狂」せずに、もしくは、「発狂」しても(笑)、生きていくことができるのだ。だから、「勿(カレ)レ忘(ル)」、「forget_me_not」などというのは、やめよう♪   オヤブジラミ(セリ科)。花。セリ科らしい、切れ込みのある葉。右は、オヤブジラミ(セリ科)、の実。ヤブジラミより「実」が細長く、「柄」が長い、のだそうだが、「オ」は「雄」なのだろうか? 久留米絣での藍染は著名なものだが、ここでの純正藍染の技法にも発酵は重要なは働きをになっている。材料は藍(藍の葉だけをす・く・も・にした極上もの)、水、ソーダ灰、水飴、貝灰で、まず適量の沸かした水にそれらの材料を入れ、一晩桶のなかで寝かせる。その間、四、五回攪拌し、翌日深さ約一八〇センチメートルほどの藍甕に移し、その後毎日一―二回攪拌して三〇度Cで約一五日間ほど発酵させる。発酵期間中、液の表面は発酵のために泡立っており、この時の管理が不十分であると発酵が緩慢となって色の調和がくずれるから、こういう場合は他の甕で盛んに発酵している元気のよいものを少し加えたり、フスマやブドウ糖、水飴などを入れて元気づけしてやる。 こうして出来上がった発酵染液に、あらかじめ水に浸してひとまとめにした糸を浸しては絞ることを繰り返す。・・・藍は空気にふれることにより見事な青藍に染まるから、絞るごとに床に叩きつけて繊維の中までよく空気を通し、染め上がりをよくする。 「発酵」小泉武夫(中公新書) 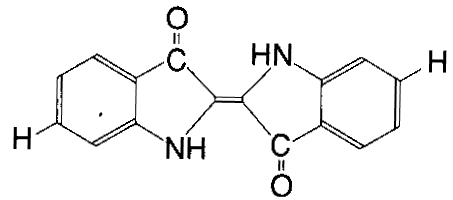 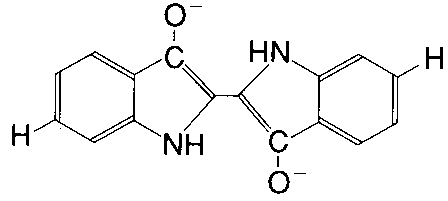 インディゴ(indigoC16H10N2O2)。アルカリ性下で「還元」されて右の「ロイコ型」になる、というけれど、いったい何が「還元剤」なの?、と「悩んで」いたのだが、・・・、きっと「発酵」(↑)の関与した複雑な、「バッタもん」の「化学の先生」(笑)には理解できない(!)プロセスなのでしょう・・・。 猫トイレに敷くために職場から古新聞をいただいてくるのだが、・・・、そうでなければ、私は新聞を「読む」習慣がないから、・・・、地方紙の「付録」みたいなタブロイド版に、「やんばる」の藍染め工房、そう、十年前に見学させてもらったところだ(!)、の広告が載っていて、懐かしさに涙した♪ 名護市というのは、ものすごく広いところなのだ。ヤンバルクイナと、ワオキツネザルを見に「自然公園」に行くだけでへとへとに「疲弊」してしまったくらいだから、ちゃんとたどり着けるかどうか?、不安だけれど、・・・、国公立二次後期試験が間もなく終われば、本当に「用無し」(笑)に、「閑」になるから、もう一度、出掛けてみたいものである。 キツネノマゴ科に属するという、その、リュウキュウアイという草本を、どうしてもも・う・一・度・目にしたい、・・・、それがさしあたりの、「生きる」希望、であるから・・・。   左:ヤンバルクイナ(クイナ科)、右:ワオキツネザル(キツネザル科)  ヤナギバルイラソウ(キツネノマゴ科)、キツネノマゴという「雑草」は、「本土」では普通に見られるものなのだそうだが、もちろん私は覚えていない・・・。当地で見られる「キツネノマゴ科」植物は、さしあたり、「園芸植物」の逸出、である、このヤナギバルイラソウ、のみ、であるから・・・。 びー♪、動かない後ろ足の肉球、暴れて籠の壁に擦れてしまったのだろう?、また、出血してしまった。血が出ると、血の匂いに誘われて、舐めてしまう。「普通」は、神経があるから、「痛い」と感じて、舐めるのをやめる。でも、神経がないから、その「スイッチ」が効かなくて、いつまでも、舐め続け、・・・あんなざらざらの「肉食獣」の舌だから、たちまち傷が深くなってしまう。 傷というものは、本・来・、空気に触れて血液が凝固して、表面がふさがれる。そうして、治・癒・するように生き物の身体は「出来て」いるのだが、・・・、仕方ない。下半身が動かない状態で「生き延びる」、などという事態は、「進化」の過程においても「想定外」(!)だったのだ。 だから、治りは遅くなるけれども、「舐められない」(!)ように包帯で覆って、・・・、そうして、お互い、「生き延びるべ・き・で・は・な・か・っ・た・」(笑)生き物として(!)、「不自然」に、生きていこうぜ♪ 一番上の写真は、そんな、・・・、人の膝の上で、ご機嫌♪、でもないか?、びー様。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.03.06 20:28:57
|