
|
|
|
カテゴリ:奥州南部糠部三十三観音霊場
奥州南部糠部三十三観音を廻り始めてすぐの頃、初めて天台寺に向かって運転しているときに、突如道路わきに巨大な鳥居が見えてきて興奮したのを覚えています。その時はスルーしたんですが、後に札所だと知って再びお参りしました。
大鳥居を抜けてすぐに左折し、突き当りを右にずーっと進むと朱塗りの鳥居が見えてきます。駐車場もあるので、車でも安心。ここから観音堂までは歩いて数十分くらいです。車で上の駐車場まで行けるとガイドブックにありますが、道は大変に傾いていたり凸凹だったりと、整備が行き届いているとはお世辞にもいえません。おすすめはしませんね・・・。 奥州南部糠部三十三観音二十九番札所:鳥越観音 それでは登っていきましょう。鳥居をいくつか抜けると、だんだんと道が急になり、狭く険しくなっていきます。  参道は山道で、特に階段があるとかではないので、装備はきちんとした方がいいと思います。 中ほどまで行くと弁慶石という石があります。弁慶の手形が残っているそうですが、それらしいものは見えません。  弁慶石からすぐに開けた道に出ました。車で上がってこれる第二駐車場(重ねておすすめはしません)から、ここに出られるんですね。一時期天台寺が別当であったからか、地蔵菩薩には赤い羽織が着せられています。昔話の様な光景ですよね  ついに山門まで到達しました。山門の周囲には手水舎や小祠があり、内部には仁王像が納められています。山門の建立は安政6年(1859年)で鳥越山の額がかけてあります。他にも二十九番札所・三番札所の立板も打ってあり、もともとは二つの札所を兼任していたのかもしれません。  小祠です。小祠にさらに小さい小祠がくっ付いているという面白い造りです。うっすらと内部に馬の置物が見えたので、八幡神か馬頭観音か蒼前様を祀っているんだと思います  手水舎です。木の根元から湧き出る水が手水として使われています。今はちょろちょろとしか流れておらず、使える状態ではありませんでした。  阿吽像吽形  阿吽像阿形  山門をくぐり、ふと見上げると懸造りの奥院が見えました。津軽三十三観音霊場八番札所:見入山大悲閣に似ていますね  岩壁の隙間から小祠が顔をのぞかせています。これら以外にも数個の祠が鎮座していました。  この階段を昇ればついに観音堂です。特徴的な狛犬がお出迎えする中進んでいきます。  観音堂です。他と同じ宝形造ですね。ガイドさんの話では、こちらの観音堂は別に札所ではないとのこと。あくまでも奥院が札所だということでしょう。  到着です、奥院! 石段を登り、木階段を上ると、木の棒で閉じられている入り口があり、ここから奥院内に入ることが出来ます。内部の写真撮りは忘れてしまいましたが、入って右に札所本尊の鳥越観音、その左に不動明王の小祠、更に左に龍神の小祠がありました。明かりも無く非常に暗いので、ライトの準備は忘れずに  説明書きです。 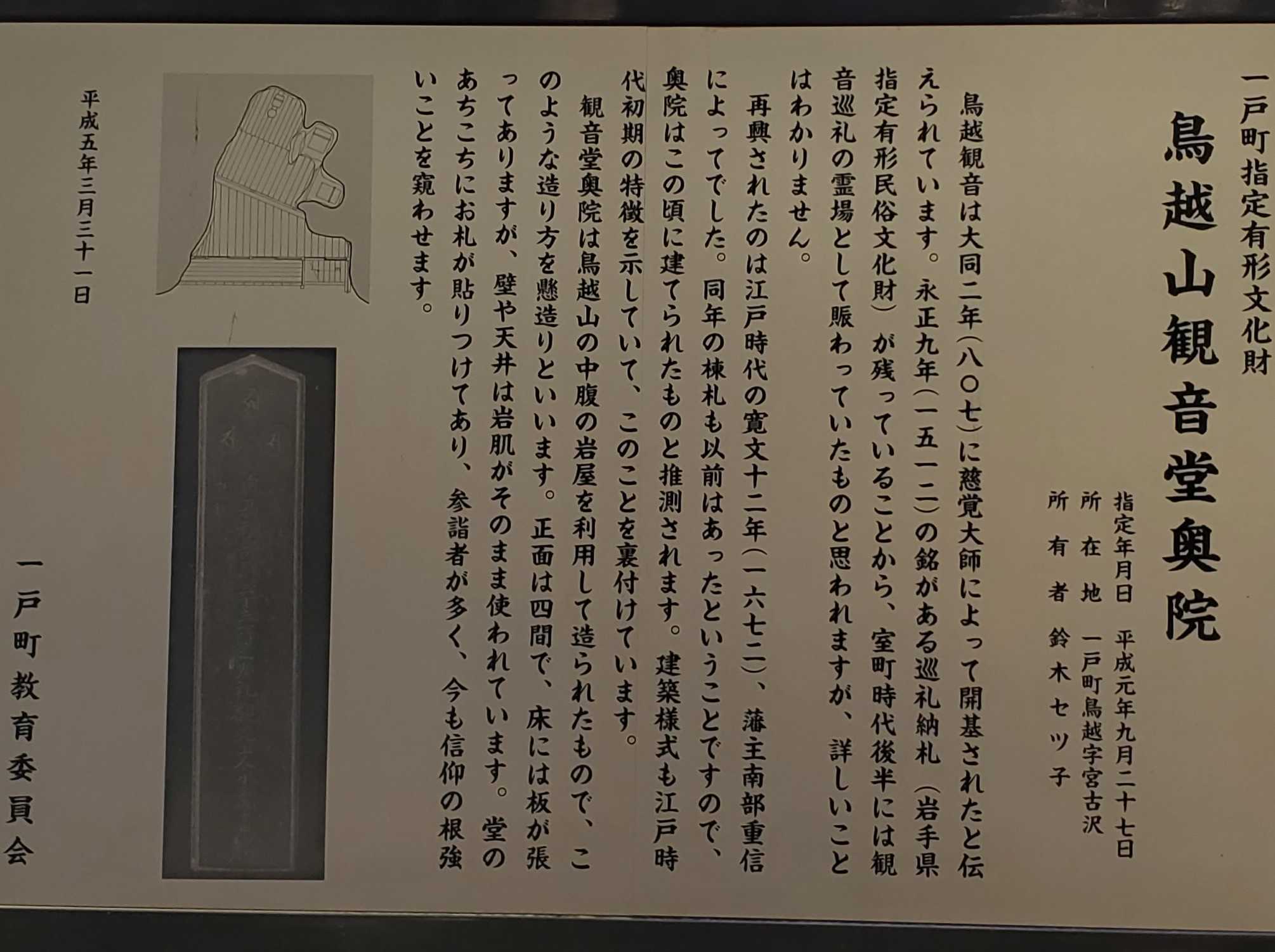 鳥越山観音堂奥院 鳥越観音は大同2年(807年)に慈覚大師によって開基されたと伝えられています。永正9年(1512年)の銘がある巡礼納札(岩手県指定有形民俗文化財)が残っていることから、室町時代後半には観音巡礼の霊場として賑わっていたものと思われますが、詳しいことは分かりません。 再興されたのは江戸時代の寛文12年(1672年)、藩主南部重信によってでした。同年の棟札も以前はあったということですので、奥院はこの頃に建てられたものと推測されます。建築様式も江戸時代初期の特徴を示していて、このことを裏付けています。 観音堂奥院は鳥越山の中腹の岩屋を利用して作られたもので、このような造り方を懸造りといいます。正面は四間で、床には板が張ってありますが、壁や天井は岩肌がそのまま使われています。堂のあちこちにお札が貼りつけてあり、参詣者が多く、今も信仰の根強いことを窺わせます。 平成5年3月31日 一戸町教育委員会 次に由来です。 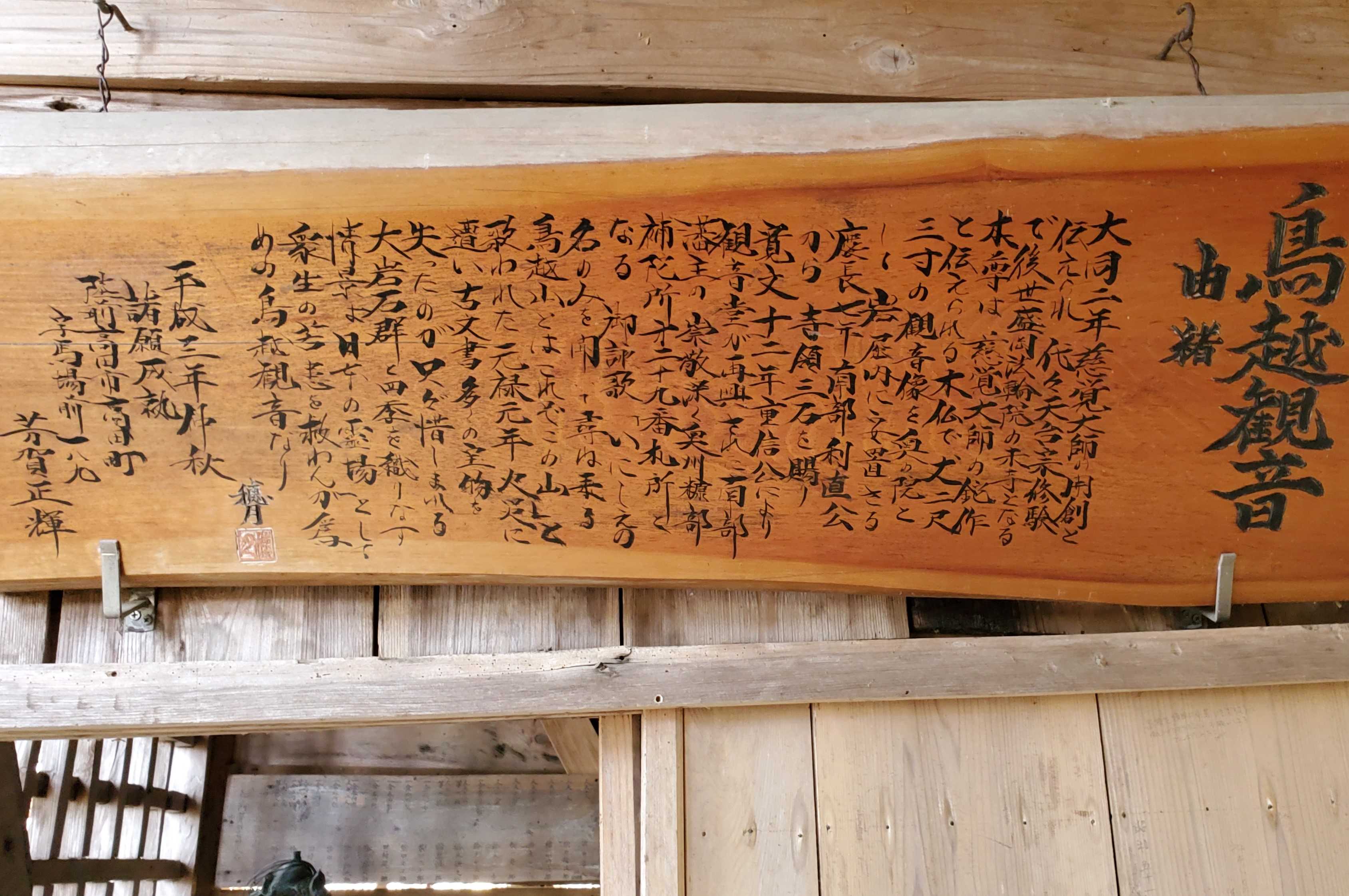 鳥越観音 由緒 大同2年慈覚大師の開創と伝えられ、代々天台宗修験で後世盛岡法輪院の末寺となる。 本尊は慈覚大師の鉈作と伝えられる木仏で、丈二尺三寸の観音像を奥之院として岩窟内に安置さる。 慶長7年南部利直公から寺領3石を賜り、寛文12年重信公により観音堂が再興された。南部藩主の崇敬深く奥州糠部補陀所第二十九番札所となる。御詠歌「いにしえの 名のみを聞いて尋ね来る 鳥越山とは これぞこの山」と歌われた。元禄元年火災に遭い古文書多くの宝物を失ったのが只々惜しまれる。 大岩石群と四季を織りなす情景は日*の霊場として衆生の苦患を救わんが為の鳥越観音なり。 奥院です。 この奥院にはもともと大蛇が住んでいたという伝説が残っており、開基の慈覚大師によって成敗され敗走、以降馬淵川の主となり、大渕大明神と呼ばれたそうです。こうした伝説の背景には、もともと当地に住んでいた民族が中央によって征伐されたとか、そうした物語が基になっていそうですよね。昔に何があったのか知る術はもうありませんが、そうしたことに思いをはせながら巡礼するのもまた一興です  御詠歌 鳥越の 御山は須弥峯観世音寺 如日虚空住 念彼観音 とりごえの みやまはしゅみほうかんぜんおんじ にょにちこくじゅう ねんぴかんのん 本尊:聖観音 आर्यावलोकितेश्वर 今回貰った御朱印です。御朱印は駐車場奥の別当宅でいただけます。 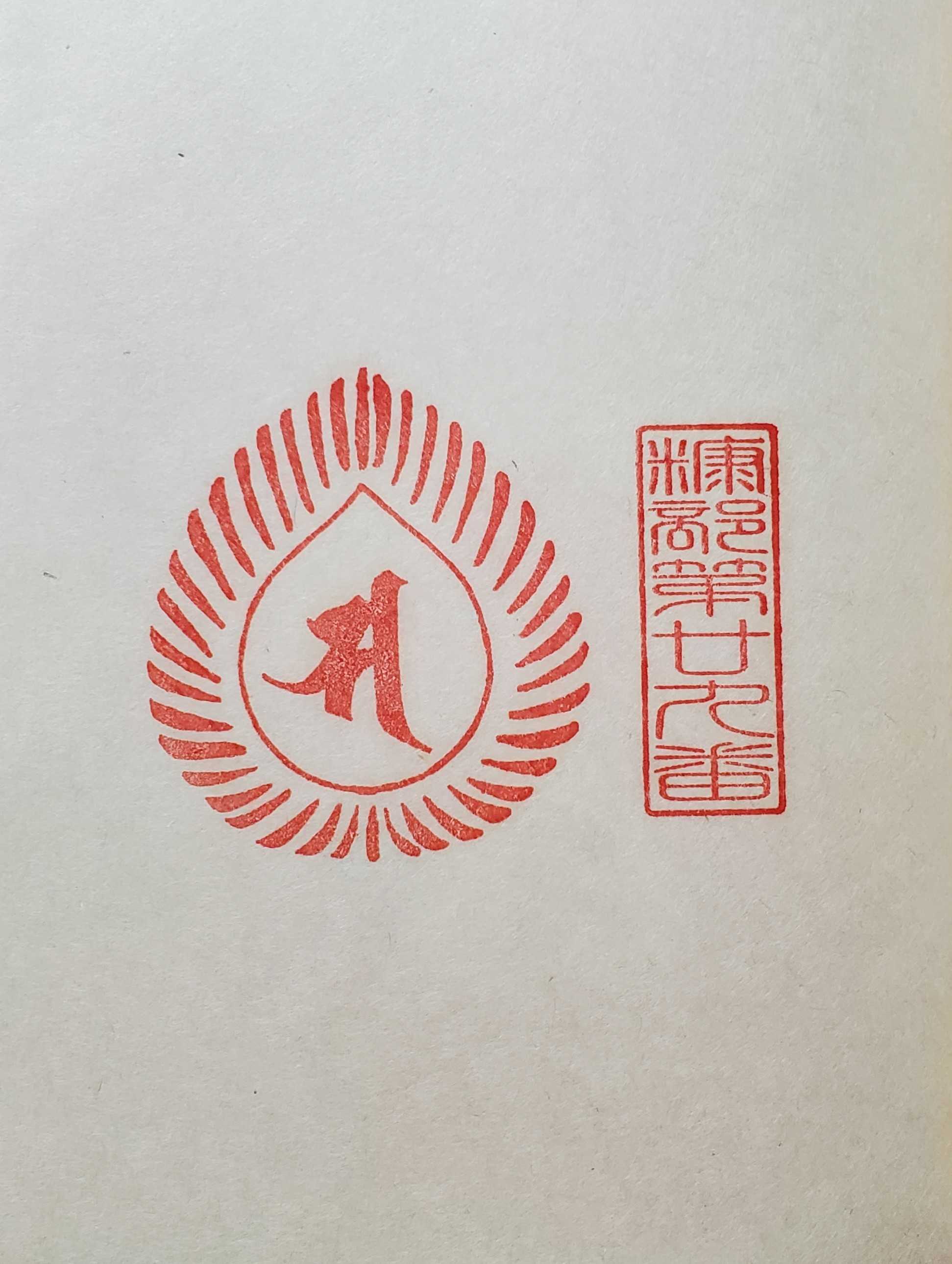 以上です。 次の記事 三十番札所:朝日観音 白馬伝説の観音堂 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.06.23 18:36:47
コメント(0) | コメントを書く
[奥州南部糠部三十三観音霊場] カテゴリの最新記事
|