
|
|
|
カテゴリ:戦国
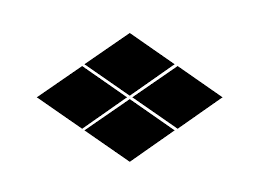 『勝山記』によれば、都留郡においても同年12月に吉田山城(富士吉田市)を拠点とした今川勢と郡内衆が戦い、永正14年(1517)1月12日に吉田山城が陥落すると、郡内衆と今川氏の間で和睦が成立した。 この頃、今川氏は遠江国において大河内貞綱・斯波義達が引間城攻めを行っていたため今川氏親は信虎との和睦に転じ、『勝山記』『宗長手記』『宇津山記』によれば、武田・今川間は連歌師の宗長が仲介し3月2日に和睦が成立し、今川氏は甲斐から退去した。なお、永正15年は今川氏の間でも和睦が成立している。 永正17年(1520))に信虎は大井氏とも和睦し、信達の娘(大井夫人)を正室に迎える。 甲斐国の守護所は信昌・信縄期には石和館(甲府市川田町・笛吹市石和町)に置かれていたが、『王代記』によれば、信虎は永正15年(1518)に信虎は守護所を相川扇状地の甲府(甲府市古府中町)へ移転する。 『高白斎記』によれば、信虎は永正16年(1519年)8月15日から甲府に居館である躑躅ヶ崎館の建設に着手し、城下町(武田城下町)を整備し、有力国衆ら家臣を集住させた。 『高白斎記』によれば、詰城として躑躅ヶ崎館東北の丸山に要害山城(甲府市上積翠寺町)を築城した。永正16年4月には今井信是が信虎に降伏し、甲府移転は信是の降伏を契機にしていると考えられている。 『高白斎記』によれば、有力国衆は甲府への集住に抵抗し、永正17年(1520)5月には「栗原殿」(栗原信重か)・今井信是・大井信達らが甲府を退去する事件が発生し、信虎は6月8日に都塚(笛吹市一宮町本都塚・北都塚)において栗原勢を撃破し、さらに6月10日には今諏訪(南アルプス市今諏訪)において今井・大井勢を撃破している。 『塩山向嶽庵小年代記』によれば、永正18年/大永元年(1520)27日に今川氏配下の土方城主・福島正成を主体とする今川勢が富士川沿いに河内地方へ侵攻した(福島乱入事件)。 同年8月頃には今川・武田両軍の間で合戦が発生しており、この間に空白期間があることから、穴山氏当主・信風が今川方に服属していたと考えられている。 『勝山記』によれば、同年8月下旬に信虎は河内へ出兵すると、今川方の富士氏を撃破している。 これにより穴山氏は武田家に降伏し、信虎は駿河にいた「武田八郎」(信風の子・信友か)の甲斐帰国を許している。 9月には今川勢が攻勢を強め、9月16日には大井氏の居城である富田城(南アルプス市戸田)を陥落させた。信虎は要害山城へ退き、10月16日に飯田河原の戦い(甲府市飯田町)で今川勢を撃退し、勝山城(甲府市上曽根)に退かせる。 さらに11月23日に上条河原の戦い(甲斐市島上条一帯)で福嶋氏を打ち取り、今川勢を駿河へ駆逐した。 この最中に、要害山城では嫡男・晴信が産まれている。信虎は穴山氏も服属させるが、福嶋勢は翌年正月の武田・今川間の和睦まで甲斐国内で抵抗を続けた。 大永元年には信虎自身の左京大夫への補任と叙爵を室町幕府に対し申請し、『歴名土代』によれば、同年4月に政所執事の伊勢貞忠が伝奏の広橋守光とともにこれを奏し、信虎は従五位下に叙せられる。 武田家では信重・信守・信昌三代が「形部大輔」の官途名を名乗っていたが、信虎は自身の官途を改める意志を持っていたことが指摘される。また、嫡男の晴信の幼名も歴代の「五郎」に対して「太郎」を用いている。 今川勢を撃退した大永2年(1522)に信虎は家臣とともに身延山久遠寺へ参詣し「御授法」を受けている。 また、『勝山記』によれば、信虎は身延山参詣の後に富士山への登山を行っている。信虎は富士山頂を一周する「御鉢廻り(八葉、八嶺)」を行っている。 「お鉢廻り」は富士山頂の高所を八枚の蓮弁に見立て「八葉」と称し、後には富士山頂の八葉を廻る御鉢参りの習俗が成立する。信虎の富士登山は御鉢参りの習俗が戦国期に遡る事例として注目されている。 信虎の身延山参詣と富士登山については、甲斐一国の平定を成し遂げ駿河今川氏、相模後北条氏との緊張関係が続いている情勢から、自身の地位を確立するための宗教的示威行為であると考えられている。 また、大永2年には前年に信虎が甲府における菩提寺として建立した大泉寺に国内の僧侶を集めて夏安居を開催したのも、その一環とされる。 「両上杉氏との同盟と対外勢力との戦い」 大永年間には対外勢力との抗争が本格化する。信虎は両上杉と同盟し伊勢氏(後北条氏)と敵対する信縄期の外交路線を継承し、大永4年(1524)2月には両上杉氏支援のため都留郡猿橋(大月市猿橋町猿橋)に軍勢を集め、相模国奥三保(神奈川県相模原市)へ侵攻する。 同年3月にも武蔵国秩父へ出兵し、関東管領の上杉憲房と対面している。なお、憲房は3月25日に死去し、家督相続を巡り混乱が生じている。 『高白斎記』によれば同年7月20日には北条方の武蔵岩付城(埼玉県さいたま市岩槻区太田)・太田資高を攻める。 信虎は遠征から帰国すると翌大永5年(1525)にかけて北条氏綱と和睦する。 まもなく氏綱は越後国の長尾為景と連携して上野侵攻を企図し信虎に領内通過を要請するが、信虎は山内上杉氏に配慮してこれを拒絶し、和睦は破綻する。 『勝山記』によれば、信虎は山内上杉氏の家督を預かった上杉憲寛とともに相模津久井城(相模原市緑区)を攻撃している。『神使御頭之日記』によれば、同年4月1日には諏訪頼満に追われた諏訪大社下社の金刺氏と推定されている「諏訪殿」が甲府へ亡命し、信虎はこの「諏訪殿」を庇護して諏訪へ出兵し、8月晦日に諏訪勢と甲信国境で衝突するが、武田方は荻原備中守が戦死し大敗した。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024年04月24日 10時18分05秒
コメント(0) | コメントを書く
[戦国] カテゴリの最新記事
|