
|
|
|
カテゴリ:アルゴリズムの時代
5/25の日本新聞労働組合連合会のイベントにパネラーとして参加することになっている。 そのサイトから、「スポンタつーのは、誰やねん」とやってくる人のことも考えつつ、書き進めることにする。 ☆ 安心して欲しい、歌川先生には失礼になるかもしれぬが、「新聞のなるなる日」はこないと思う。 「ネットは新聞を殺すのか」といえば、湯川氏に失礼になるかもしれぬが、消費者たちは、新聞を抹殺・根絶やしにはしない。何故なら、新聞がまったく世の中から存在しない不都合を感じるから…。 勿論、それが、いまの新聞社の組織や新聞人の給料を保証するわけではないが…。 ☆ さて、ネットがリアルに太刀打ちできないのは、当然のことである。 リアルなパワーは、当事者(ステークホルダー)のパワーである。 当事者とは、生産者であり、NIMBYでない人・直接被害者である。 だが、日本のコミュニティーにおいて、殆どの事象における、当事者の割合は、99:1以下だろう…。 たとえば、日本の人口が一億三千万人。その1/10が新聞の消費者として1300万人。その1/100はといえば13万人。新聞従事者の数は把握していないが、無理のない数字かもしれぬ…。 どちらにしても、数的に圧倒的に劣る生産者が消費者に勝てるはずはない。 では何故、いままで、生産者が消費者に勝ててきたか。 その理由は、次の三種である。 ☆
1.に関して…。 たとえば、板ガラス業界。 寡占状態になっているのは、あまりにガラス工場の建設に関わる費用が高いからである。 * 2.に関して…。 たとえば、けちなラーメン屋のオヤジは、スープの出汁の中身を教えない。 何故なら、駄目なラーメン屋のオヤジは、レシピ以上のスキルを持たないからだ。レシピで伝わるようなスキルが料理人のスキルでないのに…。 * 3.に関して…。 アマチュアとプロでどちらがスキルがあるかといえば、それは何ともいえない。 アマチュアよりもスキルが劣るプロもいるし、プロよりもスキルが高いアマチュアもいる。 私は映像のプロだが、予算の範囲以上の仕事をしないことをモットーにしている。だから、アマチュアの作品よりも、手数が少ない。それをして、私の作品が手抜きであると断ずることもできる…。 ☆ さて、表題の「新聞vsネット」である。 新聞をおおまかに捉えて報道機関・情報産業としても、答えは同じだ。 要約すると、次のよう…。
1.に関して…。 インターネットでは、ほとんど費用ゼロで情報発信できることは言うまでもない。 * 2.に関して…。 新聞社は独自のネットワークで豊富な情報を得ている。一方の消費者の持っている情報は社会全体が持っている情報と等価である。 その情報がインターネットによって、ネットワークでつながれるのだから、新聞社は太刀打ちはできぬ。 その上、新聞社には、社会的影響力を勘案しなければならないため、未確認情報を発信することはできぬ。また、公官庁からの縛りもある。 ならば、情報ディーリングの自由度について、消費者に劣るのは当然のことだ。 * 3.に関して…。 新聞人は専門教育を受けて、文章修行をする。モラルにおいて、知識において、技術において、そのスキルは消費者の追随を許すものではない。 と、百歩譲って考えたとしても、それは個としての場合だけである。
☆ 結論をいえば、公愚・エリート愚とでもいうものを発生している原因は、単一のアルゴリズムでしか、意思決定・代表決定ができぬ組織構造で営まれているからである。 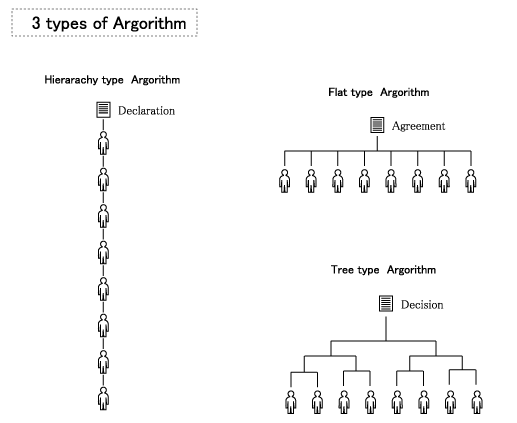 たしかに、1:99のパワー差はある。 だが、それは言っても仕方のないことだし、世の中のすべての人が新聞人になる時間的余裕などないのだから、言うべきではないだろう。 ということで、新聞vsネットという図を作成した。 図は諸要素を書き込んだつもりであるが、総覧的になってしまった。 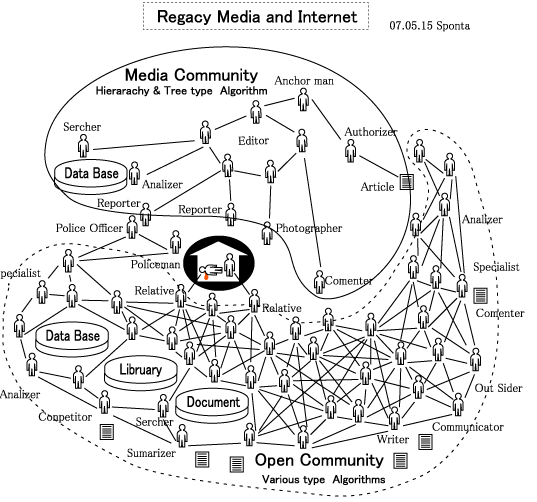 この図に示されていることで重要なことは、新聞は、一つの事件をさまざまな視点から一つの記事(言論)に仕立てる。 しかし、ネット言論は、一つの事件からさまざまな言論を生むということ。
その差は大きいのである。 
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007年05月16日 06時30分36秒
[アルゴリズムの時代] カテゴリの最新記事
|