
|
|
|
カテゴリ:探訪 [再録]
 弘善館・菊水飴本舗の次の探訪地は「ウッディパル余呉」でした。 ここは「森とのふれあい」をテーマにして、さまざまな屋外レクレーション施設があるところです。木工体験のできる工房、テニスコート、パターゴルフ、アスレチックなどなど。 今回ここに立ち寄ったのは、「近江水の宝」という視点から、地味だけれど着実な活動を進めている事例の紹介でした。 つまり、関係者以外は絶対に見逃してしまいそうな、小さな設備があるのです。   これです。「ピコ水力発電」という実用実験(?)施設。わずかですが500Wと言う起電力の設備。小さな小屋の中に、上流からパイプで導水された水力発電装置がちょこっと入っているのです。小屋が大きめなのは冬期の積雪などを考えた結果だとか。その心配がなければ、もっと小さな建屋でもOKなのです。 これで何ができる?  実はすぐ近くにある「ツブリナハウス」というこれまた小規模野菜栽培工場(ちょっと大げさ・・・)に必要な電力が賄えているのだとか。エコな試みです。  すぐ隣に小さな小さな赤子山スキー場があります。幼児や小さな子供たちのスキー場としては十分ですね。前方の小高くなった斜面のところから、須恵器が出土しているそうです。漢字を見て「あかごやま」と読んだのですが、地元では「あこやま」と呼ぶそうです。  下丹生地区を高時川に沿って少し北上すると、「茶わん祭の館」があります。 駐車スペースはけっこう大きいです。  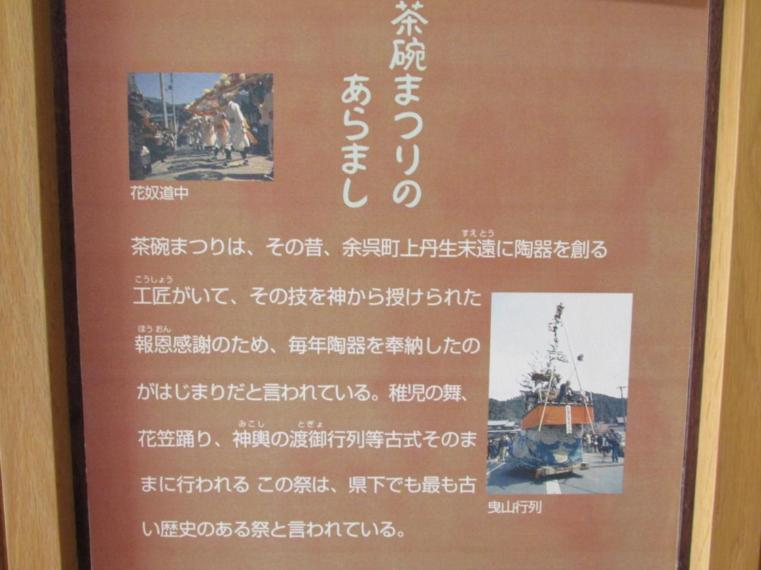   館内には「茶わん祭」の山車のシンボル展示がフロアー中央にあり、上部に実物を組み入れた曳山レプリカだそうです。 山車の最上部分の飾りは絶妙のバランスで保たれた形です。曲芸まがいの飾りです。  これが山車の見送り幕。一例ですが1671年に購入された綴錦見送り幕が現存するとか。 これは余呉町・丹生神社の大祭で、4年に一度行われているそうです。上丹生は良質の陶土の産地で、「名工末遠春長は、優れた陶土と技を自分に授けてくださった神に感謝し、毎年欠かさずに新しい陶器を神社に奉納したといいます。これが『茶わん祭』の由縁です」(資料1) 探訪した翌年、つまり2014年5月4日に「丹生茶わん祭り」が無事終了しています。奇しくも来年2018年5月4日に、このお祭りの実施が予定されていることになりますね。   3基の曳山が丹生神社の摂社・八幡神社に渡御するそうですが、この部分拡大写真に見られるように、囲いの手すり部分などが、陶器をつなぎ合わせた飾りとなっています。「数千を超える陶器をつなぎ合わせた山車飾りが取り付けられ、その高さは約10mにもおよびます」(資料1)  実物山車の前方に、「曳山行列ミニ・ジオラマ」のショーケースがあります。縮尺20分の1で作製されていて、行列全体の構成、人の配置や役割などが図入りで説明されています。写真は、行列の最後尾を撮ってみたものです。 三方の壁面沿いに祭り関連の諸道具や衣装が展示されています。そして、このお祭りについてのわかりやすい説明パネルが掲示されています。   この花笠を使い花奴が花笠踊りを披露して、お祭りの花形になります。    現存する太鼓や鼓は天保年間に購入されたものだとか。中世の拍物(はやしもの)が持っている特色をすべて揃えているそうです。  館の前の通りを北に眺めると、前方に七々頭岳がそびえています。  高時川の上流域は丹生川と呼ばれているそうです。この丹生川沿いの道路を遡上していくと、妙理の里があります。高時川の支流妙理川沿いに建てられた野外活動施設。 その少し北、余呉町菅並に曹洞宗の塩谷山洞寿院があります。ここが最後の探訪地です。  洞寿(/壽)院への道の入口 「曹洞宗洞壽院」の標識の側面には参禅研修道場と表記されています。かつては近江における曹洞宗の一中心地になりました。    山門を入ると、一対の苔むした石塔や、右手に六地蔵尊石仏などがあります。  これが本殿。1406(応永13)年、如仲禅師(道元禅師より八代目の法孫)の開山。祝山(ほりやま:現西浅井町)に洞春庵を創建されていたのが、この地に移ってきたそうです。湖北の寺では最北端に位置します。 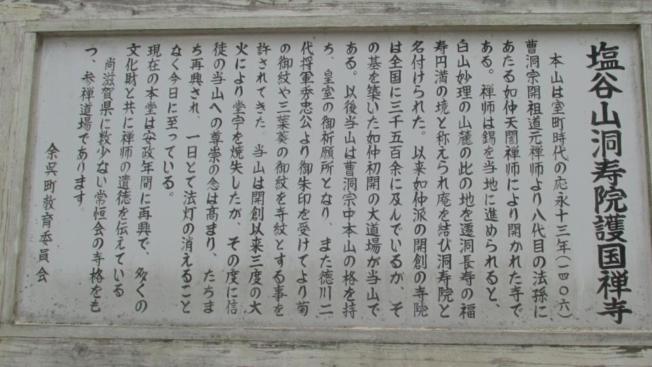 白山妙理の山麓の地であり、白山妙理権現より塩泉を施され塩谷山と号し、遷洞長壽(幽仙に移って長生きする)というフレーズから洞壽という名が由来するとか。 本尊に釈迦三尊像が祀られ、大日如来像、開山の如仲禅師像、十六羅漢像なども祀られています。(資料2)この大日如来像は管山寺からの由来だそうです。 残念ですが本堂内は撮影禁止でした。開創以来3度の大火に遭い、現在の本堂は安政年間に再建されたものだそうです。柱に施された彫刻や欄間の透かし彫りなども見応えがあります。 1788(天明8)年、当寺の住職が京都霊鑑寺の戒師を努めて以来、菊の紋章を本堂につけることが許されたとか。德川秀忠から朱印地三十石の領地を受け、葵の紋章を寺紋とすることが許されたといいます。本堂の棟瓦のところに、それら紋章が輝いていました。また、座禅堂の屋根には曹洞宗の宗紋が輝いています。  昔は「越前永平寺・能登総持寺へのとおり道・禅道場」として栄えたようです。まだ真新しくみえる座禅堂は本堂に向かって左手にあります。入口から撮らせていただけたのがこの写真。一般の人の参禅体験ができるそうです。(資料2) こんな草深い地に、こんな大きな禅寺が・・・・という感じを受けます。永平寺へのとおり道ということで、なんとなくわかるという思いです。永平寺に参禅修行するまえの一行程として、この地で禅修行に励むという位置づけだった側面があるのかもしれません。 これで今回の探訪地のご紹介は終わりです。 ご一読ありがとうございます。 参照資料 1) 「茶わん祭の館」(余呉町交流促進センター)リーフレット 入館時に入手 2) 探訪当日配布のレジュメ資料 【 付記 】 「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。 ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。 再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。 少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。 補遺 ウディパル余呉 公式サイト 丹生茶わん祭り 滋賀県長浜市余呉町上丹生-丹生神社 丹生神社 :滋賀県観光情報 日本古典奇術「釣り物秘伝」について 河合勝・斎藤修啓共著論文 P103-105に、「山飾りについて」という見出しで、論じられています。 Niu Chawan Matsuri Festival 丹生 茶わん祭り :YouTube 丹生茶わん祭り :YouTube 丹生茶わん祭り 神子の舞 :YouTube 丹生茶わん祭り 扇の舞 :YouTube 丹生茶わん祭り 鈴の舞 :YouTube 釈迦三尊 :ウィキペディア 曹洞宗 公式サイト 洞寿院所蔵の禅師頂相図 妙理の里条例 :「長浜市」 妙理の里 :「polish+」 『妙理の里』風景(その1) :YouTube 滋賀県余呉町「妙理(みょうり)の里」の取り組み :「林野庁」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。 その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪 [再録] 滋賀・湖北 余呉湖今昔と周辺地域 -1 余呉湖の天女羽衣伝説 へ 探訪 [再録] 滋賀・湖北 余呉湖今昔と周辺地域 -2 余呉湖・桐畑太夫の羽衣伝説&菊石姫伝説 へ 探訪 [再録] 滋賀・湖北 余呉湖今昔と周辺地域 -3 蛇の枕石、あじさい園、路通の句碑、七本槍の地 へ 探訪 [再録] 滋賀・湖北 余呉湖今昔と周辺地域 -4 飯浦送水/余呉湖放水・隧道、烏帽子岩・お膳岩、乎弥神社 へ 探訪 [再録] 滋賀・湖北 余呉湖今昔と周辺地域 -5 意波閇神社、里坊弘善館、菊水飴本舗 へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2017.10.30 18:00:09
コメント(0) | コメントを書く
[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事
|