
|
|
|
カテゴリ:クラシック音楽
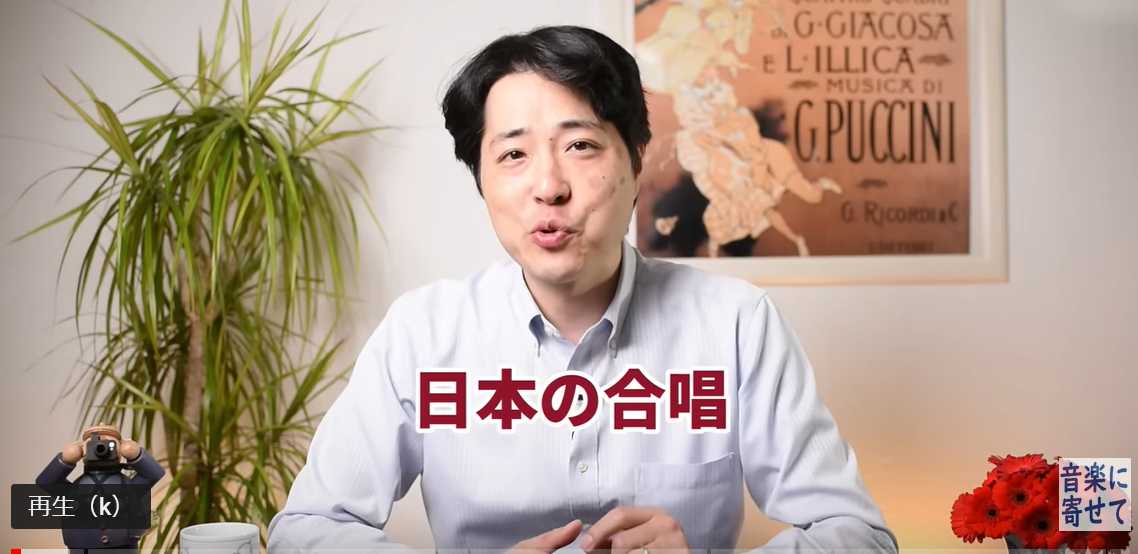 金曜日の夕方から右の耳が変なので音楽を聴く気にならない。 以前患ったメニエール病の再発かと思い、昨日病院に行って検査してもらった。 聴力検査の結果、少しだけ聴力が落ちているそうだ。 どうやら回復途中で、点滴もいらないとのこと。 幸い軽かったので、良かったのだが、症状が重くて、病院に行っていなければ、土日を挟んで悪化していたかもしれない。 やはり、この病気は病院に早く行くに限る。 そういえば、プールで泳いでいるときに、時々耳が詰まったような状態になることがあったので、あれが前兆だったのかもしれない。 ということで、今回は音楽を聴く気になれないので、別な話題。 最近よく見ているドイツ在住の車田和寿氏の「音楽に寄せて」の43回目の「独自の道を歩む日本(中高生)の合唱」という動画について。 氏はザクセン国立歌劇場専属の歌手として活躍していて、このチャンネルを見始めた頃は音楽史の話や演奏家の話が多かった。 最近、吹奏楽や合唱の問題、音楽大学の就職事情などについて持論を述べている動画が出て来て興味深く拝見させていただいている。 吹奏楽については目新しいことはなかったが、氏の意見、特にコンクール偏重で、視野が狭いという指摘には全面的に賛同できるものだった。 学校教育での合唱については全く不案内だったのだが、この動画は学校教育での合唱特有の問題点があからさまに語られていて、大変興味深い。 以下、少し長くなるが、文字起こしの要約。 『中高生の合唱は独自の道を歩んで独特の音楽が出来上がってしまっている。 日本の中高生の合唱において非常に独特なのがその発声。 歌うジャンルにおいて好まれる声の音色は少しずつ違ってくるのだが、日本の中高生がやってる合唱というのは、同じ合唱でも、これらの合唱とは全く違った音色で歌っている。 音色の違う理由は発声が全く違うからだ。 中高生の合唱で行われている発声は非常に独特だ。 歴史の中でいろんな合唱が誕生したが、それらと全く違う発声で歌っているのが中高生の合唱だ。 中高生の合唱の発声というのはものすごく不自然だ。 一般に少年には少年の声、中高生には中高生の声、大人には大人の声がある。 中高生の声というのは大人への成長過程なので本来未熟なものだ。 中高生が声楽の個人 レッスンに通ったとしても、良くて勉強中ですといったような声しか出ない。 だから中高生に合唱を指導するならば、この本来未熟で不揃いな姿を考慮しなければならない。つまり、ある程度許容した範囲で合唱をやるのが中高生にとっては 自然な姿なのだ。 そうすると中高生らしい合唱になって、大人はそれを見て微笑ましく思うのだ。 中高生がコンクールで勝ち負けを争ったら、ほとんどがリズムや音程の正確さで競われることになる。 その結果、この不揃いさ、未熟さというものが許容できなくなってしまう。 一人ひとりの声の響きがばらばらなことを認めていては、コンクールでは勝てなくなってしまうのだ。 そこで未熟さ不揃いさを解消しようと、皆できるだけ同じ声を出そうとする。 本来声は一人一人違うものなので、合唱部では無理やり同じ声にしようとするので間違った方法に耐えることになる。 本来は正しい方法だったら歌声は一人一人違ったことになる。 それを無理に同じような声にしようとするので、殆どの場合は舌を奥に引っ込めて、さらに喉を上げて歌うことになる。→皆同じ癖で歌うことになる 裏を返せば、誰1人として自分の本当の声では歌っていないことになる。 ちなみに、モノマネっていうものは何なのか。 実はモノマネというのは曲を真似ることだ。 多かれ少なかれ人には話し方とか歌い方に癖があり、そういった曲をうまく 捉えて誇張すると良いモノマネになる。 だから中高生の合唱は上手い団体ほど誰かの曲を真似した同じような声で歌ってしまう。 このような、曲を真似した歌い方は、声楽的な観点から外れた、ものすごく不自然な姿だ。 中高生には、どんなに頑張ったって大人のプロの合唱団 のような声は出せない。 それは声が成長するにはものすごい時間が かかるからだ。 ほとんどの中高生は、合唱っていうのは、こうじゃなきゃいけないっていうイメージを真似した発声だ。 コンクールでこうした未熟さ不揃いさを 排除したことの影響というのは発声面だけ じゃなくて音楽面にも現れる。 コンクールで勝とうと思ったら、 いかに隣の人とぴったり合わせることが できるかというのが大事になる。 その結果、合唱においては自分の個性を消して隣の人と合わせていくという方向になっていく。 合唱はだいたい4 part から 8パートぐらいしかないので、周りと合わせようとする比重はものすごく大きい。 ちゃんとした発声で歌えば 歌うほど、声はどんどん大きくなる。 中高生の合唱においてはこういう人は邪魔になってしまう。 結果的には自分を消して周りと合わせるという音楽が癖になってしまう。 日本人は自分を消して周りと合わせることに喜びを感じてしまう傾向が強い。 しかし自分を消して演奏した音楽には周り の人を感動させる力っていうのはあまりない。 演奏というものは、自分ではやりすぎだと思うぐらいであって、初めて人の心に届く。 だから本当は自分を抑えたり消したりすることなく一人ひとりが自分の声に感情のせるような歌い方をしないといけない。 コンクールで上を目指すほうが、綺麗だけど、どこか人の心にまでは届きにくい 音になってしまう傾向が強い。 それでも中高生というのは一生懸命なんで、なんとかして、その心の中にある感情を届けようとする。 しかし抑えて歌っているので、声でそれを届けることはできない。 そうするとそのしわ寄せが顔の表情に現れる。 顔で表現すれば、その感情を観客に届けることができると思って、一生懸命、顔で表情を作ろうとする。 その結果、大体目を見開いたような顔をして笑顔を作った不自然な顔になってしまう。 ところが、顔にいくら表情がついていても、目に光が宿っていないとやっぱりそれは不自然に 見える。 』 この内容を見ると、生徒さんたちは現在の学校教育における合唱のあり方の犠牲者になっているといっても言い過ぎではないと思う。 自分の個性を押さえつけられたうえで、別な手段として表情で一生懸命訴えかけるしかないのだろう。 なにか涙の出てくるような内容だ。 管理人も前に中高校生の合唱をテレビで見て、異様に目を大きく開いて表情を作って歌っている女子学生を見たときに、違和感を持ったことがある。 以前有名な児童合唱団のコンサートを観に行ったときは、そういう異様な風景は見られなかった。 おそらく、コンクールという制限がないので、指導に対する考え方が学校教育とは全く違うのだろう。 管理人は学校では吹奏楽をしていたが、それほど実力の高い学校ではなかったので、揃えるということにそれほど注意していたことはない。 また、ホルンだったので、ハーモニーが多く、揃える意識はクラリネットに比べると、ないに等しかっただろう。 コンクールでいい成績をとることが大事なのか、生徒に音楽の喜びを体験させることが大事なのか、難し問題だが、せめて卒業後に音楽が嫌いになるようなことだけは、してほしくないと思う。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2022年08月28日 15時00分34秒
コメント(0) | コメントを書く
[クラシック音楽] カテゴリの最新記事
|