
|
|
|
全て
| Non-group
| DiaryScene
| Economy
| Education
| Management
| Society
| Ramble
| History
| Health
| Sports
| Life
| politics
| World
| mountain
| car&drive
| lecture
| flowers
| culture
| technology
| science
| environment
| event
| view
| travel
| topics
| gardening
| museum
| weather
| america
| china
| training
| bird
| food
| book
| calamity
| Energy
| corona
カテゴリ:Management
仕事を苦痛と感じるニッポン人の比率が世界でも最高なのだそうです…。
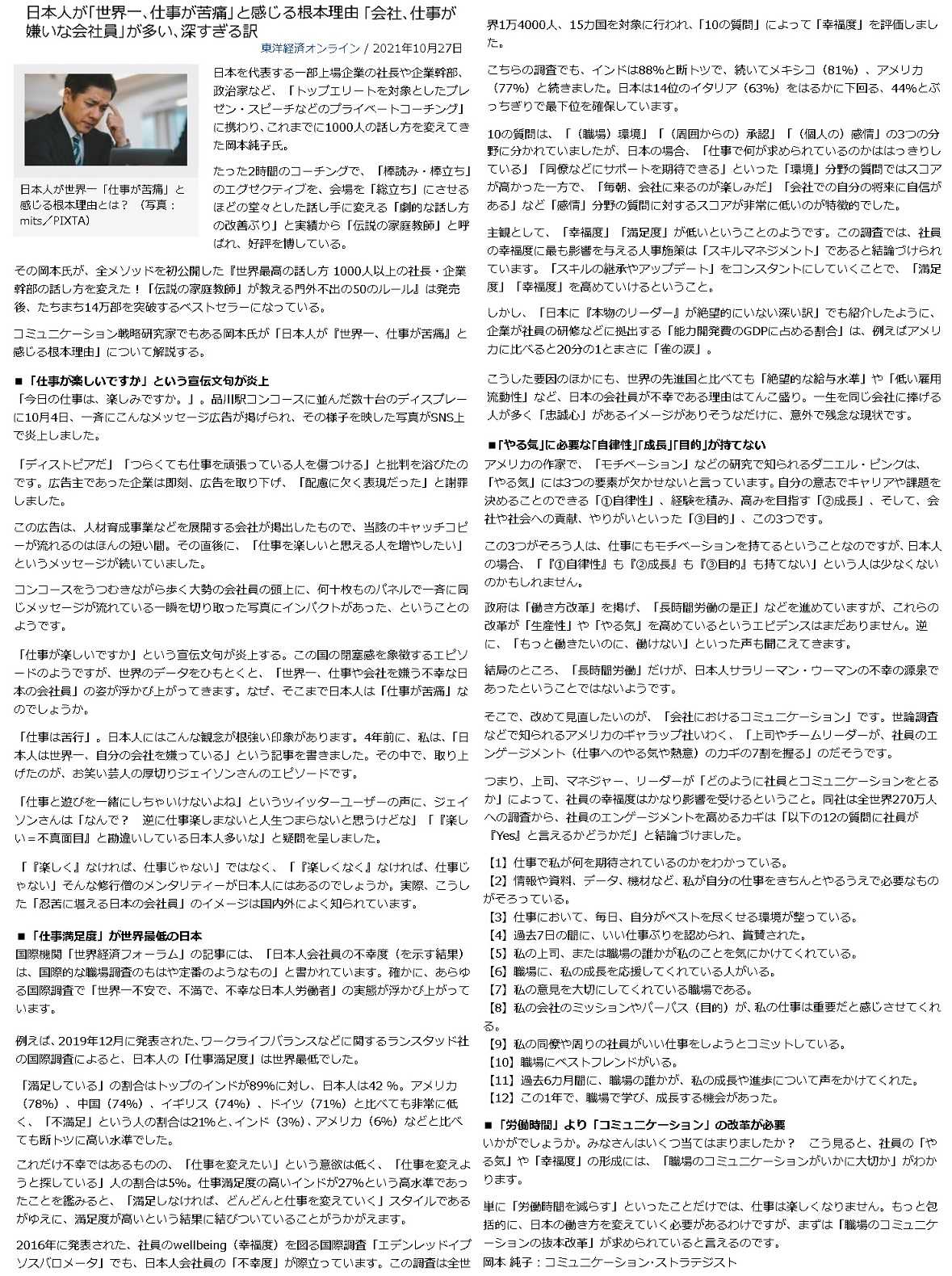 上の記事では、ニッポン人の従業員の仕事への苦痛観が世界で最も高いと問題提起して、それを仕事改革の根拠にするべしと指摘しているように思われます。 なぜに仕事に苦痛を感じるのかについての分析があれば、この議論はより説得性をもつにいたったのじゃないかと云いたいですが、それはないものねだりになるのかも…。 私見では、ニッポンの職場での”仕事の割り振り”と云いますか”与え方”が概括的または包括的で、そこに”苦痛”の生じる根があるように思っています。仕事の全体構成が明らかにされておらずに、それに基づいた”部分”の従業員への役割分担ができていない。 そのために、従業員間の”協働”のありようがあいまい化されてしまい、明確な支援関係の成立が為しえないために、個別的ワーカーの負担が過大になってしまいがちになるし、仕事上の目標も到達度も評価もあいまいに失してしまう。 この関係性の中において仕事上の”苦痛”とか”楽しめなさ”が湧き出てしまうのでしょう。ワーク分析、それの部分集合体としてのジョブの分担、したがって仕事の内容の明確化、その進度や達成度のチェック、それのもとでの助言や支援など…。ここに仕事の自律性と自己評価と達成感の基盤が創り出されるのです。 ここにも”思考の論理性”の適用が求められますね。それが低レベルであるほど、仕事の苦痛は消えないし乗り超えられないでしょう。論理性こそ”要”なのです。まずは、ヒトづくりから始めねば…。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
November 6, 2021 07:25:18 AM
コメント(0) | コメントを書く
[Management] カテゴリの最新記事
|