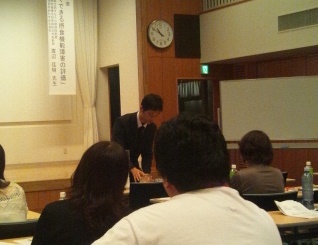今回、顔面神経麻痺になって、咀嚼という作業が如何に顔の色々な機能を使っているかを体感しました。
あごが動いて噛むだけでは咀嚼という作業はできず、舌や口腔内の様々な筋肉を使っているのです。
顔面が麻痺して頬の筋肉が動かないだけで非常に不自由しました。
同様に嚥下(飲み込むこと)も不自由になります。
咀嚼ほどではないですが、ひどいときはよくむせました。
そんなこともあって、ある方から介護講習会に誘われました。
内容は「今すぐ出来る摂食機能障害の評価」ということで、日本障害者歯科学会の指導医でもある渡辺佳樹先生の講演でした。

内容は専門外の私にはわかりにくい部分が多かったですが、こういう機会でもなければ学べないことばかりでしたし、新しい発見もあり、非常に参考になりました。
わかったことを整理するとこんな感じです。
1.嚥下を円滑に行うには姿勢が大事であること
座位であれば少し顔を前に傾けた方がよい(頸部前屈)
ねたきりの場合はすこし体を起こして、枕などで頭を上げる
=>こうすると食道の入口が開くようです。
2.食べるペース(飲み込むペース)に注意すること
確かに飲み込むタイミングと食べ物を口に入れるタイミングが悪かったりでむせてしまうことがあります。
3.口腔内のケア
これはホントに実感しています。
顔面麻痺では唇と歯の間に食物が入ってしまうと舌で取り出せないので、歯茎の根本あたりに食べ物が残ってしまいます。
高齢で咀嚼の機能が落ちている方も当然、そうですよね。
口腔内に問題があると唾液の分泌が悪かったり、味覚にも障害があったりするので、余計円滑に食べることができなくなるのはうなずけることです。
そして、大きな問題として誤嚥性肺炎などの要因になります。
肺炎については、この話を聞くまで知らなかったのですが、単に肺が炎症を起こすのではなく、細菌が原因となっているらしいです。
一般の肺炎ではマイコプラズマとか黄色ブドウ球菌とかよく名前だけは耳にしますが、誤嚥性肺炎の場合は、特に口腔内にいる細菌が唾液を誤嚥することで胃に運ばれて起こるようです。
特に誤嚥性肺炎を起こす細菌は通性嫌気性菌というそうですが、酸素の少ないところにいるものの、酸素があると増殖する性質があるようです。
つまり、口腔内にいるときは酸素が少ないのであまり増殖しませんが、肺の中で空気に触れると増殖して肺の炎症を起こすのですね。
4.口腔内の乾燥にも注意
これも確かに...ですが、暑いコーヒーを飲むときに空気を吸いすぎてのどの奥が乾いて、むせってしまうことがあります(私だけ?)
口腔乾燥に対してはこれをケアするジェルなどがあるようです。

口腔用保湿ジェル マウスモイスト★税込1980円以上で送料無料★口腔用保湿ジェル マウスモイスト(20g)
5.そして食事の選択
- 咀嚼しやすいのもの
- 咽頭を通過しやすいもの・・・残留しやすい豆腐や変形しやすいこんにゃくなどはNG
- 食塊を形成しやすいもの・・・肉とかイカなどはNG
- 嚥下反射を誘発しやすいもの・・・一口量と温度に注意
一口量はカレースプーン7分目程度で少なすぎでもNG
温度は冷たい方が嚥下しやすいとのことでしたが、冷たいものばかりでは高齢者には向かないので、交互に食べると良いとの話でした。
さて、嚥下反射について書き漏れましたが、咀嚼すると口の中で口蓋(口の上側の部分)にそって梨上窩と呼ばれるのどの奥の部分(咽頭の上)に落ちていきます。
この口蓋には神経が集中していて、ここを食べ物が通ることで咽頭へ「食べ物が行くぞ」という信号が送られるとのことです。
したがって、急いで飲み込んでしまうと咽頭に信号が行く前に食べ物が通過してしまうので、食道の入口が開かず、つまってしまうらしいです。
よく食べ物がのどに詰まったら胸をたたいたりしますが、これは何の意味もなく、静かに咽頭に信号が行くのを待った方が良いとおっしゃっていました。
そんなこんなで、まだまだ色々な話がありましたし、私の理解が間違っている部分もあるかも知れません。
普段の仕事には関係のない講演におじゃまさせて頂きましたが、麻痺を経験したことで、一部実感を伴って話をお聞きすることができました。
そして、自分や家族にいつか必要になる話だなあと感じました。
これは「とろみ」の実演