
|
|
|
カテゴリ:音楽 [プログレッシブ・ロック]
 屋久島の森 (画像参照:Wikimedia) 日本生まれの音楽ジャンル Progressive Rock プログレッシブ・ロック を聴いてみましょう! 【初級編】第7回 『日本のプログレ』Ver.2.0 ■ お久しぶりですVoyager6434です☆ さて、数カ月ぶりの更新となりました今回は 又々楽天ブログ最大級となる、 本文で7万文字、画像、アフィリエイトを加えて9万文字もの文章を駆使し 約8年(!)前の 2012年12月12日に更新した 『プログレッシブ・ロック』特集【初級編】第7回の 大幅な改定と増量した文章によりw ほぼ新作となったヴァージョンアップ版をお送りします。 なぜ、今この記事なのか? というのは、特に理由はなくW 平素からアクセスの多い過去記事のリンク切れを修正し 読み返すのも苦痛な拙い文章を人知れず修正し更新し続ける中で、 こんな時代に「おうち時間」を使って修正している内に 当時のサクッと書いてパパッと上げていた頃の お手頃仕様の更新が 現在の大量文章を嫌がらせの様にお見舞いする 出版仕様で執筆してしまい 特に「美狂乱」のパートが、楽曲の紹介というよりも 「美狂乱」を通して見た、 「音楽と地域の関係性に於ける表現としてのロックのあり方」 という お茶を飲みながらせんべいをサクッと食べようとして 北京ダックが出てきたかの 読んでいて吐きそうになる大量の文字数を駆使した 評論まがいの文章となり それ以前に、 INTROパートの「ブルース」の説明が 本記事の約半分を有する大量文章となり、 果たしてメインの記事に辿り着けるのかという 近所の無料スポットのイルミネーションを眺めながら 今年をしめやかに振り返るつもりが ペルーのウルバンバ渓谷に沿った山の尾根にあり 世界一の標高チチカカ湖を見下ろす空中都市の異名を持つ 世界遺産「マチュピチュ」で 15世紀のインカ帝国の繁栄と衰退に 壮大な思いを馳せる事になる様な mailで商談する情報をTwitterで収集してると Instagramに上げた写真がLINEで炎上して TikTokがカオスになる こんな時代だから おうち時間を使って観たAmaz◯n Primeビデオで 今頃「逃げ恥」のダンスにハマる様な ライザップでコミットしてサンバするマツケンの筋力に 人生100年時代を見る様な 時代に逆行(テネット)するブログの大量文章に疲弊する ある種の達成感に浸る日常が健全に見えてくる様な 一生聴き続けたいマニアにとっては「永遠に鑑賞するまでがテーマ」となる 一生聴く事のない一般人にとっては「鑑賞するまでが永遠のテーマ」となる そんなプログレッシブ・ロックを紹介する今回は プログレカテゴリー発祥の地「日本」のプログレ に 再度スポットを当ててみようと思います それではスタート☆ ----------------------------------------------------------------------------------- ■ もくじ ■ - INTRO 前枠解説 - ■「形から入る」形で認知された日本のロック■ 1.「不良の代名詞だったROCK」 2.「オーセンティックでは無い日本独自のビジュアル系ROCK」 3.「ブルースの影響と欧米音楽の変移」 4.「ブルース黎明期の多様性と統合への近代化」 5.「ブルースが停滞した大恐慌」 6.「エレキ時代に埋もれゆくブルース」 7.「逆輸入で再評価されるブルース」 8.「社会に影響を与えるブルース」 9.「原点回帰を促すブルース」 10.「ブルース体験と正統派ROCKとの関係」 11.「日本に上陸したブルースと定着しなかった要因」 12.「日本のROCKの特異な発展とその脆弱性」 13.「サブカル化するROCKと見限られる邦楽界」 - 楽曲解説 - M1(1984)NOVELA『調べの森』 M2(1985)難波弘之『ブルジョワジーの密かな愉しみ』 M3(1982) 美狂乱『二重人格』 1.「レコード会社の事情に振り回された当時のバンド事情」 2.「音楽的個性の根付きと偏狭性との関連」 3.「地方型音楽を形成する音楽的地盤」 M4(1974) 四人囃子『おまつり』 M5(1986) PRISM『TAKE OFF』 M6(1982) 高崎晃『逃亡 ~STEAL AWAY~』 M7(1983) TAO『Hello Vifam』 - OUTORO 後枠解説 - ■新世代音楽の個人化とコラボとの関連性■ 1.「バンド形態が廃れた欧米事情」 2.「誰も語らない、Tic Toc以外の『香水』のヒットの背景」 ■楽天市場■ ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- - INTRO - ■「形から入る」形で認知された日本のロック■ -----------------------------------------------------------------------------------  The Spiders (画像参照: wikimedia) それでは まず、「日本のロック」に付いて いつもの偏狭な視点で、時にはお得意の「妄想」を交えて 少しばかり紐解いてみたいと思います ロック黎明期の60年代の日本は カントリー&ウェスタン、JAZZなどが開いた洋楽の扉を その後ロカビリーブームを経由した「ベンチャーズ」人気が GSブームへと押し広げる中にありましたが、 これらの音楽はライターが楽曲を書き歌手が唄う 「洋楽ポップ」の様式をベースとした 「芸能人」による音楽中心の時代でした。 それが64年のビートルズの登場により シンガー・ソングライターによるオリジナルの音楽に 世の中の興味が移行すると ブリティッシュ・インヴェンション(英国音楽の侵攻)の波が 米国にまでとどろき ビーチボーイズの様なサーフミュージックバンドが刺激を受けて変貌し 「ペット・サウンズ」の様なコンセプト作品をリリースするまでに 影響を与えたのに対して 日本でも米国同様にビートルズに刺激を受けながらも、 GSが歌謡曲化した時期の日本の歌謡界で 「ロック・ミュージック」にオリジナル性をもたせるという様な 世間の期待に応えるだけの楽曲を輩出する音楽的基盤は無く GSブームも終焉して行きます。 という訳で今回は、 音楽的基盤の無い日本のロックという話を中心に 如何にブルースがロックの基盤となり得たのか、 ブルースの歴史と共に、 日本のロックの今の姿をお話しして行きます。 曲紹介を挟んだ後後半では、 今やボーダーレスとなった音楽業界で 流行りつつあるものと廃れつつあるもの 更には、 誰も語らない「香水」のヒットと ネット新世代との関係を紐解いて行きたいと 思います。 さて やがてこの期待は「フォーク・ブーム」の方にスライドして行くのですが 60年代後期にはこの「フォーク・ミュージック」を一つの切り口として 68年に 加藤和彦率いるフォーク・クルセダーズが放った 『帰ってきた酔っぱらい』の様な フォークの造りで「楽曲の存在」に「ロック」を感じる作品が登場する事で ようやく日本の音楽に「ロック」の精神が根付き始めて行きます。 ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- 1.「不良の代名詞だったROCK」 -----------------------------------------------------------------------------------  Kanda Quartier latin1968/06/21 (画像参照: wikimedia) 折しも「ベトナム戦争」反対運動を通して、 「学生運動」が再び盛んになってきた時期でもあり 「ロック」と言えば激しいサウンドというイメージから その様な運動に熱狂する若者達が共鳴するカルチャーとして 怒れる若者達が好む音楽が「ロック・ミュージック」という形で 世間一般の知る所になって行きます しかし学園闘争が過激さを増し、暴力や死傷事件へと発展すると これまでこれらの運動に共感してきた世論からの求心力を失い それと同時に「ロック」も、 「ロックは反抗」「ロックは暴力」「ロックは不良」という 反社会的イメージが定着する様になり 70年代に登場したハードロックも ヘビメタも プログレも 音楽ジャンルとして一般的に 認知されない 一部の愛好者が聴く マニアックなものとなり 欧米に比べてロックが定着しづらい土壌が作られます。 当時の日本のミュージシャンの中でも ロック支持派のミュージシャン達は、 ロックが定着しない当時の音楽業界で創作意欲の表現先を求めて ネットはおろか Youtubeも無かった時代に 何とか国内にロックを発信する為に、 楽曲を聴きやすく妥協した形に変えてリリースするか 歌謡曲に許容範囲内でハードなアレンジを施すか 様々な要素が渾然一体となった流行歌の素材の一部とするか、 或いは、 ハナから売れない事を承知で本格ロックを演り、 食べる為の職は他に持つか 「ロック」はその様に「異端」なもの扱いを受けながら それを甘受する中で作られて行きます 結果、そうしたロック的な音楽によって 徐々に「ロック」が浸透し受け入れられる土壌が 作られて行くのでした。 ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- 2.「オーセンティックでは無い日本独自のビジュアル系ROCK」 -----------------------------------------------------------------------------------  BOØWY 1984 (画像参照: wikimedia) 80年代に入りますと BOØWY のブレイクもあり ロックは徐々に一般層の認識に至るまでになりますが 音楽性よりも「ファッション性」の方が大きな話題として取り上げられ X JAPAN の登場後の「J-Pop」全盛期に入りますと 日本独自のサブカルチャー文化を背景とした 「ビジュアル系」と呼ばれるスタイルのバンドが多数登場し いわゆる見た目から入る形で 日本のロック黄金期の到来となり 欧米には無い独自のビジュアルとサウンドは 「異なる肌触り」がするエキセントリックで魅力的な音楽として 欧米からも注目される様になり いきなりジャンルとしての到達点に達します。 一方で、この「ビジュアル系」ロックは 欧米の音楽シーンでのムーブメントで、 70年代後半にチャートを賑わせた 「商業ロック」に対する反発として 「ブルース」から派生した 正統派なロック への回帰を目指して登場した 「オルタナティブ」などのジャンルとは異なり 「ブルースから派生した正統派ロックに影響を受けたバンド」 を輸入盤で聴いて影響を受けるという、 コピーしたものをファックスして受け取る様な形で 「ロック」に触れた 日本のロックの歴史が投影された様な、 「ロック」から「ブルース」が・・・では無く 「ロック」から「ブルース体験」が 抜け落ちた オーセンティック(正統派) なものとは 言えないものでもありました。 ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- 3.「ブルースの影響と欧米音楽の変移」 -----------------------------------------------------------------------------------  Eric Clapton & Roger Waters (画像参照: wikimedia) 「ブルース」では無く、 なぜ「ブルース体験」が抜け落ちると 「正統派」とは言えなくなるのか ・・・を語る前に ここで「ブルース」の歴史を少しばかり紐解いてみたいと思いますw 「ブルース」はエリック・クラプトンなどの ブルースギタリストが中心となって演奏する バンドで演奏するスタイルが有名ですが、 元はアフリカが起源の、 17世紀から19世紀中期にかけての時代に農業が盛んな米国南部地区で、 大規模農園での奴隷として従属を強いられ 奴隷解放後も人種差別などの迫害を受けてきた黒人達の 為す術も無く苦境に立たされて来た受難をベースにした 憂鬱でふさぎ込んだ気持ちを歌にして癒やしとする 「黒人霊歌」「労働歌」などが発展した、 ギター1本で弾き語る黒人のローカルな伝承音楽で 地方によって異なるスタイルで発展したものや 時代と供に変化したもの 現在のバンドスタイルとなったものなど、 これら全てを含めた総称を「ブルース」と呼んでいます。 ブルースの音楽的な特徴は 西洋音楽の音階から外れた「ブルーノート」と呼ばれる音階を加えた 5音階の「ブルーノートスケール」で構成される 「ブルース形式」と呼ばれる独特の反復されるコード進行と 「シャッフル」と呼ばれる跳ねるリズムに乗せた 独特の節回しのフレーズで構成された演奏に、 奴隷解放が成立した後も 準奴隷システム「黒人取締法」「ジム・クロウ法」などの悪政が続いた 当時の米国南部で暮らす黒人達の、 いわれのない罪で投獄された監獄で過ごす理不尽さや 作物の被害を受けた自然災害に遭う成すすべもない苦難や 「♪俺はお前の奴隷さ」の様に男女の関係を「奴隷」の立場に置き換えて 迫害への抗議の念を唱える、二面性の意味を持たせたものなど、 白人と黒人を平等に扱わず階層社会の底辺に封じ込め様とする 当時の米国社会への反発を原動力とした 「ブルース」ならではの表現を使った自傷的な歌詞に乗せて レイドバックした雰囲気で唄うのが様式で、 ミシシッピ・デルタ地帯で発生した アコースティックギターの伴奏で唄う「デルタブルース」や シカゴで流行したピアノの伴奏で唄う「ブギウギ」形式のものなど、 地方によって様々なスタイルを持った多様なものが知られています。 この様な、黒人のローカル音楽の「ブルース」が普及したのは 米国の場合は、 50年代以前メインストリームのラジオから 流れる事すら無かったブルースが その後「アフリカ系アメリカ人公民権運動」をきっかけに 50年代中盤以降からチャック・ベリーなどの 黒人スターのブレイクを通して根付いて行き、 英国の場合は、 第2次世界大戦中 英国に駐屯した米軍兵からブルースが渡り やはり50年代からブルースが根付いて行ったという 歴史があります。 ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- 4.「ブルース黎明期の多様性と統合への近代化」 -----------------------------------------------------------------------------------  W. C. Handy - The "St. Louis Blues" - First page (画像参照: wikimedia) さて、「ブルース」の歴史ですが、 いつ、どこで、誰が、どうやって、ブルースを誕生させたのかは 定かでは無いそうですが 1900年代初頭、「ブルースの父」と呼ばれるW・C・ハンディという人が 米国南部を旅して耳にした地元に根付いた音楽を 譜面(シート・ミュージック)にして広めたものが 「ブルース」の始まりと言われております。 そうして広まった「ブルース」が南部各地で根付いて行き 米国南部のミシシッピ州デルタ地帯やテネシー州メンフィスなどで発生した ギター弾き語り哀歌が 1920年代以降、チャーリー・パットンやロバート・ジョンソンの登場で 黒人の間で人気の高いジャンルとなり 「デルタ・ブルース」として世に広まったとされてます。 加えて、 「ミシシッピ・デルタ・ブルース」「メンフィス・ブルース」 「ジョージア・ブルース」「テキサス・ブルース」の様な 地域によって違うスタイルのブルースも レコードの普及によって 地域を越えて広く知られて行く様になり レコードを通して各地のミュージシャン達も 異なるスタイルのブルースに影響を受ける様になって行きます。 又、大都市では、 レコード普及より前から先行する形で、 様々な地方から都市へと集まって来た 各地のブルースミュージシャン同士が お互いのスタイルに影響を受け合い ギター、ピアノなどの 異なる楽器、スタイルのコラボが流行した 「シティー・ブルース」と呼ばれるムーブメントが発生し シカゴの様な都市で徐々にブルースが、 洗練されたものになって行きます。 一方で、 南部での迫害を逃れて北部へ移住し それぞれの地域で活躍するブルースミュージシャン達が こぞって都市へと進出したり、レコードを通したりして 異なる地域のブルースに影響を受ける事で それまで地域ごとに異なるスタイルとして存在していた 地域性が失われて行き 様々なスタイルが混在した 地域性に於いて多様性の無いものになって行きます。 それと引き換えに「ブルース」は 全国のミュージシャン同士の切磋琢磨によって より洗練されたものへ進化する事になったと言えます。 やがて「ブルース」が全国的に知られて行く様になりますと、 人の心の闇を赤裸々に語る内容や 歌詞の中に良く出てくる「呪い」のワードなど ブルース特有の表現に反応して 敬虔なキリスト教徒などの中で 嫌悪感を抱く人々が現れたり 元説教師のブルースマン、サン・ハウスの様に 宗教とブルースの間で葛藤しながら活動を続ける者が現れる事で ブルースは「悪魔の音楽」や「スピチュアル」といった 神秘性を帯びたものとして語られる様になります。 これは、 当時の米国内でブルースへの関心が高くなった風潮に対し 白人社会に黒人が進出する事を憂慮する白人達が 偏見故に歪んた形で拡めた現れとも 言えるものがありますが、 1929年10月に発生した「大恐慌」によりレコード業界が大打撃を受け ブルースは30年代の前半に停滞の憂き目を見ます。 ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- 5.「ブルースが停滞した大恐慌」 -----------------------------------------------------------------------------------  Crowd gathering on Wall Street after the 1929 crash (画像参照: wikimedia) ・・・ちなみに「大恐慌」の原因は ざっくり言いますと 第一次世界大戦中の戦争景気で大きな利益を上げた1920年代の米国は 大都市にはビルが立ち、自動車が普及し、大量消費時代に入り 世はバブル経済景気にありました。 そんな当時の米国の企業も消費者も 世の中の好景気に熱病の様に浮かれて、 消費者側は、散財はステイタスとばかりに、消費に明け暮れて、 企業側は、巨大な利益は巨大な投資とばかりに、 過剰な設備投資と過剰な生産をし続けていました。 やがて消費と供給の均衡は崩れて供給が消費を上回ると 世の中に物が溢れて売れ残り、 結果、物価が急激に下がり始めます。 折しも企業への投資がブームだった事もあり これまで企業へ過剰に投資して来た投資家達は 世の中がデフレ傾向にある事に過剰に反応し、 投資が回収出来なくなる危機感から一斉に企業株を手放した事により 株価が暴落し恐慌を引き起こしたと 言われていますが、 元々この時代の好景気は、かつて大農園や工業の企業主が 多くの黒人労働者達を奴隷同然の低賃金で雇った事による、 黒人側から見れば、 白人達によって搾取された理不尽な利益によって支えられた経済で もたらされたものであり その経済がバブル景気にほだされる様に高コスト化に陥って 社会に還元出来ない程の高価格商品で溢れてしまった事による 実物資産の収益率が低下した事で引き起こされた 価格低下による結果であるので 当時の理不尽なシステムの中で米国経済を支えた黒人労働者達の、 働けども報われないこの様な資本主義的理不尽さも、 ブルースの原動力の一つとなった訳です。 ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- 6.「エレキ時代に埋もれゆくブルース」 -----------------------------------------------------------------------------------  Gibson L-5 (1928), Maybelle Carter, CMHF (画像参照: wikimedia) さて、時代は「エレキ」の時代に入りまして・・・ ・・・所で、ここまで読んでくださった方の中で、 「ブルースへの脱線が過ぎるのでは?」と思ってる方が おられると思いますが、 これがこの先ちゃんと「プログレ」に繋がって行きますのでw なのでここでブルースとロックの関係をある程度掘り下げておかないと 理解に繋がらない という事で どうかもう暫くお付き合い頂ければと思いますwww・・・ ・・・ともあれw、1930年に登場したエレキギターにより ギタリストはバンドや楽団の中でも埋もれない大音量を獲得し それまで楽団の主役だったサックスやトランペットなどの管楽器と並び ギターはソロ楽器として楽団の前面に出る様になります 40年代に入りますと、第二次大戦後米国北部のシカゴやデトロイトで 南部の「ブルース」をバンド形式へ発展させてエレキギターを導入した 「シカゴブルース」が登場し マディ・ウォーターズ などのスタープレイヤーを輩出して行きます 同時期に、北部、西部、東部で「ブルース」「ブギウギ」から発展し 「ゴスペル」「JAZZ」を加えた都市型ブルース 「R&B (リズム&ブルース)」が誕生し、 これらのムーブメントが 南部のクラシック・スタイルなブルースマン達にも 影響を与えて行きます。 エレキギターの登場は「JAZZ」や「ブルース」での ギタリストの役割を前面に押し出したばかりでは無く、 新たなサウンドを求める動きにも好都合のアイテムとなりました。 50年代には 「R&B」に「カントリー」と「ブルース」を加えてエレキギターで演奏する 「ロック&ロール」が誕生し、 チャック・ベリー などの黒人のロックスターを生み 10代の若者の間で人気を博す一方で、 南部メンフィスでは「ロック&ロール」に先行する形で 「ブルース」「カントリー」に アイリッシュの伝承音楽「ブルーグラス」などが加わった 「ロカビリー」のムーブメントが発生し 「ロックンロールの誕生」と呼ばれる 『ロック・アラウンド・ザ・クロック』のビル·ヘイリーや 歴史的大スター エルビス・プレスリー が登場し 「ロック&ロール」人気を牽引して行きますが 先程のチャック・ベリーを始めとした黒人のブルースベースのものを 「ロック&ロール」 プレスリーを中心とした白人のカントリーベースのものを 「ロカビリー」とジャンル分けしながらも これらは多義的に「ロック&ロール」と呼ばれ供に人気を博しながら 次々と大ヒット曲を飛ばし、音楽界が活気づいて行きます。 一方「ブルース」は、ロックンロール人気に押されながらも 50年代に入りますとバディ・ガイなどの新鋭ギタリストが これまで伴奏楽器だったギターをリード楽器として使う 「ウェスト・サイド・サウンド」と呼ばれた、 現在もバンドでブルース演奏をする際に良く聴かれるスタイルを 確立させますが 結局ロックンロール人気に潰される形で「ブルース」のムーブメントは 活気を失って行き、 1950年代半ばから黒人の権利と平等を求める 「公民権運動」が盛んになり その動きに呼応した様に生まれた「ソウルミュージック」が 流行り始めた頃には、 厳しい差別のある南部を離れ北部へと移住した黒人達が生み出し 「奴隷」だった時代の故郷でもある南部への想いを乗せた「ブルース」は 記憶から消去してしまいたい屈辱に満ちた歴史を象徴するものとして 米国内で自由と権利を主張する新たな時代を切り開いて行こうとする 黒人達にとって 過去の亡霊とも言うべき忌み嫌われるものとなって行きます。 しかし、チャック・ベリーがインスピレーションの源と語る マディ・ウォーターズのブルースに影響を受けて音楽を始めた様に 「R&B」に「ゴスペル」的要素を拡大させて、 強力なリズムに乗せ人種問題を定義し解決の道を叫ぶ メッセージ性の強い「ソウルミュージック」にしても これらの音楽を育んだのは「ブルース」の力があっての事でした。 ■ ブルースが忘れられた音楽となった60年代初頭、 ブルースマン達は海を渡って英国に上陸し マーティン・スコセッシ監督がプロデュースした2003年のドキュメンタリー 『レッド、ホワイト&ブルース』でも描かれた 1962年に行われた 『アメリカン・フォーク・ブルース・フェスティヴァル』に出演した事で ブルースに転機が訪れます。 この時、生のブルースに触れた英国や欧州の若者達が衝撃を受け それがブルースのブームとなって英国や欧州へと拡がって行き それが、折しも英国での新しいサウンドを求める動きにも合致した事で ロックサウンドでブルースを演奏する 「ブルース・ロック」が誕生し フリートウッド・マック、ローリング・ストーンズなどの ブルースに影響を受けた多くのバンドを生み出します ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- 7.「逆輸入で再評価されるブルース」 -----------------------------------------------------------------------------------  Fender Precision Basses / Fender Jaz Bass (画像参照: wikimedia) ・・・ここで「ロック」に付いて少しだけ説明しますとw 「ロック」は 「ロックンロール」「ブルース」「カントリー」などから 派生したジャンルですが ラブソ・ング主体の歌を唄う「ロックンロール」「ロカビリー」や 愛国心や故郷への想いを唄う「カントリー」とは異なり 「激しい男女関係」「体制への反抗」「社会問題への憤り」 など多義に渡るテーマを扱う所に大きな特徴がある 非常に幅広いジャンルと言えますが 最も大きな音楽的特徴としては ベースパートに アコースティック・ベース(ウッドベース)を使用していた 「ロックンロール」「ロカビリー」「カントリー」の編成に対し、 ベースには「エレキ・ベース」を導入して エフェクター、アンプ機材で楽器音を歪ませたエレキ・ギターに乗せた ラウドなサウンドで演奏する3ピースバンドを主体とした編成に 大きな違いがあると言えます。 さて、 ブルースに影響を受けた英国の音楽界が 60年代中期辺りから ビートルズ の登場を皮切りに 「ブリティッシュインヴェンション」と呼ばれる英国ロックの新たな潮流を 世界に拡げて行く中で、 今度は米国で、ビートルズ、ローリング・ストーンズの渡米をきっかけに これら英国の音楽が実は 米国で忘れられた「ブルース」に影響を受けて生まれたものだという事を 英国人によって逆輸入の様な形で知らされます それによって「ブルース」再評価の動きが 全米に広がって行く事になります。 これにより「三大キング」と呼ばれた B・B・キング、アルバート・キング、フレディ・キングを筆頭とした ブルースの名手達が 新たなマーケットとなった「ロック」のカテゴリー中で 再びスポットを浴びる事になるのでした。 忘れられた名手達にスポットが当てられる中で 「ブリティッシュ・インヴェンション」の余波は米国の音楽界の図式を書き換え 作詞家作曲家が書いた楽曲を歌手が唄う「芸能」から 自作の楽曲を自ら唄い演奏する「創作」が主流となる アーティストが活躍する流れを生み出します。 その様な波の中、ブルースに強い影響を受け エレキギターで短いパターンを繰り返す 「リフ」を核としたヘビーサウンドを確立し これまでのギターミュージックを覆すプレイで 多くのミュージシャンに影響を与えた ロック・ミュージックのパイオニア ジミ・ヘンドリクス の登場と共に 新たなサウンドを支えるエフェクター類、 音楽器機の発展に加速がかかり、 新しいサウンドを求める動きが活性化し 60年代末には レッド・ツェッペリン、ディープ・パープル を始めとする 歪んだ巨大なギター音をフィーチャーし R&Bをフォークミュージックの文脈とラウドなロックの形態で演奏する 「ハード・ロック」が登場します 加えて、シンセサイザー、メロトロンなどの最新楽器を使用し 「ロック」に「JAZZ」「クラシック」などの 音楽様式を掛け合わせた実験的サウンドと 文学的理念をエモーショナルに表現する高度で先進的な音楽を演奏する 「プログレッシヴ・ロック」も同時期に登場し、 ピンク・フロイドやキング・クリムゾン、ジェネシス、イエス、EL&Pなどの プロクレッシヴ・ロックを代表するバンドが次々と誕生して行きます。 ここでようやくプログレが出て来ましたが、 これがオチではありませんので、 もう暫くお読み下さいw ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- 8.「社会に影響を与えるブルース」 ----------------------------------------------------------------------------------- この様にロック時代を牽引した「ブルース」がある一方で、 レイ・チャールズ、サム・クック、ジェイムズ・ブラウン アリサ・フランクリンを生み出した「ソウルミュージック」は 「ブルース」から発展したR&Bが生み出したジャンルで 白人社会にブラックミュージックの存在を認めさせた音楽でも ありました 70年代に入りますと「ニュー・ソウル・ムーヴメント」と呼ばれる ソウルミュージックよりも更に社会問題へ言及する形で ジャズやフォーク、民族音楽などの 異なる要素の音楽を加え化学反応させた 複雑で高度な音楽性を内包した楽曲を輩出する 新世代ブラックミュージックが誕生し マーヴィン・ゲイ、スティーヴィ・ワンダー、カーティス・メイフィールド、 ロバータ・フラック、ダニー・ハサウェイなどのアーティストの登場で ブラックミュージックは全米音楽チャートを賑わせる メインストリームの音楽として 米国の音楽界で揺るぎない地位を獲得する事になります。 続いて、70年代中期から後期にかけて ファンク、ソウルミュージックをベースに強力なダンスビートが加わった 「ディスコミュージック」が一斉を風靡し スウェーデンのPOPグループ ABBA のブレイクや 元はソフトロックデュオグループだった ビージーズ が ディスコティックサウンドへ大胆な変身を遂げ 音楽を担当したジョン・トラボルタ主演1977年の映画 『サタデーナイトフィーバー』の大ヒットなどのきっかけで 一大ブームが巻き起こります。 ブルース界でも エリック・クラプトン、ジョニー・ウィンターなどの 白人ブルースマンの登場など、 ブラックミュージック界での白人ミュージシャンの進出が 目立つ様になって行きます。 これらは先程も出てきた 「公民権運動」に呼応した動きと言えますが これは当時の米国白人社会の中で 黒人が地位を獲得した事を意味するだけでは無く 白人社会の中に黒人が生み出した音楽が根付いた事を 象徴する動きだと思われます・・・ ・・・かつて40年代、50年代の米国の音楽界では、 黒人ミュージシャンによるR&Bのヒット曲を 白人ミュージシャンがリメイクし 黒人ミュージシャンのヒットを上書きする様なヒットを遂げて 大ヒットした事実を白人のものへとスライドさせる、 音楽界での黒人の台頭を許さないとばかりに あからさまなまでに功績を横取りしてきたという 歴史がありました。 現在でも人種問題で全米が分断される中、 日本では「都会風」と訳される「アーバン」という言葉が 白人音楽界の「ポップ」の対極にある 差別的な言葉であるという問題が浮上し ポリティカル・コレクトネスの見地から使用の是非が問われ 米グラミー賞では「アーバン・コンテンポラリー」という名称を 「プログレッシブR&B」に変更しようという名称問題が 音楽ファンの間でも取り沙汰されましたが 名称問題の是非はともかくとして この騒動の要は、 現代の米国音楽界に人種問題のメスが入った所にあるのでは無く 黒人アーティストの功績を軽視する傾向が 40年代、50年代はおろか、80年経った現在に於いても 未だ米国の音楽界に 根強く残っていた事を浮き彫りにした 点にあると言えます・・・ ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- 9.「原点回帰を促すブルース」 ----------------------------------------------------------------------------------- 80年代に入りますと、 音楽器機がアナログからデジタルへ移行し アース・ウィンド&ファイアー の様なファンク・ソウル・バンドや アレサ・フランクリン、ティナ・ターナー などの大物ソウルシンガーが アナログ時代には存在しなかった クリアで綺羅びやかでゴージャスなデジタルシンセサウンドをバックに スタイリッシュなコンテンポラリー・ミュージックを唄うアーティストへと こぞって変貌を遂げ 音楽配信TVサービス「MTV」人気や ハリウッド作品の主題歌起用ラッシュによって 景気低迷で停滞していた音楽界は再び活気を取り戻します しかし90年代に入りますと、 経済を立て直す経済再建策レーガノミクス疲れが出たのか 「癒やし」を求める風潮が拡がり 音楽界で新しいサウンドを求める動きが行き詰まり始めます 一方で、 媒体がアナログレコードから CDへ移行 した事を期に レコードで揃えた愛聴盤をCDに買い換える「リバイバルブーム」が起こり 世の中のその様な動きに呼応する様に派生した 「オルタナティブ」ムーブメントに代表される、 原点に立ち帰る動きが音楽界の中で広がって行きます。 ロック界でも「ヘビーメタル」ブームが収束した反動の様に アンプ機材を使用しない、アコースティック楽器のみで演奏する 「アンプラグド」ブームが起こり、 その流れから数多くのアーティスト達が 自身のルーツとなる「ブルース」へ回帰 する作品をリリースしました。 21世紀を迎えますと、 インターネットの普及とCDパッケージ販売からダウンロード販売への移行で 音楽業界は激変し 大手レーベルの資金力と機動力を借りなくても ネットでのダウンロード販売とSNSによる拡散で プロダクションレベルでのリリースが可能となった事で 音楽界はそれぞれのアーティスト力を糧とする 業界の多様化が加速して行きます。 ■ 農業革命ではノーフォーク農法の普及で穀物生産を増大させ 経営に資本主義的理念を導入し 産業革命後は、手工業に替わる機械への移行と それに伴う生産技術の革新と、それを支える石炭などのエネルギーの変革を起こし 小品種大量消費が社会の主流の世の中となり、 音楽業界もそれに倣い 大衆が好むとされる音楽を大量消費させるやり方を推進させる 資金力と機動力のある大手メジャーレーベル独占体制が続きました しかし、 20世紀の最後に登場したインターネットによる第三の波 情報革命により かつて黒人を低賃金労働者として隷属させ 「ブルース」を過去のものとしてきた歴史を持つ米国は 大衆音楽をリリースし続ける大手メジャーレーベル主導の図式を崩壊させ 21世紀に入り人種問題で国を分断させ 個人の価値観が主導する時代へと変化した事で 現在の様な大きな岐路に立たされる事になるのでした。 そしてこの様に先の見えない世の中になった時は 初心の気持ちで原点に立ち返り自分探しの旅を行ったり 原点回帰からの再起を図るなどの行動を取ったりするものなのですが、 ジャンルが行き詰まった時、 自身の原点に回帰しようとするのは音楽も同様で、 ロックアーティストの場合も 自身が影響を受けた音楽の中に 全てのロックの源泉となる「ブルース」を見出して それが、 自身の音楽性を見つめ直して起死回生を目指したり あるいは本格的にブルースに取り組んだり 新たなジャンルを生み出す「原動力」となったりする訳です。 これは、 「影響を受けた音楽」の中に「ブルース」を発見する作業、という 文字通りの「源泉探求」の作業を指す他に 「影響を受けた音楽」を通して自身のDNAの中に 「ブルース」を体験していた自分を「発見」するという、 元から自分が持っていたものを「再確認」する行動を指し、 それにより自身の音楽的基盤が「正統派」なものであると捉える 音楽的「指針」を見出す行為を指す事を意味し、 これが、 ジャンルが行き詰まった時に再起する為にリセットし 原点回帰しようとする動きの原動力になるのだと言えます。 ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- 10.「ブルース体験と正統派ROCKとの関係」 ----------------------------------------------------------------------------------- ここで「ブルース」では無く なぜ「ブルース体験」が抜け落ちると 「ROCKの正統派」とは言えなくなるのかという 最初の話に戻りますが、 「ROCKの正統派」のベースに 「ブルースを聴く体験」では無く「ブルース体験」があるのは 欧米の人々が生活する中で蓄積されて行く 知識、経験に基づいた「体験」の中に、 「ブルース」の様に 人々の営みから派生して根付いて行った音楽が 生活をして行く中で自然と体の一部となる様な 音楽体験が含まれているとするなら、 同じ様に人々の営みの中から派生した 「ROCK」も 音楽体験という形でブルースとの繋がりがあるので その様な音楽的基盤のある音楽から派生した「ROCK」は 正統派な音楽だと言う事になります。 つまり「ブルース体験」という形で「ROCK」は 欧米人の体の一部となっているので 「正統派」な「ROCK」のベースには 「ブルース体験」があると、いう事になる訳です。 それに対して日本の場合は 戦後欧米の様に「ブルース」が体の一部となる 「ブルース環境」が作られる様な音楽的地盤も機会も無かったので 70年代に「ブルース・ブーム」が起こっても 数年の短期的なブームで終焉し 日本の音楽界にブルースが定着する事は ありませんでした。 その後、 日本のROCKが大きく欧米に遅れを取る事になったのは 正統派なブルースが日本の音楽に根付かなかった所に 大きな要因があったのではないかと思われます。 この「ブルース環境」とは何かという事ですが、 コレを日本の音楽に置き換えると理解しやすくなると思います 日本人が演歌のこぶしと「和」の手拍子の「間」を理解する事に 何の理由も必要なく、 DNAの中に演歌と「和」を いつの間にか体験していた自分を発見して 音楽的基盤が正統派な邦楽にある事を自覚して 「邦楽体験」を理解するのと同様に 欧米人がブルースのノリとインテンポのリズムを理解する事に 何の理由も必要なく、 DNAの中にブルースを体験していた自分を発見して 自覚して理解出来るので その様な社会的な環境の中で 音楽的基盤となるものが体の一部となり 生活レベルでブルースが根付いた環境が 「ブルース環境」という訳です 故に日本人はROCKのインテンポ(リズムの裏)を取るのが苦手で ブルース特有の歌いまわしが理解出来なくて 欧米人は演歌や民謡の手拍子の「間」を取るのが苦手で 演歌特有のコブシが理解できない という事になる訳なのでした。 ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- 11.「日本に上陸したブルースと定着しなかった要因」 -----------------------------------------------------------------------------------  B.B. King (画像参照: wikimedia) さて、 日本でブルースがブームになったのは欧米から遅れること10年 1971年、B・B・キング初来日公演をきっかけに起こりました 加えて1974年に開催されたブルースフェスティバルで B・B・キングを通して生のブルースに触れた 当時の日本の音楽ファンやミュージシャンが 正統派シカゴブルースを演奏する スリーピー・ジョン・エスティス&ハミー・ニクスンと、 ロバート・ジュニア・ロックウッド&ジ・エイシズに衝撃を受け 日本でブルースのアルバムのセールスが一気に伸び 竹田和夫率いるブルース・クリエイションや憂歌団などの ブルースバンドが人気を博す様になります このフェスティバルの模様は75年に発売されたライブ・アルバム 『ブルース・ライヴ! ロバート・Jr.ロックウッド&ジ・エイシズ』 で聴く事が出来ますが このフェスティバルが翌年75年まで3回開催された後は 日本のブルースブームは まるで潮が引く様に収束するのでした。 これは、1930年代にロバート・ジョンソンの様な人物が存在していた米国や 第2次世界大戦の米軍駐屯で米兵を通して拡がった英国の例の様に 「ブルース」が浸透する音楽的地盤が 日本には無かった事や、 欧米で「ブルース」が定着した50年代中期は 日本では戦後からようやく復興した時期に当たり 戦時中洋楽は敵性音楽として鑑賞禁止となり 音楽的な鎖国状態が続いた後に 戦後進駐軍を通してようやく洋楽体験をするという、 欧米の音楽の潮流から大きく外れた事などが要因となり ブルースが定着する基盤を作れなかった所に 理由があったように思われます。 これにより日本の音楽界は世界の潮流から10年遅れて 日本にブルースが根付く土壌を作ることが出来ないまま 今後もこの差が埋まる事がなかった所に 日本のROCKが欧米に対して大きな差が付いた 要因となったと言えます。 加えて日本では、 「ブルース」から派生した「R&B」から「ロックン・ロール」を経由して 新しいサウンドを求める機運の中で「ビートルズ」が登場する という 欧米が体感した順当な「音楽的体験」をしないまま、 戦後入ってきた「白人音楽」で突然洋楽を体験した後に 64年に「ビートルズ」を体験してから 70年前半の「ブルースブーム」となっているので、 欧米の場合「ビートルズ」を聴いた人々が ビートルズを通した「ブルース体験」を体感しながら 『ブルース、R&B から発展した新しいサウンド』という様に ビートルズの「画期性」を理解して行った事に対して、 当時の日本の音楽的状況では ビートルズを真の意味で理解できない状況だった事が分かります。 それに加えて、例えば ・・・欧米の音楽に触れながら 洋楽に対しての「音楽的情緒」というものが形成されていく、 「民族的成長因子」がというものがあるのだとしたら・・・ この時点でビートルズを理解出来なかった事は 「世界的音楽の潮流」から10年乗り遅れただけでは無く 本来なら60年代前後の時期に「ブルース」を体験して その後にビートルズを体験して一様に衝撃を受けた後に 欧米のロックに触れて、 「ロック」の中に「ブルース」を発見する 「正統派ロック」の因子が定着するという それらの音楽的情緒が育っていく大事な時期に、 「ブルース」を聴いた時に受けるべき衝撃を体験する前に いきなり「ビートルズ」という発展形に触れて 日本中が衝撃を受けた事で 日本民族から「ブルース」という因子がゴッソリ抜け落ち 「ロック」から「ブルース」を感じられない状態が 日本では「ロック」のデフォルトとして 定着した事になります。 後にブルースがブームになっても ブルースへの関心が5年と保たなかったのも、 「ブルース・クリエイション」の様な本格ブルースバンドが 世界の潮流とは異なった日本の音楽界で居場所を模索しながら 「ニュー・ミュージック」のムーブメントに押される形で 81年に「クリエーション」と改名してサウンドをポップ化し シングル「ロンリー・ハート」で 奇しくも自身最大のヒットを飛ばす事になったのも、 昭和の歌謡界で「ブルース」と名の付いた楽曲が 「ブルース」とはかけ離れたものだったりするのも、 そもそも日本のロックが欧米のものとは サウンドも仕様も大きく異なるのも、 日本人の音楽的情緒から「ブルース因子」が抜け落ちた所に 理由があった様に思われます。 ■ この様に 原点回帰出来る様な歴史的音楽基盤の無いまま発展した日本の音楽は 廃れたら消えて、新しいものが「根無し草」の状態で生まれて又廃れる、 を繰り返す 「体力のないジャンル」となり 日本の音楽界の「10年の遅れ」はその後も埋まる事無く 21世紀を迎える事になります。 一方で、 「ビートルズ」を体験した後に 音楽をマニアックに学問的側面から捉える 日本人ならではの「探究心」が昂じて ピンク・フロイドやディープ・パープルやブラック・サバスの様な どれも「ロック・バンド」ではあっても サウンドも演奏理念も全く異なるこれらのアーティスト達を 全て「ROCK」というひとつのジャンルで括り レコード店の同じ棚に置いて販売していた 当時の欧米の音楽業界とは異なり、 「フォーク・ロック」「ソフト・ロック」「ハード・ロック」などの 音楽用語で差別化し、 レコード店でも細かくジャンル分けして販売管理する 「音楽ジャンルの細分化」が行われる事に繋がり その様な中で後に世界的なカテゴライズとなる 「プログレッシブ・ロック」という 日本独自のジャンルを 生み出す事にも繋がるのでした☆ という訳で、これでプログレに繋がりましたW ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- 12.「日本のROCKの特異な発展とその脆弱性」 -----------------------------------------------------------------------------------  L'Arc en Ciel (画像参照: wikimedia) ・・・さてここで再び80年代「ビジュアル系」の話に 話を戻しますが・・・ これまで話してきた「ブルース」とロックミュージックの関係から 「ブルース」から派生したロックを「正統派」とするとして 先程説明した様に日本の音楽界は 「ビジュアル系ロック」の様なジャンルが、 正統な道筋を通らずに派生した音楽的土壌があり 欧米とは異なった特異な発展を遂げた事から 日本のロックは近年欧米に注目される様になっても 音楽的には「根無し草」に近い 派生しても廃れたら消えてしまう 体力の無い脆弱なジャンルとなったと語りました。 これは思うに、 ロックミュージックもポップスも同等に捉える 欧米の音楽の評価とは異なり これまで語ってきた 70年代に「ロックは不良」90年代に「ビジュアル系」といった、 本来の音楽性とは異なった「見た目から入る」捉え方が 一般的な評価のあり方だった所に この様なブルース体験が抜け落ちた国民性となった 一つの大きな要因があったのかもしれません。 ■ 日本では、 90年代にROCKが音楽ジャンルの一つとして世間に認知されましたが 当時のバブル景気も相まって 音楽界はこれをひとつのビジネスチャンスと捉え 「ロック」でも何でも無い曲をラウドに演奏した「企画物」から ロックをネタにした「ネタ物」に至るまで 様々な音楽を「ロック」と称して量産し ヒットを飛ばし話題となるのですが それによって音楽市場は玉石混交の飽和状態となって行きます。 やがてバブルが弾けると同時に、 そうして世に出たバンドの多くは姿を消すか、タレント化して行く中で 「ロック」はコアなジャンルとしてインディーズ化したり、 ロックとも歌謡曲とも違うノンジャンル音楽へと姿を変えて 存続して行きます。 ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- 13.「サブカル化するROCKと見限られる邦楽界」 -----------------------------------------------------------------------------------  影山ヒロノブ (画像参照: wikimedia) そんな90年代後期、 バブル期以前から存在したロックバンドのアーティスト達は バブル景気を経て態度を硬化した日本の音楽界の洗礼を受けながら、 音楽界の中で生きる術を模索していた頃 日本特有の発展を遂げてきたという点では日本のロック文化と酷似する 日本のサブカルチャー文化を代表する「アニメ」文化から派生し すべてのジャンルの音楽を貪欲に吸収してきた「アニソン」が 表現の可能性を求めるロックアーティストの 受け口となって行きます。 元々アニソンは作品の劇伴(BGM) 「サウンドトラック」としての性質を持っている事もあり、 「ヘビーメタル」の重厚感に「ハードロック」の攻撃性と 「プログッシブロック」の先進性物語性などを兼ね備えた ロックの楽曲は エモーショナルに作品の世界観を表現する楽曲が求められる 「アニソン」との相性も良く 日本のロックは 新たなマーケットとして登場した「アニソン界」という 巨大な渦の中に糾合されて行くことになります。 アニメの大ヒットによりブレイクした ロックアーティスト達はアニソン界での成功を受けて 今度は封印していた自身のバンドを再結成し アニメの劇伴制作を通して学んだ グローバルな視点とクレバーな観点で 日本の音楽界にこだわらない音楽活動を開始し ロック・ミュージックのメッカとなるドイツでレコーディングをして 欧州のロックシーンを見据えた海外での活動を展開して行きます これは欧米ロックの「ブルース」への回帰とは いささか異なる動きではありますが、 こうして日本のロックは 日本のサブカルチャー文化を通して音楽活動の原点に立ち返り 再びロック・ミュージックに回帰して行くのでした。 ■ 日本のロック元年となった60年代後期から数えて約半世紀が過ぎ これまで日本のリスナーや業界は偏狭な見立ての中、 果ては「アニソン界」へと流れて行く様になるまで 様々な形で「ロック」を冷遇してきましたが 21世紀に入り「ネット社会」の誕生で 表現場所を選ばない発信が可能となり 米国は「POPS」欧州は「Hard ROCK、METAL」 日本は「アニソン」といった 世界的な「音楽シーンのエリア化」が進み 全ての物事がより良い環境を求めて多様化が始まりますが、 この様な新たな潮流の中 豊かな文化があっても経済の目線でしか物事を捉えず、 文化を推し量るフレームワークが成っていない 日本では 訪日外国人によるインバウンドブームが過ぎて 「観光公害」が叫ばれる事態に陥る事も予期できなかった様な、 「会社を立て直す」名目で「技術」を売払い 「金」の代わりに会社を「空」にしてしまう様な、 「必要ない」という理由で過去の技術が 次々と海外(主に中国)に流出させている様な、 この様な日本の社会問題同様に 日本のロックのこの動きは 音楽を文化の一環と捉えて国策として推進してきた欧米諸国とは異なり 日本が昔から音楽文化の発展に無関心だった事で、 遂に「ロック」の方に見限られた 形で 日本から「ロック」が離脱しつつある事を意味し 本格的に音楽の「根無し草化」が加速している 状況に陥っている証の様にも見えます。 その様な形で「柱」となる音楽ジャンルが次々と空洞化し 日本と欧米との音楽文化の遅れが「格差」として拡がっている現れとして、 演技にもルックスにもそんなに特徴の無い俳優でもある歌手が ドラマの最後にダンスする懐かし風の曲がなぜか大ヒットしたり メインストリームから外れた香水の曲がTikTokでバズリ突如話題になったりする 予測不能の「異常気象化」がよく見られる様になっております。 これは日本の音楽界の多様化が形骸化し 将来メインストリーム不在の 暗黒の時代 を迎える事になる と言っても過言ではない状況にある現れなのかもしれません。 ・・・その真偽はさておき (※あくまで個人の偏狭な意見の妄想ですW)・・・ その様な中でも「ロック」は 表現の場を求めて隙間を縫う様に 形を変えながら生存し育って行く 地に根の生えた木々の様に力強く、雑草にも勝る生命力で開花する 「生きるカルチャー」だと 思えるのでした。 それでは、順番に聴いて行きましょう♪ ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- - 楽曲解説 - ----------------------------------------------------------------------------------- △▼△▼△▼ NOVELA - 調べの森 (1984) 収録アルバム 『サンクチュアリ(聖域)』  Forests in Yakushima (画像参照:Wikimedia) ギターの平山照継率いるプログレッシブロックバンド「NOVELA」の めくるめくダンジョンの世界に足を踏み入れたかの ダークファンタジーを思わせるマジカルなナンバーです NOVELAは元祖ビジュアル系バンドとしても 多田かおる の漫画 『愛してナイト』 のモデルとなった事としても 有名なバンドで 当時関西系ロックバンドの実力派『シェラザード』から 平山照継(Gr) 五十嵐久勝(Vo) 永川敏郎(Key) 秋田鋭次郎(Dr) 『山水館』から 高橋ヨシロウ(Vo/Bs) 山根基嗣(Gt) の2バンドが合体しデビューした 選ばれた精鋭によって強化されたスターバンドでもありました。 しかしそうなった背景には プログレ というジャンルに難色を示したレコード会社が 話題性をという付加価値を付け足した 企画バンド としての結成という実情があり この様に当事者達が望まない形で新人バンドがデビューするのは 当時の音楽業界では珍しくない事でした。 ■ ノヴェラのサウンドは、 初期のジェネシスの様な寓話性に溢れた内容を ツインギターによるハイレベルな演奏で ドラマティックに表現するのが特徴で まだビジュアル系という言葉が無かった時代に 少女コミックの主人公たちが画面から飛び出してきた様な 美しいルックスのミュージシャン達が それに相応しい美しく幻想的でドラマティックなロックを演奏する 美形バンドとして話題となり イギリスのグラム系バンド GIRL の前座を演っていた時 メインのGIRL を見ずに帰る客も居たという伝説を残している程の 女性ファンからの支持の高かったバンドでもありました。 3枚目のアルバム「PARADISE LOST」では もうひとりの中心人物でボーカルも担当したベースの高橋ヨシロウの音楽性を 全面に押し出した様なハードロック的なアプローチが際立つ内容となり これまで以上にパワフルな楽曲作りは 「ハードプログレ」と称される程の進化を遂げるのですが 中心人物が二人いるバンドとしての限界点に達したのか このアルバムでの成果が結果として ハードロックバンド「ACTION」結成の手応えへと繋がり 高橋ヨシロウ(Bs) 山根基嗣(Gt) 秋田鋭次郎(Dr)の脱退劇を 生み出す事になります ■ 本曲はそうした山水館組の脱退後 新たなメンバーとして 笹井りゅうじ(Bs) 西田竜一(Dr) 招き 新体制となったNOVELAの、更なるプログレ色を強めたアルバムからの 表題曲的ナンバーで テクニカルでエモーショナルな演奏のNOVELAらしい語り口で 富野由悠季監督作『聖戦士ダンバイン』を思わせる ジャパニメーションの映像が浮かぶ様な ダーク・ファンタジー的な世界へ誘いつつ ある種の寓話的世界を現代へと投影させる世界観で 自己啓発を誘う様な内容になっております。 これまで比較的オリジナル色のある楽曲を排出してきたNOVELAが 本曲では冒頭のドラムがGENESISの『Wot Gorilla?』そのままだったり 別曲では『One For The Vine』を模した導入など 「静寂の嵐」時の GENESIS を 露骨なまでに模したアプローチが多数聴かれ サウンド的には進化というよりはリーダー平山の音楽性が色濃く投影された マニアックな内容になった様な印象の作品となりましたが 元々少女コミックから抜け出した様なビジュアル系バンドという触れ込みの 実力派バンドだった事もあってか ファンタジーコミックをベースにした印象の 現在の「アニソン」を思わせるサウンドに仕上がっている所に、 日本特有の「アレンジ文化」の最たる姿が見て取れると共に 現在の邦楽界の源流を感じさせるものがあり そういう意味においても本作は 非常に興味深い作品と言えると思います。 ▲目次へ▲ △▼△▼△▼ 難波弘之 - ブルジョワジーの秘かな愉しみ (1985) 収録アルバム『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』  KORG Mono Poly (画像参照:Wikimedia) 山下達郎のバックとしても、プログレ好きとしても知られる 日本屈指のキーボーディスト難波弘之が、 これまで関わってきた日本の歌謡曲、ポップスを自身の解釈で プログレミュージックで昇華させた作品集からの表題曲です。 難波弘之は70年代後半からスタジオ・ミュージシャンとして活躍してきた 人気キーボーディストで アカデミックで確かな音楽的背景と、 クラシックからジャズ、ポップス、歌謡曲まで網羅する幅広い音楽性と キース・エマーソン率いるEL&Pを始めとする欧州ロックに傾倒する 音楽的個性を兼ね備えたミュージシャンで 山下達郎を始めとする様々なアーティストが 絶大な信頼を寄せる事でも有名なミュージシャンです 又、SF作家として小説を発表したり タレントとしても番組司会をする多才な人物でもあります ソロでは自身のバンド『センス・オブ・ワンダー』での活動を 数十年に渡って続けており 大きな影響を受けたキース・エマーソン同様の3ピースバンドで 今もプログレッシブ・ロックを演奏するこだわり様で センス・オブ・ワンダーの25周年記念ライブでは ゲスト出演した山下達郎に ムーディー・ブルースの「サテンの夜」を唄わせた程の徹底ぶりを見せ付け デビューから一貫したスタイルで演奏活動をし続ける 数少ないミュージシャンの一人と言えます。 ■ 本曲はフランスの監督 ルイス・ブニュエル の代表作 『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』を題材にしたイメージ曲で ドラマティックな変拍子のイントロの後、 トレブリーで重いベースサウンドでリフを奏でる インタープレイの無い構築されたアレンジで曲が進行し 上流階級の精神的退廃と衰退を非現実的な視点で語る歌詞を 難波の個性的な歌唱でリリカルに歌い上げながら ハイライトとなるメカニカルで緊張感溢れるソロパートへと 流れていくという ミュージシャンとしてアレンジャーとしての音楽活動で培われ 作家活動を通して身に付けた確かな構成力に支えられた 多分に文学的でエモーショナルな楽曲として仕上がっており 自身が傾倒するプログレッシブ・ロック・サウンドをベースに フランス象徴派の退廃的で耽美なモチーフを歌謡曲とロックに昇華した 80年代中期までの活動に於いて、ある種の到達点に達した 聞きやすくドラマティックでスリリングな音楽が堪能できる 難波弘之の代表作的楽曲になっております。 ■ 本曲の作詞を担当した森雪之丞は、 布袋寅泰作品、氷室京介作品などで知られる 「ビジュアル系」と呼ばれる日本特有のロック・ミュージック生誕に関わり 歌詞のスタイルを確立させた一人として 日本ロック史に於いても重要な音楽家と言える人物で 本曲では耽美主義的文学が持つ「退廃」さを スタイリッシュな形でロックに昇華させた 「ビジュアル系」ロックの原型が伺える 小説家でもある難波弘之が作る音楽の文学的側面を支える 傑作に仕上がっております。 難波弘之によると、森雪之丞が作詞する歌詞は アーティストや音楽プロデューサーが方向性のみを伝えて 後は作詞家の作家性にお任せする、 ありがちなやり方で作られたものとは違い 作曲者やアーティストに 楽曲にまつわる様々な事を「イメージ」として語ってもらい 時には一見楽曲とは関係のない、脈絡の無い会話の中から 必要なイメージをアーティスティックな形で引き出し その様にして受け取った様々な濃密なイメージから インスパイアされたものを再構築して 楽曲へと転化させる、エモーショナルなものだと語り 言わば、 バンドに於いての「セッション」を重ねた末に生み出される様な 極めて「音楽的」なものではないかと思います。 ▲目次へ▲ △▼△▼△▼ 美狂乱 - 二重人格 (1982) 収録アルバム『美狂乱』  日本のお面 (画像参照:Wikimedia) リーダーでギタリストの 須磨邦彦 率いる 「和製キング・クリムゾン」と呼ばれた 超個性派音楽ユニット 美狂乱のデビュー・アルバムから 東洋的神秘感漂う静寂さと英国ロックの躍動感を併せ持った 息苦しい程の緊張感が全編を覆うオープニング・ナンバーです。 このバンドは音楽性もそうですが、 デビューに纏わる話が変わっており、 先程の「NOVELA」のメンバーが、プロミュージシャンとして世に出る為に 紆余曲折を経て「混成バンド」としてレコードデビューを果たした事に対して この時代にプロ・ミュージシャンを目指した セミ、アマ・ミュージシャン達の最たる例を見る様な 美狂乱のレコードデビューには「MOVELA」とは全く違った 紆余曲折がありました。 という訳で、美狂乱の紹介は楽曲に付いてはそこそこに・・・w 主にバンドがデビューするには そのバンドがどれだけ魅力があるのかという点よりも その様なバンドを排出する周囲の音楽環境と音楽的土壌が より重要になってくるという、 人気バンドがレコードデビューに至るまでの音楽事情に目を向けて よりディープな見地から作品を捉えてみたいと 思います☆ ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- 1.「レコード会社に振り回された当時のバンド事情」 ----------------------------------------------------------------------------------- 美狂乱のレコードデビューは 同レーベル所属で先行デビューしたNOVELAが一定のファンを持ち レコードセールスが順調だった事で クリムゾン・コピー・バンドとして名を馳せた「まどろみ」時代から 音楽コンテストで高い評価を受けていた事から 鳴り物入りで浮上するのですが この時 美狂乱はレコーディングのリハーサルまで漕ぎ着けながら メンバーの離脱に遭い、 残ったメンバーとでは、音楽で生計を立てるかどうかで悩み 当時傾倒していたクリムゾン・フリークを貫きたいリーダー須磨は プロ活動を諦め、最期のメンバーも美狂乱から離脱 美狂乱は事実上の解散状態となり、レコーディングは頓挫します。 美狂乱はキングレコードのプログレ部門だったNexusレーベルから 2枚のアルバムをリリースしていますが、それは 唯一のメンバーとなった須磨が レコード担当者からの再打診を受諾し 実姉がコーラスで参加した経緯から 「トランザム」のチト河内をプロデューサーとして迎え、 ドラムとベースは静岡時代の仲間に声を掛け 集めて、 ゲストミュージシャンとしてチト河内の紹介で 当時芸大の学生だったバイオリニストの 中西俊博 と 「HeavyMetalArmy」 のキーボーディスト 中島優貴 の協力を得て 解散したバンドのメンバーの一人が 身内の力を借りて ソロアルバム を制作した様な レコードリリースでした。 美狂乱もそうでしたが、 当時のセミ、アマ ミュジシャンが 一様にプロを目指す中で ライブバンドとして名を馳せながら、地方から都市進出を目指す途上で メンバー間との方向性の相違による脱退や、 疲弊したメンバーのリタイヤなどに遭いながら 失意の中で帰郷するというケースは多々有り、 バンドブームと呼ばれた80年代後半に活躍した 「十二単」や「ハリースキュアリー」の様な人気バンドがCDデビューが無く その後なぜかメンバーのソロアルバムだけがリリースされるという 現象が見られたのは レコードデビューが決まり契約した直後に 様々な理由でバンドが解散状態となり せっかくの契約を破棄したくない、又は 契約不執行にならない様に 残ったメンバーでの代替えリリースとなった というのが主な理由ですが ライブで名を馳せながらもプロとしての力量に欠けるバンドや 人気の無くなった有名バンドの「解散」を一つの話題としてCD化させる、 などの辛辣な理由も含めて、 CD全盛のバブル時代には、好景気に日本中が浮かれていた事も相まって 次々と立てた企画が直様通り、CD化が決まる様な状況にあり 出せば売れる世の中だった事もあり、次から次へとCDが量産され 音楽業界は玉石混交の飽和状態と化していました。 その様な中でデビューしたバンドの多くは まともな販促も受けられ無いままCDをリリースされ ライブ活動をする予算もプロモーションも無いまま飼い殺し状態となり 在庫のCDを抱えて全国をどさ回りに近いライブ活動を行い 手売りでCDを捌いた挙げ句、疲弊したメンバーの相次ぐ脱退に遭い 残ったメンバーは身内のミュージシャンやセッション・ミュージシャンで 脱退の穴を補填しながら 契約分のアルバムをリリースした後は解散し その後スタジオ・ミュージシャンになったり、 リタイヤしたりするというのは バブル時代の音楽界では良くある話でした。 美狂乱の場合も、レコーディングの為にメンバーを補填して 契約分のレコーディングと数回のライブをこなした後は解散しているので 表面上は良くあるバンドの顛末だったと言えますが 殆どのミュージシャンがたとえ一人になっても アルバムリリースをチャンスと捉えて プロとしてアーティスト活動をして行く橋頭堡として レコーディングに挑む事に対して、 美狂乱の場合は、リーダーの須磨がこれまで積み上げてきた楽曲の披露と クリムゾン研究で費やした実験成果を記録するという 個人的理由の目的でレコードリリースを承諾したらしく、 音楽で身を立てる事を止めた一介の一般人ギタリストが 純粋にアマチュア精神で取り組んだ音楽的成果を披露する為に 商業音楽を利用したという、 Youtube全盛の現在ならともかく バブル時代以前の厳格な音楽界に於いて、極めて珍しいケースと言えます。 結果的に美狂乱の代表作となったこの2枚のアルバムは、 リーダー須磨邦彦の個人的嗜好性が反映された 「キング・クリムゾン」そのままのサウンドとなり コアなファンの間で話題となりました。 80年代初頭は「真似」も再現度が高ければ評価されていた時代で 再現は不可能と思われたクリムゾンが美狂乱で再現されたばかりで無く 日本の音楽と融合したクリムゾン的な完成度の高いサウンドが より高い評価を得る事に繋がるのですが これは「ロックギタリスト」を目指した当時のミュージシャン達が 一様に判で押した様に 「ブルース」に傾倒した後、やがて音楽性の不足感を感じて 流行りの「フュージョン」にのめり込む 定番の流れに対して、 須磨自身はそうした当時の風潮を含めて忌み嫌い 定番で人気の演奏を強いられる「プロ」の立場では不可能な、 自己の表現の道を「アマ」の立場で見出して 「ブルース」を徹底排除し独自の音楽を嗜好した一つの結果だったと言えます。 ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- 2.「音楽的個性の根付きと偏狭性との関連」 ----------------------------------------------------------------------------------- ロックを演る上で「ブルース」とは 言わばロックの基盤に当たる避けては通れない楽式なのですが、 チョーキング(弦を指で引っ張り音程を変える奏法) すら否定する 須磨のこだわりは尋常では無く 60年代後半から殆どのセミ、アマミュージシャンが R&Bに傾倒し 「魂」をウリ文句としながら「流行」としての「R&B」に陶酔する状況や 70年代後半に「フュージョン」がブームになると日本中がのめり込んだ様を 「堕落」に映ったと語る須磨の感性は、 一見極端で偏狭なものに映りますが 当時のバンド事情は現在の様に、 アーティストがサウンドを求める事に何の縛りも、 ジャンルにも捕らわれる事無く、 何をするにも全てのジャンルにお手本となる名盤、名手が存在し 奏法、手法が確立され、求めるままに自由に音楽を追求出来る 情報溢れる21世紀の時代とは異なり 登場したミュージシャンの作品が後世のジャンルとなり名盤となって行った ロック未開の日本の60年代後半から70年代初頭に至っては、 ロックがブルースから派生した音楽である限り ロックを志す者がブルースから入るのは当然の流れであり この後「ハードロック」「プログレ」の様な ロックから派生した音楽が登場する以前の世の中で 音楽の入り口が皆一律同じになるのは当然で、 それが当たり前な事なんだと、誰もが疑問に思わない世の中にありました。 又、 学生運動が収束する最期の時期と重なっていた事もあり 商業音楽に手を染める事は堕落を意味するという 一部 極端な風潮が根付いており フォーク音楽の大御所、吉田拓郎が「結婚しようよ」を大ヒットさせた時 フォーク歌手がメジャーな音楽を演ったという理由で 世間に媚びた音楽としてコアなフォーク・ミュージック・ファンから 怒りを買う様な世相の中にあり 音楽を嗜好する事が思想の一部と捉える考えが まだ残っていた時代でもありました。 当時は、 「ギターはカッティングしか演らない」「ジミヘン以外は音楽じゃない」 の様な偏屈な考えを持ったミュージシャンは数多く居ましたが 80年代がマニュアル重視の 管理社会 となるのと同時に 音楽界でも型にはまった「教則」「理論」「手法」が重視される様になり 結果 無個性の時代 と呼ばれる様になって行った事とは逆の理由で、 70年代に活躍したミュージシャン達のルール無用の極端な捉え方が 音楽を通して影響を受ける際の ある種のフィルターとして機能して 楽器音を聴いただけで誰が演奏している事が分かる程の 独特の個性を持つ要因となって行ったとも 考えられるものがあります。 その様な60年代70年代の時期に、 情緒が形成される少年期青年期にかけて音楽に触れ続けた事が 少なからず須磨少年の独特な感性を決定付けた 要因となって行ったのかもしれません。 ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- 3.地方型音楽を形成する音楽的地盤 ----------------------------------------------------------------------------------- 美狂乱のアルバムはリーダー須磨のソロ・アルバムと呼べる 個人的嗜好性が収録されたものでしたが 同時に、 一般人ミュージシャンとなった須磨の音楽活動のベースとなった 故郷 静岡の音楽シーンと そこで活躍していた プロ、アマ、含めたミュージシャン達の存在が反映された 地方型音楽 という側面を持ったプロジェクトでもあった様に思われます。 リーダー須磨は1970年の中学時代、 地元静岡県沼津でギタリストとして頭角を表し スタジオ・ミュージシャン時代の「一風堂」土屋昌己の目に留まり、 土屋昌巳がプロデュースするバンドのメンバーに抜擢された事をきっかけに 静岡県に在住する凄腕ミュージシャン達との長年に渡る交流が始まり ギタリストとしての音楽的な基盤が形成されて行きます。 美狂乱の2枚のアルバムから感じる、 クリムゾンとは違ったある種の懐かしさと突き放した様な疎外感が同居した様な 美狂乱特有のサウンドが生まれたのは 学生時代からギタリストとして活動して来た須磨が 東京とも大阪とも違う、メインストリームから離れた 地方特有の情報が偏りがちな音楽環境の中で 知り合った才能ある様々な地元ミュージシャン達との交流と ジミー・ペイジに傾倒しながらブルース・フィーリングが肌に合わず ラテン系ミュージックやワールドミュージックに表現の糸口を求めて模索し ロック・ギタリストとしては行き詰まっていた須磨が クリムゾンのギタリスト、ロバート・フリップとの出会いで活路が開かれ クリムゾンの研究に明け暮れて来た「まどろみ」時代の1977年に 折しも日本中のミュージシャンが夢中になっていた フュージョンブームの台頭で メンバーすら感化された事に失望した体験が背景となり その様に混沌とした静岡の音楽シーンが須磨の感性で切り出した様な所に 美狂乱特有のサウンドへと繋がって行ったという 印象があります。 ある意味「美狂乱」とは 須磨に音楽的刺激を与えてきた 静岡のミュージシャン達全てが関わってきた成果の呼称であり 美狂乱がメインストリームで流行しているサウンドを嫌い あくまでアマチュア精神に固執するのも 70年代当時に於いては、音楽の入り口を自ら狭めている業界の風潮を嫌い、 21世紀の現在に於いては、音楽の間口が拡がり過ぎた事から 売れる為には考えうる限りの全てを導入し 結果中身の無いものを排出する業界の実態に迎合したく無い事に加えて、 自ら求める音は可能な限り追求し 最後は限られた時間内にどこまで完成度を高められるかで 如何に折り合いを付けるのかという プロの世界で 結果、商品価値の高いサウンドを輩出するのが 「商業音楽」である事に対して、 無制限の時間と、自らが求める音をとことん追求出来る環境の中で 納得行くまで音作りが出来るのが アマチュア精神であり 結果、プロでは出来ない採算度外視の究極のサウンドに到達するのが 「嗜好の音楽」と言えるので、 一般人ミュージシャン という立場に行き着いた所に 大きな理由があると思います。 「夢の様な環境」と語る音楽スタジオを自宅に持ち 何時間も籠もって音楽に没頭するのは 音楽を嗜好する「オタク」的な印象を受けますが その頂点にいるのは山下達郎という ハイレベルな世界でもあります。 山下達郎が商業音楽の世界に居るのは 山下達郎が「商業音楽」が好きだからだそうですが 山下達郎の音楽には自身が傾倒する 「オールディーズ」への回顧する想いが 反映されている所があります。 対して美狂乱が一般人の立場で音楽を追求しているのは一見 「キング・クリムゾンサウンド」の再現の為の様に見えますが、 美狂乱の成り立ちが、 これまで話してきた様な背景があるのならば 須磨の音楽を育んだ かつての静岡の音楽シーンへの 回顧する想いが投影されている様に思われます。 故に美狂乱は、 Youtube以前の時代から 一般人ミュージシャンの立場で音楽を発信し 80年代には2枚のアルバムをリリースし 90年代には再結成し独自の環境で独自の音楽を追求し続けて 2003年には アニメ『魁!!クロマティ高校』の音楽に抜擢されるという 日本の音楽界の中で 一般人ミュージシャンの音楽が、商業音楽で起用される 唯一無二のユニークな存在だと言えるのかも しれません☆ ▲目次へ▲ △▼△▼△▼ 四人囃子 - おまつり (1974) 収録アルバム『一触即発』  日本のお祭り (画像参照:Wikimedia) ドラマーでリーダーの岡井大二と、 初代「プリズム」ギタリスト 森園勝敏を中心とした 日本屈指のプログレ系バンド「四人囃子」の 気怠い耽美的幻想美とロックのダイナミズムが アングラ劇テイストな切り口で括られた 70年代の日本のロックのみならず、 当時の日本の世相を彷彿とさせるサウンドの響きを持っている点に於いても 非常に重要でユニークな作品で占められているアルバムからの 人気作となっております。 ■ 四人囃子は GSブームを経て世の中が「ビートルズ」の時代になって行った 50年代60年代の音楽に触れて ロックが現在の形へと進化して行くその空気を知るミュージシャンの集団で 日本では数少ない、巨大な音でドラムをプレイする 「ハード・ショット」正統派ロック・ドラマー岡井大二と、 「ブルース」ブームにあった当時の日本の音楽界で 十代の若さで頭角を表した天才ギタリスト森園勝敏のユニットとしてスタートし 当時の洋楽ファンも納得する高い音楽性と演奏力、構成力を持つ 日本のオリジナル・ロックを目指して 一般には「和製ピンク・フロイド」と知られる 単にプログレの枠組みでは語れない 多才な楽曲を発表し 現在も活躍している音楽ユニットです。 ■ 本曲は「和製ピンク・フロイド」の名の通りの 幻想的で揺蕩う様な気怠いサウンドが特徴の作品ですが 演奏はブルースベースでありながら、欧米のものとは響きが異なり まだロックの黎明期にあった60年代後期から70年代初頭の日本の音楽界で 「GS」ブームで登場した歌手、バンドを含めて 「芸能人が唄う音楽」とは異なる 「ビートルズ」が登場した以降の 「オリジナル作品」を求めるムーブメントに呼応した 現実と幻想が交差する様なシュールな世界感で 日本の粛然とした伝統と、激しさを秘めた混沌が同居する 極めて日本的な音世界をロックに昇華させた 初期の日本のロックを代表する楽曲だと思います。 ■ 本曲の持つシュールさは60年代以降の学生運動が収束した後 70年代の政治的に無関心となった 当時の「しらけ世代」と呼ばれる若者文化を反映した様な 「フラワームーブメント」「サイケデリック・ミュージック」 「アングラ劇」テイストを感じる 作詞の末松康生による歌詞に依る所が大きい様に思われます 末松康生は四人囃子、森園勝敏作品ゆかりの作詞家で 自身もアングラ劇経験がある事が 当時の若者文化を肌で感じる様な、気怠さと狂気が入り乱れた この時代特有の表現を持った作風へと繋がった様な印象があります。 ■ 四人囃子の中心人物のひとり、ギタリストの森園勝敏は 四人囃子が「和製ピンク・フロイド」と呼ばれる事に対して異論は無くても、 元々「ピンク・フロイド」には興味が無かったらしく、 ドラマーの岡井大二に勧められるまで、その存在すら知らなかったと言います むしろブルース・ロックに傾倒する見地から 「オールマン・ブラザーズ」の様なサウンドを目指して 「サンタナ」の様な仕上がりになったとの事で、 ロックの音楽史に精通し曲作りに於いて必然性を重要視し、 後に音楽プロデューサーとしても成功する岡井と 何となく思って作った結果がたまたまイケる形となれば良しという 感性を重んじる森園との まるで水と油の様な取り合わせが、 サウンドに絶妙な緊張と弛緩を与えて、 本曲「おまつり」から感じる、 気怠さの裏に潜む攻撃性と狂気を抱えた演奏に繋がったのかもしれません。 それ故に、この奇跡のユニットは短命で終わり 森園勝敏は脱退し、その後四人囃子はセカンドアルバムで加入したベーシストで BOØWY、ザ・ブルーハーツ、GLAY、JUDY AND MARY、 エレファントカシマシ、くるりのプロデューサーとなる 佐久間正英を中心人物に据えて活動を続け 作品ごとに方向性を変え、企画力の高さを見せますが バンドとしては迷走していく事になります。 脱退した森園勝敏は1976年に当時結成間近だったフュージョンバンド 「プリズム」に合流するのですが 1978年には脱退していますので、 これにしても理由は「何となく」だったのかもしれませんw ▲目次へ▲ △▼△▼△▼ PRISM - TAKE OFF (1986) 収録アルバム 『DREAMIN』  Korean Air Airbus A380-800 with contrail (画像参照:Wikimedia) ギタリスト和田アキラとベーシスト渡辺健を中心とした音楽ユニットで 過去に元 四人囃子の森園勝敏が在籍し ツインギター、ツインキーボードの インストゥルメンタル・バンドとしてスタートし 高い演奏力とジャンルにこだわらないロックベースのオリジナル曲が話題となり デビューライブでは最寄り駅から長蛇の列が出来るなどの伝説を残し 森園勝敏 脱退後は 激しいメンバーチェンジを繰り返し 「カシオペア」「T-SQUARE」の様なグループがポップ化して成功して行く中で その度にプログレッシブ・ロック色を増して行き 唯一無二の音楽活動を続ける音楽集団 プリズム の サポートメンバーとしてドラムス木村万作、キーボード松浦義和 ゲストにシンセ・ミュージックで名を馳せた 深町純という 強力布陣となったTDKレコード移籍 第二弾アルバムで 青空に飛行機雲が印象的な マイルドセブンのCM曲としても採用され シングル・カットされた この時期のプリズムを代表するヒット・ナンバーです。 ■ 本アルバムはベースの渡辺健がボーカルも披露する意欲作で インストの本曲では 渡辺のハイレベルなスリリングで縦横無尽の ベースプレイに圧倒されるナンバーとなっており ベースソロから始まるという珍しい構成で 清々しい朝の光を表現する会心の演奏で幕を上げると同時に 曲が一気に加速し、 大空を飛行する様なスピード感溢れる演奏となり 再び、大空に心を馳せる様なロマン溢れるベースソロへと繋がるという ベースソロを取り、ハイテンションなリフをプレイし、 ギターの様に和音でカッティングをするなどの7色のプレイで ほぼベースの渡辺健の独壇場とも言える フュージョン・ミュージックの枠内では語れない エモーショルな演奏が堪能できます ■ 現在唯一のオリジナルメンバーとなったギターの和田アキラは グループサウンズで音楽に目覚め、ベンチャーズを経験した後 ブルースに傾倒し ハード・ロックにのめり込んだ 当時の典型的な「ギター小僧」の一人で 高校には進学しないで音楽の世界に飛び込んだ ロックな人生を歩むロックギタリスト中のロックギタリストな人物で ロックギタリストの代名詞の「速弾き」ギタリストとしても知られていますが 只の「速弾き」ギタリストとは違い プリズムのメンバーだった森園勝敏によれば、 和田アキラのギターの練習は尋常では無く 毎日何時間も集中して練習し、その練習量は ギターのフレットが変色する程のものだったそうで その様な凄まじい練習量に裏付けられた確かなプレイで アル・ディ・メオラの様な流麗で複雑なスケールを高速で演奏する おおよそロックギタリストの範疇では語れない 多彩なテクニックと幅広い音楽性を持ったギタリストと言えます。 そんなロックギタリストの和田アキラが フュージョンバンドの体でインストミュージックを始めた背景には 60年代後半から70年代前半に掛けての日本の音楽界が GSブームからフォークブームにシフトした時期に当たり 正統派本格ロックを排出する様な音楽的土壌が無かった事と、 和田アキラが先程の美狂乱の須磨邦彦とは違って 音楽ジャンルや楽式に対して拘りが無くどんなものにも興味を持つ ギターを弾く事そのものに拘る「ギター小僧」だった事が要因となり それまで「インストミュージック」を形容する言葉が無かった時代に 折しも世界的ギタリストでロックスターのジェフ・ベックが 75年にリリースした「ブロウ・バイ・ブロウ」を大ヒットさせ フュージョン系インストミュージックを認識させた事で 日本でもインストミュージックが認知されヒットに繋がった事を受けて 和田アキラが当時傾倒していた サンタナ、アル・ディ・メオラの様なラテン、ジャズミュージックの他 「グランド・ファンク・レイルロード」や 「レッド・ツェッペリン」の様なハードロックや 当時登場し始めた「イエス」や「キング・クリムゾン」の様な プログレッシブ・ロックなどの 異なる音楽性を持ったこれらの欧米音楽を 日本人が理解できる形で受け入れる 日本のお家芸でもある「アレンジ文化」の精神で フュージョンミュージックへと融合した 「ハイブリッド」な音楽を追求した事で 和田アキラの音楽性が爆発的に開花した事が 大きな理由としてあった様に思います。 その様な「ハイブリッド」な音楽を追求する精神は演奏する機器にも向けられ 本作「ドリーミング」リリース当時、 井上堯之が司会するFMラジオ番組にプリズムが出演した時 スタジオに持ち込んだ機材は、同時期に活動していた 他のフュージョン系バンドと比べて ベース、ドラム、ギターの機材のに加え、 二人のキーボーディストが所有する機材の量は 尋常では無い多さだったそうで、 この反動から数年後この大掛かりなユニットの解散後は、 ベース、ドラム、ギターの3ピースのシンプルな構成に切り替わる事になるとして、w この時期のプリズムの余りの機材の多さに泡を吹いた井上に 『こんなに機材がなければ音楽が出来ないのか』 と言わしめた 当時の日本が誇る最高のスタジオ・ミュージシャンの 最先端のサウンドを聴く事が出来るという意味に於いても、 本アルバムは非常に重要で興味深い作品と言えると思います。 ▲目次へ▲ △▼△▼△▼ 高崎晃 - 逃亡 ~STEAL AWAY~ (1982) 収録アルバム『ジャガーの牙』  高崎 晃 (画像参照:Wikimedia) 日本屈指のヘビーメタルバンド LOUDNESS のギタリスト高崎晃が LAZYの解散後、 プログレ系ミュージシャン笹路正徳をプロデューサーに迎え制作した ソロ・アルバムから、 作曲の笹路正徳らしい変拍子を多用した非常にプログレ色の強い楽曲です。 ■ このアルバムが制作されたのは、 元々ソロアルバム制作の話が先にあって、 アルバム制作を通して後の「LOUDNESS」結成へと繋がるという 当時アイドルグループとして人気のあった「LAZY」解散後の活動の一環、 という流れと、 高崎自身が 元「LAZY」という肩書から逃れ、 ロックギタリストとして本格的な活動を始めた、という現れと、 高崎自身が 元「LAZY」という肩書があっての、 自由な采配のソロアルバム制作となった、という 相反する実情が背景にあったものと思われます。 それらを物語る様に本アルバムは、 日本で本格ロックギタリストを目指す高崎晃が 志を同じにする若きミュージシャン達と共に制作した ロックギタリストのアルバムであると共に マライア、ナスカの笹路正徳によるプログレッシブ・ロックを思わせる内容という 同時期にリリースされた「BOWWOW」のギタリスト山本恭司のソロアルバム「Horizon」同様に コアなロックでは無く、 サンタナ やエリック・クラプトン、ジェフ・ベック の様な ロックギタリスト主体によるアルバムが 音楽ファンに受け入れられ大ヒットした世の中の流れを汲んだ方向性で 制作された様な印象があり ロックギタリストのジェフ・ベック がフュージョン・ミュージックのカテゴリーで インストアルバムを制作し キーボーディストのヤン・ハマーに楽曲の作曲を依頼して 自作にこだわらない新たなエレクトロニック・ミュージックの可能性を 見出している所に共感する様な形で 既に「LAZY」時代に楽曲を自作してきた高崎が敢えて全曲自作にしないで 外部のライターとして笹路正徳に楽曲依頼をするなど、 まだ海とも山とも言えないロック黎明期にあった日本の音楽界に於いて 本格ロックを追求しようとする若きミュージシャン達が正に手探り状態で ブリティッシュ・ロック、アメリカン・ロック 更にはプログレッシブ・ロック、ラテン・ロック、 加えて「LAZY」時代に培った「歌謡ロック」の方法論まで詰め込んで 日本に於ける本格的なロックアルバムのあり方を模索する姿が そのままアルバムとなって生み出された様な造りになっている点に於いても 非常に興味深いアルバムだと言えます。 故に、本格ロックを期待したロックファンは 詰め込まれた内容に肩透かしを食らったり 全体的に笹路色の濃い内容になった事で 『これはギターのソロ・アルバムでは無い。ギター・ソロのアルバムだ。』 と揶揄されるなど 「LOUDNESS」誕生以前の日本の音楽シーンであらゆる意味で話題となった 作品でもありました。 ■ 本曲は作曲 笹路正徳のペンによる 変拍子が多用されたプログレッシブ・ロックな仕上がりとなった楽曲で 笹路正徳のスリリングなオルガンプレイがフィーチャーされた 作品に仕上がっています。 過ぎ去った想い出を回顧する様なオルゴールから曲は始まり 進撃するイメージと闇夜の疾走をイメージする2つのパートを 終わりを予感する様なミステリアスなオルガンリフと 何かの誕生を見る様な変拍子のセクションで繋いだ、 曲名通り、繋ぎ止める何かから「逃亡」をする苦悩を描いた ドラマティックなナンバーになっています。 本曲は「ペテンの唄で未来が消えて行く」「名声は恥辱によって荒廃させる」 と唄われる様に かつて本格ロックグループとして 「Free」のポール・ロジャース描き下ろしによる楽曲で デビューを約束されながら、その約束を反故にされるばかりか 当時日本でも人気のあった英国のバンド 「ベイシティーローラーズ」の日本版としてアイドル活動を強いられた 「レイジー」時代を回顧する様な内容になっており 人気が出る程、 演りたく無い音楽を強いられる事への不満と それによって、 演りたい音楽から遠のいて行く焦りと 演りたく無い音楽が、 実は高度な演奏力を必要とする事を思い知らされる力量不足の実感と それが売れる事で、 ロックバンドとして周りが認めてくれなくなる事への苦悩と 売れなくなれば、 苦悩の日々から救われる代わりに全てを失う事への恐れなどの ストレートなロックでは表現出来ない様な、複雑に入り組んだ深くて巨大な感情を プログレッシブ・ロックが持つ欧州音楽の陰りと アカデミックなアレンジに裏打ちされたフュージョン・ミュージックの洗練さと ロックが持つ破壊的な衝動を併せ持つハイブリッドな演奏をバックに 表現したい全てをぶつけた様な 高崎晃のギターソロが圧巻で レイジー デビュー後リリースしたシングルが振るわず、 3枚目が不振となれば契約解除となる中で、 逆に考えれば 売れなければロックバンドに戻れると安堵していた矢先に 「赤頭巾ちゃん御用心」の大ヒットで アイドル活動が決定的となった苦い経験を 苛まれる悪夢から逃れようとする逃亡者として描いた様でもある点に於いても 日本のヘビーメタル・ミュージックが開花する夜明け前に その中心となるギタリストの瑞々しいプレイが堪能できる 日本のロック史に於いても非常に貴重な「名曲」と呼べる楽曲だと思います。 ■ 本曲のボーカルは二井原実が担当し、 他の曲ではベースに山下昌良、ドラムにレイジーの樋口宗孝が参加するなど このソロアルバム制作が後に 日本のロックが1985年に『Thunder in the East』で 初の「全米アルバムチャート」ランクインを果たす快挙を遂げる 本格ヘビーメタルバンド「LOUDNESS」結成に繋がって行きます その「LOUDNESS」も、世界進出で全米チャートインを果たす代わりに 「LOUDNESS」の代名詞だった複雑でコアなメタルサウンドを封印し 米国のロックファン向けのシンプルな アメリカン・ロックサウンドを強要されるという 「レイジー」時代の苦悩が再び繰り返されるという 皮肉を経験する事になるのですが 今回その苦悩は既に経験済みとして、 高崎晃はメンバーと共に乗り越えて 「LOUDNESS」は世界に羽ばたくバンドへと成長して行くでした。 ■ 本曲の冒頭の 『DANCE!』 という二井原実の出だしに ドラムの辻野リューベンは 鳥肌が立ったという 未確認の話が残っていますがw そのドラムのリューベンは テンポが変わった唄の出だしで 笹路の変拍子アレンジに毒されて 頭が混乱したのか スネアの位置が裏返ります 普通ならNGで録り直しの所ですが 全体の出来の良さに 瑣末な事とされたのか黙認された様です 実に大らかな時代でしたw ▲目次へ▲ △▼ △▼ △▼ TAO - Hello Vifam (1983) タオ - ハロー・ヴァイファム 収録アルバム『FAR EAST』  NGC 4414 (NASA-med) (画像参照:wikipedia) オープニングは衝撃的でした・・・ グローバルな活動を見据え結成され80年代にデビューした ギターボーカルのデビッドマン率いるロックグループTAOの アニメ『銀河漂流バイファム』の主題歌になった 代表曲的ヒット曲です ■ TAOは日本のROCKバンドには珍しい ヴァイオリンを導入した所にサウンドの特徴があるバンドで UKや中期キング・クリムゾンの編成を思わせる プログレッシブ・ロックを嗜好するロックサウンドをベースに ギター・ボーカルのデヴィッド・マンによるポップなセンスを加えた ユニークなサウンドを作り出す音楽集団でした クラシカルで格調ある 宇宙空間を進撃する壮大なイメージをバックに デヴィッド・マンのポップで少年性を帯びたボーカルが光る 宇宙を漂浪する主人公達を描いたSFアニメーション作品にマッチした本曲や キューピーマヨネーズのCMソングとなった『アジュール』などの 牧歌的で爽やかな印象が小気味よい コマーシャリズムな楽曲を制作する事に長けた音楽集団でもありました ■ このバンドはヴァイオリン&キーボードの関根安里を加えたリズム隊に デヴィッドマンを加えたユニットという色合いが濃く プログレッシブ・ロックを志向するバック3人と ポップなサウンドを目指したデヴィッドマンという 水と油の取り合わせで起こる化学反応によって 個性的な楽曲を生み出していた所に音楽の特徴があり 全曲英詩によるバンドとしてはゴダイゴの様な聴きやすいサウンドという側面を持ったバンドでもありました。 ハイクオリティな音楽を高音質で鑑賞する事がブームとなる 内需拡大路線に入る直前のJ-POPのムーブメント以前の音楽界に所属していた為 純粋にクオリティーの高い音楽を提供する以前に バンドを存続させる為に来た仕事は何でもこなし TVCM曲やドラマの主題歌を担当し、売れる為の布石を惜しまない コマシャーリズムの枠組みの中で世に出てブレイクするタイプの 商業バンドの一つでもありました。 特に80年代前半はアニメブームの過渡期に当たる時期でもあった為に アニソンが新たな表現を求めてシティーポップ化した頃にあたり 当時ハイクオリティな音楽を演奏する集団だった 「トランザム」「TALIZMAN」「クリスタルキング」や「ゴダイゴ」 実力派ボーカルとして活動していた「杏里」などが 主題歌で起用され その流れで当時ゴールデンタイムという非常に重要な枠で放送された 「銀河漂流バイファム」の主題歌にTAOの起用が決まった様な印象がありました。 現在の様にSNSはもとより、ネットが存在しなかった当時は TV、ラジオが音楽発信の場であり、 特に楽曲がヘビーローテーションされるのはFMラジオの音楽番組よりも TVCMでの起用曲が有力だった時代に TAOの様に個性的な音楽性を持ったロックバンドが元々持っていた音楽性を変えて CM曲やTV主題歌を担当してブレイクを狙うのは 当時の常套手段の一つでもありました。 TAOの場合はキューピーマヨネーズのCMが好調ではあっても 「ヴァイファム」の視聴率不振で (※裏番組はドラえもん) 番組そのものが途中で子供向け作品に制作方針を変更するなどの迷走があった為か 杏里の「キャッツアイ」の様な社会現象を生むまでのブレイクには至らずに シングル数枚とAlbum1枚をリリースした後は 元々の音楽性を追求しようとするプレグレ組3名が 80年代中期の洋楽ブームが引き金となった空前のROCKブームに乗る形で 新たなサウンドのロックバンド結成を目指して デヴィッドマンを残して脱退し、TAOは解散状態となります その後プログレ組はギタリストとボーカリストを加えて「EUROX」結成し 『ヴァイファム』と同じサンライズ作品の『機甲界ガリアン』の主題歌を担当し 当時流行だった綺羅びやかでスタイリッシュなサウンドのバンドへと 変身を遂げますが Album1枚をリリースした後は活動を停止します J-POP以前の日本の音楽界で全曲英詩でアルバムリリースをするのは 当時としても珍しい事で 「ゴダイゴ」の成功あってのものだった様に思われますが バンドが続かなかったのは、 「デキシーズ・ミッドナイト・ランナーズ」に近いケルティックテイストな 欧州ロック特有の陰りのあるプログレッシブ・ロックサウンドが 当時全世界的に「デュラン・デュラン」を始めとする スタイリッシュなブリティッシュ・ニューウェーブ・サウンドに傾いていた事で 大衆に受け入れられなかった事と 離脱したプログレ組が「EUROX」でプログレサウンドをあっさりと捨てて ニューウェーブサウンドに切り替えた所を見ますと、 TAOサウンドを貫きたいデビッドマンと「方向性の違い」で仲違いした事が 大きな理由だったのではないか と思われます。 後日デビッドマンはメンバーを集めて「TAO」を復活させながらも メインストリームで活躍する事はありませんでしたが 「David Mann」名義でコアなファン向けに活動を続けた様です。 思うに「TAO」は、 空前のROCKブームの最中、J-POP誕生以前の日本の歌謡界で 自身の音楽性を持ちながらも需要があれば臨機応変にサウンドを供給する 「商業音楽」の括りで誕生した最後に当たる音楽集団であり 故に期間限定で短命に終わる事は約束された様な中で 「ケルトティックなプログレサウンド」という 通常なら音楽的にも共存出来ない様な個性的なサウンドを 「商業音楽」として輩出出来たのだと思います☆ △▼△▼△▼ ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- - OUTRO - ■新世代音楽の個人化とコラボとの関連性■ -----------------------------------------------------------------------------------  Tina Turner and Eric Clapton at Wembley Arena, June 18, 1987 (画像参照: wikimedia) さて、 INTRO 前書きでは ロックを中心に見た 日本の音楽界のあり方を やや 偏狭な視点から(※シニアの視点とも言う) 語ってみましたが 次は やや閉鎖的な視点から(※若者の視点とも言う) 語って見ますw と言うわけで後枠では、 現在は世界的な傾向で 異なるジャンルの個性派アーティスト同士が組んで 画期的でエモーショナルなサウンドを排出する コラボレーションが音楽の主流で 既に「バンド」という形態は廃れている というお話をします。 ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- 1.「バンドが廃れた欧米事情」 ----------------------------------------------------------------------------------- バンドが廃れたと言っても、 ボンジョビやメタリカの様なアーティストが 人気が無くなった訳ではありませんが、w 近年「バンド形態」にこだわらない 現代の世代ならではの価値観が投影され 新たなサウンドを追求する中で生み出される JAZZの様式で生まれたヒップホップテイストのR&B作品 などの新時代のコラボ作品に代表された これまでに無い肌触りの作品に人気が集まり 同世代のリスナーもアーティストも ロックバンドそのものに響くものが無くなってしまい ジャンルとしての王道の「ロック」は追求しても 「ロックバンド」は継承しなくなったというのが 理由と言われています。 どうしてこうなったのかと言いますと、 現代の世代が生まれた時点で既に存在していた「ネット」に 大きな要因がある様に思われます。 90年代以前の時代、バンドの音楽を演るには 演奏するメンバーを集めるしか無く 個人でバンドの音楽を演るには 高価な多重録音機材や全ての楽器を演奏する能力などが 必要でしたが PCの普及でDTMが身近なものになり スタジオを借りてバンドで演奏するというスタイル以外の 選択技が増えて 一人で全てのパートをカバーして自宅のPCのみで帰結する 個人での音楽活動が可能となり 音楽をより身近なものに捉えて 個人で活動するアーティストが増えた事で、 意気投合した不動のメンバーで唯一無二のサウンドを生み出し 息の長いバンド活動を続けるよりも 異なる音楽性を持ったアーティスト同士が組んだ化学反応で 流動的なサウンドを構築し続ける事に 意義を感じる様な風潮が生まれます。 又、ネットの普及によって離れた場所に居る人物と 瞬時にコミュニケーションが取れる様になった事で これまで「集団行動」でしか得られなかった事が 個人レベルで行う事が可能となり 若者の間で一人の時間を優先し個人行動に価値を見出す 個人主義的傾向が現れる様になります。 この様なネット新世代は、 ネットでリアルタムに海外のメインストリームの音楽に触れて来た事で 海外の音楽が輸入盤によるレコード鑑賞や エアチェックしたラジオ番組の音源から得るしか無かった 昭和旧世代のシニアの洋楽ファンが抱く様な 「圧倒的な距離感」から生じる、洋楽に対しての憧れの様なものや それこそ、英語の授業で流暢な発音で教科書を読む級友に対して 教室内が「何だコイツ」という空気になるような いわゆる「英語、洋楽コンプレックス」 という様な 特別感は持っておらず ネットでリアルタムに海外のメインストリームの音楽に触れて来た事で 洋楽に関して物理的な距離感を感じる事も それによる憧れもコンプレックスからの特別感も持つ事は無く 音楽は常に身近にあるものとして ダイレクトに「個人」で世界と通じているという 感覚を持っている所に 昭和旧世代との大きな違いがあります。 昭和の時代、旧世代アーティスト達は 日本で通用する音楽が海外では響かない事を痛感して 山下達郎の様な英語力に長けた洋楽通が世界進出はせずに 日本の音楽家として日本に於けるPOPに拘る様な 音楽的内需拡大路線へと流れて行った事に対して 宇多田ヒカルが登場した2000年前後の時代に 本場のR&B言語で音楽を演る日本人が現れたと感じてから約20年、 現代の若い世代のアーティストが グローバルな展開を見据えると言う様な自負の念からでは無く 何の衒いも無く、ごく当たり前の様に自然に、米国に居る様な感覚で いきなり米国のメインストリームのサウンドで音楽を演る様になったのも、 身近な仲間でバンドを結成して世界を目指すよりも より身近に世界を感じる者同士で 世界とか仲間とか関係なく 意気投合した者同士で個人的な音楽をコラボする事に 意義を感じている所に バンドが廃れていったと言わしめる 大きな要因があった様に思います。 ▲目次へ▲ ----------------------------------------------------------------------------------- 2「.誰も語らないTik Tok以外の『香水』のヒットの背景」 -----------------------------------------------------------------------------------  BLOCK30, 旧居留地, 兵庫県神戸市 (画像参照: wikimedia) 一方で、シニア世代のアーティストが90年代に 世界に通用する日本の音楽を目指し躍起になって吸収しようとした 「ゴージャスな洋楽テイスト」なサウンドが 米国との「圧倒的な距離感」から来る憧れと コンプレックスの念から生まれたものだとしたら 現代の若い世代のアーティストの特徴として挙げられる 世界に繋がり孤立していない「個人」の現れを音にした様な 「音数の少ないシンプル」なサウンドが 世界と繋がっている意識を抱きながらも物理的に関わっておらず、 独りで部屋に居続ける様な 世の中との「圧倒的な閉鎖感」から来る孤独感と、 その様な状況で溜まって行く負の意識を物理的に向ける先の無い やり場の無い「怒り」の念を訴える為に生み出している様な 印象を受けます。 その様な世代が、 複数の仲間と集い時には衝突しながら共同作業の末に音楽を生み出して行く 「ロックバンド」の音楽にリアルなものを感じられないのは、 当然であり 先の話題となったインディーズ出身のアーティスト 瑛人の『香水』がヒットした背景にあるのも ギター1本の唄とバックダンサーという 真似しやすい仕様にヒットの要素があった、とか SNSツール「Tic Toc」でのバズりで拡がり大ヒットに繋がったという 良く言われる見解の他に、 巨大なカリスマ性を持った 長渕剛 の様なアーティストが 圧倒的存在感の音色を持った生ギターでの演奏による 魂の弾き語りをする様な 形では無く、 閉鎖的な空間での孤独感を助長する様に響く スタイリッシュなスパニッシュ奏法でカッティングされる、 生ギター感が希薄な「ループ的」ギター音をバックに 唯一実存感を感じる歌声の感情的な歌唱で いつまでも癒えない心の傷が、かさぶたの様になってまとわり付く 行き場のない「憤り」をさらけ出した所に 現代の若者の心に刺さったのが、 大ヒットした大きな要因だった様に思われ、 王道の「バンドサウンド」で 「反抗心」をたぎらせるのでは無く、 シンプルな構成の音楽に「癒やし」を求めていた現れだと言えます。 イントロの前書きでは「ロックの方から見切りを付けた」と書いた 現在の日本の音楽界でしたが、 ネットの世の中となり現在の若者が現在メインストリームとなる本場のR&Bを リアルタイムで体験する中で 同じ様に「ロック」の核となる、 日本のロックの歴史の中で失われた「ブルース」体験がなされたとしたなら 王道の「ロックミュージック」への関心が高まり 「バンド」人気復活へと繋がる日が 近い将来、来るのかも知れません☆ というわけで いかがでしたでしょうか。 次回は一体 何が 更新されるでしょうか ごきげんよう☆ ▲目次へ▲ ■■■■■■■■■■■■■楽天市場■■■■■■■■■■■■■■■  【CD】サンクチュアリ(聖域) [ NOVELA ] 価格:1410円(税込、送料無料) (2020/7/30時点) ■ 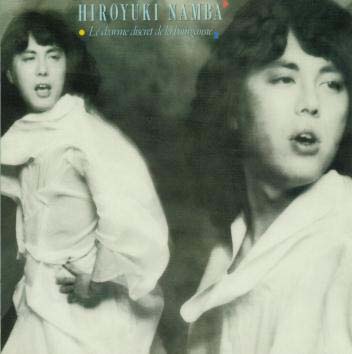 【CD】難波弘之 / ブルジョワジーの秘かな愉しみ 価格:2200円(税込、送料別) (2020/7/30時点) ■ 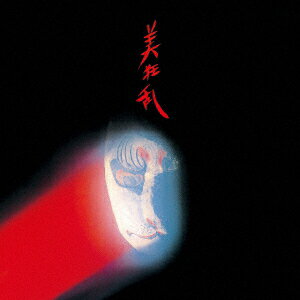 【CD】美狂乱 [ 美狂乱 ] 価格:1430円(税込、送料無料) (2020/7/30時点) ■  【CD】一触即発(+2) [ 四人囃子 ] 価格:1468円(税込、送料無料) (2020/7 ■  【CD】DREAMIN' [ PRISM ] 価格:2620円(税込、送料無料) (2020/7/30時点) ■  【CD】ジャガーの牙〜TUSK OF JAGUAR〜 [ 高崎晃 ] 価格:1650円(税込、送料無料) (2020/7/30時点) ■  【CD】FAR EAST(紙ジャケット仕様) [ TAO ] 『Hello Vifam(SE入りSingle Ver.)』『never give up』収録 価格:2750円(税込、送料無料) (2020/8/30時点) ■  【CD】BOOWY THE BEST “STORY”(Blu-spec CD2) [ BOOWY ] 価格:3142円(税込、送料無料) (2020/12/25時点) ■  【CD/DVD】アンプラグド〜アコースティック・クラプトン DELUXE (2CD+DVD) [ エリック・クラプトン ] 価格:3345円(税込、送料無料) (2020/12/25時点) ■  【CD】コンプリート・レコーディングス (Blu-spec CD2) [ ロバート・ジョンソン ] 価格:2337円(税込、送料無料) (2020/12/25時点) ■  【CD】ベスト・オブ・マディ・ウォーターズ +8 [ マディ・ウォーターズ ] 価格:785円(税込、送料無料) (2020/12/25時点) ■  【CD】ベスト・オブ・チャック・ベリー [ チャック・ベリー ] 価格:1602円(税込、送料無料) (2020/12/25時点) ■  【輸入盤CD】Buddy Guy / Blues Is Alive & Well 【K2018/6/15発売】(バディ・ガイ) 価格:1790円(税込、送料別) (2020/12/25時点) ■  【CD】B.B.キング・ライヴ・イン・ジャパン [ B.B.キング ] 価格:990円(税込、送料無料) (2020/12/25時点) ■  【CD】デビュー40周年記念 影山ヒロノブBEST カゲちゃんパック〜君と僕の大行進〜 [ 影山ヒロノブ ] 価格:3127円(税込、送料無料) (2020/12/25時点) ■  【先着特典】すっからかん (CD+DVD+スマプラ) (あの香水のミニボトル) [ 瑛人 ] 価格:4620円(税込、送料無料) (2020/12/25時点) ■  【エレキギター】[高崎晃モデル・ランダムスター] EDWARDS E-RS-145G ローズ指板 [国産,MADE IN JAPAN] 価格:127,600円(税込、送料無料) (2020/7/30時点) ■  【中古フィギュア】 けいおん! 平沢唯 1/8 アルター 価格:4345円(税込、送料別) (2020/8/30時点) ■  【コミックス】逃げるは恥だが役に立つ(1-11巻 全巻) [海野つなみ先生描き下ろしボックス付き] 全巻セット 価格:5226円(税込、送料別) (2020/8/30時点) ■  【文庫本】ゴールをぶっ壊せ 夢の向こう側までたどり着く技術 (中公新書ラクレ)[ 影山 ヒロノブ ] 価格:880円(税込、送料無料) (2020/8/30時点) ■  【ボードゲーム】カタン スタンダード版 価格:3427円(税込、送料無料) (2020/8/30時点) ■  【電子書籍】そうだったのか! 日本現代史 [ 池上彰 ] 価格:660円 (2020/8/30時点) ■  KeLT ケルト 3点セット《カフェテーブル+チェア2脚》 自然 新生活 人気 おしゃれ モダン カフェ アイアン ミッドセンチュリー インダストリアル アンティーク 北欧 価格:29800円(税込、送料無料) (2020/8/30時点) ■  【CD】サンクチュアリ(聖域) [ NOVELA ] 価格:1410円(税込、送料無料) (2020/8/30時点)アニメ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020年12月27日 00時07分27秒
コメント(0) | コメントを書く
[音楽 [プログレッシブ・ロック]] カテゴリの最新記事
|
|