
|
|
|
カテゴリ:常識から考えてこれはおかしいよ
新映画『破戒』は「部落民宣言」を奨励している この映画が賤称語を広げる契機にならないように注意してください (この記事は、消えゆく「部落民」―心のゴースト⑩ 前篇-島崎藤村の小説『破戒』の丑松はもういない の後編です。) はじめに 全国水平社創立100周年記念映画製作委員会製作の東映映画『破戒』(製作統括・組坂繁之部落解放同盟中央本部前委員長)を観せていただいた。 私たちはこの映画が「解放同盟」の肝入りで、「告白」(「部落民宣言」)の意義を宣伝することを目的に製作されたのではないかという疑念を持っていたが、そこは映画のこと、観てから評価するのが原則だから封切と同時に事務局員(4人)全員が観に行った。 『破戒』は一作目は木下恵介監督(1948年)、二作目は市川崑監督(1962年)で映画化された。いずれの作品もこの記事を書くために改めてDVDとネットで観賞させていただいた。これらの両作品は白黒であったせいか暗く重苦しく、父親の「戒め」のもつ深淵な意味が極限まで描かれていた。一方、新映画『破戒』はカラーで画面は明るく、父親が丑松に「戒め」を与える場面は短く、軽い。そのためか、前作のような「戒め」に恐怖感はなく、この種の映画ではありがちな重厚感はなく、気軽に映画を最後まで観ることができた。 「内容が浅くないか?」と、若い事務局員に聞いたら、「やたらに暗くて重い時代劇映画は受けないからです」と言われてしまった。「時代劇?」、確かに小説『破戒』が出版されて110年以上も経っているのだから、今の若者からいえば新映画『破戒』はチョンマゲの無い時代劇のようなものなのである。 水平社100周年を記念して「解放同盟」は差別規制法を課題として掲げ、マスメディアも一斉にそれに同調している。新映画『破戒』も超人気若手俳優を揃えることで部落解放運動に広く国民の耳目を集めるために製作されたことは間違いない。さらに、この映画をよく検討すると、小説『破戒』の主題を歪めるような新場面が挿入され、必要でもないのに賤称語が使用されていることに気づく、もし、この映画を契機として賤称語が独り歩きしたり、何の前提もなく自由に使用する道が開かれるとしたら国民の分断は大きく広がる危険性があるのだ。 お断りしておきたい。この記事は新映画『破戒』を観るなという意見を発信しているものではない。観ることで自分の部落問題に対する見識を高めていただくために発信させていただいているので、できれば原作を読み、すべての映画『破戒』を観て、ご考察願いたい。  小諸城(こもろじょう)の青松 小諸城は長野県小諸市にある日本の城祉である。 「小諸なる古城のほとり 雲白く遊子(いうし)悲しむ」(「旅情」)ではじまる有名なこの詩は藤村が愛した小諸城祉から見た景色を思い浮かべながら創作したといわれている。 藤村はよくこの城址を散歩し、詩想や小説の構想を練ったといわれる。 城祉は城下町である市街地よりも低地に縄張りされ、市街地から城内を見渡すことができるが、城の西端に行くと展望台があり、その下は断崖となっている。そこからゆるやかに流れる千曲川を見下ろすことができる。 1、映画『破戒』にみる苦悩と「告白」 ※「たとえいかなる目を見ようと、いかなる人に邂逅(めぐりあ)おうと決してそれを自白(うちあ)けるな、一旦のいかりかなしみにこの戒めを忘れたら、その時こそ社会から捨てられたものと思え」 (丑松の父の戒め・小説『破戒』第一章) 「告白」という言葉の意味は秘密にしていること、心の中で思っていたことを、ありのまま打ち明けることである。特に人生を左右するような重大な秘密を吐露する時に用いられている。キリスト教では自己の信仰を公に表明すること。また、自己の罪を神の前で打ち明け、罪の許しを求めることである。小説『破戒』の「告白」は「部落民」であることが原罪かのように扱われ、丑松の「告白」は「懺悔」のように扱われていることを既に指摘した。 市川崑監督の『破戒』では冒頭シーンに、暴れ牛の角に刺され死ぬ父親の姿。葬式にかけつけてきた丑松の叔父が父親の「戒め」を語ることで、「戒め」を破り「告白」することの恐怖を理解させる。その結果、丑松の「告白」に至るまでの苦悩の深さが理解できるようになる。 新映画『破戒』では霧の煙る杉林で幼い丑松が別れ際に父親に「手紙を書く」と言うと、父親は「書かなくてもよい。ふるさとを隠せ。決して他人を信用してはいけない」と「戒め」る。同じ「戒め」の重大性を説明する場面ではあるが、「部落民」の状況描写がないため、差別の与える恐怖は浅い。そのためか前記のように丑松の「告白」を逡巡する姿に深く感情移入ができない。ましてや、小説『破戒』の知識のない人が観ると『破戒』の意味さえわからないはず。 市川崑監督の『破戒』では「告白」はクライマックスの子どもたちへのものだけであるが、新映画『破戒』では友人の銀之助にも「告白」する。銀之助は丑松の「告白」に対して「謝らなければならないのは僕だ。君を傷つけてきた」と反対に謝罪する。そして、子どもたちに「告白」する場面では、「部落民」であることを「告白」するが、原作や前作品とは違い「隠していた」ことを土下座して謝罪はしない。「本当はこの教室でいつまでもいつまでも皆さんと一緒に勉強したかった」と子どもたちと別れるのが悲しくて膝から崩れ落ちることになっている。「告白」を聞いた子どもたちは「先生は先生だ!先生に変わりない」と叫ぶ。 市川崑監督の『破戒』の「告白」は原作通りであり、キリスト教の懺悔に近い。だから部落差別の不合理性は告発しても、解決への展望は見えない。新映画『破戒』の「告白」は「部落民宣言」である。「宣言」をすれば友人や仲間、支持者が多く生まれ、それが部落差別解消につながると誘導する。 「告白」は部落差別解消の始まりとなるのだ。  藤村記念館 長野県小諸市の小諸城祉の敷地内にある小さな資料館を訪ねた。目的は藤村が部落差別をテーマにして小説を書こうとした動機が知りたいからだ。 資料館には藤村の小諸時代を中心とした作品・資料・遺品が多数展示されていた。 藤村の直筆の原稿や手紙の文字を見ると、作家にありがちな修正があまりない。恐らく、頭の中でしっかり構想してから文章を書いているからであろう。 資料館で感動したのは『破戒』と『千曲川のスケッチ』(初版本)を見つけたことだ。 2、映画『破戒』の愛と友情 1906(明治39)年に発行された島崎藤村の小説『破戒』は部落問題に対する認識や表現に誤りが多く、原作通りに映像化すれば部落問題に対する誤認を広げる危険性があることはいうまでもないが、作家の知名度、作品の持つ深淵な人間洞察と物語性から名作として評価されているから、今後とも映画化される価値と可能性は存在している。 しかし、この作品を「告白」という視点から小説を見ると、誠に不遜ではあるが、『破戒』は極めて単純な構成で出来上がっていることがわかる。父親の「告白するな」という「戒め」に苦しむ主人公が、その「戒め」を破り「告白」することにより、友情を深め、志保の愛を獲得し、希望の道を拓いていく物語である。差別が苛酷であればあるほど「告白」は意義あるものになり、友情と愛情は尊く、深いものになるのである。 土屋銀之助は小説の中でも、映画の中でも最も魅力的な人物として描かれる。一作目は、戦後の民主主義を体現するかのような部落差別に批判的な人物として描かれている。二作目は、「部落」に対する偏見を持ち、露骨な差別発言をしながらも、友人丑松の苦悩を理解することで、部落差別の不条理を理解し、丑松を支援する。新映画『破戒』では、丑松が「部落民」であることを知らず、志保と丑松の恋のとりもちをする。丑松が「部落民」であっても変わらない友情を示す。 丸山志保は没落士族の娘で口減らしに蓮華寺に養女に出された苛酷な境遇にもかかわらず、汚れのない心をもっている聖女として描かれている。第一作目は志保への「告白」の手紙からはじまる。丑松は自分が「部落民」であることを打ち明け、志保への想いを伝える。第二作目では、丑松は志保には「告白」しないが、銀之助が丑松の想いを伝え、志保も丑松に思いをよせていることがわかる。新映画『破戒』では丑松が「告白」する場面はないが、随所に相思相愛になっていく二人の姿が描かれている。 原作、前二作の映画に共通しているのは志保には「部落民」への偏見がないことである。その理由については説明されていない。新映画『破戒』では歌人与謝野晶子に傾倒する女性として描かれている。与謝野晶子の思想や行動が近代的人権論に裏付けられたものではないことは広く知られていることであるから、この結びつけには違和感を感じる人も多いはず。 志保については、藤村が「告白」した丑松に救いの女神を差し伸べたと考えるべきで世俗的な理由づけの必要はないものと考えられる。 ※あの人が私を愛してから、自分が自分にとってどれほどの価値のあるものになったことだろう。 ゲーテ『若きウェルテルの悩み』(岩波書店)  藤村の東京の文壇への強い想い 明治学院時代の教師で牧師の木村熊二に誘われて、明治32(1899)年4月上旬に小諸義塾に国語と英語の教師として赴任した。同年5月に冬子と結婚。 教育者として詩人として活躍しつつ、小説も書き始める。なんと『旧主人』という小説で姦通を描いたため発禁処分を受けているから、当時としては相当急進的な人物であったことは間違いないようだ。 当時、文学の中心は東京であった。藤村の心の底には「東京の文壇で評価を得たい」という気持ちが強かったに違いない。 小説『破戒』は小諸の教師時代に構想したが、小説に専念できる経済状況にはなく、『破戒』完成までの生活費を知人から借金する。そして、6年間勤めた小諸義塾を退職し、東京に戻ったのである。 3、新映画『破戒』で使われた不必要な賤称語 「穢多」という言葉は賤称語である。賤称語というのは身分社会において使用された賤称を現代社会においても特定の個人・集団を差別・排除するために使用する言葉のことである。この言葉の使用が許容される範囲は、①歴史的事実を記述する場合。②部落問題を解決する目的で使用される場合。③「穢多」をルーツとする被差別者が自らのアイデンティティを語る場合とされている。 映画『破戒』の第1作、第2作では「穢多」という言葉は使用されていないが、新映画『破戒』では原作にも第1作、第2作もない演説会の場面をわざわざつくり、丑松も参加させる。その眼前で猪子蓮太郎は「われは『穢多』なり。されど『穢多』を恥じず」と、敵対する候補者高柳利三郎と雇われた壮士ら(自由民権運動のなれの果て)の前で声高に叫ばせる。聴衆は熱狂的に拍手と歓声を蓮太郎に送る。それに感銘して丑松は「告白」を決意するのである。 この映画のクライマックスはここにあったのだ。「穢多」であることを「告白」すれば未来は拓けるというメッセージを観客に与えているのである。これは「解放同盟」が「解放学級」などで進めてきた「部落民宣言」に通じる。しかも、この場面が加えられたことにより、新映画『破戒』は原作から離れ、リアリティを失い時代劇となったのである。こんな演説会は明治時代とはいえどありえないだろう。 演説会に猪子、丑松、高柳を一堂に集めて対決させるという荒唐無稽ともいえる場面を創出したことによって、「穢多宣言」(「部落民宣言」)を感動的に描こうとしたのであろうが、藤村が緻密に構成した丑松の「告白」に至るまでの心理的過程が無視される結果となったのである。そのために、子どもたちへ「部落民」であることを「告白」することで、苦悩から解放されるという場面はつけ足しになってしまったのである。 新映画『破戒』が「解放同盟」の運動方針に沿ったものであることは明白のようだ。そのために新しい場面を付け加え、賤称語を使用しているのである。前記の賤称語の規定からいえば、この場面で「穢多」という言葉を使用しているのは問題はないように思えるが、この規定には前提がある。賤称語を使用する場合は、相手の歴史的な知識・用語に対する理解度を踏まえなければならないということである。今回の映画にはそうした配慮が全く見られない。賤称語に対する理解不足から言葉だけが独り歩きし使用される弊害は「ネット差別」ですでに証明されているはずである。そうした弊害を生まないためには他の用語に置き換えて表現する方法がすでにあるはずだ。 「穢多」という言葉は封建社会において人間を最大級に侮蔑し、排除するために生まれた言葉であり、本来、人間が人間に対して使用すべき言葉ではないからだ。だから映画『破戒』の1作目も2作目も「穢多」ではなく、「部落民」という言葉が使われているのである。  小諸義塾―藤村と木村熊治 小諸義塾は1893(明治26)年11月に地元の青年たちの熱意ある要請にこたえて、木村熊二によって誕生した私塾である。 その後私立中学校認可を得て、やがて島崎藤村等を教師陣に加えて充実した中学校教育へと発展するが、日清日露の戦を契機にして、個性的で自由を特色とする教育は国家的な教育制度に阻まれて、遂に1906(明治39)年、13年間の短い歴史を閉じた。 木村は兵庫県出石生まれで、明治初年アメリカに渡り12年の留学によって近代の西欧文化を身につけた新進気鋭の教育者であり、キリスト教の牧師であった。 藤村との出会いは明治学院時代で、教師として藤村の悩みをよく聞き、指導した。藤村は木村を尊敬し、木村から洗礼を受けている。その木村の誘いで小諸義塾に来たのであるから、藤村のキリスト教に基づく理想主義は生半可なものではない。 4、小説『破戒』を部落問題解決に利用するのは限界 小説『破戒』は日本人の頭が封建社会とほとんど変わっていない1906年(明治39)年3月に自費出版されたものである。藤村がこの小説を書いた目的はひとつには藤村の詩人から小説家への転身をかけ、文学界での出世をめざした野心作であること、もうひとつは藤村が信仰したキリスト教の同情と救済思想に基づく小説であることからいえば、小説『破戒』は部落問題を扱っているが、部落問題の解決を目的とする小説ではないことは明白である。 部落問題の現状と課題は社会の発展とともに変化するが、小説のストーリーは固定化され、原作者のその小説に設定したテーマも変化することはない。だから、小説『破戒』を部落解放運動団体などが部落問題の解決を託して映画化するのは限界がある。さらに、強引にストーリーやテーマを変更すれば小説の本質を歪めることになるのである。今回の新映画『破戒』がそれを示したといえよう。 しかし、小説『破戒』には普遍的に愛される二つの側面がある。ひとつは舞台が学校で、子どもに愛される主人公の教師、出世主義の校長、ごますりの教師、正義感の強い教師、などは今日でも通用する学園ドラマの構成要素が揃っていることである。もうひとつは丑松と志保の間に通い合う純愛である。 不思議な偶然だが、夏目漱石は松山市の中学校の教師の体験をもとに『坊ちゃん』を書き、藤村と同じ年に発行している。その中で描かれている学校の人間構成は『破戒』のものと酷似している。さしずめ勝野文平は赤シャツ、銀之助は山嵐、風間はうらなりとなる。 藤村と漱石は教師の体験をし、その体験をもとに小説が書かれているから構成が酷似するのは仕方がない。この二人が今日まで続く日本の学園ドラマの原型を創りだしたといっても過言ではないかもしれない。だから読み継がれていく。一方は「根クラがよむ学園小説」もう一方は「根アカが読む学園小説」としてである。 夏目漱石は、『破戒』を「明治の小説としては後世に伝ふべき名篇也」(森田草平宛て書簡)と評価している。勿論、学園小説として評価しているわけではなく、自然主義文学の傑作としてであるが、描かれたテーマは違っても二人は来るべき未来の社会像を見通していたようである。 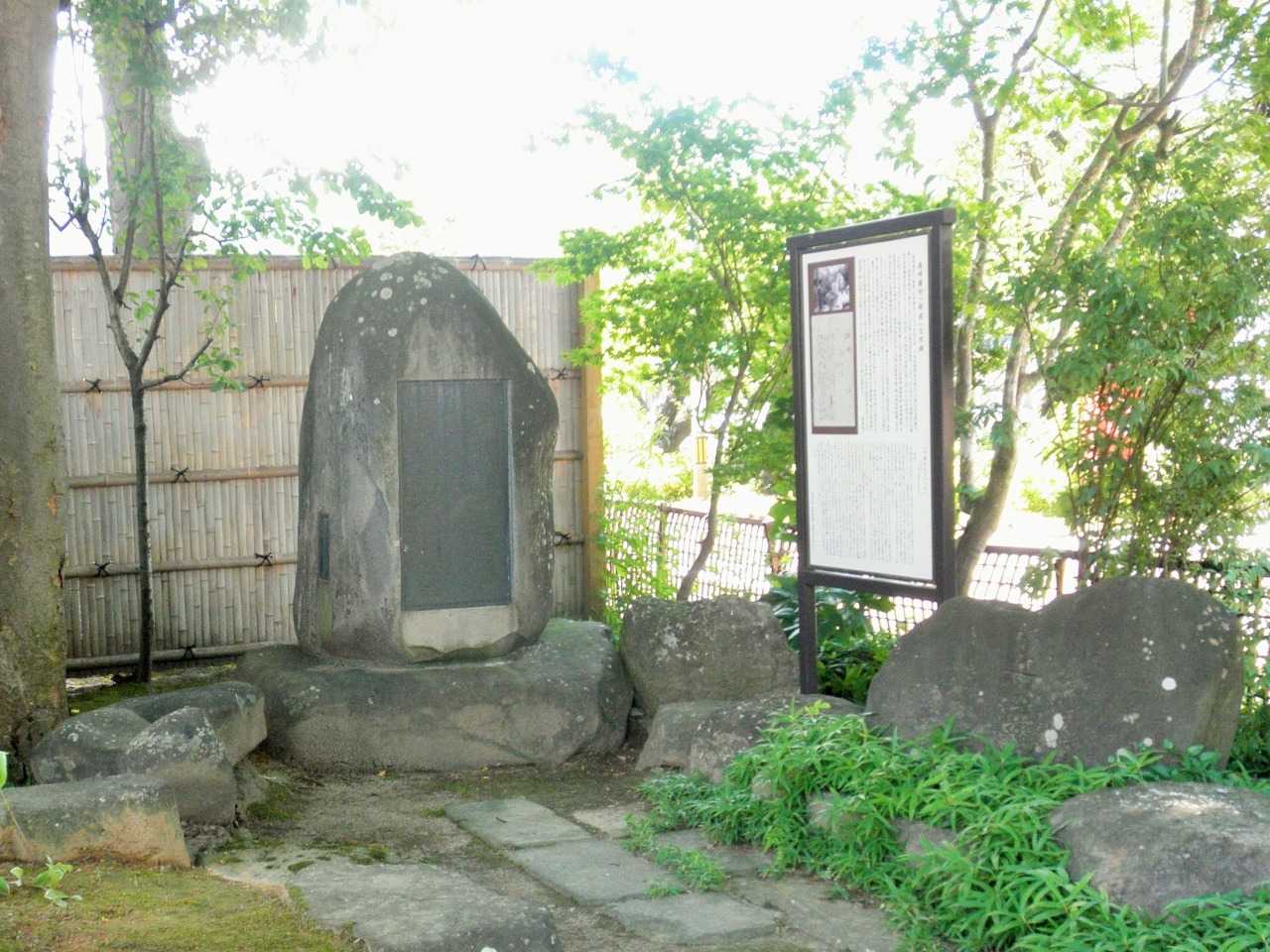 飯山市上町の真宗寺 飯山市にある蓮華寺のモデルとなった真宗寺を訪ねた。藤村が描いた飯山を想像ではなく現実として把握するためである。その方が藤村の本質により迫ることができると考えたからである。 藤村は東京の文壇にデビューするために選んだテーマは近代化に突き進む日本が直面しつつあった封建社会の解体過程であった。 藤村は『破戒』の舞台に住み慣れた小諸ではなく飯山市(当時・飯山町)を選んだ。千曲川を囲むように山が連なり、その山峡の細長く狭い土地に人々は住み、冬は非常に積雪量が多く、市内全域が特別豪雪地帯に指定されるほどの厳しい地域である。 藤村は開けた城下町の小諸より、この苛酷な自然環境に閉ざされた寒村の方が出自を隠し密かに生きなければならない丑松の重苦しい心情を表現するのに相応しいと考えたのであろう。 5、映画の力を利用した思想・世論誘導 映画には人間の価値観を変える力があるといわれている。その力の最大のものは感情移入できることである。映画に登場する人物たちに感情移入し、人物たちの心と行動を共有することである。単純化すれば、丑松の苦悩が理解できれば、部落差別に否定的になるということである。もうひとつの力は伝達する力である。未知なこと、マスメディアが伝達しないことも知ることができるということである。映像は新聞や本よりも理解しやすい。さらに、映画は、計算された音響・視覚効果により、観客の感情移入を極限まで高めることが出来るから虚構を現実として信じ込ませることもできる。 映画が教育・啓発の手段として有効なのはこのためである。新映画『破戒』を製作した東映は教育・啓発映画の老舗であり、多くの自治体の注文を受けて製作している。 しかし、映画に人間の価値観を変える力があるゆえに大きな問題も生まれる。特定の団体や政党が自らの正当性を主張し、支持を勝ち取り維持し続けるために利用されるプロパガンダ映画である。勿論、プロパガンダ映画はすべて悪いとは思わないが、観る者を特定の思想・世論・意識・行動へ誘導する性格が強いことから、かつて少数民族や異教徒を排除したり、侵略戦争を遂行するために利用されたために否定的に扱われ、プロパガンダという言葉自体が軽蔑的に扱われ、嘘、歪曲、情報操作、心理操作と同義と見るようになっている。 今回の新映画『破戒』をプロパガンダ映画であると決めつけるつもりはないが、企画・製作が全国水平社創立100周年記念映画製作委員会であること、製作統括が「解放同盟」前委員長であること、映画の主題が「告白」(部落民宣言)となっていることから見ると誠に「プロパガンダ臭い」映画であり、小説『破戒』の芸術性を深く理解し、製作されたとは考えられないのである。 今後、この映画がDVD化され、人権・同和教育の現場や、職場や学園、宗教界、企業研修において広く利用されることが予想されるが、その際は、小説『破戒』の本旨から外れていること、「解放同盟」の「解放理論」が深く反映した映画であることを理解したうえで利用されることをおすすめしたい。  蓮華寺の『破戒』の石碑 真宗寺の境内には蓮華寺のモデルとなったことを示す石碑がある。藤村は、小説『破戒』の取材のため、1902(明治35)年から03(明治36)年ごろにかけ数回取材のため、この真宗寺を訪れ宿泊している。 小説では蓮華寺を「借りることにした部屋というのは、その蔵裏つづきにある二階の角のところ、寺は信州下水内郡飯山町二十何ヵ寺のひとつ真宗に付属する古刹」とある。現在でも寺は多く信仰深い都市であり、真宗寺という同じ名前の寺が他にもあるから驚かされる。 この真宗寺は1952(昭和27)年の飯山大火の際に山門や本堂等を焼失し、藤村が訪れた時代から残っているのは六角堂のみとなっているから、小説で描かれた寺を想像するのは難しい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2022年08月26日 16時14分23秒
[常識から考えてこれはおかしいよ] カテゴリの最新記事
|