
|
|
|
カテゴリ:カテゴリ未分類
「研究者という職業」 林周二著 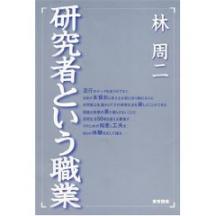 研究生活50年を超える著者が、文系理系を問わず、研究者としての生き方・あり方を語る作品です。 読んでいると、お爺ちゃんに説教されているような気分になってくるのですが、著者の述べられている意見はほぼ同感できることばかりで、今の自分の背中を強く押してくれる非常にencouragingな読み物でした。 作品の冒頭で述べられている8つのポイントを抜粋させて頂きます。 (1) 研究者たろうとする者は、世間に追随したりせず、自分独自のユニークな研究テーマを持つべきだ、ということ。特に戒めたいのは、流行りのテーマの尻だけを追っかけてはいけない、ということである。 (2) その点を熟慮したうえで、研究上これこそは重要(essential)だと考えられるテーマに取り組むこと。詰まらない(trivial)研究テーマにかかわりあって、研究者人生の貴重な時間をあたら浪費してはいけない。何が重要で本質的か、何が瑣末で末梢的かを見極めることは、研究者の眼力に関わる最も大切なことである。 (3) 研究者たる者は、常に開拓者精神でその研究活動に当たること。周到な計画性をもってその仕事に取り組み、いったん作業に入ったからには必ず成功する覚悟をもつこと。(失敗するのは、事前の研究計画の立て方が杜撰だったことに原因するところが大きい) (4) 研究者は、実際に世の役に立つことを、自己の研究の主旨とすること。(なお「世の役に立つ」とは、空論のための空論を徒らに弄ばないということであって、目先の世俗的・実利的な役にすぐ立つとの意味ではない。) (5) 狭い日本でより、広い全世界で、自分の学問や研究仕事が認められるように努力すること。研究者は活動の舞台を狭くでなく、大きく広く取るようにすること。 (6) 研究者と志す人は、なるべく優れた立派な師を頼って、その下に就くよう努めること。東大総長だった有馬朗人も、この点を特に強調し、「師に仰ぐならノーベル賞級の人の下に就け。研究者としての君の将来は、全く違ってくるはずだ」と断言している。 (7) これからの学術多様化時代に研究者が生きてゆくには、狭いタコツボ的な道場(=研究室)に閉じこもったりせず、武者修行的にいろいろな道場の門をたたき、他流試合つまり他部門や隣接部門研究者達との積極的交流に努めること (8) 研究者にとって研究の職場を5年ないし10年ごとに変えることは、研究環境の転換、したがって研究そのものの視界拡大に大きく役立つと考えること。 (1)から(5)に関しては、研究に没頭している自分を客観視し、間違った方向に向かっていないか、常にcheckせよ、ということの裏返しで常に念頭にいれておきたい教えだと思います。 (6)(7)(8)については、僕が選んだ選択肢が間違ったものでないということを後押ししてくれる言葉であり、非常に強く胸に突き刺さりました。 これ以外にも、思わずページに折り目をつけてcheckした言葉はたくさんあるのですが、それらもまた折に触れて日記上で紹介していきたいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|
|