
|
|
|
カテゴリ:カテゴリ未分類
 「難聴」と一概に言っても、木のそよぎが聞こえない程度の「軽度難聴」から、車のクラクションやジェット機の通過音も聞こえない「重度難聴」まで、人によって大きく程度が異なるのです。 日常生活でよく耳にする音の大きさは下記の図のようになっています。 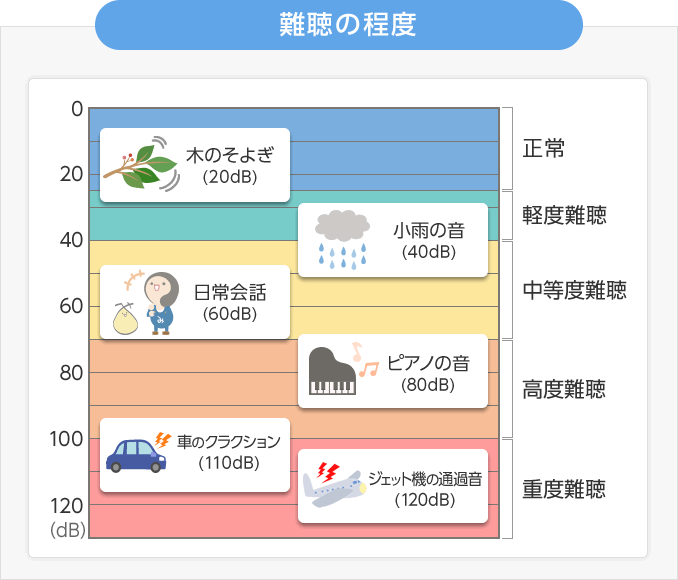 聴力の度合いによって難聴の程度は分類されます。難聴の程度は、音の大きさ(dB)を目安にして「軽度難聴」「中等度難聴」「高度難聴」「重度難聴」の4つのレベルに分類されます。 あくまで目安としてですが、 1)正常:25dB未満 2)木のそよぎ(20dB)が聞こえない場合には軽度難聴。25dB以上40dB未満 小さな音や騒音がある中での会話の聞き間違いや、聞き取りにくさを感じる。 3)小雨の音(40dB程度)が聞こえない場合は軽度~中等度難聴。40dB以上70dB未満 普通の大きさの会話での聞き間違いや聞き取りにくさを感じる 。 4)日常会話(60dB程度)が聞こえない場合は、中等度難聴。 5)ピアノの音(80dB程度)が聞こえない場合は、高度難聴。70dB以上90dB未満 非常に大きい声か、補聴器を装用しないと会話が聞こえない。聞こえても聞き取りに限界がある。 6)車のクラクション(110dB程度)やジェット機の通過音(120dB程度)が聞こえないと重度難聴となります。90dB以上 補聴器でも聞き取れないことが多い。 加齢性難聴の症状・診断・治療方法 症状: 50歳代以降になると、個人差はありますが加齢に伴い少しずつ聴力が悪化します。 特に高音域の音(鈴虫の音や電子機器の音)が聞こえにくくなるのが特徴です。 時に、耳鳴りを伴うこともあります。両耳が同じように悪化してゆきます。 診断: 外耳道や鼓膜の所見は正常です。聴力検査の聴力像において、両耳とも同じように高音域が主に障害されている場合は、加齢性難聴と診断します。 同じ年齢であっても聴力については個人差がありますが、難聴に関わる遺伝子も複数発見されており、単に年齢だけでなく遺伝的な素因も関与していると考えられています。 治療: 根治的治療はなく、生活に不自由される場合は補聴器のフィッティングを行います。補聴器は眼鏡ほどすぐに効果が感じられないため、3か月ほどかけて補聴器に慣れてゆく必要があります。 オージオグラムとは 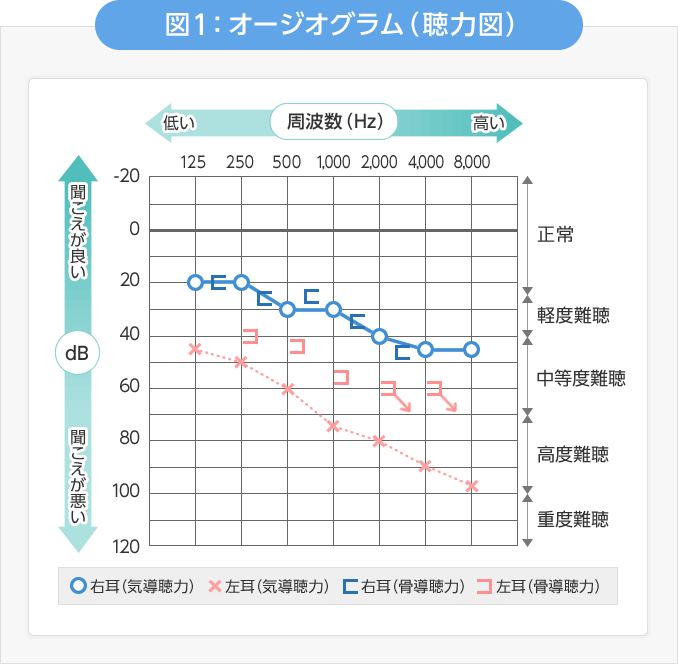 オージオグラムは「聴力図」(図1参照)ともいい、オージオグラムを見ることで自分の聞こえの「音」を理解することができます。 オージオグラムでは横の軸が音の周波数(Hz)つまり音の高さ、縦の軸は聞こえのレベル(dB)を表しています。右に行くほど高い音を表し、上に行くほどよく聞こえていることを表します。○印は右耳、×印は左耳の気導聴力を示します。気導聴力とは、空気を伝わって耳から聴く力のことです。 対して、カギ印(⊏が右、⊐が左)は骨導聴力を示します。骨導聴力とは骨を伝わってきた音を聴く力のことです。難聴の種類により、気導聴力と骨導聴力の下がり方は異なります。 1) 「伝音性難聴」の場合、音を内耳に伝える部分に障害が起こるため、気導聴力は下がりますが、骨導聴力は下がりません。 2)「感音性難聴」の場合、気導聴力も骨導聴力も同じレベルで下がります。 3)「混合性難聴」の場合、気導聴力も骨導聴力も下がりますが、下がり方に差が出るのが特徴です。 日本における平均聴力は「大抵4分法」 と呼ばれる方法で行われています。 大抵4分法による平均聴力算出式: {“500Hzの聞こえ”+(“1000Hzの聞こえ”×2)+“2000Hzの聞こえ”}÷4 図1はオージオグラムの一例です。仮に図1の平均聴力を計算してみたとします。 1)右耳の場合、500Hz=30dB、1000Hz=30dB、2000Hz=40dBなので、{30+(30×2)+40}÷4=32.5dBとなり、右耳の平均聴力レベルは軽度難聴となります。 2)左耳の場合、500Hz=60dB、1000Hz=75dB、2000Hz=80dBなので、{30+(30×2)+40}÷4=72.5dBとなり、左耳の平均聴力レベルは高度難聴となります。 また、図1のオージオグラムを見てみると 1)右耳の場合には気導聴力(○印)と骨導聴力(⊏印)がともに同じように下がっています。そのため右耳は「感音性難聴」であるといえます。 2)対して、左耳の場合、骨導聴力を示すカギ印(⊐)が×印よりも上方にあり、かつ正常なレベルよりも下にあるので、「混合性難聴」であるといえます。 このようにオージオグラムを見ることで聞こえている範囲と、どの種類の難聴なのかを知ることができるのです。 語音明瞭度は「言葉」の聞き取り能力のことを指しています。 「音が大きければ聞こえは良くなるのでは?」と思われている方も多いかもしれません。しかし、残念ながらそうとも限らないのです。それは、「音が聞こえる」と「言葉を聞き取れる」ことは少し違うからです。 言葉の聞き取り能力(語音明瞭度)が下がってしまうと、耳から入ってきた音を変換する力が弱くなります。そのため、いくら音を大きくしてもはっきりと聞こえてきません。つまり、言葉の聞き取り能力が低下することで、補聴器を装用して、耳に入る音を大きくしたとしても、言葉や会話を聞き取ることが難しくなってしまうということです。 語音明瞭度の測定では、「あ・き・し・た・ば……」などの言葉を聞き取ってもらい、何文字正解できたかを0~100%で示します。 語音明瞭度を測定した例を図2に示します。  図2では、○印が右耳の語音明瞭度、×印が左耳の語音明瞭度を示しています。 右耳(○印)の正答率を見てみると、 40dBでは0%、つまり小さい声で話をされると全く聞き取ることができないということになります。 55dB(普通の会話)では20%でありほとんど理解できない状態です。 70dB(大きな声)になると、正答率は50%となり、ある程度理解ができるようになります。 90dBになると正答率は90%になり充分会話が理解できるレベルになります。 一方、左耳(×印)は70dB(大きな声)でも正答率は20%と低く、ほとんど理解できないレベルです。 さらに、100dBでも正答率は50%と、ゆっくりでなければ理解できないレベルです。 激しいめまいに襲われる、メニエール病。 めまいと同時に耳鳴りなども起こりますが、さらに進行すると難聴になってしまうこともあるんです。 メニエール病と耳鳴りの関係: メニエール病の症状とは メニエール病は強いめまいを起こす病気です。原因は耳にあります。 内耳で内リンパ液というものが過剰に生産されることによって起こる病気です。  内リンパ液は音を伝える「蝸牛(かぎゅう)」や平衡感覚をたもつ「半規管(はんきかん)」や「耳石器(じせきき)」に内リンパ液が溜まることでめまいや耳の症状が起こります。  片耳だけに起こるケースが多いですが、両耳に発症することもあります。 症状は病気の進行具合によっても変わってきます。 1)初期 メニエール病といえばめまいがするもの、と思いがちですが、はじめは耳の閉塞感や耳鳴りを感じ、低音が聞き取りづらくなる難聴になっていきます。この症状が出たり、治まったりを繰り返し、次第にめまいを引き起こすことが多いです。 ですが、人によって症状の出方はそれぞれです。いきなり激しいめまいを起こすケースもあります。 2)活動期、安定期 続いて、めまいなどの発作を繰り返す活動期と、数カ月に一度しか発作が起こらない安定期が交互に起こるようになります。 活動期は大体2~3ヶ月ですが、もっと長くなる場合もあります。活動期が一度治まるとその後は数か月に一度発作が起こるという安定期に入ります。これを繰り返していきます。 3)慢性期 活動期と安定期をくり返していくと、聴力機能が徐々に低下していってしまいます。そのため、難聴が悪化していきます。めまいは、症状が悪化しすぎると治まってきたり、発作自体が起こらなくなる場合があります。 めまいの原因は前庭機能というバランス機能が乱れているためです。ですが、ある程度まで機能が低下してしまうと代わりに中枢部分が補ってくれるようになるのです。 聴力に関わっている蝸牛には代わりになる器官がないため、症状は悪化し続けてしまいます。ですから、慢性期に入ってくるとめまいよりも耳鳴りや難聴が大きな問題となってきます。 メニエール病の難聴の特徴: メニエール病の難聴の特徴は、はじめに低音が聞き取りづらくなることです。 低い男性の声が聞こえない、という人も多いです。はじめは低音だけですが症状が悪化するにつれて、中音域や高音域も聞き取りづらくなってしまいます。 ですから、「なんとなく聞き取りづらいかな」という初期の段階で治療を行うことが大切です。 難聴を改善させるには 難聴の改善には早めの治療が重要 メニエール病は進行性の病気です。治療すれば完治、改善は可能ですが症状が悪化してからですと完治しにくくなってしまいます。 また、めまいや難聴の原因はメニエール病だけとは限りません。命にかかわる重大な病気の可能性も否定できませんので、そういった意味でも早めに受診しましょう。 病院ではめまいを止める薬は処方されますが、難聴や耳鳴りを緩和させる薬というのは残念ながらありません。 メニエール病はストレスが原因で起こる病気だといわれています。ですから、ストレスを緩和させることが大切です。 無理をせず休むようにしたり、ストレスの発散方法を見つけたりして、心と体に負担をかけない生活をしていきましょう。病院で精神安定剤が処方されることもあります。 また、発作が起きたときも慌てず、ゆっくり休むようにしてくださいね。 さて、次に、聞こえに効果がみられるという“蜂の子”をご紹介します。   【D会員5倍】桜華 蜂の子カプセル 60粒 生後21日目のオスをだけを厳選 栄養価が高く、様々な健康効果があるといわれている蜂の子。 具体的にどのような症状に効果的なのでしょうか。 蜂の子の効能と、健康効果をご紹介していきます。 1)耳鳴り、難聴に 蜂の子の効能効果で一番注目されているともいえるのは耳鳴りや難聴など耳への効果です。 特に耳鳴りは、原因不明といわれているのでなかなか治らなくて困っている人も多いですよね。ですが、蜂の子を摂取して耳鳴りが改善した、という人も多いです。 耳鳴りを長引かせている原因に、ストレスがあります。蜂の子には、ストレスを軽減させてくれる成分を含んでいます。実際に蜂の子を一定期間摂取した人は、ストレスを感じると発生する「コルチゾール(ストレスホルモンともいわれる)」が減ったというデータもあります。これは期待が持てますよね。 人間は、誰もがサーカディアン・リズム(生体リズム)と呼ばれる体内時計を持っています。そして、サーカディアン・リズムは「コルチゾール」というホルモンの分泌を調整する役割を担っています。実はこのコルチゾール、ストレスに敏感に反応するホルモンとして知られていて、脳を覚醒させる働きがあり、特に朝の8時〜9時の間に分泌されるのです。  しかし、せっかく脳が覚醒する朝8時〜9時にカフェインの入ったコーヒーを飲んでしまうと、コルチゾールの分泌が減少してしまうのです。 結果、体内にカフェイン耐性がついてしまい、今までより多くのカフェインを欲するようになってしまいます。 コーヒーを飲むなら「9時〜11時」、「13時〜17時半」 ストレスが溜まっていると、耳鳴りだけでなく、様々な病気を引き起こしてしまうことがあります。ですからストレスを軽減させることは心身ともに健康に導いてくれるのです。 さらに、蜂の子は、聴力の向上に役立つ亜鉛とマグネシウムも含まれています。補聴器をつけるしか治療方法がないといわれている老人性の難聴でも効果を感じている人がいるのです。 2)疲労回復に 蜂の子を摂取して疲労回復効果を実感している人もたくさんいます。疲れがたまっていると病気にもなりやすくなってしまいます。しっかり疲労が取れて元気に過ごせたら、活動的にもなりますので体によいですよね。 蜂の子は古くから、滋養強壮のために食べられてきました。それは蜂の子はたんぱく質が豊富だからです。たんぱく質というと、体をつくるエネルギー源というイメージがあると思いますが、実はそれだけではなく体力を増強する効果もあるんです。ですから、疲労回復にも効果が期待できるんですね! しかも蜂の子に含まれるたんぱく質は必須アミノ酸9種を含む18種のアミノ酸がバランスよく含まれていて良質なたんぱく質なのです。 さらに、蜂の子は強い抗菌作用も持っているのでウイルスなどから体を守ってくれます。ですから、体の弱い人でも、蜂の子を飲んで毎日元気に過ごしているという声もあるのです。 その他にも蜂の子には様々な健康効果が期待できます。めまいが改善したり、髪の毛が黒くなってきたという人もいます。 蜂の子にはたんぱく質だけでなく、ミネラルやビタミンも含まれています。蜂の子で、足りない栄養素を補うことで、不調が改善されることが期待できるのです。 閑話休題: 汗のにおいを消すには  体臭は自分では気づきにくいものですが、エチケットとして日頃から気を付けたいですよね。特に汗をかきやすい夏は気になるという方が多いのではないでしょうか? 実はこの汗による臭い、食事を改善することで抑えることができるのです! 今回は、体臭を防ぐために知っておきたい食事の基礎知識についてご紹介します。 汗はなぜ臭う?原因と予防策 臭いの発生源は「アポクリン腺」 汗が出てくる汗腺には、「エクリン腺」と「アポクリン腺」という2種類があります。 「エクリン腺」はほぼ全身に分布していて、暑い時や運動した時にかくサラサラとした汗を分泌します。そのほとんどが水分です。 一方、「アポクリン腺」は主に脇などにあり、ベタベタとした汗を分泌します。この汗には、水分の他に、タンパク質や脂質など独特の匂いのもとになりやすい成分を含んでいます。 汗が臭っているわけではない。 実は汗自体に臭いは無く、皮膚にいる雑菌(皮膚常在菌)が体臭という不快な臭いを生成していいます。 この雑菌は高温多湿の環境下で繁殖する菌で、汗がたくさん出てジメジメしているところ、特に脇、股、足などに発生しやすいのです。 食事に気をつければ「臭い」は防げる! 体臭は食事に気を付けることでも抑えることができます。アポクリン腺から分泌されるタンパク質や脂質を少なくするために、摂取量を減らせばいいのです。 1)動物性タンパク質・脂質が多い洋食の食事より、和食の方がオススメです。 2)体臭を引き起こす食べ物 肉類: タンパク質の消化にはエネルギーをたくさん使います。その分体温が上がり、汗をかきやすくします。汗に含まれたタンパク質や脂質を皮膚常在菌が分解することで、ニオイが発生します。 にんにく: にんにくを切るとアリシンという物質がつくられます。これが口臭の原因になったり、体内に取り込まれて胃で消化され、それが血液中に取り込まれて皮膚からも排出されるため、体臭の原因になります。 動物性脂肪(チーズ、牛乳など): 大腸まで届いたタンパク質が腐敗し、ニオイ成分を作り出します。さらに、腸内の悪玉菌などによって分解され、アンモニアが作り出られることでニオイの原因になります。 辛い食べ物: 辛い物を食べると汗が出やすくなり、その汗と雑菌が混ざり合いニオイの原因になります。 リノール酸が含まれる油(サラダ油、植物油): リノール酸は血中のコレステロールや中性脂肪を増加させ、体内で「過酸化脂質」になり、様々なニオイ物質をつくりやすくします。 アルコール: アルコールが体内で分解されるとアセトアルデヒドという成分になり、それが血液の中を通って肺や汗腺に送られ、そこからニオイが出てきます。 また、アルコールは口の中も乾燥させてしまうので、唾液が出なくなり口臭の原因にもなります。 3)体臭を抑える食べ物 抗酸化食品: ビタミンC、ビタミンE、βカロテン、カテキン、ポリフェノールなどが多く含まれる緑黄色野菜や緑茶などを積極的に摂りましょう。タンパク質や脂質の酸化を抑制し、酸化臭を防ぎます。 アルカリ食品: お酢や梅干し、海藻類などは体内での乳酸などの産生を抑えて、ニオイを抑制します。疲労回復効果も期待できます。 腸内環境を整える食品: 食物繊維やオリゴ糖を摂ることで、腸内の善玉菌を増やし悪玉菌を減らします。腸内で悪臭成分の産生を抑制し、ニオイ物質を便とともに体外に排出します。 4)「動物性タンパク質」由来の体臭を抑えるには? タンパク質は、分解されるとアンモニアや硫化水素など、ニオイの強い物質を産生します。食べるタンパク質の量が多ければ多いほど、ニオイ物質は多くつくられます。 野菜が苦手または嫌いな方で、肉類や乳製品などタンパク質を中心に食べることが多い方に発生しやすい体臭です。 予防・対処法 メインのおかず(主菜)は 1食1皿までにし、野菜のおかず(副菜)を2皿以上食べるようにしましょう。食物繊維が豊富な野菜や海藻(もずく酢やめかぶ)がおすすめです。 また、タンパク質の代謝にはビタミンB6が必要です。マグロやカツオ、レバー、ニンニク、きな粉、ごま、大豆などに含まれているので、タンパク質を摂る時は、できれば一緒に摂取しましょう。 肉類や乳製品の摂取を控えましょう。特に洋食にはこれらの動物性タンパク質が多く含まれていますので、注意しましょう。 気を付けたい「便秘」由来の体臭の予防法 野菜など食物繊維が少ない食事をされている方や腸内環境が悪い方は、便秘の危険性があります。また、あまり水分を摂らない方も便秘になりやすいです。 便秘になって腸内に不要物がたまってしまうと、それから悪臭のガスが放出されて血液中に入り、汗と一緒に体外に出てきます。 便秘体質の方や腸内環境が悪化している方に発生しやすいです。また、偏食をしている方や小食の方も便秘になりやすいので注意しましょう。 予防・対処法 乳酸菌などの善玉菌や善玉菌のエサになるオリゴ糖、食物繊維をたくさん摂り、腸内をきれいにしましょう。 乳酸菌はヨーグルトやチーズ、味噌、塩麹などに多く含まれています。オリゴ糖はごぼう、玉?ぎ、大豆などにたくさん含まれています。 水溶性食物繊維は野菜や芋類、豆類に多く、エシャロット、ごぼう、納豆、バナナ、切り干し大根、さつまいもなどがおすすめです。 不溶性食物繊維は豆類やキノコ類に多く、インゲン豆、おから、まいたけ、エリンギ、乾燥プルーンなどがおすすめです。 食物繊維には「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」があり、「水溶性食物繊維」は、人体に有害な物質の吸収を妨げ、便として排出させます。「不溶性食物繊維」は水分を含んでカサを増し、腸を刺激して便の排泄を促進します。 にほんブログ村←ポチッとね お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2019.07.19 20:00:06
|