
|
|
|
全て
| よもや話
| 映画をノベル
| 夢日記
| すぽこん野郎
| 軟弱日本を斬る!
| 勝手にまにふぇすと
| 歴史上人物を可たる
| 神秘体験空間
| にっぽんむっかしばなし
| トークドラマ
| 単なる戯(たわ)言戯(ざれ)言
| 人間は芸術である
| 生きることは食すること
| 輪廻転生考察
| 世がヨガ余が善が!
| 魔術とは秘術なり
| アニメフィスト
カテゴリ:神秘体験空間
「素敵な選タクシー」という面白いドラマが以前地上波でやっていたが、つい最近、CSでやっていた。竹野内豊扮するタクシー運転手が、実はタクシーではなく、タイムマシンなのだが、「人生は選択の連続である。どの選択をするかで、その後の人生が変わってくる。」というセリフが非常に印象的だった。
脚本を書いているバカリズム氏は喜劇の天才に思えてくるが、以前、同じように脚本を書いていた「前世不動産」という短編ドラマも非常に面白かった。 残念ながら、タイムマシンは光の速度が問題となる素粒子や天体宇宙の話で、物質界では実現不可能である。というのも、光の速度に近づくには、質量を限りなくゼロにしないといけないので、いかに軽量化を図ろうとも、質量がある限り、光速度に近づくほど、物質は崩壊していくので、タイムマシンは物質ではつくれないからだ。 ドラマなどで、よくお目にかかるタイムマシンは、なぜかタイムマシンと乗組員だけは時間の適用を免れ、自由になっているが、時間の制限を超えるには、アインシュタインの特殊相対論を基にすれば、光の速度で運動する前提が必要となる。 光の速度で運動できなければ、時間の制約を受けるので、過去にタイムスリップすれば、その戻り具合により、タイムマシンも乗組員もつくられる前や生まれ育つ前に戻るので、エントロピーの法則がある限り、存在が崩壊するか、消えてしまう。 また未来にいくにせよ、一瞬にして光の速度に到達できなければ、未来の時代に合うような進歩を遂げないと、浦島太郎のように、年老いて、消えてしまうだろう。 物質構造を持つ限り、質量をもつので、光の速度には近づけない。近づくほど崩壊しはじめる。だから、タイムマシンを過去、もしくは未来に持ち込もうと、光の速度に到達するほど、益々自然に崩壊していく。 つまり、光の速度では、物質は運べないので、タイムマシンは不可能なのである。物質ではタイムマシンはつくれないが、素粒子や、天体レベルの、日常を超える、もはや物質構造をもたない情報の塊などであればタイムマシンはできる。 というかそもそも、タイムマシンが未来にあるとするなら、過去に戻って、その製作法を教えればいいのである。それが可能になっていないという事は、タイムマシンをつくってはいけないか、つくれないか、もしくは実はできているのだが、現代のタイムマシンのイメージにはあてはまらないか、のどれかだろう。 この3択を考えると、タイムマシンという概念が既にあるので、恐らく、現代のタイムマシンのイメージにあてはまらないタイムマシンが既にあると考えるのが尤もに思われる。 時間を操作するには、時間の支配を受けないのが必要不可欠なので、それがアインシュタインの特殊相対論では光の速度になるわけだが、それには質量をゼロに近づけなければならないので、物質界から出ないといけない。 タイムマシンは時間を操作するものだから、時間の支配や影響を受けないものである。つまり換言すれば、永遠のものである。 永遠のものとはなんであろうか? タイムマシンにみえないタイムマシンとは、情報伝達の事で、実は知識の事である。言葉や知識なら、質量はないので、未来や過去にも送れるだろう。例えば、俗に閃きとは、未来から過去にきた知識ともいえる。 どの時代にも通用する知識とは、真実である。 真実とは何だろうか? 真実とは宇宙を永遠に成り立たせている神聖の徳目である。 人智学では真実とは、道徳である事がわかっている。 知識を超えるものは道徳である。知性も人類にとって学ぶべき重要なものだが、知性よりも大切なのが道徳であり、倫理である。 道徳は、現代人が神と呼ぶ未来人から、常にタイムマシンに乗ってやってきている。 人智学では、神界から道徳が秩序として、人生を生きる土台として、キリストが弟子の足を洗うように、下されている事がわかっている。 人智学では、人間は道徳を学びに物質界にきて生きる、のがわかっている。物質界には誘惑が多いので、道徳を学ぶのに絶好の場所なのである。 「選タクシー」の話から大分逸れてしまったが、我々は、肉体という選タクシーに乗って、この世にやってきて、なるべく道徳に沿った選択ができるように、学びにきているといえる。 そういうわけで、健康な選択ができるように、以前に続けて人智学的医術を紹介する。 シュタイナーの人智学的医術では、糖尿病の病因は自我の弱さにある、と考えているが、その事と関係するような記事が以前日刊ゲンダイに載っていた。 それは運動持久力が高い人は糖尿病に罹りにくい、というものである。 自我の強さ、ゆえの運動持久力の高さと考えれば、自我と糖尿病の関係が想定できる。自我が強いと、肉体を巧く制御できるので、運動持久力が高いと考えられる。 逆に、自我が弱いと、運動持久力も低く、理屈っぽく頑固で、怒りっぽく、糖尿病に罹り易い、という事になる。 さて、話は変わるが、瞑想について知りたい、というようなコメントを戴いたので、瞑想について少し紹介したい。瞑想の教科書としては、シュタイナーはあまりはっきりと書いてないので、ドーリルの本を紹介する。 その本はドーリルの「ヨガの真義」である。なかなか分厚いのと、訳が古臭い文体なので、読むのに難儀するが、驚くべき事が書かれている。 少し簡単に紹介すると、第1章は、呼吸法とクンダリーニについてである。ドーリル曰く、クンダリーニは、尾骶骨下に眠っている潜在意識の力だという。 クンダリーニを目覚めさせるには、呼吸法をマスターし、自由自在に呼吸できるようにならないといけないという。 以下の話は、この本の難解さから、ある程度の推測も交じっているので、話半分で聞いてほしい。 通常、人は左右の鼻から大体1時間毎に交代で空気を吸い込み、人体に必要な酸素などを取り込んだ後に吐き出しているが、左右の鼻を自由自在にコントロールできれば、両方の鼻を使って呼吸する事で、クンダリーニを目覚めさせられるらしい。 ドーリルによると、空気のなかには現代科学で知られている元素以外のエーテルも含まれていて、驚くべきなのは、シュタイナーも講義などで軽く触れているが、脊柱の左右と中央にスシュムナと呼ばれる4次元の管が、脳の延髄の上の橋とうから、尾骶骨下部の小さな穴まで、通っていて、左右の鼻からバランスよく呼吸し、エーテルを取り入れると、左右が釣り合って、中央の管にエーテルが流れ、尾骶骨下部に眠るクンダリーニを目覚めさせられるらしい。 クンダリーニは三回転半した尻尾を咥えた蛇で象徴化されているが、この象徴化されたイメージはメリクリウスの杖などで有名である。シュタイナーによれば、このイメージは、人類の進化の道であり、生命の樹を表すという。 ドリールによると、左右の鼻や、口や喉頭を自由自在に操り、呼吸する事で、スシュムナの管を通じて、エーテルを満遍なく人体に流せば、不調和や不均衡に陥っている病気を治療できるという。 スシュムナの左の管をイダ、右の管をピンガラと呼び、クンダリーニが隠れている穴をカンダと呼ぶらしい。またそのような呼び名はヨガの伝道師のヨギや流派により色々あるらしい。 ヨガは瞑想の初歩のようで、要約すると、エーテル体と肉体のバランスをとったり、エーテルを集めて、クンダリーニを用いて、未来の人生をつくるのが目的のようである。 要するに、ヨガは、人体に(エーテル)エネルギーを集める方法のようである。 重要なのは、矢鱈にエネルギーを集めても、その使い方が問題で、使い方を決めるのが、瞑想であるようだ。瞑想で、エネルギーの方向性を決めるようで、瞑想を誤ると、創造エネルギーを破壊に使ってしまい地獄をイメージして地獄に堕ちていく羽目になりかねない。 少しでも恐怖感などのネガティヴなイメージが残っていると、増幅されてしまうので、自分で地獄を創り出して、地獄に堕ちてしまうようだ。自殺などがその典型。 瞑想は、メディテーションと呼ばれるが、メディは、ラテン語で、「熟考」を意味し、メは、「人」の事であるという。また時にはコンテンポレーションとも呼ばれる。 瞑想については色々と書かれているが、読んでいるうちに訳が分からなくなってくるのだが、結局のところ、御釈迦さんが説いたように、あらゆる欲望を滅する事、つまりこの世の執着心をなくして、一時的な快楽を求めるのではなく、永遠の揺らぎのない安定の平和を求める事が要諦であるらしい。 譬えとして、ある金持ちの息子が、キリストの弟子にして欲しいと願い出た有名な話があるが、キリストは、私についてくるのなら、財産を全て売り払ってきなさいとアドバイスしたが、ドリールによると、それは金持ちだから、悟れないのではなく、その息子が、金に執着し、この世で最も価値があるのは金だと思っている価値観があるうちは、金に囚われ、金に依存し、束縛されているせいにあるという。 自由な意志を束縛しているうちは、神に仕える事は出来ないので、瞑想をしても、徒労に終わる。この世での、名声欲や所有欲などの一時的なものを欲するうちは、そのものに囚われ、自由な意志を明け渡してしまっている。要するに奴隷になっている。 最も価値があると思うものに、束縛されるのだから、永遠に束縛されずに自由にコントロールするには、永遠な存在、つまり神に仕えるのが最も自由になれる秘訣である。 御釈迦さんが説いた永遠の法に仕えるべきである。永遠の法とは神の事である。何者にも束縛されない自由な存在である。 神に仕えるには身を清めて、謙虚にならないといけない。 神は道徳である。 欲望を捨てるには謙虚にならないといけない。 金銭や権力などの欲望の奴隷から解放する運動が起こらないといけない。これは集団による革命ではなく、一人一人の個人による奴隷解放革命なのである。 というわけで、神に仕えるために、人智学的医術の続きを紹介する。 ★ ★ ★ ルドルフ・シュタイナー 「精神科学と医学」第16講 1920年 4月5日 ドルナハ -------------------------------------------------------------------------------- 提出して貰った質問が、少しずつ登場してくる、のがわかるだろう。ただ、これらの質問にラツィオ(理念、原理)に則って答える為の土台を築くのが重要である。今回は、前回の最後に急いで述べた脾臓の働きの重要性を引き継いでいきたい。 脾臓は、潜在意識上の呼吸などの生命活動を制御している。 脾臓を単なる附属臓器とみなすなら、全体を見誤る。脾臓は、物質というよりも、霊に偏った臓器で、その働きを補助させる為にエーテル体を引き寄せ、容易に肩代わりさせるので、脾臓を単なる附属臓器とみなすような誤解が生じやすい。 (脾臓を摘出しても、人体にそれほど害はないが、感染症に罹り易いといわれている。それはおそらく、新陳代謝にリズムを与える働きに関係しているせいだろう。) しかし、もし、脾臓の働きを、覚醒意識へと引き上げたなら、脾臓の働きの特異性がわかるだろう。脾臓の特異な働きを手掛かりにして、近代において、興味を引く対象となった治療法が実際に観察できる。 その治療法が特異なのは、脾臓の特異な働きに負う。つまり、脾臓の辺りを弱くマッサージすると、栄養摂取などの活動に対して、均衡=バランスをとるように覚醒意識を働かせる、のが確認できる。 脾臓の辺りを、そっとマッサージすると、生存本能的な活動に均衡を与え、つまり人体に見合った食事がわかり、食事の取捨選択ができるようになり、食に対して健全な関係が持てるようになる。 とは言え、この脾臓付近のマッサージはすぐに限界に突き当たる。マッサージが強すぎると、かえって活動を弱めてしまう。従って、活動の均衡点と呼べるものを独自で獲得し、保持しないといけない。また、マッサージの範囲を、あまり広くしてもいけない。 さて、では、この事実から何がわかるのか? 脾臓の辺りをマッサージすると、通常は、この脾臓の辺りにないものが導かれる。つまり、マッサージした部位に覚醒意識が投影される。 このように覚醒意識を呼び起こし、均衡を図る事で、人体の健全化が成し遂げられる。このような霊的な治療法を、無骨で粗雑な現代の言葉で表わすのは困難である。 奇妙に思えるだろうが、脾臓により媒介される、潜在意識上の理性と、覚醒意識上の人体の働きとの間には相互作用が存在している。 それでは、覚醒意識上の働きとは何なのか? 覚醒意識上の物質体の活動が、高次の潜在意識上の活動、特にイメージ活動を伴う形で起こる場合、物質体に害を与える、という事実を見過ごしてはならない。 物質体が、イメージ活動に通じると、自らを害するようになる。この自らを害する(ネガティヴ=自虐)状態は、潜在意識上の自我のなかの意志によって絶えず中和されている。 脾臓には、この潜在意識上の意志の中心がある。マッサージして、脾臓を、覚醒意識で満たすと、高次の潜在意識から発する強い毒性に対抗する働きかけができる。 (毒性とは、物質体にエーテル体とアストラル体がひきづられて、自我による物質体の制御を困難にすること。脾臓には、人体のリズムを調節する司令塔みたいなものがあるらしい。) 脾臓マッサージは、必ずしも肉体の外から行うだけでなく、内からもできる。そもそも、この治療法をマッサージと呼ぶのに異論があるかもしれないが、わかりやすさを採った。例えば、内からの脾臓マッサージは、次のように行なえる。 例えば、エーテル体やアストラル体の活動が強烈で、物質体がそれにひきづられる場合、1日の主な食事(ドイツでは昼食)の時に食べないか、なるべく少なく食べ、その分、間隔を開けて、数回に分けて食べる事で、1日の食事の間隔を、通常よりも短かくする。 このように1回の食事を、少量にして数回に分けて食べれば、内から、マッサージのように脾臓に影響を与えられる。ただし、あらゆる治療法に難点があるように、この内からのマッサージにも難点がある。 というのも、今日(1920年)のように慌ただしい時代では、少なくとも大多数が、四六時中、肉体活動に追われ、食事の消化に時間をかけられず、脾臓の働きは、肉体活動に強く影響を受けざるをえない。 人間は、動物とは異なり、地面に横たわって、消化活動を妨げないようにすることで、健康の維持を図らない。動物が、脾臓の働きを労わっているのは事実である。 神経症ともいえる慌ただしい肉体活動のなかにあるときは、脾臓を労わらない。その結果、文化人などで、脾臓の働きが次第に大変異常なものになっていく。そうすると、いま少し述べたような治療法で、脾臓の働きの負担を少しでも軽減するのが意味をもつようになる。 内、外を問わず、脾臓マッサージのような霊的なマッサージに多少とも注意を向ければ、潜在意識を媒介する霊体(エーテル体)と、覚醒意識を媒介する物質体との間の関係についての素晴らしい治癒原理が得られる。それによって、マッサージ全般の意味を理解するのも容易になる。 マッサージが意味を持ち、特に効能を発揮するのは、人体のリズム活動の調節であり、状況によっては強力な治癒力を与える。マッサージは、主にリズム活動の調節に影響する。 しかし、マッサージの治療成果を上げるなら、人体を霊的に知る必要がある。例えば、次のような事を考慮に入れてみるとよい。 腕と脚は霊的にも大変異なっている。 人間の腕は、重力から免れ、自由に動かせるが、腕のアストラル体は、脚よりも、遥かに物質体との結びつきが弱い。脚は、アストラル体と緊密に結びついている。腕のアストラル体は、外から皮膚を通じて肉体の内へと作用するほうが多い。 アストラル体は人体を包み込むように働くので、腕や脚を包み込み、外から内へと作用する。脚と足では、アストラル体を貫いて、自我のなかの意志が、内から外へと遠心的に強く放射しながら作用している。腕と脚とでのこの違いは大きい。 その違いの帰結として、脚と腕とでのマッサージは、根本的に違う影響を与える。 腕のマッサージは、アストラル体を、外から内へと通常よりも引き入れることで、自我の意志の道具となり、外から内へと、腸から血液までの消化で生じる新陳代謝の調節を引き起こす。 すなわち、腕のマッサージは、消化から造血まで多くの影響を引き起こす。 対して、脚のマッサージは、内から外へと意志を拡げ、そのイメージに沿って物質体を変化させ、内から外への排泄-分泌の新陳代謝の調節を引き起こす。 つまり、腕のマッサージは、外から内への人体の構築活動とつながり、脚のマッサージは、内から外への人体の解体活動とつながる。このマッサージの働きの違いが、人体内外につながっていくなかに、人体の本質である霊体の微妙な働きが見て取れる。 このようにラツィオ(理念)に則って人体を探究すれば、どの部位も、他の部位と対極的な関係を持ち、マッサージが、この相互作用を霊視した知見に基づくのがわかるだろう。 下腹部をマッサージすれば、呼吸活動にも良い成果をもたらす。下腹部のマッサージが呼吸活動に良い影響を及ぼすのは興味深い。しかも、心臓の下あたりをマッサージする場合、上から下へといくほど、呼吸活動への影響は強くなり、更に下にいくと、今度は咽喉頭への影響が強まる。 つまり人体が丁度逆になっていて、胴体のマッサージでは下にいくほど、上に位置する臓器が影響を受ける。また、例えば、腕のマッサージは、胴体の上部を同時にマッサージする事で強められる。このような事実は、人体の個々の部位の関係を具体的に示している。 例えば偏頭痛などで、離れた位置にあるが、密接に関係している上下の部位の相互作用が、特に顕著に現れる事から調べられる。偏頭痛は下腹部の消化活動が、頭部に移行したものである。 従って、例えば月経のような下腹部の強烈な活動により、偏頭痛などで、頭部も相応に影響を受ける。このように頭部にはなかった消化活動が生じる事で、日常は免除されている負担が、頭部の神経にかかる、のである。 頭部は消化活動をせず、摂取活動のみを規則的に行うので、頭部の神経は消化の負担を免れ、摂取したものを知覚するだけの知覚神経になる。しかし、消化活動のような、無秩序な活動が起こると、神経は知覚神経でなくなる。 すると、頭部の神経は、前よりも感じやすく敏感になり、感受すべきでないものを感じ取ってしまい、偏頭痛が起こってくる。周囲の外界を知覚する代わりに、突然、頭のなかを知覚するように強いられたら、どんな風に感じるか、想像に難くないだろう。 さてしかし、この状態を正しく見通せたなら、偏頭痛の最良の薬は、やはり安静にしてよく眠るだけだと指摘できる。というのも、通常(1920年)用いられ、推奨されている薬は、有害な作用を及ぼすからである。 この逆症療法(アロパシー)の薬を使用すると、過敏になっている神経を麻痺させ、その活動を低下させる。確かに、例えば、劇の公演にどうしても出なくてはいけないときに、偏頭痛になり、多少、神経を害しても、出たいと考え、薬で、神経を麻痺させてしまう事がよくある。 このような事例から、人体の精妙精緻の極まりなさがわかるが、社会に参画するだけでも、しばしば健康の素養を阻んでしまう。 このような事例は当然起こり得るもので、決して無視できない。だから、社会的立場を通じて引き起こされる害を受け入れて、場合によっては、その後に生じる後遺症の治療も考えないといけない。 結局、この人体の精妙精緻さは、症状に応じた形で色彩-光療法(光線力学療法)を研究していく場合にも示される。この色彩-光療法は、過去の研究よりも、少なくとも、将来もっと盛んに研究していくべき治療法である。 更に、人体上部に内から働きかける色彩の影響と、吸収されるなどして人体全体に外から働きかける光の影響との違いも研究していく必要がある。 色のついた光で全身を照らすか、一部を照らすかすると、外からエーテル体の活動が誘導できる。 また色のついた光で照らす代わりに、覚醒意識に働く、色彩の印象を用いた治療法で、つまり色に塗られた部屋に連れていって、ある色の印象を意識に強く働かせると、アストラル体のなかから自我に影響が与えられる。 この主観的な色彩療法では、直接、自我に働きかけられる。先に述べた、光による客観的な色彩療法では、まず物質体に作用するので、物質体を迂回してから、自我に影響が及ぼされる。 だから、「目が見えない人を、色のついた部屋に連れていっても、無駄じゃないのか」などの反論は無意味で、間違っている。 眼がみえず、色が視覚として吸収されない分、より顕著に、人体の感覚を通じて現われてくる。眼がみえなくても、赤か青の部屋に連れていけば、その違いが知覚できる。 つまり、この色の違いは、知覚の本質に関わるので、眼がみえなくても、青い部屋に連れていけば、自我の意識を、頭から下へと誘導できる。また、赤い部屋に連れていくと、逆に、下から上の頭へと誘導できる。 以上の事例から、色彩療法の本質は、色彩を変えたときに、人体に生じる違いにある、のがわかるだろう。青や赤という色が本質ではなく、赤から青にいくか、或いは、青から赤にいくかの違いが本質なのである。この色の違いに本質がある。 一般的に、頭への強い刺激を通じて、下部の代謝機能を改善したい場合、青い部屋から赤い部屋に連れていけばよい。逆に、人体下部への強い刺激を通じて、頭部の神経機能を改善させたいなら、赤い部屋から青い部屋に連れていけばよい。 このような事実は、将来、非常に重要となり、光療法だけでなく色彩療法が大きな役割を果たすようになるだろう。 また覚醒意識と潜在意識との交替が、将来の治療では、重要な役割を果たすようになるべきだろう。というのは、この交替によって、入浴を通じて、物質特有の人体への働きについて、健全な判断を養成できるからである。 また、人体を、外から冷やすのか、温めるのか、では大きな違いがある。湿布や入浴などで冷やす場合、冷却物質の特性が強く現れるので、治療には、その影響を加味しないといけない。人体を冷やす場合、物質薬の特性が大きく影響する。 冷却でなく、温める場合は、どんな物質を用いようと大差なく、温度こそが重要で、つまり人体を温める場合、物質の特性にはほとんど無関係で、温度や熱が大きく影響する。 だから、冷湿布に用いる液体に溶かす、薬となる物質の特性に注意を払う必要がある。物質を薬にするには、冷水で有効なときで、つまり、低温度で溶解する物質でないといけない。 対照的に、強い香りを発するエーテルに近い揮発性の物質は、高温でも、物質の特性が引き出せるが、そのような物質を度外視すれば、高温度で固体として溶解し安い物質である。 温湿布や温浴では、物質特有の作用は引き出せない。対して、硫黄や燐に近い物質は、温浴でこそ、霊の特性を展開できる。 つまり、上述したような関係を、霊体にまで繊細に観察し、表現するのが重要である。霊の関係=法則を表現するには、原現象(ウアフェノメーン[Urphaenomen])というモデル(イメージ)を設定すると非常に役立つ。 (現代でいうところの、思考実験のようなもの。例えば、シュレディンガーの猫とか。) 原現象を設定する、という方法は、医学教育(医師の養成)が、秘儀(霊能力)から発するのが多かった時代では、大きな役割を果たしていた。 当時の事実や法則は、現代のように理論的に表現されたのではなく、原現象で表現された。 だから、例えば「お前の内に、蜂蜜か、ワインをもたらせば、宇宙からお前に与えられた力を、内から強める。」と表現された。もしくは「そうすれば、お前は自我の力を強める。」とも表現された。 原現象は事実をわかりやすくする。 また「お前の体に油を塗れば、お前のなかにある、有害な地の力を弱める。」などと表現された。地の力とは、自我の(意志)力に対抗する(物質)力のことである。 また、「内からの甘いものによる強化と、外からの油による弱化の間に正しい割合を見つければ、人は老いる。」とも表現された。 以上の古代人たちや、古代の医師たちが述べた原現象は、次のように表現できる。 「肉体にエーテルの油を塗り、その働きにより有害な地の力を抑えられるように、自我の意志やエーテル体が弱くなければ、ワインか蜂蜜を飲めば、自我の力が強まり、叡智に導く。」 以上は、当時、原現象として表現された事実である。古代人は、教義ではなく、事実を通じて正しい道を示そうとした。このような事実に、現代人もまた立ち返っていくべきである。 というのも、以上のように原現象を解き明かせると、外界の多様な物質のなかでも、事実を見通せるからである。新しい具体的な現象などが登場すると、すぐに霊魂を度外視し、抽象的な自然法則なるものに回帰するよりは、遥かに容易に事実を見通せる。 さて、次のような簡単な表現の原現象もある。 「両足を水に入れたなら、造血の調整を下腹部に呼び起こす。」 また、生活の指針となる原現象もある。 「頭を洗えば、排泄の調整を下腹部に呼び起こす。」 これらは教唆に富む原現象である。原現象のなかに法則が示されているからである。このような原現象は、人体に関する事実である。というのも、人体を考慮しなければ、原現象は無意味だからである。以上のような原現象では、人体を考慮する事に大きな意味がある。 さて、以上の原現象は、人体に関する様々な力の空間的法則を示すものだが、時間的法則もあり、例えば、子供か、青少年の初期の頃に、不当な扱いを受けた結果、その時代に育成すべきものが育成されず、または、年配になってから育成すべきものを、既に育成してしまっている場合に現われてくる。 幼少期(約7歳まで)には既に、エーテル体をつくっていく力をもっている。しかし、例えば、少年期(約14歳まで)につくるべきアストラル体が、正しくつくられるわけではない。 (7歳までの幼少期=エーテル体作成、14歳までの少年期=アストラル体作成、21歳までの青年期=自我作成。) また、少年期にアストラル体をつくるのは、青年期になってからようやく活動を始める自我を準備する為でもある。つまり、子供の頃すでに、エーテル体がつくられるが、子供のときに使われるだけでなく、歳をとってからではつくりだせないので、この時期につくられる。 以上について、次のような事が考慮されていない。 つまり、歯が生え変わるまでは、模倣を通じて教育する必要があり、歯が生え変わってからは、秩序や権威という父性が大きな役割を果たすように教育し、育成する必要がある。 (歯が生え変わるまでは、模倣によるエーテル体の作成、歯が生え変わってからは、秩序や権威に従う父性によるアストラル体の作成。) もし、上述の事実が考慮されなかったら、歳を経てから使われるべき(準備されるべき)エーテル体、アストラル体、自我が早期に使われてしまう可能性が出てくる。 今日の唯物論的な思考法では当然、次のように非難するだろう。 「模倣か、権威か、がそんなに大きな意味を持つはずがない。」 しかしながら、この事実は、非常に重要な意味をもっている。というのも、エーテル体、アストラル体の働きは人体のなかで継続していくからである。 子供は、寝ているときの魂の状態も含めて生活全体のなかで模倣している、という事実を考慮しなくてはならない。例えば、次のような事は非常に大きな意味を持つ。 考えてみればわかるが、教育する大人と同じ食物を好むように、子供を育てれば、好みを子供に(強制的に)植え付ける事になる。 すると、この模倣の原理から、大人と同じ食欲を、子供に根づかせ、子供のアストラル体をエーテル体に結び付けてしまい、エーテル体に模倣された、アストラル体の食欲が継続してしまう。後の権威に基づく教育も同様である。 要するに、歳をとるまで使われることなく、準備されるべきアストラル体が、子供のときに使われてしまうと、恐ろしいデメンティア・プラエコクス(精神分裂病)が起こる。 デメンティア・プラエコクス(精神分裂病)の根本の病因は、成人後に使うべきアストラル体が、子供のときに使われてしまう事にある。だから、次のような結論に至る。 「適切な教育は良薬である。」 従って将来(現在(1920年)、ヴァルドルフ学校では、適切な教育を行うよう努力しているが、幼児のはじめまでは拡げられず、六歳か七歳になってから、ようやく可能な段階にある)、「人智学の観点からの子供の教育」(1)という小冊子で提示したような意味に沿って、教育全体が変わっていけば、デメンティア・プラエコクス(精神分裂病)も消滅するだろう。 (1)「精神科学の観点からの子どもの教育」(1907)は「ルシフェル-グノーシス、論文集1903~1908」(GA34) に収められているが、個別小冊子としても何度も出版されている。最新版は1985年。 「精神科学の観点からの子どもの教育」は、1906年の年末から1907年初頭にかけて、ドイツの諸都市で行なった講演内容をもとに、シュタイナーが論文形式に改めたもので、まず雑誌「ルシフェル・グノーシス」に発表された後、単行本としても何度か出版されている。邦訳は「霊学の観点からの子どもの教育」(高橋巌訳 イザラ書房)。 (精神分裂病は大人の価値観を子供に植え付けることが病因のようである。) というのも、教育を、そのような意味から行えば、歳をとってから使うべき霊体(エーテル体、アストラル体、自我)を早く用いてしまうのが防げられるからである。この事実は、適切な教育を行うのに必要である。 さて、また逆の事も、人生では起きる。逆というのは、少年期の成長のために使うべきアストラル体を、使えずに後に残しておく事である。子供や青少年の成長の為に主につくられる霊体を使ってしまうのは全生涯にわたって起こり得るが、成長以外に使われるのはよくない。でないと有害な結果をもたらすからである。 例えば、様々な理由から、精神分析が、今日(1920年)の思想全般に入り込み、混乱を生じさせる分野となっている。大きな誤りはすぐに反駁されるため、それほど有害ではないが、むしろ有害なのは、多少の真実が混じっている場合で、議論が極端に進んで、誤用されるからである。 では、精神分析とは、どういうものなのか? 止むを得ないとはいえ、人間を外界の環境に適合させない今日(1920年)の不自然な生活様式によって、子供のときに与えられる外界に対する印象の多くが消化されないままに残る、という問題が生じている。 魂(アストラル体)に与えられた印象の多くが、物質体に適切な形で編入(フィードバック)されずに残ったままになってしまう。というのも、アストラル体の働き自体は弱くても、持続していき、肉体への働きにも影響を与え続けるからである。 また現代の子供たちは、魂(アストラル体)にいつまでも残り続けるほどの異常な印象を数多くもっている。これらの印象を、エーテル体や物質体の働きに転化するのがもはや不可能となると、これらの印象は、魂(アストラル体)のなかだけで働き続け、成長に関与せずに、肉体から分離した魂のなかの欲望であり続ける。 これらの印象が肉体の成長に関与していれば、後の人生、いわゆる大人になったときのための準備となり、子供のときに与えられた印象の為に使われずにすむ。 このようなことから、人体全体(肉体、エーテル体、アストラル体、自我)に不都合が生じてくる。魂(アストラル体)の分離が、そのときに使うべきでない自我に影響せざるをえなくなる。 以上は、精神分析を正しく適用すれば確認できる現象である。数理を用いて問診すれば、魂(アストラル体)のなかに消化されずに残り、無理にでも消化すれば、既に老いてしまった物質体の中で破壊を行うような印象を見つけ出せる。 しかし、精神分析では、治療は不可能で、診断なら可能なので、診断に限定して用いるならよいとはいえる。 ただし、適切な順序に則って正しく精神分析が行われ、一切の非難、批判めいた手紙が寄せられず、それらにより裏づけされるような悪事もなされずに、すなわち、精神分析家たちが、教理を用いた問診の際に、強制的に情報を引き出そうとして、患者の発言を、スパイのような監視人などを使ってでも獲得するような事がなければ、という条件が必要である。 このような事はしばしば起こるので、精神分析には酷い不正が隠れている。しかし、このような不正を度外視すれば、精神分析に携わる人たちの道徳性が非常に重要であり、次のような結論に至る。 「精神分析を診断に用いるなら、多少の真実も含まれているが、治療に用いるのは不可能である。」 これもまた、この時代の現象と関わりがある。 唯物論の悲劇は、唯物論が物質の認識からも逸れていて、その認識を妨げる事にある。つまり唯物論は、霊の認識というよりも、物質をつくっている霊の認識にとって有害なのである。 霊は物質と結びついている。だから、物質のなかに霊の働きが探究できる、という洞察が阻まれ、人生についての健全な理解の多くが阻まれてしまう。 たとえ唯物論者であっても、これまでの考察で議論してきたような特性全てを物質に帰するなどは不可能である。物質に備わる様々な特性を、物質に帰する、というのは全く馬鹿げている。つまり、その矛盾が、既に、物質の認識から逸れている、のを意味する。 (素粒子論では既に粒子では全てを説明できないので行き詰まって、超弦を持ち出している。) 唯物論の物質認識では、燐や塩の現象をナンセンスとみなすので、霊の現象を語れない。物質のなかの霊の認識から逸れているので、霊の働きを的確に研究する可能性からも隔たり、特に人体の本質が、いずれも二重の課題を担い、一方が自我の意識づけと関係し、他方がその反対の、物質体の作成へと向かう、という洞察から離れていく。 以上のような見解は特に、これから議論していく歯の診断では失われてしまった。歯は、唯物論的に、単なる咀嚼器官と見られているが、そうではない。 歯が二重の性質をもつのは、化学的に調べれば、歯が骨と関わる事からも明白である。しかし、発達史(進化学)では、歯は、皮膚から発している。歯は二重の性質を持っているが、ただ、第2の性質は深く潜伏している。 動物の歯並びと比較すれば、この講義の冒頭で述べたエーテル体の違いが強く現われている、のがわかるだろう。サルの頭蓋骨の図から示した下への負荷のことである。 サルとの比較から、人間の歯には、垂直上向き(エーテル)の作用が見られる。この力から、歯が単なる咀嚼器官ではなく、吸収器官でもあり、外へ向かって機械的に働く他に、内へ向けて吸収する霊の働きがある、のがわかる。 そこで、次のような疑問が浮かぶ。 では歯は何を吸収するのか? 歯はできる限りフッ素を吸収している。歯はフッ素の吸収器官なのである。 つまり人間は、微量のフッ素を必要とし、フッ素がないと、衝撃的な事実を述べるが、人間はあまりにも利口になり過ぎてしまう。 人間は、自らをほとんど破壊しかねないほど利口になってしまう。つまり人間でいるには適度な愚かさが必要で、フッ素の働きにより、利口が和らげられる。人間は、利口になりすぎない為の絶えざる抵抗手段として微量のフッ素を必要する。 だから歯が悪くなると、フッ素の吸収を損なう事になるが、フッ素の吸収が過剰になっている場合、歯を損なう事で、フッ素の愚かさを抑え、利口にしている事になる。 つまり、フッ素を吸収し過ぎて、愚かになりすぎないように、歯を壊す、のである。上述の微妙な関係を考察すれば、愚かになり過ぎない為に、歯を損なう事がわかる。 このような事実から、人間に利益をもたらす活動と、害をもたらす活動の両方へと揺れ動く、密接な対極関係が洞察できる。 あまりに利口になりすぎて、人でなくならないように、人はフッ素の愚かさを必要とするが、逆にフッ素の愚かさを強く吸収しすぎると、愚かになりすぎてしまうので、エーテル体を通じて、歯を破壊する。 これらの事実をよく考察すべきである。というのも、これらは人体の根底に関わる究めて意味深い事実だからである。 1-16 自我が、シリカを通じて四肢に作用する、この奇妙な作用を図を用いて表現するなら、以下になる。 「シリカを通じての自我の四肢への作用(下図参照、赤点線と内のピンク)の本質は、人体を統合する事なので、体内の液体として区別なく統一へと結合し、混合するため、四肢では、自我は全く区別なく(固体化しない)全体への一様な統合力となっている。」 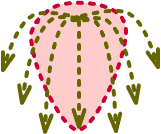 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[神秘体験空間] カテゴリの最新記事
|