
|
|
|
テーマ:映画レビュー(890)
カテゴリ:フランス映画
MINA TANNENBAUM
Martine Dugowson 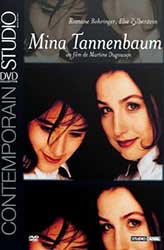 寸評:ストーリーはいいが、もしかしたら色々な面で欲張り過ぎで、内容・構成・演出・演技すべてに関して崩れる寸前の危ういバランスで出来ている。あと含みが多く、本当に味わうには60・70・80年代のフランスに関するかなりの知識が必要。  1958年4月に生まれたミナとエテルというユダヤ系フランス人の女の子の半生を、2人の友情と離反を中心に、題名通り画家ミナの物語の枠で描いている。脚本・監督が1958年生まれであり、自伝ではないけれど自分の生きてきた時代を描いていると言えるだろう。寸評に知識の必要性と書いたが、フランス社会におけるユダヤ人の位置づけはもちろんのこと、マシアスやダリダのシャンソンにしても、1968年の5月革命にしても、ただ流行歌や事件という理解ではなく、フランス人にとっての印象や思い出と深く結びついている。その辺の理解があればあるほど深く鑑賞することができるということだ。  (以下どうしてもネタバレを含む) 映画はちょっとマーラーの交響曲の緩徐楽章風の荘重な音楽とともにタイトルロールが始まる。そこで夭逝した女性画家ミナ・タンネンボームを生前知っていた人々の彼女に関する短いインタビュー風のコメントが挿入される。やがて従姉が登場し、カメラに向かってミナの生涯を語り始める。その内容がほぼ映画の全体で、従姉も要所要所で語り手として登場し、最後に冒頭の従姉の場面に戻り、この従姉が取材カメラに向かって話をしていた、という枠を示す映像で映画が終わる。  1958年4月初め、ミナが生まれ、その68時間後にエテルが同じ産院で生まれる。ほとんどの解説やレビューは「同じ日に生まれた」としているが、最初の産院の風景は1958年4月5日で、そのときミナは生後73時間、エテルは生後8時間とナレーションが入る。観客のレビューならいいけれど、goo映画等の映画専門サイトやアマゾン等ショッピングサイトがこういう安易な間違いをしているのはお粗末。  物語の構成は3つの時期からなると言えるだろうか。2人が10才で出会って、ミナは眼鏡のためにいじめられっ子で、エテルは肥満のゆえに、どちらも容貌に自信がなく、また親との問題もあって、互いに精神的に頼り合う奇妙な友情で結ばれている時期。次にそれぞれが自分の人生を送るようになり、やがて離反していく時期。最後は再会で、エテルは懐かしみながらも既にミナを必要とせず、ミナは交通事故で顔に傷が残るなどの不幸や、それとも関連してエテルが自分の幸福を奪ったという思いの中で一人孤独な人生を送っていて、不可能なエテルとの幼少時代の復活に夢を抱き、結局人生に絶望して自殺する時期の3つだ。  寸評に「欲張り過ぎ」と書いたようにあまりにも内容が盛りたくさんなので、いちいちの説明はせず、印象の羅列を書くことにする。  自伝ではなくとも自分の生まれて生きてきた時代を監督は描いた、と上に書いたが、結局のところどこに物語の、あるいは監督の言いたい主張があるのかがちょっと不明確。たとえば親子の断絶。特にユダヤ人独特の伝統的な信仰や人生観の親世代と新しい自由を求める子供世代、そのどちらに軍配を上げているのか、つまりどちらを肯定的ないし否定的に描いているのか、主張したいのかが、ボクの知識の範囲内で見るかぎり明確ではない。明確な視点の欠如だ。  あるいは、たとえば1968年はテレビの連続ドラマの影響で女の子たちはみんなバレリーナに憧れたといい、2人もバレエ教室に通うシーンがあるわけだけれど、映画の中の誤りをあげつらう仏サイトを見ると、電話番号の桁数とか商店の計量秤の形式とか、時代考証はかあなりいい加減らしい。主人公たちと同時代を生きた監督のイメージ的回想だから誤りはあってもいい、とも言えないことはないが、結果としては正確な年代記にはなっていない。その意味では監督の主観的記憶の物語と解釈した方がいいのかも知れない。  あとは冒頭で産院の看護婦たちが新生児を抱いてバレエのように踊る演出、2人の出会いのシーンでそれぞれの守護天使たちが空に現れ言い争うシーン、カフェで言い争うミナとエテルからそれぞれの分身が現れて、実際の2人とは別に分身たちが取っ組み合いをするシーン、その一方では最初の方で眼鏡でいじめられて去っていく並木道の静かで美しい映像、そんなこんな映画の描き方の流れに統一感がない。こういう演出で一つだけ効果的だったのは、家のエレベーターを降りた今のミナが、入れ違いにエレベーターに乗る眼鏡でランドセルをしょったかつての子供のミナを見るシーン。ここは美しかった。この映画の中で最も美しいシーンかも知れない。  最初に2人が出会うキッカケとなる二人のひそひそ話しをする少女を描いたゲーズボロのミナの模写。最初の部分では10才のミナの絵の上手さを描いているし、絵自体は二人を象徴する2人の少女の絵で、喧嘩のときにミナに返されたこの絵が部屋に残って最後を締めくくる。なかなか上手い使い方です。  ボクは役者としてではなく女性としてはロマーヌ・ボーランジェにはほとんど何の魅力も感じないのですが、演技的にはミナとエテルを演じたロマーヌ・ボーランジェとエルザ・ジルベルスタンがともに好演してますね。欲張らずにもう少し整理して作っていたら、ミナの心情ももっと良く描かれたと思います。彼女の悲劇の人生をあまり暗く描きたくなかったのかも知れませんが、孤独の絶望による自殺が明るいはずはもともとあり得ません。  なんかの受賞をしているだけにシナリオは良く書けていると思いますが、もう少し整理すればもっといい映画になったのかも知れません。でもやっぱり明確な視点を欠いていますかね。でもなんとなく忘れ難い映画です。  お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.01.30 03:13:52
コメント(0) | コメントを書く
[フランス映画] カテゴリの最新記事
|