ヘーゲル『大論理学』25 第三巻6・第一章概念
ヘーゲル『大論理学』学習も、今回で第25回目となります。
『大論理学』第三巻は「主観的論理学または概念論」と題されてますが、
今回はその第三巻・第一章「概念そのもの」です。
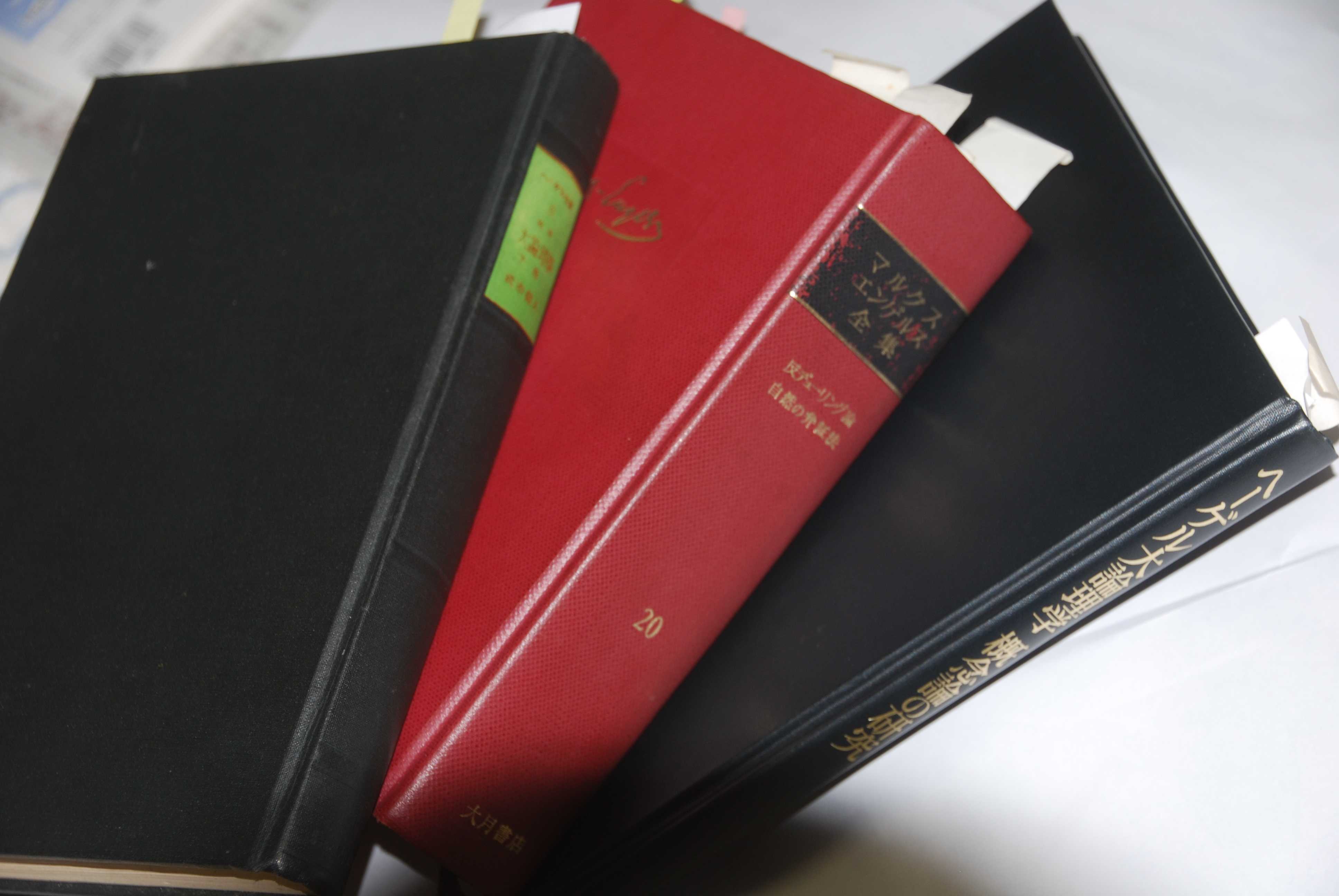
このヘーゲル『大論理学』の学習などというグダグダした中身に付き合おうというなどという人は、私などは、今の世の中では奇特な方だと思うんですよ。
私はそれだけの価値があるとおもうから、しつこくもこだわっているんですが、こんな中身を突然に提出されたら、私なども「何、言ってるんだ」とパスしていると思います。おつきあいしていただいている方には、閲覧していただいている方には、そのことに心底敬意を感じています。
一、さて、前回(第24回)の第三巻に対するヘーゲルの案内図を紹介して以降のことですが。
1、あらためて、この問題・課題の大切さとともに、それを理解し問題共有をしていただくことの難しさを考えさせられています。日本の人口は1億人弱かとおもいますが、なかなか具体的な反応は無いんです、ダルマ状態です。まぁ、それはそれで良し。とにかく私自身がヘーゲルの『大論理学』が提起している問題について、大よそであっても第三巻・第三篇「理念」の終わりまでたどり着くということです。
2、ヘーゲル自身のプレゼント。前回と前々回に紹介させていただいたように、この難書の第三巻について、ヘーゲルがこの冒頭の「区分」(P31-34)で、大よその案内図を書いてくれていました。これは貴重なアドバイスだと思うんですよ。こうした案内図の指摘がないと、実際に大きな山に登るのは困難なんです。ヘーゲル自身もそれをよく承知していたんですね。しかし、このヘーゲル作の案内図ですが、当人の意図にもかかわらず私などにとってはそれはそれで難しいものだったんです。
3、そこには、ヘーゲル自身の探究のあゆみがあると思うんです。
『哲学入門』(岩波文庫)は、私などが手にしうる論理学についてのヘーゲルの最初の講義レジュメです。これは1808年にニュールンベルグのギムナジウム(高等学校)での講義した時のもの。それから『大論理学』、『小論理学』、最後は『1831年ベルリン大学で講義』と、24年もの歳月の間に、ヘーゲルはくりかえし大学で論理学の講義をしてきていたんです。ヘーゲルは、シミのついた同じ話を繰り返すのではなく、その都度に新しい事例や問題点を、くり返し推敲に推敲を重ねていたんですね。だから私たちもそうした歴史的な探究の過程としてヘーゲルの諸作品を見なければならないということです。
だいたい、第一章概念ですが、『大論理学』では34ページをついやして概念・普遍・特殊・個別を個別に論じています。ところが同じ該当する部分が『小論理学』では8ページ、「1831論理学講義」では4ページのみといったことですから、それ以前の論述をまとめて簡潔に整理しちゃっているんですね。それらの特徴を見て、ヘーゲルが言おうとしているのは同じことですが、そこでどのように言っているのか、その特徴にせまるようにする。それによりヘーゲルが言いたい点が見えてくるということです。
4、さらにその後、第三巻『概念論』に焦点を当てた一つの本を見つけました。
『ヘーゲル大論理学 概念論の研究』(大月書店 1991年5月刊行)です。その巻頭の序論なんですが。
鰺坂真氏が書いているんですが、ヘーゲルの「区分」に対応する部分を解説してくれていました。
私などは、前々からこの『大論理学の研究』全3巻というのは、『大論理学』を読むのにその難解な部分について理解の参考にしようと、『見田石介ヘーゲル大論理学研究』(大月書店)を用意していたんです。しかし、解説によると見田石介氏は1975年8月に死去されたんです。第二巻本質論を学習会で報告していたところのことだそうで。その後、その学習グループの13人の人たちが、1991年5月に第三巻の「概念論」の部分についても、続編としてまとめられたんだそうです。これは現代の日本の哲学者たちによる『大論理学』研究についての、貴重な成果をしめすものとして読みました。
とにかく、これらの補助も参考にして、私など素人でも難攻不落の『大論理学』について、その頂上まで登ってゆくこと。そのための案内図が、一つのガイドブックとして、提供されているということです。
二、私などが『大論理学』を学習していて思うことですが、今は、ラフスケッチをつかむことでしかないということです。細部にわたって把握することは難しいということです。
なにしろヘーゲルが24年もの歳月をかけて積み重ねてきた事柄ですから、個々には大事な問題がたくさんあると思うんです。『小論理学』の補遺などは、積み重ねを示しています。そうした労作を私などの哲学に素人の農夫が、炎天下の草刈りの間に、その限られた短期間の間に、それにの問題の全体的な成果をつかんで、検討するなどということは、おこがましいことで、やはり無理があるとおもうんです。
後日、機会を見て個々の各論にも踏み込めるように、今の時点では課題として、そこにある諸問題を確認しておくしかないと思うんです。
今回の場合、ここから探究すべき諸問題を列挙しておくとすると。
一つ、本質論から概念論への移行は、本質の相関関係の必然関係から概念の自由への問題であるとされていること。ここにはスピノザの実体論が必然性をとらえていたことに対する評価とともに、自由にまで展開できなかったスピノザに対するヘーゲルの批判があると思います。
二つ、ここでの自由と必然との関係の問題ですが。
エンゲルスが『反デューリング論』で「ヘーゲルは、自由と必然性の関係についてはじめて正しく述べた人である」(第1篇11道徳と法、自由と必然)と述べていますが、それは『大論理学』『小論理学』のこの箇所で展開された問題だろうと思います。この自由と必然の問題というのは、人間の主体的な努力、自由を開くという大切な大事なテーマですから、あらためてこの問題について、よく検討しておく必要があるんじゃないかと思います。
三つ、ここにはカントについて二つの問題点が指摘されていると思います。カントは理性の認識能力を検討していますが、それは功績ですが、1つの問題は主観的な概念は「物自体」を認識できるのかという点です。不可知論、懐疑主義の問題です。カントは否定した。もう一つそのことは、カントはアリストテレス以来の形式論理学を批判し切れずに、その論理学が原理として思考形式の問題にとどまり、内容まで進まなかったと指摘されている問題です。人は世界を認識できるのか、この日常的には当たり前の認識なんですが、カントはそこを疑って抜け出せなかったとのヘーゲルの批判です。ヘーゲルは「概念一般について」で、そもそも批判とはどのようにあるべきか、との点までも指摘しています。
四つ、マルクスの『資本論』ですが、その第一章「商品」ですが、
ヘーゲルの提起している問題がヒントにも刺激にもなっていること。たとえば、何から始めるべきかとの問題、概念としての商品と商品価値の二重性、労働の二面性の問題、価値形態-本質とその現象形態。
マルクスにとって、その基本には、ヘーゲルの概念弁証法の考え方をつくりかえた、唯物弁証法の考え方があること。
これはマルクスが『資本論』の「あとがき〔第二版ㇸの〕」(1873年1月24日)で、『経済学批判』の唯物論的基礎とも関連して、弁証法のヘーゲル的形態との違いを明らかにしていること。これは先の共産党創立99周年講演で、志位委員長が紹介していましたが。
レーニンが『哲学ノート』で、『資本論』の第一章を理解するには、このヘーゲルの『論理学』の学習がが大事になっていると指摘していましたが、それはここの点だったんですね。
三、もう一つ、この第一篇「主観性」の第二章「判断」を考える上で、
エンゲルスの『自然の弁証法』の「判断の分類について」が参考になると思うんです。全集20巻・P531にあります。私などは、まだ中身を紹介できる力は無いんですが、文献紹介だけはしておきます。
この『大論理学』の学習ですが、
私などには、いまは大まかにであっても、第三篇「理念」の終わりまで、行くことが大事なんです。
こうして山を登ってくる途中には、いくつも、いくつもの検討すべき大事なテーマが出てきます。そこに大事な論点があるのはわかるんですが、各論を一つ一つ探るわけにはゆきません。仕方ありません。細部にこだわりすぎると、終わりまでたどり着けなくなりますから。だいたい認識というのは螺旋的にすすむといわれていますから、いつか次の時に学習するときには、個別の問題探究をするようにしたいと思います。
今後についてですが、
あと少し、第一章のA普遍-B特殊-C個別を学習するようにして、
そして、第二章判断と、第三章推理を駆け足で学習するようにして。
次回は、第二篇の「客観性」へすすみたいと思います。
