秋月龍みんの『誤解された仏教』(講談社学術文庫)を読んだ。
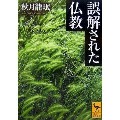
秋月氏の本を読むのはこれが初めてだ。
とかく本邦においては釈尊の仏教とは著しく異なる仏教に変わり果てている、というのは、夙に云われているところなので、軽い読みものとして買ってみたのだ。前半は軽い読みものだったが、後半はそれなりに仏教用語もちりばめられており、なかなか楽しめた。
簡単にいうと、釈尊が始めた原始の仏教は、輪廻を解脱し、縁起の法をあらわし、無我の我を悟ったものである。よって、仏教は無神・無霊魂の宗教である、ということらしい。したがって、水子供養だの除霊だのはいうに及ばず、盆や葬式だって本来の仏教とはなんら関係がない、となるのである。
このあたりは、まぁよく聞く話なので、別段新しくもなかったが、秋月氏の誤解された仏教への批判は非常におもしろかった。ひろさちやや梅原猛に対する批判も楽しく読めた。
しかし、気になるのは、東アジアにおいて先祖崇拝と結合し、日本においてアニミズムと習合した仏教を完全に否定しきっているところだ。宮崎哲弥のようなラディカル・ブッディストを標榜する人なら、かかる主張も受け入れることができるであろうが、一般的な日本人にとって、このような原始仏教を受け入れるのは、頭で分かってもなかなか感覚的には受容できないのではないか、とかなんとか思う。
秋月氏本人は、本著のなかでも述べているとおり、葬式に一切出席しないというほどの厳格かつ敬虔な仏教徒振りだが、ごく一般的な社会人にとってこれを真似するのはほとんど不可能に近いであろう(それにしても秋月氏は、その他の戒もすべて守っているのであろうか)。
おもしろかったのは、釈尊が悟ったのは、決して上座部派がいうように縁起の法ではなかったということだ。悟りというのは、分別知によって理解するものではなく、あくまで宗教的体験、無分別知による体験、プラジュニャーなのである。釈尊は縁起の法を悟ったのではなく、悟りという宗教的体験を伝えるために、縁起の法を用いたのである。このあたりは納得できる。
「心性本静浄」とか「円生成実」とか「妙有」とかそういう言葉もなかなかおもしろい。
※(もっとも、こんなことを書くとアレかもしれないが、個人的には、鯨統一郎の『邪馬台国はどこですか』(創元推理文庫)にみられるように、釈尊は悟ってなどいなかったという、暴論(?)にかなり衝撃を受けており、ホントのところはこんなかもな、という邪推をしたりしている)。
基本的に、原始仏教こそが仏教であり、ナーガールジュナ(龍樹)、チャンドラキールティ(月称)と続く、中観帰謬論証派こそが仏教の本流であるという、宮崎哲弥などの主張は正しいと思う。如来蔵思想(タターガタ・ガルバ)、または無著、世親による唯識仏教(アーラヤ識をたてることによる疑似主体の復権)、密教(バラモン的色彩の強い梵我一如等の神秘的思想)などが、そもそもの釈尊の教えとかなり隔たったものであることは、それとなく理解した。

ナーガールジュナ
そして、ナーガールジュナの思想などについては、本当にほーんのちょこっと齧っただけに過ぎないが、非常に高度な思想だと思うし、読んでいてユニークで魅力溢れる思想だと思う。だから、僕は結構仏教が好きなのだが、だからといって、日本に生まれて日本に育った以上、なかなかこの神仏習合した仏教観、宗教観から脱することは困難である。
ここから先は、暴論なのだが、原始仏教がどのようなものであったか、原始キリスト教がどのようなものであったか。このあたりを探るのは知的な営みとしては多分に興味があるが、信仰の対象云々となるとまったくもって難しいと思う。
宮崎哲也がかつて文春紙上において、仏教は輪廻を否定する。したがってチベット仏教ゲルク派における活仏とは政治上の産物に過ぎず、宗教上の意味はないと述べた。ゲルク派の創始者であるツォンカパ自身が、中観帰謬論証派のチャンドラキールティをよりどころとしている以上まったくもって矛盾することを指摘したところ、チベット仏教学者福田洋一から批判があった。
僕は両者の立論をみて、宮崎氏のいっていることに間違いはないと思ったけれども、しかし、一方で秋月氏のいうとおり仏教は分別知(ヴィジュニャーナ)によって理解するものではなく、無分別智(プラジュニャー)いから、己の信仰しているものを根底から覆されることに強い抵抗感を覚えることは理解できなくもない。チベットの僧侶に活仏否定論をぶてば、どういうことになるかは容易に想像できる。
秋月氏は、本著のなかで日本風の神道、アニミズムを幼稚な宗教観として、世界宗教に比して一段も二段も低く取り扱っている。
しかし、上述のとおり、信仰としての宗教と、思想としての緻密さとは、微妙な関係にあると思う。
批判を恐れずに云えば、はっきりいって、日本に生まれて日本育った場合、本当の意味でのキリスト教徒や仏教徒になるのは無理なんじゃなかろうかとずっと思っていた。日本に生れて日本に育った以上(「東京生まれ、ヒップホップ育ち」とかではない以上)、はっきりいって日本的思想の軛から逃れることはそもそも不可能なのではなかろうか(ちょっと筆が滑りすぎたかも)。もっといえば、偉そうに世界宗教などといったって、あくまで机上の空論に過ぎず、結局は土地土地の習俗や土俗宗教を吸収・消化せずには広まりえないのであるから、実際に世界の大半の人々が進行しているのは、純粋理論的な世界宗教ではないのじゃなかろうか。
しかし、「誤解された仏教」は結構ためになった。
八正道を単純化すると「戒」(シーラ)「定」(ジーラ)「慧」(パンニャー)となり、この三学を極めるのが仏弟子のみちであることや、日本仏教の代表である、浄土真宗、禅宗のいずれもが無我の我をめざすものであり、方法論こそ違え、目指すところはいっしょであること(さらにいえばキリスト教も。ホントか?)
それ自体正しいかどうかという点は留保して、機能主義的に定義づけると、宗教って云うのは、病んでいる人のための処方箋である。
とすれば、宗教理論的に正しくない水子供養というものがあったとして、それによってなにがしか救われる人がいるのであれば、存在意義というものはあるのではないかという考え方も可能である。
京極夏彦氏の対談集『妖怪大談義』で知ったのだが、水子供養というのは、江戸時代に祐天上人(ゆうてんしょうにん)いわき四倉出身(寛永十四(1637)年~享保三(1718)年)が始めたそうである。祐天上人は、祐天寺の地名の元となった僧侶で、増上寺の大僧正にまで上りつめた人物である。京極氏によれば、祐天上人は、本来仏教が除霊・供養のようなことをするものでにないことは百も承知であったが、水子供養をすることによって子供を堕ろした女の罪の意識がはれるのであれば、と思い始めたとか(もっとも、この点については、日本人の宗教観として重要な要素を孕んでいる。日本は世界希に見る中絶天国であるが、それは現代に始まったことではないのだ)。
とにかく、最終的に悩める衆生を救うということを第一義に考えれば、この水子供養というものは、一定の社会的機能も有しているのであり、原始仏教と違うから有無をいわさず切り捨てることができるかというと、そう単純なものでないような気もする。もっとも京極氏は、人を救うための送致であった水子供養が、現在は人を苦しめるためのもの商業的なものに変化していることを強く批判していたが、これにはハゲドウである。
ただ、秋月氏について疑問に思ったのは、「仏教は、キリスト教のように人間の苦しみ(死とか病気とか貧しさとかそういうの)を神に対する原罪というように設定せず、自らおかした業(ごう=カルマ)の報いであるとした。現在を正しく生きれば、未来は救われる」としている点である。
秋月氏が本著の中で、禅とは常に「即今(いま)・此処(ここ)・自己(じこ)」を問題とするものであり、そこには時間の流れ、三界を流れる自己は存在しないといっていることと矛盾しないのかがわからない。自己なる主体が存在せず、過去・現在・未来がないのであれば、この立論はそれこそ誤解を招きやすいのではないだろうか。人が生老病死に悩まされるのは、偏に、十二縁起の法理に基づくものであり、
無明→行→識→名色→六処→触→受→愛→取→有→生→老死
という因果の流れに基づくものである。
一切は空であるとさとり、縁起のながれを絶てば、その瞬間救われる(ブッダとなれる)のであるから、ここで、現在とか未来とかいちいち言う必要はないのではなかろうか。間違ってるかな。
あと最後に、
「摩訶般若六波羅蜜多!」と叫ぶのはちょっとどうかと思った。いや、マジで。
六輝=友引 九星=二黒土星 中段十二直=満 二十八宿=危 旧暦九月三十日
