
|
|
|
テーマ:司法試験・法科大学院(2199)
カテゴリ:刑事訴訟法の教材
松尾浩也『刑事訴訟法 上』[新版](弘文堂,1999)360頁
松尾浩也『刑事訴訟法 下』[新版補正第二版](弘文堂,1999) 400頁 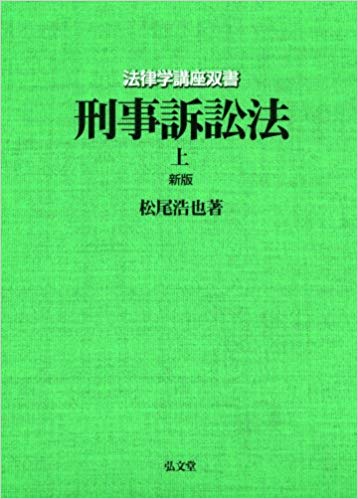  東京大学名誉教授の著者による体系書。 著者は,第22代東京大学総長を務めた刑事法の大家である平野龍一博士の高弟でしたが,惜しまれながら,2017年12月に鬼籍に入りました。 平成28年改正には対応していません。 本書は,刑事法学の第一人者であり,かつ,日本法学界の重鎮である著者が著した刑事訴訟法の体系書です。 著者は,「精密司法」という言葉の考案者であり,主に刑事訴訟法関連の業績で有名ですが,近年の刑法改正においても指導的役割を果たしており,正に刑事法学の第一人者というに相応しい人物です。 そのような著者が著した本書は,多少古くなってしまってはいるものの,司法試験の受験対策においては,今でもなお最も信頼のおける参考書の1つだと思います。 上巻には,捜査,公訴の提起,公判の手続などの内容が,下巻には,証拠法,公判の裁判,上訴,非常救済手続,略式手続,裁判の執行などの内容が収載されています。 なお,本書は2冊とも1999年(平成11年)に出版されていますが,上巻については,1998年(平成10年)から2004年(平成16年)にかけて行われた法令の改正などに対応する補遺が,下巻については,2000年(平成12年)以降の法令の改正および重要な新判例に対応する補遺が,弘文堂ホームページでダウンロードできるようになっています。 ここでちょっと脱線しますが,先日, 「松尾って誰だよwwそんなに有名な人なのかよ?」 と話している司法試験受験生がいると耳にしました。 これには,ジェネレーションギャップというか,正直,驚きました。 たしかに,教材の著者や各科目の大家と呼ばれるような法律家の名前は,受験勉強に臨むうえで覚える必要はないのかもしれませんし,覚えなくても試験には合格できるのかもしれません。 もしかしたら,そもそも私が知らないだけで,もうすでに,憲法の芦部,行政法の塩野,民法の我妻,商法の鈴木竹雄,民事訴訟法の新堂,刑法の団藤といった法律家の名前を知らない受験生も少なからずいるのかもしれません。 若い受験生から見たら,私は(まだ30代ですけれども)年齢的にいわゆる“ベテ”と呼ばれる受験生でしょうが,それでも,同じ司法試験受験生の多くが上に挙げたような法律家の名前をほとんど知らない時代が来ることを想像すると,何だか少し淋しい気がします。 次回も,刑事訴訟法の教材を紹介します。 それでは。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[刑事訴訟法の教材] カテゴリの最新記事
はじめまして。
基本書を検索していて、たまたま、むらきぃさんのブログに行きつき、参考にさせて頂いております。 私は今から20年近く前にサラリーマンを辞めて、司法試験に挑戦したものの、夢を果たせず、法科大学院に進学することなく2006年の旧司法試験論文式試験を最後に撤退しました。 私自身は伊藤塾の入門本科生でしたので、予備校本がメインの学習をしており、基本書はごく限られた本しか買わなかったのですが、それでも憲法の芦部先生や、民法の我妻先生などのお名前を知らない受験生がいるとは、私も隔世の感を抱きます。 最近、在宅勤務で時間ができたこともあり、趣味で法律の再学習を始めました。我妻先生の「民法案内1 私法の道しるべ」(勁草書房)を久しぶりに読んで、「私法の学び方」「私法の基本原理」「私法の解釈」等を学びなおし、法律学習を楽しんでいます。 これからもブログの更新、楽しみにしております。 試験勉強、頑張ってください! (2020.06.23 09:54:06)
もきちさんへ
はじめまして。 コメント,ありがとうございます。 もきちさんは旧司法試験の短答式試験合格者なのですね。 恐れ入ります。 私は,何事も経験が大事だと思い,法科大学院へ進学する前に1度だけ旧司法試験を受験したことがあります。 けれど,受験勉強を全くせずに臨んだ記念受験だったので,右も左も分からないままあっと言う間に3時間30分の時間だけが過ぎ去っていったのを今でもよく憶えています。 同時に,私の事務処理能力では,旧司法試験は短答式試験すら合格することはできないだろうと痛感した次第です。 現在,大学在学中に予備試験および司法試験に合格するような優秀な学生の中には,自分の使用した基本書の著者ぐらいしか学者の名前を知らない方も実際にいるのかもしれません。 それどころか,予備校中心の受験勉強を経て大学在学中に短期合格を果たす受験生には,自分の受けた司法試験の考査委員が誰だったのかすら知らない方もいるのではないでしょうか。 旧司法試験と比べると,現行の司法試験では判例重視の傾向がより強まっているので,主要な学説の提唱者や支持者が誰なのかを知る必要がなくなってきているのも,受験生の学者離れの1つの要因ではないかと考えられます。 私も,とりわけ学者・研究者に明るくなりたかったわけではないのですが,法科大学院では数多くの論文,概説書,注釈書などを読まざるを得なかったので,その著者・編者である学者や研究者についても自然と詳しくなってしまいました。 けれど,本音を言えば,こんなに詳しくなる前に合格したかったです。 最後に余談になりますが,今の若い受験生は,もきちさんが挙げた我妻榮『民法案内1 私法の道しるべ』や『民法1~3』(通称ダットサン)がかつては一粒社から出版されていたことは,おそらく知らないのでしょうね。 (2020.06.23 23:54:59)
むらきぃさんへ
返信ありがとうございます。 一粒社のダットサン民法は、学部生時代の基本書でした。とはいえ、当時の私には高度で難しく、全然使いこなせませんでした。なので、法学部生にも拘わらず、民法は総則・物権・債権総論どまりで、単位認定が厳しい先生だった債権各論は必修科目でなかったこともあり、受講すらしませんでした。今のように読者本位の親切な基本書や予備校本に囲まれている学生さんたちをうらやましく思います。 (2020.06.24 06:05:38) |