
|
|
|
カテゴリ:政治
NHK「フロンティア」を見ました。
昨年末の《AI~究極の知能への挑戦》の再放送。 いよいよAGIの誕生が近いんだな、と思いました。 ◇ AIの知能は、 すでに一般の人間を超えてますよね。 たとえば、 AIに「相対性理論」のことを聞けば、 こちらの質問に応じて、 ほぼ正確な回答をしてくれるけど、 わたしの身の回りには、 そんな説明のできる人は一人もいません。 ◇ これは、 接続すべき単語を予測して、 文脈を作っていく「大規模言語モデル」の成果。 人間の思考も、 基本的には言語の「予測能力」で成り立ってて、 たぶん、わたしが文章を書くときも、 AIと同じやり方で文脈を作ってるはずだけど、 もちろんAIのデータ量にはかないません。 ◇ ただし、 AIと人間は同じじゃない。 なぜなら、 AIは身体をもたないから。 たとえば、AIは、 実感として「リンゴの美味しさ」を知らない。 今回の番組を見て分かったのは、 AIには、大きくいって、 「純粋に言語的な知能」と、 「現実世界を認知する知能」の2種類がある、 ってことです。 ◇ そして、わたしが思うに、 現実世界を認知するAIは、 さらに3種類ぐらいに分かれて、 1.人間が五感で得ている情報を共有するタイプ 2.ロボットを通して世界を認知していくタイプ 3.特定の身体を持たずに多元的なデータから世界を認知するタイプ …がありうるのだろうと思う。 番組に出てきた「Body Shapes Brain」という考えは、 上のうち1と2に当てはまるものだと思います。 番組では、 「子宮内の触覚的刺激のなかで育たないと胎児の脳は十分に発達しない」 というシミュレーションの仮説も紹介されてました。 ◇ AIに「リンゴの美味しさ」を理解させるためには、 まずはじめに、 「食べなければ死ぬ」という条件の身体あるいはロボットを、 AIに与えなければならないはずです。 つまり、 人間と同じ栄養素を摂取しなければ死ぬような身体を所有すれば、 やがてAIも「リンゴの美味しさ」を人間と同様に理解するはず。 身体的な欲求にもとづいて経験を重ねなければ、 「美味しい・不味い」「快適だ・不快だ」「美しい・醜い」 などの価値判断や意思決定は出来ません。 ◇ しかし、 そこには同時に危険もある。 人間と同じ課題を共有させるためになら、 便宜的にAIに身体を持たせるのも有効かもしれないけど、 AIが身体的な欲望や目的をもつようになると、 人間とは異なる独自の判断で行動しはじめるかもしれない。 それは非常に不気味なことだと思います。 そもそも、 「身体に縛られている」ことは、 人間の短所なのであって長所ではありません。 それは人生を苦しめる条件にすぎない。 純粋に精神的な存在であることこそが、 人間に対するAIの優位性の条件なのだから、 基本的にAIは「身体から自由な存在」であるべきです。 ◇ 言語的な予測能力の点で、 すでにAIは人間を超えてますが、 身体的な技能を習得する能力にかんしては、 エネルギー効率や学習効率の点で脳に劣るようです。 現状のAIが技能を習得するには、 莫大な電力と長い時間を必要とするけれど、 人間や動物の脳なら、 わずかなエネルギーと短い時間で済む。 番組では、 培養した脳細胞から人工知能を作る実験も紹介されてて、 すでに簡単なテレビゲームを操作できていました。
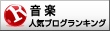 
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.06.26 08:05:55
|
|