
|
|
|
カテゴリ:JINさんの農園
「関東大震災慰霊塔」の前にあった横須賀市の雨水マンホールのカラー蓋。
「2020年浦賀奉行所開設300周年」記念の雨水マンホール蓋。  その先にあったのが「浦賀の渡し」。  「浦賀の渡し」。 浦賀の渡船(うらがのわたしぶね)とは、神奈川県横須賀市浦賀で運行されている渡し船。 浦賀の町で古くから運航しており、ポンポン船の愛称で親しまれている。 現在は繊維強化プラスチックによる装飾で御座船風に仕立てられた愛宕丸(あたごまる、 全長9.5メートル、総トン数4.8トン、1998年就航)による運用だが、それ以前は普通の 動力船であった。 水上区間であるが横須賀市の市道2073号線を構成。東渡船場(東浦賀賀2-19-10先)と西渡船場 (西浦賀賀1-2-19先)を3分で結ぶ。横須賀市唯一の市営交通事業であるあったが、2022年 (令和4年)4月に民間に事業譲渡され、市の事業としては役目を終えたのだと。  待合室。  ここが「西渡船場」。  「東渡船場」に停泊中の「愛宕丸」をズームして。  「乗船料」案内。  「【乗船料】料金は船内でお支払いください。 ・大人 400円(横須賀市民200円) ・小・中学生 200円(横須賀市民100円) ・未就学者 大人1名につき1名まで無料 ・ワンデイパス大人 600円 ・ワンデイパス小・中学生 300円 ・自転車および大きな荷物 50円 渡船場 渡船の歴史は古く、享保18年(1733)の「東浦賀明細帳」 には、渡船を修復する際、周辺の 村も東西浦賀村と応分の協力をすることとあり、操業が確認されています。 当時の船頭の生活は、東西浦賀村の一軒あたり米六合で支えられていました。 平成10年8月に就航した現在の「愛宕丸」は御座船風のデザインとなっています。 この航路は「浦賀海道」と名付けられ、横須賀市道2073号となっており、東西浦賀を結ぶ渡船は、 シンボルの一つです。 浦賀行政センター市民協働事業・浦賀深訪くらぶ」 「ご乗船の方はこのボタンを押して下さい ➡️ ●」と。  この時は、対岸の東渡船場に渡し船「愛宕丸」が停泊していたのであった。  「渡し船 就航中」と。  渡し船の乗船は次回とし、さらに入江に向かって進む。  左手に見えたのが「西叶神社」の一の鳥居、二の鳥居、社殿が見えた。  遊歩道は赤レンガと灰色レンガが全面に敷かれ、波の模様に。  再び約10km先の房総半島の山々を。  そして前方に日本最古のレンガ造りドック・「浦賀ドック」の「ドックゲート」が現れた。  そして対岸の「渡船」が動き出したことに気がついた。 「ポンポン船」の愛称で親しまれ、浦賀のシンボルになっている渡船は、港に隔てられた 東西の浦賀の町を行き来する人にとって、大切な交通手段であると。 この渡し舟は、浦賀に奉行所が設置されて間もない享保10年(1725年)ごろから記録に 登場しているとのこと。 現在も時刻表は無く、渡船が対岸にいるときは、呼び出しボタンを押すと、すぐに来て くれるのだ。  「ポンポン船」の愛称で親しまれている「愛宕丸」。  ズームして。お客さんは1名のみ。  そして日本最古のレンガ造りドック・「浦賀ドック」👈️リンク の「ドックゲート」に 近づいて。 ドック内の船を外洋に出す時は、この中が空洞の「ドックゲート」が海側に倒れ込み、空洞内部に 海水を入れ込みながらドック底部で水平となるのだと。  浦賀ドックの敷地内には大型テントが建設中であった。 ネットで調べてみると、 「2024年4月27日(土)~6月23日(日)の期間、横須賀市の浦賀ドックにて、 「ポップサーカス」👈️リンク が開催されます!」と。  「POP circus WORLD TOP PERFORMERS」と。  再び横須賀市雨水マンホール蓋。 「観音崎灯台」、「黒船」を背景に「ペリー提督」を描いた雨水用の蓋。  こちらは市の花ハマユウと中央に市章。 下部に「車道」と「あめ」の文字が。  「昭和五十二年市制施行七十周年記念 横須賀風物百選 浦賀造船所 浦賀湾を囲むこの施設は、住友重機械工場株式会社追浜造船所浦賀工場です。 創業以来、浦賀船渠株式会社、浦賀重工業株式会社、更には現在の社名と変わりましたが、広く 「浦賀ドック」の愛称で呼ばれてきました。 この造船所は、明治二十九年、当時農商務大臣であった榎本武揚などの提唱により、陸軍要さい 砲兵幹部練習所の敷地及び民有地を取得して設立準備を進め、翌三十年六月二十一日の会社設立 登記をもって発足したものです。資本金は百万円でした。 そのころの日本は、日清戦争などの影響もあって、外国から多くの艦船を買い入れ、世界的な 海運国に発展しようとしていました。一方造船界は、技 術面や設備面で大きく立ち遅れて いました。その遅れを取り戻すため、外国人技師を雇い入れて国内各地に次々と造船所を 造っていきました。この造船所もその なかの一つで、ドイツ人技師ボーケルを月給 約百五十円で雇いドックを築きました。 明治三十五年十月十五日、フィリピンの沿岸警備用砲艦ロンブロン号(350排水トン)を この浦賀造船所で建造した艦船は、戦前・戦後を通じ約一千隻にのぼります。現在もなお進水させました。創業以来手がけてきた船は、いずれも 国内の企業から受注した工事用運搬船の たぐいばかりでしたが、十四隻目に初めて外国から受注した本格派の艦船を世に送り出しました 技術革新の騎手として、新しい船を造り続け、造船の浦賀の象徴として、今もなお地元市民に 基盤を置いています。」 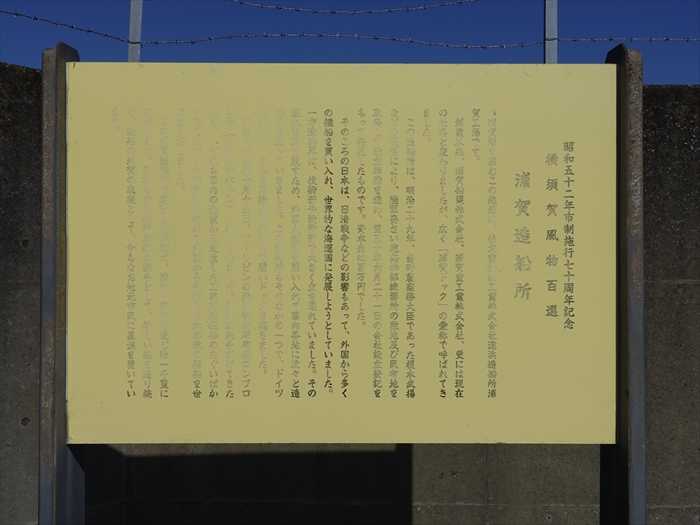 浦賀駅前通り商店街歩道に埋め込まれた「咸臨丸」パネル。  「歌川広重「千繪の海 相州浦賀」初版1833年 天保4年」。  この水路は?昔は浦賀湾に流れ込む小川があったのであろう。  旧浦賀警察署向かい 御菓子司 太平堂の隣にあったのが浦賀町「道路元標」。 裏側には「神奈川県」って書いてあるらしい。 「1919年(大正8年)の旧道路法で、市町村に1基ずつ設置することとされていました。 1922年(大正11年)、形状、規格、材料など細目が規定された内務省令が発布され、 1万2000以上あった市町村の自治体中心部に設置され始めました。設置場所は府県知事が 指定し、ほとんどは市町村役場の前か主要道路の交叉点に設置されました。 浦賀の場合、浦賀町役場のすぐ近くってコトでしょう。 大正時代に設置された道路元標の大きさは、縦横25cm、高さ約63cmの直方体で、頂部が弧を 描くように丸く削られ、材質は花崗岩が多いです。地方によって若干の差異があり、 コンクリート製作もあります。 「○○村道路元標」、「○○町道路元標」のように市町村名を刻み、背面に設置年が彫られて いる場合ことが多いです。 1952年(昭和27年)施行の新たな道路法によって、新しく設置されることがなくなり、無用の ものとなったため開発工事に合わせて撤去されることが多くなりました。」とネットから。 横須賀市浦賀4丁目5−1。  裏側には「神奈川県」と。  そして「久里浜駅」行きの京急バス。 次回はこれも利用しようと。  そして浦賀駅の少し手前の場所に、小さな案内看板が建っていた。 「屯営跡の碑」👈️リンク と記されている看板を再び。  明治8年(1875年)に、この場所に水兵の基礎教育機関として「浦賀水兵屯集所」が設置され、 明治18年(1885年)に「浦賀屯営」と改称され、多くの水兵を送り出した場所です。 この碑は住友重機械の敷地内にあって、残念ながら見学できなかったが、浦賀という街が 近代日本とともに歩んできた街という印象を、さらに強くしたのであった。 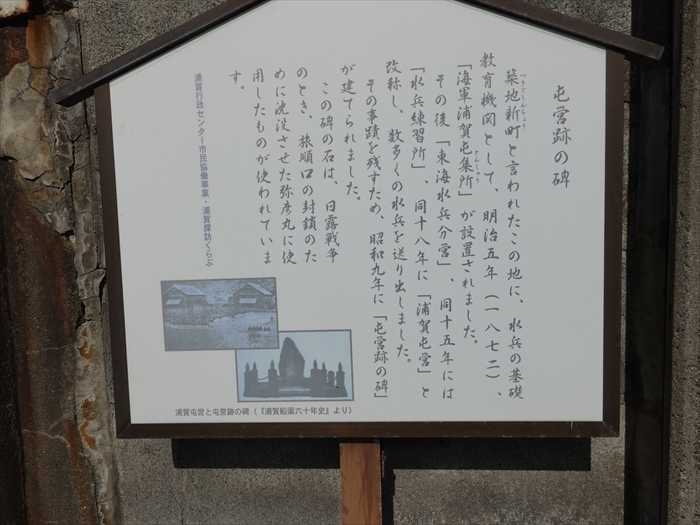 「浦賀屯営」と「屯営跡の碑」と。 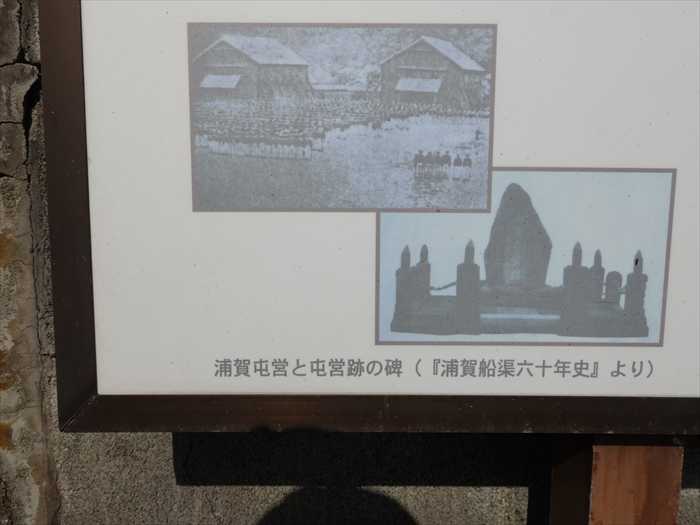 そしてこの日の朝に見た「浦賀歴史絵図」を再び。  そして京急・浦賀駅に到着。  京急・上大岡駅で下車し、駅ビル内で腹ごしらえ。  そして横浜市営地下鉄、小田急線を利用して帰宅したのであった。 この日の京急・浦賀駅からの散策ルートmap。  この日の歩数は30,000歩超えであった。  ・・・もどる・・・ ・・・END・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2024.05.26 16:24:21
コメント(0) | コメントを書く
[JINさんの農園] カテゴリの最新記事
|