
|
|
|
カテゴリ:夏目漱石
明治38年(1905年)12月14日に誕生したのが四女の愛子です。愛子の誕生に一役買ったのが漱石でした。漱石は、産婆の代わりに、鏡子の出産を手伝ったのでした。 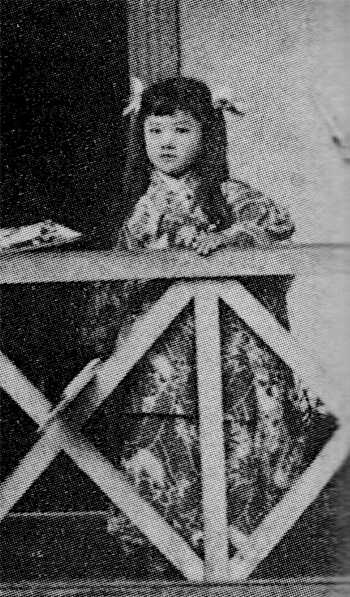 『漱石の思い出』には、「十二月が臨月ですが、私はいつもお産が重いほうなので、十四日の夜の三時ごろに、しきりに陣痛が起こって、いたみ出したのですが、今から始まって、いつもだと明日の正午ごろでなければ生まれまいと高をくくっていますので、まあまあこの時刻に人騒がせをするでもなかろうと我慢してますと、四時ごろになってはどうにも我慢ができません。そこで夏目にも起きてもらい、女中をお医者さんのところへ走らせて、いつもかかりつけの牛込の産婆へ電話をかけさせました。がだんだん痛みは激しくなる一方で、これではならないというので、誰でも構わん、付近の産婆を起こして連れてきてくれというわけで、また女中が走り出します。五時にもなるとどうやら生まれそうな気勢ですから、さあ困りました。もうあなた産まれそうですというので、夏目の手につかまってうんうんいってるうちに、とうとう産まれっちまいました。さあ、たいへんだと狼狽するのですが、私は当の産婦で動きもできず、夏目も取り上げ婆さんは始めてのことだから、どうしたらいいのかさっぱりわからない。ともかく悪い水が顔にかかるといけないということを私は聞かされていたことがあったので、ともかく脱脂綿で赤ん坊の顔をおさえておいてくださいと申します。よしきたとばかりに一ポンドの脱脂綿で夏目が上からおさえているのですが、それが海鼠のようにいっこう捕えどところがなく、ぷりぶり動くような動かないような、すこぶる要領を得ない動き方で気味の悪いたらない。そこへ牛込の産婆が飛びこんできて、第一私に酌邪を引かしちゃならないというのうで、着物を着させてねかせるやら、そら産湯をわかせというえらい騒ぎで、やっとのことで大役を明け渡したのですが、これには夏目も度胆をぬかれたようでした。(夏目鏡子 漱石の思い出 27生と死)」というわけだったのですが、漱石はこのことを『道草』に登場させています。 「産婆を呼ぼうか」 「ええ、早く」 職業柄産婆の宅には電話が掛っていたけれども、彼の家にそんな気の利いた設備のあろうはずはなかった。至急を要する場合が起るたびに、彼は何時でも掛りつけの近所の医者の所へ馳け付けるのを例にしていた。 初冬の暗い夜はまだ明け離れるのに大分だいぶ間があった。彼はその人とその人の門を敲く下女の迷惑を察した。しかし夜明まで安閑と待つ勇気がなかった。寝室の襖を開けて、次の間から茶の間を通って、下女部屋の入口まで来た彼は、すぐ召使の一人を急き立てて暗い夜の中へ追い遣った。 彼が細君の枕元へ帰って来た時、彼女の痛みはますます劇しくなった。彼の神経は一分ごとに門前で停まる車の響を待ち受けなければならないほどに緊張して来た。 産婆は容易に来なかった。細君の唸る声が絶間なく静かな夜の室を不安に攪き乱した。五分経つか経たないうちに、彼女は「もう生れます」と夫に宣告した。そうして今まで我慢に我慢を重ねてこらえて来たような叫び声を一度に揚げるとともに胎児を分娩した。 「しっかりしろ」 すぐ立って蒲団の裾の方に廻った健三は、どうしていいか分らなかった。その時例の洋燈(ランプ)は細長い火蓋の中で、死のように静かな光を薄暗く室内に投げた。健三の眼を落している辺りは、夜具の縞柄さえ判明はっきりしないぼんやりした陰で一面につつまれていた。 彼は狼狽した。けれども洋燈を移してそこを輝らすのは、男子の見るべからざるものをしいて見るような心持がして気が引けた。彼はやむをえず暗中に摸索した。彼の右手はたちまち一種異様の触覚をもって、今まで経験したことのない或ある物に触れた。そのある物は寒天のようにぷりぷりしていた。そうして輪廓からいっても恰好の判然しない何かの塊に過ぎなかった。彼は気味の悪い感じを彼の全身に伝えるこの塊を軽く指頭で撫でて見た。塊りは動きもしなければ泣きもしなかった。ただ撫でるたんびにぷりぷりした寒天のようなものが剥げ落ちるように思えた。もし強く抑えたり持ったりすれば、全体がきっと崩れてしまうに違ないと彼は考えた。彼は恐ろしくなって急に手を引込めた。 「しかしこのままにして放って置いたら、風邪を引くだろう、寒さでこごえてしまうだろう」 死んでいるか生きているかさえ弁別のつかない彼にもこういう懸念が湧いた。彼は忽ち出産の用意が戸棚の中に入れてあるといった細君の言葉を思い出した。そうしてすぐ自分の後部にある唐紙を開けた。彼はそこから多量の綿を引き摺り出した。脱脂綿という名さえ知らなかった彼は、それをむやみにちぎって、柔かい塊の上に載せた。(道草 80) 『道草』は、自伝的小説のため、周りにも影響を与えました。愛子がみんなの気持ちを代弁したこともあります。また、お菓子のありかを漱石に教えることもありました。 京都からかえりましてしばらくしてから、六月ごろからだったでありましょう。「朝日新聞」に「道草」を連載し始めました。これは主に私どもの千駄木時代に起こったちょっとした事件を題材に取りまして、それに自分の昔の記憶などを結びつけて書いた、いわば自叙伝小説とかいうものなのでしょう。この中に私はじめ親類のものなどが出て参ります。それにその前の「硝子戸の中」にも昔のことなどが出て来るので、自然矢来の兄さんなどにも差し障りのあることがあったのでしょう。いつぞや兄さんから、ああやって書くのもいいけれど、自分たちも子供が大きくなってるのだから、あんまり打ち明け話を書かれたりすると、子供の手前みっともないからとかいう、ちょとした抗議が、私まで出たことがありますので、そのことを申しまして、私なんぞは「猫」でもさんざん書かれてるからいいようなものの、あんまり家のことや人のことを書くのは感心しないとか何とか言ったものです。すると夏目は、何だ、お前たちそれで飯を食っているくせにと申しますので、これにはまったくそのとおりなので参ってしまいました。 この兄さんの話をどう聞きかじっていたのか、四番めの愛子というそのころ十か十一だった娘が、ある時夏目に申します。 「お父さんたら、伯父さんのことや人のことばかり書かないで、もう少し頭を働かせなさい」 夏目は笑いながら、 「このやつ、生意気なことをいう。そんなこというと、こんどはお前のことを書いてやるよ」などとからかっていましたが、「硝子戸の中」の一番終わりに焚火をしている子供たちのことなんか書きまして、「あら、いやーだ」と悲鳴を上げさせておりました。 この愛子がお父さん思いで、夏目がよくお菓子をつまんだりするので、お腹によくないと思いかくしておきますと、書斎で勉強をした後で一つ羊羹でもつまみたくなって出るのでしょう。戸棚をさがしてもありません。すると子供は目が早いので、私の隠しておいたところをちゃんと知っていて、気の毒だと思うのでしょう。お父さん、ここにあってよと出してやります。おおいい子だ。おまえはなかなか孝行者だなんかとにやにやしながら、お菓子をつまんで頬張っております。胃の悪いくせに、こんなことは平気な方でした。 娘の子でも、上の二人とは、娘の方で夏目の頭の悪い時の記憶などでか自然しっくりなずまない様子でしたが、下の二人とはよく両方で裸になって、角力をとって遊んだりからかったりしておりました。次の年に夏目が亡くなるのですが、よく二人とも生きてるうち角力なんかばっかりとっていないで、その暇に書画でもたくさん書いてもらうんだったになどと今でも言い言いしております。(夏目鏡子 漱石の思い出 56子供の教育) 愛子が物心がつく頃には、漱石をやり込めることもありました。『漱石の思い出』には、「これが四女の愛子で、女ばかりこれで四人です。この子が六つ七つになったころ、つくづく顔を眺めてはどう見てもわが子ながら不器量だなどと申しまして、『愛子さんはお父さんの子じゃない。お父さんが弁天橋の下で拾ってきたのだ』などと揶揄いますと、愛子も敗けてはいず、『あらいやだ。わたしが生まれた時に、自分じゃ脱脂綿でわたしをおさえていたくせに』とさもさも知ってるのにと言わぬばかりにあべこべに食ってかかります。『こいつつまらないことをいつの間に聞いているんだい』などと笑っていたことがよくありました。(27生と死)」と書かれています。 ※愛子は利発な性格で、みんなから名前の通りに愛されて育ちました。 津田青楓が愛子の肖像を描いたこともあります。この話はこちら 愛子は鎌倉の仲地家に嫁ぎました。先頃刊行された『定本 漱石全集』の月報には、愛子の『父漱石の霊に捧ぐ』が掲載されています。「三月三日が近づくと、父はいつも女の子たちに決まってお雛様を買ってくれた。普通の家では、お雛様などは皆母親が買ってくれるものだと思う。だが夏目家では、それが毎年父の仕事のひとつになっていた。父は着物の着流しに鳥打帽、手にはステッキという出立で、姉と私を連れて近くのおもちゃ屋に雛人形を買いに行く」というもので、愛子は他の兄弟姉妹とは異なり、漱石の底にある優しさを見抜いていたようです。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020.12.07 19:00:06
コメント(0) | コメントを書く
[夏目漱石] カテゴリの最新記事
|