
|
|
|
カテゴリ:正岡子規
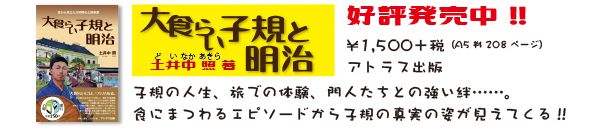 菜の花のさく頃里の餅赤し(明治26) 虫はみて一枝赤き李かな(明治26) 赤飯に春日さしたる祠かな(明治29) 飯赤く栗黄にあるじすこやか也(明治29) 旱雲西瓜を切れば眞赤也(明治29) 赤い實の一つこぼれて霜の橋(明治29) 冬枯や八百屋の店の赤冬瓜(明治29) 草枯るゝ賤が垣根や枸杞赤し(明治31) 苔の上にこぼれて赤しゆすらの実(明治33) ハンケチの赤く染みたるいちご哉(明治33) 赤き林檎青き林檎や卓の上(明治33) 子規は赤い色が好きでした。 明治32(1899)年5月10日発表の『赤』には「天然の色でもその中で最も必要なのは赤である。赤色のない天然の色はいかに美しくても活動することがない。山深く林茂ったところでは気が静まるばかりであるが、ここに赤い鳥居が一つあると気が動いてくる」とあります。また、明治34(1901)年3月20日発表の『くだもの』「くだものと色」には「くだものには大概美しい皮がかぶさっておる。覆盆子(いちご)、桑の実などはやや違う。その皮の色は多くは始め青い色であって熟するほど黄色かまたは赤色になる。中には紫色になるものもある。(西瓜の皮は始めから終りまで青い)普通のくだものの皮は赤なら赤黄なら黄と一色であるが、林檎に至っては一個の菓物の内に濃紅や淡紅や樺かばや黄や緑や種々な色があって、色彩の美を極めて居る。その皮をむいで見ると、肉の色はまた違うて来る」と、美味しさの後ろには「色彩の美」があり、「熟するほど黄色かまたは赤色」になることから、成熟の意味は赤く(または黄)なることであるといっているようにも思えます。 明治31(1898)年12月10日発表の『わが幼時の美感』では「四つ五つの子が隣の伯母さんに見せんとていと嬉しがる木履の鼻緒、唐縮緬の帯、いづれ赤ならざるはあらず。こころみにおもちゃ屋の前に立ちて赤のまじらぬ者は何ぞと見よ。白毛黒髪の馬のおもちゃにさえ赤き台の車はつけてあるべし」と、赤が子供たちのおもちゃに役使われていることを示し、「われが三つの時、母はわれをつれて十町ばかり隔りたる実家に行きしが、一夜はそこに宿らんとてやや寐入りし頃、ほうほうと呼びて外を通る声身に入しみて夢覚さめたり。(ほうほうとは火事の時に呼ぶ声なり)すは火事よとて起き出でて見るに火の手は未申に当りて盛んに燃えのぼれり。我家の方角なれば、気遣きづかわしとてわれを負ひながら急ぎ帰りしが、我が住む横町へ曲らんとする瞬間、思ひがけなくも猛烈なる火は我家を焼きつつありと見るや母は足すくみて一歩も動かず。その時背に負はれたるわれは、風に吹き捲まく焔の偉大なる美に浮かれて、バイバイ(提灯のこと)バイバイと躍り上りて喜びたり、と母は語りたまひき。あくまで惨酷なる猛火に対する美感は如何にありけんこの時以後再び感ずる能はず。年長じて後、イギリスの小説(リツトンのゴドルフインにやありけん)を読む。読みてまさに終らんとす、主人公志を世に得ず失望して故郷に帰る、故郷漸く近くして時、夜に入るふと彼方を望みて、丘の上に聳し宏壮なる我家の今や猛火に包まれんとするを見る、の一段に到りて、心臓は忽ち鼓動を高め、悲哀は胸に満ち、主人公の末路を憐れむと共に、母の昔話を思ひ出ださざるを得ざりき。しかれどもなほ細かに考ふれば、荒村の丘の上に、高き大きなる建物が火を吐きつつある光景は、いくばくかバイバイ的美を想ひ起さしむる者なきに非ず」と、幼児体験が心に赤を刻んだと書いています。  明治2年(1869)、正岡家は温泉郡湊町新町(現在の湊町四丁目一番地)、中ノ川沿いにある約180坪の屋敷に移ります。この家の近くには高浜虚子の生家である池内家、従兄半・三並良の歌原家、母の実家の大原家、河東碧梧桐の生家など、後の交友につながる人たちの家が並んでいました。 この年の12月5日、正岡家が全焼したのです。 その日は、官吏の藤野漸と八重の妹・十重の結婚式が行われた夜で、母親と子規は大原家に出掛けていました。その留守に、同居していた曾祖母の久と父が飲酒し、酔って火事を起こしてしまいました。火事の原因は、炬燵の上に置かれていた糀に火が着いたとも、七輪の火の不始末ともいわれていますが、二人が引き起こした火災であることに違いはありません。 八重は、突然の火事に驚き、子規をおぶって家に帰りましたが、すでに全焼していました。子規は、自宅の火事を不幸とも思わず笑っていたといい、回らぬ舌で「焼てた」「ヤテタ」と繰り返したといいます。暗闇を染める火事、焼けてしまった下駄の鼻緒、消防の提灯など、赤い色が子規の心に強く残ったのでした。 この夜、我が家には曾祖母と父と下女一人なりしが、曾祖母と父は酒を好み給うゆえ、熟眠し給い、下女もいぎたなく眠りいし折から、誤って火事を起こせしなり。母は我が家とも知り給わず。我が家の見ゆる角に来給いて、我が家と知り給うより大方ならず驚き給いしが、余は喜びて躍り狂い、提灯よ提灯よとて、笑い興せしとぞ。(筆まかせ 余) 升が三歳の時、大原がお客で私と二人で泊まりに往っておりましたら、火事じゃ火事じゃというので仲間が見てきましたら、大変大変正岡が火事じゃと言います。そこで升をおんぼして帰ってきますと、もう火事もおしまいになって、龍吐水も去ぬる。提灯がたくさん戻ってきますのを見て、升が大変に喜びました。(正岡八重 母堂の談話)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2018.03.26 07:01:30
コメント(0) | コメントを書く
[正岡子規] カテゴリの最新記事
|