
|
|
|
カテゴリ:正岡子規
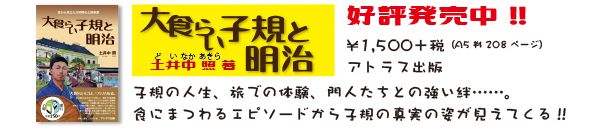 明治23(1890)年1月23日、冬期休暇を故郷で迎えた子規は、東京へと帰途につきました。松山の三津から神戸までの船旅を『上京紀行』として文章にしています。この旅は、子規にとって快適なものではありませんでした。海が荒れていたため、松山から多度津に着くまでに多くの時間がかかり、子規は船に酔ってしまいます。そして、泊まったところも芳しくありません。そうした不満が爆発したのが、これらの戯れ歌です。 松山の小町もあとになり平や きせんにのらん風に大伴 三津を出た時の歌。六歌仙のうち、小野小町、在原業平、喜撰法師、大友黒主が詠み込まれています。また小町は「古町」、喜撰は「汽船」、大伴は見つ(=三津)の枕詞で、これらの洒落も含んでいます。 松山をたつとすぐきつ三津か浜 いつ多度津へはつく都合かや この歌は削除されています。「たつ」「きつ」「いつ」「つく」と韻を踏んで、ラッパーのようです。 平穏と祈りしかひもあら海や 金比羅さまへあげし小間物 この歌は、船酔いの中で詠まれた歌です。「祈りし甲斐もあら」ずと「荒海」の洒落、金比羅への捧げものと嘔吐が「あげし」で繋がっています。 便たつね乗りて野暮流(のぼる)や丈鬼(じょうき)船 まゝ吐き出して泣いた正岡 こちらは、子規の本名「常規」が「つね乗り」、幼名の「升」が「野暮流」、ペンネームの「丈鬼(常規の音読み)」が「蒸気船」とかれられています。 紂王の飲む無道酒は池をなし 昼の牛肉はやしたるまま 紂王は殷朝第30代の王で、無道で暴虐な悪政を行なったとされています。「無道酒」は「葡萄酒」の洒落。「はやす」は「囃す」と「吐やす」の意味がかけられています。 三津よりは四十里足らぬ海上を にくさも二九し十八時間 「憎い」は「二九・十八」となっています。この日の昼、子規の食事は牛肉と葡萄酒でした。そのため「飯は山の如く、しかも葡萄酒のために淡紫にそみたり、昼くいし牛肉はそのままにて飯山を点綴す」という状態になりました。 さぬきなる海より深き多くみ屋は 巧な口で人をつるの間 多度津について汽船問屋「多組屋」に泊まった子規は、通された「鶴の間」の汚さに驚きます。海より深い「たくみ(たくらみ)」を抱く「多組屋」と汚い「鶴の間」は、巧みな弁で「人をつる」ことであてがわれたと嘆いています。 血にあらぬ小間物までも吐き出して 大損かけたと子規啼く 遅い船と汚い宿に泊まったことは、時間と金の損であることを嘆いています。血ならぬ腹のものまで吐き出して啼くホトトギスのように、子規も泣きたい気持ちになったことを詠んでいます 小間物をささげし甲斐もありがたや 金比羅丸と船も名のれり 今迄の書生の姿あら神や 俄に鼻を高くなしつつ ところが、多度津から神戸までの船は、金龍丸という大型船でした。この感謝を、金毘羅さんへ参拝したおかげだと考えた子規でした。 子規は、よほど気分が良かったのか、次のような洒落の詩も書いています。 床待の歎 いつか見そめし赤功(てがら) 三年このかた気る楓(かえで) 雲のふる日も通ひ筒 くれどなびかぬ深工(たくみ) 廊下静かに時は虹(にじ) それでも女郎はきて紅(くれない)  一月廿三日 人々にとどめらるる聞かず、とうどう故郷を出立して東京へと放立つ事になりぬ、この日は平穏丸という大阪商船会社にて最下等の舶なるよしなれど、思いたつ日に立たざればまた故障の出来るも知れずとて、松山停車場へと急ぎたり。停車場に「強風起らんとするの虞(おそれ)あり」との警報ありたれど、それらにもかまうことにはあらず、黒烟の中に松山城をは見すてたり。 松山の小町もあとになり平や きせんにのらん風に大伴 正午に三津へ下りしが、船は中々に来らず、新浜のいけ巣へも御暇乞に行き、塩揚に入り晩餐を喫し、久保多へ帰りたれど舟は猶見えず、 (抹消 かくてはいつ紳戸へつくやら覚束なしとて 松山をたつとすぐきつ三津か浜 いつ多度津へはつく都合かや 送りし人も皆帰りて独り問屋にて眠らんとする折から、汽船着港せり。飛びおきて時計を見れば十二時也。二時頃出帆せしが船足遅きこと甚しく、船が波を蹴たてるとはいえず、白い波は立つことなく、只波の輸ができるのみ。今治を経て新居浜につきし時は、はや翌廿四日正午なりき。午餐を喫し船は出帆するや否や、急に少々の風起りたり、この二三日は腹具合わるき故にや、また食事のしだちなりし故にや、船にゆられて心持のわるきこといはんかたなく、四時頃に至りて益甚だしかりしかば、余は独り帰念す。時は明治、舟は平穏と我は平気にて金比羅大明神、帰命頂礼、六根清浄、南無アーメンと祈りしが、遂にむかむかとするにたえかねて頭を窓外に出し、ゲロゲロゲロゲロとやっつけぬ。 平穏と祈りしかひもあら海や 金比羅さまへあげし小間物 便たづね乗りて野暮流(のぼる)や丈鬼(じょうき)船 まゝ吐き出して泣いた正岡 なお時々は胸のむかつくによりて、頭を角窓の外に出し、風にあたりながら、前に吐きし嘔吐をつくづくと拝見するに、飯は山の如く、しかも葡萄酒のために淡紫にそみたり、昼くいし牛肉はそのままにて飯山を点綴す。 紂王の飲む無道酒は池をなし 昼の牛肉はやしたるまま 午後六時多度津につきぬ、船は碇を下してより益ゆれ強く、胸のわるさは一倍せり。頭は再び窓外へ出で……しばし……ゲロゲロ……余はここより上らんと思ひいれども、取りちらしたる荷物を片づける能はず、折からボーイは余の室へ入り来れり「……ボーイ、そこの……ゲロゲロ……荷をしまってくれ……ゲロゲロ……その風呂敷へ一処に……ゲロゲロ……終に勇を鼓して端舟(はしけ)に乗りうつりぬ、小舟はようように蒸気船をはなれしかども、大波のためにゆりあげゆりおろされ、今にも翻らんと思わる。楫夫(かこ)も自由には舟を漕ぎ得ず、波のひまを窺って時々一こぎ、こぐ許り、ようよう阜頭の内に入り、桟橋より上りたり。余は明治二十年夏、遠州洋にてかなりの風に出あひしかとも、それでさえ吐きしことなし、我腹中の食物を出して魚の腹中に与えしは今度が始めて也。また三津より多度津まで十八時間を費せしことも今度が始めて也。 三津よりは四十里足らぬ海上を にくさも二九し十八時間 多度津の汽船問屋多組屋に上りぬ。人を待すること雲助同様なり(漱石の筆法を用ゆ)余を鶴の間とかいう処に導く。この間はきたなき、そうぞうしき間にて、からかみに下手な鶴がごてごてと書きあるには、一見して又またへどを催す程なりき。室をとりかえくれよというに、かにかくというて善き間へは入れず。腹だたしさ限りなし。 さぬきなる海より深き多くみ屋は 巧な口で人をつるの間 翌朝ここにて故郷の友人へ迭りし余の状文に曰く 拝啓仕候。一昨夜はわざわざ三津まで御送別被下奉萬謝候。平穏丸は夜中に三津へ着船、直ちに乗りくみ出帆仕候処、名詮自性とや申べき一時間二里の速力ということにて、内海中ても自慢の遅足なれば、その平穏なることは御推察被下度候。今度は始めより念ぎし故遅い船でも早く出た方が早く着神すべき見こみにて、商売人が商機を争う如き有様なりし処、一時間二里やっとというにはとんともう御気がつかれ、この上は少しでも食時なりと余計にもうけてやらんと愈商売気を出し、昨日正午新居浜にて可なりに食料品を腹中にしこみ候処、同港を発せしより多少の風浪ありて胸もちのわるきこと一方ならず。三時頃にとうとう窓外に小間物店をならべて海神に供し候うども、龍王の逆鱗なおやまず六時頃多度津へ着候。ボーイに片づけさせいる内帰りがけの置き土産に底を払うて残る小間物をみてくらと致し候。時間は損する食うた者は出す。問屋では金を使う。誠に誠に大損を致し候。御一笑可被下候。 血にあらぬ小間物までも吐き出して 大損かけたと子規啼く 手紙書き終りて後、直ちに汽車にて丸亀へ行き増田氏を訪う。この汽車は大きさ東海道の鉄道に等しく、車は新しき故にや。前者よりも却て奇麗也。乗客は下等さえも寥々として冷まし。しかし金比羅のお祭には一時にもうけることならん。正春氏は松山地方へ行きし留守にて、残るは大叔母さんと増田夫人也(夫人というものか何というものか知らねど、最早貴女の仲間入せられしと聞きてこの称号を与う)ここで御馳走にもなり面白き話を聞きつ語りつせり。叔母さんの話の中に『ここによしかねやという男があるが余程面白い男で、この間始めて内へも来たが、一寸煙草入れを出して筒をたたいて「づつうがするすると思へば皮色が違うとる、しかし心配することはない、ここにおじめがついておる」などとしゃれをいうたり、また内の家内中が先日一処に写した写真を見せたら、その時丁度かなめ(夫人の名〉がわきで蜜柑をたべておったが、よしかねやが要女の顔を見て「この写真の顔とあなたが蜜柑をくうておいでなさる顔とは顔が違う」じゃのいう男じゃ。この男はじゃぎ(あばた)があるが「私の若い時は種痘といふものはなし、ほんとに私が自分で鏡を見ると気の毒になる」じゃのいうて、えっぽど面白い男じゃがナ、******内の下女が先日いうことにゃ「おならがブーっとおっしゃった」ハ〜*****いつか土佐の人に小烏賊を出したら、せんごともにがぢりとおかみて、えっぽどおかしかッた』などということを聞きたり。余も相槌をうちて『あたしがいつか信州の岩岡という男にあった時その男が話すのに「僕は国にいる内は海の肴(=魚)は塩水にすんでいるから辛いものだと思うた」というたが、これは信州へ送る肴は皆塩づけにしであるから、そう思うたんじゃ』などと話しながら御馳走をつめこみ、暮あいの汽車にて多度津に帰りしが、店の者が「今夜はきんりょう丸が早く着きますから、これにおのりなさってはどうでございますか」という。余は川という字のついた詐りを善きと心得、むしゃうに有りがたがッている故、即川字号崇奔者故、金陵などとは名を聞いた許りでも小さそうだと、その速力を問えば早しという、さらば川いい船を思いきりてこの船に乗らんと思い直し(この夜遅く大和川丸がくる故、乗りくまんと思いいたりし也)室に入ればこんどは鶴の間にあらず、一番奥の二階半の間なり。暗さにこまりてはい上りし故、仮にこれを亀の間と名づく。茶など飲みつづけいける内に小厮(しょうし)来りて「金りょうはどうしましたか、まだ見えませぬが、その内参りますから、お炬燵でもこしらえさせますから、少しおあたりなして……」と置炬燵をしつらえくれたり、ここで有難いのはこれ許りだなどとつぶやきながら、炬燵へはいって枕をすけ、アアいい心持だと思ッたきり、舟を押す間もなくはや東京へ着きぬ、こんどは頼まれの書状が多い故、そのくばりかたに世話しく、車をはせてかけまわりいる内「旦那、船が参りました」とだしぬけに呼びさまされて残念、忽ち多度津へ後戻りせり。「何船かと問えば「金りょうなりと答う。「なに斤量がついたと、笑わしゃァがらァ、何噸ある船だか知らないが」と独りぐずぐずいいながら時計を見れば十二時也。眼をこすりこすり支度をととのえ、はしけにのりうつり阜頭を出ればすぐ眼の前の近き処に碇泊せり。「オオ安ッぽい金びらさん」だと船の横へ回ってびっくり。大形風の丸窓也。角窓の獄門首とは事代りければ忽ち金比羅崇拝者と変じたり。蒸気への上り口も小舟の縄ひっつかえのやッとこさ上りとは事違い、正々堂々と階子より上り「上等だよ」といえば別の入り口よりはいらしめたり、ここを下り右に一室あり。お定りの半円形にて余り広き室ならぬに、男一人女二人真中に坐をしめたり。余はつと進み入りてその正面につき立ち、にらめいるに向うの女も「オヤすかねえ野郎だよ」といった様な風をして余をにらみかえしたり、おのれこしゃくなといはんとせし折柄、ボーイがこちらですと後の方へ導きしに、これはしくじったと思えど、何くわぬ顔でついて行けば、この上等は一人一人別々の室也。その中の一室をあけて余の荷物を棚にのせ、おはいりなさいましと丁寧にいう。余は三分の一は喜び三分の一は驚き三分の一は恐れて、入らずへでもはいる様にこわごわはいッて見れば、三畳許りの室にて寝室は二重に構えたり、ボーイは直に枕を持ち来て(木枕にあらず、空気枕形の藁の入りし枕也)据えたり。この時の余の喜びは如何ぞや。この船は金陵丸といえば、翻訳すれば金比羅丸也。去年の参詣が今きいたかと婚しく 小間物をささげし甲斐もありがたや 金比羅丸と船も名のれり 今迄の書生の姿あら神や 俄に鼻を高くなしつつ 室の前に長きテーブルありて、上に新聞十葉許り。煙草盆火鉢茶道具を備う。おまけに、よびりんまでがジット用事があるかと待ちうけたるさまに扣(ひか)えたり、余は余りの嬉しさに室内に安んずる能わず。一先ず甲板へ出てあちこちあるきしが、忽ちまた室中に帰り、上の寝室に寝て考えたり。「さっき東京へいった夢は吉兆であった、これが実に感歎の枕であった、さっきよその室へ迷いこんだはいかにも不体裁であった、おまけにあいつが素的な美人であったから間がわるかった」などと妄想浮び出てどうしても寝られず、乃ちまた起き出でて前のテーブルに腰掛け、戯れに左に記したる詩か歌か分らぬものを書きつけなどしたり。相の子の毛色のかわった処を御笑観あらまほし。 床待の歎 いつか見そめし赤功(てがら) 三年このかた気る楓(かえで) 雲のふる日も通ひ筒 くれどなびかぬ深工(たくみ) 廊下静かに時は虹(にじ) それでも女郎はきて紅(くれない) この紀行なども書きたる内、労(つか)れければ寝牀に上りぬ。翌朝夢さめて甲板に上り見れば、この船は金陵にあらで金龍なり、こいつはしまった。咋夜已来の妄想は尽く夢となった、アア金比羅様にばかされた。 午前九時半神戸に着きぬ、これからさきは相変らず書生となった、もうこれぎり。(上京紀行 筆まかせ 第二篇)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2018.02.13 01:42:47
コメント(0) | コメントを書く
[正岡子規] カテゴリの最新記事
|