
|
|
|
カテゴリ:茅ヶ崎市歴史散歩
【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次
次の目的地の「熊野神社」を訪ねる為に進むが、途中「上正寺」👈リンクがあったが、 この寺は2019年の「旧東海道を歩く」で訪ねているのでこの日はパスした。 そして「熊野神社(小和田)」に到着。 神奈川県茅ヶ崎市小和田2丁目3-66。  左側に、「小和田 総鎮守 熊野神社」の石柱が建つ  朱に塗られた「鐘楼」が右手に。  鐘楼には「熊野神社」の文字が。  左手にあった大きな石碑。  「大震災碑」と。  「大震災碑 元代議士 勲四等 山宮藤吉篆額 神奈川縣町村長会長、新田信撰文 大正十二年ノ秋九月朔日午前十一時五十八分倏惚トシテ関東ノ野ヲ襲ヒタル大地震ハ無數ノ屋舎ヲ倒シ多大ノ人命ヲ毀傷シタルノミナラズ之ニ次グニ劫火ヲ以テシ猛火ノ凶焔天ヲ焦シ 燎原ノ火勢ハニ日ニ夜ニシテ殆ンド帝都ヲ廢墟トナシ帝國ノ関門タル横濱ヲ挙ゲテ灰燼ト化シ 其ノ災害ノ及ブ所東京神奈川千葉埼玉静岡山梨茨城一府六縣ノ廣キニ亘リ許多ノ財寶ト生霊トハ 須臾ニシテ鳥有ニ歸セリ加之此間交通機関杜絶シタルガ為メニ流言蜚語盛ンニ傅ハリ人心洶洶ト シテ倍々其惨害ヲ大ナラシム殊ニ湘南ノ地ハ震源地帯ナリシヲ以テ淒愴ノ状最モ甚シク全地域ニ 亘ル焼失並ニ倒潰家屋六十九萬四千餘戸ノ内本縣内ノ被害數實ニニ十三萬七千餘戸本町三千三百 八十四戸本區熊野神社外三百戸内金潰百ニ十五戸半潰百七十五戸ニシテ其惨憺タル筆舌ノ能ク盡ス ベキニアラズ又死傷者ノ総数十五萬七千餘人ノ内本縣ニ於ケル死傷者五萬千餘人本町二百七十三人 本區十四人内死者七人傷者七人ニシテ酸鼻ノ極人ヲシテ面ヲ背ケシムルノミ是レ蓋シ有史以来ノ 大禍難ニシテ國運ノ伸暢ハ為ニー頓挫ヲ来シタルノ観アリ然レドモ災民ハ當時全國ヲ始メ遠ク 欧米各国ヨリ寄セラレタル同情裡ニアリテ復興の志燃ユルガ如ク翌十三年一月十五日ニ於ケル 再度ノ強震ニモ屈スル處ナク奮励努カ遂ニ帝都ヲ始メトシ震災前ニ數倍スル美観ト設備トヲ施シテ 復興ノ計漸ク就ナル 固ヨリ不測ノ天變地妖ハ人力ノ如何トモスルベキ所ニ非ズト雖モ災禍ノ範囲ヲ縮挟シ救済ノ道ヲ シテ遺算ナカラシムルハ人事ノ敢テ能クスル所ナリ茲ニ本区復興ノ計全ク就ルニ際シ即千鑑戎ヲ 末代ニ胎シ遺範ヲ後毘ニ垂レ以テ来者ノ指針ニ供セン為メ區民相圖リテ碑ヲ建ツ云爾 昭和五年八月一日 室政吉書 辻堂 高野宏哉刻」  右側の池の中にあったのが「厳島神社」。  太鼓橋の先に「厳島神社」の社殿。  「小和田道祖神」と。  「道祖神」碑。  「双体道祖神」であろう。 男神と女神がしっかりと肩を抱き合い、手を握って。  石鳥居に掛かる扁額は「熊野神社」。  参道の先に拝殿が見えた。  「庚申塔」群。  「熊野神社社務所」。  「手水舎」その後ろに「神輿殿」。  「神楽殿」。  「熊野神社」の西門。  境内から見る。  正面に「拝殿」。  口の中が真っ赤な狛犬(阿形像)。  狛犬(吽形像)。  「拝殿」。 創立は不明であるが、元禄元年(1688)再建の古棟札があると。 諸説には「熊野信仰」が広まった平安末期とも伝わると。 相洲大庭荘小和田村鎮守と記されているので、大庭荘の管轄だったので大庭氏が活躍していた 時代からあったと推測される。 弘化4(1847)年、明治17(1884)年、大正13(1924)年に再築の棟札及び 熊野三社権現社号の古札がある。 ご利益は、海上守護、魚漁、交通安全、殖産、興業、厄難除、家内安全等とされている。 なお、摂社、姥母神社は、安産の神、病気平癒の神と尊ばれて来た。  唐破風懸魚の見事な彫刻。  水引虹梁の上の中備(なかぞえ)にも見事な龍の彫刻がおかれていた。  右側の袖の彫刻。  左側の袖の彫刻。  拝殿の扁額、「熊野神社」。  正面にはガラス戸が。 御祭神:熊野久須毘命 ( くまのくすびのみこと ) 熊野夫須美命 ( くまのふすみのみこと ) 速玉男命( はやたまおのみこと ) 家津御子命( けつみこのみこと )。 祭礼: 1月2日 歳旦祭(さいたんさい) <年賀祭 (ねんがさい)> 1月15日 豊漁祭(ほうりょうさい) 7月海の日 浜降祭(はまおりさい) 8月1日 例祭(れいさい) <神幸祭 (しんこうさい)> 8月1日 例祭(れいさい) <宵宮祭 (よいみやさい)> 8月2日 例祭(れいさい) <例大祭 (れいたいさい)> 12月30日 大祓(おおはらえ) 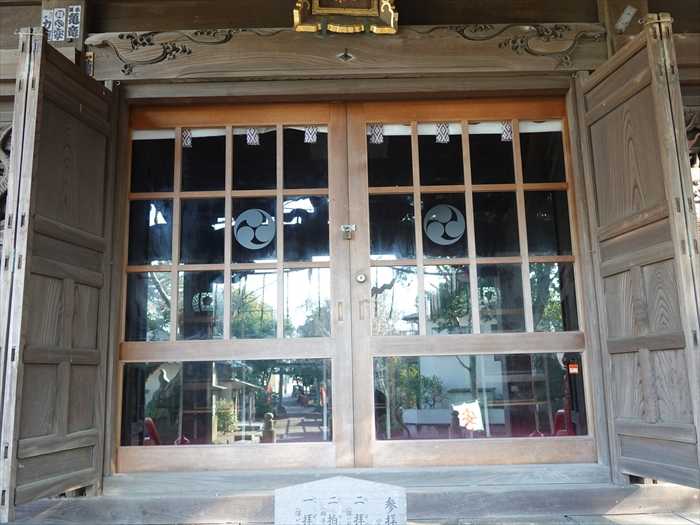 「神輿殿」。 「浜降祭」に参加する「神輿」👈リンク。  「靖國之碑」。 同地区における明治28年から昭和21年にかけての戦没者130柱を合祀した慰霊碑。 地元有志によって、昭和25年8月15日に建立された。 碑高255㎝、幅119㎝、厚さ17㎝、台石60㎝。 碑正面: 「靖國之碑 靖國神社宮司筑波藤麿」 碑裏面: 「戰歿合祀者(篆額) ・・・数多くの戦没者の命日と名前が刻まれていた・・・ 昭和廿五年八月十五日戦没者記念碑建立発起人一同」  拝殿の左側にあったのが「豊受稲荷社」。 その手前に石碑が三基。 右:「日〇神社」、「天照皇大神」、「〇〇神社」 中央:「不◯大明王」、「富士淺間神社」、「石尊大權現」 左:「國狭土尊」、「國常立尊」、「豊斟淳尊」  「拝殿」からの出入口。  「白虎神門」と。西方を守護する白虎。  「豊受稲荷社」を正面から。  社殿に近づいて。  内陣。  「豊受稲荷社」前から「本殿」を見る。  社殿左奥には「木曽御嶽信仰の三神」の石碑が。  右から八海山大頭羅神王(八海山大神)・御嶽大神・三笠山刀利天。 ・八海山大頭羅神王(八海山大神)は越後の八海山の神様。 ・御嶽大神は長野県と岐阜県にまたがる御嶽山の神様。 ・三笠山刀利天は群馬県上野にある「三笠山」の神様。 平安~鎌倉~室町時代を経て山岳信仰と民間信仰が結びつき、江戸時代に全国に広まって いったとのこと。  「辨才天・堅牢地神(けんろうじしん)」碑。 「農村では「地神信仰」がありました。名称を「地神講(じしんこう)」といいます。 春分と秋分に最も近い戊(つちのえ)の日を社日(しゃにち)といい、 この日に大地を守護(しゅご)する土地の神様を祭る地神講が行われます。 春の地神講は作物の育成を祈り、秋の地神講は収穫のお礼詣りをするものです。 地神講は、床の間に堅牢地神(けんろうじしん)(地天)と 弁財天(べんざいてん)(弁天)の掛け軸をかけ、煮しめと白飯を供えてお祭りをしました。 この日は、土地を掘り起こしてはいけないとされているため、農家にとっては休日となりました。 <堅牢地神(けんろうじしん)>
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2022.09.15 06:19:23
コメント(0) | コメントを書く
[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事
|