
|
|
|
カテゴリ:本のこと 映画のこと など
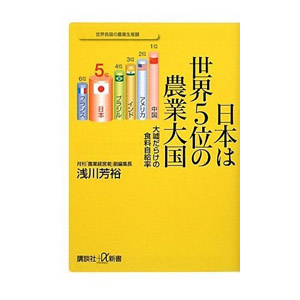 日本の食糧自給率は40パーセントしかないので、いざ食料危機となったら、大変だ!なんとか早く食料自給率を上げて、来るべき危機に備えなければ! と、私もこの本を読むまで信じていました。 が、この本は、それは農水省の作戦にまんまと引っかかったものであると結論する。 まず、40%という食料自給率は「カロリーベース」であるところに第一のトリックがあるという。 カロリーベースの自給率の計算式は 国民1人1日当たりの国内生産カロリー÷国民1人1日当たりの供給カロリー 国民一人当たりの供給カロリーというのは、国民一人当たりの「必要カロリー」ではない、というところがミソ。 ゴミとして捨てられる分まで含めたカロリーとなっている。 ということで、分母は2005年で2573kcal。 実際に口に入ったカロリーは、平均で1805kcal。 本来は、後者を分母とすべきなのだが、の農水省の計算は前者が分母となっているので、国産農産物の一人一日あたりの供給カロリー1013kcalを分子とすると、 1013÷2573で、39.3%になる。 もしも、平均摂取カロリーを分母にすると、 1013÷1805で、56%になる。 39.3%と56%では印象が大きく違う。 なおかつ、戦後の日本農業は、カロリーの高い米の減反と、野菜やフルーツなどの高付加価値産品の増産を行なってきました。 これは、高カロリーなものを減らし、低カロリーなものを増やすので、カロリーベースでは明らかな「自給率低下」要因になります。 農水省は、一方では自給率低下を促す政策をすすめ、一方では「自給率向上」を訴えるという矛盾を平気で行なっている。 ではなんでこんな印象操作までして、自給率にこだわる理由は何なのか? そういった分析や、日本農業の潜在的な力や、補助金政策の弊害や、国際的な食料事情など、とっても分かりやすく教えてくれる本です。 お役人のすることに、あらためて頭にくるとともに、希望も湧いてくる内容です。 何事も多面的に見ないと騙されますね。 もちろん、この本の内容も鵜呑みにせずに、自分でしっかり吟味することが大事です。 やはり、ひとつのテーマで、複数の違った論点を持った本を読むことが基本ですね。 ひとつの物事に、いろんな方向から光をあててみるから「立体的」で奥行きのある理解ができます。 一面的で、独善的で、とらわれたものの見方というのは、厳に慎まねばと思った次第です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010/12/15 01:05:39 PM
コメント(0) | コメントを書く
[本のこと 映画のこと など] カテゴリの最新記事
|