
|
|
|
全て
| 目次
| 2nd ライフ
| ネットワーク社会と未来
| マルチチュード
| アガルタ
| シンギュラリタリアン
| 地球人スピリット
| マーケットプレイス
| ブログ・ジャーナリズム
| OSHOmmp/gnu/agarta0.0.2
| mandala-integral
| レムリア
| スピノザ
| ブッダ達の心理学1.0
| シンギュラリティ
| agarta-david
| アンソロポロジー
| バック・ヤード
| チェロキー
| 環境心理学
| osho@spiritual.earth
| スピリット・オブ・エクスタシー
| 22番目のカテゴリー
カテゴリ:地球人スピリット
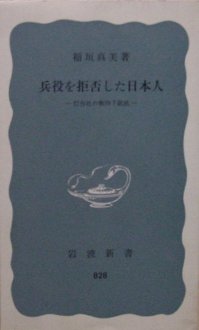 「兵役を拒否した日本人」 灯台社の戦時下抵抗 稲垣真美 1972/7初版 1993年第10刷 岩波新書 最近読んだ「禅と戦争」つながりで、この一冊を読むことになった。すでに1972年に発行されている本だが、評判が高かったらしく、1993年までには10刷を重ねている。私はこの10刷を閉架書庫から出してもらって読んだ。著者には74年岩波新書に新興仏教青年同盟とそれを率いた妹尾義郎について書いた「仏陀を背負いて街頭へ」が、あり、私は当時それを出版直後に読んで感動した記憶がある。 なんの予備知識もなく読み始めたこの本であったが、この本の主人公となる明石順三の師のひとりに、地元クリスチャン大学の第一回生の牧師がいたことで、なんだか最初から、親密な感情が湧いてきた。戦争中、明石が服役した牢獄も、また私の地元の刑務所だったので、なんともすぐ近くにこういう人が存在していたということを知るに及んで、なおリアリティが高まった。 この本もノンフィクションの秀作と言っていいだろう。最初、キリスト教と来て、やがて灯台社ときたので、もしやとピンときた。これは「ものみの塔」「エホバの証人」の人たちの、明治、大正、昭和の話であった。10代の頃は、茶目っ気たっぷりで無神論的であった明石は渡米して「ウォッチタワー」運動と出会う。帰国後「灯台社」を主宰して、当然の帰結として、数名の同志達と兵役拒否する。 1935年の治安維持法による大本教事件に先立つこと2年、灯台社は宗教結社としても最初の弾圧を受けたのであった。p50 戦後、出獄した明石は、アメリカ本国の「ウオッチタワー」本部と決別し、伝道の実践から離れた。そして、もっぱら静かな読書と執筆に静かな歳月を送った、とのことである。 読書は、仏典など広範囲におよび、聖書真理の解明についての論考もつづけられたけれども、仏典研究をも進めることによって、いっそう普遍妥当的な宗教上の真理に近づこうと努力したあとがみられる。執筆活動のほうは、彼は著述をすぐに世に問うことにはもはや興味を示さず、聖書と浄土三部経、歎異抄、万葉集などの思想を現代の舞台に立体化し、かつ本願寺の体制や浄土真宗の宗教の本質を衝こうとした新聞小説体の「浄土真宗門」、ほかに2000枚を超える三部作「彼」「道」と題する宗教小説のほか「運命三世相」という戯曲など、いずれも丹念に新聞紙面の小説欄のスペースの升目に書かれた肉筆の形の遺稿がのこされている。p190 本来、この本は兵役を拒否した、ということが切り口ではあったが、それは拒否のための拒否ではなく、キリスト者としての宗教上の当然の帰結としてそのような行動があったということであろう。 エホバの証人、と聞いた時、私はすぐに、現在でも時たまやってくる5~6人ののんびりした歩きのあの人々のことを思い出した。そういえば、ある時期、輸血拒否問題で話題を提供したのもこの人々だったなぁ。明石が兵役を拒否するスタンス、現代のエホバの人々が輸血を拒否するスタンスに、どこか通じるなにかを感じる。 兵役そのもの、輸血そのもの、に対する価値判断というより、聖書に依拠すれば、このような結論がでる、というどこか回りくどい教義がそこには横たわっているように思う。しかしながら、戦後、この冊子伝道を離れた明石は、カルト(教団)やマインドコントロール(教義)という次元を、次第に離れた地平で、ふたたび心の中の平和を問い続けたに違いない。 非戦や反戦が普遍妥当的な宗教上の真理でもあり、人間としてのあたりまえに心情である時代がやってくることを願う。戦争がない時代ならば、兵役を拒否することすら必要ない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|
|
||||||||||