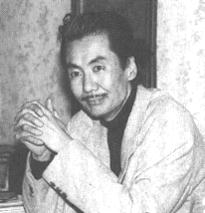地球人スピリット・ジャーナル2.0につづく
「おまるから始まる道具学」 モノが語るヒトの歴史
村瀬春樹 2006/3 平凡社新書
村瀬と村上とふたり春樹が存在する、ということにごくごく最近ようやく気がついた私ではあるが、いまだにこのふたりの違いがよくわかっていないというのが本当だ。ということでで、村瀬氏のほうの新し目の新書を一冊読んでみることにした。イメージをもっと鮮明にするために、二人の写真を検索しておこう。
こちらが、村瀬春樹氏。
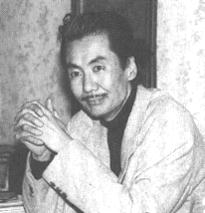
で、こちらが村上春樹氏ね。

あんまり変わらないような感じもするが、まぁいいか。
さて、この本、道具学という言葉はともかくとして、その上の部分がちょっと、あまり直視したくないものだなぁ。確かに私も、外便所だったので、小さい時は縁側におまるや尿瓶をおいてもらって、夜間はそちらを利用していたので、この「道具」にはお世話になりっぱなしだったが、でも、こうして再会することになるとは・・・。
<人類は、道具と言語と二大発明によって、霊長類の中でもぬきんでた存在となりえた>
まさにそのとおりである。そして・・・というか、しかし・・・いうべきか、<道具>と<言語>は人類が生み出した輝かしい二大発明にはちがいないが、地球上に存在してきた人類のドキュメント(証拠としての記録)としてこの二つを考えるとき、両者がもつ意味は大きくちがってくるのではないか・・・そう思ったのである。p13
この日本にしかないという「道具学=DOUGUOLOGY(ドーグオロジー)」、洒落なのか真面目なのかよくわからないこともあるが、結構、こりゃ、面白いことになりそうだぞ、という予感は感じさせる。しかし、人類の二大発明のひとつとされる道具である、その研究範囲は膨大なものになり、この世界の半分はその対象となりうるということにさえなりかねない。
日本にしかない学問といいながら、村瀬氏が一番最初に対象としたのは、西洋のおまる。いやはや、この本、新書なのに、こころなしか、なんだか匂いがしてきたような感じさえしてくる。このあと、次第にゆたんぽの話になり、ロックンロール世代らしく、ビートルの話から楽器の話に移行していったので、ちょっとホッとした。
いずれにしても、この人たち、次第に「定年後」世代とほぼ変わらないジェネレーションに移行しつつある。この洒脱な人たちにとって、「道具」としてのパソコンやインターネットがどのようなものか、ちょっと聞いてみたい気もした。おまるや湯たんぽに比較すると、現在私たちの生活に溶け込んでいる車やIT機器というのは、とてつもなく発展してきたものだなぁ、と改めてびっくりした。